福島第一原子力発電所事故から間もなく10年を前に、「原子力の」とタイトルに付く新書が立て続けに刊行されました。戸谷洋志さん『原子力の哲学』と山本昭宏さん『原子力の精神史――〈核〉と日本の現在地』の著書です。
哲学研究者・戸谷さんの新刊は、核兵器と原発をめぐるハイデガー、アーレント、ヨナス、デリダなど7人の代表的な哲学者の考えを紹介し、原子力の脅威にさらされた世界はどのようなもので、そうした世界に生きる人間はどのように存在しているのか、その根源を問うていきました。
一方、日本近現代文化史が専門の山本さんの新刊は、広島への原爆投下から3・11以後まで歴史的・思想史的にたどりながら、安全保障の前提としてアメリカの核兵器に依存し、政治・経済上の要請から原発と核燃料サイクルを維持するという、核エネルギーを利用するシステムがいかに日本社会に根を下ろしているかを明らかにしました。
お二人それぞれ異なる専門の視点から、原子力(核兵器と原発)の在り方について根源的に問い、そして問題の核心に迫っていくための対談を企画しました。
そこから浮かび上がる〈核〉と日本の現在地とは――。
※2月20日に代官山蔦屋書店さんで開催されたオンライントークイベントを記事化したものです。
■震災から10年が経って
戸谷 昨年12月、集英社新書から『原子力の哲学』という本を上梓しました。マルティン・ハイデガー、ハンナ・アーレント、ハンス・ヨナス、ジャック・デリダといった20世紀を代表する哲学者たちが、原子力の問題についてどのように考えていたのか。そして、東日本大震災を経験した私たちは、彼らからどんな示唆を得ることができるのかを、自分なりに考えてみた本です。
ハイデガーの原子力論に関しては、國分功一郎さん、森一郎さんといった方々が本をお書きになっています。ただ、現代思想史の中で、ハイデガーだけが原子力のことを考えていたわけではありません。その後に登場した数々の哲学者たちも、ハイデガーから影響を受けたりしながら、原子力と世界の関係を問うてきました。『原子力の哲学』では、こうした思想史的な系譜についても捉え直しています。
山本 私も同じく集英社新書から、今年2月に『原子力の精神史』という本を出版いたしました。くしくも原子力という同じテーマで、戸谷さんと私の本が同時期に出版されることになったわけです。
私の本は3章構成で、第1章では核エネルギーを利用する社会を批判的に考察するための手がかりを、過去の科学者、知識人、ジャーナリストの議論から拾い上げてみました。佐藤嘉幸・田口卓臣『脱原発の哲学』(人文書院、2016年)や、川村湊『原発と原爆:「核」の戦後精神史』(河出書房新社、2011年)など、重要な著作がありますが、改めて私なりに振り返ってみたいと思いました。第2章は歴史編で、なぜ日本が原発大国になったのか、これまでの流れをざっと振り返っています。第3章は現代編です。今年3月で、東日本大震災の発生から10年を迎えますが、この10年間で何があったのか、整理しています。
戸谷 山本さんの著書を拝読してまず思ったのは、山本さん自身のオリジナルな思想が前面に出てくるというよりも、網羅的に論点を整理したタイプの本なんだな、ということでした。原子力の問題を考えるときに押さえておかなければならない手がかりを、ものすごくたくさん提示してくださっているので、僕にとっては非常に勉強になりました。
山本 この10年間、私も書店でいろいろな本を見てきましたが、こうすべきだというメッセージを込めた本を見つけるのは簡単です。でも、問題を考えるときの手がかりを求めようとすると、ハードカバーの専門書になってしまう。その中間に位置するような本があってもいいのかな、と思ったんです。思想家ではない私にできることはそれかな、と。
戸谷 僕は東日本大震災のとき、東京の大学に通っていたこともあって、当事者意識を強く持っていました。大澤真幸さんや中沢新一さんといった日本の知識人たちが、原子力についてどんなことを語るのか、注目して見ていました。すると、意外とみなさんメッセージが強烈だったんですね。とにかくこうすべきだ、こう考えるべきだ、みたいな。震災直後ということで、次のビジョンを強く打ち出すことに使命感を持っていたのだろうと思うのですが。
しかし、10年が経過して、そうした声は小さくなってきたように思います。かつて原子力について語っていた知識人たちも、最近ではあまり語らなくなってしまった。こうした状況の中、改めて冷静に原子力について考える手がかりを与えてくれたのが、山本さんの『原子力の精神史』だと思います。その意味では、まさに今出されるべき本だったのではないでしょうか。
山本 読者のみなさんに言いたいのですが、私の本より先に戸谷さんの本を読んだほうがいいですよ! より根本的で、面白いと思います。私の本は、日本を事例にしていますから。
原子力というのは目に見えない、イメージしにくいものです。しかも、賛成か反対かという二元論的な議論に直結しがちです。原子力について何かを語ろうとすると、すぐに色をつけられてしまう。論者も、有形無形の圧力にさらされて、どんどん歯切れが悪くなる。つまり原子力は、いまなお語りにくいテーマなんだと思います。その語りにくい原子力を、過去の哲学者はどう語ってきたのか、戸谷さんは見事に整理されて、私たちの前に並べてくれました。
戸谷 ありがとうございます。こうして面と向かって褒めてもらえることはあまりないので、とても嬉しいです。
■原子力への想像力を拡大する
山本 私が戸谷さんの『原子力の哲学』を読んでいて、なるほどと思ったのは、ジャン=ピエール・デュピュイの「みんな破局が来る可能性があるのは知っているが、その可能性を信じることができない」という指摘です。私は何を伝えるべきなのか、どのような言葉を使うべきなのか、いつも自問しているのですが、その根本には、「どうしてみんな破局の可能性を信じ切ることができないのか」という問題があるのだと認識できました。

『原子力の精神史─<核>と日本の現在地』の著者、山本昭宏氏
私たちの身体は、原子力を利用している社会にしっかり埋め込まれているのに、考え方や想像力は、社会からはじき出されています。確かに核エネルギーは目に見えないし、電気を使っていて原発のことを思い浮かべる人はあまりいません。社会が原子力を利用していることに、想像力が及ばないこと、及びにくくなっていること。そのこと自体を問題化することが重要ではないかと、戸谷さんの本を読んでいて思いました。
戸谷 山本さんは『原子力の精神史』の「おわりに」で、核エネルギーは私たちの日常生活を規定しているが、なかなか意識しづらい、本当は危険なのに、危険を感じることができなくなっている、という指摘をされていました。まさにデュピュイが危惧していたことと共鳴します。
デュピュイやヨナスは、原子力について判断を下すときは、想像力を拡大することが必要だと言っています。原子力についての科学的知識を学ぶことも大切ですが、それだけでは足りなくて、むしろ文学的な想像力や、芸術やカルチャーを通じて培われるような想像力が求められると言っているんです。僕もその主張には賛成で、原子力に関する文学作品や映像作品にどんどん触れるべきだと書いています。
それについて山本さんは、両義的な見方をしているように感じました。『原子力の精神史』のなかで展開される、戦後の文化史における原子力の表象をめぐる議論が、個人的にはとても面白かったんです。
山本 以前、『核と日本人』(中公新書、2015年)で取り上げたのが、まさに今指摘してくださったテーマでした。日本は原爆を落とされた国なのに、実は1960年代あたりまで、漫画や映画などのポピュラー文化の中で、原爆を気軽に描いているものが多いんです。米国では、スパイダーマンや超人ハルクのように、核実験や原子力研究によってすごい能力に目覚めるという設定がよくあります。映画『放射能X』では巨大アリが出現する要因として核エネルギーが使われています。それらの作品のなかに、核エネルギーへの批判的な視点を読み込む余地がないわけではありません。ただし、多くの読者を想定しているためか、核への批判は表面的には薄いです。日本でも同様に、母親が広島で被爆したことで、主人公である息子がすごいパワーを持った、といったような話が存在します。現在ではほとんど読まれていませんが、原研児による絵物語「アトム少年」(『少年少女譚海』1949年7月特大号)や、園田光慶(当時は「ありかわ栄一」名義)の柔道マンガ「車大助」(『週刊少年キング』1963~64年連載)などです。もちろん『はだしのゲン』や、こうの史代さんの『この世界の片隅に』など、批判的に捉える文化の脈流もしっかりあります。しかし、原爆を何でも説明できてしまう「魔法の杖」として使ってきた経緯もあるんです。
他方で、原発については、それほどポピュラー文化では描かれません。スポンサーの問題があるからでしょう。私たちは核の危険なイメージや、放射能による変異などのイメージを消費する一方、チェルノブイリや、福島第一原発で事故が起こったときには、少なくとも一時的には真剣に恐怖し、真摯に向き合おうとしている。私たちの社会にはその両面があるのだと思います。
先ほど戸谷さんは、私が両義的な見方をしているとおっしゃってくれましたが、その通りだと思います。両義的な見方を提示することで、作品に対して批判的に介入できるリテラシーを養ったり、批判的に介入できる空間をつくったりすることに貢献できるかなと思うからです。
ところで、戸谷さんがおっしゃった、想像力の拡大という言葉はとても大切ですね。たとえば、私が学生に「想像力を伸ばすのは大事だから、伸ばしなさい」と言ったところで、想像力は伸びないでしょう。そもそも、教師にやれと言われてやることが主体的な行為なのかという前提的な疑問がありますよね。小説や映画などが素晴らしいのは、人物への感情移入を通して状況を把握し、ここではないどこかの経験を追体験できることです。そこに、主体的な想像力の行使へといたる通路があると思います。
■アーレントの「公共性」とは
山本 私は戸谷さんの本を読んでいて、とくにアーレントの章が面白いと思いました。核のある社会、核エネルギーを利用している社会が、はたしてどれだけ自由で民主的なのか。この巨大な問題へのアプローチを、戸谷さん経由でアーレントから学べたと思うんです。
戸谷 僕も今回、アーレントの原子力論を改めて読み直したんですが、やはり彼女はかなり変わった思想の持ち主だと思いました。彼女のベースには、師匠であるカール・ヤスパースの思想があるんです。本書でも扱っているヤスパースの原子力論は、ある意味ですごく単純で、核というのは人間の生命を脅かすからダメなんだ、ということを言っています。しかしアーレントは一歩進んで、核の本当の脅威は生命を脅かすことではなく、生命を脅かすことによって自由を脅かすから危険なんだ、と考えるんです。彼女の関心は常に公共性と自由をいかに守るか、という点にあったように思います。
アーレントの考えている公共性というのは、少数の人たちが国会議事堂でむっつり議論することではありません。人々がそれぞれの共同体の中で、おたがい顔を見せ合って、一人の個人として意見を言うこと。その共同体の中では、誰もが対等な立場であること。公共性とはそういう空間であると、アーレントは考えていました。
ただし、この公共性が成り立つためには条件があります。それはそこに集まる人々が一つのリアリティを共有しているということです。彼女はそれを「世界」とも呼んでいます。たとえば、街に住んでいる人たちが広場に集まって、時間をともに過ごし、そこで語り合うといった状況です。感覚可能な物理空間に人々が集い、共通感覚を共有することで、政治的な公共性の基礎が生まれてくると、アーレントは考えたのです。
ところが現代社会において、私たちの生活の多くが原子力発電によって賄われているのだとしたら、それは原子力によって日常生活が規定されている、ということを意味します。電気を使うにしても、それがどこからやって来るのかわからない。感覚不可能なものによって日常生活が成り立っている状態に、私たちは置かれています。すると人々は、自分がいる世界をリアルなものだと確信できなくなります。であるがゆえに、自分が他者と同じ世界を共有しているというリアリティを持つこともできなくなり、公共性もまた浸食されていく。
アーレントの問題提起は、原発推進派と脱原発派の議論の食い違いや、原発をめぐる当事者と非当事者のすれ違いに光を当てるものだと思います。それぞれに自分の考え方はあるけれども、その多様な考え方を統合するようなリアルな世界が存在しない。それはだからです。それは、人々が原子力についてリアリティを共有することができず、リアリティを共有できない以上、公共性も成り立たないということを意味します。ここに原子力の政治的な危険性、原子力を語ることの構造的な困難さがあると言えるのではないでしょうか。
山本 かつての米ソ冷戦時代には、全面核戦争が起こりうるという緊張感がありました。そのため多様な反核運動が世界中で起こり、活発な議論も行なわれていました。リアリティを共有している公共圏も、たくさん存在していたはずです。しかし今では、ICANがノーベル平和賞を受賞しても、新聞やテレビで報道はされますが、私たちが日常生活でICANの話をするかといえば、ほとんどしませんよね。その意味では冷戦下のほうが、皮肉にも感覚可能な空間が存在していたのかなと思いました。
原発について言うと、チェルノブイリや福島第一原発の事故後は、一時的にものすごくリアリティが高まったんです。そのときは確かに多様な議論があり、具体的な細かい場所では、公共圏が立ち上がっていました。対話を通して個人が変わったりする空間は、存在していたのだろうと思います。原発に関して言うと、「原発はもうこりごりだ」という気持ちは、10年経った今も風化せずに日本社会に残っているとみています。
■漫画、映画に見る核のリアリティ
戸谷 西岸良平の漫画『三丁目の夕日』に、キューバ危機を扱った話があります。いよいよ核戦争が始まるかもしれない、というラジオ放送を聞いた小学生の男の子が、それをリアルに恐怖して、どうせ死ぬのなら夏休みの宿題なんかしてもしかたないと、家出してしまう話です。そういうリアリティが、かつては本当にあったんだろうなと思うんです。今では隣国の核ミサイルの件が報じられても、ここまでの危機感は誰も感じていません。この感覚の麻痺はどこから来ているのでしょうか。
山本 リアリティの話で必ず思い出すのが、黒澤明の『生きものの記録』という映画です。主人公は核戦争が起こり、自分が築き上げた財産を失ってしまうと恐怖します。でも、家族の誰もそれを信じない。主人公はどんどんおかしくなって、あるときこのように考えるんです。みんな財産に固執している、だったらこの財産をなくしたらいいんだ、と。それで、自分で自分の工場を焼くんですよね。最後は、精神病院に入れられて終わるという後味の悪い話なのですが、傑作です。
核エネルギーの恐怖を突き詰めていくと、理性のたがが外れてしまうのではないか。はたして、正常に怖がるということは可能なのか。非常に踏み込んだ問題提起をしている映画だと思います。
戸谷 『原子力の哲学』でも取り上げたギュンター・アンダースは、広島への原爆投下に参加した、クロード・イーザリーというパイロットと往復書簡を交わしています。イーザリーは原爆投下の任務を終えて帰国したあと、広島の写真を見て、発狂してしまったそうです。
アンダースは、次のように分析しています。イーザリーは写真を見ることで、自分が行なった行為に見合う想像力を手に入れた。つまり、初めて自分がやったことを理解した。その結果、正気でいられなくなり、発狂したのだ。核攻撃は、人間が正常な精神では受け止められないような結果をもたらします。もしかしたら、原子力の問題が正気で語られているうちは、実はまだ何もわかっていない、ということなのかもしれません。逆に言えば、いかにして日常との連続性のなかで原子力の問題を判断するための想像力を獲得していくのか。こうした問題もあろうと思います。
■大切なのは「落ち着くこと」
戸谷 僕は『原子力の哲学』で、想像力を持つこと、対話することと並んで、「落ち着くこと」が大切だと言っています。ハイデガーの放下(Gelassenheit)という概念を、自分なりに解釈してみたのですが。

『原子力の哲学』の著者、戸谷洋志氏
原子力の問題がやっかいなのは、原発推進と脱原発の二者択一で考えられがちなことです。「原発推進派じゃないなら、お前は脱原発派なのか?」といった、鋭い問い詰めを常にされているような感じがします。しかし当然ですが、原子力の問題はそれほど単純ではありません。ある局面においてはこう判断を下すが、ある局面においては別の判断を下すということは、当然ありえます。このような総合的な判断を下していくためには、ある種の落ち着きというか、ただちに結論を下さない余裕のようなものが必要だと思っているんです。この余裕が、今の日本社会には欠けている気がします。
山本 もちろん「投票」という局面では、多様な要素からなる私たちの意思が二者択一へと収れんされていきます。でも、そこに行きつくまでの過程には、さまざまな議論の位相や論点があるはずです。その論点の幅を、自分の中でどれだけ持つことができるのかが大事だと思います。それが、戸谷さんの言葉で言えば「落ち着くこと」につながるし、私の言葉で言えば「疎外されている状況から、想像力を広げていくこと」につながります。論点の幅を持つこと、位相を考えてみるというのは、机上の空論ではなく、実践的な、生きていくうえでの知恵にもつながっていくのかなと思っています。
戸谷 想像力を持つこと、対話することにも言えますが、本当に落ち着くことは、実践するのが非常に難しいと思うんです。でも、そういう難しいことをあえて実践していこうとする心がまえが、私たちには必要なのかなと。
山本 その論点に関わってくるのですが、私は『原子力の精神史』で、男性性と女性性に注目してみました。近代の科学は、新たな発見をして、自然を征服して、名を成していくという、男性性と強く結びつく側面があります。もちろん女性の科学者もいましたが、圧倒的に男性が多かった。
これについて、『原子力の精神史』でも触れたエピソードをここで紹介させてください。1970年代初頭、「朝日新聞」の女性記者が核燃料サイクル施設へ取材に行ったところ、「女性は入ってはいけない」と言われたそうです。「ここは男だけの神聖な場所だから」という理由だったそうです。このように原子力は、男たちの技術であったという点も、現代の視点から見直すときに指摘する必要があると思います。
そう考えると、脱原発運動において女性たち、とくに主婦が強いリーダーシップを持っていたというのは、うなずける話です。つまり彼女たちは、原発そのものに反対するのと同時に、原発を抱え込んでいるこの社会、つまり男たちによる核社会に対して異議を申し立てていたのです。
こうした見方は、先ほど二人で話したような、どれだけの論点の幅を持つかという問いへの、一つのヒントになります。この場合は、女性性という見方を保持しておくことで、原子力へのちょっとした違和感が生じる。その違和感が対象への距離を生む。戸谷さんの言葉で言う「落ち着き」を獲得していく手がかりになるのではないかと思うんです。
■他者と関わり複数の視点を養う
戸谷 僕たちが今、日常的に考えている政治参加の方法というのは、ときどき選挙が巻き起こって、ネットなどで公約を調べて、誰かに投票する、そうしたことにすごく限定されてしまっていると思うんです。アーレントが考えていた政治的行為は、そうしたものではありません。自分の顔をさらして、自分の意見をみんなの前で伝える。語り合うことが重要な政治的行為であると、彼女は考えていました。私的利害、つまり自分にとってのメリット、デメリットを超えて、共同体のために考えることが公共性である、というわけです。そう考えると、今の代表制民主主義、とくに日本の民主主義が遠く及んでいないのは事実でしょう。
ただ、熟議や熟考が重要だということには完全に同意しますが、人々が熟議や熟考をするようになるにはどうすればよいのか、ということも考えないといけないと思います。原子力について、みんなもっと考えなくてはいけないと叫ぶことは、誰にでもできます。でも、どれだけ叫んでみても、人々は「じゃあ、原子力について考えてみるか」とは思わないでしょう。人々に考えたくさせる、考えたいと思わせるような仕組み、仕掛けが必要だと思います。
山本 そうですね。私も『戦後民主主義』(中公新書、2021年)で日本の民主主義を再考したときに、共同体との関係で同じようなことを思いました。ここでは、他者と同じ空間を共有して対話する際のポイントとして、雑談の重要性を指摘したいと思います。テレビの討論番組などが代表的だと思いますが、みんな自分の言いたいことを言っているだけで、バトルにはなっているけれど、対話にはなっていない……ということがありますね。これで相互批判を通じて、より高次元で同意に至ることはできません。
今はコロナ禍で難しいですが、私は仲のいい人たち、信頼の置ける人たちと食事に行くのが好きです。そこで議論を交わすことで、こだわりなく自分を少しだけ変えることができる。そうした場を、いくつ持っているでしょうか。雑談は、熟議の一歩手前の関心の抱き方、方向づけという点で、大事な要素だと思っています。
戸谷 僕も最近、似たことを思っていて、友情って大事なんじゃないかと思っているんです。アーレントは晩年、人間が思考するときには、孤独に一人で思索にふけるのではなく、自分の中にもう一人の対話のパートナーがいると考えました。では、その対話のパートナーとは誰なのか。それは友人だとアーレントは言います。つまり、自分の中に架空の友人を思い浮かべ、その友人と語り合うようにして、人間は思考を深めていく。ただ、そうした思考の深め方をするには、社交性を身につけていないといけない。
雑談ができる友人が実際にいて、友人と忌憚のない議論を交わす経験をして初めて、「あいつだったらこう思うかな」という複数の視点を持つことができます。一人孤独に思考して判断するのではなく、まずは他者と関係性を結んで、複数の視点を養っていく。その訓練をすることが大事ではないかと、山本さんの話を聞いていて思いました。
山本 そこからすべて始まるのかもしれませんね。
戸谷 今日は山本さんという、分野が近くも遠くもない、絶妙な距離感の方とお話ができて、とても楽しい時間になりました。今年は東日本大震災から10年という節目の年です。この対談が何かのきっかけとなって、私たちが今、置かれている現在地を考える手がかりになったらいいなと思います。
執筆/石井晶穂
撮影/三浦咲恵(戸谷洋志さん写真)
プロフィール

戸谷洋志(とや ひろし)
 1988年東京都生まれ。哲学研究者、大阪大学特任助教。法政大学文学部哲学科卒業、大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。現代ドイツ思想を軸に据え、テクノロジーと社会の関係を研究。著書に『Jポップで考える哲学――自分を問い直すための15曲』『ハンス・ヨナスを読む』、共著に『僕らの哲学的対話 棋士と哲学者』、『漂泊のアーレント 戦場のヨナス――ふたりの二〇世紀 ふたつの旅路』がある。
1988年東京都生まれ。哲学研究者、大阪大学特任助教。法政大学文学部哲学科卒業、大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。現代ドイツ思想を軸に据え、テクノロジーと社会の関係を研究。著書に『Jポップで考える哲学――自分を問い直すための15曲』『ハンス・ヨナスを読む』、共著に『僕らの哲学的対話 棋士と哲学者』、『漂泊のアーレント 戦場のヨナス――ふたりの二〇世紀 ふたつの旅路』がある。
山本昭宏(やまもと あきひろ)
 1984年奈良県生まれ。神戸市外国語大学准教授。京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。専門は日本近現代文化史。主著に『核と日本人――ヒロシマ・ゴジラ・フクシマ』『戦後民主主義――現代日本を創った思想と文化』(ともに中公新書)、『核エネルギー言説の戦後史1945~1960――「被爆の記憶」と「原子力の夢」』『大江健三郎とその時代――「戦後」に選ばれた小説家』(ともに人文書院)、『教養としての戦後<平和論>』(イースト・プレス)などがある。
1984年奈良県生まれ。神戸市外国語大学准教授。京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。専門は日本近現代文化史。主著に『核と日本人――ヒロシマ・ゴジラ・フクシマ』『戦後民主主義――現代日本を創った思想と文化』(ともに中公新書)、『核エネルギー言説の戦後史1945~1960――「被爆の記憶」と「原子力の夢」』『大江健三郎とその時代――「戦後」に選ばれた小説家』(ともに人文書院)、『教養としての戦後<平和論>』(イースト・プレス)などがある。


 戸谷洋志×山本昭宏
戸谷洋志×山本昭宏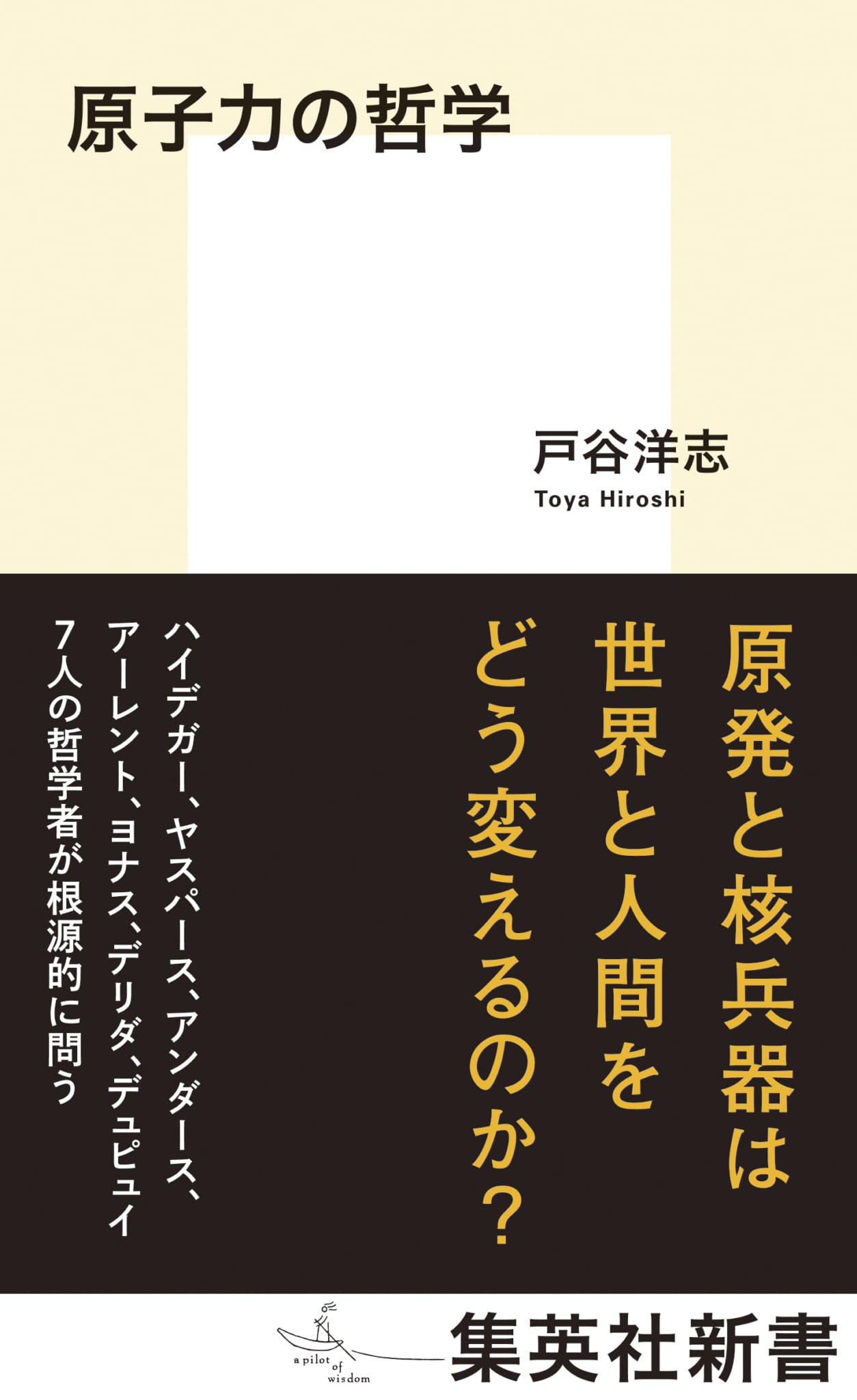 原子力の哲学
原子力の哲学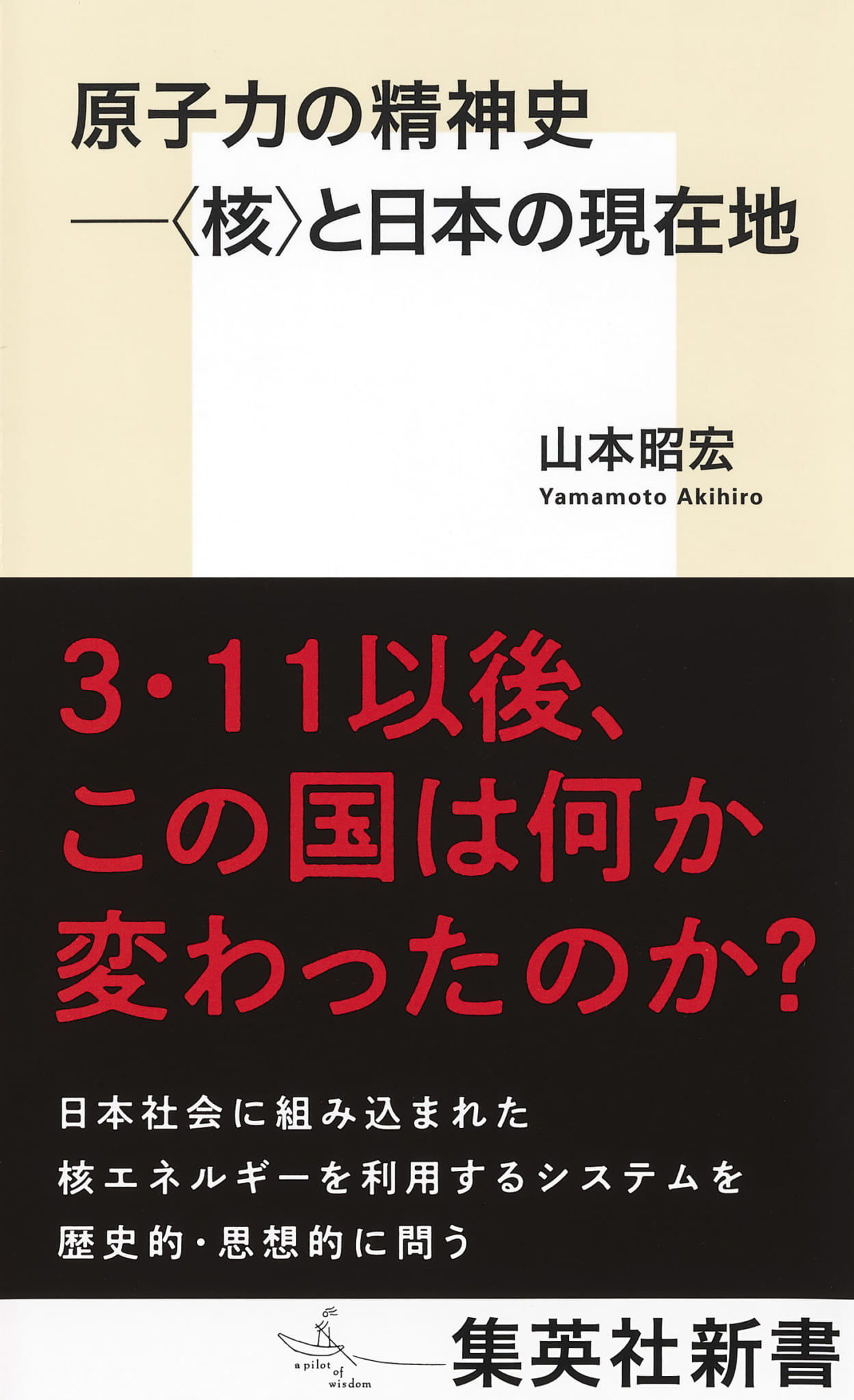
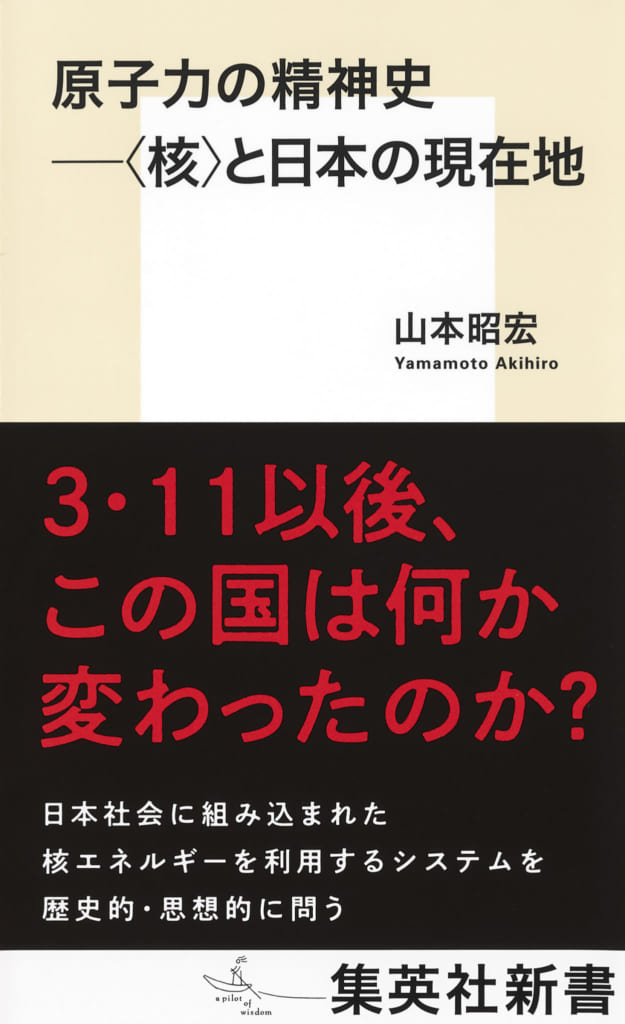
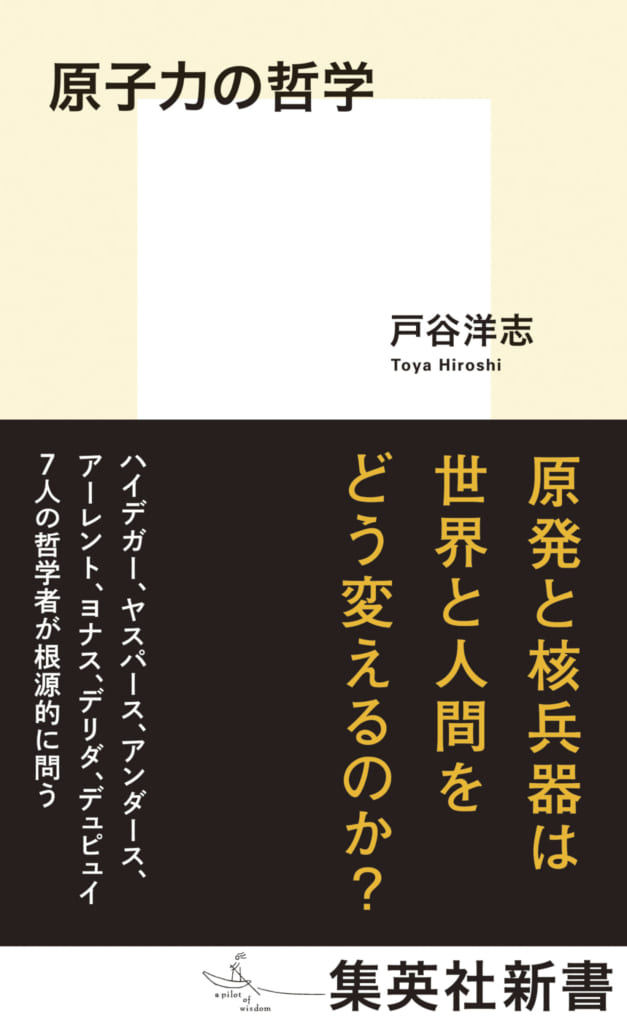










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


