連載
生成AIの登場によって、人類はより情報や知識にアクセスしやすくなった。それゆえ、「知識があるだけの人間は意味がない」「いっぱいものを知っていることより、創造的なアイデアを持っている人のほうがいい」といった言説も流通し始めている。人間にとって「知る」ことの意味とは何か。そして、現代の「知る」ことの困難とは何か。
哲学・批評・クイズ・ビジネスの領域で活動し続ける田村正資氏が、さまざまな分野を横断しながら、「知る」ことの過程をひもといていく。
-
第3回
詐欺師はどうして社会学を教えることができたのか2026.2.25 -
第2回
ペーパーテストと陰謀論—「解けるはずだ」と信じることの功罪
2026.1.20
-
第1回
イントロダクション——知ることはあなたの世界をどう変えるのか
2025.12.17
いつから人は働くことが当たり前になったのか?労働を嫌い、働かない生活を送る著者が、人類における労働の思想史を辿る。
広島・長崎に投下された原子爆弾の被害者を親にもつ「被爆二世」。彼らの存在は人間が原爆を生き延び、命をつなげた証でもある。終戦から80年を目前とする今、その一人ひとりの話に耳を傾け、被爆二世“自身”が生きた戦後に焦点をあてる。気鋭のジャーナリスト、小山美砂による渾身の最新ルポ!
-
第20回
負担増を隠す政府と、卑劣な「後出しじゃんけん」を繰り返す厚労省―2026年度〈見直し〉案をめぐる今後の動きとその問題点とは?2026.2.19 -
第19回
【衆院選直前!】高額療養費制度・〈見直し〉案をどう捉えているのか?―各政党の主張を検証する
2026.2.4
-
第18回
最新の研究成果をもとに、2026年度政府〈見直し〉案を検証する
2026.2.3
推し活がビックビジネスになりつつある昨今。とりわけ、アニメ、アイドル、お笑い分野はかつてない活況を呈している。
それと同時に、かつては存在しなかった言葉がファンの間で流通し始めた。それが「公式」である。作品の制作者の意図、アイドルの世界観、番組の意図などその言葉の使われた方はさまざま。共通するのは「公式の判断が絶対視」されていることである。なぜユーザーたちは「公式」を絶対視するようになったのか?
日本のメディア・消費の変化の最前線を取材し続けてきた著者が、「正解」や「絶対者」を超えた欲望をあきらかにする。
私たちの睡眠は、完全な休息とは切り離されはじめている? 哲学者の伊藤潤一郎が、さまざまな睡眠にまつわるトピックスを、哲学を通して分解する。
プラスをSNSでも
Instagram, Youtube, Facebook, X.com


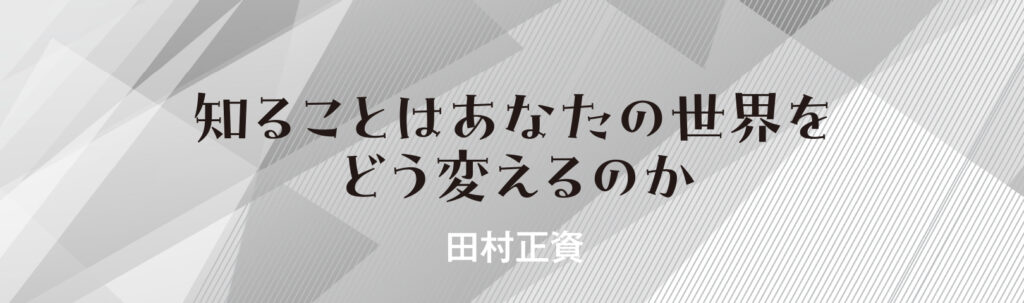
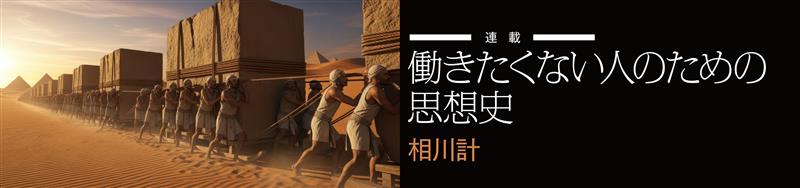


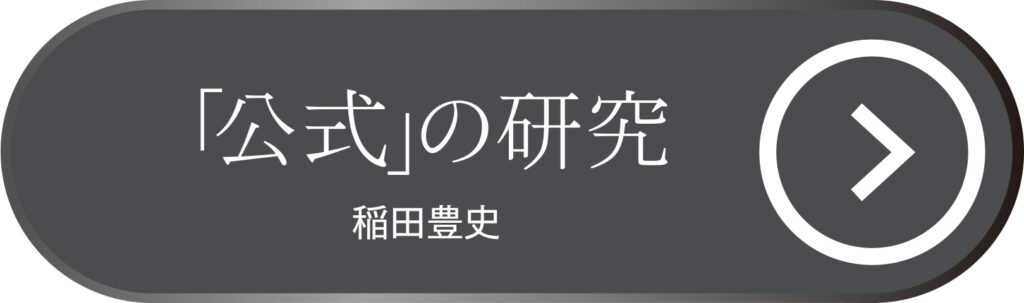










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


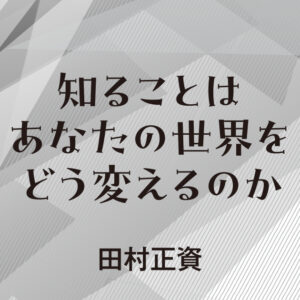
 田村正資
田村正資