高原に佇む大久保家から見下ろす広々とした水田。古老は縁側に座り、田んぼの水がきらめく春を楽しむ。夏は風に揺れる緑の絨毯になり、秋は黄金色になって、稲わらの香りを胸いっぱいに吸い込む。飯舘村に生まれ、102歳まで一歩もここを動かなかった大久保文雄さん。彼が見ていたその日本一美しい村の風景は何度も丁寧に描写される。読者は映画のシーンのように想像する。春を告げる花の香り、梅雨の湿った土と草の匂いまでも。
もしも、縁側にゆっくり腰を掛けてそれを楽しむ朝が突然奪われたら。どこかのプレハブで目が覚めて、ああ、もう二度とあの朝を迎えられないのだと絶望する日が来たら。私でも、直前に自分の時計を止めてしまおうと思うかもしれない。
102歳で自ら命を絶ったと本の帯にもあり、それを承知で読み進める。原発からかなり遠い飯舘村なのにと地図を確かめながら、文雄さんが抱えた切なさ、悲しみを徐々に理解していく。しかし青木氏の筆致は民族誌的アレゴリーの世界を行くように、100年を超えるスパンで山村生活の機微を描く。最も近代化の到達が遅れた山村で、最も長く豊かな営みが続いていたことも教えてくれる。寒村に生きて恨み言も言わず、酒席では相撲甚句を披露し、盆になれば息子と縄を綯い、大きな盆棚を拵える飯舘村の日々。古老の102年目の出来事に胸が痛んだとしても、その生活史を俯瞰すれば、決して悲しい人生などではなかったことを知る。「全村避難」は死刑宣告に等しかった。だが結果的に、見渡す限りの輝く田んぼが黒いフレコンバッグに埋め尽くされた光景を、文雄さんは見ないで済んだ。それが彼の見た最後の風景にならなかったことにせめてもの救いを求める自分がいる。
しかし私はこの本を、全編胸をかきむしられる思いで読んだ。「全村避難」の残酷さは過去の話ではない。私のドキュメンタリー最新作「戦雲」は、まさに今政府が「武力攻撃予測事態」と認定した瞬間に「全島避難」を宣告される与那国島や石垣島を描いている。主人公のおじいはカジキ漁の名人。毎朝家のベランダから久部良の港を眺め、風を読む。おばあは、おじいの船が大漁して戻る夕景に心躍らせる。人生最後の日まで見つめているはずのこの風景と穏やかな日々は、今、風前の灯火になりつつある。「台湾有事」に備える軍備が島の運命を大きく変え、島に残ることも許されぬ日が来るかもしれない。そんな不条理を突き付ける犯人は誰なのか。この国はまた新たな文雄さんを大量に生み出す方向に舵を切っている。一体いくつの挽歌がその悲しみを鎮められるだろう?
原発という「国策」を支えてしまった国民の一人として、二度と加害者にも被害者にもならないために何ができるのか、私たちはもっとのた打ち回って考えなければならない。
プロフィール

(みかみ ちえ)
ジャーナリスト、映画監督。毎日放送、琉球朝日放送でキャスターを務める傍らドキュメンタリーを制作。初監督映画「標的の村」(2013)でキネマ旬報文化映画部門1位他19の賞を受賞。フリーに転身後、映画「戦場ぬ止み」(2015)、「標的の島 風かたか」(2017)を発表。続く映画「沖縄スパイ戦史」(大矢英代との共同監督作品、2018)は、文化庁映画賞他8つの賞を受賞。著書に『証言 沖縄スパイ戦史』(集英社新書、第7回城山三郎賞他3賞受賞)、『戦雲 要塞化する沖縄、島々の記憶』(集英社新書ノンフィクション)、『戦場ぬ止み 辺野古・高江からの祈り』『風かたか「標的の島」撮影記』(ともに大月書店)などがある。


 三上智恵
三上智恵










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


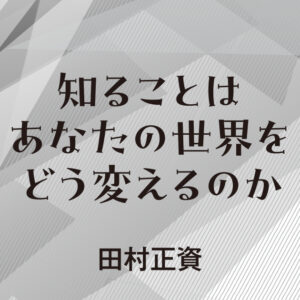
 田村正資
田村正資