コロナ禍を経て、急速な成長を遂げたゲーム産業。e スポーツの浸透やYouTubeにおけるゲーム実況のブームのみならず、米大統領選のキャンペーンに「どうぶつの森」が用いられたり、オリンピックの開会式にゲーム音楽が使用されたりするなど、その影響力は現実の社会にも及んでいる。
そうした状況を受けて、批評家の藤田直哉氏は、大人気ゲームの読解を通して、陰謀論、分断、叛乱、新自由主義、家族といった重要なテーマを考える新書『ゲームが教える世界の論点』を上梓。
本記事では、SF作家の柴田勝家氏と対談。柴田氏はさまざまなジャンルのゲームをプレイするのみならず、ゲームのシナリオも手掛けている。そんな実作者である柴田氏と藤田氏が、ゲーム文化がSF小説にもたらした影響と、ストーリーの語り口の豊かさ、そして現代のゲームが表象している「ノスタルジー」の問題について、『メタルギアソリッド』『DEATH STRANDING』などから考える。

ゲーム的、インターネット的な感覚をフィクションに
柴田 今回、藤田さんの作品を読ませていただいて、現代ゲームのシナリオは、昔とは違う表現がいろいろ出てきているということに改めて気づかされましたね。それを踏まえたうえで、ワシがゲームから何かを受け取って小説を書くということは、映画を見てそれに影響されて小説を書くのと全く同じことだったんだなと改めて思いました。
もしかしたらこれからの時代は、ゲームから影響を受けて小説を書きましたっていう人が珍しくなくなっていくでしょうね。
藤田 たしかに柴田さんの小説には、ゲームからの影響を感じます。一番感じるのは、作品の質感がとてもゲーム的な感覚であるということです。僕はゼロ年代にデビューしているんですが、ゼロ年代前後というのは、サブカルチャーやインターネットが出現して、ゲーム的、インターネット的、サブカルチャー的な新しい感覚をどう文学やフィクションの中に盛り込むかというのが扱われていました。そこに伊藤計劃というSF作家が出てきた。彼は小島秀夫が手がけたゲーム『メタルギア ソリッド』(以下、メタルギア)の影響を強く受けていたそうですが、それに留まらず、私たちの自己認識とか自己の身体イメージ、社会のシステムがゲーム的になっているというリアリティが作品に描かれている。
「伊藤計劃以後」という言葉がありますが、柴田さんのようにハヤカワSFコンテストを受賞された新しい作家たちには、ゲームの影響を受けた世界観がある人も少なくないように思っていました。そこがずっと気になっていたんですよ。
柴田さんの作品の場合は、特にその中でも死とか伝統とか、民俗学的な古いものにこだわっていて、それが新しいテクノロジーの中でどう変わっていくか、あるいは変わらないかみたいなことを問うていて、そこが好きですね。伝統的な死生観などがどう変化していくかを思索することは、小松左京はじめ、日本のSFがずっとやってきたことなんです。ゲーム、もしくはインターネットというメディアが、我々のリアリティ、イメージなり世界像、あるいは自己観、生命観に何らかの影響を与えるとして、そういう時代にそれをどう受け止めるべきか、あるいはこの先どうなるのかを考えている作家として、僕は柴田さんは大変面白い方だなと思っていました。
柴田 ありがとうございます(笑)。ワシも今の藤田さんの話を聞いて、腑に落ちる部分もあって。キャラクターを書いて作品の中に登場させるんじゃなくて、ゲーム的な文法っていうんですかね。まず世界観があって、システムがあって、そこにこういうパラメーターを持ったキャラクターが参加したらどういう反応が起こるか、どういうアクションをしたら解決できるかを書いていて、その視点は作者本人でもないし、読者本人でもないっていう、感覚があるなと思いました。
藤田 『信長の野望』をとてもプレイされていたんでしたっけ。確かにゲーム的な「質感」なんですよね。ところで、柴田さんが昨年11月に刊行した短編集『走馬灯のセトリは考えておいて』(ハヤカワ文庫JA)の表題作は、死んだ人がVTuberのようになって生き続けるというような話でしたよね。ライフログを取って、AIのVTuberとして復活して、死後の世界でも我々とコミュニケーションし続けることができて、まるで生きているかのように感じられると。これは実際にやろうとしているベンチャーがありますが、死生観で言えば、僕らが『ポケモン』をやっていて、ピカチュウとかに生命感を感じるのとちょっと似ているんですよ。ピカチュウたちも要するに電子生命体であって、物体であり、コピーじゃないですか。だけど、それにある種の生命を感じる。海外の研究者はよく「それは日本がアニミズムだから」とか言うんですけど。でもそうだとすると、死者があの世で生きているとか、死者が山に行くみたいな伝統的な信仰の延長線上で、VTuber的なものに死後の生を見いだしてもおかしくはないし、あるいは、死んだ人間が情報として存在するみたいな一つの信仰もあるわけだけど、この世に何か形を残せば、それを思い出す人がいる限り、生き続けられるっていうふうに次の世代が思ってもおかしくないんですよね。そういう大規模な変容が起きるだろうとは思っています。
つまり、VTuberとやり取りをするのが当たり前の人たちにとって、VTuberっていうのは、人間に等しいか、もしくは人間よりも親しい何かとしてもう感じられていると想像されるわけだけど、AIで再構成されても、そういうふうに思われるかもしれない。そういう社会がどうなるのかみたいなことを、柴田さんは文化人類学的なアプローチを用いて、ちょっと俯瞰的に書かれていますね。

柴田 一歩離れていますね(笑)。
藤田 僕が書く批評はもっと社会と人間への距離感が近くて、新しいメディアが政治的状況にどう影響しているか、それに対してフィクションを通じてどう介入するか、みたいなことに力点を置いている。そういうタッチの差というか、構えの差はあるように感じました。
柴田 そうですね。だから実際の実社会のほうに接続して何か訴えるみたいなことは、ワシはしていなくて。一歩離れてから観察するというのが癖づいていますね。そこで見たものは、皆さんが適宜お使いいただければというような感覚で書いていると思います。
藤田 これは未来を舞台にしているけど、現在の日本世界をある種民俗学的に見て感じたことの寓話としても読んでいいわけですよね。
柴田 そうですね。ワシは今あるものから引き寄せて、恐らく未来にも共通点があるだろうっていう部分を書いていければと思っています。

「現実とは何か?」を描いた『メタルギアソリッド 2』の衝撃
—— 今の世の中から未来的なものを考えるという意味で、柴田さんが影響を受けたゲームはありますか?
柴田 先ほども話題に出ていた『メタルギア』ですね。
たしか自分が小中学生のころに出たゲームだったのですが、それまでのゲームは何かを稼いでポイントをためるのが基本でした。ただ『メタルギア ソリッド 2』(以下、MGS2)では、作品の中で自分のプレイの意味が全く変わってしまうという仕掛けがありました。それ以前のゲームももちろんそういう側面はあったとは思うんですけど、その体験が如実に感じられたんです。
藤田 僕もまさに『MGS 2』に大きな衝撃を受けました。小さい頃にファミコンとかスーファミで遊んでいた頃には、システムと戯れるとか、あるいは競技性がメインで、いわゆる現代ゲーム性っていうのは強くは感じなかったんです。だけど、『MGS 2』に至って、初めて、政治的な、9.11以降のアメリカのような主題が偶然とはいえ入り込んできて、SFのかたちを通じて、いわゆる軍産複合体的な問題とか、核の問題とか、あるいは情報操作の問題みたいなものを描いていて、圧倒されました。
で、さっき柴田さんがおっしゃった仕掛けがまさに僕もすごいと思っているところで、プレイヤー自体を巻き込んで、これがシミュレーションであるということを伝えたり、あるいはゲームオーバーの偽物の画面を出したりするような、ゲームのメタフィクションみたいなものをやっている。あれに一番しびれましたね。それによって、この世界が真実かどうかわからなくなるような混沌とした状況をプレイヤーも体験させられて、パニックにさせられる。そのうえで、「現実とは何か」みたいなところに話をやったあの作品のすごさっていうのは、むしろ「ポストトゥルース」とか「フェイクニュース」とかで大騒ぎしている今でこそよりわかるというか(笑)、あれでゲームはちゃんと論じなきゃいけないと感じましたね。
そして、そのタイプの作品がより増えていって衝撃を受けたのは2010年代ですね。特に、『The Last of Us』とか『Detroit:Become Human』とか国際的なAAAタイトルのゲーム(大きな予算で作られたゲーム)が軒並み、ここまで露骨に政治的な、現実の社会につながるような政治的主題を扱いつつ、メタフィクション的な仕掛けを取り込んできた。こういう時代は僕は初めてじゃないかと思いますね。ゲームにそんな印象ってなかったですよね?
柴田 なかったです(笑)。単純に楽しいのが基本だったのが、目線が変わりましたよね。『MGS2』もそうだったかもしれませんが、あくまで「逆にそれがすごい」という評価で、ゲーム全体を見渡しては少数派でしたよね。あと、翻って2010年代以降にそういう作品をプレイしたことで、逆にそれより前の作品への目線も増えたかもしれませんね。
藤田 そうですね。『ゲームが教える世界の論点』では、『ファイナルファンタジーVII』についても書いていますが、この作品が出た1997年当時は単に面白いな、すげえ楽しかったなっていう印象で終わっていて。で、リメイクを通して最初のシナリオとかを見返してみると、めっちゃ原子力の話じゃないですか。原子力災害の話で、故郷が汚染されたとか、原発が爆発するみたいな話をしているわけですよね。そんなことやってたの?っていう。
柴田 すごいですね。
藤田 で、そういう目線を得てから遡っていくと、実は『ウルトラマン』とか『ゴジラ』もそうだっていうようにも見えてくるので、日本のフィクションの伝統なのかもしれないんですよね。『ウルトラマン』のシナリオライターたちは、結構政治的な意識が高くて、そういう物語を寓意的に織り込んでいたと言われています。ギリシャ悲劇とかもそうですが、時代と状況の中で、何か大事なことをフィクションの寓話を通じて伝えるっていうのが、むしろ標準だったんじゃないかと最近は思うようになっていますね。逆に、80年代から2000年代ぐらいの、政治的・社会的現実を忘却させる装置としてオタク文化が機能していた時期の方が例外と考えてもいいのかなと。
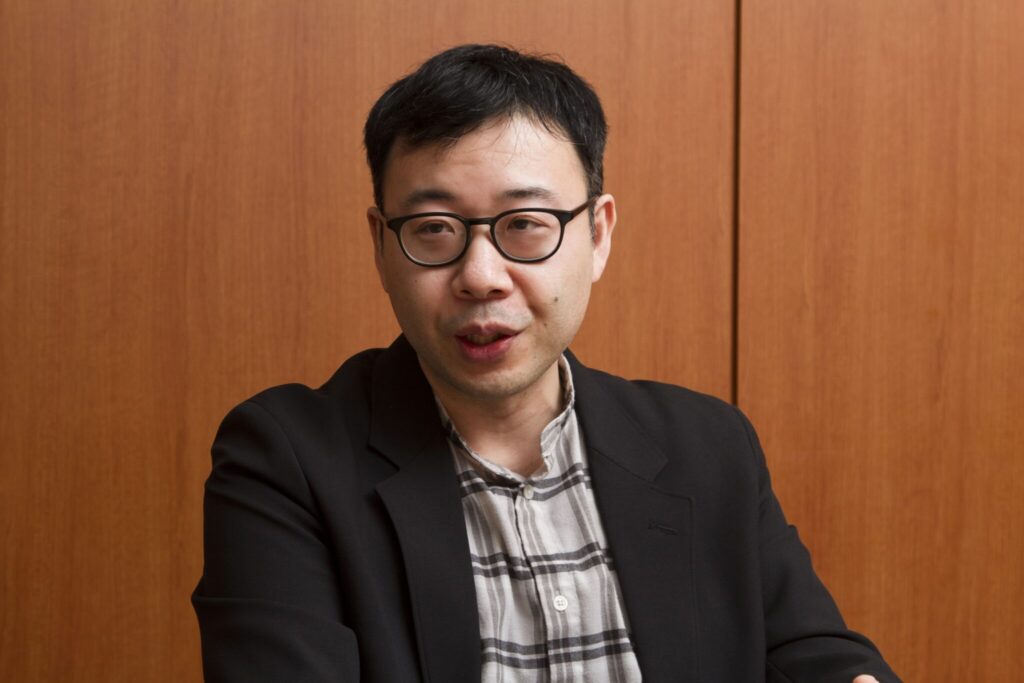
「懐かしさ」を求める現代と、その問題を描いた『DEATH STRANDING』
藤田 過去に戻りたいっていう願望が、今、強いじゃないですか。過去にあった世界に戻りたい、かつてあって日本を大事にしたいとか、あるいは男らしさを維持したい。つまり、変化に対する抵抗と反動みたいなのがあって。その中には信仰みたいなものも含まれていますよね。新しくなろうとすることと、過去の懐かしさへの執着に引き裂かれ、悩まされているのが現代だと思ってて。
柴田 ワシの作品も擬似的な懐かしさを描く作品がいくつかあるんですけど、懐かしさっていうのは、悪く取れば、あの頃はすばらしかったに違いないっていう。で、これは扱い方を間違った例だとワシは思っていて。懐かしさを感じること自体はいいんですけど、そこに人生すべてを懸けないというか。
例えば、今だっていろんな伝統文化、いろんなものを引き継いでやっている人たちがいて、一方でアイデンティティがないっていう人たちもいて、いずれにしても結局つながっているもの、自分の前からあるもの、国だったり社会だったりしますけども、それが自分の部分にあるって思い込みすぎちゃうと、多分、暴走しちゃうんですよね。
だからもっとフラットに懐かしさを感じてもらいたい。特に、ワシが書いたやつの中だと、『走馬灯のセトリは覚えておいて』に収録されている「絶滅の作法」っていう短編があって。ほかの星の生命体が地球に来て、懐かしい日本を再現するっていう、話としてはただそれだけなんですけども。主人公たちは異星の存在なんで、全く懐かしさを感じる必要なんてないし、懐かしいなんて思っちゃいけない立場にある。でも、結局懐かしさを感じてしまうっていう感じなんですね。で、もしかしたらそれぐらいの感覚が大事なのかもしれないっていう。
藤田 実体験や現実に対応しない懐かしさっていうことですね。そういう自分が経験してもいないのに懐かしく感じる作品ってありますよね。
柴田 ありますよね。懐かしさに身を寄せるんだったら、それぐらいのものと捉えて、アイデンティティとは何か、奥深いところに自分の真実があるみたいには思わないほうがいい。
藤田 ただ、僕は批判していますけど、懐かしさに浸りたい気分自体はよくわかるんです。本書で扱った政治的なゲームは、世の中を新しくしていこうというメッセージがあるわけだけど、それに反発する人たちっていうのはいっぱいいるわけですよ。それこそ、ゲームに反発して「外でメンコやで遊ばないと駄目だ」とか言っていた上の世代と似ていると思いますけどね。
政治的ゲームを作る人たちは、このゲームを通じて、世の中の価値観なり社会をちょっと変えていこうとしているけど、それに反発して炎上させる人たちは、そうじゃない方向に変えたいと思っている。それが何かを守るための戦いだとも思っている。そこで、何が守るべき「故郷」というか「原風景」になっているのかなと思うんですが、それが要するに政治性とか社会問題を意識しないで気楽に楽しめた80年代頃の世界、ということなのじゃないかな。レトロゲームの流行もそうだし、ヴェイパーウェイヴとかもそうだけど、80年代の、いろんな社会や世界の難しいことを考えなくてよくて、ただ単に戯れていられた頃のゲームの画面とか、レトロ系の画面とか、色味とか、サイバーパンク的な色調とか、あるいは音楽、あれが懐かしいわけですよね。そういう世界が「奪われて」、現実や社会の問題に覚醒させられるのが嫌なんだと思うんですよ。確かに、僕にもそういう気分はあります。あの時代が懐かしいとも思います。それは当然。
でも、わかるだけに、やめといたら?っていう感じがするというか、そうはいったって、戻れないだろうよ、という諦念の方が強いですね。かつてのドイツは栄光があってすばらしかった、昔の日本はすばらしかったみたいな、ロマン主義が第二次世界大戦のときに流行ったけど、現代ではそれに相当するものとして、80年代ぐらいの時代がロマン主義的な美化された過去になっているんだと思うんです。「レトロトピア」ですよ。それは、ちょっとまずいような気が僕はしてしまったんです。
ここで注意を促したいのは、ある種、変わりたくないとか、作られた伝統、美化された自分たちのアイデンティティみたいな、現代的な政治思想というか心情を担う媒体に、今、ゲームがなっちゃっているということ。そういうことが起きているっていうことは、もうちょっと多くの人に伝えたいですよね。
柴田 やっぱり懐かしいは懐かしいんですよね。これは逃れられないとは思いますよね、人間である限りは(笑)。
藤田 そこを否定しないのが、柴田さんのいいところなんですよね。「懐かしい」と感じて惹かれてしまう心情を受容しつつ、未来に移行していくことを促すような、折衷案が多分今は必要で、柴田さんはそれを生み出せると思う。
例えば、『メタルギア』シリーズを作った小島秀夫の『DEATH STRANDING』(以下、デススト)とかは、いろんなものが滅び去ったあとの世界で、その中で死者がよみがえってくる、あるいは滅び去った文明や過去がよみがえってくるということの問題系を扱っていましたよね。
柴田 あれは確かに、ワシも視点として好きなところですね。滅んだものはもうしょうがない、それを取り払って先へ進まないといけないということを描いていて、これは印象的でしたね。『デススト』って、主人公に死者が絡みついてくるなか、荷物を運ばないといけないっていうゲームじゃないですか。
藤田 そうですね。
柴田 荷物を運ぶという普通の生活の象徴のために、一歩動かないと、この死者を振り払わないといけない。あの感覚が心地よかったですね。死者に対する思いももちろんありますけども、今、生きてること、仕事をして、ただ届けて、本当に単純な作業をする、これを繰り返すしかないんだっていう、力強い諦めを世界観を含めて感じましたよね。
藤田 この作品って最初は、死者が怖いものとして現れますよね。ホラーみたいに、悪い、怖いものとして描かれているのだけど、最終的には怖いものじゃなくて、良いものなんだと心理的に和解する。その結果、未来の可能性・象徴としての赤ちゃんが外に出ていくし、主人公たちも過去や死者と繋がったことで社会への信頼を取り戻すことができた。あれは僕もすごく影響を受けましたね。過去や伝統を単に悪いものだと見なすような偏見も駄目なんだと。ちゃんと過去と、死者と繋がらないといけない、そのことによって未来ができるんだっていうメッセージがある。
『DEATH STRANDING』はSF的で海外の映画的なルックスであるけれど、実は日本の伝統的な価値観に近いとは思うんですよね。死者と「橋」でつながるとかは、和歌や能のセンスですよね。民俗学的・伝統的な死生観の現代的な折衷の凄く良い例がここにあるなと、感動しました。
柴田 そうですね。死者、幽霊が普通に存在してくるっていうのは日本的ですもんね。
——主人公サムの義理の姉として登場するアメリは、サムにとっての過去の美しい記憶を象徴する存在ですよね。サムはアメリがいるから俺はこの仕事を頑張るというモチベーションとしても描かれていますが、実はアメリはこの世には実体を持たないホログラムのような存在で、実在しない人間であることがのちに明かされます。
あれも先ほどお話しされていた、ある種の過去の執着みたいなところっていうのをすごい、それ自体が幻想であるみたいな見せ方をしているんじゃないかなっていう。
柴田 そうですね。懐かしさを求める部分はアメリが象徴してて。で、結局、懐かしさっていうのは偽物だったっていうのが一旦の解決で、そのあとにどう動くか、どうあがくかを問うていたのかなって思うと、より奥深く感じますね。
藤田 アメリは実質的には死んでしまったお母さんでもあったわけですよね。亡くなった母を求めるという心情の象徴でもある。日本のサブカルチャーの中で、母親っていうのはオタクのユートピアと言うか、宇野常寛さん的に言えば「母性のディストピア」ですけど、外部の世界と競争したり戦ったりという嫌なことをしなくていい世界の象徴で、それが理想的な過去の象徴にもなるわけですよね、そういうものを追いかけていった結果、それが幻想だと知って、どう埋葬するかみたいな話になっていく。
だからそれは現代に対するメッセージだと思うんですよね。母親と2人っきりの世界、あるいは美少女と2人っきりの世界みたいな捉え方でもいいけれど、あそこはビーチという、生命が絶滅する場所でもある。それはそういうのにハマっていると絶滅するぞという作り手のメッセージを感じるんですよね。幻としての過去の幻想に執着していると、絶滅するよ。過去や歴史や伝統や祖先への敬意をちゃんと持って、「未来」につなげていこうよ、というメッセージは、同時代の状況に対して本当に見事だったと思います。

(取材・構成:ノイ村 撮影:内藤サトル)
プロフィール

藤田直哉(ふじた なおや)
批評家。日本映画大学准教授。1983年、札幌生まれ。東京工業大学社会理工学研究科価値システム専攻修了。博士(学術)。著書に『虚構内存在』『シン・ゴジラ論』『攻殻機動隊論』『新海誠論』(作品社)、『新世紀ゾンビ論』(筑摩書房)、『娯楽としての炎上』(南雲堂)、『シン・エヴァンゲリオン論』(河出新書)、『ゲームが教える世界の論点』(集英社新書)、『百田尚樹をぜんぶ読む』(杉田俊介との共著、集英社新書)ほか。
柴田勝家(しばた かついえ)
SF作家。1987年東京生まれ。成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻博士課程前期修了。在学中の2014年、『ニルヤの島』で第2回ハヤカワSFコンテストの大賞を受賞し、デビュー。他の著作に『クロニスタ 戦争人類学者』『ヒト夜の永い夢』『アメリカン・ブッダ』『走馬灯のセトリは考えておいて』(ハヤカワ文庫JA) 、《心霊科学捜査官》シリーズ(講談社タイガ)などがある。2018年、「雲南省スー族におけるVR技術の使用例」で第49回星雲賞日本短編部門受賞。2021年、「アメリカン・ブッダ」で第52回星雲賞日本短編部門を受賞。戦国武将・柴田勝家を敬愛する。


 藤田直哉×柴田勝家
藤田直哉×柴田勝家










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


