第14戦日本GPを終えて3日が過ぎた10月4日(水)、マルク・マルケスが11年間所属したRepsol Honda Teamから今季限りで去ることを発表した。マルケスは2013年に20歳で最高峰クラスへ昇格して以来、数々の記録を塗り替えながら6度の世界タイトルを獲得し、MotoGP最強の存在としてホンダ陣営を牽引してきた。だが、このところ歴史的な低迷が続いて復活の兆しが見えないホンダの苦戦にしびれを切らせて、長く続いた〈婚姻関係〉をついに解消した恰好だ。
マルケスとホンダの当初の契約関係は2024年末まで継続となっていたため、はたして本当に早期解消があり得るのかどうかということが、シーズン後半戦はずっと大きな注目を集めてきた。マルケスの離脱が明らかになったことで、今後の注目ポイントは、選手たちとメーカー間の戦いの構図がどんなふうに変わってゆくのか、そして、長期的な不振が続く日本メーカー、ホンダとヤマハは復活を果たすことができるのか、ということに移ってゆく。
その勢力関係を推測するヒントは、日本GPが行われたモビリティリゾートもてぎのパドックにたくさん転がっていた。そこで、まずは10月1日(日)に決勝レースが行われた日本GPの振り返りと検証からはじめることにしよう。
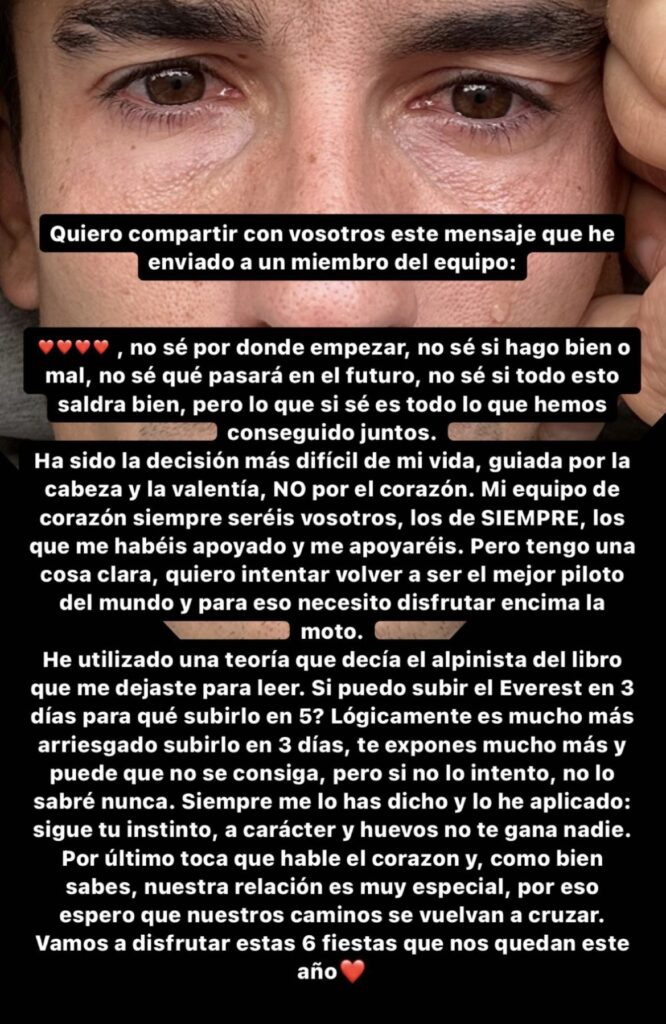
地元日本GPでもダメだったホンダとヤマハ
日本GPは、今シーズンの趨勢を反映してドゥカティ勢が圧倒的な強さを見せつけた。
今年から土曜午後に導入された、決勝の半分の周回数で争う12周のスプリントは、ホルヘ・マルティン(Prima Pramac Racing/Ducati)が勝利。2位はKTMのブラッド・ビンダー(Red Bull KTM Factory Racing)。そして昨年度チャンピオンで今シーズンもランキング首位に立つドゥカティのエース、フランチェスコ・バニャイア(Ducati Lenovo Team)が3位に入った。
日曜の決勝レースは、開始直後から降り出した雨が次第に激しさを増してきたために、赤旗が提示されて中断。当初予定されていた24周の半分、12周でレースが成立した。この決勝レースでもマルティンが優勝。バニャイアが2位で終えたことにより、ふたりのチャンピオンシップポイントはマルティンが3点差まで迫ることになった。
また、この決勝レースでは、マルケス(Repsol Honda Team)が3位に入り、昨年の第18戦(オーストラリアGP)以来となる表彰台を獲得した。かつてなかったほどの不振に喘ぐホンダの苦況を考えれば、この結果はひと筋の光明のようにも見えるかもしれない。

しかし、実際のところは、降りしきる雨で各マシンの特性差が出にくいコンディションの中で、マルケスの卓越したライディング技術が性能面の不利をカバーして獲得した表彰台、と見るべきだろう。その証拠に、ドライコンディションでの計時セッションや予選では、マルケスに限らずホンダ勢は全ライダーが相変わらず欧州メーカー勢に圧倒的な差をつけられる状態が続いた。
それはホンダに限らず、もうひとつの日本メーカーであるヤマハにとっても同様だ。2021年チャンピオンのファビオ・クアルタラロは今回の日本GPを土曜スプリントは15位、日曜の決勝は10位、という非常に厳しい結果で終えた。ちなみに、マルケスのチームメイトは2020年にスズキで世界タイトルを獲得したジョアン・ミルだが、ミルの土曜スプリントは13位、日曜決勝は12位、というリザルトだった。つい先年のチャンピオンで年齢は20代半ばという、アスリートとして最盛期にあるはずのふたりがこのような低位に沈んでいるところが、現在のホンダとヤマハの〈実力〉をよく示している。
対照的に、欧州メーカー勢は絶好調のドゥカティ陣営に加え、KTM勢も良好なパフォーマンスを発揮している。今回の日本GPでは、ビンダーとチームメイトのジャック・ミラーはともにカーボンファイバーを使用した新車体を投入していると明かした。KTM関係者によると、この車体は「新しいコンセプトと技術」を使用したもので、9月のサンマリノGPではテストライダーのダニ・ペドロサが実戦テストを兼ねて参戦した際に、表彰台に肉薄する好結果を残している。

それからわずか1ヶ月弱のうちにファクトリーチームのライダー両名へニューフレームのマシンを供給し、上記のような好リザルトを残すのだから、これはまさしく、企業の斬新かつスピーディな技術開発と実戦からの迅速なフィードバックが好循環を形成していることのあらわれだろう。バニャイアとマルティンの微妙なチャンピオン争いは、KTM勢が彼らの間に入ることで、王座獲得のキャスティングボートを握る可能性も考えられる。
これら欧州メーカーの先進的な開発姿勢とは対照的に、日本メーカーは概して臨機応変な迅速さに欠ける、というのはよく指摘されるところだ。一般的に、日本企業の製品開発姿勢は、万が一のトラブルを避けるために入念な検証を行ったうえで投入するので欧州企業よりも長い時間がかかる、といわれることが多い。入念な品質確認と迅速な現場投入対応は両立させることが難しく、どこで妥協点を見いだすか、というところに企業姿勢の差があらわれる。現在のMotoGPでは、日本企業の保守性が、ドゥカティやKTM、アプリリアの飛躍と進歩に対して大きく後塵を拝する結果に繋がっている。
ホンダワークスよりドゥカティのサテライトの方がマシ
歴史的な低迷が続き、一向に戦闘力が改善する気配を見せないホンダ陣営を離れることが明らかになったマルケスだが、2024年シーズンの移籍先はドゥカティ陣営サテライトチームのGresini Racingだと言われている(10月5日午後12時現在、ドゥカティ側からの正式発表はまだない)。ドゥカティ陣営はファクトリーチームとサテライトを合わせて8台を要する最大勢力で、2024年は最新ファクトリースペックのバイクを4台、実績のある前年仕様(つまり、2023年のファクトリーバイク)を4台、というラインナップで臨むと言われている。サテライトチームの中でもGresini Racingは前年仕様を供給される体制で、つまり、マルケスはドゥカティ陣営に移っても「1年落ち」のバイクでシーズンを戦うことになる模様だ。

そのような背景事情を踏まえたうえで一般論を言えば、サテライトチームに移籍するよりもファクトリーチームに残留するほうが、環境としては圧倒的に有利だ。ファクトリー体制では最新の部品が供給され、ライダーが思いのままにバイクを仕上げてゆくことができるのに対して、サテライトチーム体制で前年仕様を使用する場合は、すでに評価が定まって実績のある安定感を期待できる反面、最新ファクトリーマシンと比較すると性能面ではどうしても一段劣る傾向があるからだ。
だが、それはあくまでも一般論で、ドゥカティ陣営の場合は前年仕様のマシンでも最新スペックを相手に、互角以上のパフォーマンスを発揮している。たとえば2022年は、まさにマルケスの移籍先とされるGresini Racingに所属していたエネア・バスティアニーニが4勝を達成。今年も、サテライト陣営で昨年仕様のマシンを駆るマルコ・ベツェッキが決勝レース3勝、スプリント1勝を挙げ、第14戦日本GPを終えてランキング3番手につけている。これに対してホンダは、ファクトリーの最新仕様でもドゥカティのサテライトマシンと互角に戦えていないのが現状だ。
このような事情を考えれば、「自分はいつも勝つことを目指してレースをしている。トップシックスに入ればいいとかポイントを獲得できればいいというメンタリティではない」と日頃から話すマルケスが、「このままホンダに残っても低位に沈み続けるだけかもしれないが、ドゥカティのマシンならサテライトチームでも充分に優勝争いをできる」と考えたとしてもまったく不思議なことではない。また、アスリートとしてピークの状態で戦える時間が無限にあるわけではない30歳という年齢も勘案すれば、悠長に復活を待っていられるほどの時間的余裕はない、と判断するのも必然の結論かもしれない。
この日本GPの週末には、HRCの渡辺康治社長も現場に姿を現した。練習走行の際にガレージ前のピットレーンで短い会話をする機会があったが、その際に渡辺氏は「今はスピード感を持って様々なことに取り組んでいる最中です。我々のこの弱い時期を、どうかよく憶えておいてください」と述べた。問題は、彼らの言う「スピード感」が現場でライダーたちが求めている様々な変化の「迅速さ」に見合う水準に達しているのかどうか、ということだ。
たとえば、走行初日の金曜にマルケスのバイクには、フロントフォークとハンドルバー近くの部品に小さな変更が加えられていた。だが、その効果については、
「明日は以前の仕様に戻す。ごくわずかな変更で、たしかにリクエストをしていたものだけれども、ああいうことではない。今後また、リクエストしていた部品を持ってきてくれれば試してみたい」
と、性能に改善がなく却下する旨のコメントを述べた。
また、この金曜日の走行では、ミルが2024年プロトタイプの車体を試した。これは9月のサンマリノGP翌日の事後テストでホンダライダー全員が試したもので、ミルはテスト後のインドGPで使用したいと話していたが、配送供給などの事情で間に合わなかったため、その翌戦の日本GP金曜にトライすることになった。
シーズン中に翌年のプロト車体を投入する姿勢は、日本企業の保守性が変わりつつあることの兆候だろうか、とミルに訊ねてみると「そうじゃなくて、もうちょっと単純な話だと思う」という言葉が返ってきた。
「2024年用に開発しているプロトタイプが良好なら使ってみよう、というだけのことで、それが機能するならもちろん歓迎したい。でも、これは2024年に向けて僕たちが求めているバイクではなく、こちらの要求からはまだまだ遠い」
結局、ミルはレースウィークの走行では充分に見極めきることができない、という理由でプロト車体の採用を取りやめた。つまり、このプロト車体には実戦で使用するほどのメリットがないとライダーに判断された、ということだろう。
また、サンマリノGP事後テストでは、サテライトチームの中上貴晶(LCR Honda IDEMITSU)もこのプロトタイプ車体で走行しており、夏には空力面を改良した外装をホンダ陣営でもいち早く採用していたことから、今後のホンダはファクトリー優先という従来の序列を見直して、競合陣営へ追いつくために積極的にサテライトチームを実戦テスト等に活用していくのではないか、という憶測もあった。

これは、ドゥカティがサテライトチームのPramac Racingを活用してアグレッシブな実戦開発を進めてきた方法だ。そこで、走行前の木曜に2024プロト車体を使用する可能性があるのかどうかについて中上に尋ねてみたところ、
「車体の本数が少ないという事情もあると思うのですが、使うか使わないかの選択権は僕たちのチームには与えられていません。もしもHRCから提案されれば、もちろん喜んで試してみたいところですが……」
という言葉が返ってきた。やはり、ホンダの方針は従来どおり、新しい部品などの投入やトライはすべてファクトリーチームを優先させ、サテライトチームにはあくまでも「実績のあるもの」を供給していく、という姿勢に今後も変化はなさそうだ。「スピード感を持って取り組む」とHRC渡辺社長が言うホンダ陣営の〈スピード感〉は、はたしてどこまで切迫した感情なのだろう。そしてまた、彼らは欧州陣営の臨機応変かつ迅速な開発の進化と速度をどこまで皮膚感覚で理解し、追いつき追い越してゆく覚悟を固めているのだろう。
プロフィール

西村章(にしむら あきら)
1964年、兵庫県生まれ。大阪大学卒業後、雑誌編集者を経て、1990年代から二輪ロードレースの取材を始め、2002年、MotoGPへ。主な著書に第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞、第22回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作『最後の王者MotoGPライダー・青山博一の軌跡』(小学館)、『再起せよ スズキMotoGPの一七五二日』(三栄)などがある。


 西村章
西村章











 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


