常盤橋に響く大声
たった金一両を携えて江戸に独行した篤胤が、親類縁者もなく二〇代前半をどのように過ごしていたのかということは実はあまりわかっていない。養子の銕胤が伝えるところによれば、「ただ正義があり学識豊かな良い師を得たいと願って、各地を巡って学問を試みられた。あるときは学問の用事のために使われ、またあるときは生計を立てるために人に雇われ、あるいは仮に主君を取ったりもして日々をやり過ごされたこともあった。その期間はおよそ四、五年に及んだという。その間に経験した苦労や困難は、言葉では言い表せないほどであったと、のちにご本人が語っておられる」[1]というようなものであった。当然、脱藩をして藩からの援助も得られないのだから、江戸という大都市で、たった一人学問の道を探していくほかなかった。
この時期、篤胤が実際にどのような生活を送り、何をしていたのかについては、いくつもの言い伝えが残されている。ただし、それらが史実であるかどうかを確かめる手立てはなく、後世の人びとによる潤色が加えられている可能性は高い。とはいえ、そうした逸話の数々は、篤胤という人物にどのような期待や意味が託されてきたのかを知るうえで、決して無視できない。そこで以下では、史実性の問題を留意しつつ、語られてきた伝承を紹介してみたい[2]。
江戸に出たばかりの篤胤が最初に就いた仕事は、大八車を引く人夫であったと伝えられている。まもなくその仕事を離れ、今度は消防夫として働くようになる。ところがある日、組内で頭に逆らった男が、仲間によって寄ってたかって打ちすえられ、ついには撲殺される光景を目にしてしまう。あまりに残酷な職場いじめに言葉を失い、篤胤はその場を去る決心をしたという。その後、歌舞伎役者・市川團十郎[3]の門下に入り、その家庭教師を務めるようになった。しかし、歌舞伎界の退廃した空気をいやというほど感じ取り、役者の道もまた断念する。そして転じて、ある商家の炊事係として働くことになる。
当時の炊事係は、仕事が終われば基本的に自由で、時間の余裕があった[4]。篤胤が雇われていたのは、常盤橋(現在の東京都千代田区大手町)近くの大きな商家で、夜も明かりがともっていた。炊事が済むと、その灯の下で、すぐさま本を開いたという。しかも読書の仕方が独特だった。音韻の軽重や句読点の切れ目を強調しながら、朗々と爆音で声を張り上げて読むのである。静かな夜気の中、その声は常盤橋一帯にまで響きわたり、行き交う人びとが思わず耳をとめるほどだったと語られている。
常盤橋は、江戸城三十六見附の一つで、江戸幕府では譜代大名が交代で警護にあたる要地であった。ある年、その警護を担当したのが、備中国松山藩主・板倉勝政[5](一七五九―一八二一年)である。早朝の持ち場に立つと、堀の向こうから、やけに大きな音量で本を読み上げる声が響いてくる。毎朝欠かさず続くので、勝政は不審に思い、家臣に調べさせた。すると、近くの商家で働く炊事係が、暇を見つけて読書しているのだという。そう聞いて、その場はひとまず納得した。ところが三年後、再び常盤橋の警護に就いたとき、以前とまったく同じ場所から、あの朗々たる読書の声が、依然として堀を越えて届いてくるのである。今度は見過ごせないと考え、番頭の平田藤兵衛を遣わして詳しく調べさせた。やがて分かったのは、その声の主こそ、若き日の篤胤・大和田正吉であったということである。そこで、お前はこんなところで炊事係をしているよりも、学問をした方がよいという話へと進んだのだという。
もちろん、こうした逸話そのものの信憑性を、史料によってはっきり証明することはできない。それでも、これらが数多く語られるようになった明治時代の状況を考えると、篤胤という人物が〈修身〉の模範として位置づけられ、学問の力だけで身を立てた人物として描かれていったことが見えてくる。実際、秋田藩を脱藩したのちの篤胤には学問以外に頼るべきものはほとんどなかった。だからこそ、こうした言い伝えは、新しい時代を生きる人びとにとって、一つの希望として受け止められたのである。
家格問題で紛糾する恋
おおよそ寛政一一年(一七九九年)前後のことだろうか、二五歳の篤胤は一八歳の少女・石橋織瀬(一七八二―一八一二年)に熱烈な恋をすることになる[6]。当時、篤胤はある旗本屋敷の武家奉公人となっていたのだが、その旗本屋敷で奥つとめをして必要な行儀作法を学んでいたこの織瀬という少女と、激しい相思相愛の関係になったのである。
織瀬は沼津藩士・石橋清左衛門を父、豊島郡沼袋村の百姓の娘を母にもち、兄弟に清右衛門という人がいたという[7]。篤胤がのちに「睦魂あへる人」(霊能真柱初稿)と呼びかけるように、教養のある女性で、相当気が合ったものと思われる。一説には、古本の山の中から織瀬が『古事記』を指差して、「これは、この国の古史であるから必ずお読みください」というように言ったことが、篤胤の国学への端緒となったという話もある[8]。織瀬もまた、気概溢れる若き学者に惹かれ、そのほとばしる実在感に強く恋心を抱くようになった。そしてついには、親がまだ認めてもいないのに二人で結婚の契りを交わしてしまったのである[9]。
しかし当時は私通や駆落ち、すなわち親の許可を得ずして恋仲になるなど言語道断であり、武家出身の織瀬としても篤胤としても死を覚悟しなければならないほどの危ない恋愛であった。そこで二人は、決して短慮を起こさず、現実的に結婚が可能な道をめげずに模索していく。
まず、篤胤の身分をなんとかしなければならないということになった。当時の篤胤は、身分としては、武家の織瀬に全く釣り合わない一介の武家奉公人であったため、まずはいずれかの武家の養子になる必要があった。そこで、上総国久留里藩士・高久喜兵衛が叔父分として奔走してもらう形で、寛政一二年(一八〇〇年)七月、備中松山藩士で山鹿流兵学者の平田藤兵衛篤穏の養嗣子になった。これによって、はじめて「平田篤胤」という名前を名乗るようになる。「胤」とは、生家・大和田家の通り字(同じ家で世代を超えて使用される名前の一字)であり、また「篤」とは養子に入った平田家の通り字である。この養子縁組によって篤胤は正式に松山藩主板倉家の家臣となり、牛込神楽坂の本多家屋敷に転居した。
平田家の養子となった篤胤は、平田家の養父母、そして石橋家の織瀬の両親のあいだを粘り強く行き来して縁談を進めていった。武家である平田家が、養嗣子・篤胤の妻として沼田藩士の石橋家から織瀬を正式に迎え入れるという形をとった。長い交渉の末、両家がようやく折り合い縁談はまとまった。幾度もの行き違いを越え、ふたりが夫婦として結ばれたのは、享和元年(一八〇一年)八月のことである。
しかし、結婚生活の現実は甘いものではなかった。平田家は名目上こそ禄高五十石を誇っていたが、実際には家計は火の車である。夢見た新婚の暮らしどころか、織瀬は家を切り盛りする「母」としての役割を、いきなり背負うことになった。翌年には長男・常太郎を授かるが、幼くして亡くしてしまう。文化二年(一八〇五年)に長女・お長を、そして文化五年(一八〇八年)には次男・半兵衛を出産する。喜びと別れが交錯する日々のなかで、織瀬は家族の中心に立ち続けた。
そのころ、篤胤は次第に国学に魅せられ、学問に打ち込むようになる。家計も時間も余裕のない暮らしであったにもかかわらず、学ぶ夫を支え続けたのは、ほかならぬ織瀬であった。そして、この結婚はおよそ一〇年後、大きな不幸を抱え込むことになるが、それはまた後段に紹介したい。
「没後の門人」の誕生
篤胤が国学者・本居宣長(一七三〇―一八〇一年)の著作に出会い、国学に殉ずることを決心したのは、享和三年(一八〇三年)[10]のことといわれている。宣長と出会った篤胤は、その中に自らの方法論を発見し、国学者として特異な位置を獲得していくのである。世界を分裂したものとしてしか捉えられなかった少年・正吉は、ここにきて宣長という、世界を統合するための一つの柱を発見したのである。初期の著作『伊吹於呂志』(一八一一年)には次のように書かれている。
はじめて宣長先生の著した書物を読み、その内容の尊さに打たれ鈴屋門下(宣長の学派)に入り、古道というものが限りなく尊いのだと、ますます感じるようになったのです。以来、ただひたすらこの道を学び続け、今年で三十六歳になるまで精進いたしました。(中略)この道をできるだけ世の人びとに知らせようとして、先生が書き残された書物は、全部で五十七部にものぼります。その中には、歌物語や音韻について論じたものもありますが、つまるところ、広く人々に「眞の道」を示そうとして著されたものであるからに、あまりに心くばりが細やかで深く心の底から丁寧なので、その書物を読むたびに思わず涙がこぼれるほどでございます[11]。
宣長の著作を読むということは、思わず涙の溢れるような経験であったというのである。そして、それは「眞の道」というものを明らかにしているためであって、言い換えるならば世界を「正しく」見つめる方法というものを、宣長を通して発見したというべきだろう。
本居宣長の著作に出会ったあと、篤胤はすぐにその思想を吸収しはじめた。そして同じ年のうちに、早くも最初の著作『呵妄書』の執筆に取りかかる。これは、儒学者・荻生徂徠(一六六六―一七二八年)の高弟である太宰春台(一六八〇―一七四七年)の『弁道書』(一七三五年)に対する批判として書かれたものである。なお、篤胤の『呵妄書』は習作というべきもので、写本のまま秘蔵され世間に流布されてはいない。
春台の『弁道書』において、「眞の道」とは中国古代の聖王・堯舜の道であり、儒学が伝わる以前の日本には、まだ本当の道はなかったものとされる。儒学は唐土(中国)の道、仏教は天竺(インド)の道、神道は日本の道というのは誤りであって、神道は「巫祝」(鬼神を祀る者)の極めて小さな道であり、聖人の道である儒教を祀らないことは政治が乱れている証であるといった内容が主張されていた。この見解に対し、宣長はすでに「直毘霊」(一七七一年)で反論している。日本には「天地のおのづからなる道」、すなわち非制度的な自然の道があっただけで,それを儒学的な規範意識に仮構された外来の道と区別するため、「神道」というのであるとしてむしろ儒学伝来以前を重要視した。
篤胤の『呵妄書』においては、まず儒教仏教は「偽り作れる道」を「眞の道」と取り違えたものであって、それは大海に流れていく細い川のみを見て、大海そのものを見ないのと同じなのであるというように批判する[12]。「眞の道」はすべての枝葉末節の小川をあますことなく包括するような大道なのである。「眞の道」である神道とは、天地開闢のときから神勅・故事のままを守ってこの国を穏やかに治めてきたものであり、儒教仏教のように人によって作られた人工のものではないのだという[13]。というのも、春台のように考えたならば、聖人が道を制作しなかったならば、世界の人々は土偶の如くぎこちなく動いていたことになってしまう。敬意を表すという点においては同じなのに、天竺(インド)、阿魯亞(ロシア)、漢国(中国)での礼拝の仕方は現に全く違うではないか。だから、聖人の道だけが「眞の道」であって他は違うなどということは狭い見解である、と述べた。
このように儒学批判として第一作は展開されたが、基本的には宣長の結論の範疇を越えるものではなかった[14]。しかし、ここから篤胤は日本固有という点に限らない、「眞の道」というものを模索していくようになるのである。それは何よりもまず、分裂した世界認識そのものを、どれをも偏向することなく捉え、確かに一つ存在するはずのどれでもない「一つの真理」[15]を発見するものとして展開される。この時点で篤胤は、一つの比喩を用いて説明していた。小さな子供が、自分の家の上に照っている月を見て、「これは僕の家が持っている月だ」などいうことはとても幼稚なことだ。月は光のあたらない場所などなく世界万国を平等に照らしておられるのを、どうして我が家のものだというのだ[16]。
日本・中国・ロシア・西洋という、分裂したいくつもの世界認識を、そのどれをも越え出るような「眞の道」が探求されるようになるのである。
宣長はこうした「眞の道」を漢字文化伝来以前の、ある種名状することのできない「天地のおのづからなる道」という消極的な非規定性に見出していた。しかし、篤胤はこれをむしろ、「積極的規範」として転化させたものということができる。わかりやすくいうならば、名状できない消極的なものであった「眞の道」を、むしろどの学知をも包含しうるような一つの真理として積極的に再構築していくことになるといえる[17]。
宣長の議論を正しく理解しながら、そしてそれゆえに、篤胤はその「眞の道」を確かに捕まえるために逆向きに走り出していったのである。
宣長との夢中対面
篤胤にとって唯一悔やまれる事は、宣長が生きているうちに入門することができなかったことである。宣長の著作を来る日も来る日も読んでいるが、果たして生きているうちに宣長の正統な弟子になることはできなかった。自分の学問が正統に認められないような気持ちが強まってくる。すると、文化元年(一八〇四年)[18]のある日、不思議なことが起こった。宣長の息子・本居春庭(一七六三―一八二八年)が篤胤の「夢中対面」について語った文章を引いてみる。

平田篤胤殿は、以前からこの学問の道に強く志しており、故・宣長先生が著された書物を朝な夕なに読み続けて深く信じながら、「どうにかして先生に一度お目にかかりたい」とずっと願っていた。しかし道のりも遠く思うようにならない身の上もあって、ついに実現しないまま終わってしまったことを常に悔しく思っていたが、昨年三月の末ごろのこと、夢の中に人が現れて「さっきまで、宣長先生がここに滞在しておられたが、今まさにお帰りになったところだ!」と篤胤に言うのだ。それを聞いて篤胤は驚き、取るものも取らず急ぎに急いで後を追った。どうにか品川のあたりで追いつき、まずは胸に思っていたことの一端を打ち明け、少しばかりお話をすることができ、ついには先生のお弟子の一人として数え入れていただけた。そういう夢に見たのだ[20]。
篤胤はある夜、奇妙な夢を見たという。突然人がやってきて、宣長先生が今まさにそこに居ったのだけれども、たった今帰路につかれてしまったというのである。篤胤は驚き慌てて、とにかく走って追いかけた。品川のあたりで宣長に追いつくと息を切らして土下座をして、常々心中に募っていた敬慕の念を吐露して入門を願った。すると、宣長はよかろうといって門下に加えてくれたのだという。この夢中対面は、篤胤にとって至上の喜びとなった。そして、直ちに絵師に頼んで描かせたのである。
さらに文化二年(一八〇五年)には筆を執って本居家宗家の春庭に当てて書面をしたため、お伊勢参りする者にこの書簡を託して、鈴屋門への入門を願ったのであった。春庭宛の手紙には次のようにある。
宣長先生の御著作を拝見して以来、先生を敬慕する思いは昼夜やむことがありません。先生がこの世におられた間、私篤胤はそのお名前すら知らず、同時代に生まれ合わせながら、弟子の一人として数えていただくこともできませんでした。それが本当に残念で、恨めしく耐えがたい悲しさを抱え続けていたところ、昨春、不思議なことが起こりました。夢の中で先生にお目にかかり、そのまま師弟の契りを結ぶことができたのです。これはただ私が一途に先生を慕い続けてきた、その心の内を、先生の御霊がご覧くださったからにほかなりません。なんとも有り難いことだと、身にしみて感じております。そこで、この夢の出来事を、松平周防守家中の斎藤彦麻呂という人物に語りました。彼は大平大人(宣長の養子)の門人であり、古翁の御容貌を描くことに長けているので、お願いして肖像画を描いていただきました。それを朝夕拝して先生にお仕えするつもりで日々過ごしているのでございます[21]。
宣長に直接弟子入りする事はできなかったが、宣長の後継者である春庭に晴れて入門することが叶った。春庭は快く篤胤の入門願いを引き受け、先述の夢の説明書きを記したのである。
かくして、篤胤は本居宣長の「没後の門人」として、国学の道を邁進していくことになった。
ロシアという対外危機に対する情報収集
実は、このように篤胤が江戸で過ごした一八〇〇年前後は、日本史にとって極めて重要な転換点となっていた。すなわち、ロシア帝国の極東進出による対外不安の高揚である[22]。
寛政四年(一七九二年)、ロシア帝国ロマノフ朝のエカチェリーナ2世の命のもと、日本人漂流民・大黒屋光太夫を伴ってアダム・ラクスマン(Адам Лаксман,1766-??)が遣日使節として来航し、江戸幕府に通商協定の締結を迫った。ラクスマンが根室に来航したため、松前藩が初動対応にあたって松前に移動させ、幕府側においては老中・松平定信(一七五九―一八二九)が松前では国書を受理できないとして、通商交渉にあたりたい場合は長崎に廻航するように求めた。ラクスマンは入港許可証(信牌)のみを受け取って帰国した。
しかし文化元年(一八〇四年)に、ロシア帝国アレクサンドル一世の命のもと、この入港許可証(信牌)を持って外交使節ニコライ・レザノフ(Никола́й Реза́нов,1764-1807)が来航することになる。采配を握っていたはずの定信がすでに失脚しており、代わりの担当者として老中・土井利厚(一七五九―一八二二)が指揮に当たった。土井は相手にしなければ帰国するだろうと考えていたために、レザノフは半年近く幽閉に近い状態に置かれることになり激怒、部下のニコライ・フヴォストフ(Никола́йХвосто́в,1776-1809)に命じて樺太の松前藩居留地および択捉島駐留地への武力攻撃を指示(フヴォストフ事件)。局地的な戦闘が繰り返され、文化四年(一八〇七年)には、日本人捕虜の返還の際にロシア語、フランス語訳文、日本語訳文(カタカナ)の三種の脅迫文書を持ち帰らせた。そこには「今回ロシア人が日本帝国に与えた損害はごくわずかであったが、それによって、日本の北方領土はいつでも占領され得ること、そして日本政府がさらに長く強情を張り続ければ、その土地を失うことにもなりかねないことを日本側に示そうとしたにほかならない」[23]と記載され、ロシアとの戦争の危険性が現実的なものとして浮上していたものといえる。こうした中、翌年にはナポレオン戦争の余波として、フランス占領下のオランダへの攻撃の一環として英国艦隊フェートン号が長崎に来襲し、長崎奉行の松平康英(一七六八―一八〇八)が責任をとって自害する事態が起こっていた。
実は篤胤は、こうした現実的な対外危機のもと、積極的かつ着実に情報収集を進めていた[24]。まず篤胤はロシア語を自分で勉強し、キリル文字とロシア語の発音の対応表などを載せた「ロシア文字練習帳」「露西亜語」などを作成している。その上で、ロシア史の基本資料として皇帝系譜を綴った「ロシア皇帝系図」やロシア史の略伝である「赤夷伝略」などをまとめていた。また千島列島や樺太の地図として「蝦夷諸島一覧略図」「エトロフ島図」「蝦夷地図」などを転写してまとめ、地理情報の把握にも努めている。幕府翻訳御用レベルでなければ入手困難であったはずのロシア語原文等の外交機密フヴォストフ文書も入手しており、ロシアとの外交緊張の実証的かつ速報的に把握しようとした形跡がある。ほとんど諜報員かのような情報収集によって、対露緊張を把握しようとしていたのである[25]。
文政十年(一八一三年)に完成することになる稿本「千島の白波」は、このように収集した時局情報を編纂してまとめたものであった。フヴォストフ事件の蝦夷地攻撃やフェートン号事件の諸情報を編纂したこの「千島の白波」は、ロシアやイギリスの対外不安に対応して刊行されたのである。添付される関連地図も、探検家の近藤重蔵(一七七一―一八二九)や最上徳内(一七五四―一八三六)に相談して作成しているという周到ぶりである。
「千島の白波」序文には「普通の人にはまったく知られないような秘伝書までもうかがい知ることができたので、互いに照らし合わせて誤りを正し、ますます熱心に取り組んだ。その結果、思いがけず、これほど多くの資料になったのである」[26]と、篤胤によって断りが入れられている。ロシアから戦艦が千島列島、択捉島にやってくる。戦闘があり、脅迫的な外交文書が送られてくる。北方におけるロシアとの外交危機をめぐって、あまりにも多くの情報が錯綜していた。近世前期において国際秩序における日本の地位は静態的なものとして把握されていたが、ロシア帝国の拡張とナポレオン戦争によって、もはや旧来的な図式は意味をなさなくなってしまった。世界は文字通り、分裂していた。ゆえに篤胤は、こうした中で何が実際に起きているのか、今世界そのものをどのように正しく認識するべきかということを問うているのだ。
平田家に養子縁組を済ませ、最愛の妻・織瀬と家庭を築きながら、宣長の国学へと邁進し、迫り来るロシアの危機には迅速に情報収集をしている。そんな行動力の並々ならぬ二〇代の姿をここでは見ることができた。その行動力の源泉は、おそらく「眞の道」の探求という、分裂した世界を捉えるための方法論を獲得したことが大きかった。
世界認識はどうしようもなく分断しても、必ずや神の示すところの「眞の道」がある。そうした確信こそが、篤胤に並々ならぬ行動力を与えた。そしてその勢いのまま、激動の三〇代を迎えることになるのである。
(次回へつづく)
[1] 「唯正義博学ノ良師ヲ得ムトシテ。諸所遊学シテ試ミ玉ヒ。或ハ学事ノ為ニ使ハレ。或ハ糊口ノ為ニ人ニ雇ハレ。又ハ假ニ主取ヲモシテ打過玉ヘルヿ凡四五年。其間ノ艱難辛苦。云ベキヤウ无カリキト。後ニ御自ラ語リ玉ヘリ。外ニ記録ナキ故ニ。ソノ御履歴委ク知ルヿ能ハズ」。平田銕胤「大壑君御一代略記」『新修平田篤胤全集』名著出版、一九七七年、五九七-五九八頁。引用者現代語訳。
[2] 渡辺金造『平田篤胤研究』六甲書房、一九四二年、一九頁、田原嗣郎『平田篤胤』吉川弘文館、一九六三年、八九―九〇頁にまとめられて列挙されるエピソードであるが、どちらもそれを信憑性のあるものとして取り扱っていないことに留意が必要である。
[3] 時代的にこの「市川團十郎」は六代目に当たるが、六代目の襲名が一七九一年で一七九九年に二二歳で亡くなっていることを考えると、おおよそ一七九五年に脱藩してから一八〇〇年までの期間の話であるから信憑性が下がる。したがって山田孝雄・渡辺金造などは、五代目市川團十郎(白猿)を指す可能性を指摘している。
[4] このエピソードは長田偶得や山田孝雄、沖野岩三郎などが紹介するものであり、ここでは山田孝雄『平田篤胤』畝傍書房、一九四二年、五―七頁、沖野岩三郎『平田篤胤とその時代』厚生閣、一九四三年、六五頁を抜粋して紹介している。逸話であることに留意が必要である。
[5] 各伝記には「板倉侯」とあるのみで、具体的に何代目藩主であるかということは明らかにされていない。おおよそ一七九五年に脱藩してから一八〇〇年までの期間の話であるから、当代の藩主が勝政であったため、このように記述している。板倉勝晙である可能性があるが、三年後の警護とあるので少なくとも三年のスパンを考えると、勝政とした方が良いと考えた。
[6] 前妻織瀬との馴れ初めに関しては、基本的には伊藤裕『大壑平田篤胤伝』錦正社、一九七三年、同『織瀬夫人伝』弥高神社平田篤胤佐藤信淵研究所、一九八六年を参照し、その上で現代的な水準での整理については平野日出雄「平田篤胤の夫人織瀬伝の再検討」『神道宗教』神道宗教学会、一一二号、一九八三年、七六―九六頁、宮地正人「三人織瀬」『歴史評論』板倉書房、六七二号、二〇〇六年、五四―六六頁を総合した。
[7] 織瀬の出自に関しては、研究史上議論が分かれるところである。まず、「大壑君御一代略記」においては「水野侯藩士。石橋宇右衛門常房主ノ女」(六〇一頁)とあり、しかし石橋宇右衛門の年齢を鑑みると織瀬とほぼ同世代ということが平野によって指摘されている。一方で、歴史民俗博物館所蔵の「平田篤胤による妻織瀬履歴書付」には「石橋清左衛門何某一子」(宮地正人編「平田国学の再検討」『歴史民俗博物館研究報告』歴史民俗博物館、第一二二集、二〇〇五年、一六四頁)とあり、宮地はこちらの記述に従ったものと思われる。しかし平野の「沼津藩水野家の石橋家史料」検討によると、父とされる清左衛門と一〇歳ほどしか年齢が異ならないものと指摘され、齟齬が生じる(しかし同時に、これも在任期間からの逆算であるから根拠が心許ない)。平野は、織瀬は父も百姓であって、最初、清左衛門との縁談のために石橋家に養女に入ったとする説を唱えているが、本稿では「平田篤胤による妻織瀬履歴書付」にしたがってこれを退け、父を清左衛門と記述した。なお平野説において、石橋宇右衛門を父とするのは形式上の建前であったとする説には従っている。
[8] 国学者・井上頼圀による伝聞。渡辺金造『平田篤胤研究』六甲書房、一九四二年、二一頁。
[9] 「実は、篤胤平田家を相続の前方、或旗本の家に仕へたる時、りせハ其奥に勤居りしを、互に親の許さざるを私に相約して、種々辛苦の上にて双方の親等熟談の上にて、此時に嫁来れるなり」(宮地正人編「平田国学の再検討」『歴史民俗博物館研究報告』歴史民俗博物館、第一二二集、二〇〇五年、一六四頁)
[10] 篤胤が宣長の正統な後継者とするにあたって、宣長の死没年の享和元年(一八〇一年)以前に宣長に出会っていたのかということが大きな争点となり、篤胤の宣長との邂逅は研究史上大きな議論となってきたものである。今回は、ほぼ定説となっている村岡典嗣による享和三年説を参照した(村岡典嗣『宣長と篤胤』創文社、一九五七年参照)。争点となっているのは「大壑君御一代略記」の「今年春初メテ。鈴屋大人ノ著書ヲ見テ。大キニ古学ノ志ヲ起シ。同七月松坂ニ名簿ヲ捧ゲ玉フ」(六〇一頁)であるが、「文化四年三月十六日付大友直枝宛書簡」において「小生事は故翁御沒故は一昨年と申年に、始而御名をさへ承り、且古典をも讀始候事に御座候へば、淺學の所御察可被下候」とある矛盾であった。享和三年説をとる村岡説に対して山田孝雄は享和元年説をとって反論したが、これは三木正太郎によって退けられている。三木は「本居春庭宛書簡」などの新資料によって批判しており、「篤胤が享和元年宣長のもとに入門の名簿を捧げ、その生前の間に間に合わなかつたといふのは事実ではなく、宣長の生前はその名さへ知らなかつたのである。そして享和三年に至つてはじめて宣長の学問に没頭することとなり、文化二年三月宣長ではなくして春庭の門に入門の願書をしたため、春庭は同年六月三日に、入門許可の返書を認めたのであった」(三木正太郎『平田篤胤の研究』臨川書店、一九六九年、三九頁)とまとめている。
[11] 「去る享和元年のことで有ますが。二十六歲の時より。始めて鈴の屋先生の著はされたる書を讀み。其の數の有難き事を知て。其の門に入り、益々古道の。上もなく尊きことを覺えまして。夫よりは。只管に此道を學びて。今年三十六歲になるまで。精勤いたし。(中略)この道を。善く世の人に。知らしめんと致されて。その書き遺されたる書等。すべて五十七部。中には歌物語。音韻のことなどをも。論ぜられたるも有りますが。云ひ以て行けば。普く人に眞の道を示さんとて。著されたることで。その深切丁寧なること。其の書どもを見る每に。淚も落るゝことゞもで御座る」(平田篤胤「伊吹於呂志」『新修平田篤胤全集』名著出版、二〇一三年、一一三頁)。引用者現代語訳。なお、入門時期はここでは「享和元年」となっているが、これは篤胤の心中における理解であるとする三木説を採用し割愛した。
[12] 平田篤胤「呵妄書」『新修平田篤胤全集』名著出版、二〇〇一年、第十巻、一五七頁。
[13] 前掲書、一五一―一五二頁。
[14] しかし、これは宣長学の方法論的基軸に依って書かれたものではなく、実体的な議論が展開される。結論を多く宣長に学びながらも、未だ方法論の獲得には至っていない(田原嗣郎『平田篤胤』吉川弘文館、一九六三年、一〇八頁参照)。
[15] 仏教学者の彌永信美は「一つの世界」が作られていく十九世紀的状況について「真理の一元論」を用いて説明している。「真理の一元論」とは一つの原理によって世界を全て説明できるような魔術的性格の強い真理観のことであり、こうした系譜は西洋と東洋が結ばれた江戸近世の特に平田篤胤において「唯一の神」を求める「一つの世界」への希求へと転化したものとされている(彌永信美「唯一の神と一つの世界」『「一つの世界」の成立とその条件』財団法人国際高等研究所、中川久定編、二〇〇七年、二〇八頁)。
[16] 「譬へば小児の我が家の上に照る月を見て、是は我がいへの月たと云が如くの甚稚きことでム。月は至らぬ隈なく萬國を御照しなされるものをどうして我家ばかりのことだと云ませう」(平田篤胤「呵妄書」『新修平田篤胤全集』名著出版、二〇〇一年、第十巻、一七六頁)。
[17] 「古道は一つの積極的規範となる。既に宣長に内在してゐたこの傾向は彼の没後の門人、平田篤胤によって更に押進められた。歴史的所与はもはや単に所与として受取られずに、古道という一つの政治的「イズム」の批判に服するようになる」(丸山眞男『日本政治思想史研究』東京大学出版会、一九五二年、一八一頁)などを参照しながら再構築している。
[18] これは、山田孝雄の享和二年説を反証した三木正太郎の文化元年説にしたがった(三木正太郎『平田篤胤の研究』臨川書店、一九六九年、三九頁参照)。
[19] 弥高神社編『平田篤胤大人図集』弥高神社平田篤胤佐藤信淵研究所、一九九三年より引用。
[20] 「平田篤胤ぬしの年ごろ道に心ざしふかくてわが故翁のあらはされたる書どもを明くれ見つつし深く信じていかで対面せばやとおもひわたられつるを道のほど遠くかつは心にまかせぬ身にてついにそのことなくてやみぬること、つねにくちをしう思ひためるに去年の三月の末つかた夢に人の来てこのごろ鈴屋の翁のこゝにものせられてありつるが今なむかへられしと告げるにおどろきてとるものもとりあへずいそぎに急ぎておひ行けるにからうじて品川といふあたりに追しきてまづ思ふこゝろのかたはしうちかたらひなどしてをしへ子の数に数へなむくははりぬると見たりつる」『夢中対面の図』より。引用者現代語訳。
[21] 「古翁之御書物共拜見仕候 己來奉欽慕候情昼夜相止候事無御座、世にまし〳〵、候間に御名も不存、同じ時代に生合候身之弟子之数にも入り侍らざりし事、本意なくうらめしく、実に不堪悲痛存つゞけり候所に去春不思義にも翁に見え奉り候而乍夢師弟之御契約申上候、是偏に私義斯斗り慕へ奉り候心庭を、御霊之見そなはし賜候而之御事と如何斗〳〵難有奉存候、則右夢中之事松平周防守様御家中齋藤彦麻呂と申仁、是は大平大人之御門人に而古翁之像を絵書れ候事をよく得られ候故相頼候面掛ものに仕候而朝暮仕奉候事に御坐候」(三木正太郎『平田篤胤の研究』臨川書店、一九六九年、三七頁)。
[22] ロシア対外危機と篤胤の関係については、主に宮地正人「千島白波」『歴史の中の『夜明け前』』吉川弘文館、二〇一五年、三五一―三五五頁を参照した。
[23] “Les Russes ayant cause cette fois si peu de dommage à l’Empire du Japon, ont voulu seulement leur montrer par cela que leurs États du nord peuvent toujours etre investis et qu’un plus long entêtement du Gouvernement du Japon peut lui faire perdre ces terres”(斎藤阿具訳註『ゾーフ日本回想録』雄松堂出版、二〇〇五年、二〇〇頁。引用者翻訳。
[24] 下記資料は平田篤胤関連資料として歴史民俗博物館に収められているもので、宮地正人編「平田国学の再検討」『歴史民俗博物館研究報告』国立歴史民俗博物館、第一二二集、二〇〇五年、一二七―一二九頁および宮地正人ほか編『明治維新と平田国学』国立歴史民俗博物館、二〇〇四年、一六―一九頁参照。
[25] 「常に対外意識に関心を払っていたにもかかわらず、当時の列強の接近を侵略的危機として深刻にとらえていないのである。日本は神国であるが故に、たとえ外国に侵略の意図があっても、いかなる時も神に守られるのだという非合理的な思考は篤胤において絶対的な位置を占めている」(星山京子「新たな知性の誕生―平田篤胤考察」『日本思想史学』日本史学会、第二六号、一九九四年、一二〇頁)という指摘がある。本稿では、対外を意識しながらも、一方で外交的危機に関しては楽観視していたというこの二面性をどう捉えるかということを重要視したい。
[26] 「常人は絕て知られぬ祕記さへに。伺ひ得つれば。互に校合て誤りを正し。弥いそしむにぞ。慮らずもかく多にハなりにける。但し見聞くまにまに廣く書集メたれば。同シ文の重複れるも有れど。其時の事情を知べきものハ、省かずして並べ擧げ」(平田篤胤「千島白波」『新修平田篤胤全集』名著出版、二〇〇一年、補遺五、一頁)。

マイクロビオテックやグルテンフリー、オーガニック……現代において、健康志向とスピリチュアルは密接に結びついている。さらに、そうしたスピリチュアリズムは反動的なナショナリズム運動と結びつき、社会のなかの排外主義や差別と結びついてしまっている。こうした健康志向・スピリチュアリズム・ナショナリズムの根底には、人間が生来持っている「死」への恐れがある。 このような時代の流れをどのように捉えればいいのか?「死」の恐怖から、人間は逃げられないのか?この問いを向き合うヒントは、平田篤胤とその門下生たちが辿った足跡にあった。 本連載では国学研究をおこなう著者が、篤胤を「人間の持つ『死』への恐れを乗り越えようとした思想家」として位置づけ、日本の国学の系譜を総攬することで、恐怖から生まれる反動的な思想を乗り越えるための思想を考える。
プロフィール
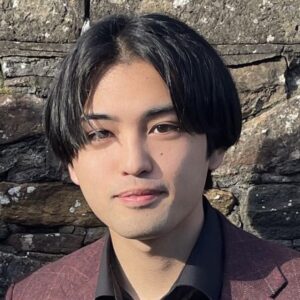
いしばしなおき 宗教学・近世思想史・文学。2001年神奈川県生。論考「ザシキワラシ考」で、2020年度佐々木喜善賞奨励賞を受賞し、民俗学を中心に執筆活動をはじめる(論考はその後『現代思想』「総特集=遠野物語を読む」に掲載)。論考「〈残存〉の彼方へー折口信夫の「あたゐずむ」から」で、第29回三田文學新人賞評論部門を受賞。論考「看取され逃れ去る「神代」」(『現代思想』「総特集=平田篤胤」)の発表以降、平田篤胤を中心とした国学思想を中心に研究を進める。編著『批評の歩き方』等々に寄稿。


 石橋直樹
石橋直樹









 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


