弁論術と共同体
この第4回で、家政学と弁論術をテーマとする第1章はひとまず完結します。教養をメタに捉えるために、3つのスケール、つまりパーソナル/共同体/環境のスケールとそのあいだの循環を見てきました。
前回書いた通り、弁論術は古代ギリシャから古代ローマ、そして中世からルネサンスのリベラルアーツ(自由技芸)のうち、基礎的なものとされた自由三科のひとつ「修辞学」に継承される体系でした。議会や法廷、劇場で、聴衆や議員、陪審員たちを感動させ説得するための技術が弁論術(修辞学、雄弁術、詭弁術)でした。
弁論術は、その場その場の時間(カイロス的時間)での説得力を生み出す技術であり、いわば事実に関わる技術ですが、これに対して永遠不変の時間(クロノス的時間)の真実に関する議論には弁論術とは区別される弁証術があると考えられていました。しかし弁論術を体系化した古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、自然や運命に関連する、いわば環境のスケールに属する「書かれていない法」を弁論術に取り入れています。
今回は、三島由紀夫の代表作のひとつ『金閣寺』と、市川沙央のデビュー作にして2023年の芥川賞受賞作でもある小説『ハンチバック』を取り上げながら、弁論術的なものと共同体のスケールのふたつの側面を論じます。共同体のスケールにはメディアと政治というふたつの側面があり、このふたつの側面によって共同体のスケールが環境のスケールやパーソナルなスケールとどのように循環しているのかを見ていきます。
三島由紀夫 『金閣寺』
『金閣寺』は、『仮面の告白』と並ぶ三島由紀夫の代表作です。1956年に発表され、15万部の大ヒットになりました。
京都の名所である金閣寺で修行していた学僧が、金閣寺に放火するという実際にあった事件をもとに創作された作品です。主人公の溝口は、幼い頃から父親に「金閣寺の美しさ」を聞かされて育ちますが、京都で実際に目にした金閣寺には幻滅を禁じえません。幼少期からの吃音を劣等感として抱えていた溝口は、自分の対極に置いていた観念上の金閣寺と実在の金閣寺とのギャップに幻滅したのでした。「美と幻滅」という三島の重要なテーマが端的に描かれていることが、本作の成功につながったともいえるでしょう。
三島は常陸国宍戸藩藩主を祖先とする名家に生まれ、自分も東京大学法学部を卒業したエリートです。第二次世界大戦中の徴兵に際して、健康状態を理由に不合格とされ、のちの自決事件まで引きずるコンプレックスを抱えたと考えられます。生き延びてしまった、それも、戦って生き延びたのではなく、健康状態の不完全さを理由に国のために命を捧げる機会を取り逃してしまった。美化された死と、その死を得られない自分自身への幻滅。この幻滅は、一億玉砕ではなく無条件降伏という道を選んだ日本国への幻滅、そして終戦まで国家元首であった天皇への幻滅でもあったはずです。「美と幻滅」というテーマは、三島の生涯を通して、戦時中に味わった健康状態に起因する後ろめたさによって常に結び付けられていました。
市川沙央『ハンチバック』
1979年生まれの市川沙央によるデビュー作『ハンチバック』は、2023年、第169回芥川賞に選ばれました。10代のうちから神童として注目されていた三島と違い、市川のデビューは40代です。
『ハンチバック』の主人公は、市川の名前に似た「釈華」という名前を持ち、市川と同じ「先天性ミオパチー」という難病とともに生きています。ミオパチーとは筋肉の疾患の総称です。この難病によって、釈華は人工呼吸器と電動車椅子を使っているだけでなく、紙の書物を読むのにも苦労しています。そんな釈華を主人公にした『ハンチバック』に事件らしい事件が起きるきっかけになるのは、釈華自身のSNSへの書き込みです。自分の身体は出産に耐えられないだろうが、中絶を前提に妊娠してみたい、というその書き込みを、釈華が暮らしているグループホームの男性ヘルパーが読んでいたのでした。釈華は、親が自分のために開設したグループホームに暮らしていますが、そのホームに勤務する年下の男性ヘルパーがその書き込みを見ていたのです。
『金閣寺』と『ハンチバック』は、三島と市川という性別も時代も異なった作者によって書かれていながら、きわめてパーソナルなスケールである「健康」からの距離の感覚が不可欠な作品だといえるでしょう。
メディアと政治
三島が学生時代から文壇で神童として知られていたことは既に触れました。戦後に東京大学を卒業して大蔵省の官僚となっていた三島は、とある編集者の強い説得を経て、いわば再デビュー作として『仮面の告白』を発表します。この『仮面の告白』は当初から高く評価されます。『金閣寺』の方が『仮面の告白』よりも商業的に成功したのですが、それは『仮面の告白』で再デビューして以来、文壇の寵児だった三島がより広い読者を得たということにすぎません。人気作家となった三島は、雑誌やテレビ、映画に登場し、そのパーソナリティを世間に認知されていきます。大資本が底支えするマスメディアという共同体のスケールに、三島は適応したといえるでしょう。しかし、のちに自衛隊駐屯地でクーデターを呼びかけた際、三島は支持を得ることができずに自決することになります。小説やマスメディア出演のような現代的な「弁論術」には長けていた三島ですが、政治という、より古典的な弁論術に賭けた「演説」は空転してしまったのです。これは、共同体のスケールが、小説やマスメディアのようなメディアと、実際に行われる政治とに分裂していることを示しています。
市川の『ハンチバック』は、難病による障害というパーソナルなスケールで語られてしまいそうですが、共同体のスケールと無関係ではありません。釈華が暮らしているのは要介護者たちのグループホームです。釈華の両親が釈華のために設立したこのホームは、「ホーム」というパーソナルとされがちな空間です。しかしこの空間は、介護者と要介護者という立場の違うもの同士の共同体の場であり、また要介護者同士もそれぞれに異なっているという意味で、他者の共同体の場でもあります。元来、ホーム=家はパーソナルなスケールと共同体のスケールの重なる場ですが、『ハンチバック』で描かれるようなグループホームは、このパーソナル/共同体の重なりを強調するものだといえます。
市川沙央の二重性
『ハンチバック』において、釈華が紙の書籍を読むのも困難であることは既に触れました。三島が巧みに使いこなした紙の書籍というメディアは、釈華(と、おそらくその作者である市川)にとって、アクセスすることすら難しいものでした。『ハンチバック』では、この釈華の困難は単にパーソナルなスケールの問題としては描かれていません。次の部分を読んでみましょう。
ヘルパーにページをめくってもらわないと読書できない紙の本の不便を彼女はせつせつと語っていた。紙の匂いが、ページをめくる感触が、左手の中で減っていく残ページの緊張感が、などと文化的な香りのする言い回しを燻らせていれば済む健常者は吞気でいい。出版界は健常者優位主義ですよ、と私はフォーラムに書き込んだ。軟弱を気取る文化系の皆さんが蛇蝎の如く憎むスポーツ界のほうが、よっぽどその一隅に障害者の活躍の場を用意しているじゃないですか。出版界が障害者に今までしてきたことと言えば、 1975年に文芸作家の集まりが図書館の視覚障害者向けサービスに難癖を付けて潰した、「愛のテープは違法」事件ね、ああいうのばかりじゃないですか。あれでどれだけ盲人の読書環境が停滞したかわかってるんでしょうか。フランスなどではとっくにテキストデータの提供が義務付けられているのに……。
(『ハンチバック』市川沙央、文藝春秋)
このくだりは釈華のパーソナルな困難の記述にとどまらない、読書困難者と社会との関係について、メディアと政治をまきこむ共同体の問題として書かれています。
メディアとしての金閣寺
村上春樹『1Q84』と村田沙耶香『コンビニ人間』に触れた際、これらの作品は描かれるのはホームエコノミクスのみで、ポリティカルエコノミーについては語られていない、つまり共同体のスケールが見られないと書きました。しかしその見方は修正が必要です。『1Q84』には、作中世界で大ヒットして世間の注目を集める、ふかえりと天吾による小説がありました。これは間違いなくメディアです。また『コンビニ人間』で古倉が自分を再生させる場所として認識する、作品のタイトルにもなっているコンビニエンスストアは、職場という共同体の空間です。その意味では、『1Q84』と『コンビニ人間』で語られていなかったのは共同体のスケールそのものというより、共同体のスケールの2面性のうちの「政治」の側面だということがわかるでしょう。
さて三島の『金閣寺』に戻りましょう。三島はこの作品のなかで、主人公の溝口にこう語らせています。
敗戦の衝撃、民族的悲哀などというものから、金閣は超絶していた。もしくは超絶を装っていた。きのうまでの金閣はこうではなかった。とうとう空襲に焼かれなかったこと、今日からのちはもうその惧れがないこと、このことが金閣をして、再び、『昔から自分はここに居り、未来永劫ここに居るだろう』という表情を、取戻させたのにちがいない。
(『金閣寺』三島由紀夫、新潮文庫)
ここで、三島は溝口と金閣寺を「戦争を生き延びてしまった存在」として重ねています。ここには、国家のために命をなげうとうとしながら生き延びてしまった三島自身の思想が読みとれます。
金閣寺は、建築というメディアであり、また溝口たち僧侶が集う共同体の場であり、戦争や国家という政治の問題に溝口や三島のパーソナルな思想を結び付けるものなのです。
メディアはカイロスとクロノスを一致させ、隔絶する
「がらんどう」という日本語があります。これはもともと、寺院(伽藍)において、寺院を守護する神仏(伽藍神)を祀る建物を指していましたが、祀られている神仏以外には空間しかないことから転じて「ほとんど何もない空間」を指すようになりました。しかしこの「がらんどう」は、寺社建築に限った性格ではありません。建築物は、その建物の内外を隔てる壁と屋根、それらを支える柱で構成されていますが、この柱に支えられた壁と屋根によって外側の空間と内側の空間を分断しているだけです。高層ビルも地下シェルターも、その内側に空間を作っていることがその存在理由であり、定義上は「がらんどう」であることが不可欠です。
金閣寺は、外壁に貼りつけられた金箔によってその外面がどうしても印象に残りますが、金閣寺もまた建築物である限りは、この「がらんどう」性を持っています。
『金閣寺』は、金閣寺という建築物が、外面のきらびやかさと、内側の「がらんどう」性を表裏一体のものとしてあわせもっていることによって成立している小説です。金閣寺の実物を目にする前の溝口が父親から言い聞かされ、心に抱いていた金閣寺のイメージはまさに、金閣寺の外面のきらびやかさだけが強調されているものであり、建築物として実在している金閣寺を目にして溝口が幻滅するのは、内実を持たない「がらんどう」性つまり現実性に溝口が直面するからです。
『仮面の告白』以降、三島は繰り返しこの外面と内面のズレを描いてきました。それは、美辞麗句や物語の構築性を得意とした三島にとって、そのような外面的で人為的な操作や技術によって、生命を賭すべき真実に到達できるかという問題意識に直結しています。いわば、詭弁で取り繕えるその場その場というカイロス的時間と、永遠不変の真実というクロノス的時間をどのように一致させるのかという問題意識です。
そして三島は『金閣寺』において、空襲を免れた現実の「がらんどう」のカイロス的な金閣寺が、回避されたはずの爆撃によって破壊されるかのように、焼かれることでクロノス的な金閣寺、つまり金閣寺の理想へと合致するという構図を提示します。「がらんどう」であり、また炎によって破壊されうる現実のカイロス的金閣寺は、外面から空想される観念的でクロノス的な金閣寺を憑依させるメディア(霊媒)的な存在として捉えられるのです。
「愛のテープは違法」事件
三島の『金閣寺』に対して、市川の『ハンチバック』には、このカイロスとクロノスを一致させるべく破壊されるようなメディアは描かれていないように見えます。『ハンチバック』には、iPadなどのデジタルデバイスが登場します。人工呼吸器にもモニターがついており、気道の内圧値を表示しています。これらの機器は、数百年から数千年の時を超える文学や文化のようなクロノス的な時間から切り離され、使用者の生命とほぼ同じくらいの時間スパン、つまりカイロス的な時間に属しています。
さきほどの引用箇所で触れられていた”1975年に文芸作家の集まりが図書館の視覚障害者向けサービスに難癖を付けて潰した、「愛のテープは違法」事件”とは、この文学・文化つまりクロノス的な立場の「文芸作家の集まり」が、法律という弁論術的な場面(共同体のスケール)で、視覚障害者たちの読書というカイロス的な立場へのサービスに勝利した事件を指しています。
「愛のテープ」とは、いわゆる紙の書籍を読むのが困難な潜在的読者に向け、図書館等の施設で製作される「録音図書」のこと。1975年には著作権を理由に「愛のテープ」は違法とされ、以後、視覚障害者が書物に触れるのは点字か、録音されていない生の「読み聞かせ」に制限されてしまうことになります。
『ハンチバック』は、ハプニングバーやデリバリーヘルス、グループホームでの売買春のような性的にセンセーショナルな描写が目を引く作品ではありますが、そのセンセーショナルな「外面」の合間に、このような政治的な社会問題が巧みに織り込まれているのです。
『ハンチバック』におけるいわゆるメディアは、一見したところ、紙の書籍と、それに対比されるデジタルデバイスです。しかしこれまで言及していなかった別の「メディア」があります。それは、いま「センセーショナルな『外面』」として挙げたハプニングバーの記述です。ハプニングバーでの性描写は、『ハンチバック』の作中で釈華がBuddhaというアカウントで執筆している「コタツ記事」です。コタツ記事とは、「取材をせず、ほとんどネット上の情報のつぎはぎで粗製濫造された PV稼ぎの記事」のこと。PVとはPage Viewの略で、Webページの閲覧数を指しています。釈華(Buddha)が原稿料のために書いているこのウェブの記事が、紙の書籍でもデジタルデバイスでもない、もうひとつのメディアです。作者である市川が『ハンチバック』という小説を書くように、釈華は「コタツ記事」を書いている。これは、三島が『金閣寺』で自身と溝口を重ね合わせ、カイロスとクロノスを合致し昇華させるために焼かれる金閣寺を描いたこととパラレルなものとして読むことができます。
しかし市川は、カイロスとクロノスを昇華させるべく合致させてしまった三島とは異なります。金閣寺は燃えることによって、作中で束の間(カイロス的時間)だけ、永遠(クロノス的な時間)に美しいものになりますが、「愛のテープ」は違法なままであり、「コタツ記事」は空虚なままです。物語のなかで美を実現させようとする三島に対して、市川は金閣寺の炎上のようなカタルシスを描くのを巧みに避けているのです。カタルシスを避けながらも、釈華の「コタツ記事」や彼女の日々の生活、つまりカイロス的時間は、市川によって作品に描かれることで、文学というクロノス的時間へと組み込まれていきます。クロノス的時間の既得権益者がカイロス的なメディアに勝利した「愛のテープは違法」事件は、この事件が抑圧する釈華の生活や「コタツ記事」とともにあらためてクロノス的時間へと登録され、そこで永遠に問題を告発し続けることになるのです。
新しいメディアとイノベーション
雄弁術、詭弁術、修辞学と呼ばれてきた弁論術は、共同体のスケールを中心に扱う技術であり学問的領域だといえます。そして弁論術は、クロノス的な、つまり永久不変の真善美と、カイロス的なその場その場の利害とを、合致させようとするものでした。
『金閣寺』は、きらびやかな外面によって美の理想とされた観念的な金閣寺が炎上することによって、現実の建築物として不可避的に「がらんどう」性を帯びてしまう実在の金閣寺と一致するという三島らしい思考回路を内蔵しています。
『ハンチバック』には、文学・文化の既得権益者によって、障害者たちの読書機会が法的・政治的に損なわれた「愛のテープは違法」事件が引用されていました。
『ハンチバック』において、「愛のテープ」やデジタルデバイスが重要な意味を占めていることは、三島的な「紙の書籍」的メディアの時代から70年近くを経て、新しいメディアが現れてきている状況を描いています。デジタルデバイスへの拒否感は古くからいつの時代でも声高に言われており、現代でも「紙の書籍がいちばん」という保守的な読者は多数派を占めているでしょうし、これからも多くのレイトマジョリティはデジタルに少しずつ馴染みつつも、苦手意識を持ち続けるのではないかと思われます。それでも、使用者の不便を改善しようとする新しいメディアは、それなしでは読書ができない少数者を救うはずです。
注目したいのは、このような「新しいメディア」「新しいテクノロジー」の登場と普及にはイノベーションが欠かせないということです。
イノベーションとは何か
イノベーションとは、日本語に直訳すると「発明」になります。辞書をひいて「発明」に該当する英語はもうひとつ「インベンション」があります。イノベーションとインベンションは、社会的に普及する発明(イノベーション)と、普及にはいたらないその場だけの発明(インベンション)として対比されることがあります。
イノベーションは市場の発展に不可欠なものとして考えられています。たとえばイノベーションが推奨されない社会主義国における計画経済は、自由競争によってイノベーションが促される自由経済のようには発展できない、と説明されることがあります。
インベンションの例としては、中国で発明された印刷術をあげることができます。しかし、漢字という字数が極めて多い文字体系の中国およびアジア圏では、印刷術の普及に限界がありました。これに対して、基本的に26文字しかないアルファベットを使う欧米において、グーテンベルクによる活版印刷術はまさに画期的なイノベーションとなりました。欧米式の活版印刷術は、のちの産業革命を加速させ、また欧米列強の軍事力や経済力とともにアジア圏に逆輸入されることになります。
『金閣寺』や、「愛のテープは違法」事件で利益を得る既得権益者たちは、このようなイノベーションによる変化を前提にしています。なぜなら、イノベーションは後発世代に利益をもたらすものだからです。いま支配的で保守的に思われがちな「紙のメディア」も、かつては「新しいメディア」としてイノベーションをもたらしたものだったことを忘れてはなりません。
可算的なものとイノベーション
カール・B・フレイ『テクノロジーの世界経済史』によれば、産業革命を推進したイギリス帝国でも、市民革命以前にはイノベーションは抑圧傾向にありました。産業革命を代表するテクノロジーである機械式織機の原型は、市民革命以前に発明(インベンション)されていましたが、圧倒的な生産性を実現する機械の導入によって職を奪われることを懸念した職人たちが宮廷に圧力をかけ、彼らの暴徒化を危惧した国王たちは技術に特許を与えることを拒んでいました。
このような技術抑圧の時代が終わるのは、王権よりも議会が重視されるようになり、またその議会に席を占めるのが世襲貴族ではなく、商人や爵位を買った新興貴族たちになってからでした。経済競争力に直結する「生産性」を重視した商人と新興貴族たちが多数派となった議会では、かつてのようにテクノロジーを抑圧することはできなくなり、かくしてイノベーションが加速する時代が始まるのです。
ここではイノベーションだけではなく、議席という可算的なもの、そして経済合理性という可算的なものが機能しています。
家政学と弁論術を循環しているもの
教養、というよくわからないものを捉え直すため、これまで家政学と弁論術をテーマに書いてきました。そこで重視したのは、パーソナル/共同体/環境という3つのスケールです。この3つのスケールを、循環的に捉えることで、教養を「メタ」に捉えることが可能になる、というのがわたしの主張です。
家政学は、主に家庭というパーソナルなスケールについての政治・経済を扱う学問や技術です。そもそも経済という概念は、古代ギリシャの時代以来、家政学と結び付けられてきました。近代になると、近代経済学が登場し、国家のような共同体スケールのポリティカルエコノミーが提唱され、家政学つまりホームエコノミクスと区別されるようになります。フェミニズムや社会運動の高まりによって、アメリカではホームエコノミクスが学問分野として制度化されるようになりますが、これは女性は家庭のこと(内側)を司り、男性は家の外に出て社会のために働くという、固定観念を再強化するものであり、近年になるまで見直しの必要が議論されてきました。
家政学を捉え直すことは、この内側と外側の役割分担の固定化を再考することです。それは内側(パーソナルなスケール)と、外側(共同体のスケール)とを捉え直すことでもあります。それはつまりイエの内側をあつかうホームエコノミクスと、イエの外側のポリティカルエコノミーを問い直すことです。イエの内と外を隔てる境界を超えているものは何でしょうか。それは貨幣です。共同体のスケールに出て行った者は、家庭に給料や売り上げを持ち帰ります。その貨幣をどのように使うか(消費するか)という課題は、消費者研究という家政学の重要な一部をなします。また、家事労働を賃労働とみなすかどうかという議論もあります。
パーソナルなスケールと共同体のスケールの境界を超えるものはほかにもあります。それは人口です。生と死は、それぞれきわめてパーソナルなものでありながら、それぞれ出生数・死者数として計測され、また記録されることにより、共同体の計画運営にとってとても重要なものになります。パーソナル/共同体という異なったスケールのあいだにあるように思われていた境界は、貨幣や人口などの「可算的なもの」によって通過され、それぞれの意味や働きを与えられています。
弁論術は、家の外、議会や法廷、劇場での演説で聴衆や陪審員、他の議員を説得するための技術であり思想です。その場その場のカイロス的な説得力を生み出す技術であり、永遠不変のクロノス的な真善美を扱う弁証術とは区別されることがあります。しかし、クロノス的な「書かれていない法」を参照することは、時として弁論術に強い力を与えます。これは、共同体よりも大きな環境のスケールの力を借りることでもあります。
また議会や法廷、演劇などのエンターテインメントの領域での説得力は、多数決を採用している民主主義の共同体では強く働きます。これは言い換えれば、可算的なものの力です。そしてこのことは、パーソナルなスケールから共同体のスケールを経由して、あるいは共同体のスケールを経由せずに直接に、環境のスケールへと循環するもうひとつの要素であるイノベーションにも繋がっていきます。
次回は、近代を舞台にして可算的なものとイノベーションがどのように環境のスケールに関わっていくのかを人口論をテーマにして考えていきます。
(次回へ続く)
参考文献
『金閣寺』三島由紀夫、新潮文庫、2020年刊
『ハンチバック』市川沙央、文藝春秋、2023年刊
『三島由紀夫論』平野啓一郎、新潮社、2023年刊
『テクノロジーの世界経済史』カール・B・フレイ 著、村井章子 大野一 訳、日経BP、2020年刊

いま「教養」の分断が生まれている。教養はそれを習得する自己目的な楽しさを持つという「古典的教養論」。グローバルに活躍するエリートビジネスマンには教養が役に立つという「教養有効論」。 この二つは対極のものとして見なされているが、どちらも「教養人」・「グローバルエリートのビジネスマン」といった限られた人々にしか向けられていない。教養人でもグローバルエリートのビジネスマンでもない人が、教養を身につけるにはどうしたらいいのか。それは、教養についての自分なりの解釈を持つこと――すなわち「メタ教養」を身に着けることである。 『積読こそが完全な読書術である』『再読だけが創造的な読書術である』『書物と貨幣の五千年史』などの著作で、本と人間と知の関係性について探求してきた著者が、新しい教養のあり方を構想する。
プロフィール



 永田 希(ながた・のぞみ)
永田 希(ながた・のぞみ)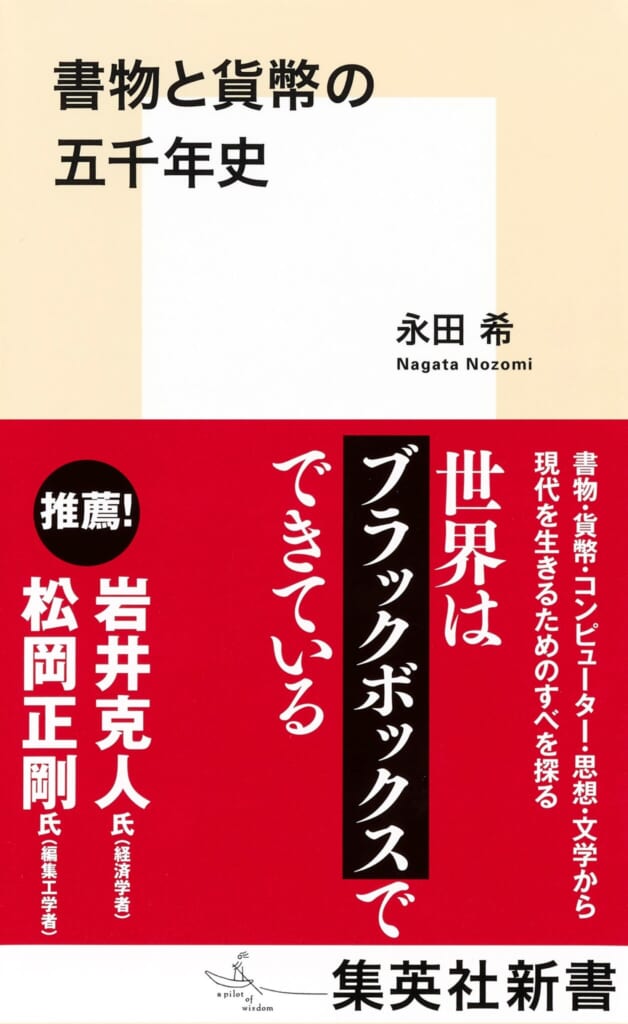










 小島鉄平×塚原龍雲
小島鉄平×塚原龍雲
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


