環境のスケールと人口
ここまで、教養を考えるうえで重要な3つのスケールのうち、パーソナルなスケール、共同体のスケールについて論じてきました。今回は、環境のスケールを主に扱います。その代表として挙げられるのは「人口論」です。「人口」は、ひとりひとりがパーソナルなスケールの存在であり、また戸籍や国勢調査によって共同体のスケールで把握されながら、総体としてはパーソナル/共同体のスケールを包括するもの、つまり環境のスケールとして捉えることができます。
人口とは、ある領域のヒトの数のこと。つまり、本論でいうところの「可算的なもの」そのものです。以下では、この「ヒトの数」を対象に、その増減の変化と社会についての議論を紹介していきます。
18世紀末(1798年)に『人口論』(光文社古典新訳文庫)を発表したマルサスは、当時すでに爆発的に増え始めていた人口が、生活に必要な資源の供給可能な限界を突破するのではないかと危惧しました。マルサスのこの考え方は「マルサスの罠」としてその後しばらく否定されますが、現代では新興国の台頭や環境問題への意識の高まりとともに見直されつつあります。
今回はマルサスの『人口論』の紹介から始め、世界人口の推移を人類発祥から駆け足で振り返ることで、マルサスの時代から現代、そして未来にいたる一貫した流れを捉えます。ここで、産業と技術と労働問題の歴史を研究しているカール・フレイの議論を紹介し、人口とイノベーションの関係に触れます。
くわえて、歴史人口学者エマニュエル・トッドの家族類型分類を紹介し、世界人口が一様に増えているわけではないことや、人口変化の複雑な絡まり合いを見ていきます。
マルサスの人口論
トマス・ロバート・マルサスは、18世紀末から19世紀初頭にかけて活躍したイギリスの経済学者です。彼の著作『人口論』は、人口学の古典的著作とされています。『人口論』の初版が出版された1798年当時、イギリスではフランスとの戦争や物価の高騰などの経済問題が出現しており、対策として救貧法改正の是非が議論されていました。この時期のヨーロッパは産業革命の最中にあり、人口は爆発的に増加していました。また、フランス革命の影響により、ウィリアム・ゴドウィンらの啓蒙思想家が、社会改良による貧困や道徳的退廃の改善の実現を主張していた時代でもあります。
マルサスは『人口論』を通して「人口の原理」を示すことで、ゴドウィンのような革新派を批判しようとしたのです(なお、このゴドウィンという人物は、のちに『フランケンシュタイン』の著者として文学史に登場するメアリ・シェリーの父親です)。
マルサスの主張は次のようなものです。もし人口が制限されなければ、人口は幾何級数的に増加するが、生活資源は算術級数的にしか増加しないため、生活資源は必ず不足する。幾何級数とは、隣接する2つの項の間に一定の商がある系列です。等比数列的、とも言えます。幾何級数と算術級数という用語はかなり抽象的なので、簡単な例を挙げましょう。幾何級数の例は以下のようなものになります。
a. 2, 4, 8, 16, 32…(各項は前の項に2を掛けたもの)
b. 3, 6, 12, 24, 48…(各項は前の項に2を掛けたもの)
c. 5, 10, 20, 40, 80…(各項は前の項に2を掛けたもの)
d. 1, -1, 1, -1, 1…(各項は前の項に-1を掛けたもの)
e. 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625…(各項は前の項に0.5を掛けたもの)
これらが幾何級数の例です。マルサスが人口について主張しているのは増大するパターンなので、d、eは幾何級数ではありますが、ここでは該当しません。当時のヨーロッパの人々には避妊が浸透しておらず中絶も強く忌避されており、しかも2人以上の子供を産むことが多かったので、マルサスは鼠算式に人口が増えていくと考えたのです。これに対して算術級数は、隣接する2つの項の間に一定の差がある級数です。等差数列とも言います。算術級数の例は、以下のようになります。
a. 1, 3, 5, 7, 9…(各項は前の項に2を足したもの)
b. 2, 4, 6, 8, 10…(各項は前の項に2を足したもの)
c. 10, 20, 30, 40, 50…(各項は前の項に10を足したもの)
d. -1, -3, -5, -7, -9…(各項は前の項に-2を足したもの)
e. 0.5, 1.0, 1.5, 2.0…(各項は前の項に0.5を足したもの)
これらが算術級数の例です。この場合も、増大の話なので、dは該当しません。つまりマルサスは、人口は倍々の掛け算で増えるが、その人口を養うはずの生活物資(たとえば食糧)は足し算でしか増えないので、人口の増加を制限しなければ生活物資は必然的に不足する、という主張をしたのです。
この考え方は、当時の古典派経済学者であるアダム・スミスやデイヴィッド・リカードと異なります。彼らは、市場経済が発展すれば下層階級まで富が行き渡り、貧困が解消されると主張していました。スミスやリカードが自由放任主義的だとすれば、マルサスは計画経済的だといえるでしょう。
当時のイギリスでは、社会改良による貧困の救済が主張されていましたが、マルサスは上記のような「人口の原理」を示すことで、社会は貧者を救済できないし救済するべきではない、救貧法は貧者に人口増加のインセンティブを与えてしまうとして、貧困の救済や社会福祉的な改革を批判しました。代わりにマルサスが必要だと主張したのは、予防的制限です。予防的制限とは、人口を意図的に抑制することです。人口増加を抑制するため、計画的に結婚や出産を制限し、人口をコントロールする計画経済的な発想です。
マルサスの罠
冒頭にも触れた通り、マルサスの理論はのちに「マルサスの罠」として否定されることになります。『人口論』が書かれた18世紀末は、自然環境が制約となっていました。たとえば、土地を耕せる場所が限られていたのです。この条件は、まさにマルサスが生きていた時代に進展中だった産業革命によって輸送技術が進歩し、より広範な領域を開拓することが可能になったため、人口増大と食糧増加は調和的に進行するという考え方が主流になりました。
また、マルサスの主張した人口の予防的制限は、たとえば中華人民共和国が採用していた「一人っ子政策」が該当しますが、社会で男尊女卑がまかり通っている場合、生まれてくる子供は選択的に男子ばかりになり、人口における男女比に偏りが生じてしまい、食糧難とは別の社会問題の火種になることが危惧されます。
思想家のミシェル・フーコーは、『性の歴史Ⅰ 知への意志』(新潮社)で、「出産率のマルサス的コントロール」に言及しています。フーコーは「権力」の分析で知られていますが、マルサス的な人口制限はその代表的なもののひとつとして捉えていました(もっとも、フーコーにとってはマルサスの主張と対立する「産めよ殖やせよ主義」も同様に権力のメカニズムとして理解されるのですが)。
しかし「マルサスの罠」は、世界人口が10億人程度だったと考えられるマルサスの時代からしばらくは否定されてきましたが、21世紀になり、人口が80億人になるかという現代、また100億人に到達することもあり得ると予想されるようになり、さらに、食糧生産を含むさまざまな人類の営みによる環境負荷の高まりが意識されるにつれて、再び議論されるようになってきています。惑星規模で人口を捉え、その人口の生活を支える資源の上限を考えることは、国という共同体をこえて環境のスケールも含めて考えることでもあります。
世界の人口推移
国連人口基金は、国連経済社会局人口部が発表した『世界人口推計-2022年改訂版-(World Population Prospects, the 2022 Revision)』をもとに、人類発祥から2100年までの人口推移をグラフや表でまとめています。
以下は、各時代における世界人口の推定値です。2022年に世界人口は80億を超えましたが、以下のような人口爆発が21世紀末まで継続するかどうかは議論の余地があります。人口爆発の収束と世界人口の減少可能性については次回以降に検討するとして、いったんは人口爆発について解説します。
– 紀元前1万年頃:数十万から数百万人
– 紀元前1000年頃:数千万人
– 西暦1年頃:約3億人
– 1500年頃:約5億人
– 1800年頃:約10億人
– 1900年頃:約16億5000万人
– 1950年頃:約25億人
– 1998年頃:約60億人
– 2011年頃:約70億人
– 2022年頃:約80億人
アフリカ大陸に登場した人類の祖先(現生人類)は、集団で狩猟採集生活を営んでいたと考えられます。この時期は、新生代第四期の最終氷期の最中であり、気温や海面の変動が激しかったことが知られています。
紀元前1万年頃から紀元前1000年頃までに農業革命が起こり、穀物や家畜の栽培・飼育が始まります。農業により食糧生産が安定し、定住生活が可能となりました。世界人口は数百万人から数千万人程度に増加し、都市や国家が形成されるようになります。この時期、メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、中国文明、ギリシア・ローマ文明などが栄えました。 これらの文明は、農業や貿易に適した河川流域や海岸地域に発展しました。 紀元前2000年頃にはウル(メソポタミア)が6.5万人、紀元前1500年頃にはテーベ(エジプト)が12万人、紀元前1000年頃にはハラッパー(インダス)が4.5万人となっていたと推測されています。
紀元前1000年頃から鉄器時代が始まり、農業技術や交通手段が進歩しました。世界人口は数千万人から3億人程度に増加したと考えられます。文化や宗教の交流や衝突が活発になり、ローマ帝国や漢帝国などの大帝国が登場するのもこの時代です。紀元前100年頃には漢帝国の都だった長安や洛陽、ローマ帝国の首都ローマの人口はそれぞれ数十万人の規模になり、それから200年後の西暦100年頃には100万人を超える人口を抱える都市が登場するようになります。
マウンダー極小期と小氷期末
人類の人口は、緩やかに増加を続けます。マルサスが登場する18世紀は、気候学で「マウンダー極小期」と呼ばれる時期の終わりとかさなっています。マウンダー極小期とは、1645年から1715年にかけて太陽黒点の数が極端に少なくなり、太陽活動が低下した時期のことを指し、寒冷な時期だったと考えられています。マウンダー極小期は、より大きな時代区分である小氷期に含まれていますが、その小氷期のなかでも、とりわけ過酷だったと考えられます。小氷期とは、14世紀半ばから19世紀半ばにかけて、地球の気候が寒冷化した時期のことです。小氷期のあいだ、多くの地域で厳冬や飢饉が発生しました。
ロンドンは18世紀から19世紀にかけて、人口50万人から約100万人の都市に成長しています。現在のロンドンの人口は、約880万人です。しかしヨーロッパで最も人口の多いロンドンでさえ、実は世界の都市のなかでは上位10位圏外です。ロンドンは、20世紀前半にアメリカのニューヨークにその座を奪われるまでは世界で一番人口の多い都市でした。2000年前、人口が100万人以上と推計される都市は、アレクサンドロス大王が建設したアレキアレクサンドリア、ローマ帝国の都ローマ、そして漢帝国の長安の3都市しかありませんでした。しかし現代では、その倍の200万人以上の人口を抱える都市が、世界中に数百あると考えられています。都市部への人口集中は、21世紀初頭に都市人口が農村人口を上回り、今後ますます加速すると考えられています。
マルサスが『人口論』を発表したのは1798年なので、それまで数千年にわたり10億人未満だった世界人口は、わずか100年後の1900年には15億人を超え、その半世紀後の1950年にはさらに10億人増えて25億人に到達し、『人口論』から200年後の1998年には約60億人になったのです。
『人口論』は「マルサスの罠」として否定されたとはいえ、人口爆発による食糧不足を懸念するのは無理もないことだといえるでしょう。むしろ、人類はなぜこれほどまでの人口増加をしながら文明や社会を崩壊させていないのかと問うべきなのかもしれません。
テクノロジー、イノベーション、人口
オックスフォード大学のカール・フレイの著書『テクノロジーの世界経済史』(日経BP)は、自動化とその結果を分析し、労働者を補完する労働促進技術と労働市場から排除する労働代替技術との区別を示します。
労働促進技術とは、労働者を補完し、生産性を向上させ、新しい雇用の道を開く技術のことです。例えば、産業革命期のイギリスで織物生産を加速させたジェニー紡績機などが挙げられます。
労働代替技術とは、労働者を労働市場から排除し、失業・他業種への転職を強制する技術のことです。産業革命及びそれ以降の工業化と自動化による電灯の普及(ガス灯の点灯・消灯をする仕事を駆逐)、自動車と機関車(馬車の御者を駆逐)の登場が具体例になります。現代では、自動車工場でのロボットが挙げられます。かつて5〜6人の作業員がフレームに特定の車部品を取り付けていた一連の組み立てラインには、現在では人間の代わりにロボットのアームが並んでいます。
フレイによれば、マルサスの『人口論』が発表された頃、1780年から1840年までの期間において、労働者あたりの生産高は約1.5倍になりましたが、労働者の賃金はほとんど変わりませんでした(1.12倍)。そしてこのズレは、現代にいたるまで拡大を続けており、また今後は加速することが想定されています。フレイは、この生産高の増進率と賃金の上昇率のズレを、マルサスが提唱した人口増と生活必要財の増産のズレに重ねて論じます。もっとも、正確には、フレイは労働者が自動化による労働促進技術の恩恵を受ける時代があったことを認めており、生産高の増大と賃金の上昇率のズレは一律に拡大し続けている、と主張しているわけではありません。フレイは、20世紀前半には生産高の増大と賃金の上昇率のズレがいったん拡大をやめていた時期があることを認めています。ズレの拡大は、20世紀後半からふたたび大きくなり始めるのです。これは「マルサスの罠」が、産業革命からしばらくは否定されていながら昨今あらためて見直されていることに似ています。
産業革命はいくつもの要因が重なって爆発的に進行しましたが、その要因のひとつに蒸気機関の発明が挙げられます。蒸気機関は、水を熱して蒸気にして、その蒸気の力でピストンを動かすというものです。ピストンは棒につながっていて、その棒が車輪を回します。蒸気機関は、ボイラーとシリンダーと弁装置という部品からできています。ボイラーは水を沸かして蒸気を作るところです。シリンダーは蒸気でピストンを動かすところです。この仕組みは共同体とは関係のない物理現象に支えられており、環境のスケールにあたります。環境のスケールに学んだ物理学が、イノベーションを通して共同体のスケールへとフィードバックが起きている、わかりやすい例だといえるでしょう。いうまでもなく、物理学は環境の摂理を研究するものです。企業や国家のような共同体は自然環境と直接には関係ありませんが、このとき、物理学を使って利益を生み出すことによって、環境のスケールから利益を引き出しているのです。物理学は環境のスケールを読み解こうとするものであり、共同体のスケールではその発見が産業へと展開されていく過程が進行していきます。また、近年話題とされることが増えてきた気候変動についても、産業革命期に始まった化石燃料使用の爆発的な増大が原因であるとすれば、これも共同体のスケールから環境のスケールへのフィードバックであるといえます。
人口と経済とイノベーションの関係
いずれも人口と貨幣を可算的なものとして扱う人口論と経済学は、当然、密接に関連しています。人口規模は国力の源であり、理論上、人口増加は労働投入量の増加を通じて、経済成長をもたらします。例えば、1990年代以降、中国では増加した労働力が繊維など軽工業に吸収され、急速な工業化に貢献したと考えられています。これは人口ボーナスと呼ばれています。
もっとも、仮に人口が減ったとしても、労働生産性が上昇すれば経済は成長したと捉えられます。一国の経済全体で労働生産性の上昇をもたらす最大の要因は、新しい設備や機械を投入する「資本蓄積」と、広い意味での「技術進歩」、すなわちイノベーションです。
イノベーション理論で知られる経済学者ヨーゼフ・シュンペーターは、人口の増加だけでイノベーションが生まれることはない、と考えました。しかし、人口が増加すると人々は密集して住むようになり、知的な交流や企業間・研究開発者間での競争が生じます。また、増加した人口は、それだけで生活必需品、医療サービスの需要増に繋がり、これもまたイノベーションを促進します。都市化はイノベーションを生み、イノベーションはこれまで人口増加に寄与してきました。しかし都市化は少子化と強く結びついてもいます。都市化と少子化については、次回以降あらためて取り上げます。
エマニュエル・トッドの家族論
フランスの歴史人口学者エマニュエル・トッドは、家族構成や出生率、死亡率などの人口統計的なデータを用いて、世界の歴史や現状を分析する業績で知られています。トッドは1976年の最初の著書『最後の転落』(藤原書店)で、ソビエト連邦の崩壊を予言したとして国際的に注目されました。その後も2002年の『帝国以後』(藤原書店)でアメリカの衰退期入りを指摘したり、アラブの春やトランプ大統領誕生、イギリスのEU離脱などを言い当てたりしていますが、このような「予言」はトッドの仕事の一部に過ぎません。トッドの研究の読みどころは、社会を分析する手法の明確さです。
トッドは家族制度を分類し、それぞれが社会や政治に与える影響を明らかにしようとします。トッドによれば、家族制度は社会の基盤に一定の価値観を埋め込み、無意識のレベルで人々の思想や行動に影響を与えます。トッドの提示している家族制度は、以下の4つの要素で区別されています。
– 親子関係:親が子供に対してどれだけ権威的であるか
– 兄弟関係:兄弟間の平等性や遺産分配の仕方
– 婚姻関係:内婚か外婚か、つまり配偶者を自分の親族内から選ぶか外から選ぶか
– 居住関係:核家族か拡大家族か、つまり子供が成人したら親元から離れるか残るか
これらの要素によって、トッドは世界の家族制度を次の9つの類型に分けています。それぞれの類型は、以下のような特徴を持ちます。
– 絶対核家族:親子関係は独立的で、兄弟関係は無関心で、婚姻関係は外婚で、居住関係は核家族。基本的価値は自由であり、個人主義や自由経済を好む。イギリスやオランダなどに見られる。
– 平等主義核家族:親子関係は独立的で、兄弟関係は平等で、婚姻関係は外婚で、居住関係は核家族。基本的価値は自由と平等であり、民主主義や社会正義を重視する。フランスやイタリアなどに見られる。
– 直系家族:親子関係は権威的で、兄弟関係は不平等で、婚姻関係は外婚で、居住関係は拡大家族。基本的価値は権威と忠誠であり、伝統や階層を尊重する。日本やドイツなどに見られる。
– 外婚制共同体家族:親子関係は権威的で、兄弟関係は平等で、婚姻関係は外婚で、居住関係は拡大家族。基本的価値は共同体と連帯であり、集団主義や社会主義を支持する。ロシアや中国などに見られる。
– 内婚制共同体家族:親子関係は権威的で、兄弟関係は平等で、婚姻関係は内婚で、居住関係は拡大家族。基本的価値は共同体と閉鎖性であり、他者や変化に対して敵対的な態度をとる。アラブ諸国やトルコなどに見られる。
– 内婚制核家族:親子関係は独立的で、兄弟関係は無関心で、婚姻関係は内婚で、居住関係は核家族。基本的価値は自由と閉鎖性であり、個人主義や保守主義を好む。アイスランドやフィンランドなどに見られる。
– 独立系拡大家族:親子関係は独立的で、兄弟関係は平等で、婚姻関係は外婚で、居住関係は拡大家族。基本的価値は自由と連帯であり、民主主義や福祉国家を支持する。スウェーデンやノルウェーなどに見られる。
– 権威的拡大家族:親子関係は権威的で、兄弟関係は不平等で、婚姻関係は外婚で、居住関係は拡大家族。基本的価値は権威と階層であり、専制政治や軍事力を重視する。インドやパキスタンなどに見られる。
– 無構造型家族:親子関係も兄弟関係も緩やかで、婚姻関係も内婚も外婚もあり得る。基本的価値は多様性と寛容性であり、自己表現や創造性を尊重する。アフリカの一部の地域に見られる。
もっとも、これらは過度に恣意的だと批判されている考え方でもあります。たとえばここで「親子関係は権威的で、兄弟関係は不平等で、婚姻関係は外婚で、居住関係は拡大家族。基本的価値は権威と忠誠であり、伝統や階層を尊重する」という「直系家族」が日本にみられるとされていますが、実の日本には、とうぜんもっとずっと多種多様な家族があります。トッドも、世界の80億の人口を構成している無数の家族を、ここまで単純な類型に分類しきることが可能だとは考えていないでしょう。トッドの提示している類型は、厳密さよりも明快さのために使われていることを忘れてはいけません。
日本という地域だけに注視したとしても、そこには1億人を超える人口があります。トッドの提唱しているたった9つの類型で、日本のすべての家族を分類することなど、荒唐無稽以外の何物でもありません。ましてや、今となっては80億人にも100億人にもなろうという世界人口を対象とするならば、その乱暴さはいうまでもありません。それでも、かつてマルサスが人口増加と生活物資の増産をそれぞれ幾何級数と算術級数というきわめて単純化されたモデルで捉えようと試み、そこに現代から未来にかけての問題に通じる部分があるように、多少は乱暴であっても類型を用いることでみえてくるものがあるのです。なお、本論でわたしが「可算的なもの」と呼んでいるのは、個々の差異をいったん無視して「数」へと個物を抽象化する働きに深く関係しています。個々の差異、つまり「数えられないもの」はもっぱらパーソナルなスケールのものと思われるかもしれません。しかしたとえば「日本」とか「イギリス」といった個々の共同体それぞれの人口が、環境のスケールである世界人口へと合算されるとき、共同体のスケールのそれぞれの差異もまた捨象されるのです。抽象化され扱いやすい単なる数字になった「可算的なもの」は、常により具体的で捉えにくい「数えられないもの」への還元を意識しながら扱わなければなりません。人口論は、それをわかりやすく示す一例だといえるでしょう。
次回へ続く
参考文献
『人口論』マルサス、斉藤悦則 訳、光文社古典新訳文庫、2011年刊
『人口の世界史』マッシモ・リヴィ-バッチ、速水融 訳、東洋経済新報社、2014年刊
『2050年 世界人口大減少』ダリル・ブリッカー、ジョン・イビットソン、倉田幸信 訳、文藝春秋、2020年刊
『テクノロジーの世界経済史』カール・B・フレイ、村井章子・大野一 訳、日経BP、2020年刊
『最後の転落』エマニュエル・トッド、石崎晴己 訳、藤原書店、2013年刊
「進む都市化とHabitat3」白戸智、三菱総合研究所、2015年10月21日
‘World Population Prospects: The 2002 Revision Volume II Sex and Age Distribution of Populations’United Nation,2003

いま「教養」の分断が生まれている。教養はそれを習得する自己目的な楽しさを持つという「古典的教養論」。グローバルに活躍するエリートビジネスマンには教養が役に立つという「教養有効論」。 この二つは対極のものとして見なされているが、どちらも「教養人」・「グローバルエリートのビジネスマン」といった限られた人々にしか向けられていない。教養人でもグローバルエリートのビジネスマンでもない人が、教養を身につけるにはどうしたらいいのか。それは、教養についての自分なりの解釈を持つこと――すなわち「メタ教養」を身に着けることである。 『積読こそが完全な読書術である』『再読だけが創造的な読書術である』『書物と貨幣の五千年史』などの著作で、本と人間と知の関係性について探求してきた著者が、新しい教養のあり方を構想する。
プロフィール



 永田 希(ながた・のぞみ)
永田 希(ながた・のぞみ)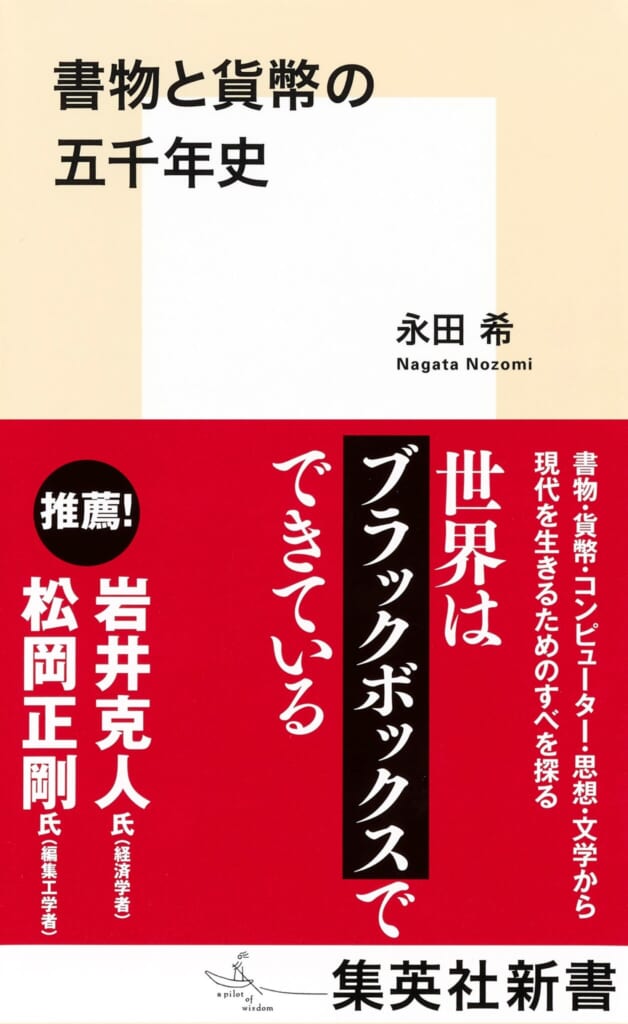










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

