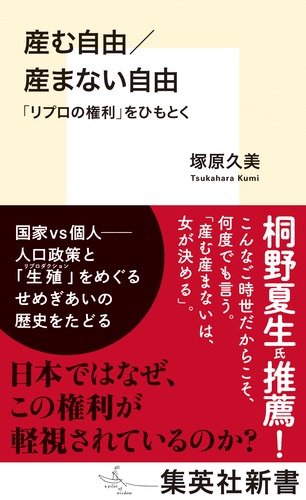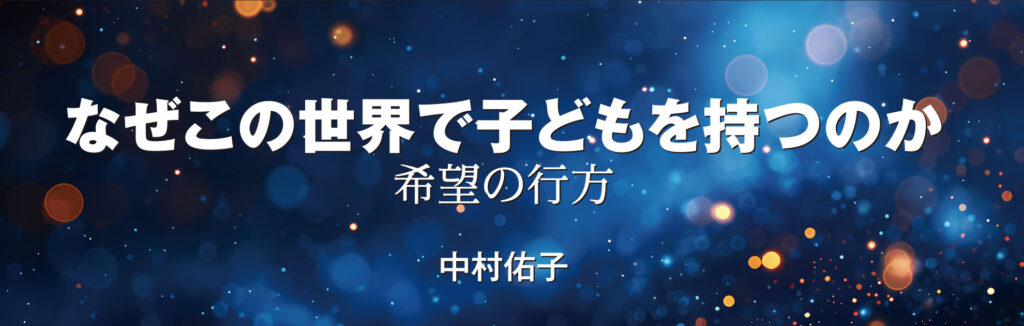近年、少子化対策を「国家の危機」と捉え、「若い女性たちにもっと子どもを産んでもらおう」という圧力がさまざまな形で強まっています。そうした動きが世界の「常識」からいかに外れたものかを指摘するのが、今年(2025年)9月に刊行された『産む自由/産まない自由 「リプロの権利」をひもとく』(集英社新書)です。著者の塚原久美さんは中絶問題の研究者として、「リプロ(生殖)」の権利が日本で守られていないことを訴え続けてきました。この問題に対し「それはおかしい」と声を上げる若い世代の一人が、「#なんでないのプロジェクト」「#緊急避妊薬を薬局で」などの活動に取り組む福田和子さんです。「リプロ後進国」の日本で「産む自由」「産まない自由」をどう実現させていくか、前編に続き、お二人の対話から考えていきます。
構成/加藤裕子 撮影/織田桂子

少子化だから女性は子どもを産むべき?
福田 前編では、日本はリプロ後進国だという話をしてきましたが、世界の潮流に沿って、リプロの権利があたりまえに尊重される社会になっていた可能性もあったんですよね。『産む自由/産まない自由』の中で、1999年に男女共同参画社会基本法が制定された流れから、2000年前後、リプロの権利に関する法改正や新法を求める動きが活発化したことが紹介されています。「日本でここまでリプロの議論が進んでいたなんて!」とびっくりしましたが、特に民主党が2006年に作成したとされる法案では、避妊や不妊手術、人工妊娠中絶の選択が「国の人口政策の対象」ではなく「個人の基本的人権」と謳われていて、「こんなまともな話がこの時期にされていたとは!」と思いました。でも、この画期的な法案を誰が書いたのかは、わかっていないんですよね。
塚原 そうなんです。国会に提出された形跡はないし、民主党も解党され、今では「民主党アーカイブ」というウェブサイトにひっそりと残っているだけです。具体的に党内でどのような議論が交わされたのかということも含め、詳細は明らかになっていません。
福田 もう20年近く経っているわけですしね。この記事を読んだ方から、何か情報が寄せられればと思います。
塚原 2000年代初めの日本では、日本産科婦人科医会や民間団体からもリプロの権利を求める声が上がっていました。でもそれが大きな動きになる前に、第二次安倍政権発足に伴う保守勢力の伸長で、大きく後退させられることになりました。
福田 性教育への激しいバッシングもありましたし、男女共同参画についての方針もどんどん中身が変わっていったということが、『産む自由/産まない自由』を読むとよくわかります。元々は性差別の解消に取り組むはずだったのに、それが実現されないまま「女性活躍」に置き換えられていき、性別役割分業等はそのままに会社等での「活躍」を求められた結果、「仕事もケア役割も担わないといけないなんて大変すぎる、だったら活躍しなくていい、専業主婦になりたい」という若い女性たちの声も聞かれるようになりました。
塚原 「専業主婦になりたい」と言っても、今は共働きでないと生活が苦しい家庭も多いですから、なかなか難しいですよね。「家事も育児もちゃんとやって、仕事でもしっかり稼いでこい」と言われ続けた女性たちが、「もう無理!」と思うのは当然です。
それで何を最初に捨てるかというと、その人自身が生きていくために一番必要がないもの、つまり生殖なんです。「自分1人が生きていくことで精一杯」という時に、子どもを生み育てることなど考えられないでしょう。要するに、日本では「産まない自由」だけではなくて「産む自由」も保障されていないんです。「少子化問題」の責任は、女性差別の問題を置き去りにし、子どもを産めば困窮してしまうような社会を作ってきた政治が負うべきなのに、「女性のわがままのせい」という話になってしまっています。

福田 この前、知り合いの高校の先生から聞いた話で、女子生徒たちから「少子化だから、自分たちは子どもを産まないといけないんでしょ?」と言われたというんですね。その先生は30歳前後、私と同世代のシングル女性なんですが、「日本は少子化で大変なのに、なんで先生は結婚しないの?」と聞かれたそうで、これはしんどいですよ。
塚原 今、「若いうちに結婚して子どもを産みましょう」というライフプラン教育を学校で盛んにやっていますからね。自治体の婚活支援もそうですが、「産ませるために、ここまで露骨にやるか」と思います。
福田 こども家庭庁の政策でも、妊娠・出産・そのための健康維持について教えるプレコンセプションケアにすごく力を入れていますよね。なぜ「産む」ことだけにこれほど重きが置かれるのか、非常にアンバランスです。
塚原 いくら無理やり産ませようとしても、女性に多くの負担を課す構造が変わらない限り、少子化は続くでしょう。子どもの自殺も増え続けているし、今生きている人間さえ大切にできない世の中で、「子どもを産もう」とはなりませんよ。
福田 さっきの女子高校生たちの「産まないといけない」という言葉は「産みたい」とは違いますよね。結婚・出産がデフォルトで組み込まれるライフプラン教育ではなく、「自分たちが本当にしたいことは何だろう?」ということを考えられる、本当の意味でのライフプランを支える教育が必要だと思います。
「少子化だから産め」という圧をかけられている女子生徒たちの中にも、「きついなあ」と思っている子がいるのではないでしょうか。そういう女の子たちに『産む自由/産まない自由』を読んでもらって、「少子化だから女性は子どもを産まないといけない」という理屈のおかしさを知ってほしいですよね。「え⁉ ○○ちゃんは子ども欲しくないの?」「少子化なのに」と言われたら、「これが目に入らぬか!」と差し出せるように(笑)、学校の図書室にも置いてもらいましょう。
塚原 高校生ぐらいまでは、「産む自由」「産まない自由」と言われても、まだピンとこない子も多いかもしれませんが、「そうか、産まないことも自分で決めていいんだ、世界ではそれは権利なんだ」とわかってもらえると嬉しいですね。
福田さんたちが頼もしいなと思うのは、SNSなどを使った今どきの発信が上手だということもあるけれど、英語の情報にアクセスできるということも、活動をしていく上ですごく大きいと言えます。リプロの情報は言語の壁が高くて、なかなか日本に入ってこないのですが、「世界ではこうなんだ」ということを知ってもらい、今の状況を変えていきたいですね。
その意味では、若い子に限らず、幅広い世代の女性たちにこの本を読んでほしいです。「女性は結婚して子どもを産むべし」という価値観に縛られてきた人たちが「これまで教え込まれてきたことはなんだったんだ!」と怒りに燃えるということがあってもいいし、アンラーニング、つまり社会から刷り込まれてきたことを正しい知識でリセットしていけば、考え方は変わっていきますから。
そういうアンラーニングのために今、ふたつのプロジェクトを進めているんです。ひとつは中絶カウンセリングの本で、これは中絶で悩んでいる人に直に接するカウンセラーのマインドセットを変えることで、カウンセリングを受ける側のアンラーニングを目指しています。
もうひとつは、中絶に偏見を持っている医療者対象の、人権をベースとした研修プログラムで、既に世界で実施され、高い効果をあげています。最近、このプログラムを実施するための一般社団法人を設立したところで、来年から研修をスタートさせる予定です。
福田 すごい、ふたつともぜひ実現させてほしいです。
バックラッシュの時代をどう生き延びるか

福田 これからはリプロの権利にとって厳しい時代になることが予想されます。海外ではトランプ政権下で中絶の権利が厳しく制限され、日本でもバックラッシュを推し進めた安倍政権の流れを汲む高市政権が発足しました。また、ネットの言論空間では、ジェンダー関連の活動をしている人たちに対するハラスメントが、本当に暴力的なものになっています。少し前までは「日本がしんどくなったら、海外に逃げよう」という考え方も正直あったのですが、これだけ世界的に極右運動や移民排斥の動きが強くなってしまうと、それも難しくなるでしょう。
こういう世の中で何ができるだろう、と考えるんですけど、今は地道に足元を固めることも大事だと思っているんです。自分がこれまで活動していて辛くなった時、やっぱり支えになったのは想いを共にする仲間の存在でした。オンラインの活動も増えてきて、その意義は認めつつも、フェイス・トゥ・フェイス、直接顔を合わせる繋がりは大切にしたいですし、それができるコミュニティを守っていきたいと思います。特に地方在住の女性たちと話すと、その孤独感や置かれている状況の凄まじさは、東京の比ではありません。彼女たちが絶望せずにいられる場所を作っていけたらと思います。
塚原 私も地方在住なので、地方の女性たちの閉塞感はよくわかります。「フェイス・トゥ・フェイスの繋がり」という話でいうと、私が尊敬しているMarge Bererさんというリプロの権利の活動家が「まず、隣の人から始めよう」と言っているんですね。パブリックに、大勢に向かって話すのではなく、自分の横にいる人にリプロの話をしていく。これ、実はとても難しいことだけれども、そういうことができる場を増やしていくことが大事になっていくと思います。
運動を発展させていくためには「仲間」を増やすことが不可欠ですが、「自分たちと異なる人々」とも手を結んでいくことが大事です。それぞれの関心事が少々ずれていても、共通の目的を持っているのであれば、その部分だけでも「連帯」し、これは無視できない大きな活動なんだということを社会に示していく。そうすれば、孤立している個人も集まってきますし、「大きくなればなるほど強くなれる」の実現につながります。これは今後、意識的にやっていかないといけないことだと思いますね。
また、世代を超えた継承は、とても重要です。世代が変わるたびに、新たに一から始めなければならないのでは、運動はなかなか前に進めません。私自身も、前の世代に手を差し伸べられてきたからこそ今があると言えます。2000年代にWHOの中絶に関する公式文書を日本語に訳してきた「すぺーすアライズ」の麻鳥澄江さんと鈴木文さんが声をかけてくれなかったら、私は単なる研究者にすぎず、アクティビズムの道に進むことはなかったかもしれません。お二人は私より上の世代のフェミニストの中では本当に貴重な中絶の権利の擁護者です。
福田 活動を始めて思ったのは、安倍政権下の激しいバックラッシュの中でも、先輩たちは生き延びてこられて、その蓄積を受け取っているんだな、ということです。塚原さんが翻訳に携わった『新版 中絶と避妊の政治学』(ティアナ・ノーグレン著 岩本美砂子監訳 塚原久美・日比野由利・猪瀬優理訳/岩波書店)をはじめ、なんとかして日本にリプロの情報を伝えようという努力をされてきた人が昔も今もずっといる、その流れを途絶えさせないようにしていきたいです。
塚原 最初に『中絶と避妊の政治学』を翻訳企画した時(旧版は2008年に青木書店から刊行)もそうでしたが、厳しい時代だからこそ、地道な活動と情報提供を続けていくことが必要なのだと思います。このところフェミニズム関連の本がたくさん出版されている様子を見ると、今は種まきの時期と言えるかもしれません。
福田さんも、哲学者の高井ゆと里さんと雑誌「エトセトラ」2025年冬号でSRHRに関する特集を組まれたとのこと、おめでとうございます。とても楽しみにしています。欲張りかもしれませんが、さらに、緊急避妊薬OTC化という目標をとりあえずクリアできた今の段階で、「#緊急避妊薬を薬局で」の経験を書籍化し、ぜひ多くの人と共有してほしいです。成功体験の「モデル」があることで、自分も何かしてみたい人の背中を押すことにもなるでしょう。
福田 そんなふうに言っていただけて恐縮ですが、嬉しいです。本という形で伝えていくことも含めて自分に何ができるか、考えたいと思います。今日は、リプロのことを塚原さんとじっくり話せて嬉しかったです。
塚原 こちらこそ、ありがとうございました。これからも一緒に頑張りましょう!
プロフィール

(ふくだ かずこ)
大学在学中のスウェーデン留学をきっかけに、日本でのSRHR(性と生殖に関する健康と権利)実現を目指す#なんでないのプロジェクトを開始。スウェーデン・ヨーテボリ大学公衆衛生学修士号取得、国連機関勤務等を経て、『#緊急避妊薬を薬局でプロジェクト』、W7Japan共同代表等として政策提言等を展開。現在、東京大学多様性包摂共創センター特任研究員。Forbes Japan 30 under 30 2023受賞。共訳に『国際セクシュアリティ教育ガイダンス[改訂版]』(明石書店)。

(つかはら くみ)
中絶問題研究家。1961年生まれ。国際基督教大学卒業。翻訳者・ライターを経て、自身の妊娠・出産を機に中絶問題研究を始める。2009年、金沢大学大学院社会環境科学研究科で博士号(学術)取得。公認心理師資格を得て、中絶ケアカウンセラーも務める。著書に『中絶技術とリプロダクティヴ・ライツ』(勁草書房)、『日本の中絶』(ちくま新書)、共訳書に『新版 中絶と避妊の政治学』(岩波書店)など。


 福田和子×塚原久美
福田和子×塚原久美