出自で命の重ささえ変わる──残酷なカースト制度が根づくインド社会において、底辺に生きる人々が被る理不尽さは過酷そのもの。池亀彩氏(社会人類学者)の『インド残酷物語 世界一たくましい民』は、そんな格差・差別当然の社会でたくましく生きる人々の姿を活写した。
その池亀氏がインドの紀行文学の最高峰としてあげるのが、ウィリアム・ダルリンプル(スコットランドの作家・歴史家)の『NINE LIVES』だ。インドに息づく鮮烈な伝統、信仰、歌、舞踏の世界を描いた、この世界的ベストセラーの日本語版を長年熱望してきたが、パロミタ友美氏の翻訳でついに実現。『9つの人生 現代インドの聖なるものを求めて』として今年1月に刊行された。パロミタ氏は、ダルリンプルの物語にも登場するバウル(ベンガル地方で歌い継がれる修行歌の伝統)の行者でもある。池亀氏、パロミタ氏とも、インドに長年暮らし、カオスを生き抜く人々に接してきた。ふたりが見つめ続けてきたインドは、強く、たくましく、深い。
構成・文=宮内千和子 写真=神崎真優
インドの多様な地域言語の魅力
池亀 パロミタさんは、このダルリンプルの本を出すにあたって、ヒンディー語やタミル語、カンナダ語など、各インド言語の日本語表記の監修をきちんとつけていらっしゃる。カンナダ語の監修は私がやらせていただきましたが、インド諸言語へのリスペクトが感じられて、本当に感心いたしました。
 パロミタ 各言語への監修は絶対必要だと思っていました。今回は可能でしたが、もし刊行が別の出版社で予算的に無理だった場合は、ポケットマネーでもやるしかないというぐらいの覚悟はありました。ヨーガの本もそうですが、インド関係の本を読んでいると、違和感がある日本語の表記でテンションがどんどん下がっていくということが多くて(笑)。翻訳書でありがちなのは、英語以外の言語へのリスペクトがとても低いこと。もうちょっと確認しようよということが多くて。インド関係の読み物でも、一人でもサンスクリット語とかヒンディー語とかの監修を入れたら、すごくよくなるのにと思うことがたびたびあります。愛情と熱意が明らかに感じられるときほどせつなくなっちゃう。
パロミタ 各言語への監修は絶対必要だと思っていました。今回は可能でしたが、もし刊行が別の出版社で予算的に無理だった場合は、ポケットマネーでもやるしかないというぐらいの覚悟はありました。ヨーガの本もそうですが、インド関係の本を読んでいると、違和感がある日本語の表記でテンションがどんどん下がっていくということが多くて(笑)。翻訳書でありがちなのは、英語以外の言語へのリスペクトがとても低いこと。もうちょっと確認しようよということが多くて。インド関係の読み物でも、一人でもサンスクリット語とかヒンディー語とかの監修を入れたら、すごくよくなるのにと思うことがたびたびあります。愛情と熱意が明らかに感じられるときほどせつなくなっちゃう。
池亀 その気持ちよく分かります。パロミタさんは、初めにサンスクリットを勉強されたんですか。
パロミタ そうです。古代文化のほうに関心があって、むしろ現代インドには特に興味がなかったので。
池亀 そこがすごいですよね。サンスクリットは、私も半年ぐらいやってすぐ断念したんですけど、「ザ・文法」という感じの言語で。これをしっかりやっておくと、あとは楽じゃないですか。そんなことない?
パロミタ いや、そんなことないですよ。サンスクリットは古代から文法が整理されて保存されてきた言語なぶん、文法がはっきりしているので、それ自体はちゃんと学んで分かればそんなに難しくないけれど、問題は語彙なんです。私なんかは全然語彙が足りないから、辞書引き引きじゃないと読めないし、それでも理解が厳しいのは、海のような語彙を前提とした言語文化だから。でも、現代の言語は文法や表現がよりフレキシブルなので、そっちはそっちでまた大変なんですよね。
池亀 確かに。いわゆる州言語は文法なんてあってないようなものだし、例外も多いですしね。
パロミタ ベンガルで、電話越しに「チョッラム、チョッラムচললাম, চললাম 」と言うと、今すぐ行くねとか、これから出るところ、というニュアンスの言葉なんですが、文字どおり直訳すると、「私は行った、私は行った」という意味なんですね。全然動いてもないのに、何ならそれから数十分別れの挨拶をダラダラしたりするのに、行ったと言う表現がすごくおかしいなといつも思っているんですけど(笑)。
池亀 カンナダ語でもそうです。すぐ行くねというのを「バンデ、バンデ ಬಂದೆ ಬಂದೆ」って言う。来た来たという意味で、文法的には過去形なんです。でも、あなたまだ向こうにいるじゃんみたいな(笑)。それを、来た、来たと言うんです。
パロミタ 私は、サンスクリット語からマラヤーラム語、その後、ベンガル語を学んだのですが、サンスクリットを先にやっておくと、日本語で言うと先に漢字を習っておくのと同じような楽さがあります。共通項や変化も理解しやすいですし。現代語だけをやるのって「漢字を知らずに日本語ペラペラ」みたいなすごさというか、生活ベースの力強さがあると純粋に思うんですけど、こういうこと言うと変な謙遜に取られたりするのですが、本当にそう思っていて。ベンガル語はサンスクリット語の子孫ですが、ドラヴィダ系のマラヤーラム語も、カンナダ語もすごくサンスクリット語彙が多いですよね。
池亀 そうそう。とにかくインドには地域言語というか、地方語がたくさんあって、1650あると言われていますね。公式言語は22かな。中にはカルナータカ州のトゥル語のように、独自の文字のない言語もあります。
エリートのキッチンランゲージ
パロミタ 都市部を中心として、英語やヒンディー語が広まっていく傾向にあるので、その結果として、若い世代に行けば行くほど、一部では地域言語や元の母語が弱くなっていく感じはありますよね。
 池亀 エリートになればなるほど、英語で教育も受けているし、現地語や州の言葉は、親としゃべるだけとか、ひどいのは、キッチンランゲージと言って、母語はお手伝いの人としかしゃべらないんですよ。お手伝いさんに「これして、あれして」と言うときだけ使って、あとは全部英語みたいなね。
池亀 エリートになればなるほど、英語で教育も受けているし、現地語や州の言葉は、親としゃべるだけとか、ひどいのは、キッチンランゲージと言って、母語はお手伝いの人としかしゃべらないんですよ。お手伝いさんに「これして、あれして」と言うときだけ使って、あとは全部英語みたいなね。
パロミタ キッチンランゲージって、きつい表現ですね。お手伝いさんは、私も知っている人もそうですけど、その土地の言語しか知らなかったり、中には文字を知らないという人もけっこういますからね。
池亀 そうそう。だからエリートの家ではキッチンランゲージになる。今は地域のなまりも昔と比べるとずいぶん標準化されているとは思いますけどね。
パロミタ 昔は隣村の言葉がもう違う言葉みたいだった、とか言いますよね。でも、マラヤーラム語でいうと、いわゆる標準語的ななまりがあるのかと彼らに聞いてみたら、スタンダードななまりという発想自体がないみたいなんですよね。ただ、みんな、これこれこの地域はなまりがすごいから、とか言う。俺も何言ってるか実は分からないんだよ、とか言いながら、横で見ていると、いやいや会話成立してるじゃん、みたいな。ある程度の分かりづらさを感じながらしゃべっているとして、それが当たり前というのも面白いと言えば面白いですよね。日本語って、なまりを標準語に切り替えちゃうから、そういう面白さはないですよね。
タミル語の不思議とプライド
池亀 最近タミル語を勉強し始めたんですけど、タミル語は文字が少な過ぎて、何かもう腹が立って、何でこれで成立するのという感じ(笑)。例えばタとダの違いがなくて、一文字「த」しかないんです。
パロミタ ガとハの違いもないし(「க」)。不思議ですよね。正直、タミル語はその点、本当に謎だなと思います。
池亀 そうなんですよ。こうやって書くけど、これはちょっと文語っぽくって、実はこう言ってますとか、こうやってつづるけど、こう発音するとか。加えて、文字が圧倒的に足りなくて、タと言ったり、ダと言ったり、ガがハになったり、サとチャとジャが一緒だったり(「ச」)……もう本当に頭きちゃう(笑)。とはいえ新しい言語を大いに楽しんでいます。
パロミタ そういうことがあるから、表記の監修が必要なんですよ。でも、ほかの州言語と比べても、タミル語圏のプライドってすごく強いところがある気がしますよね。
池亀 タミル語圏はやっぱりちょっと別格ですね。そんなに英語も使わないし。
パロミタ ある種の保守っぽさと激しさというか、『9つの人生』ではケーララ州のカースト差別について書かれていますが、差別に根差した親族間の殺人や暴力とか凄絶な話は、『インド残酷物語』でも描かれているように、現代ではタミルのほうがイメージがある気もします。
池亀 はい。タミル・ナードゥ州は反バラモン運動が一番強かったところですが、実はそれをやっていたのは真ん中のカーストの人たちで、ダリット差別がずっとあったにもかかわらず、その運動の中で隠れてしまっていて、なかったことにされてきたんですね。タミル・ナードゥは今もカースト差別が強く残っていますよね。
 パロミタ バラタナティヤムは今、インドを代表する古典舞踊になっていますが、あれももともとはタミル・ナードゥ州の寺院の人たちの踊りをバラモン出身の女性が形を変えて、新たな名前をつけて復興させたんですよね。そのことで近年いろんな議論が出てきていて、デーヴァダーシー系(寺院に奉納された伝統舞踊を担う女性)の家系の舞踊家が、どうして今、このバラモン主導のサバー(公演などを主催したりする文化センター的な施設)の舞踊家たちの中に私たちの場所が保証されていないんだと声を上げたりもしていて。バラモンは自分たちの文化を取り上げて我が物顔をしていると。
パロミタ バラタナティヤムは今、インドを代表する古典舞踊になっていますが、あれももともとはタミル・ナードゥ州の寺院の人たちの踊りをバラモン出身の女性が形を変えて、新たな名前をつけて復興させたんですよね。そのことで近年いろんな議論が出てきていて、デーヴァダーシー系(寺院に奉納された伝統舞踊を担う女性)の家系の舞踊家が、どうして今、このバラモン主導のサバー(公演などを主催したりする文化センター的な施設)の舞踊家たちの中に私たちの場所が保証されていないんだと声を上げたりもしていて。バラモンは自分たちの文化を取り上げて我が物顔をしていると。
池亀 20世紀のバラタナティヤムの歴史を考えると、ねじれというか、アイロニーというか、考えさせられますね。もともとダリットのデーヴァダーシーの伝統舞踊は、ハイカルチャーではなかったわけですからね。上品な人は見ることはあってもやるものじゃなかった芸能を、ルクミニー・デーヴィー(デーヴァダーシーに舞踊を習い、舞台芸能「バラタナティヤム」を古典舞踊として確立させた立役者)らバラモンが入ったことによって、インドの輝かしい伝統のようになった。今、欧米のインド系のエリートの家では、娘さんの習い事の一つとして定着している。
パロミタ そうなんですよね。といって、今のバラタナティヤムを否定するのもちょっと違うと思うし。ルクミニー・デーヴィーのような人が出なかったら、あの時代、バラタナティヤムの元になった舞踊自体の伝承が危うかったかもしれない。
池亀 そうそう、ルクミニー・デーヴィーのカラクシェートラは本当に美しい世界ですよね。そしてインド芸能の世界には、ヒンドゥーもムスリムもいて、セクシャルマイノリティーも多い。だから簡単にハイカルチャーだと片付けることもできない深さがありますね。
言語が分かると人間扱いされる!
パロミタ ちなみに、インドでは言葉が分かったほうが人間扱いされるというのはありません?
池亀 それはすごくあります。現地語をしゃべっているかどうかで、人間関係が天と地ぐらいの差がある。下手くそでもしゃべれると、それなりのリスペクトを受けられますよね。
パロミタ ドライバーでも、ケーララなんかだとヒンディー語が分かる派と英語が分かる派がいるみたいですけど、やっぱりマラヤーラム語をしゃべると、もう全然リスぺクトが違います。「あ、今まで私、人間じゃなかったんだな」ぐらいの感じで。文字まで分かるとなると、おーっみたいになるし(笑)。
池亀 あきらかに現地人ではないので、現地の言葉をちゃんと勉強したんだなということが尊敬の対象になるわけですよね。
パロミタ 英語ができなきゃという時代はもう終わりでいいかなと私は思っているんです。今はやっぱり英語覇権なので、英語はできたほうがいいし、どうしても得ですけど、英語だけというのは下手したらものすごく視野を狭くするなと個人的には思っています。それならいっそ日本語にこだわり尽くしたほうがいいかも、これは極論ですが。日本語と英語だけの人って、もちろん全員ではないですけど、視野が狭いなと感じる人が結構いるなと私は思うことがあるので。まあ結局、その人次第なのですが。私自身、英語が強いということは、今の私を成り立たせているものなんですけど、ある種の後ろめたさというか、コンプレックスみたいなものもあって。日本語は標準語しかできないし。
 池亀 英語だけだと限界がありますね。私の場合は、祖母がロシア語の翻訳をやっていたり、遠縁に13か国語ができるおじいさんがいたりして、そこが標準になっていたものだから、子供のときからたくさん言語を勉強しろという圧がありまして。
池亀 英語だけだと限界がありますね。私の場合は、祖母がロシア語の翻訳をやっていたり、遠縁に13か国語ができるおじいさんがいたりして、そこが標準になっていたものだから、子供のときからたくさん言語を勉強しろという圧がありまして。
受験英語はすごく苦手だったんですけど、フランス語をやったり、イタリア語をやったり、ドイツ語やったり。でもドイツ語やサンスクリットを、ちょっとやっておくと、格のこととか、いろいろなことがよく分かります。
ダルリンプルの『NINE LIVES』だけでも、チベット語も含めて、パロミタさん、6つくらいの言語の監修をつけていますよね。言語って、それだけ多様な人生と密接にかかわっている重要な文化なんだと、あらためて実感いたしました。
パロミタ ほかの文化を取材したり書くということは、その土地の言葉をいかにリスペクトするかということでもありますよね。それは翻訳書の読者の預かり知らぬことではありますが、そこに誠実に取り組むことで伝わるものはあるのではないかと思っています。監修者の多さからだけでも、もし「あれっ」と気がつく、更に想いを馳せるきっかけになったら、嬉しいですね。
【了】
プロフィール

池亀彩(いけがめ あや)
 1969年東京都生まれ。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科准教授。早稲田大学理工学部建築学科、ベルギー・ルーヴェン・カトリック大学、京都大学大学院人間・環境学研究科、インド国立言語研究所などで学び、英国エディンバラ大学にて博士号(社会人類学)取得。2015年から東京大学東洋文化研究所准教授を経て、2021年10月より現職。著書に『インド残酷物語 世界一たくましい民』(集英社新書)等。
1969年東京都生まれ。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科准教授。早稲田大学理工学部建築学科、ベルギー・ルーヴェン・カトリック大学、京都大学大学院人間・環境学研究科、インド国立言語研究所などで学び、英国エディンバラ大学にて博士号(社会人類学)取得。2015年から東京大学東洋文化研究所准教授を経て、2021年10月より現職。著書に『インド残酷物語 世界一たくましい民』(集英社新書)等。
パロミタ友美(パロミタ ともみ)
 翻訳者、バウル行者。オーストラリア国立大学アジア研究学部卒業。サンスクリット語、言語学を学ぶ。2013年、世界的に著名なバウル行者の一人、パルバティ・バウルと出会い、師事。バウルの道に入る。日印を行き来しながら、2017年より東京を中心に定期公演を開催。2018年にはパルバティ・バウルの日本ツアー「バウルの響き」を共催。訳書にウィリアム・ダルリンプル『9つの人生 現代インドの聖なるものを求めて』(集英社新書ノンフィクション)、パルバティ・バウル『大いなる魂のうた〜インド遊行の吟遊詩人バウルの世界』(「バウルの響き」制作実行委員会)。
翻訳者、バウル行者。オーストラリア国立大学アジア研究学部卒業。サンスクリット語、言語学を学ぶ。2013年、世界的に著名なバウル行者の一人、パルバティ・バウルと出会い、師事。バウルの道に入る。日印を行き来しながら、2017年より東京を中心に定期公演を開催。2018年にはパルバティ・バウルの日本ツアー「バウルの響き」を共催。訳書にウィリアム・ダルリンプル『9つの人生 現代インドの聖なるものを求めて』(集英社新書ノンフィクション)、パルバティ・バウル『大いなる魂のうた〜インド遊行の吟遊詩人バウルの世界』(「バウルの響き」制作実行委員会)。


 池亀彩×パロミタ友美
池亀彩×パロミタ友美 『インド残酷物語 世界一たくましい民』
『インド残酷物語 世界一たくましい民』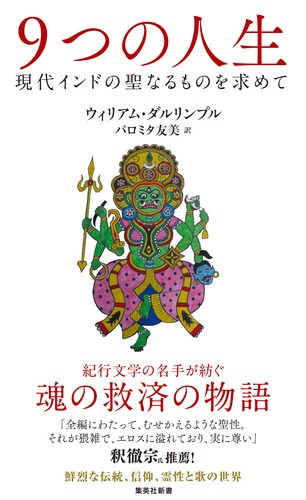 『9つの人生 現代インドの聖なるものを求めて』
『9つの人生 現代インドの聖なるものを求めて』









 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
 小島鉄平×塚原龍雲
小島鉄平×塚原龍雲


