敗戦から今年で80年。戦争の中でも悲惨をきわめた沖縄戦では、県民の4人に1人が犠牲になった。降伏を許されず「集団自決」させられたり、日本軍にスパイ扱いされて殺された県民もいた。
にもかかわらず、参政党の神谷宗幣代表が「日本軍の人たちが沖縄の人たちを殺したわけではない」と発言したり、自民党の西田昌司議員が、沖縄戦で犠牲となった「ひめゆり学徒隊」に関するひめゆりの塔での説明について、「歴史の書き換えだ」と主張するなど、国会議員による問題発言が続いている。
そんな中、「沖縄戦の真実とは何だったのか?」ということに関心が集まり、沖縄戦研究の第一人者・林博史氏が今年4月に上梓した新書『沖縄戦 なぜ20万人が犠牲になったのか』が早くも5刷の増刷となった。
その林氏と、元文部科学省事務次官で、辞任後は政権の欺瞞と闘ってきた前川喜平氏が対談。
戦争と教育の責任について語り合った。(全3回の第1回)
構成:稲垣收
島田叡知事についての認識は目からウロコでした
前川 この本は沖縄戦に関する歴史入門書の決定版だなと思います。沖縄戦に関わるあらゆる論点が網羅されていて、必要なことが全部書いてある。
私も沖縄戦についてはある程度の知識を持っていたつもりですが、この本を読んで、認識を改めた部分も相当あります。たとえば当時の沖縄県知事・島田叡(しまだ あきら)についての評価は、今まで言われているものと大分違いました。彼についてはドキュメンタリー映画も劇映画もできていて、「軍に抗って沖縄の住民を生き延びさせた」というイメージがあるけれども、そうじゃない、と。この島田知事に対する評価は、目からウロコでした。

しかし、それはそうでしょうね。権力側にいたわけだし、戦争遂行のために仕事をしたのは間違いないでしょうし。そして当時の日本軍が、守るべきものは国体であり天皇であり、「住民を守る軍隊」ではなかった。それに協力した県知事も決して住民を生かそうと努力したわけではなかったと。
もう1つはいわゆる集団自決についてです。歴史学の世界では「強制集団死」という言葉を使う人も多いと思いますが、この「強制集団死」という言葉にも、林さんは批判の目を向けておられる。単に「強制集団死」と言ってしまうと、内面化された皇国民意識みたいなものが説明し切れないということだと思うんですが、これもなるほどと思いました。
この辺は当時の学校教育との関係も十分あると思いますが、「集団自決」というのは、大日本帝国によって教え込まれた人たちが、追いやられたということだと思うんです。
この本の中にも「死なないで投降しよう」と言った人たちが出てきます。アメリカなどに移民して帰ってきた人たちが「米軍は投降した者を虐待したりしないから、白旗を掲げて投降しよう」と言った。これは当時の日本の教育を受けていない、あるいは軍の宣伝に毒されていない人たちだったから、まともな判断ができた。
もう1つは、日本の学校教育を受けていない、特に女性、お母さんたちが、一般には無学と言われているけれど、教育を受けていないがゆえに人間本来の「生きよう」とする気持ちが素直に出てきて、投降して生きられたという人が多いんじゃないか、と。これは教育のあり方を考える上で大きいと思いました。
あとは、軍隊の中にも、軍隊の統制が崩れたときに、「こんなところで死ぬんじゃない」と言う人たちが出てきた、と。「軍の統制が崩壊したときに本来の人間性が現れる」ということもあるんだなと思いました。
歴史教育や道徳教育に口を出してきた自民党のタカ派
前川 私は38年間国家公務員として、国の論理に縛られて生きてきましたが、8年前にそこから解放されたので言いたいことを言って暮らしています。でも国家公務員時代は結局、上の権力に従わざるをえなかった。自民党を中心とする政治権力です。特に「文教族」と言われた議員たちは安倍派が多い。森喜朗さん以来ずっと、自民党内でもタカ派と呼ばれている人たちが文教族で、タカ派の人ほど教育政策に関心を持つ。特に歴史教育と道徳教育にものすごく関心を持って口を出そうとする。その人たちがずっと権力を握ってきていて、私はその下で仕事をしていたものですから、心ならずもやらざるをえない仕事がありました。
そのくびきから解放されると本来の人間に戻れるわけで、私も今は普通の人間に戻っていると思うんですけど、組織の中にいる間は、まともな人間性を保つのがなかなか難しかった。特に第二次安倍政権ができてから、バランスを保つために始めたのがツイッター(現・Ⅹ)です。匿名でいろいろつぶやいていたんですが、自分の上司に当たる大臣や大臣政務官らを批判するようなことを書いていました。そうやって精神のバランスを保つことが必要だったんです。
そうした権力がなかなか崩壊しなかった体制が、参院選が終わり、ここへきてちょっと崩壊しかかっていますが、どっちのほうに崩壊するかが問題ですね。今、参政党などというとんでもないウルトラ・ライト(極右)政党が出てきましたから、それがもし政権に参加するようなことがあれば、もっとひどいことになると思っています。
ファクトや真っ当な議論を重視しない傾向
林 たしかにそうですね。以前の本書をめぐる対談でも少し触れましたが、これまでは、歴史的な事実を否定しようとする人々も、それなりに勉強して資料や文献を調べ、根拠を示して議論してきていた。それに対して我々は「いや、その資料の読み方は間違っている」とか「もっとこういう資料があるのに無視している」と反論したりして、そこで議論が成り立ちえたんです。
ところが今はもう、この前の参政党の神谷代表の発言や、自民党の西田昌司議員の発言にしても、根拠は何も示されないんです。ただ「自分はこう思っている」ということだけボンと出して、それが変に支持を得てしまう。それでは議論にならないんです。
民主主義は「考え方が違っても、対話が成り立ちえる」ということが一番の基本だと私は思っています。ですから、研究者の中で考え方が違う人はいますが、たとえば資料に基づいて議論を組み立てる人とは話ができる。もちろん考え方が違えば、解釈において対立することはありますが、対話が成り立つんです。しかし今はもう「自分はこう思う」というだけで、何の根拠も示さない。これはもう民主主義じゃないです。
トランプ現象などもそうだと思います。「事実はこうだ」という批判をしても全然通じない。これが一番怖い。これに対してどう対処すればいいのか? 研究者の議論ではちょっと対抗できなくなっている。そういうことに対して、社会全体としてどう考え、どう対処するのか。これはたとえばインターネットを含めたリテラシーの問題にも関わってくるんですが、その辺りは私もどう対処できるかわからないので……。
前川 私もそこは本当に心配しています。参政党が大きく議席数を増やしてしまったのは本当に怖いです。維新が出てきたときに「ひどい党が出てきた」と思いましたが、「まだ維新のほうがマシだ」と思えるような党が現れるとは……。以前維新に所属していた梅村みずほ(*)という人が今度、参政党から立候補して当選してしまいました。その梅村議員は先日テレビの討論番組に出演した際、共産党の山添拓議員に、選挙期間中の梅村氏らの外国人をめぐる主張の誤りをファクトを挙げて指摘されると、「選挙で民意を得たのは私たちだ」と開き直るんです。要するに、事実でないことを主張して民意を誘導したのに「有権者の票をたくさん得たのは自分たちだ」と。これは全然反論になっていません。要するに、「数は力であり、力は正義だ」という言い方ですよね。「選挙で勝ったんだから自分たちのほうが正しい」という言い方、これがまかり通るのは本当に怖いと思います。
* 梅村議員は日本維新の会所属時の2023年5月の参院本会議で、21年に、入管施設で病気になって体調が最悪なのにもかかわらず入院させてもらえずに死亡したスリランカ人女性ウィシュマさんについて、「彼女が亡くなったのは支援者のせいだ」とする主旨の発言をし、党員資格停止6カ月の処分を受けて、維新を離党し、参政党に移籍。今回の参院選では参政党から立候補して当選。
「歴史は国民の物語だ。フィクションでかまわない」と言う議員
前川 官僚時代、私は自民党の下でずっと仕事をしてきましたが、自民党には「歴史は科学だ」と考える人があまりいませんでした。でも歴史というのは、歴史学という科学で解き明かすべきものだと私は思うし、科学が進んでいけば、同じ事象を扱った歴史でも、塗り替えられることはあるし、歴史の教科書だって書き換えられることがあるんですが、でもそれは様々な資料に当たりつつ、ロジカルに検証していって見出していくということだと思います。
しかし「歴史は国民の物語だ。だからフィクションでかまわないんだ」というような言い方をする人たちが政権与党である自民党内にいたわけです。そういう人たちには話が通じません。
少なくとも歴史学者と呼ばれる人たちの間では一定の作法があると思いますが、政治家には話の通じない人がたくさんいる。そして参政党はそんな人ばかりが集まって作ったような政党です。歴史だけの問題じゃなく、陰謀論みたいなものも、いろいろちりばめられている。根拠のないことをたくさん主張して、それで人々の支持を集めている政党なので、ものすごく危ないと思います。
これは学校教育にも責任があると思います。「事実と論理を理性でちゃんと考えて組み立てていき、結論を出していく」というような、「科学の作法」を身につけるのが学校教育の大事な目的だと思うのですが、それがまるでできていない人たちが集まってこういう政党を作ってしまった。旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)をはじめとするカルトも全く反科学ですが、カルトが広がっているのと根っこが同じなのかなという気がします。カルトにハマった人には全然話が通じません。
そして戦時中の日本は国全体がカルト教団みたいなものだった。理性を保っている人もいたでしょうが、その人たちは思っていることを話すと「非国民」と言われて迫害されるから、黙っているしかなかった。抵抗した人もいるけれど、治安維持法違反とかで逮捕される。それで実際に多くの国民がカルトに巻き込まれた。
私の父は98歳でまだ存命なんですが、戦時中は旧制中学の生徒でした。旧制中学の4、5年生のときにはずっと名古屋の軍需工場で働かされて、空襲を受けて仲間が何人か死んだりしています。今はまともな判断のできる人ですけど「中学生の頃は、絶対日本は勝つと信じていた」と言っていますし、そう信じていた国民は非常に多かったと思います。「日本は神の国だから必ず神風が吹く」などと教え込まれて、全く根拠のないことを信じ込んでいた。だから日本中が1つのカルトになっていた。
そこから脱却する、脱カルトというのは、敗戦でいや応なしに経験せざるをえなかったと思うんですが、多くの人は、そこで憑き物が取れたようにカルトから脱したのかもしれません。
しかし日本の支配層の中にはカルトを引きずったままの人が相当残った。これはアメリカの占領政策もあるでしょう。冷戦構造が強まっていく中で、民主化から反共へと占領政策が変わり、共産主義に対して「日本を反共のとりでにする」ということで、古い日本のカルト国家を率いたような人たちが生き残ってしまった。昔の軍人や東条内閣の閣僚や官僚だった人たちが日本の支配層の中に残ってしまった。
日本の戦後の不幸は、そういう戦前を引きずったところにあるんじゃないかと思います。何よりも「国体が護持された」というのが……。終戦の詔勅の中で昭和天皇が「国体を護持し得て」と言っていますよね。ポツダム宣言を受諾するかどうかという際にも、さんざん議論したのは国体が護持できるかどうかです。だから戦後の出発点からして、国体が護持されたことになってしまっている。「日本は神の国だ」という全く根拠のない、神話に根拠を持つような観念、国体思想が生き延びる余地ができてしまった。
沖縄戦では明らかに、「日本の軍隊は人を守るためではなくて国体を守るためにある」と。だから、何のためらいもなく人を犠牲にした。それがハッキリ出ています。
この本の中でも林さんがお書きになっていますが、今、日本には軍はないはずなんだけども、陸海空軍に限りなく近い自衛隊がある。その自衛隊が「本当に日本の人たちを守るためにあるのか?」というのは、本当に突きつめていかなきゃいけない問いだと思います。「あなたたちは本当に人を守るためにいるのか? 人を犠牲にして国を守るなどと考えていないか?」と。
参政党の議席が伸びた要因は、経済政策の失敗による「集団的不安」
前川 参政党のような政党が伸びた背景には、集団的な不安があると思います。
日本が経済大国だと言われていた頃は皆、あまりそんなところに飛びつこうとは思わなかった。でも世界の中での日本の経済的地位がどんどん後退していき、GDPで中国にもドイツにも抜かれ、まもなくインドやインドネシアにも抜かれる、と。1人当たりGDPでは韓国や台湾より少なくて、経済的に衰退しています。
でもこれは経済政策の失敗によるところが大きい。小泉構造改革やアベノミクスのなれの果てです。この約30年間の日本の経済・財政・金融政策の失敗をちゃんと検証し「他の国に比べて日本国民がこれだけ貧しくなったのは、このせいじゃないか」というのを、経済や財政の学者たちが実証的・科学的に解明すべきです。でも、それがされていない。

そして、経済財政政策の失敗による不満や不安というものが日本に充満していて、トランプのアメリカじゃないですが、「メイク・ジャパン・グレート・アゲイン」みたいに「今は苦しいかもしれないけど、もともと日本は立派な国なんだ」と、ことさら強調する考えに惹かれてしまう。日本という国に自分のアイデンティティを埋没させ、日本人であるということを自分の支えにする。その上で「日本は立派な国なんだ」「これまで悪いことなどしなかったんだ」という気持ちにさせてくれるのが、いわゆる歴史修正主義です。ただ「歴史修正主義」というと「間違っている歴史を正しくする」ように聞こえますが、そうではなく根拠のないことを言っているのだから、「歴史改ざん主義」とか「歴史歪曲主義」とか「歴史捏造主義」と呼ぶべきでしょう。
今回、参政党で新しく当選した初鹿野裕樹(はじかの ひろき)参議院議員は、「南京大虐殺が本当にあったと信じている人がまだいるのかと思うと残念でならない」とXに投稿しています。
参政党は全体がそうなんですが、初鹿野議員は「日本軍は『焼くな、犯すな、殺すな』の三戒を遵守した世界一紳士な軍隊である」と投稿し、「日本は悪いことなどしなかったんだ」と主張しています。
こういうことを言う人たちは以前からいましたが、そういう人たちだけで作った政党が参政党です。私は、安倍晋三さんが亡くなった反動で出てきたのかもしれないという気がします。安倍さんがいる間は、自民党の中で、安倍さんという求心力の中にそういう人たちがくっついていたけれど、安倍さんがいなくなったので、より過激な形で別の党として現れたのかな、と。
おそらく背景にはそういった「皇国史観」を広げたいと思っている勢力がいるんじゃないか、と。それをバックアップしたいと思っている経済人もいますから、そういう人たちが参政党の選挙運動にお金を出しているのか、と。相当お金がないとあれだけのキャンペーンはできません。あれだけの数の候補者も立てているし、3年ぐらい前からあちこちにポスターを貼ったり、いろんなSNSでの発信をしたりしていましたし。あれは代表の神谷宗幣氏だけでできることじゃない。相当資金力がある組織があると見ています。(第2回に続く)
プロフィール

(まえかわ・きへい)
1955年、奈良県生まれ。東京大学法学部卒業後、79年、文部省(現・文部科学省)入省。文部大臣秘書官、初等中等教育局財務課長、官房長、初等中等教育局長、文部科学審議官などを経て2016年、文部科学事務次官となり、17年に退官。自主夜間中学スタッフとして活動し、執筆活動にだずさわる。『面従腹背』『権力は腐敗する』(ともに毎日新聞出版)、『日本の教育、どうしてこうなった?』(児美川孝一郎との共著、大月書店)など著作多数。

(はやし・ひろふみ)
1955年、神戸市生まれ。現代史研究者、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了(社会学博士)。関東学院大学名誉教授。主な著書に『沖縄戦 なぜ20万人が犠牲になったのか』(集英社新書)、『沖縄戦と民衆』『沖縄戦が問うもの』(大月書店)、『沖縄戦 強制された「集団自決」』『米軍基地の歴史 世界ネットワークの形成と展開』『帝国主義国の軍隊と性 売春規制と軍用性的施設』(吉川弘文館)、『朝鮮戦争 無差別爆撃の出撃基地・日本』(高文研)、『BC級戦犯裁判』(岩波新書)等多数。


 前川喜平×林博史
前川喜平×林博史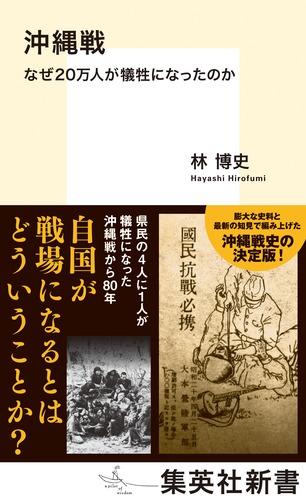
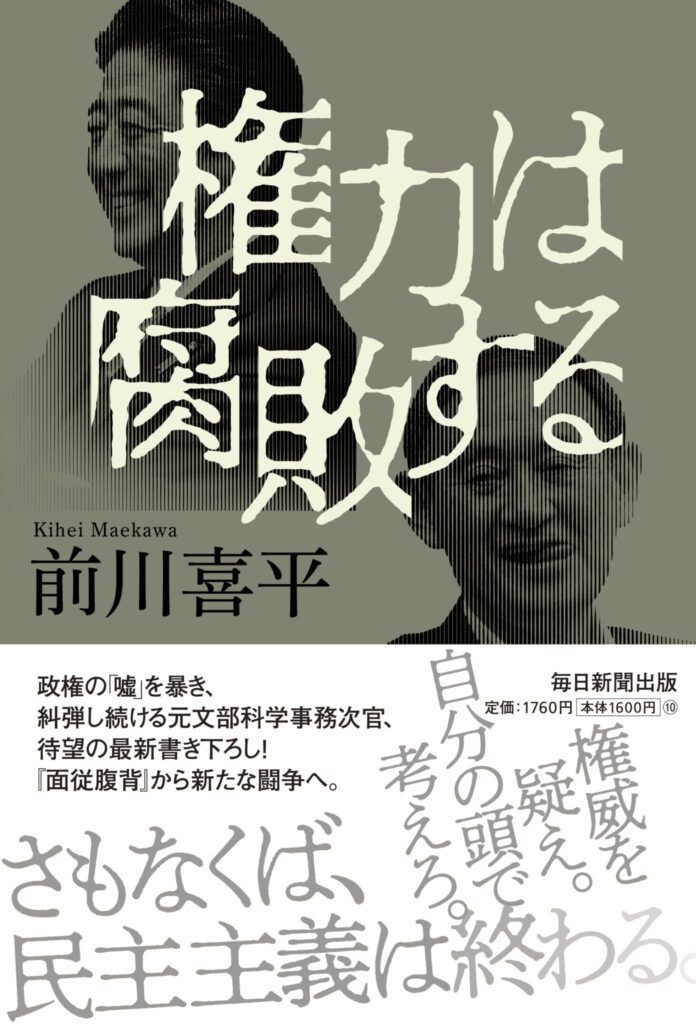






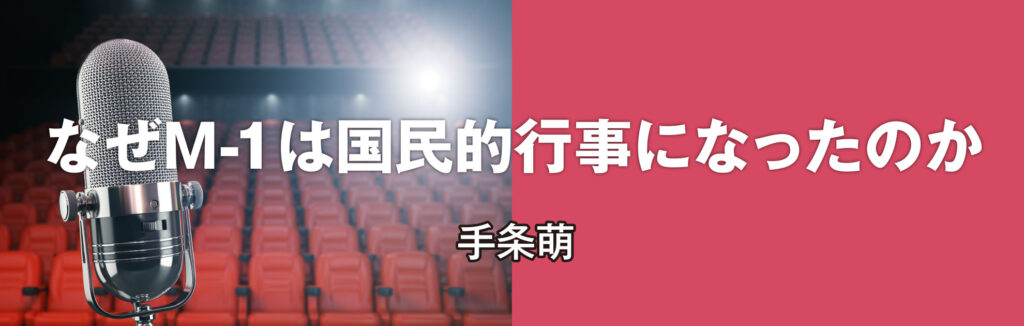






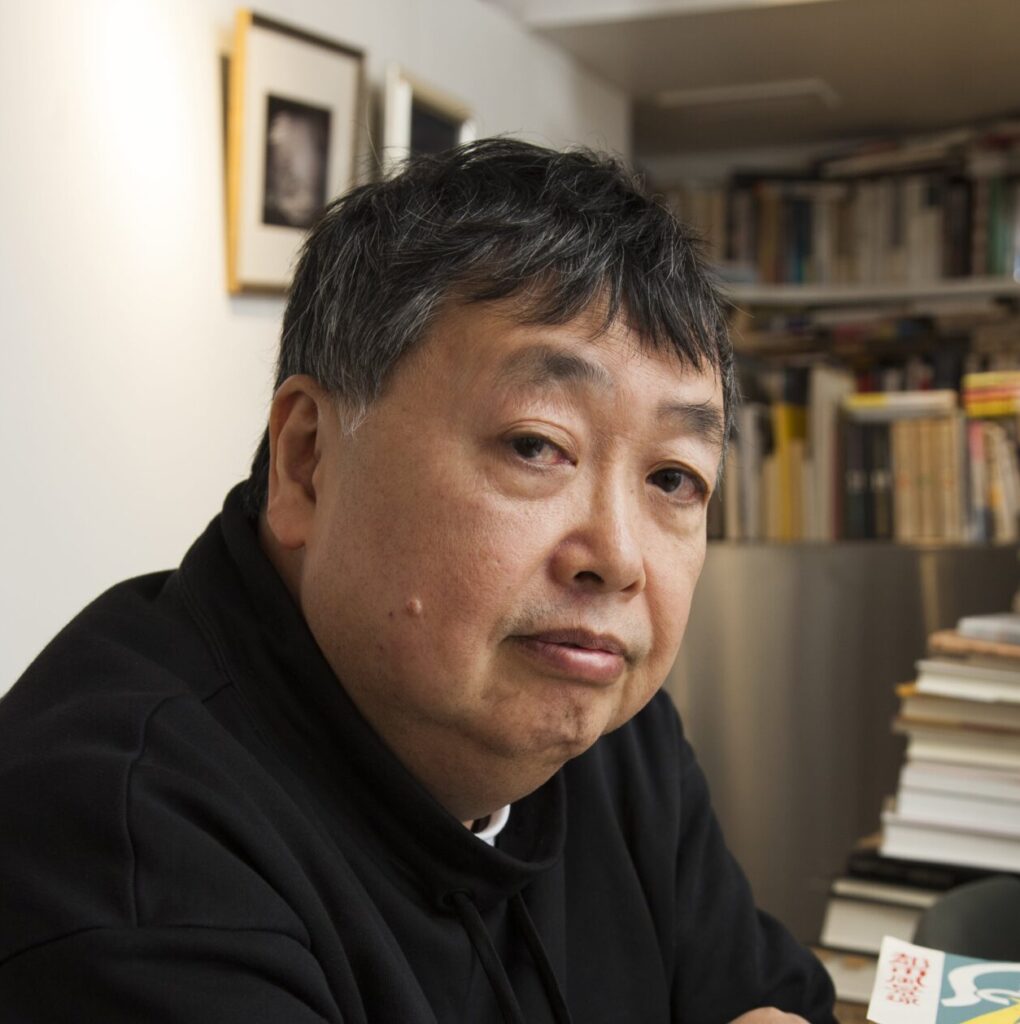
 大塚英志
大塚英志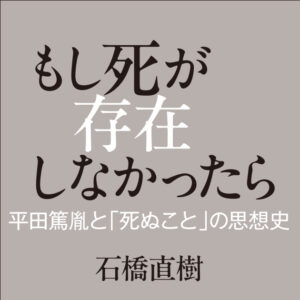
 石橋直樹
石橋直樹