敗戦から80年。その戦争の中でも悲惨をきわめた沖縄戦では、沖縄県民の4人に1人が犠牲になった。降伏を許されず「集団自決」させられたり、日本軍にスパイ扱いされて殺された県民もいた。
にもかかわらず、参政党の神谷宗幣代表が「日本軍の人たちが沖縄の人たちを殺したわけではない」と発言したり、自民党の西田昌司議員が、沖縄戦で犠牲となった「ひめゆり学徒隊」に関するひめゆりの塔での説明について、歴史の書き換えだと主張するなど、国会議員による問題発言が続いている。
そんな中、「沖縄戦の真実とは何だったのか?」ということに関心が集まり、沖縄戦研究の第一人者・林博史氏が今年4月に上梓した新書『沖縄戦 なぜ20万人が犠牲になったのか』が早くも5刷の増刷となった。
その林氏と、元文部科学省事務次官で、辞任後は政権の欺瞞と闘ってきた前川喜平氏が対談。
戦争と教育の責任について大いに語り合った。(全3回の第3回)
構成 稲垣收
日本史を教えろ、というタカ派からの圧力で「歴史総合」という科目が新設された
前川 「日本史を教えろ」というタカ派政治家の圧力があったこともあって、世界史必修はやめて、新たに世界史の中で日本史を学ぶという科目「歴史総合」が作られました。2022年度から高校で2単位の必修科目として。18世紀以降の世界史と日本史を一緒に学ぶという科目で、18世紀はさらっとやって19世紀以降はしっかりやる、と。日本の場合には、いろんな外国の船が日本にやってくるようになって、いよいよ日本が開国して、という辺りからしっかり勉強しましょう、ということで、これはいい指導要領の変更だったと思います。
それまで必修だった世界史は、メソポタミア文明や黄河文明から勉強するわけで、古代文明も大事だけれど、そこから勉強していたら高校3年全部使っても足りない。現代を生きる上で必要となる歴史の常識を身につける意味では、18世紀以降の日本史と世界史を両方学ぶ「歴史総合」という科目を作ったこと自体はよかった。
ただ、もともと世界史を教えていたとか日本史を教えていた先生が、両方教えるのは難しいということがありますが、それは先生にも勉強してもらうしかない。勉強し、世界史の中に日本史を位置づけて学んでもらう。学ばないことは教えられませんから。
私は自主夜間中学の運営に少し関わっています。「あつぎえんぴつの会」(神奈川県)と「福島駅前自主夜間中学」(福島県)です。大人のフリースクールみたいなもので、自由に何を勉強してもいいので、あつぎえんぴつの会では、神奈川県の中学の社会科の先生だった津田憲一さんという方を招いて沖縄戦の話を聞いたことがあります。津田さんは言わば市井の人で、学者じゃない。でも中学の社会科教師だから、近現代史も仕事として教えていました。今はもうリタイアしていて、元社会科教師。彼は「沖縄戦の実際を自分の目と耳で確かめよう」と、何度も沖縄に行って、沖縄戦を生き延びた人たちの話も直接聞いたりして、一生懸命自分でファクトを集めて、それを元にして中学で教えていたんです。この人の話を、自主夜間中学に来てもらって聞きました。
林 そうなんですね。津田憲一さんは、私の『沖縄戦』の参考文献リスト(342ページの4番目)で紹介している『加計呂麻島旅日記』を書かれた人で、最初は沖縄に行かれていたようですが、その後、主に加計呂麻島(かけろまじま、鹿児島県大島郡の奄美群島の島)に通って聞き取りを重ねた方ですね。
前川 はい、その方です。津田さんは沖縄や奄美で「集団自決」についての聞き取りを続けてきた。座間味島では、村の助役だった宮里盛秀さんが父の盛永さんに「軍からの命令で自決しなさいと言われている。一緒に死にましょう」と話したということを、その場にいた盛秀さんの2人の妹さんから聞き取ったそうです。津田さんが最近出されたのが『奄美“幻”の「集団自決」』(南方新社、2025年)という本で、林さんが参考にされた『加計呂麻島旅日記』も収録されています。
津田さんは、自分の活動を説明して「自分は語り部ではないけれど、語り部の伝え部です」と言っています。語り部から聞いたものを伝える、と。本来は歴史学そのものが、語り部の伝え部だと私は思います。
この津田さんのように、自らの問題意識を持って自分で勉強し、勉強するだけじゃなくて自ら足を運んで、事実を収集するところからやろうとする。そこまでできる人は少ないでしょうが、少なくとも中学や高校の社会科の教師として歴史を教える立場にいる人は、教えるだけじゃなくて学ぶということが非常に大事だと思います。
だから教師にとって、「忙しいから学ぶ暇がない、時間がない」というのは、教師の勤務条件として、非常に問題がある。教師が自ら学ぶ時間をしっかりと取れるように条件整備をすることは行政の責任ですが、逆に「こういう様式で報告を出せ」とか、役所仕事みたいに文書を作って上に上げるような仕事が学校現場でもすごく増えている。これはよくない。そういうものをできるだけなくし、先生たちがもっと自由に、たとえば夏休みに自ら自主研修で沖縄に行っていろんな勉強をしてくる、ということができる時間を与えてあげることが非常に大事です。
でも実際の教育政策は逆を行っている。「学習指導要領を勉強しろ」とか、国側が望むような教師を作ろうとする方向に戻りつつある。
国策で教師を養成する師範学校は戦後廃止になったが……
前川 戦後の民主教育を始めるときに、師範学校を全部廃止したんです。師範学校というのは国策で教師を作る学校だったわけですが、戦後は「教師を作ることだけを目的にする学校はいらない。大学で教師を育てる」という考え方に転換したのです。大学には学問の自由がある。国策で教師を作るのではなく、大学での自由な学びを土台にして教師を養成するという考え方になったんです。
しかし今また国が政策として、教員養成の大学の教育内容にすごく口を出すようになってきてる。コア・カリキュラムといって「こういう内容を必ず教員養成の際に盛り込め」と細かく指示するようになり「国策で教師を養成する」という師範学校型に戻りつつある。これは非常に危ない。
大学は本来自由な学びの場であり、学問の自由は憲法23条で保障されているわけですが、学問の自由は大学の先生にだけ保障されているわけじゃなくて、基本的人権ですから人間であれば誰でも学問の自由を持っているはずで、当然小・中・高校の先生も学問の自由を持ってなきゃおかしい。私は教師という仕事は、大学であれ小・中・高校であれ、自ら学ぶということと不可分だと思います。自ら学ぶ時間がないという今の教師の勤務実態は、何とかしなきゃいけない。そのゆとりは回復しなきゃいけないと思います。
ただ、学習指導要領だとか、教科書検定だとか、教員研修という形で、上から「こういうことをこう教えろ」という圧力が、この30年間ずっと強まり続けている。それは自民党の政治が上にあったことが原因です。私はその下で仕事をしていましたから、そういう経験を何度もしました。
2006年、第一次安倍政権時、教科書検定で官邸から圧力がかかった
前川 教科書検定では、かなり政治が反映したことが行われてきました。今でも問題だと言われているのは2006年の高校日本史の「集団自決」をめぐる検定です。私が最近読んだ『日本史教科書検定三十五年 教科書調査官が回顧する』(吉川弘文館、2025年)という本の著者の照沼康孝さんは、教科書調査官として、この2006年の日本史教科書の検定をやった人です。日本史の中でも近現代の軍事史がもともと専門の人で。彼の先生は伊藤隆という東大教授で、「新しい歴史教科書をつくる会」に参加した人です。その門下生と言われている人の1人が照沼さんですが、この人は学者だから論文もたくさん書いているし、歴史学の作法はちゃんと身につけているので、「学問的根拠のないことを教科書に書くことは認めない」という基本的なラインはあるわけです。
2006年は第一次安倍政権ができた年です。照沼さんは、この本の中で、2006年の高校日本史の教科書検定に当たって、官邸から圧力があったと書いています。当時、文部科学省に直接圧力をかけたと思われるのは下村博文・官房副長官(当時)です。もともと自民党文教族ですが、この人が歴史教科書の内容にいろいろ注文をつけ、それを当時の文部官僚たちが受け止めて検定に反映させようとした、というのです。
相当詳細に「教科書のこの記述は問題だ」という指摘があって、その一覧がコピー用紙で30枚近くもあり、事務方から教科書調査官に回ってきたそうです。
事務方の教科書課長の下に教科書企画官がいますが、これは学者じゃなく役人です。一方、教科書調査官は、身分は国家公務員ですが、学者がなる。ただ、学者だけど、偏りがあるのは間違いない。この照沼さんと、もう1人、村瀬さんという人も2006年の検定に当たりましたが、2人とも伊藤隆教授の門下ですから、伊藤隆人脈が相当に文科省の教科書検定に反映されている。
そもそも教科書調査官とか、あるいは教科書審議会の委員の選び方自体、縁故で選んでいるところがあって。その中心に「つくる会」の中心にいた伊藤隆教授の人脈があって、検定の体制が作られていた。そこに加えて2006年の第一次安倍内閣が明らかに圧力をかけてきた。
私は、このとき文科省にはいたんですが、この辺の事情は知りませんでした。直接のラインにいたわけじゃないので。でも照沼さんの本を読むと、官邸からいろいろ言われたけど、それに全部対応していると、必ず外交問題になる、中国や韓国から非難されるのは火を見るよりも明らかだった。その中で唯一、外交問題になる可能性がなかったのが沖縄戦での集団自決の問題だった。だから他の点については対応しなかったけれど、集団自決のところだけは官邸の言い分を聞いた、ということだったようです。
集団自決については、沖縄からは大変な抗議の声が上がりました。それ以前の検定では通っていた「日本軍が強制した」とか「日本軍が強いた」という記述を、この2006年の検定で突然ダメだと言い始めて、全部書かせなかったわけですから。「何で前はよかったのに、今はダメなんだ?」と抗議の声が高まった。

何か大きな歴史学上の知見が変わったということがあれば、こういうことはありえます。だけど、そんなことではないのに、以前は検定を通していた表現を通さなくなったのは、政治の介入が理由だったわけで。
私はこの件の経緯を知りませんでしたが、第一次安倍政権のときに起きたので、「官邸の圧力があったことは間違いないだろうな」とは思っていました。その辺の事情を照沼さんは具体的に書いています。官邸と教科書検定の現場との間に入った文科省の役人がいた。それは、組織としての文科省が官邸の、政治家の言いなりになった、ということです。
教科書検定については古くは家永裁判(*1)というのがあって、検定制度そのものの違憲性が争われました。「検定は憲法で禁じている検閲に当たるんじゃないのか」「言論の自由、表現の自由に対する侵害ではないか」という議論がありました。ただ私は、検定はあってもいいとは思っています。かつての検定は、左の教科書を見張るためのものという意味合いが強かったのですが、今はとんでもない右の教科書が出てきているので、右の教科書を排除する意味でも、ファクト・チェックという意味での検定はあったほうがいいと思っているんです。
ただ、その検定に政治が入り込む余地があってはいけない。だから文部科学大臣から独立させた、学者たちから成る機関を作って、そういう学者たちの代表者が検定する、ということにしたらいいと思います。たとえば日本学術会議のようなところに検定機関を置くとかですね。学術会議もこの前の法人化法で骨抜きにされてしまいましたが、これまでの学術会議みたいな組織がベースになって、あくまでも学問に基づいて検定する仕組みにしたらいいと思うのです。もちろん学者の中にもいろんな意見があるでしょうから、最大公約数的なところで検定するというようなことをしてくれたらいいと思います。
*1 家永三郎氏が執筆した高校の日本史の教科書が1962年の文部省の教科書検定で大幅な訂正を求められ、家永氏は検定が憲法違反であるとして、国を相手に裁判を起こした。
道徳が「教科」にされたことは「戦争ができる国民作り」につながる
前川 「新しい歴史教科書をつくる会」ができたのも、「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」ができたのも97年ですから、大体この30年の教育の流れが大きく右傾化していく出発点がこの年だと思います。教育の右傾化はどんどんひどくなっている。2006年には教育基本法が改正され2018年には道徳が教科化されました。
この道徳の教科化というのは、「国が作った国民道徳を学校教育で教える」ということです。道徳教育を国が進めるのは、本当に危ない。「道徳の時間」というのは、私が小学生の頃からありました。これは1958年に岸信介内閣のときに設けられた。でもその頃の日教組(日本教職員組合)の組織率は86パーセントでしたから、現場サイドで握り潰したケースが多く、国が期待したような効果は上げなかった。
それに対して、「こういう曖昧な位置づけだからよくない、国語や算数のようにちゃんと教科にすべきだ」という政治の動きが強まった。教科にするということは、国が検定する教科書を使わせるということと、「学習成果を評価する」ということを意味します。
岸信介内閣のときに導入した「道徳の時間」には教科書はなかったし、学習成果を評価することもなかった。それに対して「だからダメなんだ。ちゃんと国家の道徳を国民に教えるためには、戦前の修身のように教科にしなければいけない」と言う人たちが90年代後半から一気に力をつけてきた。
特に2000年に森喜朗さんが総理大臣になったのが大きなきっかけでした。小渕恵三総理が突然倒れたので、棚ボタ式に森さんが総理になって、森内閣のもとで教育改革国民会議が、初めて公文書で「教育基本法の改正」と「道徳の教科化」を打ち出したんです。これが決定的に日本の教育の右傾化の流れを作りました。
そして2006年の教育基本法の改正。この改正で盛り込まれた言葉が「道徳心」「国を愛する態度」などという言葉です。その言葉を入れさせた人たちが考えている道徳心というのは「国家が作る国民の道徳」ですから、教育勅語のようなものを考えている。
でも私は本来、道徳というのは、憲法で保障された思想、良心の自由の中にあるのであって、1人1人道徳は違うはずだと思います。1人1人違う道徳だけれども、その最大公約数的なものが法律になっていて、「人を殺したら罰せられる」とか「物を盗んだら罰せられる」とか、刑法の中に最大公約数的なものはあるけれど、それ以上のもの、罰せられない悪事というのがどこまであるか、あるいは、法では実現できない正義とか善とかとは何なんだろうかというのは、1人1人の精神の自由の中にしかないと思うのです。
しかし「日本人には日本人の道徳がある」という考え方をいまだに持っている人たちがいる。というか、むしろこの30年間に拡大再生産されている。それで第二次安倍政権で、ついに道徳の教科化まで実現してしまった。第一次安倍政権でもやろうとしたけれど、第一次安倍政権は1年しかなかったので、教育基本法の改正まではやったけれども、道徳の教科化まではできなかった。それが2018年についに小学校で道徳の教科化が始まり、翌年は中学校で始まった。これは本当に危ないと思います。
道徳の教科書は、検定のしようがないと思うのです。他の教科であれば、それぞれバックグラウンドとしての学問があり、歴史の教科書であれば歴史学があるので、学問の成果に基づいて検定すればいいわけですが、道徳の検定の基準になるものって、ないはずなんです。
でも学習指導要領はあるんです。1958年に岸信介内閣のときに作った学習指導要領が、その後多少の変遷を経て残っています。たとえば「日本人としての自覚をもつ」と学習指導要領に書いてあります。「父母、祖父母を敬愛する」という徳目も書いてある。でも世の中には敬愛できない父母も祖父母もいるはずです。暴力をふるったり、育児放棄したり、毒親と言われる人たちもいるわけで……。それなのに「父母、祖父母だから必ず敬愛しろ」なんていうことが学習指導要領の道徳編には書いてある。
そして今、教科になった道徳の教科書には、全部「正解」が書かれている。「全体のために自らを犠牲にする」「全体に奉仕する」「貢献する」ということが美徳とされて、「自分を活かす」なんていうことを美徳に書いてある教材はほとんどない。むしろ「我慢しろ」とか「わがまま言うな」とか「自らの成功を求めるな」とか「自己抑制や自己犠牲こそが美徳だ」と。これは従順な兵士を育てるにはもってこいでしょう。
だから道徳の教科化は「戦争ができる国民作り」につながる。昔の日本軍の兵隊のように「命令されたら何でもしてしまう」権力や権威に非常に従順な兵士を作る。だからこの道徳の教科化は本当に危ないのです。
国体思想が蔓延し、靖国神社にも接近している自衛隊
前川 もう1つ非常に危ないなと思っているのは、自衛隊の中に国体思想のようなものが蔓延しつつあることです。靖国神社との関係も非常に近くなってきているし。靖国神社は海上自衛隊の海将だった人が宮司になったし(*2)、陸上幕僚長をやった人が靖国神社の崇敬者総代になっています(*3)。こうやって自衛隊と靖国神社の関係が非常に近くなって、集団参拝もあちこちの部隊がやっています。「これは休憩時間にやった」とか「自由時間にやったんだから、自衛隊としてやったのではない」と言うんですが、部隊単位で参拝するということは、休憩時間であれ、休日であれ、集団参拝です。政教分離に反していると私は思います。

本当に危ない状況がだんだん進行していると思う。だからこそ、少なくとも中学や高校で歴史を教える先生は、少なくとも、この林さんの本は必ず読んでおきなさい、と言いたいですね。
津田さんのように自ら沖縄まで行って証言を集めて回るなんていう人はなかなかいないと思いますが、少なくともこの本を読んでほしい。この本がすごいと思ったのはもう1点あって、参考文献だけで17ページあるんです。だからこれを読んで、さらに勉強したければ、勉強するための書籍が提示されているんです。特に中高の社会科の先生には、ぜひこの本を読んでもらいたいと思います。
*2 2024年4月に海上自衛隊の海将だった大塚海夫氏が就任。将官を務めた元自衛隊幹部が靖国神社トップに就任するのは初めて。靖国神社は、太平洋戦争中は陸海軍の管轄下で、鈴木孝雄・陸軍大将が宮司を務めていた。敗戦後、GHQ(連合国軍総司令部)の指令で国や旧軍から切り離され、民間の宗教法人に転換し、宮司には元皇族や旧華族、神社関係者らが就いてきた。
*3 2023年7月に元陸上幕僚長の火箱芳文(ひばこ・よしふみ)氏が靖国神社の崇敬者総代に就任。
林 先ほどの前川さんの話の中でも2006年の教科書検定において、「集団自決」だけ取り上げられて、外交問題に発展するようなものは取り上げなかったという話がありました。その「集団自決の強制」という文言を削除するときに、実は教科書調査官が私の本を持ち出して、「林さんも日本軍の命令はなかったと言っている」と教科書執筆者に言ったんです。私が2001年に出した『沖縄戦と民衆』(大月書店)という本が、教科書検定で悪用されたんです。
あの本の中で私は「集団自決」についてある程度詳しく分析していて、「日本軍による強制と誘導によって〝集団自決〟が起きた」という結論を出しているんです。ただ、たとえば渡嘉敷島や座間味島の部隊長が「今から自決せよ」という命令を住民に出したかは確認できない、とは書いています。しかしその場で部隊長が命令しなくても、「いざというときにはみんなが自分たちで死ぬように、軍と行政が仕向けてきた」ということを丁寧に分析しているんです。ですから結論として、日本軍による強制と誘導だと。
それなのに、ある教科書執筆者は文科省から呼び出されて、私の本をぱっと出されて、ある行を見せられて「日本軍の命令はなかったと林さんも言っているじゃないか」「だから日本軍の強制はなかった。そう書いてはダメだ」と言われたと。
でもその執筆者が後で私の本をよく読んでみると、「直接の命令は確認できないけれども、結論としては日本軍の強制だ」と書いてある。これはそれまでの教科書でも、日本軍の命令によって集団自決が起きたという書き方はほとんどしていなくて、基本的には日本軍による強制、あるいは日本軍によって強いられた、という表現なんです。ですから、軍の強制を否定する根拠に私の本を使ったのは全くデタラメで、その教科書調査官は許せない人だと思っています。「上から圧力があったとしても、人として守るべき道があるだろう。それなのにそういう利用の仕方をするなどとは研究者失格だ」と。
前川 なるほど。
林 いずれにせよ、日本軍が住民を虐殺したこと、これはもう沖縄県が県議会でも全会一致で「これは事実だからちゃんと書け」と言っているので、認めざるをえない。でも日本軍を肯定したい人々は、沖縄戦の記述を何とかしたいので、西田議員や参政党代表の発言にしても、沖縄戦のことを取り上げてきてるんじゃないでしょうか。そういう意味では、ちょうどこの本を今年出せたというのは幸いでした。
また、先ほど紹介されたように、巻末に参考文献もたくさん紹介しています。沖縄県史や沖縄の市町村で沖縄戦に関する本が膨大にあります。本土ではなかなか手に入れるのは難しいんですが沖縄に行けば読めますし、いくつかウェブサイトで掲載している自治体もあって、沖縄戦体験者の証言がたくさん載っています。ぜひ私の本も活用していただいて、さらに読んでいただければと思います。
沖縄戦に関しては、沖縄県民だけにとどまらず日本国民がきちんと理解して、歴史的な事実をきちんと広め、学校教育でもやってもらわないと困るので、そういう意味で日本国民の技量が問われている問題だと思います。沖縄の人々はずいぶん抗議していますが、むしろ本土の人間こそが、沖縄のことをきちんと理解してほしいと思いますね。(了)
プロフィール

(まえかわ・きへい)
1955年、奈良県生まれ。東京大学法学部卒業後、79年、文部省(現・文部科学省)入省。文部大臣秘書官、初等中等教育局財務課長、官房長、初等中等教育局長、文部科学審議官などを経て2016年、文部科学事務次官となり、17年に退官。自主夜間中学スタッフとして活動し、執筆活動にだずさわる。『面従腹背』『権力は腐敗する』(ともに毎日新聞出版)、『日本の教育、どうしてこうなった?』(児美川孝一郎との共著、大月書店)など著作多数。

(はやし・ひろふみ)
1955年、神戸市生まれ。現代史研究者、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了(社会学博士)。関東学院大学名誉教授。主な著書に『沖縄戦 なぜ20万人が犠牲になったのか』(集英社新書)、『沖縄戦と民衆』『沖縄戦が問うもの』(大月書店)、『沖縄戦 強制された「集団自決」』『米軍基地の歴史 世界ネットワークの形成と展開』『帝国主義国の軍隊と性 売春規制と軍用性的施設』(吉川弘文館)、『朝鮮戦争 無差別爆撃の出撃基地・日本』(高文研)、『BC級戦犯裁判』(岩波新書)等多数。


 前川喜平×林博史
前川喜平×林博史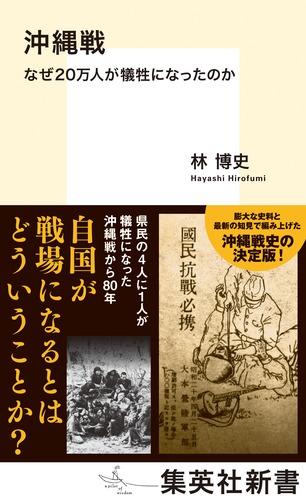
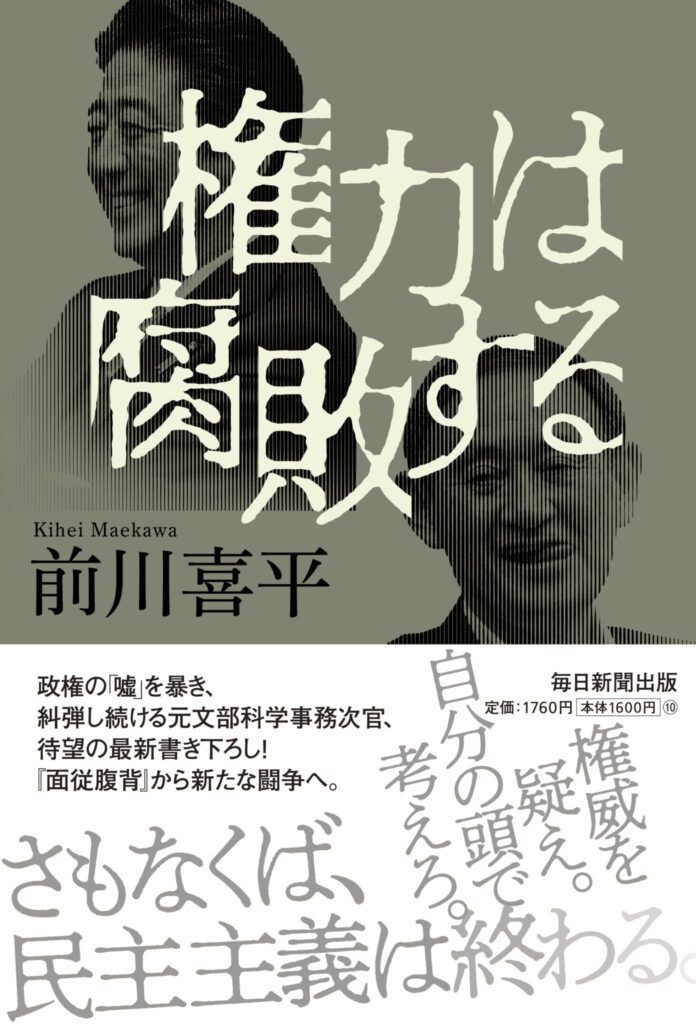










 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり



