敗戦から80年。その戦争の中でも悲惨をきわめた沖縄戦では、沖縄県民の4人に1人が犠牲になった。降伏を許されず「集団自決」させられたり、日本軍にスパイ扱いされて殺された県民もいた。
にもかかわらず、参政党の神谷宗幣代表が「日本軍の人たちが沖縄の人たちを殺したわけではない」と発言したり、自民党の西田昌司議員が、沖縄戦で犠牲となった「ひめゆり学徒隊」に関するひめゆりの塔での説明について、歴史の書き換えだと主張するなど、国会議員による問題発言が続いている。
そんな中、「沖縄戦の真実とは何だったのか?」ということに関心が集まり、沖縄戦研究の第一人者・林博史氏が今年4月に上梓した新書『沖縄戦 なぜ20万人が犠牲になったのか』が早くも5刷の増刷となった。
その林氏と、元文部科学省事務次官で、辞任後は政権の欺瞞と闘ってきた前川喜平氏が対談。
戦争と教育の責任について大いに語り合った。(全3回の第2回)
構成 稲垣收
「歴史改ざん主義」と闘うには教育を立て直す必要がある
前川 「歴史改ざん主義」の人たちと闘うのは、なかなか大変ですが、まずは教育を立て直さないといけないと思います。私自身いろいろ反省しなくてはいけないことがあります。38年間、文部省、文部科学省にいて、主に初等中等教育の担当だったわけなので。

言い訳ですけど、初等中等教育の中でも2通りの仕事があって、1つは、条件整備の仕事です。先生たちの給料の予算を取ってくるとか、施設設備の環境を整えるとか、こういう仕事、いわゆる「外的事項」と言われているのと、もう1つは学習指導要領を策定するとか教科書検定をするとか、そういう教育の中身に関わる「内的事項」と。
私は初等中等教育、つまり幼稚園から高等学校までの学校教育に関わる仕事を主にやっていたんですけど、ほとんどが外的事項です。一番大きな制度としては、義務教育の先生の給与費を国庫負担するという「義務教育費国庫負担制度」というのがあるんですけど、これが小泉改革のときに潰されそうになったんです。それで、小泉改革と闘ったのが私の仕事でしたが、「守旧派」とか「文科省は既得権益にしがみついている」などと言われました。しかし義務教育費国庫負担制度というのは、「日本国中どこでも一定の水準の教育を受けられるようにする」ためのものなので、これはなくてはならないと思っていました。
今アメリカであれだけ反科学主義的なものが広がってしまっているのは、やはり教育に問題があると思います。ああいう現象は、たとえば北欧などでは起こらないと思うんです。
アメリカというのは教育そのものが貧富の差で大きく違ってしまう。お金持ちはお金持ちだけで住んで自治体を作ったり、自分たちでお金を出し合っていい学校を作って、そこに子供たちを通わせる。貧困層は貧困層だけで集まって暮らしていて、そこの学校は、本当にまともな先生も雇えない、というふうに、貧富の差が教育の差にそのまま表れている。そうすると本当に反科学主義的な教育が広がってしまう。キリスト教原理主義みたいな人たちもいるし、「進化論を教えるな」という人たちもいる。そういうアメリカの教育は、民主主義を支える教育として非常に問題がある。
だから、日本の教育は、貧富の差で教育の質の差が出ないようにすることが大事で、そのための制度が国庫負担制度なんです。主にそういう仕事をしていて、学習指導要領や教科書に関する仕事はしていなかったんです。しかし、私はその後局長や事務次官になったので、教育の中身にも責任を負っていたことは間違いありません。
教育の中身が、長い間、保守政治の下にあったことで、相当ゆがめられてきたのは事実です。特に歴史教育で、教科書検定などにそれが如実に表れています。
それは戦争の後、戦争に責任ある人たちを完全にパージし切れなかったところに、1つの原因がある。この本にも沖縄戦のときに、教育を受けてなかった人のほうに、自決しないで生きようとした人が多かった、という話が出てきますが、教育は本当にもろ刃の剣ですから。「天皇のためには喜んで死ね」という帝国臣民を大量に作ることもできるし、一方で、自分で考えて判断して、民主主義の担い手となれるような市民を育てることもできるのです。
現代の世界を見渡しても、ロシアとか中国とかの愛国教育は、戦前、戦中の日本の教育によく似ています。そういう教育を受けたロシアの若い人たちは「ウクライナ戦争は正しい、正義の戦争だ」と思い込んでいる人が多いでしょう。だから、教育を政治的に利用することは本当に危ないのです。
学校教育は学問に基づいていなくてはいけない。歴史教育は必ず、歴史学という学問に基づいていなくてはいけない。歴史を学ぶということは歴史学を学ぶことであって、歴史学の作法を学ぶ、歴史学の方法論を学ぶ、それが大事です。
でも戦前の日本の歴史教育は、天照大神だとか、神武天皇だとか、架空の神話から始まってしまっていた。さっきも言いましたが「歴史教育は国民の物語だ」と言う国会議員が存在する余地があるということに問題があります。
学校の先生が忙しすぎて本を読まない
林 歴史教育に関して、以前は「日本では現代史の教育がきちんとされてない、現代史になる前に終わってしまう」という言い方がよくされていたんですが、その後、必ずしもそうではなくなってきました。たとえば大学入試でも、いろんな大学で意識的に現代史を入試問題で出しているケースが多くて、それなりに現代史の部分を勉強しないと受験に合格できない、という状況が生まれてきています。
ただ問題は、仮に教科書で現代史を勉強したとしても、そこで何を理解しているのかです。つまり、教科書に書かれているいろいろな項目はわかっているにしても、その歴史的背景や意味をどれだけ理解しているのか。
今、学校の先生が非常に忙しくて、本を読まなくなっていて歴史の本も読まない。そうすると、仮に教科書に載っていてそれが一応教えられているとしても、どこまで深く教えられるのか、学べるのか。時間をとって、たとえば沖縄戦とか、現代史の戦争の問題を深く教えられるのか。現代史を扱っているけれど、それを深く掘り下げて学ぶことが難しいんじゃないか。
前川 本当はそこが大事なのに。
林 ええ。だから今回の私の本でも、たとえば「日本軍の兵士がこういうひどいことをした」と書くと、「なぜその兵士の人間性を全面的に否定するのか?」「なぜ悪口しか言わないのか?」という批判が必ず出てくるんです。
でも、人というのは多様な側面があって、たとえば家庭内暴力の問題を見ると、夫が妻に対して暴力をふるうのはひどいことです。でもそういう男性は大抵、外ではすごくいい人、優しい人だとまわりに思われていたりする。だから妻が「夫がこんなひどいことをした」と言っても、なかなか信用してもらえない場合があります。
しかし人にはいろんな側面があって、ある悪いことをしたから、「その人が全面的にひどい人間だ」というわけではなくて、ある人には親切にするけれども、ある人にはすごく差別的なことをする。民族差別でもそうですが、差別をする人間が全面的にひどい人間かというと、たとえば自分の家族とか友人に対してはすごく親切であったりする。ところが、ある集団、人々に対してすごく差別をする。
つまり人はいろいろ複雑な多面性を持っていて、そういう人を「全てダメだ」と全否定したり、「全て立派な人だ」と全面的に肯定したりするのではなく、人のいい面をより育て、奨励するような組織のあり方、社会のあり方を作っていく必要があると思います。人間のひどい面ができるだけ抑えられるような組織や社会を。
この本の中でも書きましたが、日本軍兵士は軍という組織が機能しているときには本音を言えなかった。でも軍の組織が解体すると「生きたい」とか、本音を言えるようになるわけです。ですから、兵士が行った悪いことを書いても、決して「その人が悪人だ」とか、「残酷な人間だ」と言っているわけではなく、そういう、人のひどい面を増長させるような組織のあり方こそが問題だ、ということです。
住民から食料を略奪しなくてはならない状況でも戦闘を続けさせた日本軍のあやまち
林 たとえば沖縄戦で住民から食料を奪った兵士がいます。中国では日本軍がさんざん略奪をしました。でも、なぜ略奪をするかというと、軍が兵士たちに食料を供給しないからです。兵士たちは生きていくために食料を自分で調達するしかない。でも中国の農民たちも貧しいですから、渡したら自分たちが餓死するから抵抗する。すると略奪と同時に虐殺もするわけです。あるいは強かんもする。
これは兵士がひどいというよりも、兵士にそういうことをさせている軍という組織のあり方が問題なんです。沖縄戦のときも、兵士が自分たちの食料がなくなって、住民から食料を奪わざるをえないような状況というのは、もう戦争としては完全に負けているのです。本来であれば、その前に軍司令官が降伏すべきなんです。
この本には書いていないんですが、戦争の初期に日本軍がマレー半島からシンガポールに上陸します。シンガポールにいたイギリス軍は日本軍に降伏しました。その大きな理由が、シンガポール中央部にある水源地を日本軍に取られたからです。するとシンガポールにいる英軍兵士たちにも市民にも水が来なくなる。それで「これはもうダメだ」と、その段階で降伏したのです。まだ水が不足しているわけではない状態ですが、「水源を日本軍に取られた以上、これ以上、戦闘を継続すると兵士にも市民にも犠牲が出るので、もう戦争をやめて降伏する」と決定した。非常に常識的な判断だと思います。
これに対して、沖縄戦のときの日本軍が、兵士に食料を渡せないような状況というのはもうダメなわけで、降伏すべきでした。常識があって降伏していれば、兵士が住民から食料を奪うなどということは起こらないで済んだ。だから、兵士を別に弁護するつもりはないですが、兵士に略奪をさせてまで「死ぬまで戦え!」と命じた組織のあり方が問題なのです。
従来の歴史学でも歴史教育でもそうですが、戦争について語るときに単に「戦争が悪い」「戦争は嫌だ、やめましょう」ということしか言っていない。しかし「人にそういう残虐なことをさせた、人をおかしくさせた要因は何なのか」「実は社会や組織のあり方に問題があるんじゃないか」という分析をきちんとやるべきです。
先ほど前川さんも戦前、戦中の日本のあり方が戦後も引き継がれているとおっしゃっていましたが、実際そういう組織のあり方、社会のあり方自体を引き継いでしまっている。その組織のトップ、指導者たちがそのまま生き延びてしまった。でも組織や社会のあり方が変わってしまえば、かつてのトップはトップではいられなくなるはずなんです。その問題をちゃんと考えないといけない、ということも、この本を書く際にかなり意識しました。
将来も今も希望を語れなくなった日本
林 私は今ロンドンにいて、日本語のものは読まないで、世界の研究を英語で読んでいるんですけども、そうすると日本社会とか日本の学会、歴史学会も含めて、非常にガラパゴス化している、閉鎖的になっているとすごく感じます。わかっている研究者もいるんですが、全体の雰囲気として、世界の研究動向とはかなり離れて、日本独自の狭い社会の中で回ってしまっている。
先ほど前川さんが言われたこととも関連するんですが、日本で戦後補償とか日本の加害責任について、市民の中で関心が広がったのは、80年代の終わりから90年代ぐらい、ちょうどバブル期です。あの頃は人々の意識が外に向いていた。するとアジアの人々の意識のことも考えざるをえないし、バブル期の日本は自信過剰でしたが、自信があるからこそ批判をある程度受け止められた。受け止めて何とか克服しようとしていたのです。
ところがバブルがはじけ、90年代後半から「日本がよくなるだろう」という展望が見えなくなった。
私が今ロンドンで、普通の町の食堂のようなレストランで外食すると大体2000~3000円ぐらいかかります。ワインはグラス1杯で千数百円です。かつて発展途上国の人が日本や先進国に来たとき、こういう感覚だったんだろうなと想像します。ただ、かつての発展途上国は「発展途上」だから「自分たちもいつかは豊かになれる」という希望を持っていた。でも今の日本では、希望を持てなくなっている。
現実を批判できるのは、批判することによって社会を良くしようとするからです。「こういう問題があるから、克服して、いい社会を作っていこう、自分もいい生活をしていこう」という希望があるからこそできる。でも今はその希望がない。で、未来がこれ以上よくならないとすれば、現状を批判してしまうと居場所がなくなる。だから現実の中から、ともかく肯定できるものを探したい。でも今も未来にも、よりよいものがないのであれば、過去に求めるしかなくなる。それで過去、日本が世界に対して戦った「あのときの日本ってすごかったんじゃないか」と、過去にいいものを求めるしかなくなっている状況があるんじゃないか。
それと、非常に閉鎖的になって、「外の人々がどう考えているか」じゃなくて、内輪の中で「自分たちがよければそれでいい」という集団がどんどん作られている。現在のネット社会では、SNSで自分たちが気に入った集団だけで集まって「そうだそうだ」と言って喜んでいる。違う集団とは会話が成り立たなくなってくる。
日本社会全体もそうなりつつあって、そういう中で、そのような政党が出てきたのでしょう。
英国などかつての帝国は斜陽となっても「国民の生活や安全をどう保障するか」を意識している
林 そういう意味で、将来に対して何かの希望をどう語れるかが大事で。これはもちろん政治家にも語ってほしいし、研究者や教育者も語る必要がある。
ヨーロッパを見ていると、たとえばイギリスはかつて大英帝国でしたが、どんどん斜陽していった。オランダやベルギー、スペインもポルトガルもかつては帝国だったけどかつてのような栄光はないし、世界のリーダーにはなれないし、経済的にもトップとは言えない。しかし下がりながらも、その中で「国民の生活や安全をどう保障するのか」ということはかなり意識しながら社会を作ってきていると思います。
だから日本もGDPが中国やドイツに抜かれたけれど、だからといって社会がダメになっているわけじゃなくて、そういう中で「1人1人が安心して生活でき、生きていけるような社会をどう作っていくのか」という部分をきちんと、やってこなかった。たぶんこれは自民党政権がずっと続いてきた問題とつながっている。
そういう中で日本という国全体の大きさはもちろん中国には当然負けるでしょうけど、「1人1人の生活を見ると、決して卑下するようなものではなく、質の高いものをきちんと作れるんだ」という展望を示すことが大事だと思います。
今グローバルな中で、日本の中で生まれ育って、日本社会の中でも、外に出て行っても、「いろんなことで自分たちの能力を発達、発展させることができる」「そこで生きていくことができる」という希望を示すこと。そういう希望を持つことによって、初めて現実の問題を見つめ、それを批判して、自分たちで克服しようという意思が生まれてくるんだろうと思います。
1997年に発足した「つくる会」と教科書議員連盟
前川 私も若い頃にイギリスに2年間、留学させてもらいました。1980年代ですから、サッチャー首相が出てきた頃で、サッチャーが出てくるまでのイギリスは低迷していて――サッチャーの政策がよかったかどうかは検証が必要でしょうが――日本では「英国病」という言葉が使われイギリス人をバカにするような議論がずいぶんありました。「あんなふうになっちゃいけない」と。でも今の日本はまさに「日本病」です。40年前に英国病と言っていたイギリスよりもひどいかもしれない。今、林さんがおっしゃったようにバブル崩壊後の30年というのは、「自信喪失の裏返しの空威張り」みたいなものが出てきたんじゃないかという気がします。ちょうど、歴史教科書に対する政治家の攻撃が始まったのも、その頃です。
直接のきっかけは、いわゆる従軍慰安婦問題でした。1991年に韓国で金学順(キム・ハクスン)さんという女性が本名を名乗って日本政府を訴えたことです。それまで実名を名乗って出てくる人はいなかったんですが。それがきっかけで、いわゆる従軍慰安婦問題は日韓の外交問題になりました。
それに対して当時の自民党は宮澤喜一内閣で、今よりずっとまともというか自民党内でもリベラルな人たちが政権を持っていたので、「日本政府の責任で調査します」と約束して、調査の結果を踏まえて、当時の官房長官の河野洋平さんが93年に河野談話を出しました。どこまで学問的に正しいかということは別の問題としてあるかもしれませんが、「総じて強制性があった」ということを認めた上で、おわびと反省の言葉を述べて、さらに「歴史研究と歴史教育を通じて次の世代にも伝えていく」と約束しました。
それまでも中学、高校の教科書で従軍慰安婦の問題を扱ったものはあったんですが、河野談話が出たことがきっかけで全ての中高の歴史教科書に従軍慰安婦が載りました。95年度の検定の際には中学の歴史教科書で全ての教科書会社が載せるようになり、その教科書検定の結果がわかったのが96年3月。97年度から実際にそれが使われ始めました。
そしてこの96年から97年にかけて、慰安婦問題を学校教育で扱うことに対する右派の反発がどーんと出てきた。自民党の中に「教科書議員連盟」(正式名称「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」)が結成されて、初代会長になったのが中川昭一氏、初代事務局長が安倍晋三氏です。中川氏も安倍氏も当時は40代前半で、彼らが「従軍慰安婦のことを教えるな」と言い始めた。

学者の中からも、藤岡信勝氏(*)らが「こんな教科書でいいのか」と言って、「新しい歴史教科書をつくる会」というのができました。この「つくる会」が、「日本国民であることを誇りに思えるような歴史教科書を作るんだ」というようなことを言って、日本の国家、あるいは政府が行った過去の負のでき事、侵略戦争や植民地支配、それに伴う非人道的な行為などを子供たちに教えない、教えないどころか、なかったことにしてしまう。そういう歴史教育をやろうとした。そんな「つくる会」の歴史教科書と、自民党のタカ派グループの教科書に口を出す人たちとが連動していった。
この人たちは歴史教育だけでなく道徳教育も推進してきた。「戦前の家父長制をもう一度作り直したい」というようなイデオロギーが背景にあると思います。
彼らは歴史教育に関して言えば、南京虐殺を否定する。従軍慰安婦の存在は認めているんだけれども、「自らの意思で、商売のために行った売春婦だった」として、「意に反して仕事をさせられたというのは間違いだ」という言い方をします。
もう1つが沖縄戦の集団自決について。「これは住民の愛国心から行われた自発的な行為であって、軍隊が強制したり命令したりしたことじゃない」と教えさせようとして、特に中学、高校の歴史教科書に口を出すようになりました。
歴史教育は、小学校では6年生、中学校では3年生で主に日本史を教えるわけです。高校では、かつては世界史が必修で、日本史は必修じゃなかったんです。これに対してはむしろ右派、自民党のタカ派の人たちから批判があって、「ちゃんと日本の歴史を教えろ、高校で日本史を必修にしないのはおかしい、日本人なんだから」と。
確かに世界史が必修で日本史が必修でないというのはおかしかったと、私も思います。ただし、自民党タカ派が「日本史を教えろ」と言っているのとは、また違う意味です。彼らが言っていたのは、日本人として誇りを持たせるとか、皇国史観の復活みたいなことですから。(第3回に続く)
* 藤岡氏は産経新聞『正論』常連執筆者で、教育学者・教育評論家。宗教団体「キリストの幕屋」で講演会を何度も行い、旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)系のメディア「世界日報」に寄稿し、幸福実現党の党首と対談するなど、宗教団体や関連団体とも関係が深く、また参政党の学習会でも講師を務めている。
プロフィール

(まえかわ・きへい)
1955年、奈良県生まれ。東京大学法学部卒業後、79年、文部省(現・文部科学省)入省。文部大臣秘書官、初等中等教育局財務課長、官房長、初等中等教育局長、文部科学審議官などを経て2016年、文部科学事務次官となり、17年に退官。自主夜間中学スタッフとして活動し、執筆活動にだずさわる。『面従腹背』『権力は腐敗する』(ともに毎日新聞出版)、『日本の教育、どうしてこうなった?』(児美川孝一郎との共著、大月書店)など著作多数。

(はやし・ひろふみ)
1955年、神戸市生まれ。現代史研究者、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了(社会学博士)。関東学院大学名誉教授。主な著書に『沖縄戦 なぜ20万人が犠牲になったのか』(集英社新書)、『沖縄戦と民衆』『沖縄戦が問うもの』(大月書店)、『沖縄戦 強制された「集団自決」』『米軍基地の歴史 世界ネットワークの形成と展開』『帝国主義国の軍隊と性 売春規制と軍用性的施設』(吉川弘文館)、『朝鮮戦争 無差別爆撃の出撃基地・日本』(高文研)、『BC級戦犯裁判』(岩波新書)等多数。


 前川喜平×林博史
前川喜平×林博史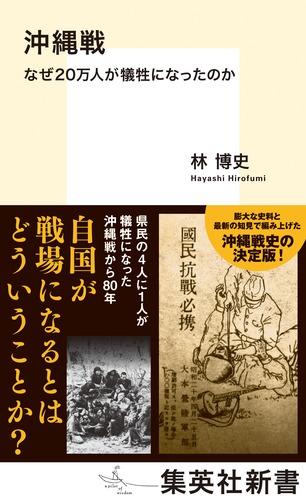
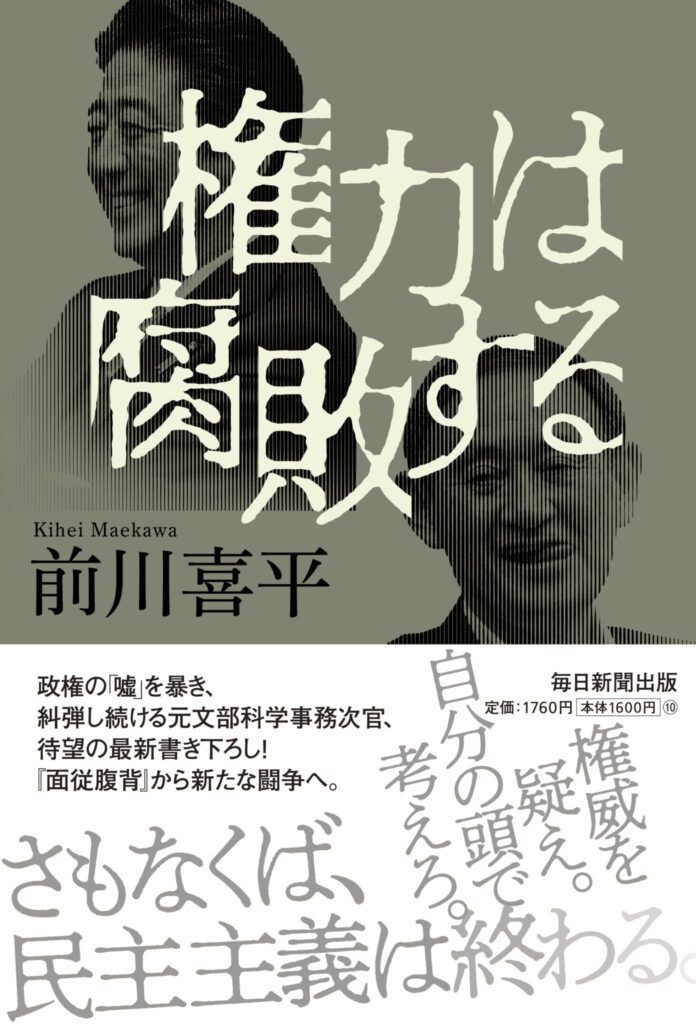





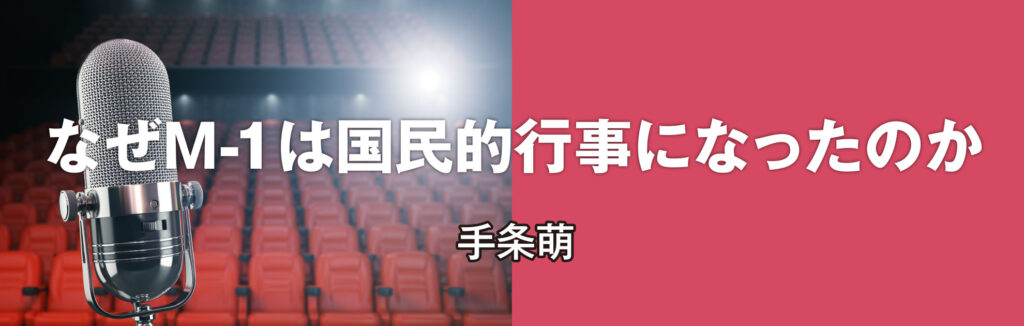







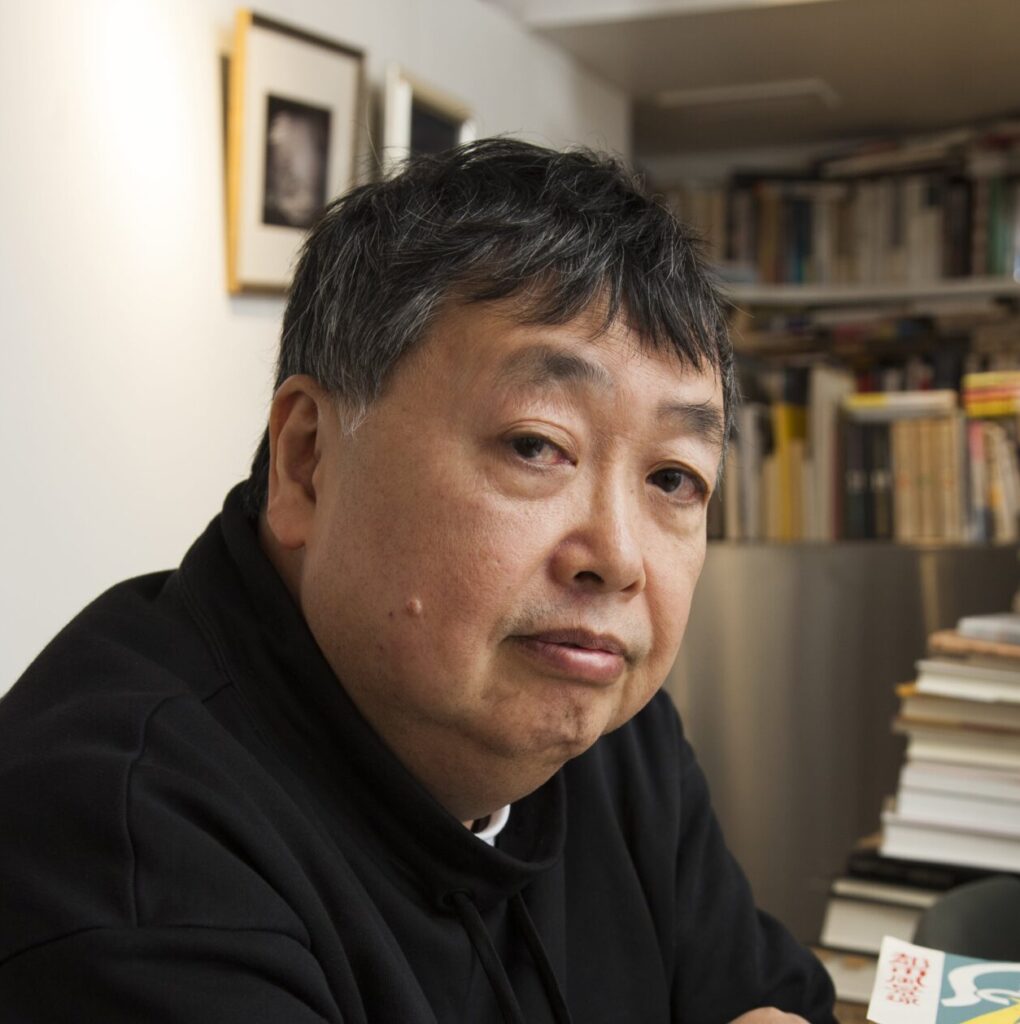
 大塚英志
大塚英志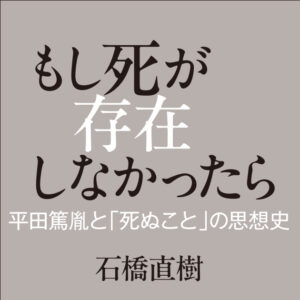
 石橋直樹
石橋直樹