知のコンタクト・ゾーンとしての医学
ナポレオン・ボナパルト(Napoléon Bonaparte,1769-1821)がフランス皇帝の冠を頭上に戴き、世界史がきしみ音を立てて動き出した一八〇四年。文化元年の日本で、平田篤胤は「真菅乃屋」という名の家塾を開いた。一枚の世界のただなかにある西洋と極東で、まったく異なるかたちの転回が始まっていた。
前年、享和三年(一八〇三年)。宣長の著作に出会って衝撃を受け、あまりの感激に夢の中で宣長に入門を願ったほどである。膨大な門弟を擁する「鈴屋」の営みを遠くに見据えつつ、国学における自らの而立を意識しはじめた篤胤は、この年、まだ二九歳だった。しかも同じ年、ロシア使節レザノフが長崎に来航する。私塾の開業は、単なる学問的独立ではない。それは、迫り来る対外危機に正面から向き合うための、最初の具体的な一歩でもあった。
私塾の開業以降、多くの著作を立て続けに執筆し、翌年には『新鬼神論』、『伊勢両宮御鎮座部類記』、翌々年には『本教外編』などの著作が続々成立していくことになる。しかし、初年度の入門者はたった三人だけであった[1]。次の年は二人、その次の年は四人だった。
私塾を開業し、学問的にもさらなる飛躍の年にしていかなければならなかった。学生もどんどん集めていく必要がある。濁流のように押し寄せる西洋などの学知に、早く自分も追いついていかなければならなかった。『千島白波』でロシア語を学び、北方の情勢を探りながら、さらなる飛躍のために篤胤が照準を定めたのが、「医学」[2]だった。そしてためらいもなくその世界へ踏み込み、篤胤は、医者になった。
文化四年(一八〇七年)、篤胤は医者となって名前を「元瑞」に改めた[3]。もともと秋田時代に伯父大和田昌順に、また江戸では藤兵衛の甥で横須賀藩士天野道順について医学修行をしたことが明らかになっている[4]。おそらく篤胤が興味があったのは臨床と結びついて、その知識の正確さがはっきりと現れる医学という〈知〉の制度であった。そしてまさに、当時の医学は、後世方派・古方派・考証学派など諸流派を形成していた東洋漢方医学と、新しく輸入された蘭方医と呼ばれる西洋医学が、正当性の沽券を争っていたのであって、篤胤は国学という観点から、この最新鋭の知識とのコンタクト・ゾーンに参入していくことになる。
東洋医学における「後世方派」「古方派」「考証学派」
篤胤の時代の医学状況を説明するために、まずは簡単に近世医学史をおさらいしていきたい[5]。「死」のアクチュアリティに関わる問題なので、固有名詞を恐れず紹介してみたい。
近世漢方医学の基盤となるのは戦国時代の医聖・曲直瀬道三(一五〇七―一五九四)の確立した医術であり、当時の明からもたらされた明朱医学を臨床で実用化し、毛利元就、足利義昭、織田信長などの主治医として活躍した[6]。近世になると宋学的な最新医学を参照していた道三の医術は重要視され、近世のスタンダードな医術として臨床に普及することになる。
しかし、伊藤仁斎(一六二七―一七〇五)などの古義学によって宋学批判が起こると、医学でも宋学的な体系以前の古典回帰を唱える「古方派」が登場する。「古方派」は実証主義的臨床を標榜し、古代中国の張仲景(一五〇―二一九)の書いた感染症に対する緊急救命の医書『傷寒論』を最も重要な古典に位置付けた[7]。古方派医家には後藤艮山(一六五九―一七三三)とその弟子の山脇東洋(一七〇六―一七六二)などがいる。特に東洋は宝暦九年(一七五九年)に人体解剖を行なって日本初の解剖図録『蔵志』を刊行して漢方医学の五臓六腑説を批判し、西洋医学への先鞭をつけた。こうした古代中国医学への回帰を志向する「古方派」に対して、道三による伝統的な宋学医学は「後世方派」と呼称される。
近世漢方医学における「後世方派」と「古方派」の派閥争いを受けて、漢方古典を文献学的・客観的に校訂・整理する「考証学派」が登場した。これは、一七九二年に私塾から幕府直轄の医官養成校になった医学館によって制度的に支えられていた学派で、多紀家が中心となって古典本文の異同を精査し、注釈と訓読、引用諸説の整理を通じて学としての再現可能性を高めることが目指された。多紀家から多紀元簡(一七五五―一八一〇)が出て、考証的な医学注釈が完成した。
このように大きく「後世方派」「古方派」「考証学派」などの学派に分裂していた東洋漢方医学であったが、ここに、全く異なる体系としての西洋医学が衝突していくことになる。東洋医学は身体全体のバランスや自然治癒力を重視し、調和の回復を重要視する体系であるが、西洋医学は病気そのものや局所の病巣を解剖学的に特定し、直接的な治療介入を行う体系である[8]。これは、融合することの難しい二つの体系なのであって、近世知のコンタクト・ゾーンを形成した。
近世医学史における西洋医学
西洋医学は、ドイツ人医師カスパル・シャムベルゲル(Caspar Schamberger、1623-1706)が、慶安二年(一六四九年)に長崎の出島に来航したことが本格的に輸入される契機になった[9]。シャムベルゲルは西洋式の「体液病理論」に基づいた施術法によって幕府高官を治療して、日本人医師に西洋医学を教授し、その知識は写本として流布して「カスパル流外科」の基礎文献となっていった。
明和八年(一七七一年)、医者の中川淳庵(一七三九―一七八六年)が、江戸参府中の出島商館長より『ターヘル・アナトミア』(Johann. A. Kulmus著、Anatomische Tabellen)を見せられ、それを杉田玄白(一七三三―一八一七年)と前野良沢(一七二三―一八〇三年)のもとに持っていったことで、西洋医学は次の段階に進むことになる[10]。この『ターヘル・アナトミア』を片手に、江戸・骨ヶ原の解剖現場に立ち会ったところ、その素描があまりに正確であることに驚き、有名な『解体新書』の翻訳事業が開始された[11]。これは文化史的にいえば、医学が解剖学としての実見と結びつき、身体の記述を観察=実証の側へ引き寄せていくことになったといえる[12]。
『解体新書』の翻訳は近世医学に革新をもたらしたが、誤訳も多かったので、杉田玄白が弟子の大槻玄沢(一七五七―一八二七年)に改訂を命じた。これを契機として、オランダ語の正確な翻訳のための学習共同体が形作られることとなり、その一環として玄沢は私塾の芝蘭堂を開業することになる。「芝蘭堂の四天王」と称されるほど優秀であった門弟の津山藩医・宇田川玄真は、複数の西洋医学書を翻訳・要約して文化二年(一八〇五年)に『医範提綱』を刊行したが、これによって内科学・生理学・病理学の国内的な受容が進んでいくこととなった。
篤胤の時代は、このように東洋漢方医学と西洋解剖医学がともに一つの成熟を迎えつつあった時期であり、「後世方派」「古方派」「考証学派」などの東洋医学と、蘭方医としての西洋医学をどのように運用するかということが、実利的な関心として浮上してきていたのである。たとえば、外科医の華岡青洲(一七六〇―一八三五年)は、元々「古方派」に属する医者であったが、実験と実証を重んじて西洋医学も区別なく取り入れ、世界初の全身麻酔による乳癌手術に成功している。まさに、学知の衝突が、生活の必要から呼び起こされているわけである。そして篤胤は、この衝突する学知の中に自らの居場所を発見した。
医者・篤胤における東洋医学と西洋医学
さてこのような学知のぶつかり合いのなかで、医師・篤胤(元瑞)は何を学び、何を構築していったのか。篤胤自身は、「古方派」に属する漢方医であったことが指摘されている[13]。篤胤は、「古方派」の医師・和田東郭(一七四四―一八〇三)の流派を学んでいることがわかっている[14]。この東郭は「古方派」を習得しながらも、それ以前の「後世方派」も折衷的に取り入れることを重要視した医術を提唱していた[15]。重要なことは、もともと実証主義的臨床を重要視して古典回帰を唱えた「古方派」は、蘭学の解剖学的実証主義と極めて相性がよかったということである。
文化四年(一八〇七年)から二年間、篤胤は蘭学塾の蘭馨堂に入学して蘭学を学んでいる。この蘭馨堂は、先ほど『医範提綱』を完成させた人物として紹介した宇田川玄真の直系の弟子・吉田長淑(一七七九―一八二四)の私塾であり、篤胤はここでもっぱら最先端の西洋医学を学んだ[16]。長淑は、日本初の西洋内科医として知られる人物である。この私塾で篤胤は、死体の解剖などにも立ち会っており[17]、充実した環境で西洋医学を研究していたということができるだろう。こうして、篤胤は東洋医学と西洋医学を折衷的に超越していくことを目指すようになる。
医学研究の成果を篤胤は、文化八年(一八一一年)に成立することになる『志都能石屋講本』(『医道大意』)で展開することになる。この書籍は、のちに「神醫道」の淵源を述べる本[18]と篤胤自身が思い返すように、東洋医学も西洋医学も超越した「神醫道」なるものが模索されていた。しかし、それはどんなものか。篤胤の記述を追ってみたい。
医師・篤胤が発見した「神醫道」
篤胤は「西洋人が解剖ということをよく明らかにしているのを見ると、つねに人体の内部はどのような構造になっているのかを心得ておくことが肝要であると分かる」[19]といって、西洋医学における「解剖」を重視し、病の根本を視覚的に理解し、その原因を治す事が重要であるというように、西洋医学の知見も存分に取り入れていく。篤胤は「魂」がどこにあるのか、神経や血液の体内循環、それから生殖過程における胎児の発生過程について、「古方派」の知識を西洋医学の知識に接続しながら詳細に説明している。
ここで、西洋医学を取り入れて、篤胤が理解しようとしていたことは、人はなぜ生まれ、なぜ死ぬのか、ということであった。「人間が、それぞれこのように生きて動くということが、第一に霊妙なことなのである」[20]として、篤胤にとっての最も重要な関心は人間の生死の原理を探ることであった。しかし、分裂する学知としての東洋医学と西洋医学は、この根本的な答えにはならない。それらは局所的な治療の技術にはなるけれども、生死の根本原理から解決する医道ではありえない。そこで、西洋医学と東洋医学の分裂を回復するために、高次元に回帰するのが神代にあったとされる「神醫道」なのである。
医薬の道は、神皇産霊大神に始まり、大穴牟遅神と少彦名神がそれを受け継がれ、さらに広く選び整えられて、この現世に至っては、万国にまで伝え広められたものと考えられる。そもそもわが国の古代においては、神代は言うまでもなく、その後の時代においても、人々の心はおおらかで思い悩むこともなく悪い病などもなかったため、医薬方術もそれほど必要とされず不足することもなかった。ところが、仁徳天皇の御代の頃から、はじめて次々と多くの漢人が渡来し書物を献上するようになり、またこちらからも彼の国の学問を学ぶために大使が派遣されるなどして、さまざまな事柄、とりわけ医薬方術、そしてそれに関する書物が伝えられてきた。人々がそれらを珍しく感じるようになるにつれて、いつの間にか、わが国本来の医薬の道はおろそかにされていったのである[21]。
この文章が示しているのは、単なる医学史の回顧ではない。医薬の起源を神代にまで遡らせることで、日本の医学が分裂する外来文化の模倣によって始まったのではなく、本来的には神々によって授けられた知であったという枠組みへと反転するのである。医道は、大国主神(=大穴牟遅神)と少彦名神の二柱によって始められ、整えられ、もともとは日本固有のものとして万国にまで広まったと篤胤は述べる。古代の日本では人々の心はおおらかで、深刻な病も少なかったため、医術は最小限で足りていたのだという。この本来的に神によって生み出された医道こそ、「神醫道」と篤胤が考えたものである。
「神醫道」といって篤胤が捉えようとしているのは、分裂する東洋医学と西洋医学のような臨床的・技術的な問題ではなく、根本としては「まじない」としての形而上的な側面、より根源的な「神の御所為」についてである。対処療法的にその場その場で治療するのも重要だが、それより重要なのが大国主神と少彦名神の二柱によって作られた神の道を理解することなのであると述べているのである。
臨床的な側面を超える神の道を把握することで「生きること」は正しく理解され、「死ぬこと」を逃れることができる、これこそが篤胤が見出した医道であった。この神の道としての医道の発見は、篤胤の「死ぬこと」の思想において長く探求されることになる。というのも、この医学から「神醫道」への移行は、まさに「生きること」の技術としての医術から神道への超越ということができるだろう[22]。
篤胤は、二年ほどで医者を辞めてしまった。その理由は、医者組合の堕落をまざまざと見せつけられたからだという[23]。そして、同時に篤胤自身が人を救うことができなかったという経験も強く響いていた[24]。「こんなことを見るたびに聞くたびに段々医者が嫌になり、またどんなに骨を折って苦労しても治療をし損じることがあって、古学の研究が日を追って忙しくなって片手間ではできないので、医者をはたと辞めてしまった」[25]と言っている。
そして、医道を経由して、「死ぬこと」を乗り越える道としての神道の探求へと再び向かっていくのである。
講説家・篤胤の誕生
文化四年(一八〇七年)には江戸の京橋守山町(現在の銀座六丁目)に転居し、さらに翌年には京橋尾張町(現在の銀座五丁目)に転居した。文化六年(一八〇九年)には、「広く古道の講演を始められた」[26]と記録されるように、積極的な門人獲得に乗り出して公開講釈を開始した[27]。この講釈には、「表会」と「内会」と呼ばれる区別があったようで、「表会」は一般に向けた公開講座であり、そこで興味を持ったものが門人となって、内輪の講釈である「内会」に参加した。
篤胤の私塾・真菅乃屋は手習所を借りて開催され、演目には「古道の大意」、「仏道の大意」、「俗神道の大意」、「儒道の大意」、「歌道の大意」、「医道の大意」、「年中行事の大意」のようなものが並んだ。これらの講釈を基にして、後年、いわゆる大意物と呼ばれる講義録の形をとった「講本」が成立することになる。すなわち、『古道大意』、『仏道大意』、『俗神道大意』、『儒道大意』、『歌道大意』、『志都能石屋講本』などである[28]。
特に養子の銕胤によって「宇宙第一の正道」を説いたものと評価される『古道大意』は、篤胤が亡くなってから入門した「没後の門人」たちによって、篤胤の講義が伺えるものとして大変重宝されたものである。『古道大意』は、篤胤の思想を満遍なく記したものであるが、まだこの段階では宣長の影響が色濃く残っている。しかしここで最新鋭の知識が顔を出している。西川如見(一六四八―一七二四)の『華夷通商考』『日本水土考』やドイツ人医師のエンゲルベルト・ケンペル(Engelbert Kämpfer,1651-1716)の『日本誌』を参照しつつ、地球球体説や地動説などに触れ、世界情勢から日本を位置付けているといえよう。その上で「天文地理および外国の説を以て、御国が万国に優れているということは、この天地の間の公論であることをここに示そうと思うのでございます」[29]と篤胤は講じている。
肘の骨が飛び出る不眠不休の執筆
この年の十月より、篤胤は駿河国(現在の静岡県)へ旅行し、翌年の正月まで家を空けている。講演の原稿を作り新しい門人獲得のため、猛烈な仕事量を昼夜問わずにこなしていた一年であった。そこで、師の多忙を気遣って保養させたいという意図から門人たちが旅に誘い出したのである。宿は、府中の門人・柴崎直古(不明―一八三五年)が一間を見繕った。その仮住まいの場所に、有り合わせの古典書籍を全部持ってきてくれというと、近隣の門人たちがやってきて色々な本を持ち寄ってくる。その初学者たちに応対しているうちに、何かを思いついたのか唐突に篤胤は部屋にこもってしまったのである。それを間近に見ていた門人は次のように証言している。
(やってきた初学者たちに)春を迎えて長閑に過ごそうとお言葉をかけられて、そのまま人に会わず静かにこもられたのが、五日の日のことであった。それ以降は、夜の寝具にもお近づきにならず、文机の前に座られてからは、昼も夜も通して書物を読み、また筆を取って執筆に没頭なさっていた。朝夕のお食事をお出しする間でさえ、少しも手を休めることなく、読み書きを続けながら、文机の上でそのまま召し上がっていたのである。そうして過ごしておられた期間は、十日あまり三日、四日ほどであったように思われる。このように昼夜続けてお励みになっていては、お身体を大切になさるべきであるから、今夜からは夜は床にお入りくださいと、強く申し上げたところ、「それではしばらくうたた寝をしよう。目が覚めるまで決して起こさないでほしい」と言われ、枕を抱え、そのまま布団を引きかぶって、すぐに高いびきを立てて深くお休みになった。そのまま一日、さらに二夜にわたって、同じ状態でお休みになっていた。あまりに長く眠り続けておられるので、こちらも次第に不安になり、そっとお起こし申し上げたところ、「起こすなと言ったではないか!」と言われるや否や、すぐに文机に向かわれ、以前と同じように熱心に執筆に励まれるのであった[30]。
この年、すなわち文化八年(一八一一)の十二月五日から二五日間、大晦日の真夜中まで、昼夜を問わず『古史成文』の編纂に取り掛かることになる。初学者たちと話しているうちに、前々から思っていた古史編纂の作業にとりかかろうと急に決心をし、寓居に籠もって、一気呵成に『古史成文』『古史徴』の二部の初稿を書き上げてしまった。起きてはずっと昼夜を問わず作業しており、寝たと思ったら何日間も寝続けた。超人的な執筆作業である。
一説によると、篤胤は左利きであったからずっと左肘を文机についている。そうすると、左肘の皮が破けて骨が飛び出てきてしまった。篤胤がそれに構わず作業を強行していたので、文机の肘が当たるところに穴を空けて、クッションなどを敷いて痛みを和らげるようにしたという[31]。この穴の空いた文机は、現在は歴史民俗博物館に所蔵されている。
完成した『古史成文』(全一六五段)は、天之御中主神の出現から神武天皇の誕生までの古伝を、『古事記』『日本書紀』や『延喜式祝詞』などから選定して、本当に古伝として起こったことを正しく記述することを目的として歴史叙述されたものである。また、『古史徴』(全四巻一一冊)は、古典総論である「古史徴開題記」にはじまって、『古史成文』の典拠を説明した総論である[32]。すなわち、これらは篤胤によって再構築された新たな正史なのである。
数多くの異伝がある日本の古伝において、どれが正しいかを選定して統一的な歴史を書くということは並々ならぬエネルギーが必要である。これを、篤胤は物凄い集中力によって、これだけの稿をたった二五日間で書いてしまったのである。
「晩き心」と「心速き人」
篤胤が構築する神代からの歴史、それはどんな歴史哲学によって記述されているのだろうか。まさに大文字の正史となる「正しい古史」は、多くの誤伝が混じっている神代の歴史を再構築するものであった。それは、篤胤の時代のリアリティを反映して、多くの分裂する学知を再統合するものとして機能していたものといわなければならない。篤胤はその方法論について、次のように述べている。
神代の出来事を聞いてから、その後になってはじめて神代とはこのようなものであったのだろうと驚くような、「晩き心」では悟ることは難しいだろう。それよりも、神代の出来事を聞く以前に、早く天地世間の有様をよく観察し、世の始まりは神の御業によって、このように成り立ったのであろうなどと、あらかじめ思い至ったうえで、神代の古典を読み、まことに自分の考えは間違っていなかったと悟るほどに「心速き人」であれば、疑いを抱くことはないであろうと思われるのだ[33]。
神代の出来事を考えてから世界の始まりは、実際はこうだったと考えるようでは「遅い」のだ。世界のさまざまな光景、学知、成り立ちをみて、すでに腹のなかに神代はきっとこうだったという風景がありありと浮かんでいるようでなければならない。古典を読むより前に、世界の始まりが思い浮かんでいなければならない。そのような「心速き人」にしか歴史は書けないのである。この篤胤の歴史への向き合い方は、研究では「神話的な眼」(山下久夫)と呼称され、「日常、天地世間を神話と関連した光景として捉える感性」[34]と述べられているものだ。
また、篤胤がこのような方法論によって構築したのは、「近世神話」(斎藤英喜・山下久夫)といわれる近世的な知のあり方である[35]。ここでいう「近世神話」とは、単なる虚構の物語のことではない。それは、それぞれの時代が必要とする〈自分たちは何者か〉という問いに答えるために生み出される、知の運動だということができるだろう。
重要なのは、こうした新しい正史が単に神代から歴史を文献学的に確認する作業ではないという点である。むしろ新しい正史としての「神話」とは、時代ごとの状況に応じて、新たな地平を切り開くための拠りどころとして見出され、あるいは創り出されるものだ。こうした新しい正史の構築によって、それまで当たり前だと思われていた事物や状況は、別の角度から捉え直される。そこで新たな意味が与えられ、価値が再発見される。その意味で神話とは、「今」という時代を理解し、意味づけるための知のコードだと言うことができるだろう[36]。
顕微鏡のなかに見た〈神〉
古代には古代の神話があり、中世には中世の、近世には近世の、そして近代・現代にはそれぞれの時代にふさわしい神話が求められる。時代が変われば、問いもまた変わるからだ。近世において生きた「神話」は、十七世紀の朱子学、十八世紀の国学や西洋科学といった学知と結びつきながら、新たなアイデンティティを形づくっていった。そしてその学知とは、さまざまに輸入されてきた西洋科学の最新知識であったり、医学、易学、古文辞学、仏教学、玄学等々の当時の最新の学問的成果であった。それの学知の分裂した状態から生じる、認識的な空間を埋める形で新しい神道の形が模索され、その神道的宇宙モデルが世界認識そのものを統一的に記述するというような現象であったということができるだろう。
篤胤が最新の科学知を基にして、どのように正史を再構築していったのだろうか。先ほど『古史成文』の注釈書である『古史伝』の記述をみてみたい。篤胤の神解釈は宣長の神解釈を踏襲しながら、西洋科学技術の驚異の中に神を見出している。周知の通り、宣長は神を「迦微」として、次のように定義していた。「古典などに記されている天地諸々の神々をはじめとして、それらを祀る社に鎮座する御霊のことも指して言い、また人間は言うまでもなく、鳥獣木草の類、さらに海や山など、そのほかどのようなものであっても、並外れて優れた徳を備え畏れ敬うべきものを迦微というのである」[37]。篤胤は宣長を超えて、「神」を科学知から全く違うものとして捉えられているのである。
まず「神」の意味についてであるが、『日本書紀』巻頭に「古には天地が未だ分かれず、陰陽が分離せず、混沌としてまるで卵の中身のようであり、その中に〈牙〉を含んでいた」と記されているが、この〈牙〉こそがそれである。(中略)このようにして、この〈カビ〉と呼ばれるものの形状を考えてみると、それはまさしく男茎の形であると考えられる(先に述べた頭槌の剣、鏑矢などの形を思い合わせるとよい)。そもそも、きのこ類は〈カビ〉そのものであるが、これは草木の生命力が地の気と結び合って生じるものであり、自然に同じような形をとるというのは、きわめて霊妙なことである。(また、一般に物体に黴が生じるとき、それは非常に細い毛が生えたような姿をしているが、いわゆる顕微鏡で観察すると、その細い毛のように見えるものは、ことごとく男茎の形を備えていることが分かるはずである[38])。
篤胤は神の原義を「カビ」に見出し、『日本書紀』冒頭の「溟涬にして牙を含めり」における「牙」を「カビ」と訓じて、霊妙なる物という意味で再解釈している。そして「カビ」というものの形状は陰茎の形をとっているというように考えている。だからいわゆる菌としての「カビ」も、草木の精気が地気に混ざって生まれた霊妙なものであるから、同様に陰茎の形をとっているのであるというように続けている。
おそらく、ここで極めて重要なのはその、菌としての黴の形状の発見が前提として存在しているということが挙げられよう。それは西洋技術である顕微鏡を通して発見されている。顕微鏡を覗くと、そこには古史にあるような「牙」のような、そしてまだ陰茎のような神妙な形状があった。その神秘に篤胤は触れたのである。顕微鏡の中に見た〈神〉、これこそが篤胤が発見した新たなる原理であった。
篤胤は、西洋科学の学知の輸入によって必然的に生じた認識的な空白そのものに神を発見するのであって、分裂した学知統合のために神と黴は同一のものとして論じられる。学知の分裂を全て統合できる知的基盤となったものが、『古事記』などの神道的知識であり、神代の知識を媒介にして新しい正史を再統合することが可能になった。顕微鏡の小さな覗き穴の中に、篤胤は高次元に回復する新たなる〈神〉を発見したのである。それは、新たな正史として時代を変えていくことができるような一つの原理でもあった。
(次回へつづく)
[1] 「入門之者三人」ほか。平田銕胤「大壑君御一代略記」『新修平田篤胤全集』名著出版、一九七七年、六〇二頁。
[2] 伊藤裕『大壑平田篤胤伝』錦正社(一九七三年)では、金銭的な困窮が医者になった理由として論じられるが、同時期に『千島白波』の編纂など精力的に活動していることを見ると、金銭面という消極的な理由とは考えられない。むしろ、医学における西洋知のあり方に触れて、自らの体系に入れ込もうとしたように思われる。
[3] 「再ビ醫師ト爲り。名ヲ元瑞ト改メ玉フ」平田銕胤「大壑君御一代略記」『新修平田篤胤全集』名著出版、一九七七年、六〇二頁。
[4] 平田篤胤関連資料として発見された「養父平田藤兵衛願書」にて記載あり(宮地正人編「平田国学の再検討」『歴史民俗博物館研究報告』歴史民俗博物館、第一二二集、二〇〇五年、一二九頁)。
[5] 富士川游『日本医学史綱要 1(東洋文庫 258)』平凡社、一九七四年。富士川游『日本医学史綱要 2(東洋文庫 262)』平凡社、一九七四年。服部敏良『江戸時代医学史の研究』吉川弘文館、一九七八年。海原亮『近世医療の社会史:知識・技術・情報』吉川弘文館、二〇〇七年。青木歳幸『江戸時代の医学:名医たちの三〇〇年』吉川弘文館、二〇一二年等を参照した。
[6] 町泉寿郎「江戸時代医学諸派の身体観と養生思想」『大倉山論集』大倉精神文化研究所、第六十八輯、二〇二二年参照。
[7] 平馬直樹「江戸時代の漢方医学と現代中医学」『日本医科大学医学会雑誌』日本医科大学医学会、第九巻第四号、二〇一三年、二一八―二二〇頁参照。
[8] 中山茂『近世日本の科学思想』講談社学術文庫、一九九三年参照。
[9] ヴォルフガング・ミヒェル「日本におけるカスパル・シャムベルゲルの活動について」『日本医学史雑誌』日本医学史学会、第四一巻第一号、一九九五年、三―二八頁ほか参照。
[10] 杉本つとむ『解体新書の時代』早稲田大学出版部、一九八七年参照。
[11] 杉田玄白『蘭学事始』岩波文庫、一九八二年参照。
[12] ちなみに『解体新書』の挿画を担当したのは秋田蘭画派の小田野直武であり、蘭画受容においていかなる形においても変型させることができるというデューラー的関心のもと、解剖学の受容は日本美術史においても極めて重要な位置を占めている。「そもそも「解体新書」の図絵を、医師ではなく、絵師の小田野直武が描いた事が革命的であったといえる」との指摘は正しく、身体を分析する医師の登場は蘭画との共犯関係においてであった。(郡佳子・田辺健一郎・織田俊郎「日本の解剖学的美術の変遷」『帝京短期大学紀要』帝京短期大学、第二二号、二〇二一年、一七三頁)。
[13] 坂出祥伸「平田篤胤の醫書『志都能石屋講本』について」『人文学論集』大阪府立大学、二〇一二年、第三十巻、一―一四頁では、「大壑君御一代略記」の記述と『傷寒論』重視の態度、和田東郭の門弟であるという手紙の記述から「古方派」であると推定されている。
[14] これは前述の坂出論文を参照した。「私儀若年の砌り上京仕り、醫業稽古仕候節、和田家門人竹井大業と申ス者より、東郭治驗の口訣相受ケ、其方書類傳授いたし、其後江戸表に於て醫業開業仕候節、云々」(渡辺金造『平田篤胤研究』六甲書房、一九四二年、六三〇頁)。
[15] 伊藤剛「漢方医人列伝「和田東郭」」ラジオNIKKEI、二〇一〇年、https://www.radionikkei.jp/kampotoday/docs/kampo-100526.pdf(最終閲覧2026/02/10)。
[16] 吉川芳秋『蘭医学郷土文化史考』一九六〇年にある蘭馨堂の「門人譜」に平田篤胤の名前が記載されている(中川和明「平田篤胤の蘭学観」『平田国学の史的研究』名著刊行会、二〇一二年、二一六―二三七頁)。
[17] 「志都能石屋講本」の四九八頁に「既に四度ほども夫を見た」と四回ほど解剖に立ち会ったことが述べられている。また宮地正人『幕末維新変革史・上』岩波書店、二〇一二年にも指摘あり。
[18] 「神醫道」という語は「医宗仲景考」でみられるのみであり、読み方も不明であるが、「医学方術」を「くすりまじなひ」と読ませていたり、「醫師または醫者など云は漢語で。それを御國の言で正しく云は。くすしと云べきこと」(「志都能石屋講本」四五四頁)というところから「醫道」を「くすしのみち」と訓読させているところが散見され、今回も「くすしのみち」と読ませた。平田篤胤「医宗仲景考」『新修平田篤胤全集』名著出版、二〇〇一年、五二五頁参照。
[19] 「西洋人の解體の事をよく明らめておいたを見て。常に體の中は。かうした物と云ふ事を心得るが肝要で。病の發るその原を知らねば。療治は成がたいでござる。其つねを知て居れば。其れに違つて居るが病と知れる事じやが。夫ゆゑ西洋人。は少し異つた病で死んだ人は。必解體して見るでござる。さて其解體の趣を知るには。醫範提綱。解體新書など宜く」(平田篤胤「志都能石屋講本」『新修平田篤胤全集』名著出版、第一四巻、一九七七年、四八〇頁)。
[20] 「この人間の。各かやうに活動く處が。第一に霊いことでござる」。平田篤胤「志都能石屋講本」『新修平田篤胤全集』名著出版、第一四巻、一九七七年、四八〇頁
[21] 「醫藥の道は。神皇產靈大神より初まり大穴牟遲少彥名神の御受繼なされ。なほ廣く御撰み有て。此御世より。萬國へまでも御傳へ遊ばされたることゝ見えまする。抑皇國の古へ。神代は申すに及ばず。其後も人の心大らかで。物思ひも无く。惡き病などは无き故に。醫藥方術も事少なくて。足はぬことも无かツたる處が。仁德天皇の大御代頃より初めて。次々に漢人ども多く參來り。書籍ども貢奉り。又此方よりも。彼の國の物學びに。大御使を遣はされなど有て。種々のこと。醫藥方術。及び其書ともゝ傳はり來て。人々其を珍らしく思ふに付ては。いつとなく皇國の方は粗略になり」(平田篤胤「志都能石屋講本」『新修平田篤胤全集』名著出版、第一四巻、一九七七年、四四三頁)。
[22] 「篤胤は医学の限界を素直に見つめた人だと思う。そういう視点から考えるなら、真に病を癒すには神明の加護が不可欠という強い自覚が篤胤にまずあったのではないだろうか」(市川修「平田篤胤の医学哲学」『明治聖徳記念学会紀要』明治聖徳記念学会、復刊第四五号、二〇〇八年、三六八頁)。
[23] 医者組合の先輩に、患者をどう騙して金銭を引き出すかという詐術を教えられ、篤胤が辟易したという話などが語られている(平田篤胤「志都能石屋講本」『新修平田篤胤全集』名著出版、第一四巻、一九七七年、四六七―四七〇頁)。
[24] 「医療活動の実践の中から得られた人間の死の前での「医学」の限界のために、「死」あるいは「生命」への強い執着をよぎなくさせたと思われる」(朴鍾祐「『志都能石屋』考―平田国学における「幽冥」と「医道」」『国文論叢』第二〇巻、一九九三年、一七頁)。
[25] 「かやうのことを見るたびに聞たびに。だん〳〵医者がいやになり。又何ほど骨折ても。辛労しても。療治を為損じたることも有り。殊に古道の学問は。日を逐つて急がしく成り。中々以て片手間に出来ることでは无い故に。医者ははたと止めたことでござる」(平田篤胤「志都能石屋講本」『新修平田篤胤全集』名著出版、第一四巻、一九七七年、四七〇頁)。
[26] 「弘ク古道の講説ヲ始メ玉フ」平田銕胤「大壑君御一代略記」『新修平田篤胤全集』名著出版、一九七七年、六〇三頁。
[27] 「大壑君御一代略記」の文化五年の記述に「神祇伯白川殿ヨリ。諸國附屬ノ神職等へ。專古學敎授セシムベキ旨ヲ賴玉フ」(平田銕胤「大壑君御一代略記」『新修平田篤胤全集』名著出版、一九七七年、六〇三頁)とあり、また「篤胤自筆履歴書項目覚」にも文化八年に「伯殿門人と相成學師職のヿ(神祇伯白川資延王)」(渡辺金造『平田篤胤研究』六甲書房、一九四二年、三頁)とあるが、遠藤潤によって「白川家側の入門記録である「名簿」(金光図書館蔵)の文化八年の項に篤胤の名前はなく、必ずしも事実とは確定できない」(遠藤潤『平田国学と近世社会』ぺりかん社、二〇〇八年、二〇九頁)とあり、今回はこの時期に白川家古学教授委嘱という立場はとらなかった。
[28] 「大壑君御一代略記」には文化八年にこれらの大意物が成立したとされているが、中川和明はこれらの「講本」が後年に刊行されたものであることを指摘する。特に、『古道大意』の刊行は篤胤没後に行われたもので、綿密な加筆修正が施されて時世に合う形で、没後の門人が篤胤の講義を追体験できるように刊行されたものであることが明らかにされた。(中川和明「古道大意の形成と刊行」『平田国学の史的研究』名著刊行会、二〇一二年、三〇―五二頁)
[29] 「天地地理及ビ外国ノ説ヲ以テ、御国ノ万国ニ優レテヲルト云ハ、此天地ノ間ノ公論ナルヿヲ、示サウト存ズルデゴザル」(平田篤胤「古道大意」『新修平田篤胤全集』名著出版、第八巻、二〇〇一年、五六頁)。
[30] 春をむかへて、長閑にこそと言ひさして、やがてさし幽り給へるは五日の日にてぞ有ける。かくて後は、夜の衾も近づけ給はず、文机に衝居より給ひてより、夜も日もすがら書をよみ、かつ筆をとりておはす。朝夕の御饌参らす間も、あからめもせで書読みつゝ、文机の上にてきこしをしたまひき。然てのみおはすほど、十日まり三日四日の比とおぼゆ。かく夜ひるならべて物し給ひなば、御軀やいたはり給ふべき、今夜よりは夜床に入たまへと、甚くしひ申しければ、然らばしばし睡らまむ、覚むるまで勿おどろかしそ、枕もてことて、頓て衾引かづき、高息引してうま寝し給ふほど、日一日夜二夜おなじ御有さまなり。余りに長寝し給ふ事の、また心もとなくなりて、そと覚かし参らせければ、勿さましそと言ひてし物をと云ひて、やがて文机に居よりて勤み給ふこと前の如くになむおはしける(新庄道雄「古史徴のそへこと」『新修平田篤胤全集第五巻』名著出版、一九七七年、一五―一七頁)。
[31] 伊藤裕『大壑平田篤胤伝』錦正社、一九七三年、八九―九〇頁参照。
[32] 中川和明「平田篤胤主要作品解題」『現代思想』「総特集=平田篤胤」青土社、第五十一巻第十六号、二〇二三年、六九―七九頁参照。
[33] 「神代の故事を聴て後に、神世は然も有リけむと、初めて驚く倫の、晩き心を以ては難暁からむか。神世の故事を聴ざらむ前に、早く天地世間の有状をよく観て、世の始メは神の御所業にて、しかじか有リけむなど、且々思ひ得たらむ上にて、神代の御典を讀み、實に案に違ざりけりと、悟らむほどの心速き人は、疑ひ無るべく所思ゆ」(平田篤胤「古史伝開題記」『新修平田篤胤全集』名著出版、一九七七年、五巻、二七―二九頁。)
[34] 山下久夫「本居宣長と平田篤胤は神道をいかに再構築したか」『現代思想』青土社、二〇一七年、四五巻、二号、二〇四頁。
[35] 斎藤英喜『異貌の古事記』青土社、二〇一四年。斎藤英喜・山下久夫『平田篤胤 狂信から共振へ』法蔵館、二〇二三年などで展開される方法論であり、「『狂信』から『共振』へ」というテーゼによって従来の「狂信」として評価されてきた篤胤像に転換をもたらし、近世における知のネットワークのなかに篤胤を捉え、「近世神話」を構築していく営みとしての「共振」を分析することを主眼としている。
[36] 「「近世神話」を云々するときの「神話」とは(中略)各時代時代の要請するアイデンティティ=存在の根拠を発見・創造していく知の運動体と捉える。その場合、自らの存在を根本的に規定する古層を確認するというのではなく、時代状況に対応し新たな地平を切り開くための拠りどころとして見出され、創造されるものと考える。「神話」によって自明だった事物や状況の捉え直し、価値の再発見を行うのである。そのとき「神話」は、新しい事態=そのときの「現在」を意味づけるための知のコードとなる。したがって、古代、中世、近世、近代、現代各々の「神話」が求められる。近世の生きた「神話」は、一七世紀の朱子学や一八世紀の国学・洋学の学知と結びつきながら新たなアイデンティティを創り出していく。当然、普遍で固定的なものではなく、常に変容していくものだろう」(山下久夫「本居宣長と平田篤胤は神道をいかに再構築したか」『現代思想』青土社、二〇一七年、四五巻、二号、一九九―二〇七頁)。
[37] 「古御典等に見えたる天地の諸の神たちを始めて、其を祀れる社に坐ス御霊をも申し、又人はさらにも云ハず、鳥獣木草のたぐひ海山など、其餘何にまれ、尋常ならずすぐれたる徳のありて、可畏き物を迦微とは云なり」(本居宣長「古事記伝」『本居宣長全集』筑摩書房、第九巻、一九六八年、一二五頁)。
[38] 「まづ神と云ふ言義は、御紀の卷首に、古天地未剖、陰陽不分、渾沌如鷄子、溟涬而含牙、云々と有る牙これなり。(中略)斯てこの加備てふ物の形狀を考ふるに決めて男昜の形なるべく所思たり。(上に云へる頭槌ノ劔、鏑失などの形思ヒ合すべし。)其はまづ菌の類は、卽加備なるが、比は草木の精氣の、地ノ氣に和合ひて生る物なるに、自然に同シ形なるもいと奇し。(また凡て物に曚の出たるは、いと細キ毛の生たる如くなるが、謂ゆる顯微鏡もて見る時はその細毛の如き物、悉に昜莖形を具せるを以て悟るべし)」(平田篤胤「古史傳一」『新修平田篤胤全集』名著出版、第一巻、二〇〇一年、九五―九六頁)。

マイクロビオテックやグルテンフリー、オーガニック……現代において、健康志向とスピリチュアルは密接に結びついている。さらに、そうしたスピリチュアリズムは反動的なナショナリズム運動と結びつき、社会のなかの排外主義や差別と結びついてしまっている。こうした健康志向・スピリチュアリズム・ナショナリズムの根底には、人間が生来持っている「死」への恐れがある。 このような時代の流れをどのように捉えればいいのか?「死」の恐怖から、人間は逃げられないのか?この問いを向き合うヒントは、平田篤胤とその門下生たちが辿った足跡にあった。 本連載では国学研究をおこなう著者が、篤胤を「人間の持つ『死』への恐れを乗り越えようとした思想家」として位置づけ、日本の国学の系譜を総攬することで、恐怖から生まれる反動的な思想を乗り越えるための思想を考える。
プロフィール
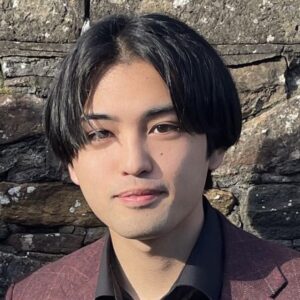
いしばしなおき 宗教学・近世思想史・文学。2001年神奈川県生。論考「ザシキワラシ考」で、2020年度佐々木喜善賞奨励賞を受賞し、民俗学を中心に執筆活動をはじめる(論考はその後『現代思想』「総特集=遠野物語を読む」に掲載)。論考「〈残存〉の彼方へー折口信夫の「あたゐずむ」から」で、第29回三田文學新人賞評論部門を受賞。論考「看取され逃れ去る「神代」」(『現代思想』「総特集=平田篤胤」)の発表以降、平田篤胤を中心とした国学思想を中心に研究を進める。編著『批評の歩き方』等々に寄稿。


 石橋直樹
石橋直樹








 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
 小島鉄平×塚原龍雲
小島鉄平×塚原龍雲


