友達が多いほどいい文化
これまで日本人の疎外感の病理と疎外感恐怖の病理を論じてきました。私が見るところ、仲間はずれが怖い、あるいは自分が仲間はずれであるという感覚を植え付けられるのは、学校生活の影響がもっとも大きいのではないでしょうか?
私自身も、たぶん現在でいうところの自閉症スペクトラム障害のような子供で、小学校を6回も転校したのですが、どの学校でも仲間はずれを経験しました。
ただ、そのころの学校文化では、勉強ができるとある程度、一目置かれるところもあり、私の母親が仲間はずれをあまり意に介さず、「勉強で見返してやれ」というタイプの人間であったこともあって、あまり傷つかずにすみました。
一部の進学校を除いて、現在は、ずいぶん状況が変わっているようです。
第3回でも問題にしたように、学校文化の中では、子供を傷つけないためという名目で「競争」が排除されていきました。
70年代から学校で成績を貼り出すことがなくなり、80年代から運動会などでトップの人間を表彰することがなくなり、さらに学芸会などで主役を決めないような動きが出てきました。
また1986年に起きた東京中野区のいじめ自殺事件を契機にいじめ撲滅運動が起こり、学校の中でいじめを撲滅しようという動きも起こります。
ここで、表向きは仲間はずれがいけないことになるのですが、その際に「みんな仲良く」が目標になって、友達は多いほどいいとされました。
勉強やスポーツで競争が許されないのに、友達が多いほうがいいということになれば、クラスの序列は友達の多さで決まってしまう、そこで生じた文化が、第3回で問題にしたスクールカーストです。
スクールカーストの実態をかなり大規模で直接的なアンケートで解き明かした、『教室内カースト』の著者である教育学者の鈴木翔氏によると、スクールカーストは立派な権力構造になっていて、教師たちもこの一軍の生徒を抑えておくと、教室運営がやりやすいので、クラスのリーダー格である一軍の人間がひいきされるようになるのだそうです。
友達の多い一軍の人間には具体的なメリットもあります。それが「観点別評価」といわれるものです。
客観的な成績より教師の主観で決まる成績
1987年に次の答申が発表されました。
「日常の学習指導の過程における評価については、知識理解面の評価に偏ることなく、児童生徒の興味・関心等の側面を一層重視し、学習意欲の向上に役立つようにするとともに、これを指導方法の改善に生かすようにする必要がある」
これが1989年に告示され、93年から施行された学習指導要領以降、導入されることになりました。これまでペーパーテストで満点をとっていれば、教師にどんなに嫌われていようが、クラスで仲間外れにされていようが、内申点は5がついていたのに、教師が「関心・意欲・態度」が悪いと判断したり、「思考・判断・表現」に問題があるとしたら、3をつけられることもあり得るようになりました。
逆にスクールカースト一軍にいるような子供は、学校で積極的に発言するし、表現力も豊かなので、ペーパーテストでは悪い点でも、内申点で4がつくことも生じます。
現在の高校入試では内申点の占めるウエイトが高まっています。
文部科学省がこの評価方法のほうがペーパーテストより生徒の総合的な学力や生きる力を見るのに適していると公言しているので、どの県の教育委員会も逆らうことができなくなっています。
文科省の意図の通りなのか、そうでないのかは別として、この「生きる力」といいうものが、教師たちに「いい生徒」と思われる力だったり、友達をたくさん従えるリーダーシップをとれる力だったり、少なくとも友達をたくさん作る力だったりするので、それを意識せずにできる子供たちを除くと、多くの生徒たちは常に人目を気にしないといけなくなります。
学校で常に教師や、ほかの生徒たちの目を気にしなくてはいけないのでは、生徒たち、少なくとも一部の生徒たちのメンタルヘルスには、かなりの悪影響が起こるのは当然のことです。
実際、これが施行された93年ごろから、とくに中学校で、校内暴力、生徒間暴力、不登校などが激増します。
しかしながら文科省はこの方針を改めることなく、ゆとり教育は撤回したものの、観点別評価は正しいものとして継続し、大学入試にも取り入れるべきという答申を2014年に中央教育審議会が出しています。
実際、医学部では国立、私立を含めて全国82のすべての大学で入試面接が行われるようになりました。
ペーパーテスト学力だけでなく、教師や大学教授に気に入られるようでないと希望の高校、大学にはいれなくなっているのです。むしろペーパーテスト学力は「知識偏重」のものとされ続けています。
幸か不幸か、文部科学省のエリート官僚が、この入試面接システムを利用して医学部に不正入試で入学したことが明らかになったり、それを契機に面接が、医学部入試の女子差別の温床になっていたことが白日のもとにさらされたりしたことによって、「ペーパーテスト学力が一番平等という古い価値観を変えないといけない」という文科省のスローガンは一時棚上げになりました。しかし、それでもいまだにすべての医学部で入試面接が続き、大学の入試面接見直しの話にはいたっていません。
ペーパーテストであれば、自分の努力である程度、成績を上げることができます。ですが、自分の力ではどうしようもない他人の評価を上げるためには自分が他人に合わせるしかないと、とくに子供は考えがちでしょう(大人だってそうなのは、これまでの同調圧力についての考察でわかるでしょう)。
うまくそれができ、表面的な友達が多い子供は、自分の本音を出せないことに息苦しさを感じ、また、それがうまくできない子供は、ひどい疎外感を覚えるというのが、私の観察と考察です。
スクールカーストの病理
これまでも何回もふれてきた「スクールカースト(教室内カースト)」について、ここで改めてスクールカーストとは何か、もう少し詳しい解説をしたいと思います。
カーストというのは、インドのカースト制になぞらえた固定的・階級的な身分制度のようなものだということです。
私自身、無知のためにカーストというのは、カースドcursed(呪われた)を語源とするものだと思っていました。スクールカーストを見ていても、自分が仲間はずれにされるということはある種の神の呪いのように、自分の努力では逃れられないものだからです。とくに自閉症スペクトラム障害のような発達障害の子供にはそうでしょう。大人になれば、たとえばスティーブ・ジョブズ(彼もアスペルガーといわれることが多いし、いろいろな評伝を読む限りその疑いは高いと思います)やエジソンのように発達障害の人が成功者になってリーダーシップを執ることはあるでしょう。
しかし、私も経験したことですが、子供時代は、いくら成績が上がっても人気者にはなれず、仲間はずれは仲間はずれのままです。インドのカーストと違って固定的なものではなく、『いじめの構造』の森口朗氏の考察でも、いつ人気者の一軍の人が三軍に引きずり降ろされるかわからず、家が金持ちかどうかとか、学校の成績がいいかは関係ないとしています。
まさにカースドのように思えたのです。
インドのカーストは、ポルトガル語で「血統」を表す語「カスタ」(casta) であり、その語源は、ラテン語の「カストゥス」(castus)(純粋なもの、混ざってはならないもの。転じて純血)だということです。
要するに、よその身分の人とは混じりあわないことで、ずっとその身分が固定されるということでしょう。人種差別にしても、人種間結婚が盛んになることで解消の動きになったように、混じりあうことは差別解消に重要なポイントなのでしょうし、逆に混じりあわないことが差別の固定化につながるのは容易に想像できます。
よくいじめられている子をかばうと、その子までいじめの対象になるといわれますが、スクールカーストでも似たようなことがあるようで、三軍の子とつきあっていると三軍扱いされてしまうことはしばしばあるようです。カーストのように混じりあってはいけないのです。
いっぽうでカーストのように固定的なものではなく、いつなんどき、下の階級に落とされるかわからない怖さもあります。
森口氏が考察したように、現代型のいじめというのは、二軍の子供を三軍に落とすように、下の階層、とくに三軍という仲間はずれに落とすということになります。
森口氏の定義では人気者でリーダーシップをとる一軍と、それに合わせてクラスの雰囲気を作っていくフォロワーの二軍があり、仲間外れの三軍がいるという構造がスクールカーストということになるのですが、その後のさまざまな調査や論考では、クラスの中にいくつかのグループができ、そのグループに下とみなされたグループが上に逆らえないような上下関係が生まれるとされています。
前述の鈴木翔氏によると、それが権力構造になっている、つまり上の階層がクラスの中で権力をもつということです。さらに性質の悪いことに、教師がそれを利用して、クラス運営をしようとして、その見返りのような形で観点別評価で意欲や態度に高い評価を与えることになります。かくして上位グループの人間は権力を確固たるものにしていきます。
いっぽう、教育学者の小原一馬氏によるとスクールカーストにも、よいスクールカーストと考えられるものがあるが、一般的には「上位グループによる下位グループに対する『抑圧』の戦略が最も安定的である結果、ほとんどのスクールカーストにおいて抑圧状態が自然に形成される」ため、多くの場合、下位グループにいることは抑圧された学生生活を送ることになります。
勉強やスポーツができない子を学校時代につらい思いをさせないために競争回避の方向性を進めた学校教育が、人気のない子供にさらにつらい思いをさせ、劣等感を植え付けていくという皮肉。人間性をゆがめ、古い学力とされてきたペーパーテスト学力から、教師による「生きる力」の評価という新基準を採用することで、余計に人目を気にして、学校生活が苦痛になる子供を産むという現実。
どんな教育政策にも副作用はつきものですが、前より悪くなったと考えるのは私だけではないと信じています。
コミュ力という呪縛
さて、このような人気至上主義、人に好かれること至上主義が学校の中で蔓延してくる中で、注目される言葉に、コミュ力、コミュ障というものがあります。
コミュ力というのはコミュニケーション能力の略でもともとはビジネスの世界で使われていたものです。
実際、平成16年発表の厚生労働省「若年者の就職能力に関する実態調査」で採用にあたり重視する能力においてコミュニケーション能力が1位になりました。責任感・積極性・外向性・資格取得・行動力・ビジネスマナーなどをおさえて、多くの企業が学生のコミュニケーション能力を採用可否の最大の柱としたということです。
このコミュニケーション能力というのは定義上、「他者と意思疎通を上手に図る能力」ということです。
これがうまくいく人を企業社会では、仕事上、もっとも大切だと考えたということでしょう。これだけであれば、コミュニケーションスキルを学習し、ほとんどの人がこの能力を身に着けることができるはずです。企業の場合、採用面接の際に重視するだけでなく、この手のコミュニケーションスキルを身に着ける研修も行っています。
ところで、私が大学医学部の入試面接に反対する理由の一つに、高校生にこのコミュニケーション能力を求めるというのに、大学では、この手のコミュニケーション教育を一切やらない大学が多いということです。
確かに医師としての臨床をやるうえでは、コミュニケーション能力は重要なものですが、それを高校生までに身に着ける必要があるとは私は思っていません。私自身、自閉症スペクトラム障害の気があるので、学生時代は立派なコミュニケーション障害でした。しかし、医師になってからそれは身に着けられたと思っています。
発達障害のほか、やはりその人の育った環境で、コミュニケーション能力には大きな違いが生じることでしょう。
やはり、大学では一定のコミュニケーション教育をやるべきだと私は考えます。
また、大学医学部というのは、臨床医だけでなく、研究者も養成するところです。
確かに研究者でも共同研究のためにコミュニケーション能力が必要だという声もありますが、独力に近い形で画期的な研究をする人が多くいるのは確かです。
それを入試面接ではじくより、医師国家試験でコミュニケーション能力のテストを行ったほうが、大学教育の中でコミュニケーションスキルを教える学校が増えるでしょう。
いずれにせよ、就職でも入試面接でもコミュニケーション能力が重視される世の中になっているのは確かなことです。
ただ、学校も含めて若い人が考えるコミュ力というのは、少し違ったニュアンスを感じます。
このコミュ力がない人に対して使われる言葉にコミュ障というものがあります。
このコミュ障にはアッパー系とダウナー系とされるものがあるようです。ダウナー系というのは、人見知りで、嫌われるのが怖いために発言が少なく、ぼっち(ひとりぼっち)なのでそもそもしゃべる相手がいないような人を指すとのことです。
これは世間のイメージするコミュニケーション障害と一致する気がします。
いっぽうのアッパー系コミュ障というのは、自己主張が強く、人の話を聞き入れない、押しつけがましい人を指すとのことです。
こうしてみると確かに両者とも意思疎通を上手に図る能力に欠けているということになりますが、たとえばアッパー系の場合、言っていることは理路整然としていてアメリカではリーダーシップをとるような人でも自信過剰に見えるとコミュ障扱いされる可能性があります。
要するに性格的にコミュニケーションに問題があり、人に好かれない人はコミュ障の扱いを受けてしまうのです。
コミュ力というのも、上手に意思疎通が図れるというより、空気を読んで嫌われないようなコミュニケーションができる人のような意味で使われている気がします。
いずれにせよ、学校という場で、コミュ力がないとスクールカーストの下位に落とされるわけですから、コミュ力が、その言葉を使うかどうかはともかくとして、強い呪縛になっているということでしょう。
スマホが加速する疎外感恐怖
前回、つながり依存を問題にしましたが、スマホ、とくにLINEの普及は、嫌われること、仲間はずれが怖い子供たちへの影響は計り知れないものがある気がします。
LINEで誰かにつながっていて、インスタグラムなどで「いいね!」がもらえることで自分が仲間はずれでないと確認している子供たちにとって、逆にそれを失うことはかなりの心理的な脅威になることでしょう。
嫌われないためには社交辞令でもいいので、みんなに受けのいいことを言い、受けのいい写真を投稿することになります。
あるいは、スマホを肌身離さずもち、LINEが送られてくるとすぐ既読にして、返信をしないといけません。
このようなつながり依存が、現在のスマホ依存の大きな要因であるということは前回指摘した通りです。ここで大きな問題は、本音を出せないということです。
精神分析的な発達理論では、第3回でも触れましたが、思春期というのは母子一体化の世界から離れて、親にはなんでも言えていた子供が親に言えない秘密ができて、親以外の誰かにその秘密を打ち明け、それを受け入れてもらう時期です。その受け入れてくれる相手が親友というわけです。
ところが嫌われるかもしれないから本音を出せないというのでは、いつまで経っても母子一体化の世界から抜け出せなかったり、自分が持てないということになってしまいます。
言いたいことが怖くて言えないから親友はできないけれど、人と合せる「コミュ力」があるから仲間はずれにはならない。ただ、仲間はずれにならないように常に気を遣い続ける……。それが自然に身についていて、友達が多い方だとのんきに構えていられる人はある意味幸せでしょう。
たとえば、みんながコロナが怖いというのでマスクを続ける、みんながロシアが悪いというのでロシアをボロクソにいう人の中には、他人の考えが自分の本音のようになってしまって、誰かが「コロナはただの風邪だ」とか、「ロシアにも言い分があるのではないか」というような意見を言うと、それを聞くなり腹を立てたり、ネット上で集中砲火を浴びせる人もいます。もちろん、自分で様々な意見や情報をよく調べた上で、自分の意見にしたのならいいのです。しかし、周りの意見と自分の考えが区別がつかないとなると、そしてそれが思春期に起こるとなると、発達上の問題が生じそうです。
いっぽうでは、「言いたいことが言えていない」「本当の自分を見せていない」ことに悩む人だっています。
もちろんSNSに自分の本音をのせて反応してもらうという形で一歩踏み出す人もいるでしょう。しかし、私の見るところそれは少数派です。
友達は大勢いるのに、どことなく疎外感を覚えている人は少なくないのではないでしょうか? 仲間はずれにされるのが怖いために、自分を殺して、みんなに合せるという風潮が蔓延している気がします。
疎外感恐怖にしばられると、学校に行くのが気が重くて仕方なくなります。
夏休みが終わる9月1日は児童生徒の自殺が一番多い日として知られるようになりました。
これは学校でいじめられているとか、先生が怖いというようなことより、うまく人と話せなかったり、人に合せるのが疲れたというタイプの子供が多いそうです。
最近はN高のような通信制の高校やフリースクールも増えてきました。
せめて疎外感や疎外感恐怖の世界から逃げる手立てだけでも子供に教えてやれないのかと、精神科医として思ってしまうのは事実です。
プロフィール

1960年大阪府生まれ。和田秀樹こころと体のクリニック院長。1985年東京大学医学部卒業後、東京大学医学部付属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェローなどを経て、現職。主な著書に『受験学力』『70歳が老化の分かれ道』『80歳の壁』『70代で死ぬ人、80代でも元気な人』『70歳からの老けない生き方』『40歳から一気に老化する人、しない人』など多数。


 和田秀樹
和田秀樹
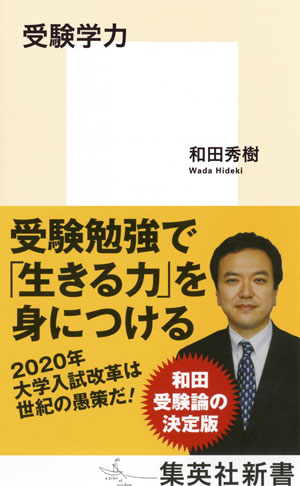










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

