疎外感恐怖と言論の自由
ここしばらく、国論が一色に染まって、疎外感を覚える人は少なくないようです。
たとえば、コロナという病気が流行ったときに、死者数や感染者数をみて、ここまで生活に規制を加える必要があるのかとか、夜に店を閉めることにどれだけ意味があるのかと思った人は少なくないでしょう。
あるいは、中国でさえ、民衆のデモによって緩和政策に切り替えたのに、いつまでマスクをさせられるのかと不満を覚える人もいるでしょう。
ロシアとウクライナが戦争になったときに、ほとんどすべての人がウクライナの味方のようになって、ロシアのプーチンを批判したわけですが、そのためにロシアからの輸入を止めてひどい物価高になったのに対して、そこまで欧米につきあわないといけないのかという素朴な疑問も持った人もいるでしょう。
高齢者が事故を起こすたびに免許返納の呼び声が高まるのですが、それでは地方の高齢者が身動きが取れなくなるじゃないかと、親などが地方にいる人が思う人もいるかもしれません。高齢者以外も事故を起こしているのになぜ高齢者の事故だけ取り上げるのだと憤りを感じる人もいるかもしれません。
最近だと、サッカーのワールドカップで、自分は日本が勝ってもそれほど浮かれる気にならないという人もいるでしょうし、ほかのニュースをつぶしてまで報道番組でサッカーだけ報じていていいのかと思う人もいたことでしょう。
へそ曲がりと思われるような話ばかりを書いて恐縮です。これまで疎外感恐怖や学校生活の中で疎外感恐怖が醸成される話をしてきましたが、こうして作られた疎外感恐怖は、周囲の意見が強く一致した際にこそ、自覚されることになるのではないでしょうか?
みんなと自然に意見が一致する場合はいいのです。しかし、そうでない場合、自分が言いたいことを言えば、おかしなやつと見られたり、仲間はずれにされたりするかもしれないと感じてしまい、一致した意見以外は言えなくなっている人は少なくないでしょう。
疎外感恐怖のために国中の意見が一致し、他人と異なる考えが表明できなくなるということです。
言論の自由が保証されているはずの国で、その自由(もちろん野放図な自由ではなく、ヘイトスピーチのようなものは許されないのですが)が認められず、全体主義の国のように国からの処罰があるわけでないのに、自分の考えや意見が表明できないのです。それは、周囲の人間からの攻撃や圧力のためのものでしょう。
しかしながら、実際のところは言いたいことをいったところでネット上の激しい批判はあるかもしれませんが、かなりの有名人でない限り現実の暴力はそう多くはありません。思ったほど仲間はずれにならなかったり、排斥されたりすることもないでしょう。私などはかなり目立った形で言いたいことを言っていますが、むしろ本は売れていますし、仲間も増えました。
しかし、疎外感恐怖があると自由な言論を躊躇したり、自制したりすることは少なくないはずです。とくに周囲の意見が一致しているときはそうです。
これまで論じてきた疎外感恐怖が、実は言論の自由の大きな障害になることは知っておいていいと私は信じています。
共感という圧力
もちろん、ワールドカップのように、日本が勝って国民が浮かれているときに、それに水を差すような言動が行いにくいというのは、おそらく万国共通の現象でしょう。
みんなで喜びあえるということは束の間かもしれませんが幸せを感じることができるし、おそらくメンタルヘルスにいいはずです。
心理学の世界では、「共感と同情は違う」ということがよく言われます。
共感というのは、相手の気持ちとシンクロすることですが、同情というのは、相手のほうが心理的に下というか不幸な状態のときに感じたり表明したりするものです。
たとえば、友達が失恋したり、失業した際に、可哀そうに感じたり、自分も一緒になって落ち込む場合には、共感でもあり、同情でもあります。
ところが友達が合格したり、昇進したり、恋人ができたという際に、我がことのように喜ぶ場合は、共感とはいっても同情という風には言わないでしょう。
前述のケースを想像してもらえばわかるように、同情は、それほど仲のいい相手でなくても比較的簡単にできるものです。相手より心理的に上の立場に立てるうえ、いい人になったような気がするので、人の不幸話を聞くと簡単に同情する人は少なくありません。
しかしながら、共感というものは、よほど仲のよい関係でないと起こりにくい感情でしょう。人が幸せになった、昇進した、受賞したというときに一緒に喜べるのは、そんなに簡単なことではありません。どちらかというとひがみや嫉妬の気持ちのほうが生じやすいのです。
人生経験を積んでくると、自分がうまくいった際、周囲の共感がそう簡単に得られるものではないことを学習します。そのために自分が成功したり嬉しいときに、他人から共感してもらえると、心理的な距離がぐっと縮まり、親密感が増すことが通常です。
サッカーの勝利でみんなと一緒になって浮かれるというのは共感の心理と言っていいでしょう。日本人としての一体感や周囲との仲間意識が高まるのも確かです。
ただ、問題なのは、その共感の輪に入れない人を見て、無意識に不快感を覚えてしまったり、自分たちとは仲間でないと感じてしまうことです。
共感とは人と人との距離を縮めるものであると同時に、「人に強要しかねない性格をもつものでもある」というのが、私の長年の人間観察の結論です。
では、たとえばロシアがウクライナを攻めたときとか、有名芸能人が不倫をしたときとか、高齢者が事故を起こした際に、一緒になって怒る場合はどうでしょう?
確かに、これは同情とは言いません。
おそらくは共感と言えるでしょう。
これが共感だとしたら、やはりそれに与しない人間に不快感や違和感、自分たちの仲間でないという意識を感じるのも納得できることです。つまり、逆から見れば、共感できない人間に圧力を感じさせるのも自然なことではないでしょうか?
これは怒りの感情だけではありません。みんながコロナというウィルスに不安を感じているときに、自分だけ「でも毎年インフルエンザだって1万人くらい死んでいるよ」とか「若者はほとんど死んでいないし、高齢者の中でも80代以上の人とか寝たきりの人が死者の大多数だ」とかいう人がいれば、やはり共感のできない人として排斥されるでしょう。あるいは、ウクライナ戦争が起こって、日本もいつ中国や北朝鮮に攻められるかわからないと国民が不安になっているときに、「ウクライナのようにもともとソ連の領土だったところと違って戦争は起こらないと思うけど」とか、「中国にしてみたら、人を犠牲にする戦争より、日本の土地をガンガン買っていくほうが、ずっと現実的と思うけど」などと発言する人がいると、国の危機を無視する「反日」の扱いを受けるかもしれません。こういう不安に共感できない人は日本の敵とさえ思われてしまうのです。
多くの学派の心理学では、共感のメンタルヘルスや人間関係に対する効用が謳われますが、実は共感にはこのように人に「共感しなければならない」という圧力があるという側面も忘れてはなりません。
テレビという圧力装置
さて、このような国民全体の共感――それが国民全体の喜びであれ、国民全体の怒りであれ、国民全体の不安であれ――の発信源であり、増幅装置なのは、やはりテレビというメディアでしょう。
サッカーの場合は、ほかのニュースを全部飛ばしても(そのおかげで、97歳の高齢者が暴走事故を起こしたニュースも、旧統一教会問題もあまりテレビの情報番組で取り上げられなかったのですが)、サッカーの快進撃一色の報道になりました。
明るいニュースの少ない日本で、国民を高揚させたことを悪く言うつもりはありません。しかし、その「浮かれ」とか「共感」の輪に入れない人(実は、スポーツ嫌いの私もその一人だったのですが)には、居心地が悪かったのは確かでしょう。
いずれにせよ、放送の頻度や時間が長くなるほど、国民の関心はそちらのほうに向かうというのは自然のなりゆきです。
特定の国や人を憎め、特定の行動を許すなという「怒りの共感」もテレビが火付け役といっていいでしょう。芸能人の不倫などの場合は、週刊誌報道をテレビが大々的に取り上げると怒りの共感の輪が一気に膨らみます。もちろん、テレビ局側が、どれに火をつけるのかを決めるようです。テレビ局の関連会社の球団の野球選手が中絶騒ぎを起こした際には、どのテレビもほとんど報じませんでした。ネットではそれに対する怒りの声があったのですが、やはり怒りの共感はほとんど広がらず、その選手も何もなかったようにプレーしていました。やはり、この国では、まだまだネットでなくテレビが共感の輪を作るという状態が続いているのだとつくづく感じたものです。
コロナ禍が始まり、国民の不安が高まると、それでも外に出ている人、夜に飲んでいる人、数人以上で会食している人を、まるで犯罪者を扱うかのように(モザイクはかかっているものの)これでもかというくらい、テレビはその映像を視聴者に見せつけました。
高齢者が交通死亡事故を起こすと、交通死亡事故は一日7件くらい起こっている計算なのに、その事件だけを大々的に取り上げます。
ロシアとウクライナの戦争でも、ウクライナ国内の悲惨な姿が連日映し出され、否が応でも共感や同情を誘います。私の知り合いのイスラム学者の中田考さんは、100万人の住民のうち20万人が殺されたチェチェン紛争のときも、あるいは米軍やイスラエル軍によるパレスチナの残虐行為でも、こんなに映像が映し出されたことがないと憤っていました。
テレビ局が、映像を通じて断罪するものを決め、それに多くの国民が共感するという構図が出来上がっているのです。
ついでにいうと、欧米どころか中国でも30くらいのチャンネルがあり、その中から視聴者は自分の見る番組を選択します。もちろん検閲はあるでしょうが、30チャンネルもあればそれぞれ論調が少しずつ違います。その中から人々は判断するのです。ところが日本では多い地域でも地上波は民放6局とNHKだけです。それでは、どれも同じような論調になるのは当然で、視聴者は自然とテレビが流す論調が正しいものだと信じやすくなってしまうのです。
このように映像を通じて共感を誘うのに、さらに火をつけるのがコメンテーターといわれる人たちです。
専門家でもないのに、コロナの不安を論じ、ロシアの非道を罵り、高齢者の免許返納を迫ります。コメンテーターだけでなく、ニュースを解説する「専門家」もテレビ局が選んだ人たちです。
私は「コロナ以上にコロナ自粛のほうが、要介護高齢者が激増するなど、高齢者に弊害が大きい」と高齢者専門の医師として訴え続けていたのですが、テレビ局からはお呼びがありません。
宗教学の立場から、ロシアとウクライナの戦争の背景を読み解く(もちろん、その名著もあります)中田考さんを呼ぶテレビ局もありません。
テレビ局は、共感を得られるであろう情報提供を行い、その方向性を補強する識者が呼ばれ、それに水を差す人は、たとえニュートラルな意見であっても排除して、あたかもすべての専門家が同じ意見であるような情報の枠組みを作り上げているわけです。
今の時代、多少の知性があれば、インターネット検索によって、コメンテーターの情報が偏っている(間違っているわけではないでしょうが)とか、自粛や免許返納にはメリットもあるが弊害もある、とか、多様な意見があることを発見するでしょう。
ところが、それを声に出そうとしたり、ネットにあげようとすると、国民全体が共感しているのに、それをぶち壊すのかと言わんばかりの反駁を受けます。
テレビがお墨付きをつけた情報や感情の方向性に国民全体が共感する、そして共感できない人たちを排斥するという文化が浮かび上がってきます。
「嫌われる勇気」の意味
国民全体が「共感」状態にあるとき、それに反駁する意見が言いづらいという言論の自由の問題のほかに、共感できない自分がおかしいのではないかという形の疎外感もあるでしょう。
みんながサッカーで浮かれているけれど、自分はそんな気になれない。コロナがそんなに怖い病気と思えない。ロシアが悪いというけど、ウクライナを味方する気になれない。
例えば、このような違和感をもった場合、学校時代に疎外感恐怖を叩き込まれている今の若者たちは、自分のことを「異常」と感じるかもしれません。
違和感と疎外感とは本来は別物ですが、「みんなの考え」に違和感をもったり、共感できなかったりすると、自分だけ異常と感じ、疎外感を覚えるというのは自然な流れのように思えます。
これまで「共感」が圧力になり、自分を失わせてしまう危険性を論じてきましたが、「共感」という概念を非常に重視した心理学者に、アルフレッド・アドラーという人がいます。ただし、彼のいう共感というのは、心のシンクロ状態より、相手の立場に立って相手の心理を想像するという意味です。
アドラーはフロイトやユングほど日本では人気のある存在ではなかったのですが、その解説書である『嫌われる勇気』が国内で200万部以上、シリーズ累計で世界で900万部売れたベストセラーになることで、一躍日本で最も有名な心理学者となりました。
アドラーが共感を重視し、共同体感覚をもつことが心理発達の目標だということを論じたため、今の日本のようにみんなが共感して、意見や感情が一つにまとまる共同体になることが理想的なことだと思うかもしれません。
確かに共同体感覚をもつことで人は周囲の仲間たちに貢献したいと思うようになります。自己中心的な自分から共同体の一員としての自分に移行するわけです。
ただ、この際の共同体というのは、周囲が「仲間」なのだと感じられることが条件なのです。
「仲間」とは、いったいなんでしょう?
私のモデルとする「仲間」というものは、思春期の発達理論でいうところの「親友」です。第3回でも触れましたが、子どもというのは小さいころは親と心理的に一体化しています。子供のケンカでは「お前の母さんデベソ」と言いますが、これは、お前の母さんを攻撃することでお前を攻撃する、ということなのです。
ところが思春期になると親に言えない秘密ができてきます。
そのような親に言えない秘密を初めて親以外の相手に言える相手が「親友」です。
ここで受け入れてもらう体験をすることで、なんでも自分の本音を話せるようになる。そして、そういう言いたいことが言い合えるグループとして親友グループが形成されます。
ここでは、遠慮もいらない代わりに、親友が殴られたら自分が殴られたように感じ、仕返しにいくこともあるでしょう。親友のために自分を犠牲にすることもある。まさにアドラーのいうところの「仲間」であり、親友グループは共同体です。
共同体感覚とは、そのような安心感を覚え、「居場所」を感じ、相手が喜ぶことをしようという感覚であると同時に、この共同体の中では遠慮なしに本音が言えるという感覚です。
嫌われることを恐れて、言いたいことが言えないのなら、それは共同体の中にいないと同じなのです。
「嫌われる勇気」というのは、勇気を出して嫌われる勇気を持とうという意味でなく、共同体感覚の世界にいれば、嫌われる心配をしなくて済むということでしょう。
アドラーに言わせると、他人の目を気にするというのは、他人が自分をどう認めてくれるのかにしか関心がないということで、それが自己中心的だということです。
共同体感覚の中では、他人の思惑を気にせずに自分の意見が言えるのです。
みんなが言いたいことが言えずにビビッているときに、そういうことを書いてくれたので、『嫌われる勇気』がベストセラーになったのでしょう。
周りがどう言おうと、周りがどう見ようと、自分は自分だし、それを受け入れてくれる仲間がいるというなら、その仲間が一人でも共同体感覚をもっているということになります。
今の日本は、いったん正義や悪が決まると、その考えを支持する人が簡単に圧倒的多数になってしまいます。
でも、それは周囲の意見であって、自分は違っていいのだ(もちろん、その意見に心から賛同できるのなら自分の意見です)と思えるのが人間の発達だというのがアドラーの結論であり、私もそう考えます。
みんなと同じ世界にいると安心なはずなのに、どこか疎外感を覚えるのは、おそらくは、十分に共同体感覚が身についていないからのように思えてなりません。
プロフィール

1960年大阪府生まれ。和田秀樹こころと体のクリニック院長。1985年東京大学医学部卒業後、東京大学医学部付属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェローなどを経て、現職。主な著書に『受験学力』『70歳が老化の分かれ道』『80歳の壁』『70代で死ぬ人、80代でも元気な人』『70歳からの老けない生き方』『40歳から一気に老化する人、しない人』など多数。


 和田秀樹
和田秀樹
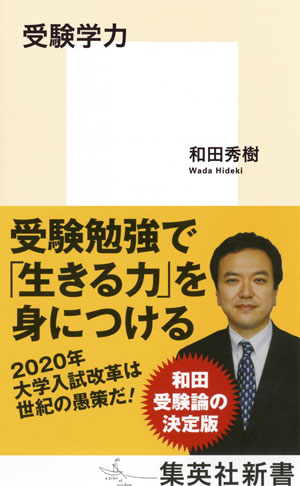










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

