3次予選のレビュー|ファイナリスト11名の演奏を振り返る
以下は、本選進出を決めたコンテスタントの出場順レビューだ。

①ダヴィド・フリクリ(David Khrikuli)【ジョージア】は、まだ24歳なのに大家の風格を漂わせている。『マズルカ作品56』は密やかな瞑想シーンと軽やかな踊りのシーンが交替する第1番、舞踊的な第2番、慟哭の第3番とどれも素敵だった。ふっと途切れるようなマズルカの最後から『ソナタ第2番』への移行もドラマティック。軽やかな右手がチャーミングな作品42、左手が切々と語りかける作品34-2とワルツを2曲弾き、最後の『スケルツォ第4番』は、テーマの休符の入れ方、続く重音のスタッカートなど、間の取り方がとてもおしゃれ。スケールとアッコードで華麗にしめくくられた。

② 桑原志織【日本】は、2 次予選期間中に 30 歳を迎えた。3 次予選はピアノの状態が一番良く、大きな曲が多いのでリラックスして弾けたと彼女自身が語るように、豊かな音量でスケールの大きな演奏を繰り広げた。 『スケルツォ第 3 番』のコラール部分はたっぷりした和音の上に装飾音がキラキラと入る。コーダも迫力満点だった。『マズルカ作品 33』は寂しげな音、活発なリズム、訴えかけるような音を駆使して色彩豊かに。『ソナタ第 3 番』の 1 楽章は、楽譜に記された通りの”マエストーゾ”で開始された。間の取り方が絶妙で、悠揚迫らざる印象を与える。 2 楽章の主部は軽やかで中間部も美しく、3 楽章は難所をものともせず、堂々と弾かれた。

③リ・ティエンヨウ(Tianyou Li)【中国】は、知的かつ驚異的なテクニックを持つ21歳の俊英。『マズルカ作品59』はリズムの処理が適切で、楽曲ごとの性格づけも理に叶っている。『ソナタ第2番』はやや焦り気味の印象があったが、ラストの『ラ・チ・ダレム変奏曲』は超絶技巧を駆使した圧巻の演奏で、会場はブラヴォーの嵐。前回大会でこの作品で大成功を収めたブルース・リウに憧れて‥‥‥。かと思いきや、15歳の時にオーケストラ伴奏で弾いているとのこと。

④ リュー・ティエンヤオ(Tianyao Lyu)【中国】は、ファイナルの翌日に17歳になるという天才少女。ポズナン音楽院で審査員の一人、カタジナ・ポポヴァ=ズィドロンに師事している。2次予選では、ショパンの若い時代の作品を可愛らしく元気に奏でるという印象だったが、セミファイナルでは一転して深刻な内容の楽曲を選択。『マズルカ作品59』の1番は優しい音で弾かれ、弱音で可愛らしく跳ねるが、音が少し明るい印象がある。2番は暖かい音で、弾むリズムを身体全体で表現するが、音楽が翳ってもあまり寂しげにならない。慟哭の3番も凄みが出ないもどかしさがあったが、そうした印象は続く『雨だれの前奏曲』で一変した。中間部ではバスを強調して音色を暗くし、音量を増していく。『ソナタ第2番』からは、可愛らしく幼いイメージを払拭する演奏が展開された。4楽章を凄みのある変ロ音で締め括ったあと、悲しみを癒すかのように優しく、優しく奏でられた『子守唄』で客席は完全に持っていかれてしまった。

⑤ ヴィンセント・オン(Vincent Ong)【マレーシア】は、ベルリンのアイスラー音大に学ぶ24歳。残り少なくなってしまった「個性派」ピアニストの一人で、大胆なアプローチが審査員にどのような印象を与えるか少し心配したが、無事ファイナルに進出した。のっけから『ラ・チ・ダレム変奏曲』。可愛らしいテーマ、ドンジョヴァンニの地獄落ち場面を連想させる恐ろしげな場面、リストの『鬼火』かラヴェルの『スカルボ』かと思わせる超絶技巧シーン等々、変化に富んでいて面白かった。『マズルカ作品41』も活き活きした演奏。『ソナタ第3番』は明るい音で達者に演奏されたが、やや重量感が不足しているようにも思われた。

⑥ 進藤実優【日本】は23歳。2次予選の『24の前奏曲』の名演ですでに人気ピアニストとなり、登場から盛大な拍手が送られた。一番好きだという『マズルカ作品56』の第1番は滑らかな響きと柔らかな中間部、ダンサブルで左手が雄弁に歌う2番、切々と訴えるような3番は客席を虜にした。その雰囲気のまま『ソナタ第2番』へ。凄みのある終楽章の後で拍手が来てしまったが、立ち上がることなく笑顔で応える。『アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ』も滑らかに美しく歌われるスピアナート部分、身体全体が躍動し、右手は煌めく音で疾走するポロネーズ部分と、いずれも素晴らしい演奏だった。

⑦ 「白いジャケット」で親しまれているワン・ズートン(Zitong Wang)【中国】は26歳。ニューイングランド音楽院でダン・タイ・ソンに師事している。温かく柔らかい音でインティメイトな魅力に満ちたピアニスト。声高に叫ぶのではなく、じわじわと気持ちが滲み出るような表現に惹かれる。『ソナタ第2番』では、祈りのような「葬送行進曲」から身をかがめたままで第4楽章を弾き始め、響きに濃淡をつけて恐怖感を煽る。『変奏曲作品12』は軽やかでチャーミングに、『スケルツォ第1番』はキレが良く、見事な出来栄えだった。

⑧ウィリアム・ヤン(Willam Yang)【アメリカ】は、ジュリアート音楽院でロバート・マクドナルドに師事する24歳。大変なテクニシャンだが、音楽が横に流れないうらみがある。例えば『スケルツォ4番』でも、イントロの4つの音は続く和音に帰結するのだが、2つの要素が独立して聞こえる。和音の連続は登って下がるのだが、上行と下降が独立している。何とも珍しい解釈だ。『マズルカ作品33』はこのパターンは姿を消し、陰影に富んだ演奏。とりわけ第3番はキレが良く、リズムの遊びも自在だった。『ソナタ第3番』の1楽章は、達者な指先を駆使して声部を巧みに弾き分ける。2楽章のトリオ部分や3楽章の中間部も、速めのテンポながらさまざまな線の絡み合いが鮮明に聞き取れる。終楽章も、つむじ風のような勢いで弾ききった。

⑨ピオトル・アレクセヴィチ(Piotr Alexewicz)【ポーランド】は25歳。第18回のセミファイナリスト。正統的なスタイルと柔らかな音で、ポーランド若手奏者の中で最も期待されている一人。『前奏曲作品45』を繊細に奏でたあと、『ソナタ第2番』のイントロを弾く。第1主題は激しい奏出ながら、フレージングが丁寧で、安らぎに満ちた第2主題とコントラストをつける。第2楽章はメカニック的にやや弱いところもあったが、第3楽章「葬送行進曲」のトリオはピュアな美しさで耳を惹きつけた。『マズルカ作品41』はリズムの弾ませ方が適切で各曲の弾き分けも見事。最後の『アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ』もニュアンス豊かな奏で、盛大な拍手を浴びていた。

⑩ケヴィン・チェン(Kevin Chen)【カナダ】はハノーファーで名伯楽アリエ・ヴァルディに師事する20歳。2次予選で『練習曲作品10』を全曲弾き、話題を呼んだテクニシャンである。『マズルカ作品41』は気持ちの籠った演奏。クリアな音で活き活きと軽やかに演奏されたが、もう少し色彩感があると良いと思った。『バラード第4番』も、指に任せて弾きまくるところがなく、自在な指先を駆使して丁寧に演奏していた。難しいコーダも余裕があり、きちんとフレージングしているのが良い。最後は『ソナタ第3番』をガッチリと構成して弾き、問題なく本選に駒を進めた。

⑪エリック・ルー(Eric Lu)【アメリカ】は2015年の第17回の第4位。当時は17歳だったが、もう27歳。体調不良ということで演奏順を変更し、セミファイナルの最後に登場した。ファツイオリを美しく響かせて『舟歌』を好演。左手はなめらかで右手の3度もよく歌う。コーダではテンポを速め、上と下の旋律を歌い合わせてさすがと思った。『ポロネーズ作品71-2』はファツイオリの音色を駆使して、キラキラとチャーミングに奏でられた。『マズルカ作品56』は転調の妙を活かした演奏で、音がよく光る1番、活気に満ちた3番、内省的な3番と弾きわけていた。『ソナタ第3番』は直前に演奏したケヴィン・チェンに比べるとやや技術的な弱さもみられたが、第3楽章「葬送行進曲」で見せた内面性はルーならではの持ち味。本選の協奏曲は第2番を選んでおり、もし優勝したら、師匠のダン・タイ・ソン以来45年ぶりの2番での快挙となる。
文中敬称略
第19回ショパン国際ピアノコンクールの本選は10/19(日)~21日(火)に行われる。指揮はアンドレイ・ボレイコ、オーケストラはワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団。
※ショパン国際ピアノコンクールに出場している日本人以外のピアニストの名前はカナ表記の後にカッコ()で欧文を記載。本大会の演奏はYouTube:Chopin Institute( @chopininstitute)で視聴が可能だ。
https://www.youtube.com/@chopininstitute
プロフィール

(あおやぎ いづみこ)
1950年、東京都生まれ。ピアニスト・文筆家。フランス国立マルセイユ音楽院卒業、東京藝術大学博士課程修了。1990年、文化庁芸術祭賞、1999年『翼のはえた指』で吉田秀和賞受賞。日本ショパン協会理事、日本演奏連盟理事、大阪音楽大学名誉教授。著書に『ショパン・コンクール─最高峰の舞台を読み解く』(中公新書)『ショパン・コンクール見聞録 革命を起こした若きピアニストたち 』(集英社新書)『サティとドビュッシー: 先駆者はどちらか』(春秋社)など多数。


 青柳いづみこ
青柳いづみこ
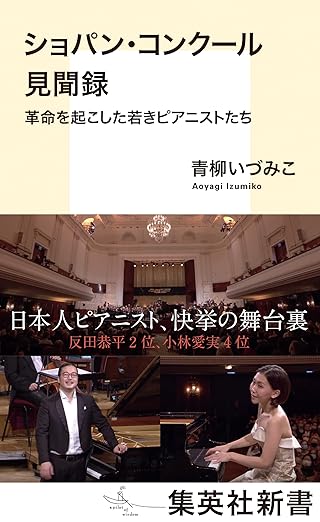










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

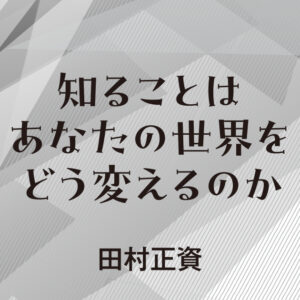
 田村正資
田村正資