1.会社は続けるためにある?
集団主義の日本企業
前回取り上げた『ロスジェネの逆襲』で「会社は会社、オレはオレ」と述べていた森山は、たしかに苦しそうだった。
つまり「会社と自分」を切り離すことが、多くのビジネスパーソンにとって、難しいことだったということである。
それはなぜか。この国の会社の成り立ちから少し説明してみよう。
社会学者の間宏(はざま・ひろし)は、日本的経営とはそもそも「集団主義」を基礎に成り立っている、という。この集団主義という言葉は、1962年のイギリスの経済紙に、日本企業は「集団主義」的であると評されたことから来る。
集団主義とは何か。それは、集団の利害を個人の利害よりも優先させる考え方のことである。
これに対比されるのが欧米的な、近代個人主義である。個人の利害を集団の利害よりも優先するのが当然だと考える自立的な欧米型と違い、日本では、集団を優先させたほうがいいという思想が一般的で、それは企業においても同じなのだ――間はそう語る。
そしてその集団主義的思想は、戦前においては、今よりずっと強固だった。
日本の社会についていえば、これまで社会の仕組みや、法律や規則などの社会規範、社会道徳に集団主義的傾向が強かったために、人々はそれに順応した態度や行動をとってきた。
たとえば、戦前では、妻が病気だという理由で欠勤する人は少なかった。それはなぜだろうか。当人にとっては、妻の病気で欠勤していてはその日の生活が成り立たなかった場合もあった。また、会社の規則が厳しく、こうした私的理由で休めば、解雇その他不利な取り扱いを受けがちだったことにもよろう。さらに、会社への責任感から欠勤しなかった場合もあっただろう。なにしろ妻の危篤をかくして出勤し、勤めを終えて帰宅したら死亡していたということが、一種の美談として伝えられた時代のことである。いずれにしても、会社中心(集団中心)に振る舞わねばならなかったのである。
(間宏『日本的経営 集団主義の功罪』1971年、日本経済新聞社)
すごい話だ。戦後80年現在の私は「夫が病気であっても出勤する」ことを問題にしているのだが、そんなことを言うよりも手前に、戦前の日本では「妻が危篤であっても出勤する」ことが美談だったらしい。信じられない。
が、この話が本当かどうかは横において(本当であってほしくないが)、美談として流布していたということはつまり「会社を優先させるという態度」が美しいものとして語られていたのだ。
それくらい、集団を優先させているというポーズ(態度)は、戦前の日本人にとっては重要なことだった。
そこには「会社」というレイヤーと、実はもう一つ「職場」というレイヤーが存在していたのだ、と間はいう。
どういうことか。たとえば戦前のある男性が、妻が危篤であっても出勤するよと言ったとする。そのとき、彼が優先しようとしているものは何だろうか?
建前としては、おそらく会社そのものだろう。会社の利益を重視する勤勉なサラリーマンアピール、という話に見える。
しかし実際のところ、本音としては、彼は会社なんて大きなものを妻よりも大切だなんて考えているわけではないだろう。本音は、妻よりも、職場を優先するよとアピールしているのである。
職場とは、働く人々の共同体であり、「内輪」であると認識できる範囲である。
職場という内輪の人間関係において、もっとも重視されるのは、和を重んじている態度なのである。つまり、職場の人間関係で仲良くしようとしていますよ、あなたたちのことを軽視していませんよ、楽しくやろうとしていますよ、と伝えるアピール。それこそが、職場を優先させる態度である。
間いわく、けして日本人は、会社という大きな集団や、国家という大きな集団に貢献しようとしてきただけではなかった。それはあくまで建前的な思想だった。
本音としては、それよりももっと重要な、職場という内輪の人間関係の和を乱さないこと――それこそが重要だと思われていたのだという。
正直、なんとなく言っていることは理解できる。本気で妻が危篤でも仕事したいなんて思っているというよりも、家庭よりも職場が大切ですよアピールをしておいたほうが、職場の人間関係がよくなるという話である。そのアピールする冗談の比喩が、今と昔で変わっただけで。
今も、違う比喩で、同じようなアピールをしているのではないか? とも思う。
「続くこと」が目的となる会社
しかし、不思議だ。
1960年代のイギリス人から見て、日本の会社はきわめて「集団主義」に見えたらしい。「自分の属する集団が持つ熱狂と無関心、集団的な好き嫌いの二つの方面で極端に走る傾向がある」(間宏『日本的経営 集団主義の功罪』より引用)という評なんて、今も有効な日本評であるように思えてしまう。
が、そんなふうに集団主義――個人の意思よりも集団の和を優先しようとする意識は、どこに起因するのだろう? とりわけ日本企業において、集団の和が大切とされる理由は、どこからやってくるのか。
これについても間はひとつの回答を提示している。
それは日本企業が、もともと明治以前からやってきた「家業」から生まれたから、ということだ。
そもそも明治以前の日本の企業は、家族で経営するものだった。明治維新が起きてからも、財閥と呼ばれる企業を想像してみればわかるとおり、家族で経営する企業は存在し続けている。そして家と企業が分離した場合も、日本では、まるでイエのように企業が存在することがとても多かった。
経営家族主義(間宏『日本的経営の系譜』日本能率協会、1963年)と呼ばれるこの風習は、経営者がまるで家長のように、労働者たちを子どもとして大切にするような関係を指す。ようは、明治以降新しい時代の経営に困った紡績企業を中心に、家族から切り離された子供たち――長男ではない青年たちや家族から手放された女性たち――に対し、家族のような居場所としての企業を与えることによって、仕事のモチベーションを与えた、ということである。
それほどまでにイエ制度は、日本企業にとって、切っても切り離せないものだったのだ(村上泰亮、公文俊平『文明としてのイエ社会』中央公論社、1979年)。そのとき、経営者はイエの家長、つまり父親のようにふるまう。つまり子どもたち、労働者にとって、家長の決定は絶対だった。
そして面白いのが、イエ制度を基礎として成立した日本企業にとって、目標とするのが、営利の追求だけでなかったことだ。
イエにとってもっとも重視すべき価値は何か。それは、イエという集団が続いていくことだ。
2025年に公開された映画『国宝』でも描かれていたような、歌舞伎のイエを思い描いてもらうとわかりやすいかもしれない。歌舞伎の家にとって、もっとも重要なのは、この場で美しい芸を披露することであると同時に、歌舞伎の家自体が続いていくことにあるだろう。だからこそ名を襲名することが重要なのだ。家を継いでいく、その役目をもらうことなのだから。
そういう意味で、日本の集団には、このイエ制度のDNA――つまり「集団が続いていくことがもっとも重視すべき価値である」という思想が埋め込まれている。
日本企業も同様だ。
企業の目標は何かと問われたら、経営者はみんな間髪入れずに、営利の追求と答えるはずだ。建前としては。儲けるためだ。利益を最大化することである。
しかし、実はその陰にある本音としてイエ制度の名残、つまり会社そのものが続いていくことが望ましいのだ、とする価値観は、根強い。
利益を考えると潰したほうがいいかもしれない屋号でも、続けていく、継いでいくことそのものが重要なのである。そのような思想は、実は「家業」の価値観から来ている。
伝統を途絶えさせないための「和」
たしかに私たちは、伝統が途絶えてしまう、という言葉になぜか弱い。本当は残すべきかどうかわからないようなものに対しても、伝統が途絶えてしまう、と言われるとなぜか胸がきゅんと切なくなってしまう。
同時に、伝統が受け継がれていく、という言葉にもやっぱり弱い。箱根駅伝を観れば、元旦からどれだけの人が、伝統を受け継ぐ若者たちを応援したくなるのか、よくわかる。甲子園を見てもやはりそこにあるのは、学校の伝統を受け継ぎ、次代に繋げていく学生たちの奮闘である。
たしかに私たちは、どこか集団の伝統を継ぐことを、問答無用で良しとする価値観の内部にいる。
イエ制度と言われると首をかしげてしまう人も、甲子園や箱根駅伝で学校の伝統を継ごうとする少年たちの姿には頷いてしまうことは、多いのではないか。
そして、甲子園や箱根駅伝を見るまでもなく、伝統を継ぐ人々にとって、集団の和を重視することが重要であることもまた理解できるだろう。いくら実力があっても、集団の和を乱す存在は、伝統を継ぐことにおいて必要がない。むしろ、伝統を継ぐことにおいては邪魔になってしまうかもしれない。それよりはしっかりと和を尊び、集団戦を戦ってくれる人の方が、チームワークには貢献してくれそうである。
競合に勝つことや利益を追求することだけを目的とするならば、集団の和なんて、気にしなくていい。
しかし、競合に勝つことや利益を追求する「だけでなく」、伝統を継ぐこと、集団を永続させることを目的としているからこそ。私たちは集団の和を重視してしまう。
個人でなく、集団のために。
それはイエ制度から来る私たち日本の集団に属する存在が持つ、ひとつの価値観なのである。
甲子園や箱根駅伝では、しばしばマスメディアによって、いかに選手たちがストイックな学生生活を送ってきたかが物語化されて放送される。そこにはしばしば「ケガを克服した」という物語も入り込む。そう、選手たちは病院にはさすがに行っているものの(行ってなかったら大問題である)、選手のケガの痛みは、しばしば集団の和を困難にさせるものとして表象される。「今年のチームは果たしてどうなるのか」というような煽り文句とともに。大抵は、ケガを克服することによってまた集団の和を取り戻した、という物語がセットなのだが。
このような表象を私は責めているわけではない。ケガという個人の痛みは、集団の和を乱すものとして、長らく日本に存在してきた、ということを伝えたいのである。
痛みは個人的なものだ。それは時に、集団の伝統を継ぐうえでの困難になってしまう。
たとえば映画『国宝』でも、家を継ぐうえで最も大きな困難が、ある痛みであったのと同様に。
2.桃太郎という名の官僚
明治の受験勉強における「団体戦」
では、企業のビジネスパーソンでなく、国家のために働く官僚の場合は、どうだろうか。企業はたしかに家業に端を発しているが、官僚は家とはむしろ関係のない「受験勉強」によってなることができる存在であるはずだ。
スポーツと違って、受験勉強とは個人的なものである。日本の官僚制度は、試験勉強によってなることができるものだ。
が、明治時代の官僚制度とは、実は集団戦だったのだ!
近代日本を突き動かした競争は、個人戦であると同時に集団戦であった。最たるものは藩、地域を単位とした集団意識である。藩のなかでの競争は集団としての凝集性を高め、ひとたび外に出ると、藩を背負った競争へと彼らを駆り立てていった。貢進生たちの学びはまさに藩の看板を背負った戦いであったし、熊本県、長野県、岡山県出身の学士官僚たちの行動は、地域を通じて生まれた理念と利権、競争と協力の構造であった。
(清水唯一朗『近代日本の官僚 維新官僚から学歴エリートへ』中公新書、2013年)
政治学者の清水唯一朗によれば、明治期の日本において、身分関係なく賢い学生さんを全国から中央に集めよう、という流れが存在していた。まさに立身出世という言葉が生まれた頃である。
このとき、身分関係なく一律に試験勉強した、というわけではなかった。身分関係なく全国からまんべんなく学生を集めるために、明治時代の大学は「貢進生」という制度をつくった。
貢進生とは、それぞれの藩ごとに推薦された、東京で学ぶことを定められた学生のことだった。そう、つまりは学費から住居費にいたるまで、当時、藩がお金を出していたのである。名前の通り、本当に中央への貢ぎ者であった。
しかし慈善事業ではない。どの藩も、良い学生を中央に送り込もうと競走した。お金をできる限り出しサポートした。目的はその先だ。自分の藩の若者が、試験でいい成績をとり、中央の官僚になってくれることを期待したのだ。
なかなかすごい制度である。家族が学費を出すならば金持ちしか集まらない。だったら藩に出させて、官僚にもっとも送り出せるのはどの藩か競争させればいいのだ、という発想である。すごく賢い制度である。
結果として、藩ごとに結束が生まれ、ある意味で藩の貢進生同士の集団力も高まった。
いまも受験勉強で、進学校の生徒たちが「受験は団体戦だ」なんて言われることがあるだろう。実際、東大を学生たちが目指す漫画『ドラゴン桜』(三田紀房、講談社、2003-2007年)において「受験は団体戦」と説かれている。雑誌の受験特集では、高校ごとに何人東大合格したか掲載されていたりする。実はこの発想は、明治時代の藩ごとに競争していたころの名残なのである。欧米でこのような学校ごとの合格実績表なんて見たことがないという。
公務員ヒーローの国
といっても、今も昔も、学生本人は本気でみんなのために勉強頑張ろう、なんて思っているわけではない。受験は団体戦というのは集団に対する建前もあったはずだ。本音としてはもう少し、自分も高い地位につきたい、いい点数を取りたい、という個人としての願いもあったはずである。
しかし現代の受験も昔の官僚試験も、集団の利益のために頑張ることと、個人の利益のために頑張ることは、けして矛盾せず、むしろ重なっている。いい大学に入れば、自分もうれしく、藩や学校にとってもうれしいのだ。
「官僚」というシステムは、ある意味でこのような存在の究極形であると言えるだろう。
どういうことかというと、「企業」であれば、国家の利益と企業の利益でどこか矛盾することがあるかもしれない。公害問題や独占禁止法を考えてみればわかる通り、企業は儲けすぎると、職場で利益を追求しすぎると、より上位概念の国家の和を乱すことがある。
しかし「官僚」は違う。個人が頑張れば頑張るほど、職場のためにもなり、さらにより上位概念の国家の利益のためになる。故郷の家族のためにもなって、それでいて、国家のためにもなる。
明治時代の日本では「官僚」は最良の立身出世コースとされた。それは政治家への道でもあったのである。
その意味において、官僚という存在を生み出したことは実に絶妙であった。自らの努力によって勝ち取った地位で公に尽くすことができる。公志が描く統治のあり方と私志が求める権力がせめぎあうなかで、政策が生まれていく。競争は学校からはじまり、官僚としての出世の階段へと続いていく。より広く、より大きな公に尽くし、自己実現を果たしたいという志は、彼らを官僚から政治家へと転進させた。志に突き動かされる自己実現のシステムが、官僚という職分を通じて近代日本に組み込まれたのである。
統治と参加、競争と協力、公志と私志という三つの構造を組み合わせ、より大きな近代日本の構造を動かすための媒体が官僚という職分であった。官僚の誕生と成長は、まさに近代日本の誕生と成長そのものであった。
(清水唯一朗『近代日本の官僚 維新官僚から学歴エリートへ』中公新書、2013年)
しばしば、アメリカのヒーローは個人主義だが、日本のヒーローは組織人である、と指摘される。たとえばアイアンマンやバットマンは起業家、社長だが、ウルトラマンやスーパー戦隊は公務員、組織人である。そしてマーベル・コミックスやDCコミックスのヒーローは基本的に一代限りだが、ウルトラマンたちは世代交代制――「ウルトラマン」の名を受け継いでいる。
現代日本においてもやはり私たちはどこか、街を助けてくれるヒーローに、集団に従事することを求めてしまうのである。
桃太郎には、鬼を排除することで、村の和を取り戻してほしいと思ってしまう。
村の和を継いでいくことを、受験勉強した先でも、私たちは望んでしまう。
ちなみに、1930年に「日本一の桃太郎を探す」というキャッチコピーで「健康優良児」を探す行事があったことをあなたはご存知だろうか。身長・体重・性格・成績そして運動能力がもっとも良い小学六年生こと「健康優良児」を表彰するキャンペーンである。性格まで入っているのが怖いことこのうえない。
しかもこれ、なんと各学校が男女1名ずつ推薦したうえで、都道府県別予選まであったのである。明治時代の貢進生の時代から発想が同じ! いやむしろ性格まで審査されるぶん基準は上がっているかもしれない。なんと学校表彰は1996年まで続いたというのだから驚きだ(石岡学「「理想の子ども」としての健康優良児 新聞報道における健康優良児のイメージ」『教育社会学研究第75集』2004年)。
ちなみに主催の一部は甲子園と同じく朝日新聞社である。ケガなくすくすく育つ日本一の桃太郎を探すべく、地方予選から全国大会に向かう子どもたちの姿を想像するだけで、どこか日本的集団意識を見出したくなってしまう。
3.ライブドアと『ONE PIECE』の2000年代
ルフィの海賊的仲間主義
が、そんな「和」を壊すようにして登場したのが、平成のニューヒーローこと、『ONE PIECE』(尾田栄一郎、集英社、1997年~)のルフィである。
なんとルフィは、公務員ではない。海賊である。公務員の敵!
2022年8月時点で5億1,000万部を突破したこの漫画の主人公ルフィは、もしかすると日本で最も愛されている非・公務員ヒーローかもしれない。
しかしそんなルフィも、国家の敵ではあるのだが、仲間たち(職場)はとても大切にする男である。
自分の夢である「海賊王」は個人の欲望だが、その夢を共に追いかける船員つまり職場の仲間は、なにより大切にする。それこそがルフィの行動原理である。幾度となく傷だらけになりながら職場の仲間を守ろうとするルフィの姿は、『ONE PIECE』の名場面として挙げられることが多い。
「…おれの仲間は…
誰一人……!!
死んでもやらん!!!!」
(尾田栄一郎『ONE PIECE』33巻)
ある意味、ルフィはきわめて職場の集団主義的なキャラクターである。個人の利益を追求しているようでいて、職場の仲間を大切にする描写が幾度も繰り返される。
そしてワンピース(ひとつなぎの大秘宝)をめぐって、それぞれの地方から集まった海賊たちが戦う、というトーナメント的な要素もどこか日本近代的な仕組みのなかにある。
なによりも、ルフィは、シャンクスという「父的な存在」から重要な伝統を受け継いでいる。父が腕をなくしてでも守ろうとしたルフィという子は、麦わら帽子をもらい、まさに伝統を継ごうと、海賊王を目指しているのである。――これがもしアメリカの映画だったら、きっとシャンクスという父を倒すためにルフィは強くなっていただろう、『スター・ウォーズ』しかり、ここで父殺ししなければいつ父殺しするのかという話である。
しかし日本ではそんなことは望まれない。むしろルフィという息子は、シャンクスという父を追って、海賊王になろうとする。これは本章で見てきた、集団の永続性を求める姿そのものなのである。
『ONE PIECE』は、海賊という非公務員的な主人公を据えつつも、物語としては王道の日本的立身出世――職場という名の集団を大切にしつつ、地方から中央へ成り上がろうとする様子を描いた漫画なのだ。
ITベンチャーブームと『DEATH NOTE』と父の伝統
『ONE PIECE』のアニメが好評になり、劇場版第1作『ONE PIECE』が公開された2000年。ニュースでは、堀江貴文の会社こと株式会社オン・ザ・エッヂが東証マザーズに上場した。
2002年、『ONE PIECE』単行本第24巻が初版発行部数252万部を記録し、コミック部門の日本最高記録を樹立したタイミングで。堀江貴文は、経営破綻した旧ライブドア社から営業権を取得し、ライブドアと名付けた。
そう、実は『ONE PIECE』の流行開始時期は、バブル経済崩壊以降の、IT系スタートアップブームと同時期にあった。
2000年の流行語大賞は「IT革命」。ルフィが公務員にならず海賊としてお宝を探していったことと、日本の若者たちがベンチャー企業という新しい大海原に沸いていた時期が同じタイミングであったことを、私はけして偶然とは思わない。
だが、よく知られるように、ライブドア事件で上場廃止となる。
堀江がプロ野球や自民党といった、日本の伝統的集団に踏み込んだ瞬間――そこで彼はベンチャー企業の時と同じようには歓迎されなかった。
それは同時期に流行した漫画『DEATH NOTE』(原作大場つぐみ、作画小畑健、集英社、2004~2006年)にも同じことが言える。警察官僚の父をもった夜神月は、デスノートを手に入れたことで、父と反対の道に進もうとする。しかしいくら世間の正義のためであっても、その道は地獄に続いていた。
戦後高度経済成長期から続くバブルが崩壊し、従来のような伝統的日本企業よりもベンチャー企業が流行するかのように見えた2000年代。しかしそのなかにあっても、日本的集団主義は、けして手放されたわけではなかった。日本ではやはり伝統をもった集団が「続くこと」が重視され、そのために集団つまり職場の和が重視されていた。個人主義が増えたかのように見える2000年代にあっても、日本人の精神性は、案外変わっていなかったと言えるのではないか。
和を重んじて、個で抱え込む
堀江は、著作『ゼロ―――なにもない自分に小さなイチを足していく』(ダイヤモンド社、2013年)において、「起業して会社が潰れても大丈夫だ」ということを繰り返し説く。そう、会社が続いていかないことを皆が恐れているということを知ったうえで、それでもそんなことは気にしなくていい、一度起業すればそれはビジネススキルにもなるし、経営を通して手に入れたスキルは次のキャリアに活かされるから、と伝える。
堀江はこう語る。
「仮に自分の会社が倒産したところで、あなたという人間は潰れない」と。
――こんなふうに思える日本人がどれほどいるのだろうかと今の私は思う。それを思えるだけの、会社という集団と、自分という個人を、切り離して考えられる人間が、日本にどれだけいるのだろう。集団のなかにいる個人という感覚のほうが、今もずっと強いのではないか。
職場にいる限り、和をできるだけ崩さず永続させたい、と思う人はきっと多い。
だからこそ、ひとりだけ病院に行くなんて、言いづらい。
会社にいて、仕事に打ち込んでいると、職場の人に自分の不調を訴えるなんて、和を乱しすぎてやりづらい。そう感じてしまう人も多いのではないか。
2010年代に堀江は『健康の結論』(KADOKAWA、2018年)を出したりするなど、現在も予防医療の啓蒙活動にも注力している。とくに『健康の結論』内において、心身の不調をひとりで抱えたまま病院に行かない人に対する注意喚起をおこなっている。
産業医の大室先生によれば今、職場でメンタルヘルス不調の人のほとんどが「一人で抱え込みすぎました」と語るそうだ。特に男性は弱みを見せたくない、という人が多い。言わなければ伝わらないのに言えず、「察してくれない」と勝手に落胆する。そして、自分からエアポケットに入ってしまって潰れてしまう。
(堀江貴文『健康の結論』)
集団の和を重んじるあまり、個人の弱さをひとり抱え込んでしまう。そんな構造が、ここにはあるのではないのか。つまり職場の空気を壊さないように、自分の痛みや弱さを吐露しづらい、というような構造が。
2025年現在、ルフィの冒険はまだまだ続いている。傷だらけになっても、チョッパーがちゃんと治療してくれるからである。素晴らしいことである。職場の仲間のなかに産業医が当たり前のようにいるのは、実は2000年代にあってとても新しい描写だっただろう。尾田先生の先見の明がここにある。
重要なのは、チョッパーが気づく前に、自分でチョッパーに会いに行くことなのだろうが……なかなかそれは難しい。なぜこんなに難しいのだろう? ルフィが傷だらけになっているのに、私が先にチョッパーに会いに行くなんて申し訳ない、と感じてしまうのだろうか。
(次回へつづく)

体調が悪くても会社に行ってしまう。休んで自分のところで仕事を止めることに罪悪感がある。サウナや筋トレは好きなのに、体調のケアは億劫になる……このような悩みを抱えている働く人は少なくないのではないか。なぜ我々は、組織や集団にいると、休むことが難しくなるのか。文芸評論家の三宅香帆が、働く人たちを熱狂させてきた作品や国民的な少年漫画を歴史からひもとくことで、その源流を探る。
プロフィール

みやけ かほ 文芸評論家。1994年生まれ。高知県出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集)。著作に『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』、『「好き」を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』、『娘が母を殺すには?』、『30日 de 源氏物語』、『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』、『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』、『人生を狂わす名著50』など多数。


 三宅香帆
三宅香帆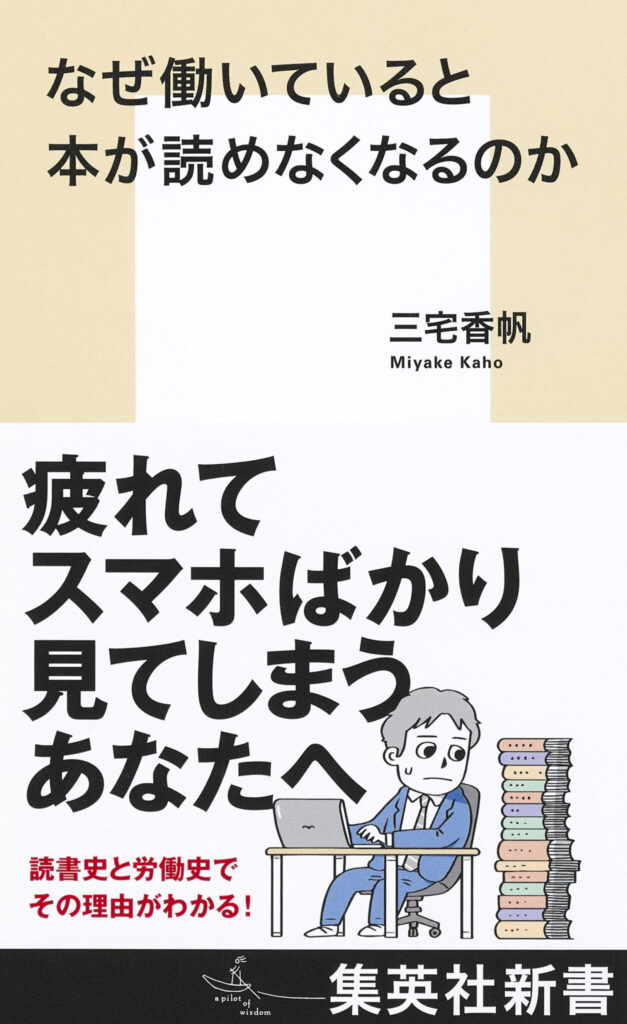










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

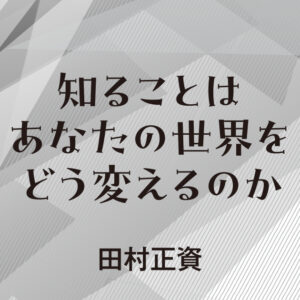
 田村正資
田村正資