関東大震災から102年。日本は変われたのか?
朴 最後に、安江玲子さんのお話をさせてください。彼女は被害に遭われた方ですが、撮影ではずっと顔を出されませんでしたね。 途中からは顔を出されています。玲子さんのお孫さんの早希さんが、おばあちゃんに、おハガキを送るんですね。あまりのつらさで、それまで笑うことができなかった玲子さんは、そのハガキによってよく笑うようになり、映画でも顔を見せるようになりました。 早希さんのハガキの文面を思い出すと、また涙が出そうです。
ばあちゃんは負けないで生きていてくれた。尊敬できる。伝えようとしてくれる。ばあちゃんのことを知れてうれしかった。勇気を出してくれてありがとう。ばあちゃんが自殺しないでよかった。ばあちゃんは負けないで生きていてくれた。それで自分が生まれてきた。
『黒川の女たち』より発言を一部抜粋
この早希さんの言葉に共感します。私たちも、両親や祖父母があの戦争を生き抜いてくれたから、私たちまで命がつながったんですよね。命をつなぐ、そして歴史をつないでいくことの大切さを改めて胸に刻むようです。玲子さんは自分の尊厳を回復させたんですね。
戦争は人殺し。女性が犠牲になるのは悲しい。軍事支出が今増えているが、日本も憲法九条を守ってほしい。それには女性が強くなってほしい。選挙では女の人に投票している、戦争反対が1票でも多いほうがいい。戦争は負けてよかったね。そういう歴史を伝えていくことが生きる者の使命 。
『黒川の女たち』より発言を一部抜粋
玲子さんの実感がこもったこれらの言葉に頷くばかりでした。まったくその通りです。
1923年の関東大震災から今年で102年目になります。昨年、すでに何度か書名が出ましたが『私たちの近現代史 女性とマイノリティの100年』(集英社新書)という本を作家の村山由佳さんと対談の形で出しました。その中で関東大震災時のことも言及しています。
非常に酷いデマが流され、朝鮮人というだけで多くの朝鮮人が殺されていった事実があります。私の祖父も危うく殺されかけました。関東大震災で起きたことを知らない人が結構いるので、これからも伝えていきたいと思います。そのときから100年以上経って日本はどういうふうに変わったんだろうか、それとも変わってないんだろうか、本当に問われていると思います。
今、この社会の状況を見ると、例えば今回行われた参議院選挙では、選挙運動に名を借りたヘイト、差別的な言葉の暴力がまき散らされていました。特に恐ろしかったのは、参政党の選挙演説のとき、支持者のひとりが参政党に意見する人に向かって「10円50銭と言ってみろ 」と声を張り上げたことです。
正確には「15円50銭」ですが、この言葉は関東大震災の時に朝鮮人か日本人かを見分けるために言わせたものなんですね。ハングルは最初の音が濁音にならないので、発音が違ったら朝鮮人だと。そのとばっちりを受けて殺された中国人や日本人もいたわけです。 そんな恐ろしい言葉を投げかけられる日本社会に危機感を覚えます。
こうした排他的な空気は、日本だけでなく、世界のいたるところで広がっています。その中で私たちが歴史から何をつないでいくか。歴史から何を教訓として学んでいくのか。それをしっかり捉えていくことが本当に求められていると思います。何より歴史の事実を積み重ねることによって、誰もが共に生きていける日本社会を作っていけたらと思うんです。
すいません。映画に対しての思いが溢れてしまい、私の方が一人で話しすぎてしまいました。
松原 いえいえ、この映画で伝えたいことをわかってくださって、私はとても嬉しいですし、黒川の女性たちは多くの方にこの事実を残したいと思ってこられたわけですから、こうやって受け止めていただいて、共有していただくことは、彼女たちが何より喜んでいると思います。彼女たちの証言を聞いて、二度と同じことを繰り返さないために何をすべきかを考えていただく機会になったらいいなと思っています。
朴
そう言っていただけてありがたいです。
松原 私は朴さんの本を読ませていただいて勉強になりましたし、今の時代に通じることが書かれています。これって百年前じゃなくて今じゃない? っていうことが。まさしく選挙の時の状況を見ると感じられるような内容でした。
日常の中にある差別性とどう向き合っていくのか
朴 ありがとうございます。映画の最後のシーンで、女子高校生たちの授業風景が描かれていましたね。先生が言っていたのは、日常の中にある差別性。普段は隠されている暴力が戦争で出てくるのだと。こういうテーマの授業が行われていることに力づけられます。
松原 映画で撮影した学校は私立の女子高ですが、この学校以外にも共学の公立の高校や中学でも具体的な事例として、授業で取り上げている学校はあります。
朴 中国に対する加害、ソ連兵からの被害、男性が女性を差し出す内なる加害と、日本の自国民への加害。これらを押さえながら男性目線の歴史の欺瞞にも目を向けつつ、女性たちの声を阻んだのは一体何だろうかと、いろいろな視点から生徒たちは話し合いを深めていくんですね。生徒のひとりは、「伝えてくれることを、私たちが向き合わないほうが問題だと思いました」と語っていましたね。
松原 映画に出てくる先生は、まだ32歳で若いのですが、先行研究や専門書、シンポジウムなどでの最新の知見などを踏まえて授業にされています。レジュメも10ページくらい作られて。
生徒からすると難しいのかなと思って取材していたのですが、全くそんなことなくて、
自分たちに引き寄せて、感じ取っていました。こちらが生徒たちの受け止めからも教えてもら貰っているなという場面が多々ありました。
朴 本当にそうですね。最後までとてもいい映画でした。ぜひ多くの人に観てほしいと思います。
『黒川の女たち』公式HPはこちら
一部文中敬称略
取材・構成:朴慶南・新書編集部
プロフィール

松原文枝(マツバラ フミエ)
テレビ朝日ビジネスプロデュース局イベント戦略担当部長。1992年政治部、経済部記者を経て、『ニュースステーション』『報道ステーション』ディレクター。2012年からチーフプロデューサー。15年に経済部長、19年から現職。「報道ステーション」特集「独ワイマール憲法の“教訓”」でギャラクシー賞テレビ部門大賞、「史実を刻む」などドキュメンタリーではアメリカ国際フィルム・ビデオ祭銀賞、放送人グランプリ優秀賞。2020年放送ウーマン賞。専修大学文学部ジャーナリズム学科特任教授。著書に『ハマのドン 横浜カジノ阻止をめぐる闘いの記録』(集英社新書)が ある。
朴慶南(パク キョンナム)
1950年、鳥取県生まれ。作家・エッセイスト。著書に『私たちの近現代史 女性とマイノリティの100年』(集英社新書)『クミヨ!』(未来社)『ポッカリ月が出ましたら』(三五館)『命さえ忘れなきゃ』(岩波書店)『やさしさという強さ』(毎日新聞社)『あなたが希望です』(新日本出版社)『私たちは幸せになるために生まれてきた』(毎日新聞社)など。


 松原文枝×朴慶南
松原文枝×朴慶南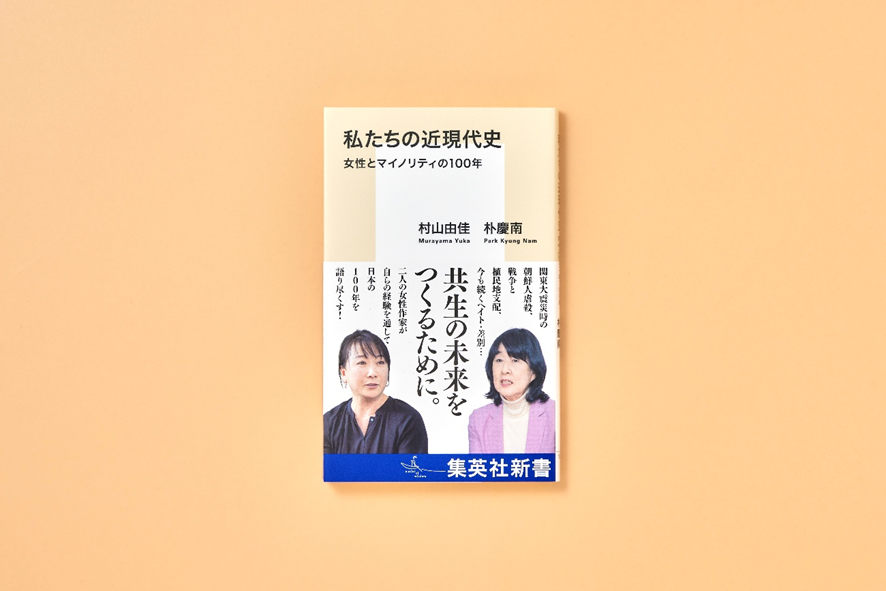
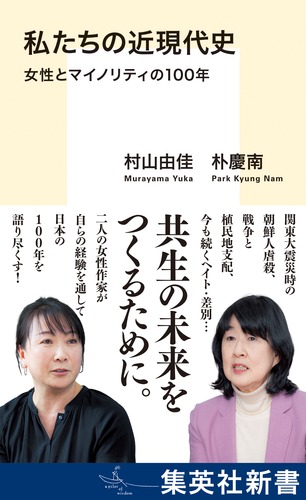
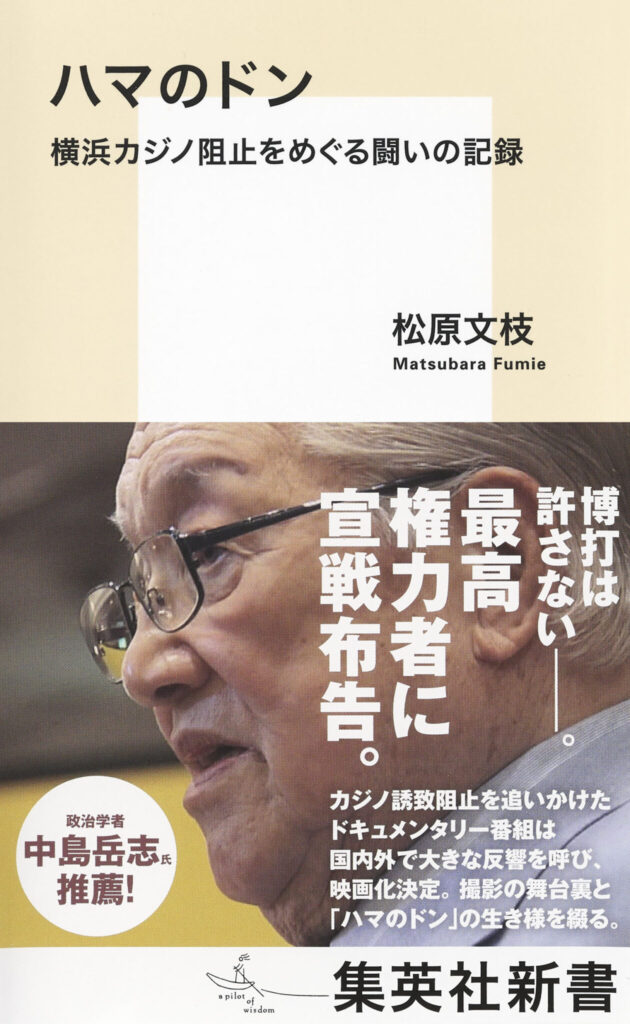










 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
 小島鉄平×塚原龍雲
小島鉄平×塚原龍雲


