「仕事に疲れて休みの日もスマホばかり見てしまう……」「働き始めてから趣味が楽しめなくなった……」。このような現代人の悩みに、文芸評論家の三宅香帆氏が向き合った新書が『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』である。
発売1か月ですでに大きな反響を呼んでいる本書の刊行を記念して、芸人・YouTuber・ラジオパーソナリティとして活動しながら、ドラマや映画などのコンテンツを紹介している大島育宙氏と著者の三宅氏が対談。現代のコンテンツ受容と、教養の変質がもたらす問題について語り合う。
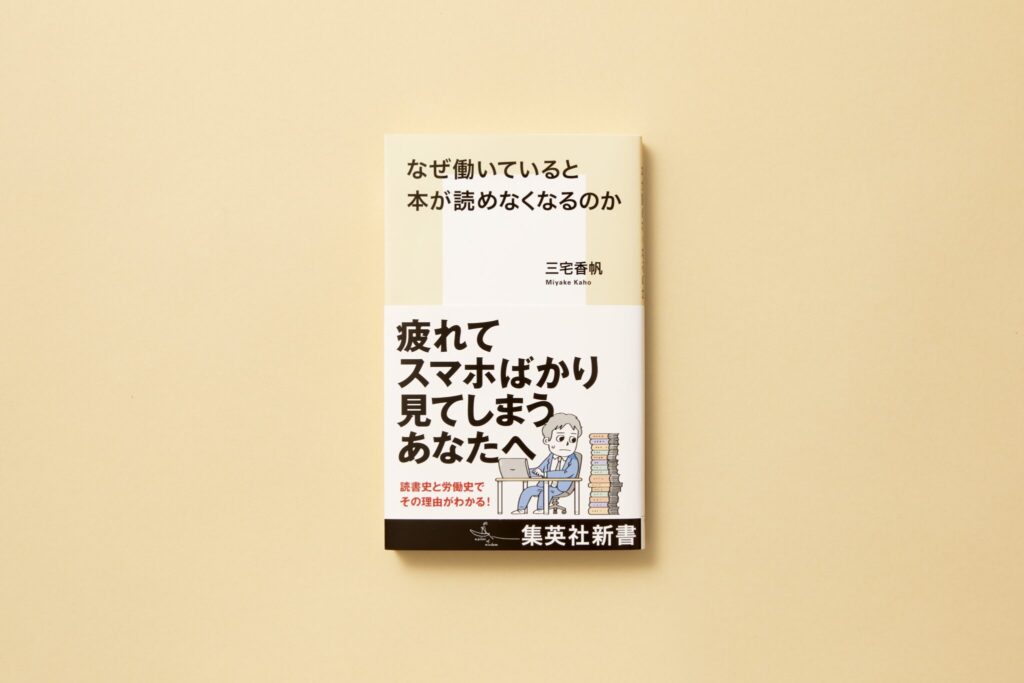
ガラパゴス化するコンテンツ受容
三宅 実は前から大島さんの普段の発信を拝見していて、勝手に親近感を持っていました。同世代ならではの感覚があるのかなと。
大島 僕の場合、初対面の同世代の人と仕事するのは、今年初めてかもしれないですね(笑) 最近だと「バラいろダンディ」でミッツ・マングローブさんやデーブ・スペクターさんと共演したり、マキタスポーツさんのYouTubeに出たり、水道橋博士や吉田豪さんとイベントで話したり……上の世代の人たちと接するほうが圧倒的に多いし、楽しくて。
三宅 じゃあ、この対談は珍しいんですね(笑)
大島 そうですね。同世代だと、同じものが好きなはずの同業者でも話がかみ合わないんですよ。それを最近顕著に感じたのは、松本人志の話です。僕より下の世代は、『遺書』とか『VISUALBUM』を通ってない人が圧倒的に多い。
三宅 共通体験や前提知識として当たり前だと思っていたものが、通じない、みたいな感覚ですよね。
大島 そうなんです。昔のものを知っているだけで、新しいとか、トガっていると思われてしまうことすらある。例えば、お笑いの現場で過去の名作映画をネタにするみたいになったときに、『ゴッドファーザー』をネタにすると通じないんです。「いや、映画好きだな!」みたいなツッコミをされてしまう。
三宅 あんな名作なのに!(笑)
大島 芸人の共通体験がガラパゴス化していますよね。YouTubeがここまで盛んになって、配信のお笑い番組が出てきてから、到底、全部のコンテンツを追えなくなってしまった。売れてる芸人さん一人一人がメディアになっていますから、みんなが見ている「必修」のようなコンテンツが無い。
そのために、最低限の教養のレベルが縮小していると思うんです。僕は教養主義的な側面が同世代の中では強いので、常に悔やみながら現場にいるのですが(笑)
三宅 逆に、大島さんは過去の作品を、どういう経緯で知ったんですか?
大島 ラジオをよく聴く子どもだったので、爆笑問題さんとか、RHYMESTER宇多丸さんの番組で出てくる言葉をメモして、翌日、渋谷のTSUTAYAに借りに行ってました(笑)
三宅 努力家!でも私も好きな作家さんの書評集で出てきた固有名詞を、一つずつ図書館で借りて読むのが楽しみでしたね。
大島 そういうアナログな方法は、好きなものと向き合う当たり前の方法だったと思うんです。でも、すべてがネットで検索できるという幻想が広まって、わざわざそういう作業をすることが損なんじゃないかという感覚に支配されてしまっている。すると、そこから抜け出すのはかなり難しくて、結局何も調べないし、何も見なくなる。

「文脈を作ること」と教養
三宅 今の話につながると思うのですが、私は「本を読むこと」は自分の中に「文脈」を作ることだと思っています。本を読むと、この本が別のあの本とつながっている、という気付きがたくさんありますよね。それは、エンタメでも音楽でも同じだと思うんです。そういう「文脈」を作る作業は、まさに教養のことなんじゃないかと。
大島 なるほど。たしかに、狭い世界の中だけで文脈消費をする人がいるのも問題だと思います。例えば、お笑いファンだと、賞レースのファイナリスト同士の関係性だけを見ている人がいる。ファイナリストたちが発信しているコンテンツは膨大で、それを見ているだけで時間が無くなってしまうから、それ以外のコンテンツを見る余裕がない。だから、M-1を多く語る人たちも、「ひょうきん族」を見たことがないことがある。
三宅 今はなかなか、コンテンツを楽しむことが、そのジャンルを楽しむことにつながりづらいんですよね。文芸の世界でも同じだと思います。ベストセラーはあるけど、その一点集中がすごい。作家やジャンルを掘るという感覚よりも、SNSでバズっている、売れている本を単体で読むという感覚の方が主流になっているのかな、と。
大島 一つ一つのものが周りの文脈や背景から切り離されていますよね。僕だと森見登美彦さんの作品が面白かったら森見さんのデビュー作から遡って全部読むというのが当たり前だと思ってしまうのですが、今は、例えば村田沙耶香さんの『コンビニ人間』だけを読んで、村田さんの他の作品を読んだことない人が、すごく多いと思う。
三宅 ドラマでも、例えば『VIVANT』が流行っても、枠としての「日曜劇場」がすごい、みたいにはならない。

教養の衰退は、世界を前近代に戻す?
大島 昔だと、向田邦子さんみたいに脚本家の名前でドラマを見るのは当たり前のスタイルだったと思うんです。でも、今は三谷幸喜さんと宮藤官九郎さんしか知らない人がほとんどかもしれない。ちょっと詳しい人は野木亜紀子、古沢良太を知って、坂元裕二を覚えて、みたいな感じだと思う。
三宅 ドラマは見ていても、その脚本家の名前を知らない、ということが増えてきたんですね。
大島 そうです。これは、作家主義の衰退ともいえると思います。例えば、映画の紹介でも、監督の話をすると、すごくウケが悪い。
三宅 面白い。小説紹介TikTokerのけんごさんと話したときに印象的だったのは、TikTokで本を紹介するときの一番のコツは、例えば「宮部みゆき」という固有名詞を出さないことだと。「このどんでん返しがすごい」みたいに盛り上がる点だけを紹介するのが大事で、作家名はノイズになると言ってて。
大島 それは、本当に作家主義の衰退を象徴していますよね。超絶トッププレーヤーの名前だけはわかるけど、「群」で捉えることが、オタクじゃないとできなくなっている。
三宅 「群」で捉えるのは、まさに、教養ですよね。言われてみれば、そういう人が減っているのかもしれないですね。
大島 そうなんですよね。コンテンツを紹介するうえで悩んでいるのは、「大島さんの紹介するもの、全部観てます!」とコメントしているユーザーの人が、僕が紹介したコンテンツしか見てない可能性がある、ということなんですね。前提として、自分の発信を信頼してくれているのは嬉しいんですけど、自分が紹介していないほかの作品も観てほしいんです。「こんなおいしいのもありますよ」って週1で料理を届けているのに、「1食を7日間に分けて食べてます!」って言われたら食べなさすぎだよとは言いたくなりますよね(笑)
三宅 「もうちょっとビタミンとか取ったほうがいいよ」って言いたくなるということですよね。今の話聞いてすごい思ったのが、私たちが中学生ぐらいのとき、2000年代の後半って、「推し」ではなくて「萌え」の文化だったじゃないですか。いま「推し」って言うとアイデンティティを全部賭けるみたいなニュアンスになりますけど、「萌え」って単純なときめきや感情を揺さぶられる体験でしたよね。逆に今は自分だけがときめいたり萌えたりするものを探すよりも、自分の「推してる」人が紹介しているコンテンツを全てそのまま受けとる、そのほうがアイデンティティにしやすいのかもしれませんね。
大島 確かにそういう部分もあるのかもしれないですね。ただ僕の発信が摂取の全部になっちゃってる人は、僕以外のキュレーターの人を見つける時間さえなくなっているんですよね。目の前のコンテンツを追いかけるのに必死で、「群」で捉えるための教養を身に着ける時間がないのだと思います。
三宅 コンテンツ過多の中でどんどん時間が無くなり、かつタイパも悪いということで、そういう感覚が無くなっているのかな、と強く思います。
大島 ネットによって世界がつながったようでいて、むしろその一人の周りに1個のジャンルのものとか、狭いものの情報が大量に置かれて、他のものを見る時間が閉ざされてしまう。社会への目が閉じられてしまうんです。それって、むしろ近代以前に逆戻りしているんじゃないかと思うんです。
三宅 少し前まではポストモダンだと言っていたら、いまは近代的になっているのか(笑)
大島 世界を俯瞰的に見ることができないわけですよね。出版が民主化されたことによって、世界を全体で捉えることができるようになったはずなのに、そうじゃない時代に戻されている。身の回りにある情報だけが世界のすべてだとするフィルターバブル的な価値観に逆行している。
反知性主義という言葉が流行りましたけど、まさに反教養、反知性になっていく時代だという覚悟を持たないといけないのでしょうね。

ゆっくり、丁寧なスターの誕生を支える
三宅 そんな中で、どうやったらジャンルごと楽しんでもらうようなエンタメ文化を復活させていけるんでしょうね?
大島 難しいですが、例えば僕は、他のエンタメについて話すYouTuberに比べると、作品の本編と直接関係のない固有名詞をたくさん言うんですよ。それによって、その人たちの中で、一つでも作家のボキャブラリーが増えたらいいと思っています。
三宅 ちゃんと若い人を啓蒙しているわけですね。尊敬。
大島 いろんなことを知ってるほうが面白いということは、われわれが行動で示したほうがいいだろうと思うんです。
三宅 すごくわかります。私も、本を読めたほうが楽しいんだというのは、主張したくて。自分の体験としても、身の回りの人に相談したり、悩んでることを聞いてもらうより、本を読んだほうがすっきり言語化されるときが昔からあって。そういう体験を知っているからこそ、本を読む楽しさは伝えていきたいですよね。
大島 さらに言えば、教養がある人のプレゼンスをどうやって高めていけばいいのかは、映画業界もお笑い界も考えるべき問題だと思います。
その点で僕は、タレントの人が本を書くのは大事だと思っていて、特に又吉さんは、ロールモデルとして偉大だと思う。又吉さんは、極端なことを言ってバズったことが、僕の知る限りではほとんどない。ゆっくり丁寧に複雑なことを話される。でも、又吉さんの言葉は今、よく聞いてもらえると思うんですよ。そういう人がスターになるのがとても大事だと思います。
三宅 たしかにそうかもしれません。
大島 他にも国民的な知名度があるラジオ的喋り手で言うと野源さんとか、朝井リョウさんとかもスターでありながら、そういったタイプの人ですよね。それから、宮崎駿のアニメがヒットするのも、すごいことだと思っていて。『君たちはどう生きるか』は、みんな「あまり意味がわからなかった」と言うけれど、多くの人が見に行きますよね。それはすばらしいことだと思う。意味が分からない、複雑なものを宮崎駿が表現して、それを宮崎駿という作家主義のもとで、みんなが分かろうとして見に行く。そういう意味で、日本人が宮崎駿のことを好きなのは、ある意味ですごく希望的なことだと思うんです。
三宅 最近、鳥山明さんが亡くなられましたが、彼があの時代に出てきたのは、もちろん彼自身の才能もあったけど、それと同じぐらい当時の日本のおしゃれな広告文化の存在が大きかったんだな、と最近改めて感じたんです。そこに文化があったからあの絵が生まれた。そういう意味で、ジブリの難解な映画が今の時代にヒットしているのも、アニメ映画をみんなで見に行く素地が出来ているからじゃないですか。
スターが生まれるのは、スター自身の能力も大事ですが、それと共に時代の追い風を受けることも大事だと思います。だから、スターだけが一人でいるというよりも、ある程度ゲリラ戦的に、そういう複雑なものを受け入れられる素地を作る社会が必要ですよね。だから、私も、ある天才が生まれたら、それをバックアップしたい気持ちがすごくあります。
大島 わかります。かつて文学や批評の世界で世代間のヨコの繋がりがあったように、ぼくや三宅さん以外に、1990年代生まれで、そうした仲間を見つけられるかが重要になるのかもしれません。発言力のあるポジションを作りながら、それだけのアルゴリズムに流されないようにしながら、思想を持っている人同士がつながっていくのが、ちょっとずつ文化を変えていくための方法なんじゃないですかね。
三宅 励まし合って、そのつながりを拡張していきたいですね。

取材・構成:谷頭和希 撮影:内藤サトル

プロフィール

三宅香帆(みやけ かほ)
文芸評論家。1994年生まれ。高知県出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集)。
著作に『娘が母を殺すには?』、『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』、『推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない―自分の言葉でつくるオタク文章術―』、『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』、『人生を狂わす名著50』など多数。
大島育宙(おおしま やすおき)
1992年生まれ、東京都出身。東京大学法学部卒業。2017年、お笑いコンビ「XXCLUB」としてデビュー。所属はタイタン。フジテレビ『週刊フジテレビ批評』ドラマ辛口放談にコメンテーター、Eテレ『太田光のつぶやき英語』に英語インタビュアーとしてレギュラー出演。MX『5時に夢中!』『バラいろダンディ』にコメンテーターとして不定期出演。ポッドキャスト「無限まやかし」「炎上喫煙所」「夜ふかしの読み明かし」「OH! CINEMA PARADISE」に出演。YouTubeでは「大島育宙【エンタメ解説・映画ドラマ考察】」を配信。


 三宅香帆×大島育宙
三宅香帆×大島育宙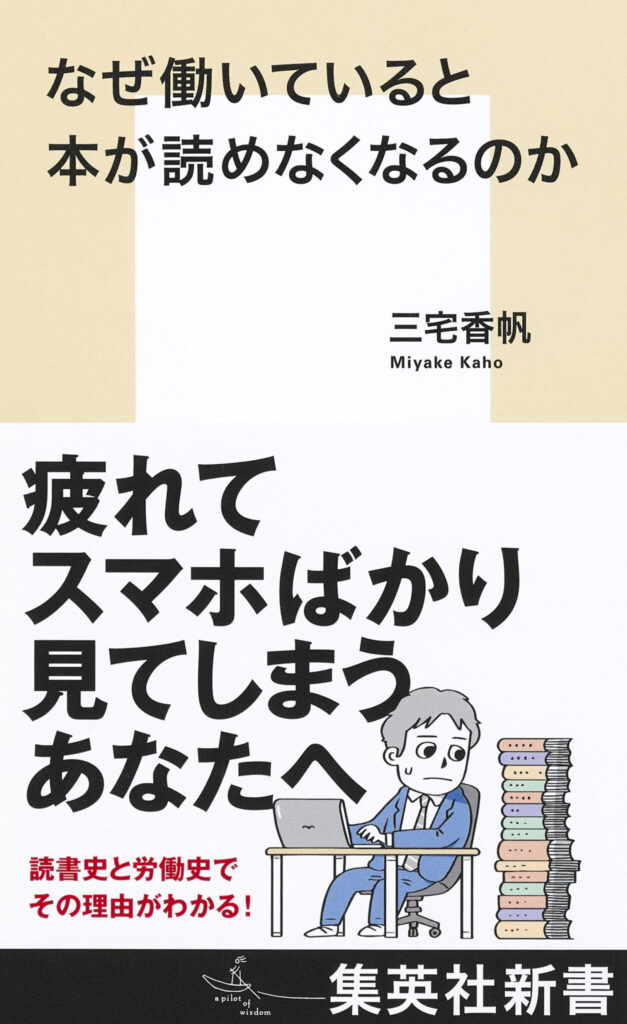










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


