情報が加速度的に増加し、スマートフォンをはじめとしたデジタルデバイスによって様々な行動が不可視化されている現代。そのような「ブラックボックス」が溢れる時代を、私たちはどう生きるべきか。
現代人にとって重要なこの問いを、著述家・書評家の永田希が、書物と貨幣の歴史を遡りながら現代思想や文学作品・SFを通して解き明かしたのが9月17日に発売された『書物と貨幣の五千年史』である。本書の主題となっている「ブラックボックス」という概念をより掘り下げるべく、集英社新書プラスでは4本の対談を掲載する。
第4回目は哲学者、千葉雅也氏との対談。テクノロジー、文化、ガジェット、フェティシズム、商品、価値、記憶……対話のなかで生まれるさまざまなキーワードから、ブラックボックス化が進む社会をどう捉えるか考える。
(構成:仲俣暁生)
「スクショ文化」のなかでの個体化
千葉 永田さんは今回の本で、テクノロジーの発達でインターフェイスが高度なものになり、技術に対するアクセスの仕方が包括的になればなるほどそれ以前の基本的な技術が覆い隠されてしまうこと、その結果、人は前より自由に行動できるようでいて、実は「見えなく」された深層構造により根深く支配されていることを多くの例を繋いで論じています。
僕の哲学の観点からみて面白いと思うのは、情報を取り出すことそれ自体を分析するのではなく、見えなさや無知、不可視性や半透明性といったもので世界はできているという、有限性の分析を行っているところなんです。我々の生活は明晰な知性よりも、有限性によってこそ組織されている。そのことに注目している点が僕の仕事との共通点ともいえるし、人間の知性の不十分さに、不自由さと同時にある種のクリエイティビティを見る両義性が、すごく現代的な観点になっていると思いました。
永田 ありがとうございます。今回、千葉さんに対談の相手を受けていただくことになり、すごく悩みました。というのも、僕自身が千葉さんの思想の影響をかなり受けていて、今回の本もかなり千葉さんを意識しながら書いた部分があったからです。
千葉 具体的に、どういうふうに意識したんですか?
永田 いちばん大きいのは千葉さんが『動きすぎてはいけない』でお書きになっていた個体化の問題です。『書物と貨幣の五千年史』におけるブラックボックスという概念は千葉さんのいう個体化を別の言い方で表現しようと思いついたものでした。そしてもうひとつ、東浩紀さんが以前に書いていた、見え過ぎてしまうという意味での「過視化」の問題からも強い影響を受けています。
千葉 今度の本で永田さんは、東さんの『動物化するポストモダン』の頃とは逆の話を書いていますよね。
永田 はい。同じ状況が主体側からはどう見えるのか、つまり目の前にあるインターフェイスがブラックボックスでしかない状態について、現代から過去に向けてブラックボックスがどんどん入れ子状態になっていく過程を示すことで、わかりやすく書こうとしたんです。
千葉 当時の東さんのオタク論では、美少女キャラクターがさまざまなデータの集まりとして構成されていることが説明されていました。その話は、データ構造を理解できるオタクのコンピュータ・リテラシーを前提にしていたわけです。でもいまの若い世代はもはやパソコンが使えなくて、スマホというガラス越しのカプセルですべてを操作している。今回の本の序盤で話題にされている「スクショ文化」は、スマホの一画面をそのまま保存するという感覚が強いものでしょう。ある時期までは、東さんが当時論じたような、テクノロジーの発展とサブカルチャーの発達がシンクロして進むというビジョンがあったけれど、デジタルメディアがスマホによって本格的に大衆化すると、事態がずいぶん変わってきた。たとえばいまは、OSの構成ファイルを開いて見る人は少ないでしょう。アップルではmacOSをスマホ用のiOSに寄せていき、パソコンのアーキテクチャのブラックボックス化が進んでいるわけです。むかしのマッキントッシュはよくフリーズしたので、システムの再インストールの際に機能拡張を一つずつ手作業でチェックしたりしたものだけれど、そういう手間をかけること自体が、いまはできなくなってしまった。
永田 そのおかげでMacもWindowsも、そしてスマホも格段に普及したといえますよね。東浩紀さんは『サイバースペースはなぜそう呼ばれるか』(河出文庫)で、シェリー・タークルのat face valueをもじったat interface value、つまり「画面に表示されているものしか信じない」という事態にも着目していました。その後の『動物化するポストモダン』では、一部のインターネットユーザーにみられるat interface value的な振る舞いが今後は肥大化するだろう、と書いていたと僕は考えています。今回の僕の本はその「予言」の先の未来にいる人間として書いたという側面があるつもりなんです。
小説だからグレーゾーンが描ける
永田 ところで千葉さんは7月に刊行された『ライティングの哲学』のなかに収録されている座談会で、小説を書くようになってから文章を書くことについての考え方が変わってきたと仰っていますね。千葉さんの小説作品は『オーバーヒート』『デッドライン』『マジックミラー』というタイトルからも明らかなとおり、いずれも境界について書かれています。境界を踏み越えるでもなく踏みとどまるでもなく、その境界をまさに踏んでいる状態。僕自身の関心に引きつけると、それはまさにブラックボックスを開けたり閉めたりする話なんです。
千葉 人間というものは過剰な認知のエネルギーを持て余していて、そこにセーブをかける。そのときのセーブのかけ方の結晶化がさまざまな形態をとる、という考えが僕の文化論の根本にはあります。僕が小説を書いてみて発見したのは、無駄とも思えるこまごまとしたディテールを書くことで、学者的な感覚では捉えられなかった中間的で微妙な解像度が得られるという事実です。境界的なエクリチュール、グレーゾーンに存在している具体性を記述するようなエクリチュールこそが、小説では問題になる。論文の場合は抽象概念によってブラックボックス化されてしまう部分が、小説として書くことで開かれるとも言えるかもしれません。最初から綺麗にパッケージしたかたちで書くよりも、断片的な具体性をどんどん書いていく方向に最近はシフトしています。
永田 僕は千葉さんの論考から、極めて明晰であると同時に、曖昧模糊としたわかりにくいほうにも切り込んでいく感じを受けていました。それらと比べると千葉さんの小説は、読み口としてはずいぶんさらっとしているように感じます。そこでも何か方向転換はあったのでしょうか。
千葉 方向転換というより、もともとグレーゾーンの問題を扱っていたのを、小説ではさらに掘り下げているつもりです。より具体的なことを書くことで、むしろ抽象度は上がっている。その意味では違うことをしているとは思わないけれど、論文のような圧縮された書き方ではなく、思考の無意識的な展開をそのまま書いてもいいと思えるようにはなった。そこは自分自身がこれまで制約をかけていたのだと思います
永田 小説のほうが抽象度が上がっているといういまの話は、とても腑に落ちました。
千葉 僕の小説は、一見するとそう見えないかもしれませんが、抽象的なんです。さまざまなイメージの幾何学みたいな組み立て方になっていて、表面上で描かれている人間関係も上部構造にすぎなくて、本体は抽象的な構築物だと思っています。
ガジェットとフェティシズム
永田 僕は今回の本で「ブラックボックス」という言葉を、様々なガジェットのことを指して使っています。もちろんスマホもそうだし、パソコンや車もそうです。千葉さんは最近、『ステレオサウンド』というオーディオ雑誌で「オーディオ存在論」という連載を始められましたが、『ライティングの哲学』でもご自身のガジェット愛をかなり語っている印象がありました。
千葉 言われてみれば、たしかにガジェットはブラックボックスですね。そしてガジェットについてであれば、僕は語るべきことがありますね。というのも、文系インテリはあまりガジェット愛を語らないから(笑) ガジェットはそもそも商品なので、特定の商品をありがたがるのはかっこ悪いという感じがするのかもしれない。でも僕はモノが持っている個体性、他の何者でないそれが持っている神秘性に惹かれる。そして、それはまさに永田さんのいうブラックボックス性だと思うんですよ。
永田 ガジェットは、スマホでもコンピューターでも車でも、基本的には大量生産されたいくつかのロットの中のひとつが、たまたま手元に来る、というものですよね。その場合、ガジェット愛とは、手元に来たそのモノに対する愛なのか、それともロットそのものを生み出している抽象的な何かへの愛なのか、どっちなのでしょうか。
千葉 たとえば車だったら「ポルシェ911」というものへのフェティシズムですね。もちろん、さらに細分化すれば、同じ911でも空冷式の昔のものがいいとか、黒がいい、赤がいいという話になってくるわけだけど。いずれにせよ、これはフェティシズムの話です。僕は人間の欲望にとってフェティシズムはすごく大事だと思っています。というのも、フェティシズムは「なぜそれを大事だと思うのか」を分析的に十分に問わない、そこを問えないからこそ成立するものだからです。だから徹底して分析的に思考する人はフェティシズムを嫌う。プログラマーの友人と話していると、原理的な意味で用が足りることを最優先に考えているようなんです。ある種の理系の人には、そうしたデザイン嫌悪のようなものがある。なぜならデザインは筋が通っていないもので、必ず不合理性があるから、理系的な思考からすると余剰なんですよ。そして僕は、永田さんの言うブラックボックス化はその部分とも関わっていると思うんです。
永田 僕はフェティシズムを、何かしらの手ざわりとか、自分の手元にあることをとても重要なこととするものとして捉えていましたが、この考え方だとまだ限定的すぎるんですね。
千葉 フェティシズムにはもうちょっと一般性があると思います。たとえば足フェチの人は、もちろん目の前の特定の足に執着することもあるけれど、足一般が問題なわけです。そのときの「足」は、「ポルシェ911」と同じ存在の水準だと思います。
永田 ポルシェの特定の型番がイメージとしてのブラックボックスになっていて、その中にあるいろいろなパーツの細かい違いもいったん箱に入れ、その全体がフェティシズム的な愛の対象になるということですね。
千葉 そうですね。もちろんそのブラックボックスをこじ開けて、エンジンまで自分でいじれる人もいる。うちの父親の話をすると、彼はまさにその「中身がいじれる人」なんです。ガジェット愛は大衆的なフェティシズムだけど、僕にはそのフェティシズムを肯定する感覚があって、それはおそらく自分の父親から継承しているんです。うちの父親はオーディオ機器も自分で作れたから、高価なオーディオ機器がどうできているかをある程度分析できた。有名メーカーの機器のよさもわかるけれど、匹敵するものを俺は作れるぞ、と(笑)
父には既製品を嫌うアンチエスタブリッシュメントの感覚がありましたが、同時に、「やっぱりポルシェはいいよな」という感覚ももっていた。この二重性は、フェティシズムの水準を理解していながら同時に分析的にも思考し、フェティシズムを全否定はしない僕自身にもあるものです。大多数のインテリは、理系的な方向にせよ文系的な方向にせよ、分析能力が進むとフェティシズムを否定する、つまり大衆文化を否定する方向に向かう。でも僕の場合、父親の影響のせいか、そのあたりがハイブリッドなんですよ。
永田 ガジェット愛といえば、何かのモノに対する「それが答えだ」みたいなものだと思っていたのですが、そんな単純な話ではなく、そのような深みがあるんですね。
サインをすれば何でも商品になる
千葉 この話の延長線上で、「商品とは何なのか」を最近よく考えるんです。ずっと昔から、本当に何でもないモノが商品になるということに興味があって、そのこともブラックボックスが生じることと多分つながっています。永田さんの今回の本でも、書物(そしてそこに載った作品)と貨幣を並べて捉えているところが僕には響いたんです。
ちょっとこれは大げさに言うんですが、僕は幼稚園のときに、どんなものでもサインさえすれば商品になる、ということに気づいたんですよ(笑) まあ、デュシャンですよね。

千葉雅也 氏 ©新潮社
永田 すごい、幼稚園でデュシャン(笑)
千葉 紙を切って組み合わせて、そこに絵を描いて日比野克彦の作品みたいなものをつくったら、すごく褒められた。それで調子にのって、ビニール袋にパッケージして「Masaya Chiba」ってローマ字でサインをしたら、おばが50円くらいで買ってくれた。素人が作ったものでも、パッケージしてサインすることで商品として成立するのはなぜか、ということを僕はこのときからずっと考えています。それから、ピアノの即興演奏を幼稚園のときからやっていて、最初の発表会でやったのは『海』という題の即興作品でした。
永田 それもすごい。
千葉 「白鍵だけ弾けば誰でもチック・コリアになれる」というタモリの有名な芸があるけれど、まったく無価値と思えるような音列でも、あるとき魔法のように作品として成立をするのはなぜかということを、それ以来ずっと考えているんです。
永田 いま千葉さんが「成立する」と仰った瞬間が、たぶん僕が言うところのブラックボックス化なんだと思うんです。そこで何か魔法のようなことが起き、パッケージとして流通し得るものになってしまう。千葉さんの即興演奏の話を受けて言うと、僕は自分がDJをするときに同様のことを考えていると思います。他人の作品を切り貼りし、加工して並べたミックスに自分のシグネチャーをつけることがDJという行為だと僕は捉えているけれど、そこで何かしらの処理をしないと、シグネチャー付きのパッケージという商品にはならない。サンプリングした断片の単なるランダムな並び方ではダメで、特定の並び方や特定のプロセッシングによって価値が生まれる。そのことに気がついたのは幼稚園時代ではなくて、ようやくハイティーンになってからでしたが(笑)
千葉 それもやはり価値はどう生じるのか、という問いですね。
永田 しかもその価値はグラデーションではなくて、どこかでぼこっと発生する。価値の発生そのものについての問いなんだと思います。
千葉 価値はサインをしたときなどに、突然、がつんと発生する。
失われた時間と身体性
永田 一種の技術決定論として、テクノロジーによって感覚や意識が変わるとはよく言われますが、千葉さん自身もいろいろなガジェットによって自分が変わってしまったという感覚はありますか?
千葉 それはあると思いますね。
永田 今度の本で僕は、いろいろな技術が今後も生まれ、世界はいっそうブラックボックス化されていくだろう、という話をしています。僕自身、いまは電子書籍のテキストをスマホに読み上げさせて聞いているし、原稿を書くときも、できれば音声入力でやりたいとさえ思っているんです。興味本位の遊びのような挑戦ですが、それをすることで自分だけのものが何か得られるんじゃないのかな、って。

永田希 氏
千葉 僕は、技術は必要に応じて使っているのであって、積極的に最新のテクノロジーに合わせた身体になろうという気持ちはないですけどね。
永田 僕自身もこの感覚が一般的だとは全然思っていません(笑) ただ千葉さんも『ライティングの哲学』で書かれていたように、いろいろな執筆ツールを使いこなしていくことにはこだわりがあるんじゃないですか?
千葉 僕の場合は、やりたいことがまず先にあるんですね。より自由に楽に文章が書けることが重要だから、その目的に叶うのであればいろんなツールも使うし、部分的に音声入力を使うこともある。でもその一方で、僕はピアノ弾きでもあるから、手で書いた文字列が目の前に表示されることと、ピアノ的な手の感覚、ある種の抽象的なリズミカルな連動によって文章が生み出されていくこととの間には特有の意味のつながりがあるんです。
永田 いま仰った、手入力の気持ちよさみたいなことは僕もよくわかるんです。スマホで書いていると、キーボードを打つときの気持ちよさは感じられなくて寂しくなることがあります。しかし、いま千葉さんが仰ったような「特有の意味」を失われないようにするべきなのか、寂しく思いながらも喪失していくほうがいいのか、僕はもう判断ができなくなってしまいました。
千葉 僕の場合、自分はこういう身体を生きてきたという歴史性に立脚しているから、テクノロジーなり、いろいろな社会の新しい状態なりとのかかわりは、あくまでも部分的なものと考えているんです。なぜならそれらによってかつての感覚が失われ、置き換えられてしまうから。僕は1990年代後半の文化をすごく大事にしていて、そこにコミットするような小説を書いているし、さっき言ったような幼稚園のときの感覚もまだ部分的に持っている。小学生だった1980年代のある種の価値観も保持していて、そのときどきの身体感覚も覚えている。そういう多層の歴史を抱えるかたちで生きてきたから、ブラックボックスがさらにブラックボックスの中に取り込まれ、そのいちばん新しいところに自分を位置づけるというふうには、どうしてもならないんです。
永田 そうならないのは固有の身体性があるから、でしょうか。
千葉 そうですね。ブラックボックスの最前面につねに押し流されていくのではない、それとは別の身体性、まさに「自分自身というブラックボックス」が、大きなタイムラインとは別にあり続けているということだと思います。
永田 なるほど。じつは僕自身は千葉さんと対極的に、過去のことは忘れている、という感覚がものすごく強いんです。幼少期から蓄積されてきた記憶もおそらくあるんですが、それが「ある」という感覚がさして強くない。むしろ基本的なテイストとしては、自分のまわりのすべてがブラックボックスである、というのが極めて実感に近いんです。
さきほど千葉さんがお父様の話をしてくださったので、僕は母の話をしますが、彼女は若年性アルツハイマーによって、いまはもう僕が誰かもわからないんですね。彼女の中にまだ何かがあるのだとすれば、それは僕らにとってはブラックボックスだし、彼女からすると、会っても誰だかわからない僕はブラックボックスになっている。ブラックボックスという譬えがここでも通用するかわかりませんが、「誰だかわからない人」という意味ではそうだろうという感じがすごくあるんです。人間のもつそうしたブラックボックス性について、今度の本ではもっとうまく書きたかったのですが、とにかく、書きたかったことのひとつでした。もしかすると、そうしたちょっと普通ではない僕個人の実感のもとで書いている本なので、過去の実感をしっかり維持している人には、「なにを言ってるんだこいつは?」という感じを与えているかもしれません。
千葉 だからこそこの本は、永田さんがテクノロジーの歴史のタイムラインとは別の時間軸から、そのタイムラインをアイロニカルに俯瞰しているもののように僕には読めました。
永田 ありがとうございます。でも、僕はアイロニカルに書こうとしたわけではないんです。時間を超えて何かを残すために書物は書かれるのに、それが仕方なしに失われてしまう、その仕方なさは重要だと思います。なぜ失われるのかといえば、時間が経つからです。そして時間が経つなかで僕自身が何を失ったかといえば、労働の時間や就寝時間、病を得ていた時間や人とのつき合いの時間によって、本当に楽しかったときの記憶が削られていた。この「削られている」という感覚と、時間のなかで書物が「失われていく」感覚が、自分のなかでは完全にパラレルでした。
千葉 残そうと思っていたものが時間の中で失われていく感覚と、永田さん自身の、ある種の忘却の中を生き延びていく感覚がつながっている。世の中のブラックボックス化が進んでいく過程で、ご自身にとっての過去も闇に覆われていく感覚があるということですか。
永田 そう、まさに闇に覆われていく感覚ですね。もしかしたらそんな過去はなかったのかもしれない、それにもかかわらずブラックボックスがそれをあるかのように見せかけてくる、という感じさえあるんです。
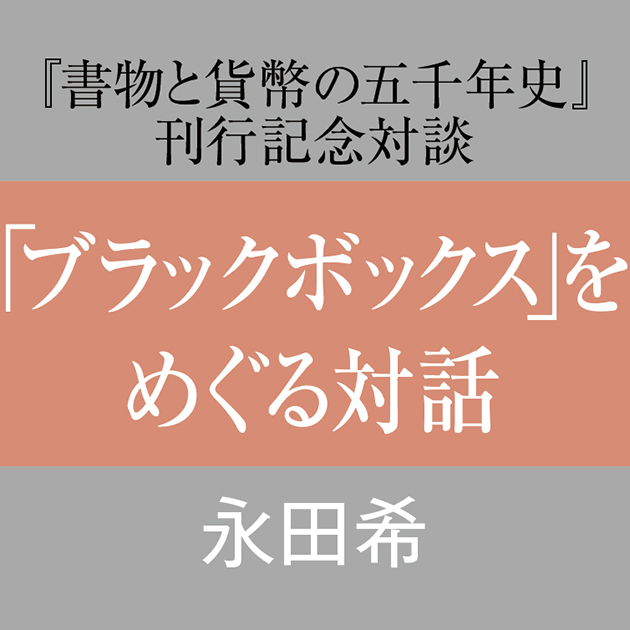
情報が加速度的に増加し、スマートフォンをはじめとしたデジタルデバイスによって様々な行動が不可視化されている現代。そのような「ブラックボックス」が溢れる時代を、私たちはどう生きるべきか。 現代人にとって重要なこの問いを、著述家・書評家の永田希が、書物と貨幣の歴史を遡りながら現代思想や文学作品・SFを通して解き明かしたのが9月17日に発売される『書物と貨幣の五千年史』である。本書の主題となっている「ブラックボックス」という概念をより掘り下げるべく、集英社新書プラスでは4本の対談を掲載する。
プロフィール

永田希(ながた のぞみ)
著述家、書評家。1979年、アメリカ合衆国コネチカット州生まれ。
書評サイト「Book News」主宰。「週刊金曜日」書評委員。
「ダ・ヴィンチ」ブックウォッチャーの1人として毎月選書と書評を担当。
著書に『積読こそが完全な読書術である』(イースト・プレス)。
千葉雅也(ちばまさや)
一九七八年、栃木県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。専門は哲学・表象文化論。著書に『動きすぎてはいけない』(河出書房新社、第四回紀伊國屋じんぶん大賞、第五回表象文化論学会賞受賞)、『勉強の哲学』(文藝春秋、増補版・文春文庫)、『メイキング・オブ・勉強の哲学』『アメリカ紀行』(ともに文藝春秋)、『ツイッター哲学』(河出文庫)、『意味がない無意味』(河出書房新社)、『デッドライン』(新潮社、第四一回野間文芸新人賞受賞、第一六二回芥川賞候補)、『ライティングの哲学』(共著、星海社新書)、『オーバーヒート』(新潮社、「オーバーヒート」第一六五回芥川賞候補、「マジックミラー」第四五回川端康成文学賞受賞)、『言語が消滅する前に』(共著、幻冬舎新書)など。


 永田希×千葉雅也
永田希×千葉雅也


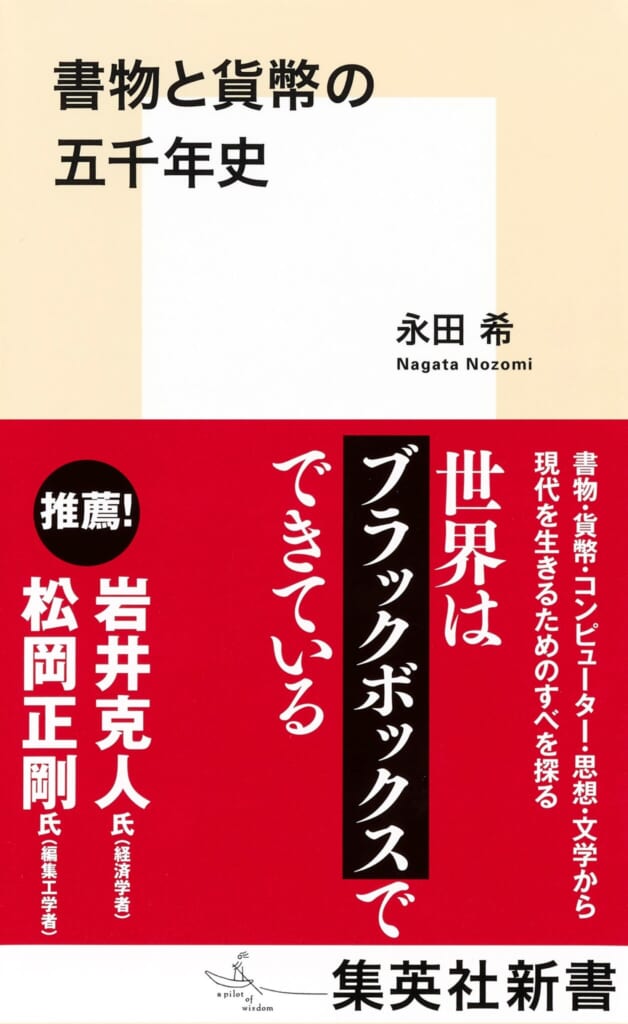










 藤原辰史×青木 理
藤原辰史×青木 理




 森野咲
森野咲