『君の名は。』『天気の子』が大ヒットを記録し、日本を代表するクリエイターになった新海誠。
11月11日には最新作『すずめの戸締まり』が控えている。新海はなぜ、「国民的作家」になり得たのか。評論家であり自ら代表を務める会社ニューディアーの事業を通じて海外アニメーション作品の紹介者としても活躍する土居伸彰氏が、世界のアニメーションの歴史や潮流と照らし合わせながら新海作品の魅力を解き明かしたのが、10月17日に発売される『新海誠 国民的アニメ作家の誕生』である。
本記事では刊行を記念し、アニメ研究の大家であり、新海誠氏を取材したこともある氷川竜介をゲストに迎え、新海誠という作家の魅力と本質に迫る。

― この記事では『新海誠 国民的作家の誕生』を題材に、「新海誠とはどのような作家か?」ということを掘り下げていきたいと思います。まず、お二人はどのようにアニメーションに関わっていらっしゃるのでしょうか。
氷川 わたしは元々、アニメや特撮に関するライティングや編集をやっていて、雑誌、DVD/Blu-rayでの解説、ウェブサイトへの寄稿が多かったですが、2010年代以降は文化庁メディア芸術祭審査委員や毎日映画コンクール審査委員などをするようになり、現在明治大学大学院で特任教授として、おもに日本のアニメや特撮の研究をさせてもらっています。
土居 僕は大学院でユーリー・ノルシュテインというロシアのアニメーション作家の研究をしていたことをきっかけに、個人または小規模でアニメーションを作る作家たちの作品を中心に評論しています。そういった作家は世界中にたくさん存在していますが、日本国内で人の目に触れるチャンスが少ないので、「株式会社ニューディアー」という小さな会社を立ち上げ、海外の作品を買い付けて日本に配給したりしています。映画祭運営の仕事もしており、新千歳空港国際アニメーション映画祭やひろしまアニメーションシーズンといった映画祭の立ち上げに携わり、後者では現在もプロデューサーとして関わっています。最近では日本人作家の短編やゲーム作品を国際共同製作で作ることも積極的に行っています。執筆・講演・評論も含め、様々なやり方で面白いアニメーション作家を「紹介」しています。
― お聞きすると、新海誠のような監督について土居さんが書かれるというのは、とても意外にも感じますね。
土居 そうですね。新海監督の本を書くというのも、そもそも僕の頭から出てきたアイデアではなく(笑)、編集者の方に企画をご提案いただいて書いたんです。でも、実際書いてみると、思った以上に僕自身も学びが深かった。新海監督の新しさについて書くことは、世界的なアニメーションの変化の動向の話ともつながっていくんだなと。転換点にあるいまのアニメーションの状況を象徴するような作家として、新海誠をみることができる。そもそも新海監督は個人作家からスタートした方なので、そういう意味では僕の専門でもあったわけです。

― 氷川さんは土居さんが書かれたご著書を読まれて、どのように感じられましたか。
氷川 新海誠というアニメーション作家を語ることを通して、アニメーションの歴史やスタート地点とは?という話から始まり、どのようにアニメーションが発展していったか、アニメーションはどのような動きを描いてきたか、ということを再定義していて大変面白かったです。
もう一つは、新海誠を世界の個人作家たちの潮流に位置付けることで、「日本のアニメーションは、世界のアニメーションとは違うものであり、世界的に見ても特別なものだ」というありがちな言説を解体している。これは、個人作家について研究してきた土居さんならではの仕事だと思います。
土居 ありがとうございます。僕はノルシュテインの「アニメーションは個人的な世界を映像化するのに向いたメディアである」という考え方に感銘を受けて、アニメーションの研究や評論をしてきました。新海誠にも、それが当てはまると思うんです。
僕は初期の新海作品のなかでは『秒速5センチメートル』がすごく好きなんですけど、この作品はまさに、主人公たちの「個人的な」世界を描いているように思えます。主人公たちが生きる孤独さの光景を描くというか。
新海誠の作品について、かつての僕は「四季折々の風景の切なさとかがわかるのは日本人しかいないんじゃないのかな?」などと思っていたときもありました。日本人の心象にピンポイントで突き刺さるタイプの作家さんなのかなと。ただ、僕も映画祭の仕事で海外によく行くのですが、とても熱狂的な新海誠のファンがかなりいることがわかってきた。そんななかで、日本を舞台に現実を美しく描くということが問題なわけではなく、今の社会のなかで孤独に生きていたり、生きづらさを感じている人たちの心象を描いているのだなと思いあたったんです。
実景を綺麗に描くことで変わりゆく現実に直面したときの孤独を描く方法論——僕は「秒速メソッド」と勝手に呼んでいるのですが(笑)——は、かなり汎用性が高いもので、たとえば中国では『詩季織々』というオムニバスが作られたり、アジア圏を中心に「秒速メソッド」で作られるアニメーション作品も増えてきている印象です。
氷川 日本の設定っていうのは海外の人にまったく通じないことは多々ありますよね。それこそリテラシー的な素養っていうのがないと、読み解けないとこは結構いっぱいある。例えば「なぜ日本は夏になるとジージーと音が鳴っているんだ?」って(笑)。
「それはセミなんだよ!」って日本人なら思っちゃいますが、桜の花吹雪や初雪の切なさが描かれても、そういうのは海外の方には壁になってしまうんです。今回の本で僕が刺激を受けたのは、アニメーション自体が持っている言語を越えて伝わっていく浸透圧の強さ、字幕などがなくても見てしまう人だったり、人の心をかきたてる力、そういう本来のアニメーションがもっている力を捉えて書いていることです。
国々の社会が違うといっても、誰か他人にときめいたり、こんちくしょうと思ったり、喜怒哀楽的なものってあんまり変わらないですよね。ゲーム、映画、漫画と比べても、人種や言語の問題や読み方・文法が違ったりして、さまざまな壁があってブロックされることがあるんですが、アニメはそういったブロックが少ないんだなと。改めて感じさせてくれましたね。
土居 すこし話がそれますが、新海監督は海外の舞台挨拶でお客さんを掴むのがめちゃくちゃうまいと聞いたことがあります。
氷川 新海さんはすごくサービス精神があって気前がいいらしいですね。彼は学生時代に留学していて、世界津々浦々に足を運んでいるので、行ってない国がないくらいじゃないですか。孤独感を描いた作品を作っているから本人も静かな感じかと思いきや、実はそんなことはないんです。ある国ではファンじゃなかった子が新海ファンの友達についていって舞台挨拶を観たら、ファンになって帰ってきた、みたいな話を聞いたことがあります。一度会えば、誰もが好きになるタイプのようです。そういった部分は、作品にも出ていますよね。観客や世界を肯定するようなまなざしは彼自身の価値観が出ているように見える。
土居 新海監督と二人三脚をしているプロデューサーの川口典孝さんとお話ししたとき、「(新海監督は)自己満足みたいなことを絶対にやらないし、本当にお客さんのことを考えている」ということを話されていたことが印象に残っています。本の中でもそのあたりはかなり重視していて、新海監督の作品には「世界はこうあるべきだ」という「否定」の態度で観客を置いてきぼりにすることはせず、「世界はこうあっていい」というような「肯定」の態度があることがいまの時代的にすごく合っているということを書いています。

― 先ほど氷川さんもご指摘されていた通り、本書では世界の個人作家と新海誠を並べて論じられていますが、新海作品と個人作家の動向の共通点とはどのようなものでしょうか?
土居 アニメーション制作のデジタル化によって、個人で所有できるレベルのパソコン一台で作品が作れるようになった。個人作家の時代が到来したわけです。そこから、すごくエキサイティングなアニメーション作品・制作方法が生まれるようになったんです。新海監督もデビュー当時はパソコン一台で、一人で作品を作り上げていた。初期の代表作『ほしのこえ』はそこが画期的だと言われました。集団制作が普通であるはずの「アニメ」を一人で作ってしまった。
氷川 『ほしのこえ』を観たときは「ああ、ここから個人でアニメを作る作家が増えるんだろうな」と思いましたが、実際はそういう人はあまり出てきませんでした(笑)。そのやり方が、新海さんにあっていたんでしょうね。
土居 世界を見渡すと、各地域に1人ぐらいの割合で、新海誠のように個人作家かつメジャーな作家がでてきた感じですね。個人作家だからこそ生まれるアニメーションの新しいあり方として本書で注目したことのひとつが「棒線画性」です。僕が自分の会社で配給した世界の個人作家に——個人ベースにもかかわらず米国アカデミー賞にノミネートするなどメインストリームにも浸透していることから、僕としてはそれぞれアメリカとブラジルの新海誠のような存在だと思っているのですが——、ドン・ハーツフェルト(『明日の世界』)とアレ・アブレウ(『父を探して』)という作家がいます。彼らの作品は、キャラクターが棒線画で表現されている。つまり、キャラクターの描き込みをしないで制作された作品なんです。
『父を探して』では、すごく大きな世界のなかで翻弄されていく豆粒みたいな人間の在り方が描かれている。そういったテーマを描くうえで、「丸書いてちょん」を人間として描いても別にいいんだよっていうような発見があり、何なら逆に「丸書いてちょん」にすることによって人間のまた別の性質が見えてくる。そういった意味をこめて「棒線画性」という言葉を使っています。
氷川 テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』(1995年)の最後2話では、紙にエンピツでキャラクターが描かれるシーンがありますけど、ああいう感じですよね。
土居 そうですね。僕は旧エヴァにリアルタイムでものすごくハマっていて、よく考えると、自分が実験的な表現を用いたアニメーションの研究をするようになったのも、あの最後の2話の影響なんじゃないかと思うこともあったりします。新海監督もエヴァからの影響は公言していますね。
話を戻すと、棒線画性は、個人作家が制作をするとき潤沢に作画スタッフを用意できるわけではなく、制作のリソースが限られていることに由来するところもあるわけですが、それによって新しい美学のようなものが生まれているともいえるわけです。
新海監督の作品は文字通りの棒線画を使っているわけではないですが、『君の名は。』で田中将賀さんと組む前のキャラクター・デザインがどちらかといえばブレの少ない「端正さ」のほうに寄っていること、さらには新海作品での背景画が非常に綺麗で、人間キャラクターよりも過剰な情報量が込められていることで、逆説的に人間キャラクターが棒線画のような存在になっている。
その形式的な特徴が、「大きな世界のなかで孤独で誰ともつながれていない」「この世界のなかで生き生きとできない」というテーマの表現に繋がっていく。個人作家もしくは個人作家出身の世界的な作家が持つこれらの性質を、この本の中で「棒線画性」という言葉で論じてみました。
氷川 アニメーションの記号性や抽象性というところを自己言及していくと、最小単位の世界でしかなくなる、みたいなね。テレビ版『新世紀エヴァンゲリオン』の最後2話をいま挙げましたけど、あの描かれ方も、線も雑になって、記号になっていくという描かれ方でしたよね。あの表現は碇シンジの自己内省を描きつつ、「アニメとは何だろう?」という自己言及にも繋がっている。
じつは『君の名は。』でも線画モードになっちゃうところがあります。橋本敬史さんという日本一のエフェクトアニメーターが描いているシーンで、豪快な線しかないアニメーションパートがありますよね、ああいう描き方をすることで、アニメーションの記号性や抽象性を自己言及していると。
― ただ『君の名は。』は土居さんのいう「棒線画性」が薄れているように見えますが、「大いなる世界とちっぽけな自分」という表現はより強くなっているように思います。
土居 そこがポイントで、初期新海作品の「棒線画性」を抑えておくと、『君の名は。』以降の大規模作品の本質も読み溶けるのではないか、というのが本書の立場です。個人作家的なアニメーション表現が集団制作の歴史における優れたスタッフの仕事と組み合わさることで、『君の名は。』は革新的かつ大衆的でもある唯一無二の作品になった、というのが本書の見立てです。この作品は、入れ替わりを通じて人間が「器」になるという話なので、実は棒線画のような儚さは保たれている、と考えられるわけです。新海作品の人間観はさほど変わっていない。
氷川 やはりキャラクター・デザインは大事なんだなと思いますよ。『君の名は。』は田中将賀さんと安藤雅司さん、日本一のキャラクター・デザインと日本一の作画監督をつれてきて、恐ろしい作品だなとは思いましたね。「個人作家の強さ」でいうと、昔私が新海誠を取材したときに『星を追う子ども』(編集部註:新海誠の4作目の劇場用アニメーション/2011年)の画面処理を目の前で実演してくれたことがあったんです。その時、木漏れ日のなかをキャラクターがたったったと走っていくシーンに、この空間だとここの光線がここに当たっているから……といって自分で影つけして、動画に載せて自分で動かしていたんです。雲の引きやうごかし方、光の加減などをご自身で細かく調整したり、新海さんご自身で調整しているカットがいっぱいあるみたいですね。
― ほかのアニメーション監督さんだと、ここまでコントロールしようとする監督さんっていらっしゃるのでしょうか?
氷川 やられている方は当然います。とはいえ、自分でチェックする方もいれば、後ろからじーっと見ていてひと声かける方、完全に丸投げして文句をいわれる方など、人によりけりかなと。宮崎駿さんのアニメ作品だと、背景がちゃんと描けていて、セルがしっかり描けていて、それを組み合わせればものすごい力を持つんだ!というやり方。「絵で殴られる」みたいなのがガンガン載っているわけですけど、新海さんみたいな作り方は、いまや一般的ではあります。
土居 新海監督は、作品の最初(脚本)と最後(編集)を自分で担当することにより、「巨大な個人制作」をしつづけているというのが本書で語っていることのひとつでもあります。自然描写の話で言うと、はじめにも言ったとおり、僕はノルシュテインの作品からアニメーションの魅力にとりつかれて現在の活動をしているんですが、ノルシュテイン作品における自然描写も凄まじい。彼の主要な作品では、奥さんのフランチェスカ・ヤーブルソワが美術監督をしているのですが、ヤーブルソワは自然のことを非常に熟知している人で、作品美術にもそれが反映されている。ノルシュテインの作品をみていると、普段生きている中ではなかなか解されないような感覚が解(ほぐ)されていく、身体感覚や知覚が細分化されていく感じがある。アニメーションは省略にも長けているし、一方で繊細さにも向いている。新海作品にも共通する特徴です。
氷川 わたしは新海作品のなかでとりわけ『言の葉の庭』が好きなんですけど、日本の高温多湿で梅雨のうっとおしい風景をああいう風に美しく再定義していて、アニメではいちばん苦手なはずの水の表現でもこういうやり方があるのかと驚きました。ビニール傘を持っているところ、傘を通して向こう側に見えるところ、目の前に降っているところ、それぞれの水滴・雨をすべて描き分けているんですよね。それ以前のアニメーションではそういうふうにはできなかったなかで、新海さんによって分解されて再定義されてるなと。

― 背景によって統一感や一貫性がうみだされ、なにより新しく感覚が生まれてくるようですらあると。
氷川 アニメーションというのは基本的に欠落した芸術なんです。背景を描く場合でもなにを省略して誇張するかということを考えるのですが、それは逆に言えば「なにを欠落させるか?」ということを選択するわけです。カップ麺に例えるなら、「フタを空けるから、御自身の頭の中でお湯を足してラーメンにしてください」というような感じですね。
新海さんの場合は背景に情報をたっぷりと載せつつ、言葉はわざとロジックを欠落させているところもある。そういった連動性のなかに音楽もしっかりといれて、見ている人にリズミカルに伝えようとしちゃう。そうすると「ここはこういう気持ちなんだ!」とお客さんの頭の中で参加させちゃう、頭をいっぱい動かして見ることができるから気持ちよくなれる。土居さんのお話している棒線画性でいうと、一番少ない情報である棒をつかってどれぐらいの情報を伝えることができるかということで、これはお客さんのなかでどれくらい想像を膨らませてくれるかなということにもなるので、とても近しいなと思います。
― 近年のアニメとそういった新海作品での描かれ方を比べると、近年のアニメ作品はまず原作ありきで制作がスタートすることがとても多いですよね。
氷川 そうですね。原作ではこういう風に動いて、シナリオではこう書かれていて、お客さんの求めているものを叶える形ですよね。いまお話したような「欠落」をやろうとすると、炎上してしまうかもしれないわけです。とはいえ新海さんの最大の功績は、アニメを好きになってくれる人をこんなにも増やしたということでもあって、他のアニメ映画もぐっと興行成績が伸びたりしていますよね。いろんな意味で新海さんは、すごく貴重な作品を作っていると思います。
土居 氷川さんとお話しすることで、日本のアニメ史における新海監督の革新性についても改めて知ることができました。新海監督の作品は、「アニメーションとは何か? どういうことが表現できるのか?」ということを考えるために、非常に有益な視点を提供してくれます。同時に、そういった視点で新海作品を観てみることで、作品自体の深みや魅力も再発見できる。世界のアニメーション史のみならず、新海誠の作品を考える一つの入り口として、今回の本を使ってもらったら筆者としてはうれしいなと思います。
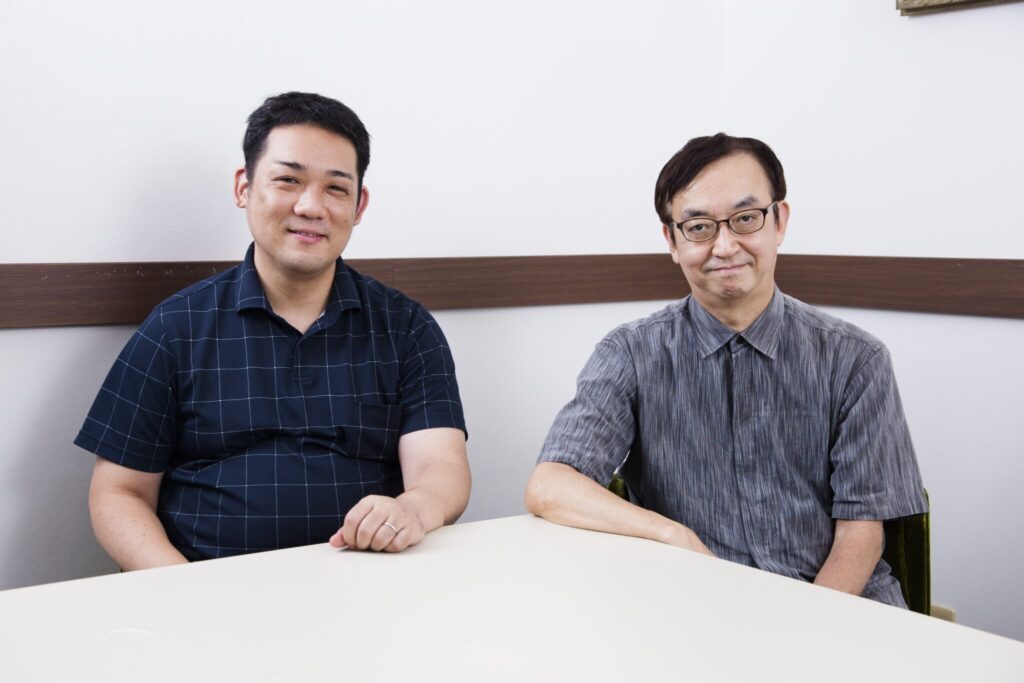
(取材・構成:草野虹 撮影:内藤サトル)
プロフィール

土居伸彰(どい のぶあき)
アニメーション研究・評論家、株式会社ニューディアー代表、ひろしまアニメーションシーズン プロデューサー。1981年東京生まれ。非商業・インディペンデント作家の研究を行うかたわら、作品の配給・製作、上映イベントなどを通じて、世界のアニメーション作品を紹介する活動に関わる。
著書に『個人的なハーモニー ノルシュテインと現代アニメーション論』『21世紀のアニメーションがわかる本』(フィルムアート社)、『私たちにはわかってる。アニメーションが世界で最も重要だって』(青土社)。
氷川竜介(ひかわ りゅうすけ)
アニメ・特撮研究家、明治大学大学院特任教授。1958年、兵庫県姫路市生まれ。東京工業大学卒。1977年に月刊OUT「宇宙戦艦ヤマト特集」でデビュー。IT系企業で通信機器開発、国際標準化活動を経験。文化庁メディア芸術祭審査委員、毎日映画コンクール審査委員などを歴任。文化庁向けに「日本特撮に関する調査報告書」「日本アニメーションガイド ロボットアニメ編」を執筆(共著)。主な編著等:「20年目のザンボット3」(太田出版)、「世紀末アニメ熱論」(キネマ旬報社)、「細田守の世界――希望と奇跡を生むアニメーション」(祥伝社、2015年)、「ジ・アート・オブ・シン・ゴジラ」(カラー)など。


 土居伸彰×氷川竜介
土居伸彰×氷川竜介









 藤原辰史×青木 理
藤原辰史×青木 理




 森野咲
森野咲