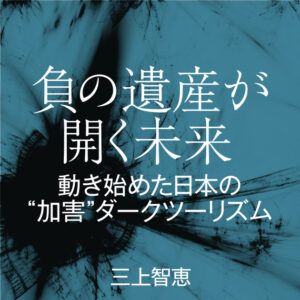2年前(2023年)、東欧を周遊しハンガリーを訪問した。首都ブダペストの観光のハイライトといえば、なんと言ってもドナウ川クルーズだろう。夕刻、ライトアップが始まった古城を眺めながら出航、ワインを片手に川風を楽しむ。クライマックスは黄金に輝く国会議事堂だ。濃紺に沈む夜空と議事堂の対比はまばゆいばかり。まさに絵葉書カットを撮影しようと、船客は一斉にスマホをかざす。ところで、歓声を上げる観光客の何割が、足元の川に投げ捨てられたユダヤ人たちの虐殺の悲劇を知っているだろうか。
600万人もの命を奪ったホロコーストの実行者は、ドイツ人だけではなかった。虐殺に手を染めた国はポーランド、ウクライナ、ルーマニアほか、リトアニアなど旧ソ連の国々を数えれば20か国以上。特にハンガリーは、ナチスの本拠地ドイツよりも格段に犠牲者の数が多いのだ。自国にそんな黒い歴史があることを、ドナウの真珠と称せられた世界遺産の街並みを楽しむ外国人には知って欲しくはないだろう。イメージダウンだし、彼らはそれを隠したいのだろう、と、わたしは日本人的な発想でそう思っていた。しかし翌日、私は頭を殴られたようなショックを受けた。


昨晩、黄金色に輝いていた国会議事堂。その見事な建築を間近で見ようと朝から川沿いを散歩していた私の目に、異様なものが飛び込んできた。護岸に脱ぎ捨てられた古い靴・靴・靴。よく見ると、男性・女性の靴、中には子どもの靴もあった。昼間なのに無数に蠟燭が灯され、いろんな国の言葉でメッセージも添えられている。追悼の場所だ。じっと見つめる人、手を合わせている人。その一帯にだけは、ほかの観光地とは違う厳粛な空気が流れていた。
それは、ユダヤ人犠牲者たちの靴のモニュメントだった。1944年から45年にかけて、ナチスに傾倒してハンガリーの実権を握った矢十字党(Arrow Cross)の兵士らによって射殺され、ドナウ川へ遺棄された犠牲者を記憶するために2005年に制作されたものだという。当時、靴は貴重品だったので、それを脱いで川べりに立たされ、銃殺されたのだそうだ。(このエピソードは2013年制作の映画「ウォーキング・ウィズ・エネミー」にも登場する)

一つ一つの靴の先には、本来それぞれの人生が続いていくはずだった。だが持ち主の人生は、突然ここで絶たれた。何もしていないのに、もうここから未来には1歩も歩けなかった。靴に個性があるだけに、それぞれが味わった恐怖と嘆き、断末魔の声が立ち上がってくる感覚に襲われ、涙があふれてきた。詳細はよくわからないのに、彼らの口惜しさが自分の体に流れ込んできて震えた。ちゃんと勉強してこなくてごめんなさい、と心の中で謝りながら、この震えるような口惜しさは体に刻み込んで持ち帰らなくては、と思った。
調べてみたところ、1941年には72万人いたとされるハンガリー国内のユダヤ人のうち、虐殺の犠牲者は終戦までに50万人を超えたといわれる。ハンガリーの人々は、同じ国に生活をしていたユダヤ人の実に7割を、正当な理由なく死に追いやったという残酷な歴史を持つ。たとえば南京大虐殺記念館の公表する中国人犠牲者の数は30万人。この数字には論争があるし比較をするものではないが、日本人は兵士以外南京の虐殺を見ていないので、それが何万人であろうとも日本人は実感できていないだろう。一方、敵国の国土ではなく、自分の生活圏の中で50万人の虐殺が進行したという記憶は、ハンガリー国民の中にリアルに重く沈んでいるのではないかと想像する。それなのに、虐殺現場を想起させる生々しいオブジェをあえて最も多くの観光客が歩く場所に固定するとは。人類史上最も残虐と言われる大虐殺の当事者であったことを、ハンガリーは国際社会に自らカミングアウトしていることになる。これは日本ではまず、考えられないことだ。
なぜそこまでするのか、と考えたときに見えてくるのは、ハンガリー国民の歴史と向き合う姿勢である。「大きな過ちを犯したことを私たちは認めるし、さらに私たちはそれに向き合い、最大の教訓にすることで乗り越えようとしている」という毅然とした態度である。とてつもない間違いを犯したことを恥じて隠すのではなく、何が起きたのか、子どもにもわかるようにして共有する。だから未来のハンガリーは二度と同じを間違った道を辿ることはないだろう。少なくともその覚悟は感じる。そのために、傷口を切り開いてでも見せているのだ。それは自虐ではなく、みんながこの傷に手を当てて進む限りは絶対に方向を誤ることはないという、正しい未来を掴むために必要な行為なのだ。そしてそれは国際社会からの信頼を獲得できる至極真っ当な方法だと理解できた。
一方で、日本には戦跡や戦争をテーマにした資料館は数多くあるが、自国民だけでなく他国の人々の命や人権を蹂躙した負の歴史に焦点を当てた展示がどれだけあるだろうか。軍国主義の中で、国と国民が犯した過ちがどんなものだったのか、目をそむけたくなるような行為であっても、子供たちの世代が間違わないため、子供にもわかるように見せていく努力がなされているだろうか。論争を呼んでも、歴史修正主義者たちに叩かれても、それを乗り越える大人たちの勇気ある姿を子供に見せてきただろうか。私がドナウ川のほとりで大きな衝撃を受けたのは、多民族が暮らし国境を巡る戦争が絶えなかった欧州の人々が、どのように負の歴史と向き合ってきたのか、その長い歴史に根差した覚悟の一端に接したからだった。翻って、なぜ私たちの国には、例えば南京の犠牲者に手を合わせ、学ぶモニュメント一つないのか。なぜ日本人は負の歴史にうまく向き合えてないのか考え込んでしまった。
私の二人の祖父は、ともに中国戦線に駆り出された兵隊だった。父方の祖父はシベリア抑留帰還兵である。私が戦争のことを聞くたびに「孫娘に言えるような話は、無えなぁ」と苦笑した。相当な加害にも手を染めたであろうし、一方で棄民された兵として辛酸をなめた犠牲者でもある。しかしこの兵士も被害者、という視点。国民も兵士もみんな被害者という語りは、日本人が大好きな無難な視点である。原爆の被害、大空襲の被害、戦争のもたらした欠乏、毎年戦争の特集が組まれると、主に被害の諸相ばかりが語られているが、それをいくら見ても「戦争は怖い、戦争は駄目だ」というところには到達しても、なぜそうなったのかを考える力は育たない。加害の側面こそ見なければ、なぜそんなことをしたのか?という問いが出ない。なぜ日本はそうしたのか?誰が選択し、誰が協力し、反対できた人は誰で、その人はどうなったのか。少なくとも「国民はみんな戦争が嫌で、戦争に突き進む為政者を憎み、体を張って抵抗した」という史実はない。なぜか。自分たちが何をどう間違ったのかを学ばない限り、次の戦争を止める視点も能力も得られない。だから戦後80年、令和になったいま、この国は再び戦前の様相に回帰してしまったのだと私は危機感を持っている。
軍国主義に染まった日本の加害について学べる場所は、実は全国各地にあるはずだ。朝鮮半島から強制的に連行された人が、非人道的に扱われた現場であったり、10代の少女に毒ガスを作らせた工場跡地であったり、いくらでもある。一方戦争中に海外で犯した罪については、その部隊の出身地などゆかりの土地を選んででも、事実を後世に伝え、犠牲者に手を合わせ「二度と同じ過ちを犯さぬために頑張ります」と子孫が誓えるような場所が、いくつも作られるべきだ。加害兵士の孫としては,せめて意識的にそういう場所に出向いて、ちゃんと歴史を見つめる機会が欲しい。そういうダークツーリズムに特化したツアーがあれば参加したいと願う人は決して少なくはないと思う。けれども日本では、戦争加害に触れる展示は「自虐史観」「反日的」「偏向教育」と槍玉にあげられ、脅迫状が送られ、撤去されたり、無難な展示に変更を迫られたりと、後味の悪い事例ばかりが積み上げられてきた感がある。それを乗り越え、戦争加害にがっつり向き合った施設があるかと問われれば心許ない現状がある。
話をハンガリーに戻すが、実はハンガリー国内にもこうした歴史修正主義の波が来ている。わかりやすい一つの事例が、この川沿いのモニュメントから徒歩15分ほどの広大な公園の一角にある「自由広場」の彫刻を巡る騒動である。これは、靴のモニュメントとともに日本人旅行客には是非見に行って欲しい、現在進行形の話である。

公園を抜けてその広場にたどり着くと、天使と鷲の銅像が現れた。翼が生えた嘆きの天使が両手を広げており、いかつい鷲が頭上から威嚇するように見下ろしている。これは、「ナチス・ドイツによるハンガリー占領70周年追悼記念碑」だそうで、2014年7月に、突然設立されたものだという。無垢な天使であるハンガリーを、強面のナチスという鷲が支配している構図になっていて、ハンガリーは完全に被害者として描かれている。これは、2期目の長期政権にあるオルバーン首相が、反対する市民の要請に耳を傾けることなく、力づくで建立してしまったという経緯がある。

この記念碑の設置を巡っては、当時100人を超える「歴史の捏造」に反対する人々が広場に集まり、社会党など左派の国会議員もデモに加わり、建設用のフェンスを破壊するなどして抵抗したが、夜陰に乗じて機動隊とクレーン車が一夜のうちに記念碑を設置してしまったそうだ。オルバーン・ヴィクトル首相は、欧州のトランプと評されるほどの右派ポピュリズムの典型的な政治家として知られている。「民族が混ざりすぎると問題が起こる」「移民は毒」という問題発言も過去にしている。まさに虐殺を引き起こす差別主義に回帰していくのかと愕然とするような言動であり、東欧の右傾化が言われて久しいがその恐怖を肌で感じた。しかし、そんなリーダーの歴史修正主義にたいして、ハンガリーの人々は黙ってはいなかった。

その彫刻の前の手すりには、夥しい数のラミネート加工されたメッセージや写真などが括り付けられている。犠牲となったユダヤ人の家族写真、彼らが使っていたカバン、靴、生活道具などが所狭しと置かれている。これらを置いた人々は「彼らの死は、すべてナチス・ドイツのせいだと歴史を捻じ曲げるつもりですか?」と猛然と抗議しているのだ。これらは、外されたり撤去されたりしても、すぐに誰かが新しい写真を掲示し、遺品が持ちこまれ、今に至っているという。これは祖父のカバンです。叔母は就学前でした。そんなメッセージとともに、彼らの命を奪ったのは誰だったのかを問い、都合の悪い歴史を塗り替えようとすることは、彼らを二度殺すようなものだと訴えているのだった。そしてこの記念碑が建立されてしまったその日から毎晩、ここに市民らが集まって抗議集会がひらかれた。それは何年も、毎日続けられ、今も定期的に継続しているという。このハンガリー市民の力。ここで起きている歴史の捻じ曲げを許さないという声明は、いくつもの国の言葉に翻訳され、世界中から来る観光客に知ってもらおうとあちこちに括りつけられている。これは、ハンガリーの名もなき国民一人一人からのメッセージなのだ。右傾化したリーダーが時の政権を握ったとしても、歴史の修正を我々市民はとことん許しません、と。

胸が熱くなった。目の前の犠牲者の写真は悲劇が確かにあったことを示しているのだが、この展示はそれだけで終わらず、その悲劇から目をそらさずに向き合うことこそが政治の劣化を止めるのだ、歴史の改ざんを許さぬ市民の力に繋がるのだと、教えている。明快なメッセージだ。負の歴史から学んで、力をつけて、二度と騙されないために我々は権力を監視して行動していかなければならないのだ。日本人が最も不得意なことをやってのける人達がいる。そのカッコよさや手法のようなものをもっと自分たちに引き付けて考えたいと思った。
実はそういうカッコよさ、骨のある展示が成功しつつある場所が、日本にもいくつか出来てきていると思っている。まだ小さな光かもしれないが、負の歴史から学ぶ、という視点に立って実践しようとしている場所をいくつか回ってきたので、それをシリーズで書いてみようと思う。その大きな動機となったのが、このブダペストでの体験だった。というわけで、次回からは国内の戦跡や資料館の事例をいくつか紹介していこうと思っている。
写真撮影:著者
プロフィール

(みかみ ちえ)
ジャーナリスト、映画監督。毎日放送、琉球朝日放送でキャスターを務める傍らドキュメンタリーを制作。初監督映画「標的の村」(2013)でキネマ旬報文化映画部門1位他19の賞を受賞。フリーに転身後、映画「戦場ぬ止み」(2015)、「標的の島 風かたか」(2017)を発表。続く映画「沖縄スパイ戦史」(大矢英代との共同監督作品、2018)は、文化庁映画賞他8つの賞を受賞。著書に『証言 沖縄スパイ戦史』(集英社新書、第7回城山三郎賞他3賞受賞)、『戦雲 要塞化する沖縄、島々の記憶』(集英社新書ノンフィクション)、『戦場ぬ止み 辺野古・高江からの祈り』『風かたか「標的の島」撮影記』(ともに大月書店)などがある。


 三上智恵
三上智恵
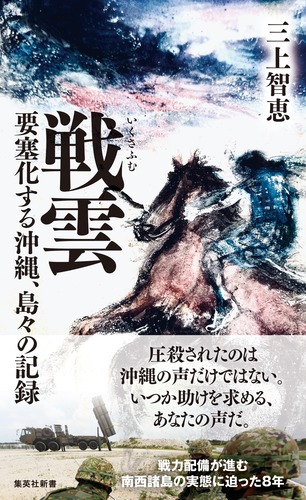
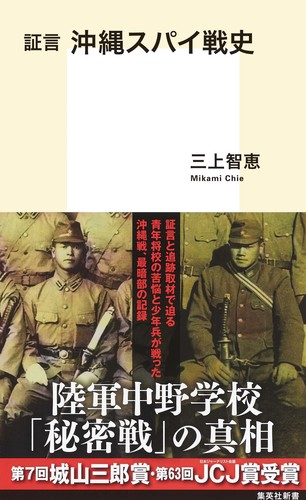






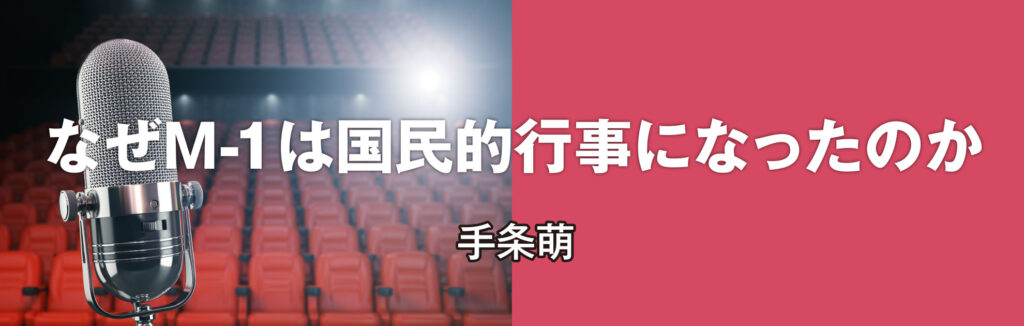



 佐藤喬×谷川嘉浩
佐藤喬×谷川嘉浩