2024年10月に発売された『崩壊する日本の公教育』(集英社新書)の著者、鈴木大裕氏は9年前に『崩壊するアメリカの公教育 日本への警告』(岩波書店)で、物事すべてを経済的な尺度で測ろうとする新自由主義に侵食され疲弊していくアメリカの公教育現場をレポートし、日本も30年遅れでアメリカの轍を踏むことになると警告を発していた。まさに今、その危惧が現実のものとなっていることを著したのが今回の本だ。
その鈴木大裕氏が、かつて教壇に立っていた千葉県の公立中学校の元教え子や同僚、教育関係者や保護者に、今の教育の現状・問題点を『崩壊する日本の公教育』に沿って解説する講演会が行われた。その模様をレポートする。
※この記事は2025年2月22日に行われた講演会の内容を抄録したものです。

鈴木 2016年に『崩壊するアメリカの公教育 日本への警告』(岩波書店)を出してから9年が経ち、本に書いたことひとつひとつが日本でも現実になってきている、というのが今の僕の正直で残念な思いです。ただ、今日はちょっと心が楽になったという希望のある話にしたいので、お付き合いください。
『崩壊するアメリカの公教育』を書いた当時は、新自由主義という言葉は日本ではまだほとんど使われていませんでしたが、今では普通に使われるようになったと思います。2019年に、大阪市立中央図書館が200万円で辰巳商会中央図書館へと名前を変えたように、今は公立図書館の命名権さえもお金で買える時代ですが、この流れが図書館で終わるはずがないんです。アメリカでは、学校の廊下の壁がゲームの広告で埋め尽くされ、食堂のテーブルにも企業広告がベタベタ貼られています。こうして子どもたちは、国の将来を担う大事な「生徒」ではなく、企業の利益になる「消費者」として自分たちを扱う社会の価値観を、日常的に刷り込まれていくわけです。
これはアメリカだけの話ではありません。経産省の諮問機関である産業構造審議会に、教育イノベーション小委員会というものがあります。この中で「学校における広告の活用」を模索しています。
教育予算がない、と国は言います。だから、これからの時代は各学校が自分の予算を稼げ、と。そのうちに校舎の壁が企業広告に使われて、公立図書館だけじゃなくて公立高校にも企業名がつくかもしれない。ここで大事なのは、「議論の枠組み」です。MIT(マサチューセッツ工科大学)の名誉教授であるノーム・チョムスキー博士はこう指摘します。「民衆を受け身で従順にする賢い方法は、議論の範囲を厳しく制限し、その中で活気ある議論を奨励すること 」。教育予算に関して言えば、国が民衆に押し付けてくる議論の枠組みは、「教育予算をどう賄うのか?」であり、その中で活発な議論を奨励してくるわけです。しかし、問われていないのは、「そもそも、なぜ他の先進国と比べて日本の教育予算はここまで小さいのか?」「なぜ各学校が自己責任で教育予算を稼がなくてはならないのか?」であり、「教育現場の自己責任を問う前に政府は投資責任を果たしているのか?」ではないだろうか。
そんな目で見ると、学校部活動の「地域移行」という問題も違った見え方がしてきますよね。国は、話す相手によって異なることを言います。教員には、学校部活動の「地域移行」は、「先生方の働き方改革だ」と言い、スポーツ関係者には、「スポーツ産業の活性化だ」と言うのです。これからは、指導者への謝金も受益者負担となり、公立学校の運動場やプール、体育館を民間企業が使ってビジネスとして成り立つようにしていく、と。国が民衆に押し付けてくるのは、「部活動は学校ですべきか、地域ですべきか?」という議論の枠組みです。ただ、問われていないのは、子どもがスポーツをしたり文化活動に親しんだりする機会は、家庭が自己責任で買うべき「サービス」なのか、すべての子どもたちに分け隔てなく保障されるべき「権利」なのか、ではないでしょうか。だから、部活動の地域移行は「教員の働き方改革」というきれいごとの話だけではない、ということです。
「教員不足をどのように埋めるか?」というのも国が押し付けてくる議論の枠組みの一つです。現在、この狭い議論の枠組みで活発な議論が奨励されています。やれ、教員採用試験日程を前倒しするだとか、大学3年生から採用試験を受験可能にするだとか、特別免許状を乱発して民間企業からたくさんの「副業先生」を招聘するだとか、授業を塾の講師に委託するだとか…。そうではなくて、大事なのは、なぜこれだけ多くの先生が精神疾患を病み、なぜこれだけ多くの若者たちが教員になりたがらないのか、ということです。
随時、質問やコメントを受け付けたいと思いますが、ここまでで何か質問はありますか。
――今日はありがとうございます。小学校に子どもを通わせている保護者なんですが、全国学力調査の他に年に一回、ちょうど先日の2月に学力テストというものを実施しました。フィードバックは何もないのですが、どのように活用されているんでしょうか。また、他の自治体でも同様のことはやっているんでしょうか。
鈴木 そのタイミングを聞くかぎりでは、4月にある全国学力調査の模試的なものでしょうか。じつは2007年に、日本の教育界にとってすごく大きな出来事がありました。全国学力調査が43年ぶりに復活したんです。では、なぜ43年前に廃止になったのか、ご存知ですか? 自治体間の点数競争が過熱して、点数を上げろという政治からの圧力で、学校単位での不正が行われるようなスキャンダルが発覚したんです。
1976年に最高裁で判決が出た旭川学テ事件(※1956年から65年まで行われた全国学力テストを阻止しようとした旭川の中学校の教師たちが起訴された事件)というものがあって、そこでは全国学力テストを通じて政治が教育に介入しているのではないかということが問われたのですが、最高裁の判決では違憲ではないという判断でした。
理由は主にふたつ。ひとつは、全国学テは簡単なものなので準備や対策をするようなものではない、ということ。もうひとつは、成績を学校別で開示しているわけではないので、競争を煽っているとは言えない、ということだったんです。今、このふたつどうですか? 両方とも崩れていますよね。学校は学力調査対策に明け暮れくれていて、学校別成績開示だって地教委の許可があればできるわけです。
全国学力調査は2007年に43年ぶりに復活した後に民主党政権になり、事業仕分けでサンプルだけを取り出す抽出式になったんですが、第二次安倍政権でそれがまた悉皆式に戻されました。それと同時に学校別の成績開示も規制緩和で可能になったため、政治が教育現場に結果責任を問えるようになったわけです。これだけ莫大な予算をかけてその費用対効果はどうなんだ、ということですね。この流れを受け、東京や大阪などの都市部では、各学校が自らの生存をかけて生徒を奪い合う「市場型」学校選択制が広がり、学校統廃合が活発になる一方で、全国初の公設民営学校も大阪に登場しました。学力テストと結果責任という二本の軸による、公教育の市場化が始まったのです。
プロフィール

教育研究者。1973年神奈川県生まれ。16歳で米ニューハンプシャー州の全寮制高校に留学。そこでの教育に衝撃を受け、日本の教育改革を志す。97年コールゲート大学教育学部卒(成績優秀者)、99年スタンフォード大学教育大学院修了(教育学修士)。その後日本に帰国し、2002~08年、千葉市の公立中学校で英語教諭として勤務。08年に再び米国に渡り、フルブライト奨学生としてコロンビア大学大学院博士課程に入学。2016年より、高知県土佐郡土佐町に移住。現在、土佐町議会議員を務める。主著は『崩壊するアメリカの公教育:日本への警告』(岩波書店)。


 鈴木大裕
鈴木大裕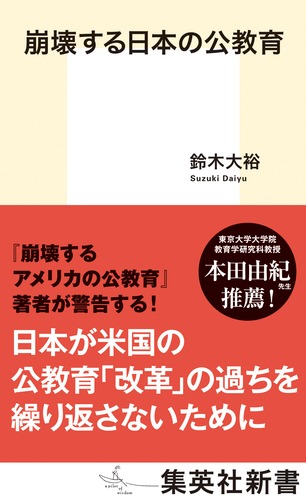










 藤原辰史×青木 理
藤原辰史×青木 理



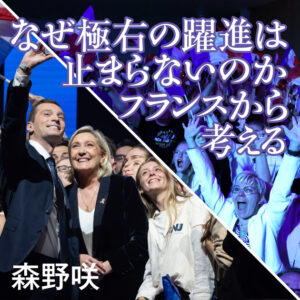
 森野咲
森野咲