地球や未来のことを考えて子を産むことを躊躇している女性の話を聞きたいと、友人たちに声をかけていたら、優秀な後輩から、知人が紹介できる人がいると言っていますと連絡が入った。
環境問題や気候変動問題を追うジャーナリストでありながら、パートナーと共にいまは子を生まない選択をしている人だという。
こまかい春雨が降りしきるなか、土曜の午前中に待ち合わせをした。オレンジっぽい髪色で、アーティスティックなカッティングのスカートにブラウスを合わせていた。魅力的な少し低い声で話す方だった。
普段はインタビューをする立場だろう、今回は初めてインタビューを受けるということで緊張されていた。
一〇年前と比べても戦争の脅威はずっと身近になったし、気候変動もまったなしの状況、世界中の若い女性たちが環境活動にとりくみ、その中からバースストライカーの動きも出始めている。子を生むことにとって、時代のフェーズが変わったという印象がある。
環境問題に取り組んでいるわけではない人にとっても、かつては子どもを産むことに理由なんて求められなかったのに、女の人だけでなく男の人も含めて子どもを持つ/持たないの選択が、責任問題となって個人に降りかかってきている。その意味を考えたいと思うんですと、企画の趣旨をお話すると「めちゃくちゃチャレンジング(笑)」と宮田さんは笑って言った。チャーミングな方だった。
宮田さんもまた同じようなテーマをウェブ媒体で追いたいと思ったことがあるという。
「数年前に“産む”ということをテーマに特集を組みたいと思ったんです。でもやっぱり結構難しくて。子どもを持っている人も、持てない人も、持たない人も取りこぼさないように伝え切るのは簡単なことではなかった。子どもを持てない、持たない、持つ選択って、長年いろいろな形でテーマになってきていて、私からするとまた違う動きとか価値観が出てきているように思うんですけれど、上司に企画を通しきれなかったんです」
たしかにこの問題に関しては、世代間で問題の受けとめ方がまったく違うという印象がある。バースストライカーの話を老齢の女性に言ったら、産む、産まないを社会活動に使うのか?!とすごくびっくりされたことがある。
一方、若い人にとっては、気候問題が心理面に及ぼす影響があると言われている。温暖化で夏が過ごしにくくなるなど状況の変化だけではなく、心理的な不安感が人の決定や選択に及ぼす影響についてはまだあまり触れられていない。宮田さん自身、気候変動問題を追ってきて、いまはメディアに身を置くのではなく、より直接的に気候変動活動を行う団体へと職を変えたという。
「そうなんです。気候変動はここ一〇年が勝負と言われていて、二〇三〇年までの意思決定が今後数千年の地球の未来を決定すると言われています。二〇三〇年なんてあと五年しかなくて……。でも気候変動の記事はあまり読まれないことが多いんです。ウェブだとPVがどれだけ取れるかが評価につながるので、気候変動のことだけやっているわけにはいかなかったんです。でもここ何年かが大事だったら、私ができる最大の選択は自分の働く八時間をすべて気候変動に使うことだと思ったんです。それが最大限コントロールできる私の選択だなと思って」
バースストライカーたちは、気候変動を解決しようとしないいまの世界に対して自分の体を使ってプロテストをしていると言えるが、宮田さんもまた自分の昼間の時間をほかのことはせず気候変動問題に捧げようと思っていらして、その真摯さに心動かされた。
いま宮田さんは、国内外の団体と連携して気候変動を解決しようという取り組みをしている。地球はこの一〇年が勝負、あと五年しかないのなら自分の時間をすべて気候変動に使おうとまで思う、宮田さんの問題意識はどのように作られていったのだろうか。
「直接的なきっかけは、SDGsに関するあるコンテンツを作っている中で、エネルギー問題のことの深刻さに気づいたのがすごく大きいです。日本で気候変動について何かやらなければいけないというとエネルギー問題が大部分を占めています。日本のCO2排出の九割近くはエネルギーから出ているので、ニアリーイコールなんですが、そうなると気候変動問題は環境を守るとか自然を守るということだけではなくて、産業革命以来の第二の産業革命ぐらいに大きな問題で、世の中の経済構造もそうだし、政治の意思決定の変化など、根本的なところまでシステムを変えないと解決できない。経済だけでなく人権の問題につながっていたりとか、食の問題があったりとか、本当にあらゆる問題の根本を揺るがすことなんだなって。かつタイムリミットが迫っていることなので、これは何か相当やばいんだなと思ったのが直接的なきっかけです」
気候変動が人権やエネルギーの問題であり、人間活動の根本を変える問いなのだとヴィヴィッドに反応できる宮田さんのベースとなる感受性はどのように育まれたのだろうか。
「私は山登りが好きで、山を登っていると割と普通に、ここ落ちたら死ぬなとか、私がいかにちっぽけなものか、自然への尊敬と畏怖みたいなことが、多分感覚的にあったのかなと思います。海に入っているときも、ちょっとした波にさらわれるだけで死んでしまうかもしれない、でもすごい美しいって。何かそういうもともとの感覚はあったのかもしれません。もう少し子どものころの話でいうと、父が有機農法の野菜の仲卸し、農園と売場をつなぐ仕事をしていたんです。子どものころよく農場に連れて行ってもらって、道がぽこっとなっているのはモグラだよとか、動物のふんを堆肥にしているところは土がすごく暖かいとか、自然とどこか触れ合っている時間があったのは大きかったかもしれないです」
宮田さんは一九九二年生まれの、現在三三歳だ。東京近郊の比較的海の近くの生まれだ。新卒では、広告営業から仕事をし始め、その後記者としてキャリアをスタートした。
「もともとメディアの世界を目指したのは、高校生のときに図書室に報道写真の雑誌があって、そこでパレスチナの現地の写真で、女の子が瓦礫に埋まって真っ白な状態で亡くなっているのを見たんです。すごい衝撃を受けて。人が死ぬことについて知った気になっていたんですけれど、私が知っているのはドラマとかの中のもっときれいな死体だったんですね。実際はこんなふうに真っ白になって、瓦礫の一部みたいになって死ぬんだなって。知ったつもりで全然知らなかったことに衝撃を受けたんです」
いまの世界情勢でこの話を聞くと、よりいっそう身につまされたが、宮田さんが図書館でその写真に出会ったのは、十数年前の話だ。
そこから宮田さんは、ジャーナリズム学科のある大学に行って、記者を目指す。至極まっすぐに進んでいく宮田さんの根幹は、きっといまでも変わらないのだろう。そんな彼女が、いまパートナーと共に子どもを持たないと決めているというのは、決断の背景にどんな想いがあるのだろうか。
「それは気候変動のことだけじゃなくって……」
宮田さんは意志が強いが柔らかい印象の方で、ここまでお話を聞いていても、ゆっくり自分の思いをかみしめながらお話されていたが、ここで宮田さんはこれまで見せなかった逡巡というか、ゆらぎのようなものを顔に表した。
「前提として子どもは好きだし、弟のおいっ子もめちゃくちゃかわいいし幸せになってほしい。いま子どもを持っている人のことは本当に尊敬しているし、その子どもも幸せになってくれと思っている。でも自然と自分には子どもが欲しいという思いが湧いてこないんですよね。何でなのかなと思って友達に聞いたことがあったんです。世間では子どもを産む大変さばかりが語られていて、子どもを産むと何がいいの? 何が幸せなの? と、周りの人に聞いた。そうすると、結論は『何だかんだかわいい』だったんです(笑)。『何だかんだかわいい』のために、山のように語られている苦労を越えなくてはならないのか。越えられないんじゃないかというように思って……」
たしかに女性は中高生のときくらいからまことしやかに、出産はスイカを出すくらい痛くて壮絶だと聞かされ、最大限の恐怖を植え付けられるのだけれど、その後誰かがそれに勝る良い話をしてくれた記憶がない。
「『何だかんだかわいい』にいろいろ詰まっているのは分かるんですけれど、社会で語られている大変なことと比べるとあまりにそれだけ?!と。まず、体がしんどいですよね。十月十日体の中にもう一人命がある大変さ。それから産むときのリスク。お腹を切るかもしれないみたいなところ。そして産んだ後、ぼろぼろの状態で子どもをケアする。統計的に見ると出産を期に年収が下がりもする。かつ私の場合は両親が同世代よりちょっと年が上なので介護が始まりそうだなと。いやあ、無理じゃない?と。アメリカ出身の夫は基本的に結婚する前から、産むかどうかは私が最終的に決めることだと考えていて」
結婚してから、宮田さんは周りの変化に気づいた。
「結婚して、かつ三〇になると、急にみんなが子どもはどうする? と聞くんです。初めて会った保険会社の女性にも、そんなに仲よくない人にまで、子どもどうするのって言われて、考えざるを得なくなった。ただ一つ気づいたことがあって、数年前に『産まみ(む)めも展』という、産むということをいろいろな角度で捉える展示があって、その中でいろいろな言葉が天井からつるされていた中に「もし男性が子どもを産むことができたら」という言葉があったんです。それを見た瞬間に、夫が子どもを産んでくれるんだったら子どもを持つのもいいなと思えた自分がいたんです。自分に降りかかる身体的なダメージとか年収のダメージを考えると気が進まないんですけれども、相手が産んでくれるんだったら欲しいかも、みたいな」
つり下がった言葉「男性が産んでくれたら」によって、宮田さんは自分が何を負担に思っていたか、引っかかっていたことが何なのかが分かったのだろう。
これは、出産や子育てにおける困難や不安ばかりを伝えてきたメディアの責任も感じるし、もしかしたらフェミニズムの功罪でもあるのかもしれない。母になることの喜びや素晴らしさは、女性を分断するものとして語ってはいけないムードが長らくある。「母」はいまでもフェミニズムにとってどう扱って良いのか難しいファクターであり続けている。それが拙著『マザリング』の中心的課題だったのだが、それはさておき、宮田さんは出産がどれほど身体的に女性にダメージを与え、その後の人生に困難をもたらすか、陰に陽に恐怖を植え付けられていたのだと思う。
「産むかどうかにあまり現実味を感じないとか、産みたいと思わないということって、割と本能的なものとして語られることが多いんですけれども、本当はもうちょっと社会的なバイアスがあって、無意識にそう思っている側面もあるな、と。経済不安もそうですし、ジェンダー差別的なこともあるし、果たして私が自然と子どもが欲しいと思えないというのは生物としてそう思っているのか、社会的な影響を受けた結果、気持ちが湧き起こらないのかわからないよねというのは、ちょうど若い活動家の人と話していたんです」
マミートラック(出産後に復職しても正規の仕事に戻れない問題)など、実際に出産後の女性の人生設計を阻む社会的課題が解決されていないなかで、一人一人の女性が決断を迫られている。さらに出産が女性個人の自己決定とされることによって、だったらあなたに責任があるでしょと、出産後の困難の乗り越えが、個人の責任問題として語られがちである。それでは出産は女性にとって幾重にも八方塞がりだ。
「家族の影響もあると思います。母がこれまでの人生をどう思っていて、何が幸せで、私たちを産んでどう感じて生きてきたのか、聞いてもあまり語る言葉を持っていない感じがして。そんな母が幸せそうに見えなかったことも影響しているのかもしれないです。私が小さいころ母は専業主婦でしたが、父の仕事がうまくいかなくなってからはパートをしながら育ててくれました。母はお茶とかお花とか着つけとかもできるし、調理師免許も持っているし、もともとは新卒で大手企業に入っていて。本当はもっとやりたいことがあったのかなとそばで見ていて思っていたし、めちゃくちゃポテンシャルがあるのにそれを生かせなかったんじゃないか、と。父はアンガーコントロールができない人で、切れちゃうと手がつけられなくて、母はいつも調整役をしていました」
きっと宮田さんのお母様は頭のいい方で、でもだからこそぐっとこらえて、外から見ると自分の人生をどういうふうに把握してきたのか分からなかったのだろうと想像した。ロールモデルにせざるを得ない母に対しもやもやするところがあるというのは、娘の出産に対する想いに大いに影響するだろう。
「だから自分も結婚をして子どもを産むという、当たり前の人生設計図みたいなものは持っていなかったです。もやもやと何となく産みたいと思わない。それにもう一つ要因があって、私はある指定難病を患っていて、免疫を抑える薬をいつも飲んでいるんですけど、妊娠中はその薬を使えないんです。それで妊娠中はまだ再発リスクが低いんですが、出産後に再発リスクがめちゃくちゃ高まると医者に言われています。なので、出産後にちょっと強い薬を使わなければいけない。といっても私と同じ病気で子どもを持っている人もいるので、経済的な不安はあるけれども、私と夫と二人で力を合わせれば経済的な条件もクリアしているし、夫は絶対に子育てをめちゃくちゃやってくれるだろうし、障壁はあるにはあるけれども乗り越えられる障壁かもしれない。でも、やはり子どもを持ちたいと思わないというか、何かそういう感じですね」
医師から、出産後の持病悪化のリスクを聞かされたとき、まっさきにパートナーが「だったら子どもはいなくていいんじゃない?」と言ってくれたという。宮田さんは気丈にさまざまな理由を話してくれたが、まことしやかに語られる出産の身体的ダメージへの恐怖に加え、現実的に自分の身体に及ぼす影響を告知されたというのは、至極大きなことだろうと思えた。
一方で、気候変動がおよぼす心理面への影響の分析が足りないということと同じように、この国の将来像や世界の未来に対して、言葉にならない漠然とした不安が世の中に流れており、それが潜在的に個人の決断にも影響しているとも思えた。
「気候変動の話をちょっとすると、もし私が今年、子どもを持ったとしたら、二一〇〇年のとき、私の子どもは七七歳ですからきっと生きているはず。でも、気候変動の世界で二一〇〇年はすごい遠い未来の何かやばいぞみたいな話が出ている。だけど子どもを持つとしたら二一〇〇年って割とリアルな数字なんですよ。でも気候変動の世界では、これからのシナリオにもよりますが、二一〇〇年に政策の強化がないと、現状のままでは世界の平均気温が三・二度上がると言われている。二〇二四年は一・五五度、世界の平均気温が上がったんです。東京ではスコールみたいな雨が降ったり。能登の大雨も気候変動の影響で一五%雨量が増えたという話もあって。もう既に一・五五度で世界の状況はそうなってる。しかもいま起きていることは、二〇五〇年に起こるだろうと言われていたことなんです」
気候変動の予想は、年々前倒しになっているという話は、最近よく聞くようになった。
「そうなんです。真夏日が五〇日以上続くというのは、二〇五〇年の予報として世界気象機関(WMO)とNHKが出したものだったですが、もう起きてる。二一〇〇年は相当まずいだろうというのが科学的に分かっているけれども、その割に解決できるような意思決定を日本政府ができていない。せめて野心的に頑張る決定をしてくれれば、私も頑張ろうかなというふうになるんですけれども、この前決まったエネルギー基本法では二〇三五年、二〇四〇年の温室効果ガス削減目標も消極的。そういう状況を見ていると現実的に子どもの未来はやばいぞ、そこに私は責任を持ち切れないみたいな気持ちがありますね」
環境活動をしている人にこそ、バースストライカーが登場するというのは、科学的な数値を未来の地球にあてはめ、その脅威を現実的にありありと感じ取ることができるからなのだろう。彼女たちは正確に数年後、数十年後の地球の危機を身体的に受け取っている。しかし宮田さんは反対のことを話してくれた。
「ただ、子どもの数が減れば環境負荷が少なくなって地球の未来にとって良いという議論は危険だなと思います。ある人が発展途上国の女子教育を充実させると、結果的に子どもの数が減るから良いみたいなことを言っていて。女子教育は人権の問題、子どもを産む/産まないという一人一人が主体的に選択するべき人権の問題です。気候変動対策として人口が減ることを期待して女子教育の可能性を語るのは、違和感があります。子どもが幸せに生きていくためにこそ気候変動も女子教育の問題も解決したいので、子どもを産まないことが地球に良い、というのは本末転倒な気がしてるんです。私もあくまで自分の選択として子どもを持つか/持たないかを考えています」
子どもを持つか持たないかの女性の選択は、人権問題。環境問題のような社会課題克服のため、女性に子どもを産むこと、あるいは産まないことを他人が期待するのは、そもそも人権問題としてアウト、という議論だ。それで言うと、バースストライカーたちも熱心に、自分は産まない活動をしているけれど、他人には決して薦めないと話してくれる。女性の出産はこれまでもずっと国家に管理され、政治に利用されてきた。出産の選択を女性自身の手に委ねること、それはフェミニズムが勝ち取ってきた功績であるはずだ。
「私はいま十分過ぎるぐらい幸せなんです。変化するのが怖いのかもしれないですね。夫もすばらしい人で、この二人でこのまま生きていけるなら幸せだなと思っていて。これが例えば、私が子どもを持って持病が悪化して、私の持病だと悪くなると手足が動かなかったり目が見えなくなったりするかもしれないというリスクがあって、私がどこか不自由になったらどうなるかとか、子育てでお互いにストレスがたまって二人の関係性が変わったら? とか、そんな不確定要素にかけるなら、いまの二人の幸せな関係が続いたほうがいいのではと思ってしまうんです」
高校の図書館でパレスチナの少女の死を目にしてから宮田さんはまっすぐとジャーナリズムの道を歩き、いまは気候変動を改善すべく尽力している。子どもを持つか持たないかの選択は、そんな宮田さんにとっても迷い、ゆらぎ、さまざまな理由が混線したなかでの発火地点という印象をもった。
たぶん普通の人よりも地球の危機を現実的にリアルに感じていることも大きいだろう。ご自分の病気のリスクもある。子どものこれからの人生に責任を取れるのかという命題は、私自身痛みをともなって受けとった。リスクがあまりにあるのだったら、いまの自分が選びとった幸せを、なるべく温存しておこう。そう感じる宮田さんと、最後はエゴの話になったが、それは次の章で考えていくことにしよう。
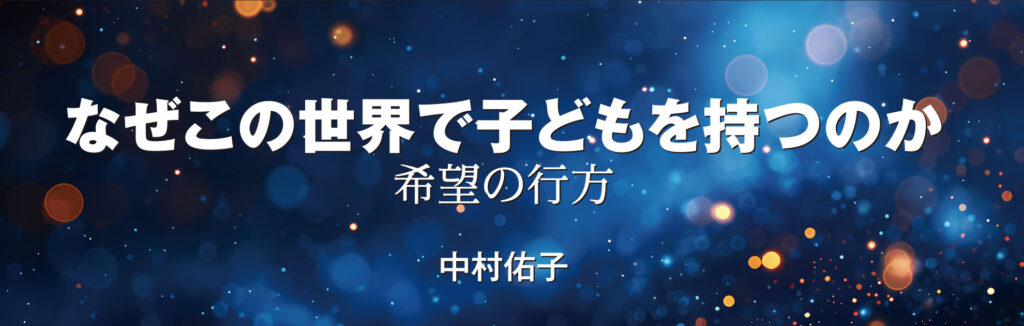
世界各地で起きる自然災害、忍び寄る戦争の気配やテロの恐怖、どんどん拡がる経済格差、あちこちに散らばる差別と偏見……。明るい未来を描きにくいこの世界では、子どもを持つ選択をしなかった方も、子どもを持つ選択をした方も、それぞれに逡巡や躊躇、ためらいがあるだろう。様々な選択をした方々のインタビューを交え、世界の動向や考え方を紹介する。
プロフィール
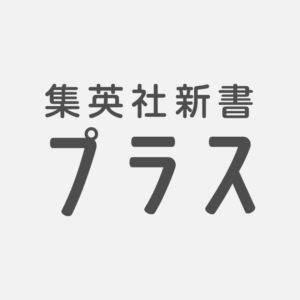
1977年東京都生まれ。作家、映像作家。立教大学現代心理学部映像身体学科兼任講師。哲学書房にて編集者を経たのち、2005年よりテレビマンユニオンに参加。映画作品に『はじまりの記憶 杉本博司』『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』が、著書に『マザリング 性別を超えて<他者>をケアする』『わたしが誰かわからない ヤングケアラーを探す旅』がある。


 中村佑子
中村佑子




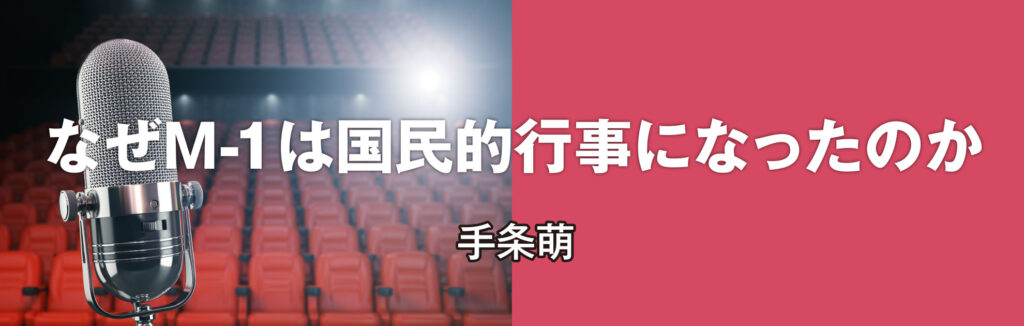







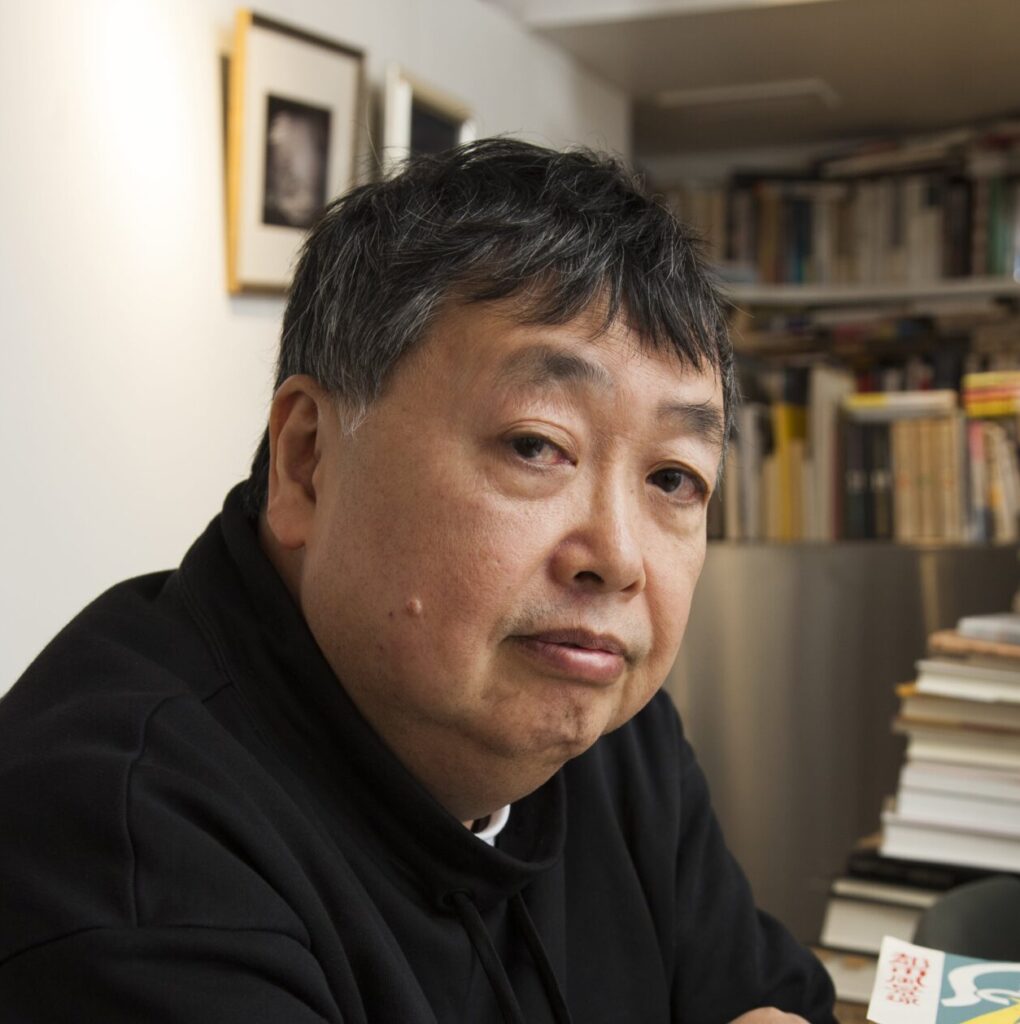
 大塚英志
大塚英志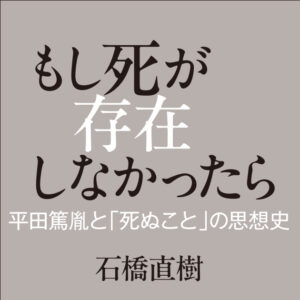
 石橋直樹
石橋直樹