被爆者の子どもとしてうまれた「被爆二世」が、どのように戦後を生き抜いてきたかを見つめる本連載。「戦後史」のシリーズでは、文献を中心に社会の変遷を辿っていく。
前回伝えた通り、戦後まもなく誕生した被爆二世たちに対しては、まず「調査対象」として関心の目が向けられた。原爆傷害調査委員会(ABCC)は新生児7万人以上を診察し、出生時の障害などについて調べた。それは、親である被爆者たちの苦悩を深め、「あの日」を直接は知らない子どもたちにも原爆の重たい影を背負わせることとなった。
「原爆は遺伝する」――未知なる兵器への恐怖と不安が広がる中で、次世代への影響の有無は社会的な関心事となっていく。
高まる遺伝的影響への関心
遺伝的影響に対する関心は、戦後の早い時期から高かった。被爆地・広島に本社を置く『中国新聞』をめくっていると、原爆の影響がどこまで及ぶのか、その不安が広がっていたことが伝わってくる。
例えば1947年3月28日付の朝刊には、「數名の畸形児誕生 米國で原爆被害其後の研究 女より男の死者が多い」との記事が掲載されている。記事では、生存者の「不妊」の可能性にも言及しつつも、「但し原子爆弾が直接の原因であるとの確認はまだ」であるとした。
さらに、同年6月8日付の朝刊では、現地調査のために来日していた「原子弾災害調査委員会」のシールズ・ウォレン海軍大佐らの言葉として、「遺傳的特徴は第二世に傳えられる可能性がある」と、より踏み込んだ内容を載せていた。
ABCCの後身で、原爆被爆者の健康影響について調べる放射線影響研究所(放影研)は、要覧(2025年4月改訂)で、「親の放射線被曝により被爆二世における異常が増加した可能性を示す証拠は得られていない」と記している。一方で、「結論を求めるのは時期尚早」「今後長期の追跡調査が必要」と調査を続ける必要性にも言及しており、ゲノム解析の実施を検討していることからも「結論はまだ出せない」、というのが実際のところであろう。
慎重な文言が並ぶ放影研の見解と比較して、先に紹介した1947年の『中国新聞』記事は、より積極的に遺伝的影響について示唆するものだ。これに対して1951年に4月14日には、専門家による見解を、より詳細に伝える記事が掲載された。
それはショウジョウバエの研究でノーベル生理学・医学賞を受けたハーマン・マラー氏が、広島のABCCで臨んだ会見について報じたものだった。彼はショウジョウバエにエックス線を照射すると、突然変異が誘発されることを発見した遺伝学者だ。
記事には、「子孫に影響なし」という大見出しのそばに、「ミューラー博士 廣島で語る 原爆と遺傳」とある。続く本文は、「ウラニウム放射能の影響で突然変異が生ずるということは疑いの余地がないことだが、それがどの程度かは今後の深い研究によらねば判らない」と、慎重な一文から始まる。
読み進めていくと、「広島市民の場合、著しい変異があるとは認められないが、ある程度の遺伝的変異があることはいえるだろう」と指摘。とはいえ、「遺伝的影響が残っていてもこれは小さいので見分けにくい」と、消極的な評価を述べていた。
一方で1956年5月2日付『朝日新聞』朝刊には、マラー氏の論文要旨が掲載されており、より踏み込んだ見解が紹介されている。ここでは、「遺伝学をあまり知らない人々は、広島や長崎で生き残った人々に生まれたこどもが正常に見えるからといって、原爆による遺伝的障害がとるに足らないものだとするものもあるが、それは(中略)誤りだ」と指摘。そして、「一定の線量によって後代の子孫にひき起こされる遺伝的障害は、バク(曝)斜を受けた本人に起す障害よりもはるかに大きいものである」と、警鐘を鳴らしていた。
『中国新聞』と『朝日新聞』とでは、伝え方にギャップがある。この論文要旨は、マラー氏がジュネーブ会議で発表しようとしたが、アメリカ原子力委員会の中で問題となり、公表が見送られたという逸話もある。
ソ連との核開発競争は激化し、核実験によるフォールアウトの影響が取り沙汰されている時期でもあった。遺伝的影響というトピックは、被爆地だけでなく、国際的にもますますセンシティブな話題となっていたのだろう。
国会でも議論されるイシューに
各紙をめくっていると、『中国新聞』と比較して全国紙の方が、子どもの異常と原爆を関連付けた記事が目に留まりやすかった。「日本における原子爆弾の犠牲者たちの子孫に肉体的奇形が発生するおそれがある」(1947年3月28日付『読売新聞』朝刊)、「遺伝的原爆症の疑い」「広島市で生後わずか二カ月の赤ん坊に原爆症の疑いがもたれ、このほど広島赤十字病院に入院した」(1955年8月11日付『朝日新聞』朝刊)などである。
次世代に影響はあるのか否か。さまざまな見方を伝える報道が飛び交う中で、市民は不安を深めていったに違いない。これ自体が原爆による被害であり、恐怖による支配だと私の目には映る。
1957年3月25日には、国会でも「被爆二世」について議論された。『広島市原爆被爆者援護行政史』によると、審議される対象となったのはこの日が初めてだという。
被爆者健康手帳の交付などを定めた「原爆医療法」について審議する、衆議院社会労働委員会において取り上げられた。八木一男議員が、手帳の交付対象となる「胎児」、つまり胎内被爆者が、いつの時点で受胎した子を指すのかと問うたのに対して、山口正義政府委員が答えている。
答弁によると「胎児」とは、広島、長崎に原爆が投下された当時、すでに受胎をしていた人を対象とし、「第二代目」――つまり、被爆二世は想定していないとしている。遺伝的影響については学会でも議論されているが、「今までのところは、むしろ第二代目については消極的な意見が割合よけい出ておりました」として、被爆二世への手帳交付は否定している。しかし、「遺伝学的にいろいろ今後検討されまして、そういうものも当然考えなければならないということになって参りますれば、当然対象の中に入れていかなければならない。これは今後の学界、特に遺伝の専門家の方々の御意見の推移を見守っていきたいと考えております」とも付け加えていた。
この政府答弁があった直後の4月1日には、日本遺伝学会と日本人類遺伝学会が共同で、「人類におよぼす放射線の遺伝的影響についての見解」を発表。両学会は、「子孫におよぼす遺伝的な影響を考えれば、どの程度以下の照射量ならば遺伝的障害はおこらないというような限界があるとは、理論的にはいえない」とした上で、「広範囲に大気や水の中の放射能を増す原水爆実験などについては、その人類にあたえる遺伝的悪影響を充分警戒する必要がある」と、警鐘を鳴らしていたのである。
政府委員は、専門家による「御意見の推移」を見守っていきたいと述べていた。しかし、今日にいたるまで、被爆二世に対しては無料の健康診断が実施されているばかりで、医療保障を伴う「援護」は実現していない。
先の国会で、質問に立った八木委員はこうも述べていた。
現にその後に受胎した胎児で、白血病になって非常に苦しんで死亡した実例を私どもは知っております。学説というものは、ほんとうに定説になるまでに時間がかかりますけれども、病気で苦しみ死んでいく人たちはそういう時間の余裕がございません。政治というものは社会生活の中に生きているものでございます。ある学説がほんとうに完全な定説になるまでの間に、どんどん死亡する被爆後に受胎した胎児がいるわけでございますから、その点は学説のみの根拠じゃなしに、政治を担当し、行政を担当しておられる省で、そういう態度で、それが含まれるようにしていただかなければいけないと思うのです。
彼の意に反して、政府の対応は半世紀以上を経た今も変わっていない。「科学的調査の推移を見守る」という言い分も、あの頃のままだ。
変わらない「援護」を巡る状況に対して、核を巡る情勢は刻々と、人類に危機をもたらす方向へ変わってゆく。もはや遺伝的影響への不安は、原爆の被害者だけに留まるものではなかった。議論すべきイシューとしての地位が確立されてゆく。
増加する「白血病」や「病死」の記事
そして1960年代に入り、年長の被爆二世たちが青春を謳歌する年頃になると、「白血病」や「病死」と関連付けて報じる記事が増加する。
「〝被爆二世〟の女高生 白血病で死ぬ」
「16歳の誕生日前に――被爆二世死ぬ」
「長崎で被爆二世 死亡 ことし三人目 原因は白血病」
上から順に、1969年6月20日付『中国新聞』、1971年10月11日付『長崎新聞』、1972年9月17日付『長崎新聞』が掲載した記事の見出しである。
いずれの記事でも亡くなった「被爆二世」の実名と親の被爆状況、そして顔写真が付されている。時代背景の違いもあるとは思うが、近年は「被爆二世」の訃報を掲載することはまずないし、あまりに詳細な報道にややたじろぐ。
戦後まもなくうまれた被爆二世たちも、10~20代の青年期にさしかかっていた。遺伝的影響が不安視されていた社会情勢の中、病気で、ましてや多くの被爆者も苦しんだ白血病で亡くなる被爆二世が相次いだことが、世間の耳目を集めたのだろう。
『広島市原爆被爆者援護行政史』には、次のように記されている。
「被爆二世、三世が世間の注目を集め始めたのは、昭和43(1968)年~44年ごろ、被爆二世の白血病による死亡者が相次ぎ、大きな社会問題となったことに起因する」
広島では、白血病により7歳で生涯を閉じた被爆二世の少年について書いた『ぼく生きたかった 被爆二世 史樹ちゃんの死』(竹内淑郎・編、宇野書店)も1968年に出版された。健康不安とともに生きる被爆二世、そしてその親たちの苦悩を知らしめる一冊となった。
「16歳の誕生日前に――被爆二世死ぬ」との見出しをつけた『長崎新聞』の記事は、中学3年生の青年が悪性リンパ腫のため死去したことを伝えている。記事は、彼の両親がともに被爆者であることに触れ、「〝被爆二世〟問題を社会に投げかけた」と指摘する。
『被爆二世 その語られなかった日々と明日』(深川宗俊・監修、広島記者団被爆二世刊行委員会・編、時事通信社、1972年)によると、長崎では翌1972年2月にも、18歳だった「被爆二世」の男性が闘病の末に亡くなった。
2人の訃報は、長崎において「被爆二世」問題がクローズアップされる契機となる。同年3月には「長崎青年と被爆二世の会」が結成され、被爆二世の生活と健康に対する保障を求める運動が始まった。
彼らの親たちは、どんな気持ちだったのだろうか。「長崎青年と被爆二世の会」が1973年に発行した冊子を開いた。ちなみに、こういった被爆二世の運動に関する資料は散逸していて、公文書館はもちろんのこと、関係者や運動団体に問い合わせて見つけることができた。
冊子は、亡くなった2人の被爆二世について取り上げ、その両親の言葉を紹介していた。
「マスコミでは二世二世とさわいでいるけれど、何の対策もたてられていないのでただされぐ(筆者註:ママ)だけで終っている。私の子供が死んだ時点で対策がたてられていれば、後の二世の方達は亡くならなかったかも知れない」
「治療対策のために息子の解剖を許しました。新聞に公表したのも、被爆二世の救済のため、運動の発展のために行いました」
共通しているのは、被爆二世を支える施策を求めていることだ。10代で旅立ったわが子の死を、未来につなげてほしいと願っている。もう、同じように犠牲になる「被爆二世」が出ないことを望んでいるのだ。センセーショナルに伝えるだけの報道に対する厳しい視線も、受け止めなければならない。特に、彼らが「被爆二世」であることと、抱えていた病気やその死について、簡単に結び付けてよいとは思わない。被爆二世の訃報を掲載していた1960~1970年代の新聞報道については、検討が必要だ。
ただし、幼い「被爆二世の死」は社会に衝撃を与え、「被爆二世」問題があることを投げかけた。それは、その後の親世代の動き、そして被爆二世自らが立ち上がることにもつながっていく。
(次回は12月4日更新予定です)

広島・長崎に投下された原子爆弾の被害者を親にもつ「被爆二世」。彼らの存在は人間が原爆を生き延び、命をつなげた証でもある。終戦から80年を目前とする今、その一人ひとりの話に耳を傾け、被爆二世“自身”が生きた戦後に焦点をあてる。気鋭のジャーナリスト、小山美砂による渾身の最新ルポ!
プロフィール

ジャーナリスト
1994年生まれ。2017年、毎日新聞に入社し、希望した広島支局へ配属。被爆者や原発関連訴訟の他、2019年以降は原爆投下後に降った「黒い雨」に関する取材に注力した。2022年7月、「黒い雨被爆者」が切り捨てられてきた戦後を記録したノンフィクション『「黒い雨」訴訟』(集英社新書)を刊行し、優れたジャーナリズム作品を顕彰する第66回JCJ賞を受賞した。大阪社会部を経て、2023年からフリー。広島を拠点に、原爆被害の取材を続けている。


 小山 美砂(こやま みさ)
小山 美砂(こやま みさ)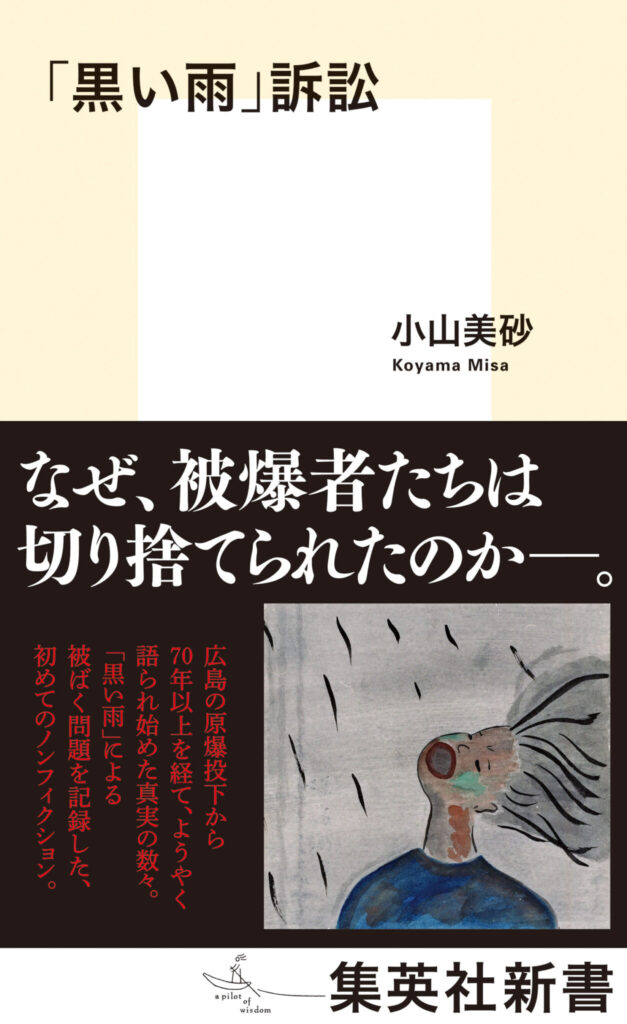









 藤原辰史×青木 理
藤原辰史×青木 理



