少子高齢化、結婚の減少、若者の自殺の増加と密接にかかわっているのが「孤独問題」だ。警視庁の調べによると、昨年度の孤独死は7万6千人を超えた。年齢別にみると、20代では780人、30代では1013人、40代は2557人、50代は7547人、60代は13705人、70代以降は50198人となる。年齢があがるごとに増加傾向であるが、決して高齢者だけの問題ではない。
物理的に孤立しているわけではないにもかかわらず、ひとりぼっちだと感じてしまう。この“生きづらさ”や“居心地の悪さ”の正体とは何か。人類学の視点で日本人の孤独を分析した『孤独社会: 現代日本の〈つながり〉と〈孤立〉の人類学』の著者が「孤独社会」(Lonely Society)ニッポンの問題を分析する。
「孤独は肥満や1日15本の喫煙よりも健康に悪い」
米国のビベック・マーシー元公衆衛生長官が「孤独は肥満や1日15本の喫煙よりも健康に悪い」と指摘したのは、記憶に新しいことと思う。新型コロナウィルスのパンデミックは孤独を世界的な懸念の的へと押し上げた。
高齢化、少子化、結婚の減少といった課題を抱える日本は、全世帯のうち単身世帯が最多で全体の34%を占め、孤独問題に直面している。その深刻さは近年、国が対策として孤独・孤立対策推進法を制定したことからも明らかだ。
そこで、医療人類学者として、日米両国で孤独を研究した者として、この問題への解決に資する2つの視点を提案したい。
よい「孤独」とわるい「孤独」の正体
第1の視点は、孤独問題、対策について考える際、日本語の「孤独」という言葉と英語の「ロンリネス」の意味することの違いを明確にすることである。
欧米の孤独研究では、「客観的に一人でいる状態:ソリチュード(Solitude)」と「主観的に寂しいと感じる苦痛:ロンリネス(Loneliness)」を区別することが効果的な政策の絶対的な基盤だとされる。前者は思索や創造性のために不可欠な時間でありうるが、後者は心身をむしばむ社会的な病である。しかし、日本の公論の中心にある「孤独」という言葉は、この2つの意味を曖昧に含んでいる。
昨年爆発的なヒットとなったガブリエル・ガルシア=マルケスの『百年の孤独』 は、スペイン語(原文)では“Cien Años de Soledad”、英語では“One Hundred Years of Solitude”だ。
この作品ではソリチュードという言葉が使用されているが、この意味を正確に表す日本語がない。そのため、最も意味が近い「孤独」と訳されているわけだが、そのせいでロンリネスが持つようなネガティブな印象を持つ人もでてくるかもしれないのだ。
このように、「孤独」をめぐる言語の問題を整理しなければ、政策の焦点もぼやけてしまう。つまり、「孤独」対策が、豊かさの源泉であるはずのソリチュードまでも否定しかねないという、深刻なパラドックスを生むのだ。近年、「孤独」の重要性を擁護する本が登場しているのもそのためだろう。 故に政策の対象が単なる孤立ではなく苦痛なのだと示すために「望まない孤独」を減らすのだと明確に言語化しなければならない。さらに、自ら選ぶ豊かな一人時間を単なる「孤独」ではなく「択独」という新しい言葉で積極的に肯定するなど革新的なアプローチも必要だ。
「共感」教育が孤独を抜け出すヒント
第2の視点として、孤独の問題は、個人の内面世界(ミクロ)、家族や地域社会といった共同体(メソ)、そして経済や国家の構造・政策(マクロ)という3つのレベルで同時に取り組む必要がある。では、この多層的なアプローチは、具体的にどのようなものだろうか。
近著『孤独社会』(青土社)でも論じたが、マクロレベルの都市計画からメソレベルのコミュニティーセンターまで、各レベルで個別の政策やプログラムを設計する必要がある中で最も不可欠なのは、「共感」を育む教育である。
例えばアメリカの非営利団体CASELによって提唱された社会的・情動的学習(SEL)は知能指数のような認知能力だけでなく、協調性、共感性、意欲、感情のコントロールといった「非認知能力」を育むことを目指す。
SELを通じて、子どもたちに孤独は誰もが経験しうるもので恐れることはなく、それには解決法があると教えてあげることは大切だ。そして、その方法とは信頼と理解に基づく深い繋がりを学ぶことで得られる「親密さ」であり、そういった価値観を学習できる意義は大きい。
これは、マクロレベルつまり政策決定者による社会的・情動的学習への支援によって、学校教育におけるメソレベルの介入ができ、それがより繋がりのある社会を築くために必要なミクロレベルのスキルを個々人に育むことができるという好例である。
孤独は社会の問題であるという認識
ここに日本の強みが存在する。日本社会は、メソとマクロの視点を重視する素地を持っている。心理的問題を個人の内面に還元しがちな米国の個人主義的アプローチとは対照的で、日本は「孤独は社会的問題である」という認識があり、孤独死をはじめ孤独問題の解決策は行政的かつ社会的なものでなければならないと理解している。
日本は今、歴史的な好機にある。日本が本来持つ社会的な視点(メソ・マクロ)を世界標準の分析ツール――ソリチュードとロンリネスの区別、そしてミクロの視点――と統合することで、日本は孤独対策において世界で先進的な新たな解決法のモデルを提示できるのではないか。
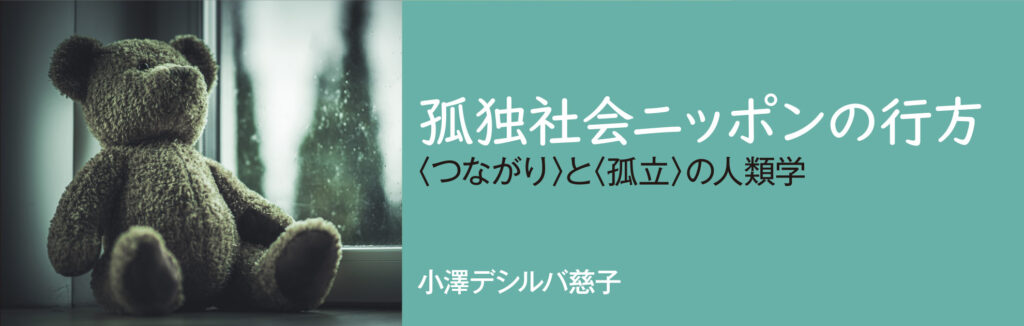
物理的に孤立しているわけではないにもかかわらず、ひとりぼっちだと感じてしまう。この“生きづらさ”や“居心地の悪さ”の正体とは何か。孤独を単に個人問題にとどまらず社会問題として扱い、いかに社会的な条件が人々を孤独へ向かわせているかについて人類学の視点で分析した『孤独社会: 現代日本の〈つながり〉と〈孤立〉の人類学』の著者が「孤独社会」(Lonely Society)ニッポンの問題を分析する。
プロフィール

(おざわ でしるば ちかこ)
医療人類学者。上智大学を卒業後、エセックス大学で文化社会学の修士号、オックスフォード大学で文化人類学の博士号を取得。ハーバード大学社会医学部客員研究員、シカゴ大学博士研究員、エモリー大学人類学部教授を経て、現在は当大学ロシアおよび東アジア言語文化学科教授。著書に“Psychotherapy and Religion in Japan: The Japanese Introspection Practice of Naikan”や“The Anatomy of Loneliness: Suicide, Social Connection and the Search for Relational Meaning in Contemporary Japan”、『孤独社会: 現代日本の〈つながり〉と〈孤立〉の人類学』(青土社)などがある。専門は医療人類学、社会人類学、日本研究。


 小澤デシルバ慈子
小澤デシルバ慈子








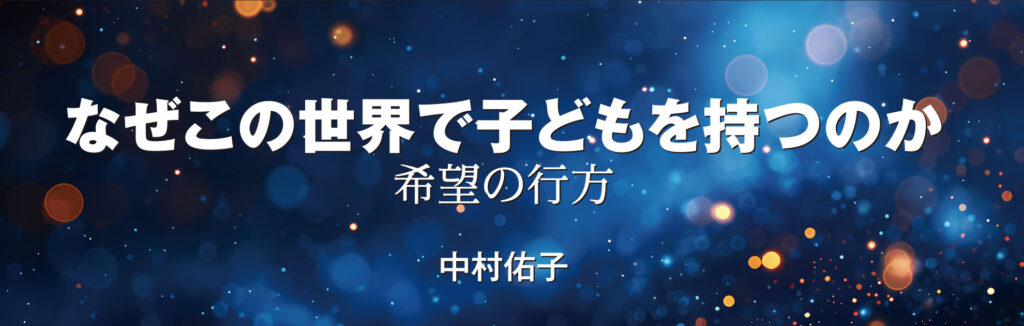

 内田 樹×青木 理
内田 樹×青木 理



