1.『キャプテン翼』が見せた夢
『キャプテン翼』と野球からサッカーへ
前回は山一證券に象徴される日本的な集団の限界を読み解いていった。今回は「個人」という単位が自覚された時代として、1980年代を見ていこうと思う。
1975年生まれの小説家、平野啓一郎は、自らが幼少期を過ごした80年代の記憶について問われた際「『キャプテン翼』を読んでいた」と答えていた。
平野 たとえば、小学三年くらいから『キャプテン翼』(連載一九八一~八八年)が突然流行ったことです。それまでは野球が圧倒的でしたが、ある日、いつものようにグローブとバットを持ってグラウンドに行ったら、皆がサッカーをしていた(笑)。でも、僕はその時、サッカーが流行るのはわかる気がしたんです。僕は父親を早くに亡くしていますが、野球はどうやったってひとりで上手くなりようがない。キャッチボールもノックも、ひとりではできない。野球マンガって基本的に、父と息子の物語なんでよ。斎藤 『巨人の星』からしてそうですね。
平野 そう、『キャプテン』とか。プロ野球選手でも、松井とかイチローとか、父親の存在感、大きいでしょう?だけどサッカーは、ひとりでも上手くなりようがある。ドリブルとかリフティングとか。野球大会に行くと、父親が熱心な子が上手いに決まっているんですよ。だけどサッカーやバスケがストリートでやられて、貧困国や貧困地域で愛されるのは、友達同士で上手くなれるからじゃないですかね。
斎藤 なるほどね、ものすごく腑に落ちた。
平野 あの時代は、父親たちがサッカーをやってきた世代ではないので、皆が同一線上だった。それはすごく解放感があったんです。『キャプテン翼』だって、父親じゃなくて、ロベルトというブラジル人が主人公に教えるという設定。これもサッカーというスポーツの本質を突いている気がします。(斎藤美奈子・成田龍一編『1980年代』河出書房新社、2016年)
斎藤 そうか。野球はやっぱり昭和のものなんだね。Jリーグができるのが一九九三年ですから、八〇年代にサッカー少年がマスとして生まれていたということですね。
『巨人の星』は部活と家族が連動して語られるが、『キャプテン翼』は部活と友情が連動したものになっている。――平野の指摘は非常に興味深い。野球とは親子のスポーツだが、サッカーとは友情のスポーツである。そのような図式はもちろん大雑把ではあるが、案外的を射ているかもしれない。文芸評論家の斎藤美奈子はその言葉を受けて、野球は昭和のもの、サッカーは平成のものではないかと語る。
実際、『キャプテン翼』は、『巨人の星』的世界観へのアンチテーゼを突き付ける。それまで日本の伝統的な部活観――先輩や親への礼儀を重視する「タテ社会」であることと、精神面を鍛えることで身体的能力も向上すると考える「根性重視」であることの双方を規律に組み込むこと――を『巨人の星』は重視していた[1]。が、『キャプテン翼』はそのような価値観を描かない。実際、主人公の翼は、繰り返し「ボールはともだち」であると強調する。つまりサッカーを友達のようにずっと楽しむことが重要であり、そこには『巨人の星』的な、苦しみつつスポーツと向き合う様子へのアンチテーゼが見える。
そしてなにより『キャプテン翼』では、サッカーとは監督の指示や規律にとらわれないスポーツであることが強調される。たとえば指導者であるロベルトから、翼は「監督の指示は無視したほうがうまくいくこともある」という助言を受ける。
「おれもよく監督の指示を無視したことがあったがな」
(高橋陽一『キャプテン翼』第一巻、集英社)
「え?」
「そしてそれが監督のたてた作戦よりうまくいったこともある 今回の翼みたいにな
翼! サッカーは自分の考えでプレイするスポーツだ! これからも自分の判断は大切にしていいんだぞ!」
サッカーは自分の想像力を活かし、自分でコートを縦横無尽に駆け巡るスポーツである。それは、攻守や自分のターンがはっきりと決まっている野球とは違う。
『巨人の星』は野球を、親や監督とのタテ関係の規律のなかで描き出した。一方、『キャプテン翼』はサッカーを、友達とのヨコ関係の自由のなかに位置させる。
1980年代には『キャプテン翼』の影響で、十代のサッカー人口は増えた[2]と言われており、[3]少年団加入者数にいたっては野球とサッカーの数が、逆転したという。[4]
昭和から平成の転換点のなかで、サッチャリズムやレーガノミクスによって新自由主義経済が始まりつつあり、その狭間をすり抜けるかのようにマンガやアニメやゲームといったサブカルチャーが興隆した。人々の話題は、文芸や政治といった重さ=権威が重視されたものから、サブカルチャーや株式投資といった軽さ=自由が重視されたものに徐々に移っていった。そのなかにおいて、サッカーという異国からやってきた自由を表象するスポーツは、野球という日本の規律意識を表象するスポーツと対比されるくらいの存在感を得はじめていた。
もっとも日本における本格的なサッカーブームは、Jリーグがスタートした1993年まで待たなくてはいけない。1990年代になると、民放のゴールデンタイムでJリーグ試合が中継されるようになる。[5]
が、1980年代、たしかに『キャプテン翼』は、日本のスポーツ少年たちに、新しい自由な風を持ち込んだことはたしかだろう。
『キャプテン翼』のやおい文化ブーム
『キャプテン翼』は少年たちにサッカーを流行させた。実は同作は、もうひとつ重要な流行の発生源でもあった。
それは、少女たちにBLと二次創作の萌芽となったことである。
1980年代後半のコミックマーケット、いわゆるコミケの同人誌文化の流行を、「やおい」と呼ばれる男性同士の恋愛を描いた二次創作作品に変化させたのが、『キャプテン翼』の二次創作だった。[6]たしかに批評家の大塚英志も、『キャプテン翼』を、男性同士の恋愛を見出して二次創作する同人誌ジャンル〈やおい本〉の代表として語る。[7]
そしてこのコミケにおける「やおい」ジャンルの興隆は、現在の「BL」と呼ばれるジャンルへ接続する。[8]そして2010年代、かつての少女漫画読者が「BL」を読むこともあるという。[9]
つまり、男性同士の恋愛を描いた「やおい」の二次創作ジャンルとは、いわゆる少女漫画――商業少女漫画誌に掲載されている漫画――とは異なるジャンルとして誕生し、それでいて読者を一部被らせながら生き延びていた、ということである。
『キャプテン翼』の二次創作に代表されるような「やおい」という二次創作。それはある意味で、少女漫画という「結婚」や「家族」からの磁場にどうしても行きついてしまう少女たちが見つけた、少年たちの身体をもって、親がいない、家族ではない形の居場所――コミケや同人誌をつくる彼女たち自身でもある――を見つけるひとつの手段だった。そう言えるのではないか。
少女漫画は結婚や家族といった主題と切っても切り離せないジャンルである。[10]もちろん結婚や家族を扱わない漫画も大量にあり、少年が主人公になる漫画も大量にある。しかしそれは主人公が「結婚していない状態」によって規定される状態――もちろん性別は少女であったり少年だったりする――を描いている、という点において、結婚や親という価値観の磁場の内部にある。
しかし、男性同士の恋愛を描くとき、作品内に結婚の磁場を登場させず、恋愛(性愛)のみを取り出して描くことができる。そこには親は登場しないことがあり得る。なぜなら読み手や書き手の女性にとって、彼らは彼らのなかで独立した関係性を見出すことができるからだ。[11]
親がいない、家族ではない関係性のなかに、居場所が誕生する。
その先にあるのが、女性のオタク文化でもあった。
おたくの誕生
1980年代、『キャプテン翼』の影響でサッカーに燃える少年と男性同士の恋愛に萌える少女が生まれた傍らで、世間はアニメやマンガのキャラクターに萌える男性たちのことを「オタク(おたく)」と呼ぶようになった。
「オタク」という言葉は、いまや1980年代のイメージから遠く離れ、「推し活」マーケティングの担い手として日本活性化のエネルギーとまで言われている。[12]
1980年代とはサブカルチャーの時代だと言われるが、いまや「サブカル」よりも「オタク」のほうがメジャーな言葉になっていることは確かであろう。
ちなみに批評家の大塚英志は、「サブカル」と「おたく」の世代差を以下のように説明する。
サブカル=全共闘世代
おたく=全共闘世代より一世代下の、ガンダム以降の世代
つまり、六十年安保と七十年前後の全共闘運動に挫折した人々が、日本のサブカルチャーの担い手となる。それは1985年に徳間書店から独立しジブリを立ち上げた鈴木敏夫であり、洋楽中心の音楽誌「rockin’on」から派生した日本のロック雑誌「ROCKIN‘ON JAPAN」を1986年に創刊した渋谷陽一でもあった。
そして、それよりひとつ下の世代は、おたく文化の担い手になってゆく。そのなかに『キャプテン翼』で、家族も結婚も出てこない、同人誌を作成した女の子たちがいたことは、言うまでもない。
『キャプテン翼』は、家族という共同体から抜け出しながら、友人同士でサッカーをしたり同人誌を出したりする少年少女の起点となる。それは大塚の指摘通り、全共闘世代的価値観からの脱出でもあった。
2.共同体アンチテーゼとしての百貨店とディズニーランド
1983年という衝撃
1983年、『キャプテン翼』アニメ第1話が放送された。最高視聴率は21.2%。まさにその後コミケに同人誌を出す女子たちが『キャプテン翼』を知ることになるきっかけのひとつだった。
実は1983年とは、「オタク」という名付けがなされた年でもあった。
命名者は、中森明夫。「お宅族」「オタッキー」「オタッカー」などと言われていた人々を、「オタク」と呼んだのが彼だった。[13]
今ではすっかり広がったこの言葉だが、案外40年ちょっとの歴史しかない語彙なのである。
そう考えると不思議な気持ちにはなるが、実は1983年に登場したものはほかにもある。
たとえば、東京ディズニーランド。開園したのは1983年。アメリカ国外では初となる「ディズニー・テーマパーク」だった。
あるいは、ファミコン。据え置き型ゲーム機「ファミリーコンピュータ」を発売したのが1983年である。ちなみにその後、1983年内に任天堂は東京証券取引所市場第一部に株式上場している。2年後に生まれたマリオは世界でもっとも売れたゲームとなった。
あるいは、26歳の浅田彰が『構造と力』(勁草書房)を刊行したのもこの年である。ちなみに前年の1982年には、上野千鶴子による鮮烈なデビュー作『セクシィ・ギャルの大研究』(河童ブックス)が刊行されている。
前年に引き続き、糸井重里によるコピー「おいしい生活」が西武百貨店において用いられ、この言葉が定着しはじめたのも1983年。
ちなみに、無印良品の一号店が開店されたのも1983年である。ちなみにユニクロの一号店の開店は1984年である。
――どれも、1983年の出来事だ。
その多くが2025年現在も影響力を持ち続けるコンテンツであり、日本の文化の輪郭が生まれたのはここだったのではないか、と思ってしまう。
ディズニーランドと百貨店
「おいしい生活」という言葉に代表されるような西武文化をつくりあげた堤清二は、作家名・辻井喬として上野千鶴子と対談した書籍を刊行している。本書において、辻井(堤)は、「百貨店の競合はディズニーランド」と語っていたことを指摘されている。
辻井さんはかつて百貨店の競合相手はディズニーランドだとおっしゃったことがありましたが、テーマパークとしての百貨店を考えた場合、スペース・コミュニケーションとして人に出会うというのは、匿名性の高い集団にハレ着を着た私を見てもらう、ということですね。私は「ステージとしての百貨店」(「(私)探しゲーム』筑摩書房・一九八七年)という論文のなかで、それを支持する説を書きましたが、その後、ハレのステージは、ホテルやレストラン、劇場など選択肢が拡がりました。
それだけでなく、コミュニケーション・モードが変わってきました。この点では、宮台真司さんの「島宇宙化」がとても当たっていると思うのは、もはや人は匿名性の高い集団ではなくて、内輪の気心の知れた人たちとの間でコードを共有したコミュニケーションしか望まなくなっている点です。あらかじめ知っている人たちとの間で、同調性の高いコミュニケーションしかしない傾向が強まっています。(辻井喬・上野千鶴子『ポスト消費社会のゆくえ』文春新書、2008年)
今日、百貨店が成り立たなくなっている状況は、新聞や総合雑誌の凋落現象と同じ。コミュニケーション媒体それ自体のセグメンテーションが起きてきて、隅発性の高いノイズはシャットアウトする。つまり、人は自分が聞きたい情報しか聞かなくなっているのです。この現象はアメリカが先行し、日本が追随しています。そうなると、ますます「万人のための」とか、「総中流社会の」という百貨店の社会的な基盤そのものが、急速に消滅してくると思えます。
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』では「書籍はノイズが多い」という指摘をしたが、すでにここで上野がノイズという表現を使っていたことに驚いてしまう。それはそれとして、百貨店もまたノイズが多い場として語られている。
では、なぜ百貨店は1980年代にあったような影響力を失ったのに対し、ディズニーランドは今もなお人々のハレの場であり続けているのだろうか?
それは、ディズニーランドが「あらかじめ知っている人たち」が「あらかじめ体験できることがわかっている体験」をするために行く場であり続けているからではないか。つまりディズニーランドにノイズはない。ディズニーが提供するキャラクターたちも、アトラクションも、すでに知っているものである。しかし知っているものを、知っている通り、クオリティ高く提供してくれる。
さらに、ディズニーランドは、家族で行く場でありながら、家族みんなが子どもになることができる場でもある。
というのも、ディズニーランド開園当時、「弁当持ち込み」というルールが話題になったという。[14]母親のつくった弁当を持ち込むことの何がいけないのか、と当時は批判されたらしい。が、いまとなっては慧眼というほかない。ディズニーランドとは、みんなが平等に虚構の世界に入り込むからこそ、現実の役割が関係ない場になり得ている。もちろん親が子の面倒を見る場でもあるが、それでもディズニーランドに入ってしまえば、虚構のなかの一部になり得る。ディズニーランドに一度入れば、私たちはその世界の一部を作り上げるキャラクターになり、匿名性を手に入れる。
かたや、百貨店は「客」としてさまざまな商品に出会う場所であるが、「紳士服」「婦人服」「子供服」とあるように、年齢と性別によって売り場が区切られているし、そこで販売されている商品は当然入れ替わる。さらに、百貨店という空間では匿名性を手に入れられるのものの、それはあくまでも自分の現実での役割を意識したままハレの場に向かわなくてはいけない。
つまり、百貨店がディズニーランドのような場所であり続けられなかったのは、「現実」と「偶然性」に接続されていた場所だったからである。
逆に言えば、百貨店は80年代特有の価値観の象徴でもあった。
『見栄講座』から40年
東京ディズニーランドが開園した1983年、ホイチョイ・プロダクションの『見栄講座』(小学館)という本が刊行された。「どんな平凡な人間でも、ここに書いてあることをすれば、労せずしてだれよりカッコよく見える!」というコンセプトで、フランス料理やスキーや海外旅行や読書を薦める……という本である。うーん若い世代がここまで見栄のためにお金を使える時代。バブルである。
しかしこれらの本を読むと、百貨店が上野の指摘する「匿名性の高い集団にハレ着を着た私を見てもらう」場であった理由がよくわかる。
どう見られるか、とにかく気にする。『見栄講座』を出すきっかけは、「最近の若い人は、スキーをする時も、どう見られるかを気にする」という人がいたからだった、と書かれてある。
いま風にいえば、承認欲求、ということである。
そう、このあたりも「どう見られるか」が若い世代にとって非常に重要になって40年か……という心地になってくる。
いまやSNSの登場によって個人がどう見られるかを考え続ける時代になったと言われるが、SNSがなくても若い世代は他人にどう見られるか考え続けてきたことが、本書を読むとよくわかる。
それはある意味、大学名や会社名や出身地のような、所属する共同体によって自分がどう見られるか決まる時代が、少しずつ変化していたからだろう。
もちろん大学名や会社名や出身地は非常に重要だ。が、それ以上に、たとえば身に着けている服、誘うお店、休日にやっている趣味など、個人に紐づく消費が自分を表現するものになっていった。それこそが消費社会と呼ばれる構造だった。
そう考えると、「どう見られるか」という意識は、個人化した社会の証左なのだった。
アンチ政治的思想共同体としての西武百貨店
『ポスト消費社会のゆくえ』において、辻井や上野は、全共闘の経験から自分たちは「共同体アレルギー」であると語る。
上野 私たちは内ゲバの世代ですから。ほんとの殺し合いが起きた陰惨な時代でした。あさま山荘事件がテレビで実況中継された頃の連合赤軍は、まだラディカリズムとヒロイズムのシンボルだったと思いますが、連合赤軍が妙義山中などで「総括」と称して仲間をリンチして殺害したことが判明してからは、この事件で理想主義を抱えた共同体の地獄を見せつけられた思いでした。
(辻井喬・上野千鶴子『ポスト消費社会のゆくえ』文春新書)
辻井 それならよけい共同体アレルギーが出てきますね。だから理想主義を結集の核にした共同体というものが、いかに怖いかです。われわれの時代はイデオロギーや思想が、どれだけ狂気になるか経験知として体験しています。では、どうしたら日常性のどこで、いかに感性の問題だけで人と繋がれるのか、またそれは理想主義などを待たない共同体なのか、という問いが残りますね。
イデオロギーや思想ではないもので、共同体をつくりだすこと。それはまさに西武百貨店のテーマそのものだった。
このような百貨店の商品に代表されるような時代を、批評家の東浩紀はポストモダンの文脈で語り、「ポストモダンとはイデオロギーの不在状態」であると解説した。[15]
政治的なイデオロギーではなく、商品が無数に存在すること。そしてそれのなかから自分を表現するものにふさわしいもの――『見栄講座』的に言えば、他人から見られてもっとも「見かけがよい」もの――を選ぶこと。それこそが、西武百貨店を支えた時代性だった。
その背後には、たしかに大塚英志が指摘する通り、全共闘に敗北した経験があった。ただしそれは単純に学生運動で革命が起きなかったというだけでなく、「学生運動によって、イデオロギーによって結びついた共同体が内ゲバを起こし、仲間の殺害にまで至ってしまった」という経験の恐怖によるトラウマという意味でもある。
理想主義によって結びつく共同体のトラウマ。それこそが、素敵なものを買うことで繋がり合う、感性の共同体をつくりだすことになる。
それはある面では、政治的イデオロギーを排するコピーライターの時代の話でもあり、さらには「萌え」で繋がり合うオタクの時代の話でもある。
集団的な思想ではなく、個人的な感性でつながること。
正しさではなく、好きなものでつながること。
それこそが1980年代に起こったポストモダンの時代の、オタク時代の幕開けでもあったのである。
3.家族に反抗するヤンキー漫画
ヤンキー漫画の流行
「ボールは友だちだ」と言った大空翼の友だちは、心臓病を持病に持ち、通院を繰り返している。あるいは翼の師匠であるロベルトは、一度は怪我によって自分の命を絶とうとするも、病院に行くために翼の家に居候することになる。『キャプテン翼』は、通院が身近な作品なのである。そのあたりも傷だらけになりながら明らかに体に無理があるトレーニングを遂行する描写が頻発する『巨人の星』へのアンチテーゼとなっている。
『キャプテン翼』が流行した傍ら、同時代にはヤンキー漫画が大流行していた。きうちかずひろ『ビー・バップ・ハイスクール』、𠮷田聡『湘南爆走族』、紡木たく『ホットロード』といったさまざまな作品が、ヤンキーを主人公に据えたのだ。
それまでは「不良」「暴走族」と呼ばれていた彼らを「ヤンキー」と呼ぶようになり、それらの漫画が生まれて流行する。ヤンキーとは「社会階層が低めとみなされがち」「旧来的ジェンダーロールを重視」「自国的、地元的であることを志向する」人々であると言われている。[16]が、一方で1980年代に流行した漫画の主人公の多くは、実家の親からの評価は高くなさそうな、つまり親から困惑されてそうな不良少年少女である。実際、『ホットロード』や『湘南爆走族』には自分を理解してくれない親が登場する。
実際のヤンキーは地元や家族を大切にし、共同体を重視する。しかし一方で、1980年代に流行したヤンキー漫画においては、基本的に自分の生まれ育った家族は疎ましいものとして描かれ、それよりもヤンキー仲間である友だちとの関係を重視する。
もちろんヤンキー仲間の内部で、兄貴がいたり、上下関係が重視はされるのだが、それは現実の家族から抜け出した場所での出来事である。
このような1980年代のヤンキー漫画の流行が、前回で扱った1990年代の『スラムダンク』に繋がる。ちなみに1990年代にはいると、Jリーグ開幕によって生まれたサッカーのサポーターたちのファンダムは、きわめてヤンキー文化的だったことが指摘されている。[17]『キャプテン翼』を読んだサッカー少年たちは、ヤンキー文化の担い手になっていった、のかもしれない。
オタクとヤンキー
1980年代、それはヤンキー漫画が流行し、オタク文化が興隆し、そして百貨店文化の最盛期でもあった。
これらの出自は実は同じところにある。親の否定である。ヤンキーは、親を否定して、喧嘩し反抗した。オタクは、家族や旧来ジェンダー観を否定し、アニメの少女や少年に萌えた。そして百貨店文化を享受できた上京者は、出自ではなく買い物によって自分を表現しようとした。――どれも、旧来的なタテ型共同体の否定のバリエーションだったのである。それこそが『キャプテン翼』と西武百貨店の流行した1980年代的な文化だった。日本の伝統的集団主義へのアンチテーゼがそこにはあった。
『ポスト消費社会のゆくえ』において、辻井は「戦後日本ではずっと共同体アレルギーがある」と語りつつ、「自分を受け入れてくれる共同体の代替として、中間組織が必要とされてきた」と説明する。つまり日本の伝統的集団――いわゆる生まれ育った「村」という地域共同体――の代替として、戦後日本では、職場共同体や労働組合や政党といった中間組織が必要とされてきたのである。
が、対談がおこなわれた2000年代、平成ではすでにそれらの中間組織が力を失っている、と辻井は言う。
辻井 地域社会では、一番小さい共同体単位が家族であり夫婦ですね。それに代る新しい共同体というのをどうやってつくるか、という問題が残っています。たとえばシンガーソングライターの愛好会へ行くと、五十人とか、七十人レベルのすごく堅い共同体が形成されています。ファンクラブなんかもそうですね。
上野 ファンダムですね。
辻井 そういう例が片一方にあるわけです。彼ら、あるいは彼女たちは、それが共同体である、という意識すら持たずに共同体を形成している。それをどう誘導し、形成していくか。これはこれからの社会を考えた場合に重要な課題であって、それにビジネスがどれだけかかわり合いを持てるか、というのはたいへん大きな宿題です。
まず、いまのビジネス体質のままで組織が共同体とかかわり合いを持ったら、共同体にならなくなる場合が多いでしょう。そこが問題なんです。こういった共同体論を用意して、百貨店の命道を考えるという思考のプロセスが必要ではないかと思います。(『ポスト消費社会のゆくえ』)
上野 いまのファンダムの話ですが、旧世代型の中間組織の解体を埋め合わせるものとして、それに代わって、疑似的共同体として登場したのがオウム真理教でした。でも、それは共同体の疑似的な代替物にすぎず、個人を集団に埋没させるトラップ(罠)でした。ファンダム現象は、オウムのような虚構の共同体よりももっと拡散しています。匿名性と同調性が高く、ノイズに極端にセンシティブな、そういう集団の形成が起きているような気がします。
SNSを通した推し活文化を予言するかのようなふたりの慧眼には舌を巻くが、まさに「匿名性と同調性が高く、ノイズに極端にセンシティブな、そういう集団の形成」とはSNSの界隈のことであるだろう。実際「オタク」は推し活文化に吸収されていく。
「ヤンキー」は反抗することがなくなり、マイルドヤンキーとして地域文化の担い手として地元の家族に吸収されていく。
そして「都市にやってきた消費者」は、消費だけでなく、自分の仕事内容で自分を差異化するようになる。第一章で見た通り、2010年代には好きなことややりたいことを就職活動で語るようになっていく。「感性でつながる」ことが、就職活動をはじめとする、会社においても語られるようになっていくのだ。
集団アンチテーゼの時代
なぜ私たちは個人よりも集団を重視してしまうのか? なぜ私たちは個人の痛みよりも集団に迷惑をかけないことのほうが大切だと思ってしまうのか?
なぜ個人主義よりも集団主義は常に優先されるのか?
そういうことを考えたくて始めた本連載だが、それでも、1980年代には集団に縛られることへのアレルギーはたしかにあったのだ。
それはボールを友達だと言い切ることであったり、勝手に男性同士の恋愛を描いた同人誌をつくることであったり、百貨店で自分を差異化するための服を買うことであったりした。
だが、どの行為も、いつのまにか現代だと集団に吸収されている。個人で楽しむためのものが、集団をつくるものに変化しているのだ。
1983年に生まれたファミコンは、いつのまにか家族で楽しむWiiの誕生につながる。無印良品やユニクロは、百貨店文化と入れ替わるようにして、日本のファッションや家具を均質化していく。
全共闘的な集団から離れたり、伝統的家族集団から離れたりして、生まれた1980年代の文化。それはいつのまにか、平成を経て、新しい集団の形成の起点となっていく。
1980年代とは、例外的に集団主義アンチテーゼの文化が生まれた時期だと言えるのかもしれない。
では1980年代に否定された集団主義とは、はたしてどのようなものだったのか。1970年代について、次は見ていこう。
(次回へ続く)
[1] 清水正典「スポーツ社会システムの構造形成 日本サッカーの発展過程と社会的背景」『吉備国際大学研究紀要 人文・社会科学系・医療・自然科学系』23号、2013年
[2] 加藤一晃「中学生・高校生における運動部活動参加の拡大過程―競技の違いと「見る」スポーツの発展に注目して―」(『子ども社会研究』29号、2019年)
[3] 松本育夫『サッカーに世界はなぜ熱狂するのか』(毎日新聞出版、1991年)にはサッカーの部員が増えたことによって野球チームが組みづらくなっている状況が語られる。
[4] 注1に同じ
[5] 宇野維正、レジー『日本代表とMr.Children』ソル・メディア、2018年
[6] 小曽川真貴「やおい、JUNE、BLそして腐女子 腐文化研究事始め」(中部図書館情報学会誌 54、2014年)には、1985年12月開催のコミケにおいて、主に男性の描き手による幼い少女を対象とした創作恋愛ジャンルから、女性の描く『キャプテン翼』二次創作作品に流行が移ったことが指摘されている。
[7] 大塚英志『物語消費論』新曜社、1989年
[8] 相田美穂「やおいをめぐる言説の構成」『広島修大論集』56号、2015年
[9] 千田有紀「貴腐人、もしくは汚超腐人の密かな愉しみ」『ユリイカ』2012年12月号
[10] 藤本由香里『私の居場所はどこにあるの? 少女マンガが映す心のかたち』学陽書房、1998年
[11] 東園子『宝塚・やおい、愛の読み替え』(新曜社、2015年)は男性のオタク文化と女性のオタク文化では違った楽しみ方をしていることを指摘し、女性のオタクはキャラ同士の人間関係を消費していることを解説する。
[12] 田中東子『オタク文化とフェミニズム』青土社、2024年
[13] 大塚英志『「おたく」の精神史 1980年代論』星海社新書、2016年
[14] 斎藤美奈子・成田龍一編『1980年代』河出書房新社、2016年 p31
[15] 東浩紀・笠井潔『動物化する世界の中で ―全共闘以後の日本、ポストモダン以降の批評』集英社新書、2003年
[16] 難波功士『ヤンキー進化論』光文社新書、2009年
[17] 注16に同じ

体調が悪くても会社に行ってしまう。休んで自分のところで仕事を止めることに罪悪感がある。サウナや筋トレは好きなのに、体調のケアは億劫になる……このような悩みを抱えている働く人は少なくないのではないか。なぜ我々は、組織や集団にいると、休むことが難しくなるのか。文芸評論家の三宅香帆が、働く人たちを熱狂させてきた作品や国民的な少年漫画を歴史からひもとくことで、その源流を探る。
プロフィール

みやけ かほ 文芸評論家。1994年生まれ。高知県出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集)。著作に『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』、『「好き」を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』、『娘が母を殺すには?』、『30日 de 源氏物語』、『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』、『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』、『人生を狂わす名著50』など多数。


 三宅香帆
三宅香帆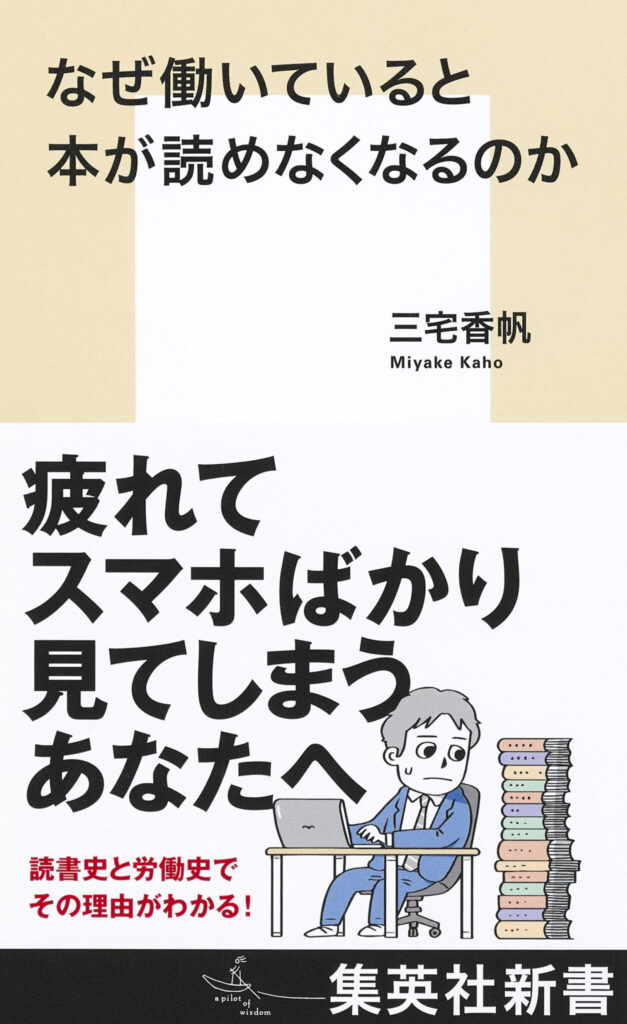










 藤原辰史×青木 理
藤原辰史×青木 理



