1.1990年代は飲酒量のピークだった
山一證券とアルコール
平成を代表する漫画『ONE PIECE』。実はこの漫画の連載開始とほぼ同時に起こっていたのが、山一證券の自主廃業だった。
1997年11月、山一證券の野澤正平社長は記者会見でこう叫んだ。
「社員は悪くありませんから! 悪いのはわれわれなんですから!」
―われわれとは誰か。2600億円の簿外債務を隠していた経営陣は、その高額すぎる赤字を処理しきれなくなり、自主廃業に追い込まれた。日本の上がりきっていた地価が下がり、株価も下がっていた時代、バブル崩壊を象徴する出来事だった。
1997年、『ONE PIECE』が連載開始され、山一證券は経営破綻した。ちなみに東電OL殺人事件と神戸連続児童殺傷事件が起こったのもこの年である。
1990年代後半、それはある意味で旧来の日本社会のシステムが挫折したことを後に知ることになる、失われた30年間の始まりだった。
……と30年以上経った今ならそれらしき顔をして、いけしゃあしゃあとこういうことを書けるのだが、まあ、当時のリアルタイムの人にとってはそんなことを予想するのは無理である。ちなみに1990年代後半と言えば、戦後増え続けていた労働人口が減り始めた最初の時期でもあった。日本の生産年齢人口(15~64歳)のピークは、1995年だったのだ。
1995年、阪神淡路大震災と地下鉄サリン事件の時期を境にして、日本は人口減少時期に入っていく。
そんな1990年代後半。「たった30年前だろ、何をそんな歴史の教科書をめくるように語っているんだ」と思われるかもしれない。が、たった30年前といえど、案外会社も社会も文化は変わっている。
変わったもののひとつに、たとえばアルコール消費量がある。
実は戦後日本において、飲酒量のピークは90年代後半。つまり90年代を境にして、私たちの身のまわりから、アルコールは少しずつ減りつつあった。
データで見ても、成人一人当たりのアルコール消費量(国税庁課税部酒税課発行の「酒のしおり」調べ)は1992年(平成4年)度の101.8ℓがピーク。そこから徐々に減少。さらにアルコール国内出荷数量もやはり1999(平成11年)度の1,017万klをピークとして減少している。逆にいうと、90年代とはアルコールの季節でもあった。会社員にとっても、アルコールは今よりずっと身近なものだった。
山一證券の経営破綻後を清算処理に奔走した人々を描いたノンフィクション小説『しんがり 山一證券 最後の12人』(清武英利、講談社、2013年)にも、驚くような場所でアルコールを飲む社員たちの姿が描かれている。
顧客相談室が設けられたのはバブル経済がはじけて株価が暴落した後の九三年である。本店や全国の支店には顧客の不満や苦情が殺到した。
その前年に損失補塡は改正証券取引法ではっきりと禁止されたため、損失の穴埋めはできなくなっていた。証券会社の中には、「証券トラブル」として簡易裁判所に持ち込み、法廷を使って補填しようというところも出てきた。訴訟の形にはするが、早々に和解して合法的に補塡するのである。しかし、それも大蔵省に届け出なくてはならないため、客が納得するような解決は容易に見いだせない。
苦情はこじれることが多くなり、声高な抗議やトラブルに発展した。その矢面に立たされたのが、顧客相談室長の樽谷だった。
(中略)
損な役回りだ。
そんな気持ちが時折、心に昏く満ちてくる。家族に打ち明けることでもないから気の紛らわしようもなく、どんよりとした不安を内側に込めたまま神経が尖ってくる。
だからということなのか、顧客相談室だけは、夕方に仕事場で酒を飲むことが黙認されていた。
(清武英利『しんがり 山一證券 最後の12人』)
まさかの、会社の職場で「酒」が黙認されていた、と語られるのである。
日本医療研究開発機構[1]によれば、ストレスを解消するためにメジャーな手段のひとつとして飲酒があり、職場で受けたストレスを解消するために飲酒している人は少なくない。山一證券のバブル崩壊後の「顧客相談室」業務にあてられた人々にとっても、たしかに飲酒は仕事のストレスを緩和するために使われる手段のひとつだった。
アルコールは、たしかにストレス緩和のためにもなるが、一方では人々の病を誘発する危険な存在でもある。
……というとお酒が好きな方には「そんなこと言うなよ!」と怒られるかもしれないが、まあちょっと聞いてほしい。たとえば世界保健機関の報告書[2]によれば、世界で2024年には260万人がアルコール摂取により死亡しているという。この260万人という死亡者数は、全死亡数の4.7%にあたる。これはたとえば結核や糖尿病より多い数字だというので驚きである。ちなみにこの数字以外にも、アルコールによって自殺行動に影響を与えている人々の数はもっといるのでは、ということである。
そしてこの結果について、WHOは、「特筆すべきは、アルコールに起因する死亡者260万人のうち、200万人が、男性であるということだ」と強調する。
痛みを「飛ばす」という麻痺
山一證券の男性たちは、バブル崩壊後のストレスを、アルコールでなんとか飛ばそうとしていた。
それはある意味で、2600億円の損害を「飛ばし」つまり損害への対処を先送りにしていた様子と、どこか重なって見える。
「飛ばし」とは、まさに株価が下がっていた時に、証券会社が痛みを先延ばしにするためにおこなっていた対処法である
〈「握り」は株価が永久に上昇し続けることを前提にする。株価が長期反落期を迎えると運用ファンドに損失が生じ、顧客法人の期待に応えられなくなる。そこで顧客法人と担当営業マンとの間に、「約束を守れ」「守れない」といったトラブルが発生する〉[3]
その決着をつけるには、顧客法人が損失を自社のものと認めてこれを呑み込んでしまうか、証券会社が損失補損をするしかない。いずれの決着も当事者に痛みをもたらす。そこで苦肉の策として登場したのが、決着を先延ばしするための「飛ばし」である。
ただ、「飛ばし」は一時凌ぎにはなったものの、証券会社に大きな問題をもたらした。
飛ばしている間も、株価下落によりファンドの含み損が拡大したからである。
(清武英利『しんがり 山一證券 最後の12人』)
実際、なぜそんな2600億円もの損害が隠されていたのか、誰も隠蔽にやばいですよとツッコミを入れる人はいなかったのか……と思ってしまうが、本作を読むとツッコミを入れることがいかに難しいことかがよくわかる。「とりあえず先延ばしで」という選択肢を取っている人に対して、「先延ばししてはだめだ、今考えるんだ」と言うのはなによりも難しい。それがバブル崩壊後の混乱の渦中にある大企業の内部なら、なおさらである。
興味深いのは、「握り」や「飛ばし」といった、証券会社における「とりあえず景気がいいときにおこなわれる慣習」が、バブル崩壊後も続いていたことだ。
ここでいう「飛ばし」とは、複数のペーパーカンパニーに赤字を負担させておくような行為である。山一證券本体の赤字は外側から見えないように、とりあえず隠す。
なぜこんなことが可能になったのか。それは、いずれ景気が回復したら、また黒字になる、その時に帳尻を合わせたらいい、と考えていたからである。
考えただけで胃が痛くなる話である。景気はたしかに循環する。待っていたら回復するばかりだから、とりあえず損害は隠しておこう、という判断をしていたのである。これはたしかに、景気が基本的に良くて、多少マイナスがあってもすぐに好景気になる時期だったらアリだったのだろう。好景気になる時期だったら。
が、歴史を知る私たちは、そんなことはないことを知っている。
まるでアルコールで、とりあえずのストレスを飛ばすように。一時的に、痛みを隠すかのように。大企業の証券会社でも、痛みを「飛ばす」ことが選択されていたのだ。
それはある意味で、我慢する、ということにも似ている。
嫌な仕事に耐える。損害に耐える。ストレスが、あるいは、損害があるという状況に自分を慣れさせ、麻痺させる。そのためには、まずは直近のストレスや損害という「痛み」を飛ばすことが必要になる。
―痛みは、SOSにも似ている。しかしそのSOSを無視して時間を耐えることによって、リターンを得られることもある。辛い仕事に耐えて、給料を得る。損害を乗り越えることで、大きな利益を得る。そういうことはたくさんあるからこそ、いったん痛みを飛ばすことは重要になる。
そうして、アルコールで痛みを飛ばす、つまり麻痺させることは、日常の風景になっていく。
仲間同士の約束
ちなみに山一證券が「飛ばし」をやることになったきっかけとなる「握り」もまた、違法になり得た商慣習であった。それは大きな企業の資産運用を証券会社がすべて任せてもらう代わりに、一定以上の運用利回りを得る約束をする、という取引だった。
当時の法律では、企業の資産運用において、これくらいの利回りを保証しますよ、ということは禁止されていた。が、巨額の資金を扱うことができて、法人も儲けることができて、株価が上がっているときはウィンウィンだったので慣習として続けられていたのだ。
もちろん危険だからやめよう、と言う社員もいた。が、そんなことは聞いてもらえなかった。
なぜなら、仲間内の結束を固める相互扶助のうえに成り立っていたからだ。
仲間内の結束のほうが、法令順守よりも、優先された。そう言うことができるかもしれない。
「ニギリによって巨額の一任運用ファンドを獲得した法人営業マンは、社内でスター視され、大きな顔ができた」と木下は証言している。
「それはずば抜けた手数料収入を稼ぎ出していたからだけではありません。一任ファンドの運用で高利益が生じても、顧客法人には当初約束の利回り相当分だけを渡せばよく、超過利益をどうするかは事実上、営業マンの裁量に任されていました。そこで仲間の運用ファンドで損失が生じているときは、そのファンドを簿価で引き取り、これを自分のファンドに生じている超過利益で相殺することが行われました。これは困ったときの仲間同士の相互扶助であり、しばしば「貸し借り関係』と呼ばれました」
(清武英利『しんがり 山一證券 最後の12人』)
ようは、仲間同士で損得の貸し借り関係を生み出すきっかけが「握り」というものだった。
貸し借りがあるなかで「もうこういうことはやめよう」というのはたしかに難しい。ぶっちゃけ自分がその会社にいる状況を想像しても、やめようと言えたかと問われると、難しい気がしてしまう。というか、今の自分であれば、そっと会社を辞めたかもしれない。しかしよく知られるように、当時は終身雇用制度が当然であった。新卒で入った企業を辞めるということは、イレギュラーなことだった。もちろん山一證券の社員たちも経営が危うくなるにつれて人がいなくなってはいたが、それでも勇気のいる決断だっただろう。
現在のように、転職が当然ではない時代に。山一證券の人々が、仲間内の貸し借りを重視してしまったのは、日本企業の文化風土を見出したくなってしまう。
そう、第三回で見てきたように、日本の企業文化には、どこか仲間内の結束を重視する文化があった。それは山一證券のような場所でも見える。
たとえ危険なことであっても、それでも目に見える仲間同士の貸し借り関係のほうを、優先させてしまう。
―第三回でも見た、間宏による日本企業批評を思い出してしまう。
家と企業とが分離して「社業」となったのちも、営利の追求だけでなく、会社そのものの永続を願う意識、それを望ましいとする価値観が経営者だけでなく、一般従業員の間に強くもたされてきた。他のあらゆる集団と同様、企業においても重視された「和」とは、まさにこの集団の永続を目的としている。会社は永続していく間に、一種の精神(「団体精神」 “esprit de corps’”)を付与され、それがそのメンバーにとって、経済面だけでなく、精神面での支えにさえなる。
(間宏『日本的経営 集団主義の功罪』1971年、日本経済新聞社)
「先延ばし」とは、会社の永続を信じているからこそ選択される行為である。まさに山一證券の場合は、先延ばしし続けた結果、痛みが膨らみすぎて、潰れてしまったわけだが。
仲間を大切にするための、仲間内の約束こそが、仲間との時間を断ち切ってしまう――そう考えると山一證券の話は皮肉である。先延ばしすればするほど、残り時間は短くなってしまう。
『しんがり 山一證券 最後の12人』を読むと、大企業で損失を隠蔽していた人々が、酒を飲んでいるときに口論する様子が描かれる。酒に酔って、握りで生まれた損失を批判する場面もある。そういう意味で、アルコールは会社の「和」を乱すひとつの本音を引き出す手段でもあった。
が、一方でアルコールが入っていたからこそ、「和」は保たれたと言ってもいいかもしれない。この批判がアルコールなしの状態だったら、批判はもう少し正面からの痛みを引き受けられたかもしれない。が、アルコールがあったからこそ、批判しつつも翌日には何事もなかったかのように喋るような事態になっていたかもしれないのだ。
2.増え続けるコーヒー的な麻痺
コーヒー的覚醒と近代
日本のひとりあたり飲酒量は、1990年代後半がピークだった。一方で、入れ替わるかのように、現在に至るまで増加してきた嗜好品が、コーヒーである。
日本のコーヒー消費量は、第二次世界大戦後の1950年にコーヒー豆の輸入が再開されて以降、経済成長とともに増加の一途を辿ってきた。結果として、全日本コーヒー協会のデータによると、1980年(昭和55年)のレギュラーコーヒー消費量を基準値53とした場合、1990年(平成2年)には100となってきた。
さらにコーヒーの場合は、アルコールと違って1990年代以降も消費は増加傾向が続いた。
2016年頃をピークに、近年ではやや下降傾向にあるものの、2024年の日本のコーヒー消費量は400,218トン(前年比99.6%)、世界第四位の消費量と高い水準を維持している。――というか人口が減っているのに消費量はこれだけ減っていないというのは、ひとりあたりコーヒー摂取量はまったく減っていない。アルコールと対比すると、コーヒーは今も大量に飲まれている。
アルコールとコーヒーを対比させると、面白いことが見えてくる。松本俊彦『身近な薬物のはなし タバコ・カフェイン・酒・くすり』(岩波書店、2025年)によれば、実はアルコールと同じくらいの依存性が高いのはカフェインであるという。
しかしその方向性は真逆である。
15世紀、イスラム教信者の間で飲まれていたコーヒーは、17世紀ごろヨーロッパにやってくる。当時のイギリスはちょうどピューリタン革命からの名誉革命、議会政治が開始された時代。ロンドンには政治について議論をしたい人々が集まっていた。さらに資本主義黎明期、証券や貿易や船舶の競売についての情報交換をしたい人々もたくさんいた。
そこに現れたのが、コーヒーハウスだったのだ!
当時のイギリスのコーヒーハウスは、紳士的であること――決して暴力や賭博は許さず大声を出さない――が規範として求められる場所だった。
居酒屋とは違う場所。紳士的で先進的な議論をできる男性が集まることのできる場所。それが、コーヒーハウスだったのだ。
依存症について研究する松本俊彦は、この衝撃を「第二の脳の爆発」の時代と呼ぶ。つまり、ヨーロッパの近代システム――民主主義と資本主義――は、カフェインによるドーピングがあったからこそ爆発的に発展できたのではないか。カフェインがイスラム世界からヨーロッパへやってきたからこそ、一日にこなせる知的労働量が増えたのではないか、と指摘する。
この頃、ビールやワインは、水よりも清潔な飲用水として生活必需品であり(一方、蒸留酒は「酔う」ためのドラッグでした)、階級に関係なく、朝からビールやワインを飲むのがあたりまえでした。
だからこそ、ヨーロッパの人々はしらふであることのありがたみを痛感していたはずです。
なにしろ、当時は「謹厳なる(ソーバー:「しらふ」の意もあり)ピューリタン」の時世です。
コーヒーは、煮沸され、抗菌作用を持つカフェインも含まれる、きわめて清潔な飲料です。しかも、酩酊しないばかりか、しらふ以上に意識を透徹させてくれるわけです。熱烈に歓迎されて当然でしょう。
コーヒーはまた、人間の時間感覚に影響を与えた可能性もあります。マイケル・ポーランは、カフェインがヨーロッパの人々の時間感覚を変化させたと指摘しています(マイケル・ポーラン著、宮﨑真紀訳『意識をゆさぶる植物―アヘン・カフェイン・メスカリンの可能性』亜紀書房、2023年)。というのも、コーヒーの伝来・普及と期を同じくして、時計の分針が誕生したからです。
(松本俊彦『身近な薬物のはなし タバコ・カフェイン・酒・くすり』)
アルコール漬けだったヨーロッパの人々が、カフェインの登場によって、意欲も意識も覚醒するようになった。そして夜を明かして、民主主義と資本主義に漬かる――つまり政治の議論をしたり、貿易や証券の情報交換をしたりすることが、できるようになった。こうして昼も夜も、分単位で、時間を測るようになった。
カフェインのドーピングがなければ近代なんて、民主主義と資本主義なんて、成立しなかったのかもしれない。なんて思ってしまうのは、私だけだろうか?
そして、カフェインが覚醒させるのは意識や意欲だけではない。好戦的にさせるのもまた、カフェインの力である。
戦争のたびにコーヒーの需要が高まった[4]ことはよく知られている。アメリカの兵士はコーヒーを飲んで戦地に向かった。近代的な戦争も、あるいはカフェインの覚醒力がなければ……とつい想像してしまう。
日本のコーヒーは「ひとりで飲む」もの
さてそんなコーヒー文化は、欧米ではコーヒーハウスを中心に拡大した。人々がしらふで語り合うなかで、社交を手伝うものとしてコーヒーは急速に伝播した。
が、日本の場合は、興味深いことにカフェは広がったものの、社交にはつながらなかった。
世界史においてカフェは交流のためのものだった。が、日本の場合、1970年代にブームになった「喫茶店」はけして交流のためではなくコーヒーを飲むことが重視された(たしかに今も『だれかと喋りたい!』と思ってカフェに行く人は少ないだろう)[5]。大量に生まれた喫茶店において、競争されるのはコーヒーのおいしさ。とにかくおいしいコーヒーを淹れられるかどうかを店主は競い合った。
さらに1990年代後半以降ブームになった、欧米のカフェを模したオープンカフェ。これもまた季節ごとのラテを出したり、キャラメルマキアートのような飲み方を提案したり、やはり人と出会うためというよりは飲み物や空間を楽しむことができるお店が多い。もちろんスターバックスをはじめとして、カフェに人と行って喋ることもカフェに行く大きな目的のひとつだろう。が、居酒屋よりもその頻度は少ないのではないか。
そう考えると、日本人にとってのコーヒーは、一息ついたり、休んだりするためのもの、という意味合いも大きい。むしろサロン的交流という側面なら、バーなどの「アルコール」が提供される場のイメージを持つ人も多いだろう。
2025年に刊行された、朝井リョウ『イン・ザ・メガチャーチ』(日経BP)では、男性同士でカフェに行くことが少ないという描写がある。男性同士で行くならコーヒーよりもお酒を飲める場所だろう、と思う人も読者のなかにいるはずである(実際に飲むかどうかは別として)。これはまさに、日本ではコーヒーハウス文化が根付いていない証左だろう。
どちらかというと、コーヒーによってストレスを忘れさせたり、カフェインで眠気や痛みを麻痺させる時間は、ひとりでおこなう行為になっていった。
缶コーヒーを片手にサラリーマン
実際、コーヒーを飲む理由についての調査では、「リラックスしたい」「気分をリフレッシュする」が上位に来ている(クロスマーケティング調べ)。[6]つまり、ひとりの時間を充実させるために飲む人が多い、ということである。
アルコールが集団でストレス緩和するものだとすると、コーヒーはひとりでストレス緩和するものである。そのように分類することは可能だろうか。アルコールが集団で痛みを麻痺させるものだとすると、カフェインは個人で痛みを麻痺させるものではある。孤独を癒したり、苦痛を和らげたりする点はアルコールもカフェインも同じだが、それが集団か個人かで異なるのではないか。
そういう意味で、職場でひとりで飲むための缶コーヒー――「BOSS」をサントリーが誕生させたのは、1990年代だった。
そもそも缶コーヒーはUCCによって1970年代万博をきっかけに爆発的な広がりを見せた。一方で、1990年代に誕生したBOSSは、サラリーマン姿の男性が飲むCMで人気を博した。
1992年にはじめて放送されたCMには、矢沢永吉が登場。ロックのイメージが強い彼が、普通のスーツを着たサラリーマンを演じた。
「儲かってるくせに、不景気だって顔、多いですよね」
「会社なんて、あんまり信用しないほうがいいよ」
「会社なんてさ、いい加減なんだから」
そう伝える矢沢の姿は、まだバブルの好景気時代の1992年にあって、新鮮な姿にうつったのではないか。今思えば時代を先取りしていたBOSSは、その後人気になっていく。
サントリーはCMが特徴的な企業だというイメージを持つ人も多いだろうが、実際、BOSSの「会社なんて、あんまり信用しないほうがいいよ」という言葉は示唆的である。
企業のことを信用できない、と言いつつひとりでコーヒーを飲む姿。それはある意味でアルコールで会社の愚痴を言い合うような風景とは真逆だ。ちなみに同じサントリーが出している、サントリー オールド ウイスキーの有名なCMでは男女の交流が描かれていた。本気の交流である。
やっぱりアルコール的時間とコーヒー的時間は異なる。
アルコール―集団で痛みを麻痺させる時間―は1990年代を境目に減少し、コーヒー―個人で痛みを麻痺させる時間―は1990年代以降増加し続けているのだ。
3.『SLAM DUNK』とアルコール的麻痺から醒めること
義理人情の90年代
このように考えていくと、1990年代とはまさに従来型の集団主義と、台頭し始めていた個人主義が、ちょうど入れ替わるかどうか葛藤していた時代であると言えるのではないか。
BOSSのCMが言うように、「会社なんて、あんまり信用しないほうがいいよ」とささやく自分もいる。山一證券のように、会社を信用していたら驚くような目に遭う人もいる。
一方で、やっぱり仲間を重視する日本の価値観はずっと存在している。
たとえば山一證券の破綻に遭った元社員ですらこう告げるのだ。
「山一に育てられました。だから山一の誰も恨んでおりません」(『しんがり 山一證券 最後の12人』)と。
もちろん山一證券がさまざまなことを教えてくれたのはそうだろうが、しかしそうはいっても会社への忠誠心、あるいは仲間への人情があるからこそ彼らはこのように語ることができるのだ。あるいは集団外の人間に対して、集団内の人間の見栄を守ろうとする文化かもしれない。どちらにせよ実際、破綻する会社の清算処理に彼らを向かわせたのは、ほかでもない仲間や会社への義理や人情だったのである。
「集団や仲間への義理人情があるやつ」こそが良い人である、という道徳規範。1990年代に人気だった、ヤンキー漫画もこの流れのなかにある。『クローズ』(髙橋ヒロシ、秋田書店、1990~1998年)、『ROOKIES』(森田まさのり、集英社、1998~2003年)、『GTO』(藤沢とおる、講談社、1997~2002年)のように、人情に厚く「いいやつ」としてのヤンキーが人気を博す。
彼らは皆、仲間想いである。まさに個人より集団を優先させる、集団主義の権化のような男たちだった。
そしてその流れのなかに現れたのが、連載冒頭から扱っている『SLAM DUNK』である。
個人が集団になる過程
ヤンキーがバスケットボール部に入る、というプロットから生まれた少年漫画『SLAM DUNK』(井上雄彦、集英社、1990~1996年)。
本作はまさに、集団としてのまとまりがなかった、チームワークがとれていなかった個人個人のヤンキーの男子たちが、チーム=集団になっていくなかで成長していく様子が描かれる。
主人公の桜木花道は、不良のヤンキー。それまでのヤンキー漫画ブームを引き継ぐかのような、人情には厚いが問題児として最初は登場する。
一方で、同じ部内でやってくるのは、流川楓。彼は個人主義を体現する、才能はあるがチームワークは苦手な男である。
ほかの部員、三井寿や宮城リョータや赤木剛憲もまた、個人の能力は高いものの、チームワークを構築することを苦手とする。
いわば『SLAM DUNK』とは、個人主義だった登場人物が、いかに集団として強くなっていけるのか、を描いた漫画として読むことができる。
―『SLAM DUNK』という漫画の凄さは、それがただ「ばらばらだったキャラクターがひとつにまとまる」という描き方にとどまらず、「個性を活かしながら、集団にまとまる」過程を描いたところだろう。
つまり、個人でありながら、集団になる、その過程をバスケットボールを通して描いた漫画なのである。
だからこそラストシーンに私たちは感動する。それはまさに、個人主義を貫きとおしていた男が、集団のひとりとして動く、その瞬間に邂逅するからだ。
『SLAM DUNK』を読めばわかる通り、集団の中にいながら、個人でいることはできる。
本作に描かれているチームとは、けして家族の比喩や、企業の比喩としての、集団ではない。
むしろ、純粋な、この場限りのチームとしての、個人を生かす集団なのである。
彼らはけしてチームに抑圧されない。自分の得意なプレイを活かし、活動する。しかしそれでいて、個人の得意よりも集団の勝利を優先させる瞬間がある。
個人でありながら、集団を生きる。――集団のために個人を抑圧し続けていた日本社会にとってはある意味ユートピアのような、ある一瞬の幸福を見たからこそ、私たちは『SLAM DUNK』に感動してしまうのだろう。
痛みを忘却しない
さらに本作で興味深いのは、その痛みの表現である。
本作で少し不思議な表現がある。それは、桜木花道の父親のために、花道が病院に行こうとすると、ヤンキーたちに絡まれて病院に行けないという場面があるのだ。
なぜ井上雄彦はこんな場面を挿入したのだろう。スラムダンクファンですら、首をひねる場面ではないだろうか。[7]
思えば、桜木花道は、なかなか病院に行かないキャラクターである。大けがをしても試合に出続ける。さらに、病院へ医者を呼びに行こうとすると、不良に阻止される。
しかし桜木は、最後のシーンではじめて、医者にかかる。
―中学生の時の桜木は、父が倒れた時にも病院に行けなかったことを考えると。ある意味で『SLAM DUNK』とは、桜木が病院に行って終わる話である。と、言うこともできるのではないか。
喧嘩したりバスケしたりして怪我してばかりいた桜木。彼はバスケに熱中し、成長し、そしてバスケの夢から覚めたとき――病院で痛みと向き合うことができるようになった、のかもしれない。
つまり試合や喧嘩のアドレナリンで麻痺させていた痛みの感覚を、取り戻すことができたのではないか。
本作を「麻痺と治癒」という観点から眺めると、案外これまでとは違った『SLAM DUNK』という物語が浮かび上がる。
そもそもスポーツ漫画において、怪我というとマイナスの印象を抱くかもしれない。『SLAM DUNK』をはじめて読んだとき、なぜ作者は桜木花道のラストシーンをあのような、病院の場面にしたのだろう? と私は不思議に思った。もっとかっこいいラストシーンが、バスケットボールを持った桜木を私たちに見せることもできたはずではないか、と。
しかしそれはもしかすると、バスケットボールを持って世界に旅立つよりもずっとかっこいい姿が、病院にもある、ということかもしれない。
桜木花道は元々恵まれた体格の男である。試合にも喧嘩にも強いし、そして痛みにも強い。ちなみにライバルの流川楓も、痛みに鈍感な男である。才能があり、体力があり、痛みも麻痺させられる。
しかしそんな彼らは、湘北高校バスケ部の活動を通して、個人の欠陥を知り、苦手なことを知り、チームに預けて休息することを知る。
結果として、桜木は怪我をする。しかし作者はそこで物語を閉じる。最後、桜木に作者は「天才」と言わせる。バスケットボールを持っていても、松葉杖を持っていても、それでも桜木は「天才」である、と。
桜木はずっと天才である。しかし同時に、痛みと向き合うことができているぶん成長しているのだと、ヤンキー時代から変化したのだと、読むことはできないだろうか。
それはもしかすると、アルコール的な痛みの麻痺―集団で喧嘩したり試合したりしているなかで、ロマンで興奮し、痛みを忘却すること――を手放すことでもあるかもしれない。集団を離れ、個人で痛みと向き合うかっこよさ。その姿が『SLAM DUNK』のラストシーンではないか。[8]
個人を生きながら、集団を生きる
強く、調子がいいうちは、アルコール的なもので「痛みを飛ばす」ことが功を奏する。体の調子が良かったり、景気が良かったり、仲間内の阿吽の呼吸がうまくいったりしているうちは、いくらでも痛みを飛ばし麻痺させ、無理をして生きることができる。
だが社会も、人生も、体も、けして調子の良いときばかりではない。
バブルは弾けるし、怪我だってすることもある。そのような折、どこまでなら痛みを「飛ばして」いいのか、どこまでだったらその痛みが致命傷にならないのか、限度を見極めることはとても難しい。
さらに―集団でいると、その痛みを飛ばし続けることが仲間内の約束になってしまったりする。
「社員は悪くありませんから! 悪いのはわれわれなんですから!」という言葉も、「われわれ」の仲間内で痛みを麻痺させ先延ばしにして放置させてしまったことを表現している。
まさに『SLAM DUNK』で桜木花道が病院に行った翌年、山一證券は痛みを隠し切れずに自己破産する。
痛みとは個人的なものである。個人であるということは、それぞれ痛みが異なる、ということでもある。だからこそ痛みを認識したときは、集団を離れて、休むかどうか、ひとりで判断せざるを得ない。
集団に慣れすぎていると、それはアルコールの夢から醒めるようなもので、しらふでいるのが辛いと感じる場合もあるかもしれない。しかし桜木花道がリハビリに挑むように、やはり怪我したら、どこかで痛みと向き合わざるを得ない。それは集団から離れることでもある。
痛みを麻痺させない、痛みと向き合うほうが最終的にはかっこいい、ということを示したのが『SLAM DUNK』という物語だったかもしれない。
痛みに鈍感だった個人主義のヤンキー少年たちが、集団になり、そして個人の痛みを知るように成長していくこと。それは試合に勝つ以外の道でも個人を生きつつ集団を生きるうえでの、ひとつの回答なのだろう。
だが実際は『SLAM DUNK』連載後、今もそうであるように、カフェイン的痛みの麻痺―個人主義でありながら痛みは麻痺させる新自由主義思想―が台頭するようになる。アルコールを強制させられることは少なくなったかもしれないが、一方で、ひとり現実を忘れるために飲むカフェイン入りのエナジードリンクは大量に売られている。
カフェインの夢も、アルコールの夢も、集団の夢も、病院に行く第一歩を、ぼんやりと遅らせてしまうのだ。
(次回へつづく)
[1]日本医療研究開発機構「職場のアルコール問題早期介入マニュアル アルコール依存症への地域連携による早期介入と回復プログラムの開発に関する研究」(研究代表者:樋口進)2019年
[2] 世界保健機関「アルコールと健康に関する報告書」2024年
[3] 作中引用される、調査委員会に提出した木下公明による論文より。
[4] ジョナサン・モリス著、龍和子『コーヒーの歴史』原書房、2019年
[5] 井崎英典『世界のビジネスエリートは知っている 教養としてのコーヒー』SBクリエイティブ、2023年
[6] クロスマーケティング「コーヒーに関する調査(2023年)」URL:https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20230426coffee 2025年10月閲覧
[7] しばしばスラムダンクファンの間では「桜木花道はなぜ一人暮らしっぽいのか」という議題は永遠の謎として問いかけられている。
[8] 実際に井上雄彦はこの後『リアル』(集英社、1999年~)という車いすバスケットボールや障がいを主題にした漫画を連載する。痛みを抱えつつバスケットボールをする主人公たちを描くのである。

体調が悪くても会社に行ってしまう。休んで自分のところで仕事を止めることに罪悪感がある。サウナや筋トレは好きなのに、体調のケアは億劫になる……このような悩みを抱えている働く人は少なくないのではないか。なぜ我々は、組織や集団にいると、休むことが難しくなるのか。文芸評論家の三宅香帆が、働く人たちを熱狂させてきた作品や国民的な少年漫画を歴史からひもとくことで、その源流を探る。
プロフィール

みやけ かほ 文芸評論家。1994年生まれ。高知県出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集)。著作に『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』、『「好き」を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』、『娘が母を殺すには?』、『30日 de 源氏物語』、『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』、『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』、『人生を狂わす名著50』など多数。


 三宅香帆
三宅香帆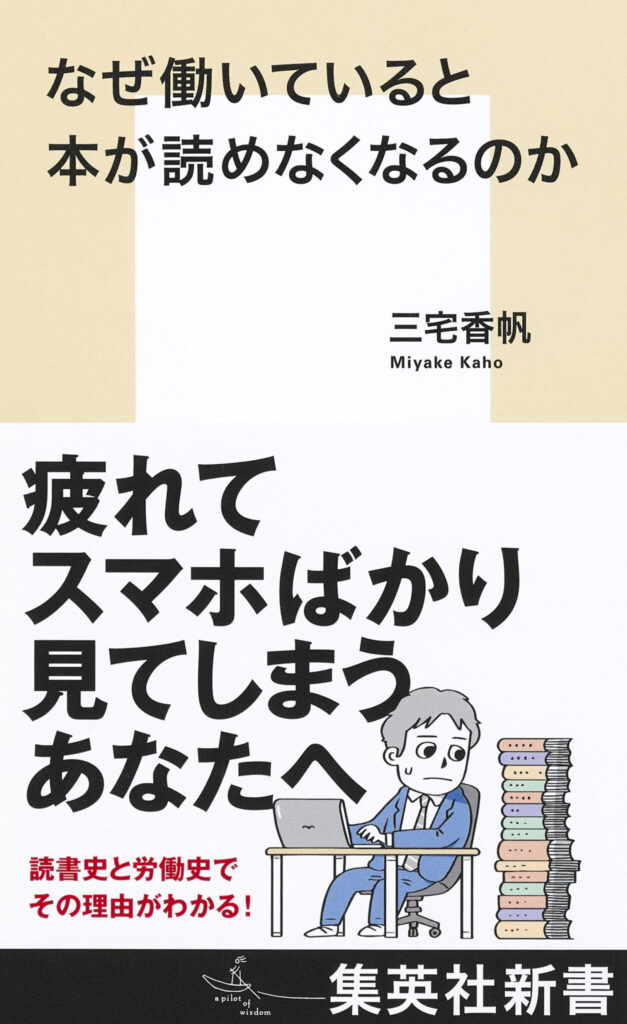










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


