私は二十七歳だった。いや違うか。もう覚えていない。
中野坂上から新宿に青梅街道を十分ほど下った神田川べりの四畳半の風呂もトイレもないアパートに暮らしていた。暮らしていたといっても、そこは女の部屋で、私は転がり込んだだけだ。
その日はとても暑かった。扇風機はあったのだろうか。もう思い出せない。
役者を目指していただけで、仕事はなかった。
女は劇団に入りながら、銀座のクラブで働いていた。
前夜、女は酒に酔い、客にタクシーで送られ、家の脇の風呂屋の前で降りた。降り際、客の首にしがみついて、キスでもしたのか。
私は電柱の陰から、それを見て、愛ではない嫉妬を振り回した。
そのくせ、女の稼いだ金をあてにもしていたのだ。
窓を開ければ、目の前には神田川がチョロチョロと勢いをなくして流れていた。まるで南こうせつが歌う「神田川」だ。
相変わらず役者の仕事もない私は部屋の熱気も手伝って、ひどくいらついていた。夜に仕事をする女は、昼間やることがなかった。
タバコをねだって、女が近づいて、うっとうしかった。私は女を突き飛ばした。はずみで安物のカラータンスに背中をぶつけた女がくの字に曲がって、私をにらみつけた。
いつもなら、取っ組み合いになったりするのだが、その日は違った。投げだした足を胸に引き寄せ、悲しく私を見た。
「もう死んじゃおうか」
「何! 何だよ」
「もう死んじゃおうヨ」
「あーいいネ、いいネ」
「……」
私は安物のカラータンスからガムテープを取り出して、テープをビリビリと切って立てつけの悪い窓枠に目張りをし、ガス栓をひねった。
シューシューとガスの漏れる音だけが狭い四畳半に響き、ふたりの耳に聞こえた。
何分か過ぎた。女はガスの栓を閉めに行かなかった。ひねった手前、私もそれができない。
シューシューとガスの音が聞こえる。私はタバコを吸いたくなって、一本くわえて、マッチをとった。
「爆発するわヨ!!」
女の乾いた声が遠くで聞こえた。
何を思ったのか、その時、私は部屋に女を残し、ドアをしっかり閉めて、外の細い道路に出た。
なぜ女を残し、私は部屋を飛び出したのか、今でも、その時の行動が理解できない。とにかく、私は女を残し、ドアまでしっかり閉めて、外に出たのだ。
細い路地は、日がカンカンに照って、道路の照り返しもあり、異常に暑かったのを覚えている。
神田川の悪臭が鼻をついた。
それでも、私はタバコに火をつけ、あと五分し、女が出てこなかったら、部屋に戻ろうかと計算をしていた。
タバコを二服はしたが、一分もたたぬうちに、女が部屋から飛び出してきた。
「あんた、殺す気」
と大声でどなって、私の胸にしがみついてきた。
女をかわいいと思った。
いつまでも、しがみついて離れないので、暑いヨと言ったら、女は地べたが熱くて、足をつけていられないと答えた。女は裸足だった。
女が愛おしくなった。
結局、何を書いているのかわからなくなった。
若い人たちが、狭く、小さな世界にいて、そこで必死にあがいている。生きようとしている。
私は何も出来ない。立派な言葉も持ち合わせていない。
なんとか笑いをタネに食いつないでいるだけである。でも、先刻のラジオに何通もメールが届いた。皆、若い人たちを心配する心温まるものである。もちろん自分の境遇を伝える人もいた。
Aさんは病気療養中で、かなり前から仕事を休んでいる。死んでしまいたくなって、最後に神様に尋ねたそうだ。
「神様、私はどうしたらよいのでしょう」
その時、それに答えるようにベランダの外から、カラスが「カアーカアーカアー」と鳴いた。その間の抜けた声に死ぬのをやめたと書いてきた。
カラスが鳴いたら、何事も一端中止すべきである。
プロフィール

おおたけ・まこと 1949年東京都生まれ。東京大学教育学部附属中学校・高等学校卒業。1979年、友人だった斉木しげる、きたろうとともに『シティボーイズ』結成。不条理コントで東京のお笑いニューウェーブを牽引。現在、ラジオ『大竹まことゴールデンラジオ!』、テレビ『ビートたけしのTVタックル』他に出演。著書に『結論、思い出だけを抱いて死ぬのだ』等。


 大竹まこと
大竹まこと










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


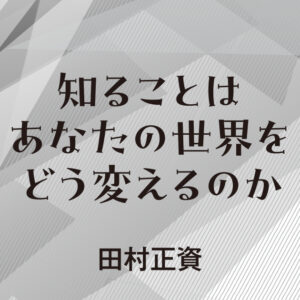
 田村正資
田村正資