昔、賞をとって物書きの数に入れてもらって間もない頃、温泉好きな文筆家の座談会に出たことがある。
その時、わたしも大学で教わったドイツ文学の先生が、
「僕は人に会いに温泉へ行くんです」
と言われた。
湯治場に知り合いがいるのだとわたしはこれを解した。しかし、そうではなかった。
「君は若いから、まだわからないだろう」
とその先生は言われた。
それから四半世紀経って、わたしにも今はわかるつもりだ。先生は一人になりに温泉へ行かれたのだ。山の静かな宿でただ一人湯につかっていると、次から次と、懐かしい人の顔や声が脳裏に蘇る。
忘れ得ぬ面影――
わたしの場合、蘇るのは人々の姿だけではない。酒というものを飲みはじめてから、これまで数十年の間に足繁く通った、今はない酒場、居酒屋が幻として立ち現われる。
以下に掲げる文章はそうした幻を書き留めたもので、いわば酒飲みの履歴である。
みなさんは、牛もつの串煮込みという料理を御存知だろうか。
「串」の一字がついているところがミソで、ふつうの煮込みとちがう。牛の臓物を部位ごとに下ごしらえして串に刺し、串のまま鍋で煮るのである。
東京の三ノ輪界隈には、かつてこれを食べさせる店がたくさんあった。
チンチン電車の終点に近い「越後屋」なども記憶にあるけれど、わたしが一番好きだったのは「大阪屋」という店だ。
大関横丁の交差点から明治通りを西へ向かって行って、三ノ輪病院の角を曲がると、鉤の手になった横丁に入る。その突きあたりの二、三軒手前に「大阪屋」はあった。
早い時間から開いていたから、午後の陽の射し込む明るい店内が印象に残っている。ガラガラと戸を開けて入ると、向かって右側の奥に座敷の上がり口があるが、こちらは店ではない。店は左側の三和土で、コの字形のカウンターのほかに、小卓が一つ二つ据えてある。立派な時計と大きな団扇海老の飾りがあったことも憶えている。
カウンターの中には、姉妹だろうか、面立ちの似た三人のおばさんが働いていて、向こうとこちらに大鍋がグツグツ煮え、その中に、もつを刺した串がたくさん入っている。種類は牛の腸、肺、ハチノス、センマイ、軟骨といったところで、客は菜箸で好きなものを自分の小皿に取り、唐辛子をふりかけたりして食べる。
大鍋の中の汁は黒々としているが、それはもつのエキスの色であろう。味つけは薄い塩味だ。同じ「オオサカヤ」でも、門前仲町の「大坂屋」――こちらも知る人ぞ知る串煮込みの名店だが――の甘辛い味つけとは異なる。
串ごとにちがう味を味わえるのが、この串煮込みの良いところだ。
ぶきぶきした軟骨に、フワフワした肺、ハチノスは弾力があって、歯の悪い人には向かないが、よく噛んで飲み下すと、一種の征服感を味わえる。煮込みに欠かせない「オオアブラ」といわれる小腸は、薄い皮の片側にたっぷり脂がついていて、味のしみたその脂が口の中で溶けて、広がってゆく。
客の小皿には串が次第に増える。お義理のように一、二本とって、あとはただ酒とおしゃべりを楽しむ客もいる。二十本も三十本も串を積み重ねる強者もいる。支払いの時は、むろん、この串の数で勘定をするのだ。
煮込み以外ではカブの漬物が旨かった。一度、常連客が鮪と白身の刺身をとっているのを見たが、品書になかったから、あれはその日のスペシアリテだったのだろう。
この店の客はたいがいチューハイを飲んでいた。
焼酎甲類の飲み方に関して、東京の東と西は文化が異なる。東はチューハイ文化圏、西はサワー文化圏とでも呼べば良かろう。
池袋から西の酒場でチューハイを頼もうとしても、炭酸水を置いていなくて、甘ったるいサワーしか出来ないことが多い。これに対し、下町の酒場はチューハイが基本である。宝焼酎、キンミヤ焼酎といった焼酎をさわやかな炭酸水で割り、生レモンの薄切りを加えたものだ。秘伝の梅エキスか何かを入れる場合もあるが、甘くないから大人にも飲みやすい。
炭酸水はおおむね地元の零細な業者がつくっていて、「ニホン・シトロン」、「吾妻タンサン」、「コダマ・サワー」といった名前も何か懐かしい。
煮込みには、やはりこれがなくてはいけない。
夏の夕方、ガラス窓の外がそろそろ青ずんで来た頃、涼しいチューハイをぐっとあおって、モツを一口、串から齧りとる美味しさ。
「大阪屋」へは、学生時代に家庭教師をした家の御主人――歯科技工士のSさん――が初めて連れて行ってくれた。Sさんはもう亡くなったが、下町が好きで、わたしに随分いろいろな店を教えてくれた。桜鍋の「中江」に「みの家」、泥鰍の「飯田家」、三ノ輪の「砂場」、河豚の「近江屋」「魚直」「三浦屋」――わたしはSさんに教わった店へ友達を案内して、下町の通のような顔をしたのである。
「大阪屋」へも仲の良い友達と何回か行ったが、わたしが知りはじめてから数年後に廃業てしまった。古い建物は小綺麗なビルに変わり、おばさんが外の道で小さい子と日向ボッコをしている姿を見かけた。
それから二十年ほど経ってからのことである。
わたしはもう長年、夏の暑い盛りを福島の微温湯温泉で過ごしている。これは一度も欠かしたことがなく、自慢ではないが原発事故の年も行った。あの年の福島の桃は、めったにない素晴らしい出来だった。
微温湯は山中の一軒家で、まわりには草と木ばかり。読書をし、物を書くにはうってつけだが、長逗留していると街の灯が恋しくなるから、たまに福島市街へ下りて、酒場から酒場へさまよい歩く。
福島駅東口から駅前通りを東に行って、大通りをひとつ越すと、小さい昔からの店が並ぶ居心地良い界隈に出る。ある時、夕暮れにそのあたりをぶらつきながら、ふと横丁を見ると、大きな赤提灯が下がっていた。
「牛煮込み 大阪屋」とあり、串の絵が描いてある。
「大阪屋」という同名の店が福島にあって、牛煮込みを出す――ここまでは偶然の一致としてあり得よう。しかし、串の絵は何だろう? 串煮込みを意味するとしか受け取れない。そうすると、偶然とは思えなくなって来る。あの三ノ輪の店と何か関係があるのではなかろうか?
たしかめるために縄暖簾をくぐって、入ってみた。
店は年輩の夫婦がやっている普通の居酒屋だった。カウンター席が四、五席と小上がりがある。壁に相撲の番付や力士の大きな写真が飾ってある。
わたしはカウンター席に坐り、品書を見た。
もつ焼きに会津名物の鰊の山椒漬け、玉子焼といった肴がある。煮込みもあるが、串に刺さない普通の牛もつ煮込みだった。
芋焼酎のロックを少し飲んでから、鉢巻をしたおやじさんに三ノ輪の「大阪屋」の話をすると、わたしの勘は大あたりだった!
おやじさんは三ノ輪の隣、南千住の人だったのだ。二十数年前に福島へ来て、この店を始めたのだが、あの「大阪屋」で串煮込みの作り方を習ったのだそうである。ここでも初めは串煮込みを出していたが、お客があまり好まないため、普通の煮込みに変えたという。
奇縁だねえ、とおやじさんは喜んだ。わたしが今南千住に住んでいると言うと、懐かしそうに目を細めて昔話を始めた。
南千住駅前の「汽車道」という煮込み屋のマスターは、俺の遊び友達だった。千住間道の「××屋」の亭主も同級生だ。もしも行ったら、よろしく伝えてくれ――
「汽車道」は、じつはわたしの行きつけの店だったが、駅前再開発でなくなってしまった。「××屋」はやっているので、東京へ帰るとさっそく行ってみた。
ここも昔からの居酒屋で、飾り気などは微塵もない古い家である。
お客は何十年と通いつけの近所の老人ばかりだ。その日は地元の小学校の同窓会が奥の座敷で開かれ、お婆さんが大勢集まっていた。
店の主人は料理をつくるのに忙しくて、声をかけづらかったが、頃合いを見はからって、「大阪屋」のおやじさんのことを話した。
ところが、主人は
「はあ、そうですか」
と一言言ったきりである。
忙しいからかもしれないし、こういう無愛想な亭主なのかもしれない。そう思い、何食わぬ顔でチューハイを飲みつづけていると、そのうち、おかみさんが横目遣いにこちらをチラと見て、
「××さん、お元気ですか」
と小さい声で言った。
「お元気ですよ」
とこたえたが、話はそれきり続かなかった。
わたしはほどほどに切り上げて店を出た。
次に「大阪屋」へ行った時、このことを報告すると、
「そうかもしれないな――」
とおやじさんは言う。
「あいつは学校の優等生だったけど、おれは番長で、よくカツアゲしてたからなあ――」
サッパリした江戸っ子で、しかし苦労人らしい温厚なおやじさんだったが、若い頃は相当の暴れん坊だったことが判明した。
わたしはその後も福島へ行くたびに、千住、三ノ輪の昔話を聞いて酒を飲んだが、暴れん坊の旦那も三年前癌で亡くなり、今は奥さんが店を守っている。
(第1回 了)
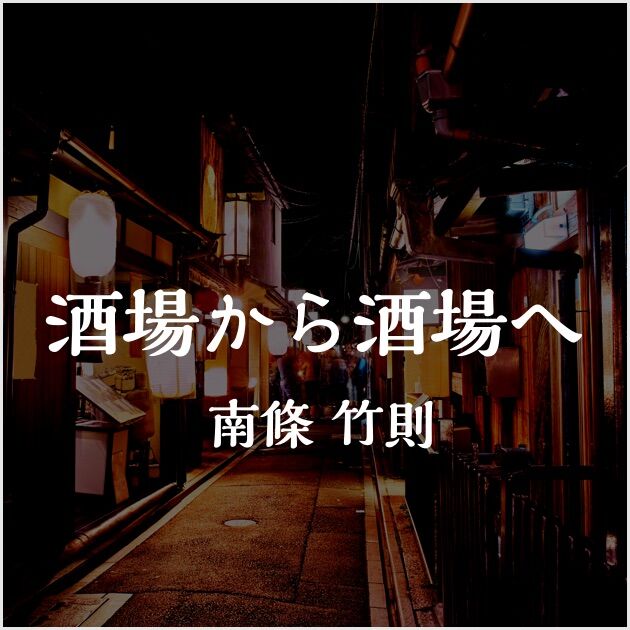
今はない酒場、幻の居酒屋……。酒飲みにとって、かつて訪ねた店の面影はいつまでも消えることなく脳裏に刻まれている。思えばここ四半世紀、味のある居酒屋は次々に姿を消してしまった。在りし日の酒場に思いを馳せながら綴る、南條流「酒飲みの履歴書」。
プロフィール



 南條竹則
南條竹則










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


