2024年4月以来、累計30万部を突破し、多くの人々に広まった『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』。著者の三宅香帆氏は、執筆活動のみならず、テレビをはじめとしたメディア出演YouTubeなどの発信を通して、読書や人文知の面白さを伝えることを模索している。
本記事では「プレバト!!」や「林先生が驚く初耳学(現在は日曜日の初耳学)」などの知見に満ちたゴールデン番組を手がけてきた毎日放送の水野雅之氏とともに、視聴者・読者との向き合い方を考える。
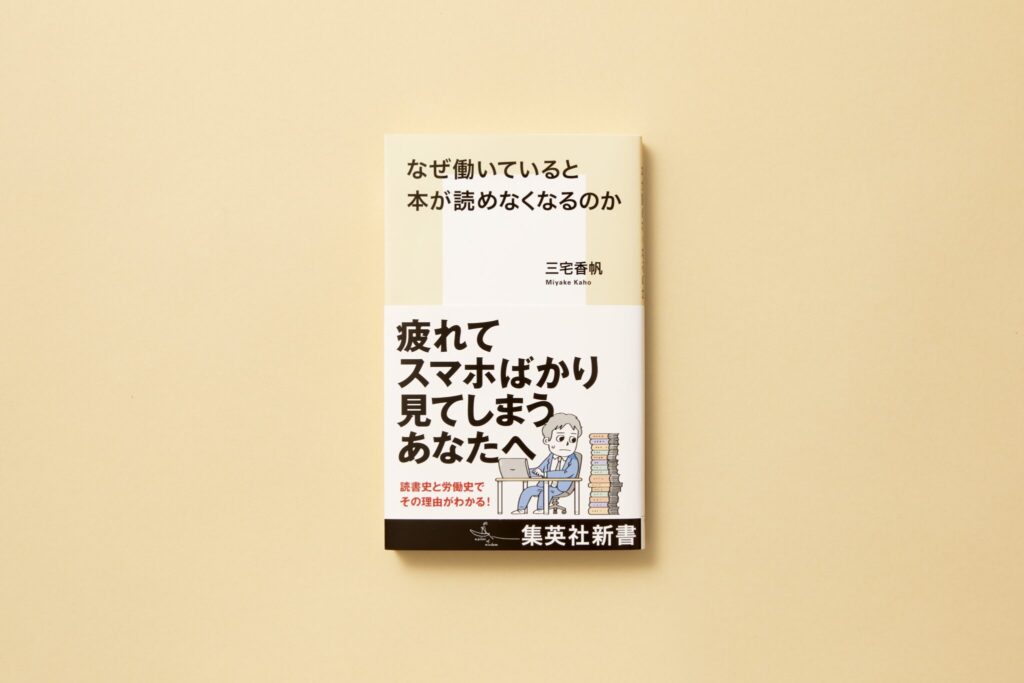
現代における「届くコンテンツ」の作りかた
三宅 今日はよろしくお願いします。『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の刊行から1年間、色々な方と対談をしているんですが、その中で、私も出演させていただいている『プレバト!!』の総合演出である水野雅之さんにお声がけさせていただきました。
水野 ありがとうございます。
三宅 『プレバト!!』に出ていつも思っていることが、視聴率が100%ぐらいあるんじゃないかということで(笑) 友達や親の知り合いまで、老若男女が見ていて感想を言ってくれるんです。今の時代、こういう番組はなかなか珍しいと思います。
私自身、コンテンツの作り手として自分の作品をどのようにマスに届けていけるのかをいつも考えているので「現代において広く届くコンテンツをどう作るのか」をテーマにお話しできればと思っています。
水野 よろしくお願いします。どんなことでも聞いてください(笑)
三宅 ありがとうございます(笑) そもそも『プレバト!!』はどういう経緯で作られたんですか?
水野 実は最初は、浜田(雅功)さんで番組を作ること、それからその番組を木曜19時〜20時の枠で放送することだけが決まっていたんです。それに対して「やりたいです」と手を挙げて、そこからさまざまなスタッフたちと企画を考えることになりました。
三宅 浜田さんと木曜19時という2つが最初に決まっていたんですね。
水野 そうなんです。それで企画を考えることになったのですが、浜田さんは芸能人の喜怒哀楽を引き出すことに関して随一の方です。スタジオの芸能人に浜田さんがプレッシャーをかけて、その感情を引き出す番組にしようと考えました。
ただ、実はそれ以前に浜田さんは19時の時間帯ではあまりレギュラー番組をお持ちでなかった。つまり、これまでの視聴者層とは違う人たちに番組を見てもらう必要があったんです。具体的に当初予想されていたメインの視聴者は、家にいらっしゃる主婦の方です。
そこで考えたのが、主婦層でも馴染む「知的バラエティー」を「プレッシャーショー」と掛け合わせることにしました。

テレビのサイズ感と「俳句」がぴったりだった
三宅 『プレバト!!』といえば、俳句や水彩画などの作品を評価して才能にランキングを付ける「才能ランキング」が人気ですよね。それは当初から企画されていたんですか?
水野 いや、実は最初の1年間は「漢字の書き順」を扱っていたんです。書き順が分かるかどうかを芸能人に問うていた。これもそこそこ人気だったんですが、問題のストックが尽きちゃって(笑)
同時並行でそれ以外の企画も考えていたんですが、1年間見つからなかったんです。そこで、番組が続くか続かないかの最後の策として「才能ランキング」を企画しました。陸上のアスリート選手が「人の歩き方を見ただけでその人がどれぐらい早く走れるかがわかる」とおっしゃっていたことが記憶に残っていて。「才能」って残酷じゃないですか。無い人はどれだけ努力しても手に入れられないし、ある人はずっと持ち続けられる。それが1回の査定でわかったら面白いので、ドラマチックになるんじゃないかと思ったんです。
三宅 なるほど。「才能」をタネに出演者の方の感情を引き出そうとしたわけですね。
水野 そうです。それで、僕だったら「何を言ってるかわからない」「アートセンスがない」「リズム感が悪い」って言われたくないなと思って、この3つで才能を査定しようと決めて、「何を言っているかわからない」のジャンルもリサーチを始めました。するとあるスタッフが、当時一般人の俳句を容赦無く講評してる夏井いつき先生の映像を持ってきたんです。その姿を見て、「何このおばちゃん! すごすぎる!」となった(笑) そこから即決で俳句企画が動き始めました。
三宅 夏井先生あっての俳句企画だったんですね。
水野 当初は、短歌に著名な先生もいるし有力だったんです。ただ、短歌は31音で、ゴールデンタイムの番組の画面としては文字数が多いんですよね。
三宅 おもしろい……!テレビのサイズ、尺感を意識して「俳句」が選ばれたんですね。水野さんのお話を聞いていると、「テレビ」というメディアにいかに適したコンテンツを作っていくのか、ということに注力されている気がします。

テレビのサイズ感と「俳句」がぴったりだった
水野 文字数以外にもテレビならではの工夫をしています。例えば、スタジオの席がランキング順に並んでいるのもそうです。視聴者が見た瞬間に、この番組がランキング番組だとわかりますよね。そういう瞬間で分かる映像作りが大切だと思います。
三宅 確かに、すぐに番組の趣旨がわかりますよね。
水野 それと、テレビの醍醐味の一つはやはり「感情表現」にあると思うんです。そこを『プレバト‼︎』でもかなり意識しています。
三宅 浜田さんが演出するのがうまい喜怒哀楽ですね。
水野 実は『プレバト!!』って、視聴者からすると「ドラマ」と同じような見方をされているんです。同じ視聴率10%だとしても、多くの人が少しずつ番組を見て視聴率が高い場合と、それより見ている人が少なくても、長い時間番組を見てもらえている場合があります。『プレバト!!』の場合は後者です。つまりコアなファンに支えられていて、その人たちが長時間見てくれている、というのが傾向としてあります。これは、物語をずっと見るドラマの視聴体験と近いんです。
三宅 なるほど。ドラマを見るように『プレバト‼︎』を見ていると。番組の緊張感と感情の起伏を楽しんでいるんですね。
水野 そうなんです。それと、実際に俳句を企画でやってみると、梅沢(富美男)さんや千原ジュニアさん、FUJIWARA藤本(敏史)さんらが俳句にハマってくれて、だんだんと「才能ナシ」から「才能アリ」になっていった。才能がナシからアリに変わるって本来、すごく矛盾してるんですけどね。本来は「一度で才能を査定する」という企画だったので(笑)
三宅 でも、逆に才能アリだった人が才能ナシ、と言われるのも面白かったりしますもんね。それこそドラマチックというか。
水野 そうなんです。視聴者がそうやって言葉の矛盾を許容してくれて、出演者の才能が変わっていくのを楽しんでくれたから、この番組が13年続いていると思っています。
三宅 番組の視聴者層も増えていったんですか?
水野 『プレバト‼︎』のようなコアなファンに支えられている番組の場合、視聴率を高めるために重要なのが、キャスティングです。新しい出演者を増やし、見てくれる母数を増やす必要があります。それでいえば北山(宏光)さんや横尾(渉)さんの活躍は1つのターニングポイントでしたね。この番組でしか見られない彼らの喜怒哀楽があって、そこを見てくれる人が多かった。

感情を生み出すフレームを作る
三宅 視聴者の「感情」をコントロールするのって、文章や本でもすごく重要だと思っています。ただ、文章だと書いた後で読み返して推敲できるのですが、映像はそれをコントロールするのがすごく難しいですよね。私自身、YouTubeをやっているので、それを痛感します。番組の演出では、そうした「感情」の演出をどのようにされているのかが気になります。
水野 感情を無理に演出しようとするのではなくて、出演者の感情が一番出る作り方を考えているだけなんです。スタッフが番組のフレームをしっかり作って浜田さんがショーアップしたら、芸能人たちの感情は絶対に画面に映ります。視聴者が一番ドキドキするのは、作り手である僕らもドキドキするときなんですよね。
三宅 確かに、はじめて番組に出て驚いたのは、あれ、ランキングもなにも演者に知らされていないんですよね(笑) それで収録はカットがあまりなくて、ライブみたいに進んでいきますもんね。
水野 そうですね、生放送でも放送できるくらいのものを毎回収録しています。
「面積の最大化」をせよ
水野 僕はテレビに限らず、コンテンツ制作においては「面積最大化論」のイメージを持っています。それは視聴率のグラフを面積で考えてそれをなるべく最大にする、ということです。例えば『プレバト‼︎』が放送されている19時から20時の場合は、人が家に帰り始める時間で視聴人数は段々と上がっていきます。その中でどれだけこのグラフの面積を最大にできるかが重要になってくる。
三宅 面白い。視聴率のグラフを面積で考えられてるんですね。
水野 これは、曜日や時間帯によっても変わります。例えば、『初耳学』は日曜22時からの放送です。そうすると、その時間帯はだんだんと人がテレビの前から離れる時間なんです。だから面積最大化のイメージも変わる。つまり、なるべく人が離脱しないように最初にピークを作ろうと考えるんです。僕が演出していたときは22時1分にピークを設定していた。最初に「いったい、これってどういうことなんだろう?」とその日の雑学で最も興味深いものを提示して、その後も次々と雑学を繰り出して、なるべく長く見てもらうわけです。ただ番組を続けて3年くらいが経つと、ネットにも「雑学」がたくさん出るようになったんです。言葉の強さや刺激性という点では勝てないと思い、「熱血授業」とか「アンミカ先生のパリコレ学」といった感情を揺さぶる企画を投入しました。
三宅 水野さんは、新木優子さんのYouTubeも手がけられているじゃないですか。テレビとYouTubeの面積でも変わってきますよね。
水野 YouTubeだと途中から見ることはないので、最初に見た人たちの離脱をどのように食い止めるのか、つまり視聴率100から始まるグラフの傾きをいかに緩やかにするかが面積を最大化させる方法になります。だから、フリは要らない。出し惜しみすることなく強い映像から出して離脱させないようにする。どんなプラットフォームでコンテンツを作るのかによって、面積の考え方も変わってきますね。
それでいうと、本はどんな面積になるんでしょうかね?
三宅 本はタイトルでどんな人をどれぐらい集められるのかが決まる気がします。それと本文でも、特に離脱ポイントになりそうなところがあれば、そこに面白いツッコミを入れたりして離脱させないようにする。息継ぎさせないというか、それが大事な気がしています。
水野 三宅さんの文章、離脱させないですよね。変な引っ掛かりがないと思う。その意味では文章の構成の仕方はテレビと近い気もしますね。ただ、例えば『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を地上波テレビの視聴率グラフで面積を最大化してください、といわれたら、本で書かれたような「時系列で読書史と労働史を振り返る」というのとは違う構成にしていたかもしれません。
三宅 わかります。私がビジネス書の作家だとしたら、トピックごとに章を分けて、結論ももっと早く書いて……としていました。それこそ最初『花束みたいな恋をした』という映画の話から始まるのは、読者を離脱させるポイントになる可能性があるんです。あの本の構成は、なんというか自分の中では面白いマンガを読んでいるような感覚を再現したいという感覚があってそうしたんですよね。

「楽しませたい」が先にあった
三宅 今までのお話を聞いていて、水野さんは特に「伝える/伝わる」というところで番組を考えていらっしゃると思いました。そういう考えを持つに至った原体験はどこにあるんですか?
水野 そもそも、僕は最初はテレビ業界志望ではなかったんですよね。部活は野球部であまりテレビっ子ではなかった(笑)どちらかといえば「多くの人を楽しませたい」というのがずっと持っているモチベーションなんです。それが叶えられる一番大きいフィールドが当時は地上波テレビだった。
三宅 なるほど。「テレビ」が先というよりも「楽しませたい」が先にあると。だからいわゆる「テレビの常識」に囚われない番組が作れるんでしょうね。
水野 さらに考えてみると、大学のときのオープンゼミで下級生に自分の研究を発表する、という機会があって、ぼくはリサーチ結果自体の発表より、それを「ショー」として見せてみたんです。オープンゼミはゼミの雰囲気が伝われば成功ですから。
そしたらすごく評判がよくて。その体験が、創作の原動力にあるかもしれない。思えば、テレビのディレクターがつないだVTRをチェックするときも、僕らの目的はリサーチ報告ではなく、楽しんでもらうことだからね、ということがありますね。
三宅 そこの「伝える楽しさ」が今の活動でも活きてるのかもしれません。
(後編に続く)

(構成:谷頭和希 撮影:内藤サトル)
プロフィール

みやけ かほ
文芸評論家。1994年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集)。累計発行部数30万部(電子版含む)突破のベストセラー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)が、新書ノンフィクションベストセラーランキング1位(日販・トーハン・オリコン)を獲得したほか、「新書大賞2025」「第2回書店員が選ぶノンフィクション大賞」「ビジネス書グランプリ2025リベラルアーツ部門賞」を受賞した。そのほかの著作に『「好き」を言語化する技術』『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』『人生を狂わす名著50』など多数。
みずの まさゆき プロデューサー・演出家。愛知県春日井市出身。慶應義塾大学商学部卒業後2000年に毎日放送入社。現在は「プレバト!!」の総合演出を担当。「林先生の初耳学」「教えてもらう前と後」の企画、演出、プロデューサーとして現在のゴールデン・プライム帯における毎日放送制作の全番組を手がける。
『プレバト!!』と『初耳学』はなぜ老若男女に愛されるのか?知る楽しさの届け方を文芸評論家・三宅香帆と番組総合演出・水野雅之が考える


 三宅香帆×水野雅之
三宅香帆×水野雅之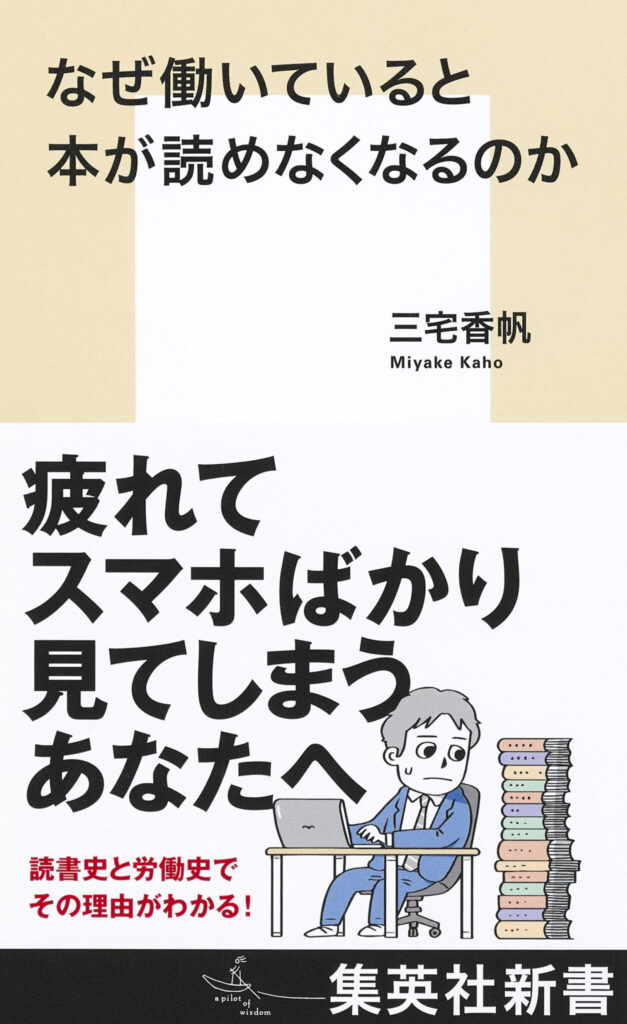










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


