「コンサル」という職業がもてはやされ、「転職でキャリアと年収をアップ」「ポータブルスキルを身につけろ」などの勇ましい言葉がビジネスパーソンに浴びせられる背景を分析し話題を呼んでいる『東大生はなぜコンサルを目指すのか』。
本記事では著者のレジー氏と『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』や『好きを言語化する技術』などのベストセラーで知られる文芸評論家・三宅香帆氏の対話を通して、昨今のコンサルや言語化のブームからアイドルやリアリティーショーのトレンドまでを考える。
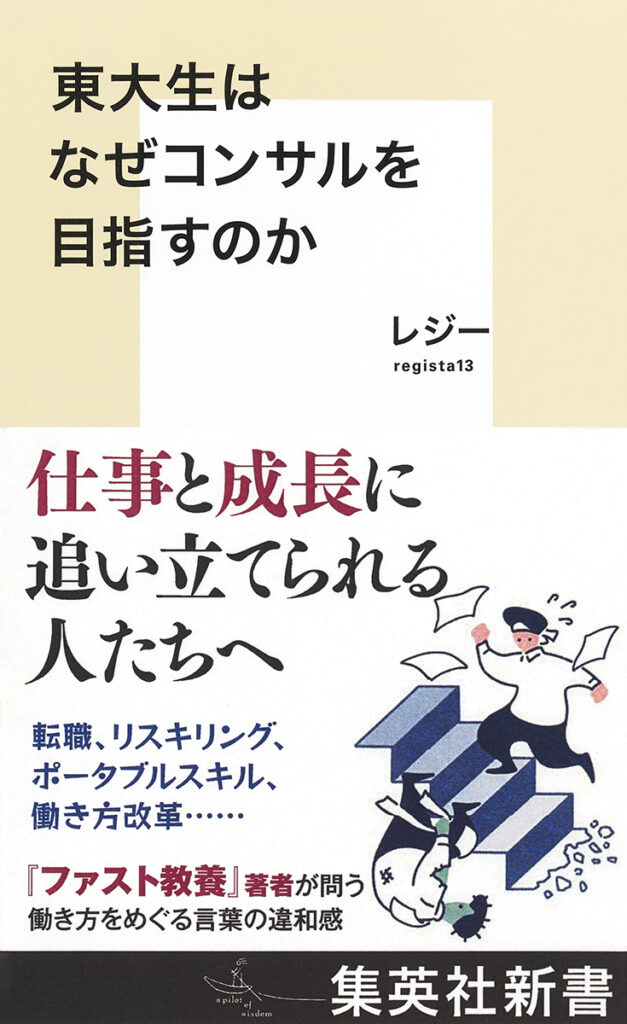
「コントロールしてる感」が時代のアイコンに
三宅 『東大生はなぜコンサルを目指すのか』だと令和ロマンさんをはじめとした大学のお笑いサークルの話と、IT化する音楽業界の話がめちゃくちゃ面白かったです。どちらもM-1やSpotifyの再生回数といった競技に巻き込まれざるを得ない構造が生まれている。本来、お笑いや音楽は競争じゃない楽しさを求めるものだけど、そうした業界にも競争とか成長という考え方が入り込んできているんだなと。
それと、私はアイドルが好きなので、アイドルカルチャーにも注目して成長について書いていることが嬉しかったです。私の持論ですが、ビジネスの世界の構図がそのままアイドルの世界でも見られるような気がしています。AKB48が日本の伝統的な大企業だとすれば、その中から独立した指原莉乃さんや宮脇咲良さんは外資系企業に就職したようなイメージで。本の内容から離れますが、timeleszの菊池風磨さんなんかは、私の周りでは慶應卒のベンチャー社長だ……って言われてます(笑)
レジー 2010年代のアイドルブームのころには、アイドルが体現する「成長」を仕事で成長することに重ね合わせて語る人が多かったですよね。
三宅 それこそ、本で書かれていたように、LE SSERAFIMの宮脇咲良さんがAKBグループでキャリアをスタートさせてからこんな世界的大スターになるなんてかつては想像していなかったです。
レジー そうですよね。彼女に関してはHKT48時代にはAKB総選挙で投票していたくらいに昔から好きなのですが、その足跡は今回の本で書いたような成長という文脈にピタッと当てはまると思ったので、しっかりめに言及しました。HKT48からIZ*ONE、そこからHYBEに移籍してLE SSERAFIMへ、というストーリーはわかりやすい「キャリアアップ」ですよね。でも、その意味やすごさが意外とあんまりちゃんと語られていなかったなと。
三宅 そういう意味ではイチローさんもそうですけど、きっと、時代によって語りやすいアイコンってあるんでしょうね。
レジー 今だと圧倒的に大谷翔平ですよね。
三宅 最近テレビのコメンテーターをやることも増えたんですが、いつ出ても大谷さんの話題をしている。もう毎日、何らかの大谷ニュースを作ってるんじゃないかと思うほどで(笑)
レジー 大谷翔平の「野球のために生きている」みたいなストイックさ、それに加えての品行方正な感じが今の時代のひとつの「正解」なんですかね。生真面目に何かを頑張ることが価値を持つ、というか。
三宅 私も同じことを思っています。大谷選手の「コントロールできてる感」みたいなところにみんな惹かれてるんじゃないかと思ってるんですよ。そういう意味では、令和ロマンさんの人気もそこにある気がします。「安定としての成長」を求める人たちのニーズにすごく合ってるというか、やみくもに成長するのではなくて、狙ってポジションを取っていく、というところにニーズがある気がします。逆に宮脇咲良さんはがむしゃらに頑張ってHYBEを勝ち取った感じがするのと対照的です。安定感のある成長が好かれるのかな、とふと思いました。
レジー 「コントロールできてる感」は言いえて妙ですね。宮脇咲良も自分のできることとできないことを見定めて今のポジションに到達した側面もあるので、大きくはこの括りに入れられるかもしれません。少し前までエンタメの世界では戦略的にやっていることをことさらに語るのはどちらかというと恥ずかしいという雰囲気があったと思うんですけど、今はかなり変わっていますよね。
三宅 本当にそうです。それこそBE:FIRSTも、もはやマネージャーまで含めた裏を全部見せます、みたいになっていますしね。

不確実性に耐えられない世の中
レジー 「人生をコントロールしたい欲」は各所でかなり強まっていますよね。特に仕事の文脈で「成長したい」というと「年収上げたい」とか「いいところに転職したい」ということになるけど、それを達成するにはある程度長期のキャリアプランを計画しないといけなくて、それはコントロール欲求の最たるものですよね。それを、大谷翔平も令和ロマンも体現している。
三宅 大谷翔平さんに娘が生まれたとき、彼が高校生のときに書いた年表が当たっている、と言う人がいて。でも、実際は年表どおりではないんです。第二子を生む、と書いた年齢で第一子が生まれているので。ただ、年表どおりだと言う人がいること自体、戦略的に成長をしてる人を見たい欲求があると思いました。
レジー それこそ、今だと高校でキャリア教育が行われていたりもして、未来をコントロール下に置こうとする傾向がどんどん入り込んでいますよね。高校生向けの本を見ると、大学に入るところから就活は始まっている、ぐらいのことが書いてあってびっくりしました。
三宅 今は昔よりペーパーテストの比重が下がっていて、かつてはAO入試と呼ばれていた総合型選抜も入試で重要になってきてますよね。そこでは志望動機書を書いたり、面接で志望理由を話したり……という就活的な要素が強くなっていて、まさに「未来のコントロール」を求められています。とにかく学力を上げればいいわけではなくなってきていて、世知辛い。
レジー そうですよね。学力じゃないことも含めた選抜になると、それこそ体験格差の話にもつながってくるから難しい問題です。
三宅 とはいえ、長期スパンで見ればそのコントロールを外れる不確実なことは絶対に起こるじゃないですか。個人の人生でも社会でも。けれど、その不確実さに耐えられない感覚は社会全体で共有されていますよね。
レジー そうですね。コントロール欲、不確実性への耐性、人生における「戦略的なアクション」の価値の高まり、すべてつながっていると思います。

「教養」よりも「頭がいい」へ
三宅 安達裕哉さんの『頭がいい人が話す前に考えてること』もすごく売れてるじゃないですか。あの本自体は、書いてあることはすごくまっとうだと思うんです。一方で最近は「頭がいい」とか「ばかじゃない」みたいなことがすごく重要になってきている気がして。書籍のタイトルでも多いし、ウェブ記事とかでもそういう表現をすごく見るな、と思っていて。
レジー 「教養としての○○」みたいなタイトルよりも、今はそちらの方が増えている感じですよね。
三宅 そうそう。ビジネス書は、売れた本の類書が増えるのはよくあるのですが、とはいえ「ばかだと思われない」ことを求めている人が多いんじゃないかと思えてくるんです。「成長」と言うときに、頭がいいことへの、しかも本質的な頭のよさというより、数字で測れたりクイズが解けたり、みたいなレベルの頭の良さや論理的思考への欲求が上がってる気がします。
この間『チ。』の作者である魚豊さんと対談して、その話になったんです。魚豊さんは、かつて頭の良さを示すものは「本を読んでいる」とか「教養がある」ことだったけど、今はもはや東大生がクイズを解いてそれを示す時代ですよね、とおっしゃっていて。
だからもはや「ファスト教養」でさえなくて、もっと数値化された何かがあるとか、実業家として何かの企業を成功させたみたいなことで「賢さ」が測られてる気がすると思っていて。
レジー なるほど。お笑いや音楽が競技化している話とも近い気がしますね。測れるものがが重要になってきていると。
三宅 それこそ、『頭がいい人が話す前に考えてること:って、昔だったら絶対に佐藤優さんが書いてたじゃないですか(笑) あるいは立花隆さんみたいに知の巨人系の人が。
レジー 確かにそうですね。「頭がいい人」と自分で名乗るわけですし。
三宅 それを、今はコンサルの人が書く。それがすごく象徴的だと思いますね。
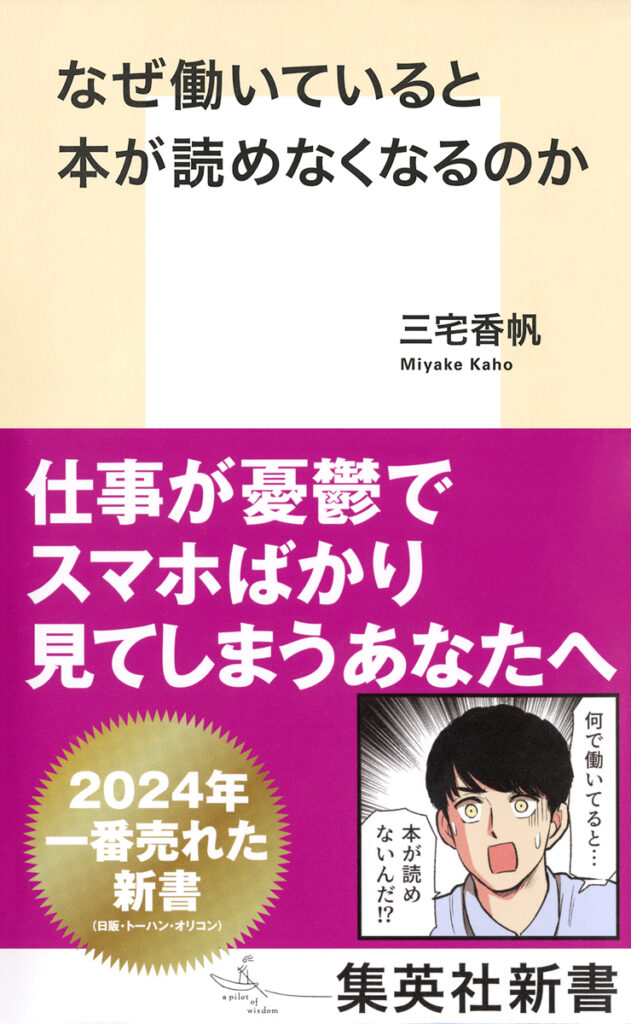
言語化ブームは「構造化」への欲求だ
レジー 『頭がいい人が話す前に考えてること』で一貫して語られているのはある種の「フレームワーク」だと思っていて、そこがとてもコンサルの人の書いた本っぽいなと感じました。フレームワークは大事なのですが、一方でフレームワークがあっても中身がだめだったら意味がないんじゃないかなというのが僕の意見です。でも、最近は中身を学ぶためではなく枠組みを学ぶために本を読む傾向が強くなっているように見えます。その枠組みを振りかざして何かを整理する、あるいは論破することが「頭がいい」となっている。
読書という行為に期待される効用が「何か新しいことを知る」よりも「考え方を学ぶ」ほうに価値がシフトしていると思います。
三宅 すごくわかります。それで思うのが、多くの人が「言語化」で求めているのは私が思う言語化というよりも「構造化」なんですよ。整理したい、という欲求。
レジー 確かに。最近「言語化」という表現が氾濫していると思いますが、「情報をそぎ落として言いたいことを伝える」みたいに使われるケースもありますよね。これはまさに整理にほかならない。その話は僕の本ともつながっていて、多くの人がコンサルに行く理由のひとつに、なんでも整理ができるフレームワークを身につけたいという期待がありそうだなと。
三宅 そういうことですよね。そのフレームワークを持つことが「頭がいい」と思われている。
レジー 仕事の中で何かを整理する場面は多いですが、コンサルの仕事は特にそこに重きが置かれているというパブリックイメージもあるように思うので、そういう部分も職業として今の時代に人気になる理由なんだな、と腑に落ちましたね。
一方で、「言語化=整理」という文脈で話しましたが、三宅さんが提示されている「言語化」にはただ情報を整理すること以上の意味合いが込められていると思います。
三宅 感想に必要なのは、確かに整理ではあると思うんです。私的には、「言語化」というと、例えば名づけられてないものを名づけることが大事な気がしています。例えば、令和ロマンさんのくるまさんの本は、漫才というこれまであまり言語化されていなかったものを整理しているから面白い。
世間で求められている言語化は簡単な言い換えみたいになっていて、情報のノイズを落とすことを示している気がします。割とみんなが言っていることを言い換えたことが言語化だといわれることもあると思って。それは単にシンプルにしただけでは、と思うときもある(笑)
レジー 言葉になってないことを言葉にするから言語化なわけで、ただシンプルにするのとは違いますよね。
三宅 本来はそうなんです。
レジー それこそ「批評」と言われているものが、三宅さんのおっしゃっている言語化の本質だと思います。
三宅 まさにそうですね。批評を読んでいて面白い瞬間って、この現象に名前が付いていたんだ、と思うときなんです。あるいは何かの作品を見て、そこにこういう構造があったんだと思うこと。じゃあ、フレームワークを会得すればそれができるかといえば、それではできない。
レジーさんの『ファスト教養』も、みんながうっすら思っていた「教養の蔓延」を言語化したものですよね。
レジー 『ファスト教養』をきっかけに「教養本」が減ったんじゃないかと出版社の人に言われたことがあります。本当にそうなのかはわかりませんが(笑)
三宅 次は『東大生はなぜコンサルを目指すのか』で東大生のコンサル志望率が下がったら面白いですね(笑)
(構成:谷頭和希)
プロフィール

レジー
批評家・会社員。1981年生まれ。一般企業で経営戦略およびマーケティング関連のキャリアを積みながら、日本のポップカルチャーについての論考を各種媒体で発信。著書に新書大賞2023入賞作『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』(集英社新書)のほか、『増補版 夏フェス革命 -音楽が変わる、社会が変わる-』(blueprint)、『日本代表とMr.Children』(ソル・メディア、宇野維正との共著)。X(旧Twitter) : @regista13
みやけ・かほ
文芸評論家。1994年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集)。累計発行部数30万部突破のベストセラー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、新書ノンフィクションベストセラーランキング1位(日販・トーハン・オリコン)を獲得したほか、「新書大賞2025」「第2回書店員が選ぶノンフィクション大賞」「ビジネス書グランプリ2025リベラルアーツ部門賞」を受賞した。そのほかの著作に『「好き」を言語化する技術』『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』『人生を狂わす名著50』など多数。


 レジー×三宅香帆
レジー×三宅香帆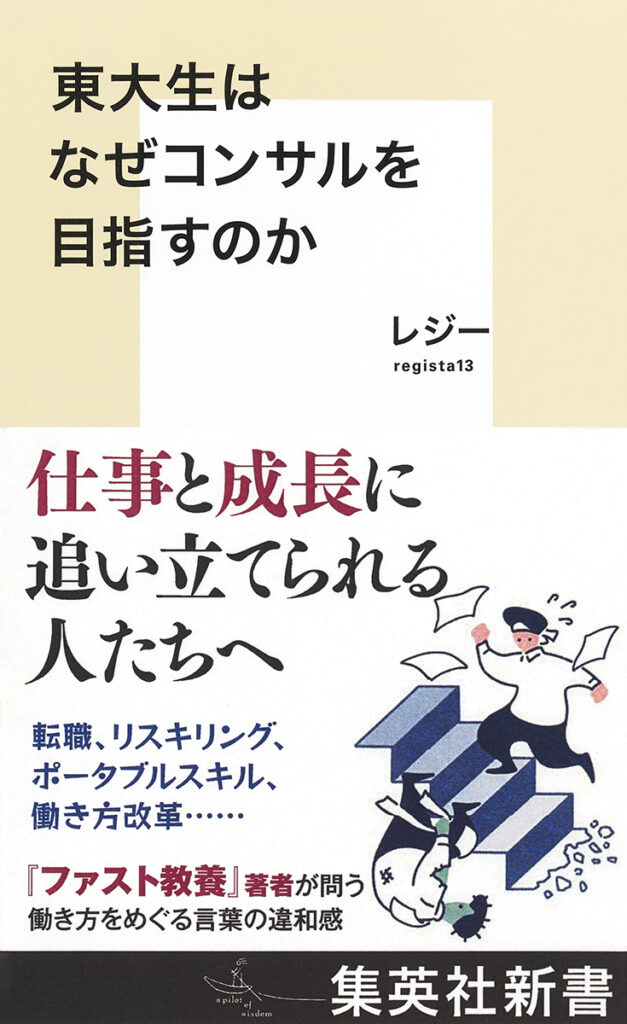










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


