こんな世界は一旦破綻するしかない…
久保 僕が定年退職したら、海外とのジョイントセミナーで一緒に話した外国の教育関係者の人たちが、お祝いのメッセージくれはったんですが、その中で、やっぱりあれは放置したらあかんと言われたんです。僕が受けた文書訓告は、軽いものや言うてもパニッシュメント(刑罰)はパニッシュメントやから、そのまま残したら未来の教育のために絶対良くない。権力がある人に意見を言っただけで処分されて、僕が黙ってしまったら、もう若い先生たちにもそういうメッセージになるし、子どもたちも、もうそういうことはしちゃいけないことなんだって思ってしまう。だから何かやっぱアクションしなあかんっていうことを言われたんです。
鈴木 なるほど、それでその「ガッツせんべい応援団」っていうのは、主に久保先生に対する文書訓告に抗うためにできたんですね。
久保 そうです。僕は、ベテラン教師の大先輩の方に「提言書は君の教師としての卒業論文やね」って言われてうれしくなって、「じゃあ、僕がもらった文書訓告は、卒業論文の合格通知ですね」とか言ったら、えらい先輩方から怒られて(苦笑)。いや、まわりがその処分に憤ってるのに、本人がそんなこと言ってもらったらあかんと。この処分を看過せずに闘おう、自分たちも応援するからと言っていただいて、「ガッツせんべい応援団」が生まれました。
辻野先生や志水博子さんはじめ、最初に9人ぐらいでつくってくれはって、弁護士会に人権侵害救済申し立てをして、それを基に教育委員会と協議を重ねていくという流れになったんです。別に会則や事務局があるわけでもないんですけども、ゆるやかなネットワークで教員以外の方にも広がっていますね。
鈴木 本当に面白い「遊び」と「すきま」の広がり方ですね。そもそも何であの提言書を書かれたかっていったら、「あのまま黙っていては自分のアイデンティティーが壊れてしまうと思った」っておっしゃったじゃないですか。

久保 最初はテレビで松井市長がいきなりオンラインにするとか言われたことに対して、それがいかに子どもや保護者、教師にとって大変なことなのか、「市民の声」窓口なんかにメールで現場の声を届けていたんです。だけど、いや自分が本当に伝えるべきは、それだけじゃなかったんやないか、と思い至ったんです。「結局は僕自身が実は行政の教育への理不尽な介入に気づきながらも、もうしんどくなるから思考を停止して何も言わずにいたんやないか。結局はこの事態を招いたのは、自分もその一人なんや」ってすごく思ったんですよね。このまま何も言わずに定年を迎えたら、僕自身は自らの手で、自分の37年間の教師生活をなかったもんにしてしまうんやないか。子どもたちにも、「いや、たった1人の意見でも勇気を持って発言しよう」「それを受け止めるのが、クラスなんやから」とか、「嫌なことは嫌って言っていいねんで」とか言っときながら、自分がそれをせずにやめてしまうっていうことは、僕を育ててくれた子どもたちや保護者に対する裏切りやないかと思ったんです。
鈴木 久保さんの37年の教員生活の発端はどういうものだったのでしょう。
久保 僕の教員生活は、大阪の同和教育から始まったんです。被差別部落の子どもたちが学校に来られていない、また在日外国人の子たちも来られてない、そして障がいのある子たちも「就学猶予」とか「免除」とかいう体のいい言葉で排除されてるみたいなとこに、教員たちが気付いて動き出していたんです。子どもたちの教育を受ける権利を担保させて、自分たちもそこにコミットしてやっていくんや、という大阪の教育者の価値観の中で育ててもらった。そのことに僕は多分、誇りを持ってたんやと思うんですね。それが、僕のアイデンティティーで、提言書を出したんは、そういう大阪の教育が消滅しかけている、自分がもう自分でなくなってしまうことを、自分が気づいたんだと改めて思いました。
鈴木 お話をうかがっていると、大阪が大事にしてきた教育というのは、弱者に寄り添う教育だったんですね。その大阪で、維新的な新自由主義がなぜここまで拡大したのかというのは、ずっと考えてきたんです。生活保護とか、怠け者に対する保護ばっかりだと言って弱者をバッシングする、そういう自己責任論、能力主義というのが、何で大阪で起こってきたのか。そう考えた時に、商人の町だったからなのかなと思ったんです。それこそ、モノ、カネっていう価値観が強かったからなのかなと考えていたら、この対談をしている隆祥館書店の店主の二村さんから、そうじゃないと言われました。大阪の商人ってのは、そんながつがつしてるんじゃなくて、もっと人情味があって、それこそ、あうんの呼吸でやってくるような、そういう商売だったはずなのに、みたいなことをおっしゃったので、自分の中で勘違いがあったなと考えをあらためたのですが、久保さんはどうお考えですか。何で大阪で新自由主義だったのか。
久保 確かに大阪って、二村さんの言うように儲けるだけでなくて、義理人情での助け合いや繋がりがあったと思うんですよ。だから、子どもたち一人一人を大事にしていこうっていう教育について、かなり多くの人たちが共感してたんやと思います。でも、この30年、日本経済がおかしいじゃないですか。労働力がその中ですごく安く買いたたかれて停滞していった。大阪はもともと低所得者世帯が多いと思うんですが、それがほんまに生活が苦しくなっていく中で、橋下(徹)さんなんかによる「怠けて努力せずに、弱者のふりして税金で助けられてる人がいっぱいいてるんですよ」みたいなアピールがあって、そんなとこに多くの人が流されてしまった。豊かさの軸みたいなんを、そっち側へ全部ずらされてしまったんやないかなと思うんです。人生はお金だけじゃないでって、豊かに暮らしてた人たちが、お金じゃないと豊かになられへんという価値観に連れていかれてしまった。
鈴木 じゃあ、ほんとにアメリカで起こったことと似ているのかもしれませんね。それこそ、全社会的に新自由主義というものがじわじわ広がって、ミドルクラスというものがどんどん縮小していった。それで、弱者に対する保護の厚かった大阪で、それへの反動がばんと出たっていうような感じですかね。
久保 だから、何か豊かさみたいなものの価値観が変わって、まさにミヒャエル・エンデの『モモ』の世界ですよ。時間に追われて人間らしさを忘れていく『モモ』の話なんか、ほんまにそのまま日本の状況になっているとすごい感じます。
鈴木 ほんと、『モモ』はタイムレスですね。僕も、今回の本を書くに当たって何十年かぶりに『モモ』を読み直したところです。
それで今、その「ガッツせんべい応援団」の取り組みはどうなっていますか。
久保 大阪市の特別顧問をしている東北大学教授をしている大森不二雄さんという人がいたんですが、この人の問題をやっています。大森さんと市教委の幹部職員との間のメールを開示請求したら、大森さんから、「久保の処分はこうしろ」「朝日新聞に記事が載ったからこう動け」「チャレンジテストをさっさとやらせろ」「動きが悪いと吉村知事に言うぞ」というような文言が並んでいて、大阪の市教委はすべては大森顧問の指示通りに動いていたことが判明したんです。大森さんについては、ジャーナリストの木村元彦さんや永尾俊彦さんが取材を申し込んでいるんですが、受けずに逃げています。
鈴木 僕が気になるのは、大森さんは、大阪市の特別顧問ですが、大阪市で首長に任命された5人の教育委員の存在はいったい何なのかということになりますね。独立性が担保されないといけない教育委員会が、東北にいるたったひとりの顧問の意向で動かされているというのが、本当に気になるんです。
久保 そうなんです。ほんで、教育委員会会議とかもほとんど非公開で、その議事録なんかも出て来ないんですね。何がどう決められていったのか、分からない。

鈴木 それは教育委員会の原則公開とその議事録公開の努力義務を定める『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』違反ですよね。
久保 そういうのも含めて「ガッツせんべい応援団」でだいぶん追及をして来たんです。「どんな議論がなされたんですか」って言うても、「いや、そこはもうお答えできへん」みたいな繰り返しになっています。
鈴木 教育委員会の議事録がまだできてないとするじゃないですか。でも音声があるから、議事録は作れる。その音声も開示請求の対象になるんですよ。なので、その音声をまずは手に入れちゃったほうが早いかもしれませんね。実際に僕は土佐町の教育委員会で、全国学力調査の参加依頼に応じるか否かっていうのを議論した教育委員会の音声を求めたんです。そしたら、教育長がそれは開示できないと言ってきたんですけども、弁護士に相談して調べたら、音声も開示請求の対象になる公開公文書だっていう判決があったので出させることができたんです。
やっぱり、お聞きしていると、大阪市の合議制執行機関としての教育委員会は機能していない。だから、政治からの教育への介入の歯止めとなってないっていうのが、根本にあると感じました。
久保 もう、おっしゃるとおりです。だから僕らも「いや、教育委員さんたちは何て言ってるのか」「僕の提言書とかも教育委員さんにちゃんと渡してくれてんのか」と問い詰めるんですが、全然動いていないようです。それでこれは議会に陳情も出さなあかんとなって、全会派の議員さんに話を聞いてもらった。すると、やっぱりそれは効果ありました。維新の議員さんも、こういうメールのやりとりっていうのは、どう見ても大森さん自身が決定権者のように見えるから、特別顧問の仕事って何なのかを明確にするように教育委員会に伝えとく、と言ってくれました。すべての会派の議員さんが、質問に立ってくれて、要するに民主主義っていうのは、こういうことなんやなと思いました。子どもらにもちゃんと教えなあかんし、そういうことが民主主義を守っていくっていうことだと「ガッツせんべい応援団」の活躍で知りました。
鈴木 僕も議員として仕事をしていて、つくづく恐ろしいと思ったのは、コロナ禍における安倍首相時代の全国一斉休校要請に対する反応です。単なる一首相によるまったく拘束力のないお願いに、全国の小中学校の99%、高校の98.8%が呼応した。従順に従ったという点です。感染症などで、学校を休みにする権限は首相にはなく、文科省にもない。教育委員会なのですが、それを大阪が、真っ先に休校にすると言った。僕は電話で確認しましたが、臨時の教育委員会は開かれていなかった。
戦時中、政治が教育に介入し、教育が戦争に加担してしまった苦い歴史に対する反省から、政治と一線を隔し、政治介入の歯止めとなるために教育委員会が作られたのに、その教育委員会が機能せずに首相の単なるお願いに右向け右で従っていた。
それをわれわれがちゃんとチェックできていないという問題もあると思うんです。先ほども話しましたが、合議制執行機関であるはずの教育委員会が政治からの介入の歯止めになってるかどうか。その機能をこれからは市民がしっかりとチェックする。教育における地方自治と民主主義の再生、これが求められているのだとつくづく思います。
対談がひとしきり終わると、会場から興味深い質問が出た。ナショナルブランドの大企業に勤めていたという参加者による体験を踏まえた問いであった。
「私自身が新自由主義の先頭に立っていた人間です。そこで疑問に思うこともあります。けれども今の社会では、経営者も個人も反自由主義的な態度を取っていたら生き残れないのです。どういう世界を目指すのか? 私は新自由主義が良くないと思っているが、個人の力ではどうしようもない。残念ながら。変えるには、一旦破綻するしかないのではと思っています。どのように考えていますか?」
これに対して鈴木大裕は、こう応えた。
「僕も、一旦破綻するしかないと思っています。資本主義があまりにも暴走してバランスが取れなくなってしまっている。『豊かさ』の概念があまりにも狭くなってしまっているのでその再定義が必要です。どこどこの良い大学を出て、いくらいくらの年収…それが『豊かさ』の定義になってしまっている。本を読むことの豊かさ、自然に触れることの豊かさ、そんなものに価値が見いだされない。僕が土佐町に移ったのも、モノ・カネに支配された世の中に対するアンチテーゼは都会からは生まれないのではないかと思ったからなんです。お金では買えない豊かさに溢れた地方から、『豊かさ』の再定義を図りたいと思っています」
取材・文/木村元彦 撮影/新書編集部
プロフィール
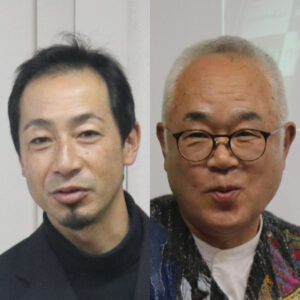
鈴木大裕(すずき・だいゆう)
1973年、神奈川県生まれ。教育研究者。16歳で渡米し、1997年コルゲート大学教育学部卒業、1999年スタンフォ―ド大学教育大学院修了。帰国後、千葉市の公立中学校で英語教師として勤務。2008年に再渡米し、コロンビア大学教育大学院博士課程で学ぶ。2016年、高知県土佐町へ移住、2019年に町議会議員となり、教育を通した町おこしを目指しつつ、執筆や講演活動を行なっている。著書に『崩壊するアメリカの公教育 日本への警告』(岩波書店)など。
久保敬(くぼ・たかし)
1961年大阪府枚方市生まれ。 1985年大阪市立啓発小学校に新卒で赴任。 2006年大阪市教育センター指導主事、2010年大阪市立波除小学校教頭、2013年大阪市教育センター総括指導主事、2016年大阪市立生野南小学校長、2018年大阪市立木川南小学校長。同小学校在任中、コロナ感染拡大防止のため全面オンライン授業の実施を指示した松井一郎大阪市長に対して、2021年5月17日、学校現場が混乱しているとして「提言書」を送付する。教育公務員としての職の信用を傷つけたとして、2021年8月20日、「文書訓告」の処分を受ける。2022年3月31日 定年退職。


 鈴木大裕×久保敬
鈴木大裕×久保敬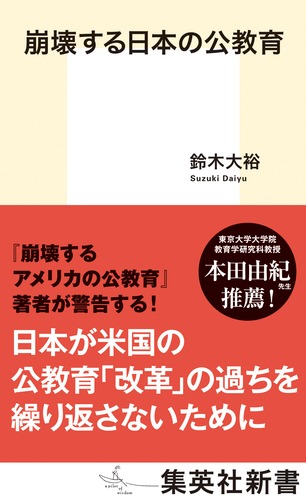










 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
 小島鉄平×塚原龍雲
小島鉄平×塚原龍雲


