日本がコロナ禍にあえいでいた2021年4月19日。松井一郎大阪市長が定例記者会見で、「緊急事態宣言が出されたら、大阪市の小中学校はすべてオンライン授業にする」と突然、宣言した。これについては教育委員会も何も知らされておらず、そもそも約420校ある学校の中では端末や回線が整っていないところもあり、実施はかなり困難な状態だった。
市教委を通さず、議事録も残されない中でのメディアを通したいきなりの発表は、首長による「GIGAスクール(生徒一人に一台のコンピューターと高速ネットワークを整備する文科省の取り組み)をやる」というスタンドプレーに他ならなかった。ITインフラの整備も大きなばらつきがある中、生徒も保護者も教師も置き去りにされた政治パフォーマンスにより、学校現場は大混乱に陥った。
これに対し、2021年5月、大阪市立木川南小学校の久保敬校長(当時)が、大阪市長と同市教育長宛てに「提言書」を郵送した。内容は、通信設備が不十分な中での市長によるトップダウンの指示で学校現場が混乱をきたしたこと、それによって「子どもの安全・安心も学ぶ権利もどちらも保障されない状況をつくり出していることに胸をかきむしられる思いである」と訴えたもので、さらには、子どもたちに過度な競争を強いる政治主導の教育こそが問題であると指摘していた。
現職の校長による正面からの抗議は波紋を呼び、多くの保護者、教育者に支持された。提言書については「支持します」というリツイートが瞬く間に10万件を超え、255人もの関係者から賛同の意見書が集まって、山本大阪市教育長に向けて提出された。
ところが、2021年8月20日、この提言書を問題視した市教委は、久保に「文書訓告」処分を科した。地方公務員法「信用失墜行為」に該当するとしたのである。しかし、学校現場に混乱が起きていたのは紛れもない事実であり、それを無かったとし、逆に久保が混乱を起こしたとする市教委の方がエビデンスを示していない。
この久保の提言書に賛同し、自著『崩壊する日本の公教育』(集英社新書)に全文掲載した鈴木大裕との対談が大阪隆祥館書店で行われた。イベントのタイトルは『子どもたちの教育を通して社会のあり方そのものを「問い直す」 』。
※この記事は2024年12月21日に行われた対談を抄録したものです。

鈴木 僕が、久保先生にぜひお聞きしたかったのは、まさにあの提言書のことです。僕は本の最後の第6章に「『遊び』のないところから新しい世界は生まれない」と書きました。今の社会は生活の中にふらっと寄り道してあてもなく探索したりする「遊び」やゆとりが無いから、今とはちがう自分や社会の姿を想像することもできず、無意識にこの競争的な格差社会に適応させられてしまっている。
ところが、あの提言書を出した久保先生そのものが、コロナ禍で閉塞感が漂う教育界での「遊び」になったと思っています。子どもたちや保護者たちがああやって声を上げた教師を守ろうと一緒に立ち上がったというのは、それまであまり見られなかったことです。久保先生が一つの風穴を日本の教育界に通して、そこから稀少な「すきま」が広がったような気がしています。なので、その後の活動や展開について語り合いたいと思っていたんです。
久保 そう言っていただけるのは、うれしいのですが、その当時、僕は大裕さんが書いてはるような「遊び」であるとか、自分がそこから何かをつくり出すみたいな意識をしていなかったんです。どっちかいうたら、提言書を出した後の反応に僕のほうが驚いてしまっていました。
また余計なことをしたと言われて叩かれるかな、とか思って学校に行ったら、「久保先生頑張れ!」というメッセージが、フェンスの金網にたくさん貼られていたり、応援の声が次々と届いてびっくりしました。僕は提言書を広げるとか、そこまで考えていなかったですが、周囲の方から、ほんまにやっぱりあの問題は放っといたらあかん、というようなことを言われて、何か退職してからも背中を押されるように徐々に展開していきましたね。
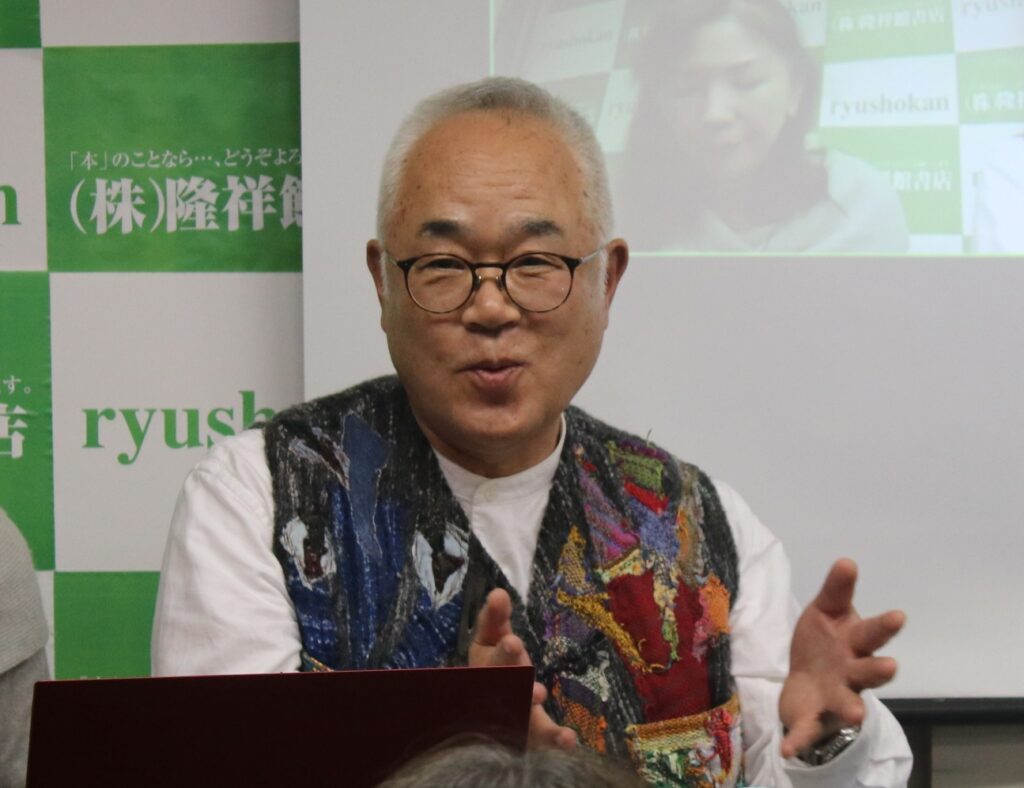
鈴木 そう、いくつかの展開があったと思うんです。例えば、大阪公立大の准教授、辻野けんまさんの取り組みだとか、あとは応援団が立ち上がって教育委員会への異議申し立てをしたとか、そこら辺を説明してもらえますか。
久保 そうですね。辻野先生とは、提言書の少し前から知り合ってたんです。面白いことに、教育委員会がコンプライアンス研修に何を間違ったか(笑)、辻野先生を講師で呼んだんです。そしたら辻野さんは、「すべてを学習指導要領に沿って教えろ」という市教委の通達を外食大手チェーンのやり方に例えて話されたんです。
「その大元の料理のレシピがそもそもつまらんレシピで、おいしくもないのに、どこのお店もそのレシピに従って、おいしい物を出して客を集めろって言われても無理でしょう」って。今の学校はそういうふうになっているんじゃないですか、と話されたんです。
もちろん市教委がその「まずいレシピ」の発信元です。その後も辻野先生が、ご意見あったらメール下さいと言われたんですね。それで僕は、面白くてメール出したんです。それは校長対象のコンプライアンス研修会だったし、みんな元気もらったやろと思ったんですね。たくさんメールが行ってるかなと思たら、メール出したん僕しかおれへんかったそうです(笑)。それで関係がつながったんです。
鈴木 それが出逢いですか。
久保 はい、それで提言書出して、うわーっとなったときに、辻野先生にも「ちょっとこんな文章を市長と市教育長に出したんです」と伝えたんです。元々、僕は辻野先生がどんな研究をしてはるか詳しく知らなかったんですけど、ドイツの教育行政とかドイツの教育制度のことを中心に国際比較をするみたいなことをされてたんですね。それでアメリカに留学してはった時にお世話になってたミネソタ大学の名誉教授のC・キゾックさんがあの提言書をネットで見つけて、Googleの翻訳で読まれて、辻野さんとこに連絡があったそうなんです。
鈴木 それはまったくの偶然ですか?
久保 ええ、まったくの偶然なんです。それで辻野さんも驚いて、これを書かれた久保先生というのは実はよく知っているんだ、ということになったようです。キゾック教授は提言書の冒頭にある「学校は、グローバル経済を支える人材という『商品』を作り出す工場と化している」という部分から反応されて、「この提言書による批判は、かつてアメリカの教育界が体験してきたことと通底する、これを書いた校長と話がしたい」と言って、僕とのオンラインによるジョイントセミナーが実現したんですよ。(2021年8月3日)
そうしたら、このオンライン対談が話題になって、国内外での教育関係者たちの間で対話の場となり、その後も2回、3回、4回と続けられて、ドイツ、インドネシア、キプロス、台湾、キューバ、ブルガリア、マレーシアなどの教育者、学者の人らが参加して来られたんですね。
鈴木 結局それは、日本の状況として久保先生が書かれたことと同じような教育に関する問題が、それぞれの国々であったということなんですね。
久保 はい。ブルガリアの先生なんかも、うちの国でも人間として子どもを育てるということよりも、いかに国の経済を回す人材をつくるかみたいなとこに一気に教育制度がシフトしてきていて、危機感を感じているとおっしゃっていました。
鈴木 それは、ある意味日本のGIGAスクール構想のように、子どものニーズよりも経済のニーズが優先された教育「改革」によって教育現場が翻弄されてしまうような状況が他の国々でもあるということでしょうか。
久保 そうですね。だから結局、ICTの導入とセットで、そういうことが入って来ているんです。当然、教員や自治体ごとの環境整備のばらつきがあって、結果的に教育格差が広がっていると。ブルガリアの先生がホストになってくれはったときにもらったメッセージでは、僕の提言書は、「今、教育が非人間化していこうとしている中で、それに抗うことを求めて出された提言やと思う」と言ってくださいました。商品やなくて人間として教育しなければ、貧困や差別に満ちた今の世界を変えていこうとする、そんな子どもたちを育てられないと。
鈴木 僕が教育に携わってきて、迷ったときに立ち戻るのは、いつもパウロ・フレイレが言ってた言葉なんですよ。「目指すところは、より愛しやすい社会だ。それの創造だ」っていうことを言ってるんです。
今、教員さえもが競争を強いられて、生徒を愛することができないような学校現場になっていると思うんです。なのでシンプルに言えば、大切なのは子どもの教育や成長に寄り添いたくて先生になった人たちが、子どもたちをより愛しやすくなる環境をつくることなんじゃないのかと思います。でもそういう視点が、今の国が進める働き方改革にあるのかどうか。

久保 大裕さんはパウロ・フレイレのことも書いておられますけども、僕もフレイレさんが言うところの「詰め込むような教育は、抑圧的で非人間的なものしか生まない」、やっぱり、学ぶ者と教える者という関係じゃなくって、お互いのコミュニケーションによって初めて人間的な教育が生まれるんやと思います。
それでその4回にわたったオンラインによる海外とのジョイントセミナーでも、キューバの先生が「キューバでこんなことをもし市長がやったら、みんなもっと怒って、わーってなってる。こんなん教員の権利が侵害されてんねんから、久保先生、放っといたらあきませんよ」って、すごく言われたんですね。
僕、キューバなんて社会主義でもっと強権的なんかなと思ってたんですけど、そうやなくて、教員はしっかりと抗議できるんですね。
鈴木 やっぱり、日本ではなかなかそうやって校長先生が行政に対して怒りをあらわにすることが、今までなかったじゃないですか。だからそれが人々の琴線にすごく触れたんでしょうね。アメリカではもうずっと前にそういうことが起こってきて、ベテランの、それこそ久保先生みたいな人たちが、教育をめちゃくちゃにした新自由主義教育「改革」に対する抗議として一斉に早期退職をしていった時期がありました。一人のベテラン教師は教育長への辞職届けを公開書簡としてネットで公表し、こう述べました。「私が教職を去るのではない。教師というしごとが私を去っていったのだ。」そのようなアメリカでの運動についてはどうお考えですか。
久保 いや、もうほんとに、その言葉そのとおりやなって感じました。ほんで、僕らもアメリカは大変なことになってるんやなっていうのは、2000年過ぎぐらいからちらちら目にはしてたと思うんです。教師が自由を奪われて管理されて、経済的にも追い詰められて児童虐待も起こる。でも、それが日本に直接関わってくるやなんて、全然そん時には思ってなかった。それが、大裕さんが言ってはった大体30年先にアメリカと同じことが、日本でも起こるという、そのとおりになった。今、思えば新自由主義の価値観とかをどんどん内在化させられていった。
鈴木 そう、結局は新自由主義的な価値観を内在化させ、そんな社会を支えてるのは私たち一人ひとりなんですよね。保護者も不安で仕方がないから、何とか子どもたちを、この競争的な格差社会に適応できるよう必死に訓練して付加価値を付けようとする。結局はそういうところで絡めとられてしまう。
だから政治を変えなくちゃいけないのだけど、どこから手をつけたら良いかわからない。でも、政治って何かといったら、目の前の子どもだったりするわけですよ。例えば、家庭間格差や地域間格差のせいで、この子は部活動ができて、この子はできない。それはれっきとした政治問題です。
それで久保さん支援の話に戻りますが、その後の活動の広がりと、サポートグループの「ガッツせんべい応援団」はどのように成立していったのでしょうか。
プロフィール
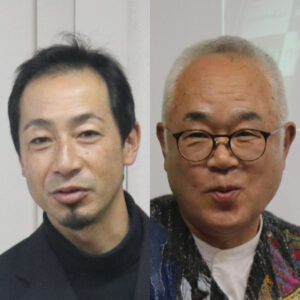
鈴木大裕(すずき・だいゆう)
1973年、神奈川県生まれ。教育研究者。16歳で渡米し、1997年コルゲート大学教育学部卒業、1999年スタンフォ―ド大学教育大学院修了。帰国後、千葉市の公立中学校で英語教師として勤務。2008年に再渡米し、コロンビア大学教育大学院博士課程で学ぶ。2016年、高知県土佐町へ移住、2019年に町議会議員となり、教育を通した町おこしを目指しつつ、執筆や講演活動を行なっている。著書に『崩壊するアメリカの公教育 日本への警告』(岩波書店)など。
久保敬(くぼ・たかし)
1961年大阪府枚方市生まれ。 1985年大阪市立啓発小学校に新卒で赴任。 2006年大阪市教育センター指導主事、2010年大阪市立波除小学校教頭、2013年大阪市教育センター総括指導主事、2016年大阪市立生野南小学校長、2018年大阪市立木川南小学校長。同小学校在任中、コロナ感染拡大防止のため全面オンライン授業の実施を指示した松井一郎大阪市長に対して、2021年5月17日、学校現場が混乱しているとして「提言書」を送付する。教育公務員としての職の信用を傷つけたとして、2021年8月20日、「文書訓告」の処分を受ける。2022年3月31日 定年退職。


 鈴木大裕×久保敬
鈴木大裕×久保敬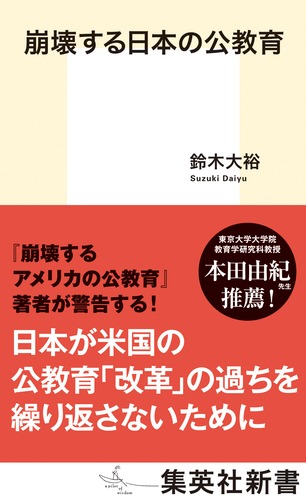










 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
 小島鉄平×塚原龍雲
小島鉄平×塚原龍雲


