「トランスジェンダー」の歩みを振り返る
言葉を使う当人がどのような経験を経て何を語ろうとしているのか、という視点は肝心だ。「心の性」の次は、「トランスジェンダー」という言葉の歴史に話題が移った。
1970年代以降、ゲイ解放運動では「外見が変」「世間の偏見が向けられる」という理由で、ゲイの人々からもトランスやドラァグクイーンの人々は排除されていた(*2)。そうした性的マイノリティ同士でも排他的に扱われてしまう「クィアやジェンダーに非順応的(ジェンダー・ノンコンフォーミング)な人たち」が、「トランスジェンダー」という言葉の傘の中で守られることになる。サンフランシスコ人権委員会が作ったトランスジェンダー差別に関する報告書(*3)で「トランスジェンダーアンブレラ」のイラストが描かれたが、その背景には共通の抑圧体験があったのだ。
しかし現在のトランスヘイトでは、「トランスジェンダーアンブレラが示すように色々な人たちがいるのだから、トランスを認めたら危険だ」というかたちで、むしろ排除のために悪用されている。
さまざまな困難を経験し、何かを説明する必要に迫られるからこそ、「心の性別」や「トランスジェンダー(アンブレラ)」の説明が用いられてきた。自分が誰なのかを説明する責任を負わされていなければ、説明する必要はなかっただろう。
日本におけるトランスヘイトは、2018年にお茶の水女子大学がトランスジェンダー(の女性)も入学を可能にすると発表(*4)したとき、その反動として活発化した。「心が女だと言いさえすれば女子大に入れる」という煽動は、「心の性」という言葉でしか自分を説明できなかった人たちの経験を踏みにじっている。
また、西田さんが列挙するように、トランスジェンダーへの学校対応には2005年以来の地道な積み重ねがある。「日本で学校対応が始まったのは2005年(*5)」で、「2014年に文科省が全国調査(*6)をしている」。「2015年の暮れに、女子中学校に親御さんから問い合わせがあった。小学校を女の子として通っている(トランスの)子が進学できますかと。その問い合わせを受けて、女子大が動き出したんですよ(*7)」。社会にも個人にも、歴史があるのだ。
学校現場は少しずつ変わっているが、あいかわらず「診断書主義」が強い、と高井さんは言う。「本人が必要なことをわかっているのだから、いちいち医者の診断書の提出を求めなくても現場で対応できることはある」にも関わらず、合理的配慮をするには診断書が必須とする風潮は、障害の文脈でよく言われるように、問題である。西田さんは「学校は校長の一存でできることがたくさんあるのに、自分たちの責任でやりたくないから医者に行けと言うのでしょうね」と語った。

(*2:『Transgender History』Susan Stryker. (Seal Press, 2017))
(*3:https://ia803408.us.archive.org/7/items/investigationint1994huma/investigationint1994huma.pdf
『Investigation Into Discrimination Against Transqendered People』San Francisco Human Rights Commission (p.72))
(*4:https://www.ao.ocha.ac.jp/menu/001/040/d006117.html
トランスジェンダー学生の受入れについて – お茶の水女子大学)
(*5:「性同一性障害を受け入れ 小2男児、女児として通学 播磨地域」神戸新聞(2006年05月18日))
(*6:https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2016/06/02/1322368_01.pdf
学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査について – 文科省)
(*7:『LGBTと女子大学:誰もが自分らしく輝ける大学を目指して』日本女子大学人間社会学部LGBT研究会 (学文社, 2018))
当事者たちの分裂
女子大の話が出たが、そもそもトランスの子どもの多くは、大学進学の選択肢に恵まれていない。西田さんは「小学生の子たちをサポートする場に顔を出すと、AMAB(assigned male at birth /出生時に男性を割り当てられた)の、性別に非同調的な子どもたちは、6割や7割が学校に通えていない、家からも出られない」現状があると話す。「ピアサポートの場でだけ、周りの子どもと一緒に楽しそうに遊んでいるんですよ。本来なら学校でもそういうふうにできるはずなのに、それをできなくさせている社会がある」と続けた。
高井さんは、SNSをめぐる状況に言及した。「当事者の若い子たちも、SNSで初めて自分と似たような経験や背景を持っている人とつながれるから、何か軽い冗談や皮肉を言ったり、諧謔(かいぎゃく)的なカルチャーを作って、そういう乗りで会話を作ったりしていた。でもネットのヘイトがひどくなってから、みんな言葉少なになってしまった」と悔しがる。
トランスヘイトが激化すると、当事者間にも分裂が持ち込まれる傾向がある。高井さんは「ヘイトが自分に向けられているわけではないと処理したくなる人がいるのは当然」だが、そこで「『品行方正な性同一性障害者』の自分は嫌われていない」と線引きをして、「本物規範」が強まっている状況を危惧する。
実は20年ほど前も、トランスの当事者間に規範が持ちこまれ、序列化、分裂や争いが生じていた(*8)。「真のGID(性同一性障害)は100円の缶コーヒーを買うのもためらって、お金を貯めてSRS(性別適合手術)をするものだ」、「結婚している人や子供が居る人はGIDとして偽物だ」というような「つらさ合戦」や「真のGID論争(*9)」になった。当時、研究者でもある吉野靫はこれを「GID規範」と名付けて分析している(*10)。
結局、こうした分裂は誰も救われず、みんなが息苦しくなるので、2000年代の終わりには下火になった。しかし、昨今のトランスヘイトに乗じて、再び「誰が本物か」という規範が強まってしまっているのかもしれない。「伊達(だて)や酔狂でトランスして何が悪い(*11)」「くたばれGID(*12)」と、SRSをすることに真面目に取り組まないのは“不謹慎”であるというGID規範を押し付けられたことに対し敢えて対極の言葉を用いる辛辣な皮肉を混えて応じるトランスの人たちもいた。
だが実際のところ、差別を受けなくて済む「本物のトランスジェンダー」がいるわけではない。シスジェンダーとトランスジェンダーの境界も曖昧だ。「私も本人に言われるまでトランス女性だと分からなかった人、結構いますよ」と西田さん。逆にトランス当事者だと思って話していた相手がシス女性だったケースもあるそう。実際の関係性においては、「ミスジェンダリングといわれるような、間違えることはいっぱいある。その時はごめんなさいねというかたちで、その人間関係の中でやりとりが行われて、そこで収まっていく話ですね」。
他にも、生きていく性別を変えることで直面する社会のジェンダー規範や、トランスの身体変化について、話題の尽きないイベントだった。
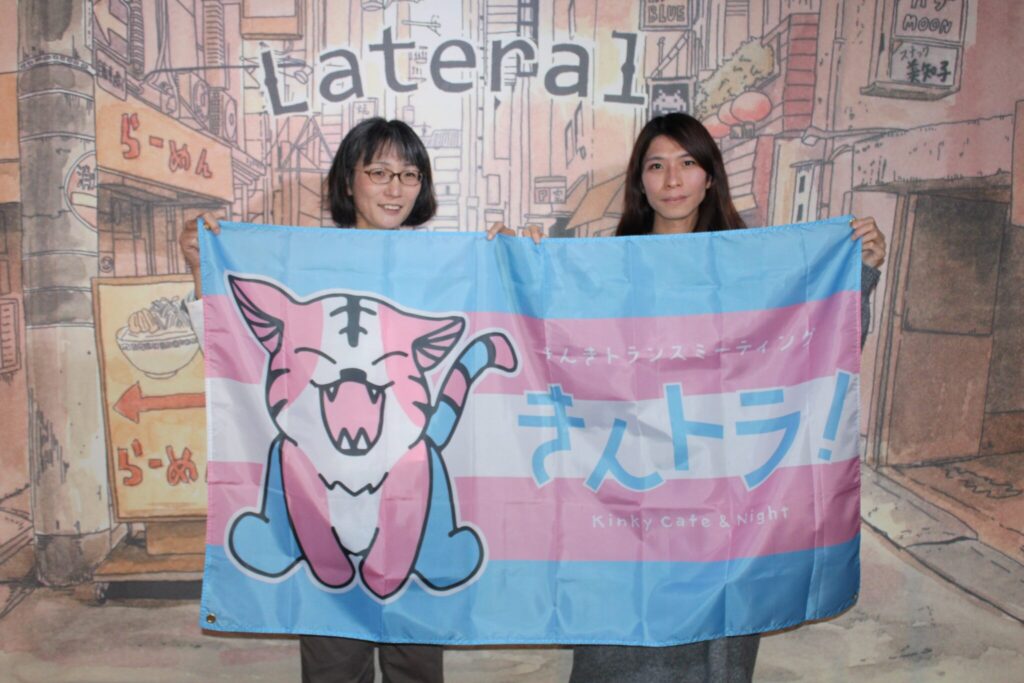
撮影/李 信恵
(*8:https://www2.igs.ocha.ac.jp/wp-content/uploads/2016/02/05研究ノート-吉澤.pdf
吉澤京助『「性同一性障害」概念の普及に伴うトランスジェンダー解釈の変化』(お茶の水女子大学 ジェンダー研究 第19号, 2016))
(*9:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsr/59/1/59_1_133/_pdf
鶴田幸恵「正当な当事者とは誰か」(2008)P.59)
(*10:http://sukudomo.g2.xrea.com/shiryo/Shiso3-yoshino.pdf
吉野靫『GID規範からの逃走線』( 現代思想2008年3月号))
(*11:https://twitter.com/ripo0079/status/816136497472491520?s=20
アニメ「銀河英雄伝説」(原作:田中芳樹)登場人物ダスティ・アッテンボローのセリフからの引用)
(*12:2018年3月に行われた米沢泉美主催『いずみちゃんナイト第17回』で、同年に20周年を迎えるGID学会について語るイベント名「くたばれ!GID学会」からの引用。)
プロフィール

(しゅうじ・あきら)
主夫、作家。著書に『トランス男性による トランスジェンダー男性学』(大月書店)、共著に『埋没した世界 トランスジェンダーふたりの往復書簡』(明石書店)、『トランスジェンダー入門』(集英社新書)。


 周司あきら
周司あきら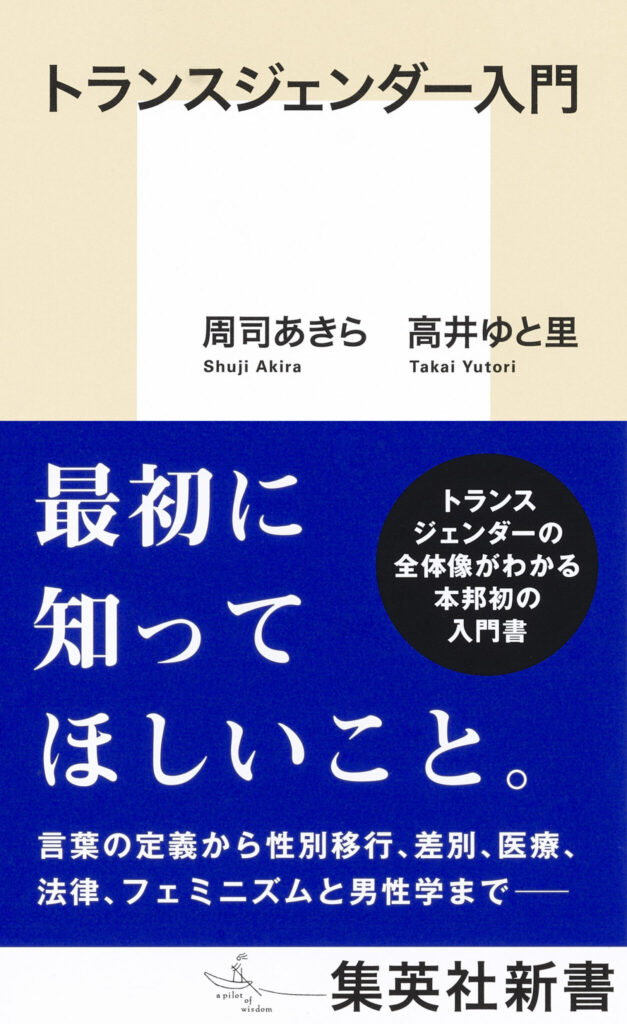










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

