学びはだれのもの?
勅使川原 面白いな。私も『「学び」がわからなくなったときに読む本』(あさま社)で気になっている点があって。最初に掲載されている千葉さんとの語り(p15「1 何のために勉強するのが」)がマッチョだなって思った。
鳥羽 さわりだけ読んで、「こんなマッチョなもの読めない 評価★ひとつ」という感想をいただいたこともありました。そう読まれる可能性はあるだろうとは思ったんですが……。
過去に「受験勉強の傷」を負った大人たちのせいか、受験システムと暗記学習を混同して、暗記そのものにとてつもない偏見が生まれています。でも、暗記自体にはやっぱり意味があると思うんですよね。
それこそ学歴社会じゃないですが、東大や京大を目指して勉強する子たちをたくさん見てきて、彼らがやった受験勉強が無駄だったとは全く思いません。本人たちと話をしてもそうなんです。
具体的に言うと、暗記することで手持ちの固有名詞が増えると、思考するときの運動性が高まると思うんです。思考の可動域が広がるというか。だから、無駄じゃないどころか意味がある。その力が本人にとっての宝にはなると感じてます。
なので、その辺りまで一緒に否定されるのは、ひっくり返したいなとずっと思っていて。
勅使川原 すごくわかります。私、鳥羽さんがそこで千葉さんに投げかける言葉も好きで。「千葉さんは、ラクして勉強なんてできないよ、というメッセージを発すると同時に、時間をかけた勉強は「贅沢だ」とも言っているわけで、そこがおもしろいところです。」(p.43)とか。
鳥羽 そうなんですよ、どっちも言ってるんですよね。だから、両方読んでからレビュー書いてほしかったな……。
勅使川原 ありますね。マッチョという評価軸については、文化資本に代表されるような、もっている資本、もっというと格差の話題にはそういう声をいただきます。
鳥羽 そうですね、「親ガチャ」なんかもそういう文脈の言葉ですね。
でも、逆説的なんですけど、「親ガチャ」「毒親」といった言葉にこだわればこだわるだけ、強者側に価値がついてしまうんですよね。だから、その言葉で自分を守る時間は当然必要なんだけど、やっぱりそこから離れていく必要が、いつかはあるんだと思います。
勅使川原 そうですね。偶然性は何人も免れないので、ガチャそのものが問題ではないですよね。格差というか、不当な不平等があるときに個人の側から社会システムの変更を申し立てられないことがきついですね。
……もう時間ですね、早い! 「学びは誰のもの?」という問いへの、私たちの案を出しておきましょうか。
鳥羽 そもそも、学びが誰かのものだと言えるのかという所有の問題はやはりあるけれど……まず、学びは1人ではできないですよね。私たちは言葉を発している時点で、対話的な関係になっている。ロシアの文芸評論家ミハイル・バフチンが言うところの多声性(ポリフォニー)ですね。ひとり単独の声で喋ってる人は誰もいなくて、そこには複数の声が鳴ってるんです。誰かたくさんの人が言っていることをバーと喋ってるんですよ。
だから、学びは豊かなんです。いつの間にか、これまで生きた人や世界と交渉しながらやっている。だから、そういったものを自分の腑に落としていく作業なんだろうなって思うんですけどね。
「わかる」とはどういうことか
勅使川原 そうかもしれない。これは「わかるとはどういうことか」という問いに置き換えられそうでしょうか?
鳥羽 「わかる」は勅使川原さんの著作でも大きなテーマですよね。『「能力」の生きづらさをほぐす』(どく社)の最後も、お子さんであるマルさんに、「なんでそんな名前になったの?」って聞かれた「母さん」が、「意味なんてないよーだ」としめています(p240)。どんどん広げていけばいい、と。だから多分、今この問いが出たことも含めて、勅使川原さんはずっと、「わかる」と「わからない」の間を考えてきた人ですよ。
勅使川原 鳥羽さんもきっとそうじゃないですか? 『「学び」がわからなくなった』ってタイトルが。
鳥羽 そうですね。逆に言えば、これを読んだからってわかるわけじゃないよって本でもあるんですけど。
勅使川原 作る前から「わからない」でいこうって決めていたんですか?
鳥羽 最初は編集者から「学びの本を作ろう」という話をいただいて、対談が始まったんですけど、途中から「学び」はいかがなものかっていうふうに。学び自体に異議を唱え始めたんですよ(笑)。 自分自身がわからなくなってるんでしょうね。
勅使川原 それで、「『学び』がわからなくなったとき」になったんだ。
鳥羽 そうですね。ちなみに、『おやときどきこども』の方は、「子どもはわからない」ってことについて延々と書いてるんですよね。わかっているふりをしたくなるのすごくわかるけど……、と。
今って、学校の先生たちが、国や世間からの要請に沿う形で、「わからないこと」に蓋をしたままなんとか社会の現実を学校で受け止めようとしているんだと思います。学校が社会側の欲望を内面化してしまっている。だから、社会の即戦力を育てるなんて方向にいってしまう。でも、学校って、本来そういった意味での社会性から解放された存在じゃないでしょうか。先生は、実社会的な意味での社会性がないから存在価値があるとさえ、僕は思っています。学校は、社会が求めるかどうか関係なく、むしろそんな声は無視して、子どもたちをまるごと受け止める場所だったはずです。
それが、実社会の側の声が大きくなるにしたがって、社会の価値観をちゃんと子どもに伝えないと、と思わされてしまった。先生には真面目なひとが多いからなおさら良くない。それが、学校全体の弱体化にもつながっている。
だから、社会から学校に対する矢印、つまり「社会でうまくやっていける人を育ててほしい」という期待は、私はもう全部ぶっ潰すべきだと思います。学校が学校として自立して、先生たちのそういう社会性のなさこそを生かして運営するべきです。「会社で使える力」なんかより、学校としてできることの、ラディカルなあの力こそをとにかく子どもたちに与えたらいいと思うし、それに集中してほしい。これは、小中学校だけでなく、大学までずっとです。
勅使川原 その意味で、『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』にもあるんですが、学校はなにかができる・できないにかかわらず、みんなの声を聞く場、存在を承認する場であってほしいなと思います。まずはこんなところに来てくれてありがとねって、先生もみんなも言ってもいいんじゃないかな。
鳥羽 本当ですよね、うん。本当に、それがうれしいって伝えたいですね。
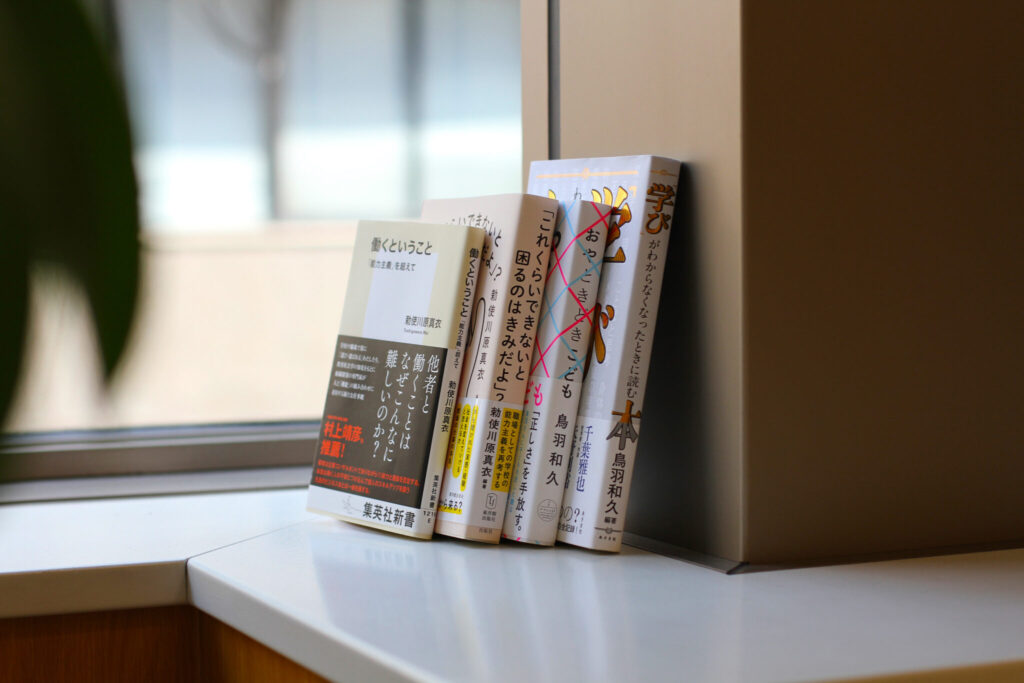
プロフィール

勅使川原真衣(てしがわら まい)
1982年、横浜市生まれ。組織開発専門家。おのみず株式会社代表。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。ボストンコンサルティンググループ、ヘイグループなど外資コンサルティングファームでの勤務を経て、2017年に独立。企業をはじめ病院、学校などの組織開発を支援する。また、論壇誌やウェブメディアなどにおいて多数の連載や寄稿を行っている。著書に、紀伊國屋じんぶん大賞2024で第8位となった『「能力」の生きづらさをほぐす』(どく社)、新書大賞2025の第5位に入賞した『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社新書)のほか、『職場で傷つく─リーダーのための「傷つき」から始める組織開発』(大和書房)、『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』(編著、東洋館出版社)、『格差の”格”ってなんですか?―無自覚な能力主義と特権性』(朝日新聞出版)、『学歴社会は誰のため』(PHP新書)がある。2020年に乳がんと診断され、闘病中。
鳥羽和久(とば かずひさ)
1976年、福岡県生まれ。株式会社寺子屋ネット福岡代表取締役。学習塾「唐人町寺子屋」塾長、単位制高校「航空高校唐人町」校長、オルタナティブスクール「TERA」代表として、150名あまりの十代の子どもたちとかかわる日々。著書に『君は君の人生の主役になれ』(ちくまプリマー新書)、『「推し」の文化論』(晶文社)、『おやときどきこども』(ナナロク社)など。編著に『「学び」がわからなくなったときに読む本』(あさま社)。専門は精神分析、日本文学。


 勅使川原真衣×鳥羽和久
勅使川原真衣×鳥羽和久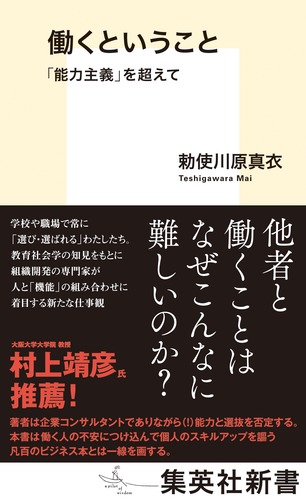










 古賀茂明×飯田哲也
古賀茂明×飯田哲也
 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


