ベジタリアンやビーガンといった言葉をよく目にするようになりましたが、日本ではまだ「一部の極端な変わった人」とする風潮があるなか、この春、哲学・倫理学を専門とする研究者の田上孝一さんによる『はじめての動物倫理学』(集英社新書)が刊行されました。
本書は、倫理学の基礎解説から始まり、肉食やペットなど具体的なテーマを切り口に、いま求められる動物と人間の新たな関係のあり方を問う、動物倫理学の入門書です。
今回は、社会哲学の研究者である稲葉振一郎さんを、対談相手にお迎えしました。動物倫理学という新しい学問は理論的、実践的にどんな問題意識を共有しようとするものなのか、語り合いました。
※3月31日に本屋B&Bさんで開催された配信イベントを記事化したものです。
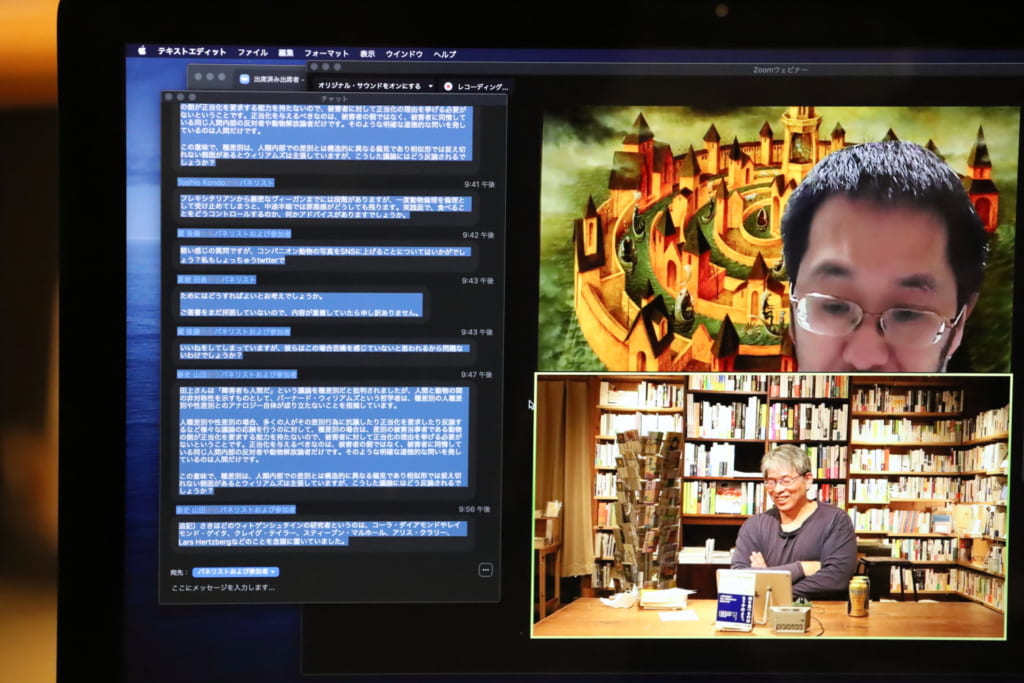
■種差別批判と動物の権利
田上 ちょっとした経緯があって、今回の『はじめての動物倫理学』が発売された3月17日に、講談社のウェブマガジン「現代ビジネス」でコラムを載せてもらえたんです。動物倫理学という学問の一番重要な概念である種差別批判、あるいは種差別主義批判について書いたのですが、それに対して否定的な反響がかなりあって、ちょっとびっくりさせられました。
種差別批判や種差別主義批判は50年以上前からある言葉でして、広めたのはピーター・シンガーが1975年に著した『動物の解放』です。もうかなり前のことなんですよね。シンガーの本は翻訳もされているんですけれども、やっぱり日本でそれを知っているのは動物解放などに関心のある人がメインであって、一般的にはほとんど知られていなかったんだと。コラムの反響を受けて改めてそう感じました。
ですから、『はじめての動物倫理学』も新書という比較的どこでも手に入るメディアで出されたことに、非常に大きな意義があると思うわけです。英語圏では動物倫理学の新しい書籍がコンスタントにどんどん出てくる状況なのですが、日本では一般的な形で知られることがあまりなかった。
それと、この本を書くにあたって心がけたことが一つあります。日本では動物倫理学に馴染みがないとはいえ、専門書はそれなりに出ていたし、一部には知られていました。その中で、どうもあまりよろしくない形での伝わり方があるなと思っていましてね。どういうことかというと、動物についてただ倫理学的に考えればそれで動物倫理学なんだというあり方です。こう考えるべきだ、こうでなければいけない、とは言わずに、いろいろな問題について両論併記して、その結論を抜きに投げ出してしまう。それはおかしいという思いがありました。
動物倫理学はどういう学問なのか。はっきりしているのは、動物の権利という概念がメインテーマだということなんです。1892年に理論家のヘンリー・S・ソルトが『動物の権利』を出して、動物の権利を明確に主張し、擁護している。それに続くマイナーな流れが前史としてあって、1970年代に本格化したのが動物倫理学です。つまり、動物の権利とはどういうものであり、なぜそれが大事なのかを追究する学問であった。そのことを伝えられたことは、今回の本を出した意義なのかなと感じています。
稲葉 イントロをありがとうございました。動物倫理学の紹介が日本で遅れているという印象は確かにありました。広い意味での動物倫理、アニマルウェルフェアの導入も相対的に遅れたといえると思います。さらに狭い意味での動物倫理となると、アニマルライツを基軸としたアニマルリベレーション(動物解放)を目標とする、党派的な色彩が強い学問なので、どうしても定着しにくいという面があるかもしれません。
ただ、英語圏の倫理学者を見ていると、ベジタリアンかビーガンかなど濃淡の違いはあれ、そういう人がかなり多い。厳格なビーガンの人もいるし、魚ぐらいは食べるという人もいるし、あるいはジビエしか食べないなど、いろいろな人がいますけれども、肉食はしないほうがいいだろうというのは多数派です。
ですから、例えば国際会議で懇親会を催すのも簡単ではありません。日本でも応用哲学会はある時期から宴会をやめて、懇親会は茶話会にし、飲みに行きたい人や肉を食べたい人は二次会から、というふうになりました。
そういう意味でいうと、動物倫理学はちょっと敷居が高いかもしれないけれど、それも程度問題であって、いずれはかなり共有意識として広まっていくのではないか。日本でも肉を食べないで済むんだったら食べないほうがいいよね、という方向性は定着していくというふうに私は思ってます。どうでしょう?
■肉食禁止は広まるか
田上 どうですかね。そうなるといいんですけど、日本の場合はそもそも倫理規範というか、具体的に何々すべきであるということに対する非常に強い拒否反応がある。僕はそこにすごく気をつけていまして、本の執筆でも大学の授業でも、あくまで理論としてこう言っていると。その証拠として、肉食がどれだけ環境を破壊しているかとか、動物を苦しめているとか、そういったことをデータ的に示す。そして、具体的な実践をするかどうかはあくまでも本人の自由だよ、と強調しているわけです。
学者は学問をやっているから、肉食をやめていく人が多いし、増えていくと思いますが、一般はどうなのかなという気はしますね。僕だって、本当は肉を食べたかったわけですよ。動物倫理学を勉強し、大学で倫理学を教えているうちに、あ、これはどう考えても肉食をやめなければいけないだろうとなった。それまでの僕は肉が大好きだったんです。
それと、僕は体を鍛えるのが好きなので、肉を食べないと筋肉が落ちるんじゃないかと危惧していました。そこでいったん肉食をやめてみて、ちょっと実験してみたんです。それで筋肉が落ち、体の調子が悪くなったら、理論的には正しくても自分は肉を食べ続ける予定だったんですよ。そうしたら、体に合っちゃったんです。むしろ筋肉の付きが良くなった。あくまで僕の場合、体の調子が良くなったから、肉をやめ続けている。
けれども、動物倫理学をやっていると、ものすごく厳しく肉食の禁止を強制しているように思われがちで。そこのところは日本の風土として仕方がないのかなと。ですから、稲葉さんのご意見は、ちょっとどうだろうかという気がします。

稲葉 僕は食の問題に関して、田上さんに言わせれば楽観的なのかもしれないけれども、代替肉であるとか培養肉といったエシカルミートの技術が発展していき、結果的にそっちのほうが安価になり、むしろ生体の肉を食べることはタブーである以上に贅沢になるかもしれないと思っています。倫理学的に言うと、クローン肉は自然の摂理に反する問題かもしれませんが、功利主義者からすればクローン肉が出てきたら、それで問題ない。植物性たんぱくに関しては、より一層選択肢が広がるでしょう。そういう意味で、食肉の問題に関しては何百年かしたら肉を食べるのは良くないとか、ださいとかになることが十分ありえます。
肉食禁止という意味でのビーガニズムに対する反発の中には、実は肉を食べることだけじゃなくて、動物との共存のあり方そのものに対する否定を動物倫理学者からされてる、という反発が混じってるんじゃないかという気が僕はちょっとするんですね。日本での反発はこのある種のエスノセントリズムとも関係するというか、反近代、反西洋主義的なところもある。
例えばアニマルリベレーションとエコロジーは、完全に同じではないけれど重なるところがあるわけで、西洋における自然保護とかエコロジズムと動物解放論はわりとリンクが強かったと思うんですけれども、日本にこのエコロジーが入ってきた時には、土着的なエコロジズムを目指した人たちから「ありがたく命をいただく」なんていう言葉が出てくるわけですね。エコロジーが動物倫理に直結しないような回路です。
つまり肉食を動物の共存とのあり方のひとつとして考える。で、その動物の共存のあり方そのものに対して動物倫理がかなり厳しい批判をしてきているということへの反発が、長期的には強くなるんじゃないかと思うんです。
■ペット飼育も批判対象
稲葉 田上さんの動物倫理学は要するに、人間は動物を搾取していると言うわけです。その搾取にはいくつかのタイプがありますが、一つは食べること、または役畜として使うこと。それから動物実験というのも入るわけですね。
で、さらにコンパニオンとして使う、ペットにするということ。これも動物倫理学からすると批判の対象になる。ペットとして動物と共にあること自体は基本的によくないことで、ペットに関しては将来的になくしていこうという路線です。
これは今回の田上さんの本で明確に打ち出されましたが、ちょうど同時期に出版された浅野幸治さんの『ベジタリアン哲学者の動物倫理入門』でもペット全廃論がかなり強力に主張されています。ここに象徴されるような形での動物との共存のあり方に関する原則論が、長期的には非常に強い反発を呼び起こすんじゃないかと思います。
理論的にも非常に面白い問題をはらんでいて、ペットや家畜限定の反出生主義だというふうに田上さんはおっしゃっている。動物を殺し傷つける以上に悪いことかもしれないと。もてあそぶために命を生み出すということは、命あるものを殺したり傷つけたりするよりもひょっとしたら悪いことかもしれないという、そういう考え方がここに表れているわけです。ある種の限定的反出生主義ですが、これを限定したままでいられるかという問題もありますよね。
つまり徹底的な反近代主義的ビーガニズムもありえて、それがどこにいくかと言うと、動物のために人間はいないほうがいいとなる。ある種のディープエコロジーと共振する考え方です。それに対して田上さんの議論は、近代主義だし、マルクス主義である。昔は動物を搾取するのは人間が文明的存在であるためには仕方なかったけれど、文明が発展してそうしなくて済むようになったからやめましょうよと言う。
ここでラジカルな反近代主義者は、だから文明はいかん、文明をやめようと言う。人間生きててすみません、という考え方にもなりえるわけですよね。でも、田上さんの議論はそっちの方向には行かない。ビーガニズムの射程を考えるとそういう過激さが出てきてもおかしくはないので、いずれそれとも喧嘩をしなければならなくなるでしょう。

田上 そうですよね。いや、いろいろとお話を聞いていて面白かったですよ。
最後のところで言うと、いわゆる人間の反出生主義というのは賛成できません。やはり僕は共産主義者なので、人間が滅びる前にちょっとまず共産主義を実現してくださいと。それを目指したいと言いたいですね。
その後に、みんなしていい世の中をつくったけれども、やっぱり人間が生まれること自体、存在すること自体が苦だとみんなが民主的に同意したら、消滅するのもありかもしれません。でも、人間にはまだまだ可能性がありますからね。その意味で僕はマルクス主義者であると思う。より良い社会というのを目指せると、そういうふうに思ってます。
それから、ペット、コンパニオン動物の反出生主義について。僕も、これを理論的にはこうなるだろうっていうことで書いてるわけです。けれども、結論的には、未来の人に任せますとしている。絶対ペットをなくさなきゃ駄目だとは言ってない。その最大の動機は自分がペットを飼っているからです。僕は猫を飼っていて、ものすごく猫好きなんですよね。
だから反発をする人の気持ちはよくわかります。犬や猫はちゃんとした人間に飼われれば、幸せな状態でいるわけです。それでいいんじゃないかっていうのもわかるんだけども、やっぱり本に書いた通り、ペットはその運命も存在もすべてを飼い主に握られてる。そして、たいていの飼い主から大事に育てられるけれども、中には虐待されちゃうのもいるわけですよ。理論的には、極めて依存的な存在としてちょっとどうなのかと。だからペットは漸減していくのがいいのかな、と思うんです。
あと、日本的な「ありがたく命をいただく」といった発想について。これはアナクロニズムの面がすごく強いと思います。明治、江戸とか、そういう時代に、例えば肉を食べるといっても自分の庭で鶏を育てて、鶏を追っ掛け回して捕まえて、首はねて羽をむしって食べるとか。そうしたことをやっていれば、確かに「あ、命に感謝」となるでしょうが、今は全然そうじゃないわけですよね。まさに工場畜産で、パックになってる肉をただ買うだけですから。
工場畜産の肉食に昔のそれを当てはめても、それはやっぱりアナクロニズムです。時代が変わったら時代が変わった通りに考えるべき。大事に育てた家畜を「すまんな」という感じで殺して食べるなんて、今では田舎暮らしをやっている人が若干そうしているだけでしょう。それを現代的に普遍化して、感謝が大事だとかというのはアナクロニズムかなと思いますね。
稲葉 食肉に関してはそういう形で、文化としての食肉に対して殺すということの悪は意義が見出しがたいという理屈は成り立ちやすいと思います。それに比べるとより難しいのはやっぱりペット、家畜よりもペットですね。
コンパニオン動物もやめるべきだという発想は、浅野さんも権利論を取っているからそうなります。動物の権利を尊重するということ、ペットは結局のところ従属的な、奴隷的な管理と保護のもとに置くしかないわけだから、存在そのものを廃すべきだと。従属的にしか生きられない生き物をつくるっていうことはよくないと。
でも、シンガーみたいな功利主義とか、あるいはある種の徳倫理の立場からすると、従属的な存在としてのペットをそれなりにちゃんと幸福にしたり、従属的な存在なりの尊厳というものを大事にしてあげたりということはできないことはないというか、意味がないわけではないという考え方も出てくると思うんですね。
■動物の権利を尊重するということ
田上 そうですね。ただ、僕らからすると、従属しながらっていうのは、やっぱりどうなのか、という感じです。
稲葉 しかし、そうすると、動物の権利を尊重するということが具体的に何を意味するかは結構ややこしい問題になります。ここで言う動物の権利というのは、基本的には個体の権利ですよね。つまり、広い意味での知性というか心を持ってるものはみんな尊重しないといけないと。認知能力を持って、情動を持って感覚を持ってるような主体は全部尊重しないといけないと。
そこの線引きは可能であるし、可能であるからそういう主体は尊重せねばというところが基本線としてあって、というのはわかるんです。ただ、個体であるような動物というか、感覚を持っていて、切られたら苦しいと思う動物というのがどこからどこまでなのか。
脊椎動物は苦痛を持ってるんですよね。無脊椎動物でもイカやタコはもう動物福祉の厳格な対象になってきつつあって、いずれ踊り食いが禁止されるんじゃないかとか思うんですが、甲殻類も結構そうなってきているという話があります。昆虫の場合はどうなんですか。
田上 僕が昔に出版した『実践の環境倫理学』では、はっきりと昆虫には権利はないと書いてあります。昆虫は痛みを感じてないだろう、ということですが、実際はわからないですよね。浅野さんの本にはちらりと、昆虫にも権利があるみたいに書いてあって、ちょっとびっくりしました。踏み込んでるなと思って。ジョーン・デュネイヤーというアニマルライツの理論家はそう言ってるんです。
僕は、それはかなり厳しいというか、わからないですよね。ただ、デュネイヤーなんかとは違って、アニマルライツを支持しているわけでもないのにこういう議論をしてる人は、そこのところも大事だけども、まず極めて明確な牛とか豚とか鶏とかの問題を考えるべきだと思っています。
稲葉 動物の権利を尊重するとはどういうことかという時に、つまり人間が動物を傷つけたり殺したりしちゃいけないっていうのはいいし、それに関して人間にそうするなという禁止もできるけれども、じゃあ動物に対して他の動物を傷つけるな、食うな、殺すなとは言えないと。
で、そうすると、動物の権利を守るということと人間同士お互いの権利を守るということの間には、やっぱり根本的に非対称性がある。この非対称性を問題視するから、例えばカントは動物は権利主体ではないと考えるだろうし、多くのカント主義者もそこに疑問を持つんだと思うんですね。要するに動物には他人の権利を尊重する義務を負わせられないから権利主体にはできない、という発想を、カント的な権利の相互性を重視する人は言うだろうと思うんですね。
で、そういう考え方をかわして、動物は権利主体だというためにはやっぱり権利概念自体を組み替えなきゃいけない。そういう、相互性のみが権利を成り立たせる、という考え方はちょっと修正しなきゃいけない。おまえの権利を尊重するからおまえも他人の権利を尊重する義務を負えとは、野生動物には言えないわけですから。
だけど、例えばコンパニオン動物に対しても責任を取れとは言えないものの、気立て良く周りを傷つけないように躾けるっていうことはしなきゃいけないし、多分してもいいんだろうと。この辺にかなりデリケートなグラデーションが生じてくると思うんですね。
だから、権利概念を捨てないとしたら、やっぱり組み替えないといけない。権利を尊重するっていうことの意味が人間と動物相手で変わらないといけない。そんなに変わっちゃうんだったら権利概念自体が空洞化するんじゃないかという、伝統的な権利論者のほうからの反論も来るかもしれません。
田上 なるほど、なかなか面白いですね。よく一般的に誤解と言っていいのか、権利と義務をワンセットで捉えるんだけど、ワンセットでできるのは一部なんですよね、人間の中でね。
稲葉 実はそうであって、一方的権利もあれば一方的義務もあるというのがどうも真相であると、倫理学的にもあるいは法学的にもそういう感じになってきてますけど、その辺の切り分けが難しい。
田上 難しいですよね。カント先生自身はどうしてそうなったのかわからないけれど、理論の中に子供が入っていないんです。だから本当に成人男性というか、自分自身、インテリジェントな成人男性をモデルにして考えちゃってるわけです。でも、考えてみたら、赤ん坊は大人から大事にされたら、ちゃんと赤ん坊としての義務を果たさなきゃいけないとはならない。赤ん坊としての義務って何なのか、泣くことなのかっていう話になっちゃうわけで。基本的に、権利というものは、決して相互的なものではないということですよね。義務とワンセットでもない。
■感情論に陥らない方法
田上 視聴者からの質問に少しお答えしていきます。
Q ピーター・シンガーは障害者差別の文脈で悪名高い人物ですが、田上さんは障害を巡る議論に関してはどのような立場でコミットしておられますか。
田上 一言でいえば、ダイバーシティの拡張なんだということです。障害者、男女差別、それから性的な差別、そういうのを全部なくしていく、その延長線上で動物の差別もなくしていく。
旧来の障害者差別批判の論理に問題があるのは、「障害者だって人間だ」と言ってしまっていて、これは種差別なんですよね。だから種差別に陥らない形で差別批判の理論をつくって、もちろんそこに障害者差別批判の論理も含めていく、そういう方向性で考えてるつもりです。
Q 最近、菜食や動物倫理に関心を持ち始めた者です。ツイッターなどでビーガンの方のお話を読んでいると、動物を苦しめたり殺したりするのは残虐だ、かわいそうだ、のような感情に訴える方法をよく目にするように思います。畜産や屠殺の残虐さも重要なポイントですが、食べるために動物を殺すのは当然と思ってる人に残虐だから肉食をやめようと訴えても議論がかみ合わないのでは、というもどかしさを感じます。感情論を超えて、動物の権利や尊厳という考え方を広め、理解を得ることが重要になるのでしょうか?
田上 その通りです。残虐な映像とか見ると、もうわーっと盛り上がって、そんな肉は食べられないとなる。で、この時、僕もその人たちの気持ちはわかるんだけれども、自分を基準にしないことが大事なんです。ここは重要で、みんな自分基準にしちゃうんですね。自分は残酷だと思う。で、肉を食べられないと。自分はもう厳格にビーガンをやってると。だからみんなやらなきゃ駄目なんだと。そういう訴えには、ちょっと無理がある。
自分を基準にしない。なかなか難しいことです。自分に厳しいと他人にも厳しくなっちゃうので。自分に厳しく、他人には優しいというのは、なかなか難しい。だいたい他人に優しいと自分にも優しいですからね。
ただ、そういう感情に訴える人も善人ですよ。だからそういう人たちをネットで揶揄する傾向があるけれども、僕はけしからんと思います。感情論でワーワー言ってくる人たちも基本的には善人で、ただ、ちょっと自分を基準にしちゃうんですよね。そこは寛容に、「この人うざいけれど、いい人なんだ」というつもりで付き合ってみてください。
執筆/オバタカズユキ
撮影/野本ゆかこ(田上氏)、新井卓(稲葉氏)
プロフィール

田上孝一(たがみ こういち)
1967年東京生まれ。社会主義理論学会事務局長、立正大学人文科学研究所研究員。哲学・倫理学専攻。1989年法政大学文学部哲学科卒業、1991年立正大学大学院文学研究科哲学専攻修士課程修了、2000年博士(文学)。著書に『実践の環境倫理学』(時潮社)、『本当にわかる倫理学』(日本実業出版社)、『マルクス疎外論の視座』『環境と動物の倫理』(ともに本の泉社)、『マルクス哲学入門』(社会評論社)などがある。最新刊は『はじめての動物倫理学』(集英社新書)。
稲葉振一郎(いなば しんいちろう)
1963年生まれ。明治学院大学社会学部教授。一橋大学社会学部卒業、東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得満期退学。専門は主に社会哲学。著書に『社会倫理学講義』(有斐閣アルマ)、『AI時代の労働の哲学』(講談社選書メチエ)、『銀河帝国は必要か? ロボットと人類の未来』(ちくまプリマー新書)、『社会学入門・中級編』(有斐閣)、『「新自由主義」の妖怪』(亜紀書房)、『政治の理論』(中公叢書)、『宇宙倫理学入門』(ナカニシヤ出版)、『不平等との闘い』(文春新書)、『社会学入門』(NHKブックス)、『「資本」論』(ちくま新書)、『経済学という教養』(東洋経済新報社/ちくま文庫)など多数。


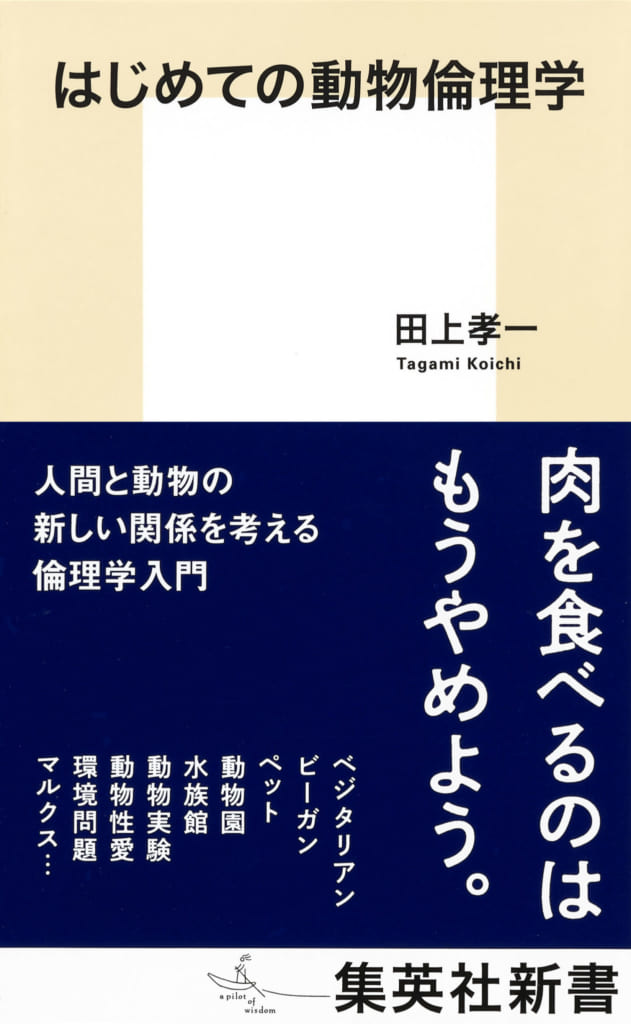










 藤原辰史×青木 理
藤原辰史×青木 理




 森野咲
森野咲