水球男子日本代表の初戦、アメリカとの試合は、14時開始。13時50分からNHK-ETVで放送が予定されていた。ところが、チャンネルを合わせるとまだテニスの大坂なおみ選手の試合が中継されていた。水球の試合展開が気になって仕方ない。大坂選手が勝利し、画面が有明コロシアムから東京辰巳国際水泳場に代わった時、すでに14時半を過ぎていた。
試合はどう展開しているのか?
実況アナウンサーの第一声は、「試合は第3ピリオドに入っています」だった。もう試合は半ばを過ぎている。スコアは?
画面の隅に目をやると、「日本9対アメリカ7」とあった。
(よっしゃ、リードしている、いいぞ、順調だ)
心が湧きたったのも束の間、テレビ中継が始まった直後から日本の厳しい時間帯が待っていた。アメリカが力で日本ゴールに襲いかかり、日本のファウルを誘い、得点を連取し始めた。一方日本は、荒井陸(あつし)、足立聖弥らがシュートを決めるが、ついに10対10、同点に追いつかれ、そして逆転を許した。

荒井陸選手(27歳)、165㎝・66kg。Kingfisher74所属

足立聖弥選手(25歳)、175㎝・76kg。Kingfisher74所属
(稲場はどうした!)
私は思わず心の中で叫んでいた。
ポセイドンジャパンが世界を震撼させている要因は、「超攻撃的」とも形容される大胆な戦術「パスライン・ディフェンス」という大胆な戦術だが、加えて、日本を軽視できない最大の要因のひとつは、「世界一のゴールゲッターがいる」という揺るぎない事実なのだ。
稲場悠介、21歳。日本ではまだそれほど有名と言えないアスリートだろう。それは残念ながら、水球という競技の知名度や認知度が人気種目に及ばないためだ。彼の名前は、日本よりむしろヨーロッパで鳴り響いている。世界の水球ファンで、稲場悠介の名を知らない者はいない。毎年開催されるFINA(国際水泳連盟)ワールドリーグ・スーパーファイナルで3年連続得点王に輝き、2019世界ジュニア選手権ではMVPを獲得した。日本は8位だったにもかかわらず、8位のチームから大会MVPが選ばれるなど異例中の異例ではないだろうか。それほど稲場の存在は際立っていた。本人にそれを尋ねると、驚いた様子もなく言った。
「うーん、あの世代では僕がずば抜けた存在だったので、当然の結果だと思います」
自他ともに、世界の世代ナンバーワンと認めている。それほどの逸材、世界が憧憬するスーパースター候補が日本にいるのだ。
稲場の持ち味は何と言っても「点を取る能力」だ。190㌢台が当たり前の世界のシューターたちの中で稲場は際立って小さい。身長180㌢。2㍍を超える選手も少なくない。稲場と相手ゴールの間には常に自分より高い壁が立ちはだかるが、稲場はそんな世界の壁を飄々とかわし、面白いようにシュートを決める。

稲場悠介選手(中央・21歳)、180㎝・79kg。左は主将の志水祐介選手(32歳)、183㎝・95kg。右はゴールキーパーの棚村克行選手(31歳)、183㎝・86kg。全員ブルボンウォーターポロクラブ柏崎所属
秘密は、「水中でのジャンプ力」と「肩甲骨のやわらかさ」だという。
「小学生のとき、世界一の水球選手になると決めて、それからずっと巻き足の精度を高めてきました」
水球選手は、水の中でずっと「巻き足」と呼ばれる方法で足をかき、身体を浮かせ続けている。稲場はその「巻き足」の技術と瞬発力が群を抜いている。日本代表のチームメイトが、呆れた顔で話してくれた。
「悠介の巻き足はちょっと特別です。瞬間的に左右に移動する距離や速さがハンパじゃないし、シュートを打つときは水泳パンツが見えるくらいジャンプしますから」
身長180㌢でも、水パンが見えるほど上昇すれば、2㍍級のガードすら上回る高さになる。さらに、稲場が編み出した独特のフェイントは世界有数のディフェンダーたちをも翻弄している。
「フェイントはだいたい、打つ真似をして打たないとか、見える動作でするものですが、僕は見えないところでフェイントをしています」
見えないところとは?
「肩甲骨です。僕はもともと肩甲骨がすごくやわらかいので、ボールを持って腕を上げたまま、ボールは動かさず、肩甲骨だけを動かしていつでも投げられる準備を整えるのです」
投げる前には必ず予備動作がある、と誰もが思い込んでいる。その予備動作から、相手はシュートを打つタイミングや方向などを予測する。ところが、稲場はボールを止めた状態からいきなり鋭いシュートを打つ技術を持っているのだ。相手の虚を突くことが簡単にできる。日本が世界に誇る得点王は、力ずくのパワー・シューターでなく、技術としなやかさ、さらには洞察力をも兼ね備えた「しなやかで頼もしいシューター」なのだ。

若き得点王・稲場の活躍が日本の命運を握る
ところが、五輪初戦、アメリカの反撃を許した第3ピリオドから稲場の存在が見えなくなった。当然のことだが、相手チームは日本のエース稲葉を抑えにかかってくる。これを素早い試合展開や他選手のフォローでどうカバーできるかが課題なのだが、アメリカ戦では途中から完全に稲場がマークされ、自由にシュートを打てなくなったように見えた。その要因は、全体的に試合の動きがアメリカのペースになり、日本が受け身に回って速さを失ったことにも一因があるだろう。
結果的に、日本はアメリカに奪われたペースを取り戻せないまま、15対13で敗れた。「6月のワールドリーグ・スーパーファイナルで準優勝した世界の強豪に大健闘」「その時は15対7で完敗した相手と大接戦」といえばその通りだが、決勝トーナメント進出に向けて、落としたくない初戦を落とした事実は消しようがない。Aグループで4位までに入るには、最低2勝、願わくば3勝が必要だ。大本洋嗣監督はアメリカを「その1勝が奪える相手」と睨んでいたに違いない。無念にも、快進撃の出鼻は挫かれた。しかしもちろん、まだ夢は消えていない。第2戦は27日18時20分から、相手はハンガリー。水球を国技とする強豪国だ。第3戦は29日18時20分からギリシャ戦。第4戦(31日)対イタリア、第5戦(8月2日)対南アフリカ。残る4戦で何としても2勝を奪ってほしい。
そのためには、序盤はもちろん、後半の勝負どころで日本のスピード感あるリズムで試合を展開すること、エース稲葉が躍動できる状況を作ること。ポセイドン・ジャパンは、大本監督が進むべき方向を示し、具体的には選手たち自身が意見を出し合い、試行錯誤し、チームを作り上げてきた。初戦の分析を重ね、選手たち自身が次への勝利の手がかりを導き出しているに違いない。

取材・文/小林信也 写真/大杉隼平 図版/海野智
プロフィール

小林信也(こばやし のぶや)
1956年、新潟県生まれ。Number編集部を経て、スポーツライターとして独立。テレビのコメンテーターとしても活躍。『野球の真髄』(集英社新書・2016年) 『生きて還る 完全試合投手となった特攻帰還兵 武智文雄』(集英社インター・2017年)


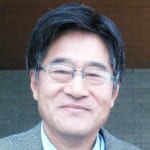 小林信也
小林信也









 藤原辰史×青木 理
藤原辰史×青木 理




 森野咲
森野咲