水球男子日本代表の闘いは1勝4敗で終わった。最初の目標である決勝トーナメント進出は果たせなかった。選手たち、監督、コーチ、関係者はみな、東京五輪での準々決勝進出だけを頭に置いて5年間努力を重ねてきた。それが果たせなかった落胆、失望は計り知れない。

最後の南アフリカ戦で57年ぶりのオリンピック勝利を挙げた。日本代表の進化を証明し、未来につながる架け橋となる1勝。だがもちろん、ポセイドンジャパンが心に描いていたのは、そのレベルではなかった。実際、初戦から強豪相手に接戦を演じた。実力の一端は見せつけたと言っていい。ではなぜ、快進撃を果たせなかったのか?
第1戦の対アメリカ、第2戦、対ハンガリー。いずれも第2ピリオドまで互角の戦いを演じた。ところが、第3ピリオド以降、日本らしい水球ができなくなって、ジリジリと離されて試合を終えた。第3戦の対ギリシャはその反省を生かし、後半も粘り強い勝負を展開したが、最後の最後に突き放された。
大本洋嗣監督が振り返る。
「日本は全ての試合で攻撃的に闘いました。守備的なことなど考えておらず、常に攻撃し続けたけれど得点できなかった、ということです」

日本の戦術は研究され、対策を打たれてきたと語る大本監督。それだけポセイドンジャパンは世界に認められていたのだ(写真 共同通信社/ユニフォトプレス)
超攻撃的な『パスライン・ディフェンス』からのカウンター・アタック。日本が生命線とする戦術への意識は終始、一貫していた。ところが、応援する立場から見ても、その勢いや切れ味に鋭さが欠けていた。
「1試合平均のデータを分析すると、攻防転換からの攻撃回数が27.8回。速攻発生が12.5回あるのに、シュートまで行ったのはわずか2.8回でした。これが5割を超える7本くらいにならないとダメ。その結果、カウンターでは1試合1点しか取れませんでした。敗因は明確です」
攻防転換の回数に対して、速攻の発生率が低すぎる。これも5割以上になってこそ日本らしい超攻撃型の水球と言えるのだが、ボールを奪っても意図通りに速攻を展開できなかった事実がこのデータからはっきりと浮かび上がる。
さらに攻撃回数54.3回に対してシュートが30.3本、ゴールが10.3点という数字は苦戦を物語っている。ボールを奪って攻撃しても、4割以上はシュートにさえ持ち込めなかった。そして、2割も点を取れなかったのだ。
その要因を大本監督は次のように分析する。
「ざっくりですが、イタリア戦では前線でパスを受けた選手にハードアタックされてノーマークにパスができませんでした。この練習は重ねていましたが、試合ではミスが多発しました」
相手の対策を見越した上で、さらにその先を行く練習をしていたが、試合で成果を発揮できなかった。そして、
「カウンターに対してゾーンディフェンスをされて、ミドル・レンジのシュートに限定されてしまいました。日本はミドルのシュートが苦手です」
相手は日本を徹底的に研究し、ミドルなら打たせていい、ミドルしか打てない守り方で対応してきた。その結果、得点力が大幅に削がれてしまった。
「日本のカウンターアタックに対して、退水(反則による一時的退場)覚悟でオーバー・アタックしてカウンターを止めに来る場面も目立ちました。日本が相手なら、退水する方が守れるという考えです」
相手が退水し、ひとり少なくなれば日本に有利な状況が生まれる。ところが、世界の強豪国は、日本が相手ならひとり少なくても守り切れると判断し、退水覚悟で速攻を止めにきたのだ。実際、日本は「退水オフェンス」が得意ではない。相手が壁を作って守れば、どうしてもミドルシュートを打つしかない状況になり、相手の退水を生かせずに終わるケースが多発した。

パスライン・ディフェンスからの日本の速攻を、相手国は反則による退水覚悟で止めにきた。新たな課題が見え、世代交代も進み、ポセイドンジャパンはさらに進化する(写真 共同通信社/ユニフォトプレス)
大本監督の話を聞けば聞くほど、リオ五輪の時とは比較にならないほど、世界の強豪各国が日本を研究し尽くし、対策を徹底してきた様子がよくわかる。それだけ、ポセイドンジャパンは世界に衝撃を与え、警戒される存在になっていたのだ。大本が言う。
「リオ五輪とは違って、各国とも、うっかりすれば日本に負けると思って相当気合が入っていました。対策されるのは分かっていたので、十分練習してきたつもりですが、及びませんでした。退水するとヨーロッパ型の水球になる。こっちはパスラインが出来ないので退水しないことだけ注意していましたが、ジャッジもかなり厳しくて退水判定をずいぶん受けました。日本選手の動きに対して外国選手は掴んでくるので退水判定が多くでるのは当然ですが、審判は公平感を出すため退水数でバランスを取ろうとする傾向があって、それで日本のディフェンスの些細なことで退水を取っていました。
水球はヨーロッパのスポーツ。ヨーロッパとの試合でレフリーもヨーロッパだとアウェイな感じです。『アジアの国がヨーロッパに勝つわけがない』という先入観があるから、必ずヨーロッパが勝つような笛になるのは否めません。ここに分厚い壁があるので、私たちはレフリングの影響を受けないカウンターアタックにかけてきたという事情もあります」
地元開催の東京オリンピック。満員の応援と無形の熱気がこうしたヨーロッパの笛にプレッシャーを与え、日本の勢いに熱を注いでくれる期待があった。しかし、想像もしなかった『無観客開催』は、ポセイドンジャパンからも地元の利を奪い去った。
「今回勝てば、(そうした慣習や常識も)変わった可能性があっただけに残念です。たらればになりますが、観客がいれば審判も相手チームも雰囲気が変わったと思うので、無観客試合が唯一の心残りです。
水球男子日本代表の闘いは、ひとつの区切りを迎えた。この大会を最後に引退を選ぶ選手が数名いるだろう。一方、エースの稲場悠介のように、今後いっそうの飛躍を期待される若い選手たちもひしめいている。オリンピック1勝がポセイドンジャパンの狼煙となり、3年後のパリ五輪でこそ快進撃を実現してほしいと心から願う。
取材・文/小林信也 図版/海野智
プロフィール

小林信也(こばやし のぶや)
1956年、新潟県生まれ。Number編集部を経て、スポーツライターとして独立。テレビのコメンテーターとしても活躍。『野球の真髄』(集英社新書・2016年) 『生きて還る 完全試合投手となった特攻帰還兵 武智文雄』(集英社インター・2017年)


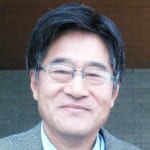 小林信也
小林信也









 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

