就職先・転職先として人気を博している「コンサル」。こうした状況の背景には、いまのビジネスパーソンが感じている仕事への不安が現れている。『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』の著者・レジー氏がビジネスを取り巻く言葉をひも解き、発売後即重版された話題書が『東大生はなぜコンサルを目指すのか』である。
本記事では文芸評論家の三宅香帆氏と対談。『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』で働き方への問題提起を行った三宅氏はこの本をどのように読んだのだろうか。
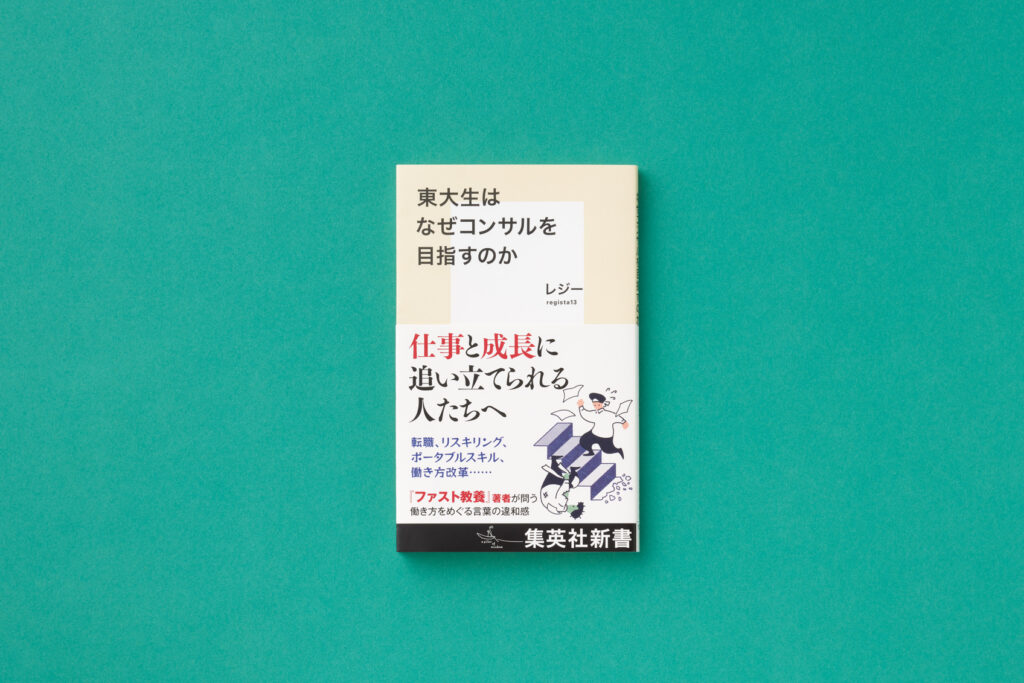
「安定したいから成長したい」という矛盾
三宅 書店を見ていると「元コンサル」の書き手が増えているなと思って。ビジネス書だけじゃなく、一般書全体で増えてる気がします。
レジー ちょっとしたブームですよね。加えて、人数自体が増えているのもあると思います。『東大生はなぜコンサルを目指すのか』でも書いたのですが、「コンサルに行けばその後キャリアも安泰」という発想でコンサルを目指す人が増えました。ただ、大量採用されても全員が昇格できるわけではないので、きっと「元コンサル」はさらに多くなると思います。
三宅 この前は「コンサルの書く技術」みたいな本を見ました。
レジー そんなのもあるんですね!MECEで書けるとかそういうことかな…まあ、今回の本もそんなコンサルブームの間に出せてよかったというのもあるのですが(笑)
三宅 もともとコンサルに注目したのはどういうきっかけがあったんですか?
レジー 就職市場におけるコンサルというものの位置づけが変わっていて、それにより二重性みたいなものが生まれてきているのに、意外とそういう観点からの分析ってないよなと思ったのがきっかけと言えるかもしれないです。ある時代まで、コンサルに就職するのは少し尖った人の選択肢でした。その人たちは、成長してスキルを身につけることで起業したり、人より高いお金を稼いだりしたいという志向を持っていたと思います。
三宅 面白い、昔は「仕事で成長したい」自体がニッチな欲望だったと。
レジー 僕が就活をした20年くらい前だとまだまだ終身雇用が基本の考え方で、大きな会社に入って定年まで働くというのが主流の価値観でした。そんな中でわざわざ成長を目指す人はかなりニッチですよね。それがいつの間にか、そんなコンサルが就職の人気ランキングで上位になってきている。色々話を聞いていくと、安定思考の表れとしてコンサルを選んでいるんです。そこでは「安定するために成長したい」というねじれが起こっていて、それが興味深いと思ったんです。
三宅 本書で書かれている「サバイブ」感覚の台頭ですよね。この社会で生き残るためには成長するしかない、という感覚を現在は多くの人が持っている。
レジー そうなんです。「安定したいから成長したい」という入り組んだ思考が社会にどう広がっているのか、そんな問いをコンサルという職業を通じて考えるのがこの本のテーマのひとつです。

成長は「文化祭」であり「まだ見ぬ美少女」?
三宅 世の中の成長思考が強いのは、どこか成長が「楽しく刺激的なもの」というイメージがあるからなのでは、と感じるんです。ただ、それって本当かな、と。個人的な感想ですが、人間はもう嫌だと思うぐらいしんどいときしか、本当の意味での成長はないと思ってしまうんです。たとえば自分の場合は受験勉強とか、入社1年目のときがそうでした。そりゃ能力的にはすごく成長したんですが、もう一度やりたいかと言われれば全くやりたくない。
でも世の中では、どこか楽しく文化祭みたいなものをみんなでやるのが成長だと思われている気がする。ユートピア的にイメージされているというか。
レジー 確かに。文化祭感があるのかもしれない。
三宅 すごい偏見ですが、就活でコンサルを受ける人って文化祭感を愛してる人が多いと思ってます(笑)
レジー そうかもしれません(笑) 決まった期限でアウトプットを出すというプロジェクトワークだから、仕事の構造も似ていると言えますね。ただ、実際は徹夜を楽しめる人だけがそこで生き残ってるという非常にゆがんだ構造がありそうですが。
三宅 実際はそういう強い人しかいられない、サバイバルな世界だけど、文化祭ぐらいのをイメージして入る人もいるんじゃないかなと思ってます。
レジー 確かに。本でインタビューしたうちの1人の方がまさにそれでした。ストレートにコミュニケーションが取れると思っていいなと思って入社したら、思ってた以上にストレートすぎて病んでしまいました、という。
三宅 なるほど。私自身は学生時代に本気で文化祭的なものをエンジョイした経験がないので分からないのですが、経験者からしたらもう一度それをやりたいと思ってコンサル的な仕事に惹かれるのかな。もちろんそういう側面がある仕事であるのはたしかだとは思いますし。
レジー あとは、成長してる実感が見えやすいのもコンサル人気の理由だと思います。普通の大企業だと仕事で中心的な役割を果たすのに入社から20年ぐらいかかるのが普通ですが、コンサルの仕事は入社早々にクライアント企業の経営戦略に関わることもあります。そういうスピードの違いもコンサル人気につながっているでしょうね。
ただ、自分が年を取ってきてわかったのは、本当の意味でのキャリアはすごく長期戦だということです。それこそ芸能界を見ていても、自分が中学生のころ急に人気者になってその後「消えた芸人」扱いされていた有吉弘行が国民的司会者になるなんて全く想像できなかったわけです。ビジネスパーソンのキャリアも、もしかしたらそういう時間軸で捉えないといけないのかなと最近よく考えます。
若い人と仕事について話すと、名のある大企業の新卒4〜5年目の人が「成長機会が〜」と言って転職を考えていたりするんですよね。「一回落ち着こう」と言うようにしているのですが(笑)
三宅 そういう人、増えてるんですね。若い世代を煽るために「ホワイト企業にいたままでは成長機会が奪われる」みたいなことを言う人、いますもんねえ。
レジー それは本当に著しい誤解ですよね。
三宅 「働き方改革」が世間的には普通になってきている中で、昨年あたりからどことなくその風潮に対する揺り戻しが来ていますよね。
レジー そうですね。この1年ほど、「ゾス」(グローバルパートナーズ会社の社長山本康二氏が『口答えせず仕事をしろ』という意味を込めて使っている言葉)を始めとして、その言説の強さが増してます。
三宅 全身全霊で働くことが「仕事の楽しさ」だという発信のほうが伝えやすいんでしょうね。
正直、私は仕事にやりがいとお給料と安定といい人間関係……とすべて求めるのは懐疑的なんですよ。それはまだ見ぬ美少女を求めているようなものではないかと。仕事にすべてを求めるのではなく、例えばやりがいや楽しさは趣味で……としてもいいと思うんです。『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』で述べたように「半身」でいることが大事だと思っているので、今の仕事全身全霊揺り戻しブームは警戒しています。
そんな中でレジーさんが改めて成長を問い直すのはすごく意味があると思いました。

「強制された自発性」が社会全体に
三宅 この本を読んで思ったのが、学校の部活動でも成長志向が根強いよな、ということです。コンクールや大会を目指してみんなで成長していこう、という志向が強い。会社だけでなく、学校も含めた社会全体にも、同じ感覚がある。
レジー 部活の場合、大会を目指したほうが教員の管理がしやすいこともあると思うんですよね。「部活動で楽しむ」というのを目標に据えると、楽しさって人それぞれなのでみんなが満足する部の運営はとても難しくなります。でも「大会」というわかりやすい目標があれば、管理もしやすいんじゃないですかね。成長という言葉は、一番シンプルで簡単なマネジメントなのかもしれない。
三宅 その視点は面白いです。それこそ『もしドラ』(もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら)でマネジメントが重視され始めたタイミングと、成長という言葉が世の中で存在感を表し出した時期は近しいですよね。成長という言葉で煽られている側の問題と、逆にそれを煽る側、あるいは煽らざる得ない構造的な問題があって今の状況が生まれてるんでしょうね。
レジー そうそう。個別で成長神話に振り回されてしまう人たちがいるだけじゃなくて、そうならざるを得ない環境的な問題がある。本の中でも「強制された自発性」という熊沢誠さんの議論に触れていますが、その人が望むと望まざるとに関わらず、そうした競争の回路に組み込まれるシステムが生まれている。
部活の話でも、大会で勝つために頑張る人がいるのは普通だと思います。本当の意味でそれを自発的に頑張る人はどんどんチャレンジすればいいと思うんだけど、大会を目的としていない人がそれを目指してしまうことの不幸はすごくあると思う。仕事もそうで、別に年収1000万を目指すことが万人にとっての幸せではないはずです。狭い意味での「成長」以外のさまざまな選択肢が増えることが重要です。
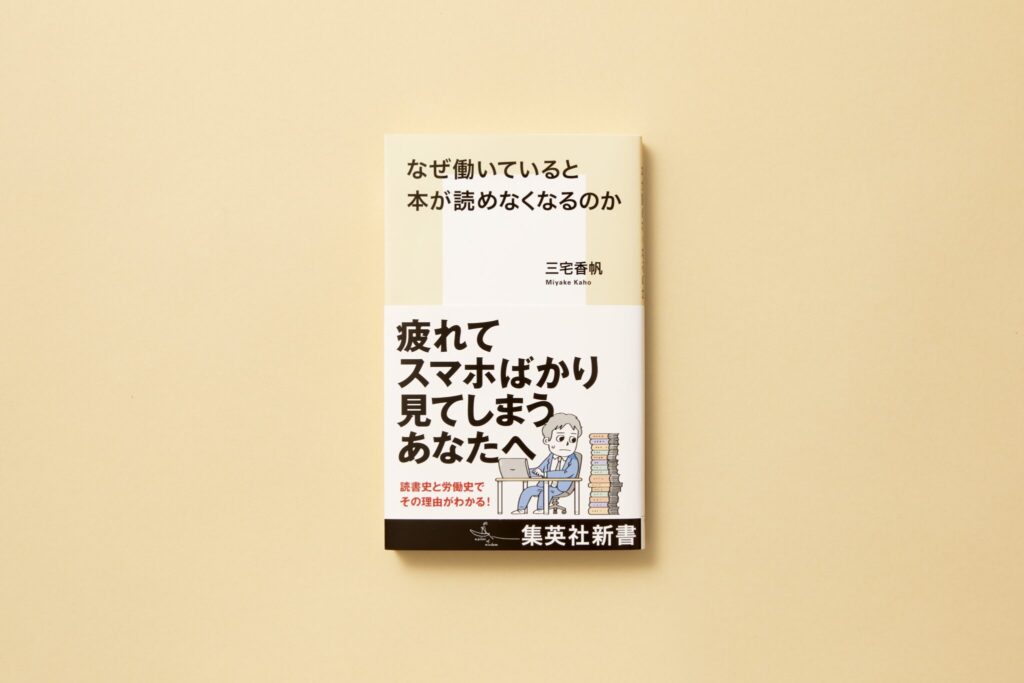
「成長」のさまざまな可能性を求めて
三宅 一方で思うのは、やっぱり完全に成長を降りることもできない、ということです。レジーさんの本で好感を持ったのは、成長しなくていいと言ってるわけではないところです。成長そのものを否定しているわけではなくて、社会やメディアに煽られた成長を目指すままでいいのかと問うている。
レジー 成長の話になると「成長を目指さなくていい」という話が多くなりがちですが、それを言っても何の解決にもならないというのが僕の考えです。ここはもしかしたら三宅さんとも感覚が近いかもしれないですね。
ここについては、僕が長年会社員をやっていて、かつ転職も複数回しながらキャリアを作ろうとしているバックボーンも大きいと思う。ある意味ではずっと「競争」の世界にいると言ってもいいはず。『ファスト教養』にも新入社員のころに堀江貴文に心酔していた話を書きましたが、そういう過去も含めて「成長が必要な時代」とずっと向き合ってきた感覚があります。
三宅 言い方が難しいんですけど、「脱成長」だと、どうしても社会は貧しくなってしまう。それに、この手の話はライフプランや、子どもの有無でもすごく感じ方が変わると思います。レジーさんは、その辺りも丁寧に書かれていてすごく誠実だなと思いながら読みました。
レジー ありがとうございます。丁寧な議論は自分なりに心がけたつもりです。成長を煽られる空気からは距離を置こう、でも自分にとって必要な成長について考えよう、という議論の構造が誤解なく伝わって欲しいと思っています。
「自己満足」を取り戻す
レジー 本来、成長というのは追い立てられて苦しくなるものではなくて、シンプルに喜ばしいことだと思うんです。たとえば、子どもが勝手に描いている絵が日に日にうまくなっていて感心しているのですが、「成長の喜び」ってこういうことなんじゃないかなと。
この感触を大人がどう見つけて、場合によってはそういうスタンスを仕事にも持ち込めるか、というのが大事だと思うんです。ただ、こういう考え方とSNSはすごく相性が悪い。かと言って、SNSをやめるのも現実的な解決策じゃないですよね。落としどころとしてあり得るのは、SNSにアップしない趣味を持つことが有効なんじゃないかと思うんですがどうでしょうか。
三宅 人の目を気にしない場、すごく大切ですよねえ。
レジー これはネット上で初めて言うのですが、コロナ禍のときに在宅勤務のお供にと思って、食事に使った後のアボカドの種を水で育てていたんです。やっているうちに本当に芽が出て、さらに葉っぱが出てきて、普段から植物に触れている人からしたら当たり前かもしれないけどすごく感動しました。何となくこれはSNSで言うことじゃないなと思って毎日淡々と水を変えて観察していたんですけど、なんだかそれがとても良かったんですよね。
三宅 私は誰にも見せない日記を書いていて、それが自己肯定感につながっている感覚があります。
レジー 誰にも読まれない文章、大事ですよね。自分が初めて音楽に関する文章を雑誌の真似事で書いてみたのが中学生ぐらいだったと思うのですが、SNSはおろかインターネットの時代じゃなかったから、基本的に読めるのは自分だけでした。ただの自己満足なのですが、あれがなかったら今自分は文章を書いたりしていないと思うんです。
三宅 成長をしなくても行為の楽しさがあるわけですね。
レジー はい。質の高くないものを不用意にネットに出して、そこに変な意見がついて傷ついて何かを作ることをやめてしまう、となるのは本当に不幸ですよね。「誰かにほめてもらいたい」とは異なる回路をどうやって持つか、というのはもっとみんなで考えてもいいと思っています。
三宅 それこそ、本質的な意味で成長できている感じがしますよね。自己満足じゃだめだ、みたいに言われることもありますけど、実は人生って自己満足こそが一番大切な気がする。
レジー 自己満足は実は仕事においても意味があるんですよね。自分の物差しを大事にして、自分の軸を突き詰めると、結果的にそれが他者と比べても秀でたものになっていたりする。最初から他者の物差しで戦うより、自分の物差しを磨くほうが、結果的に競争にも勝てる部分もあると思います。その意味でも自己満足は成長の時代に対する一つの処方箋になるのではないでしょうか。
(構成:谷頭和希)
プロフィール

レジー
批評家・会社員。1981年生まれ。一般企業で経営戦略およびマーケティング関連のキャリアを積みながら、日本のポップカルチャーについての論考を各種媒体で発信。著書に新書大賞2023入賞作『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』(集英社新書)のほか、『増補版 夏フェス革命 -音楽が変わる、社会が変わる-』(blueprint)、『日本代表とMr.Children』(ソル・メディア、宇野維正との共著)。X(旧Twitter) : @regista13
みやけ・かほ
文芸評論家。1994年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了(専門は萬葉集)。累計発行部数30万部突破のベストセラー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、新書ノンフィクションベストセラーランキング1位(日販・トーハン・オリコン)を獲得したほか、「新書大賞2025」「第2回書店員が選ぶノンフィクション大賞」「ビジネス書グランプリ2025リベラルアーツ部門賞」を受賞した。そのほかの著作に『「好き」を言語化する技術』『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』『人生を狂わす名著50』など多数。


 レジー×三宅香帆
レジー×三宅香帆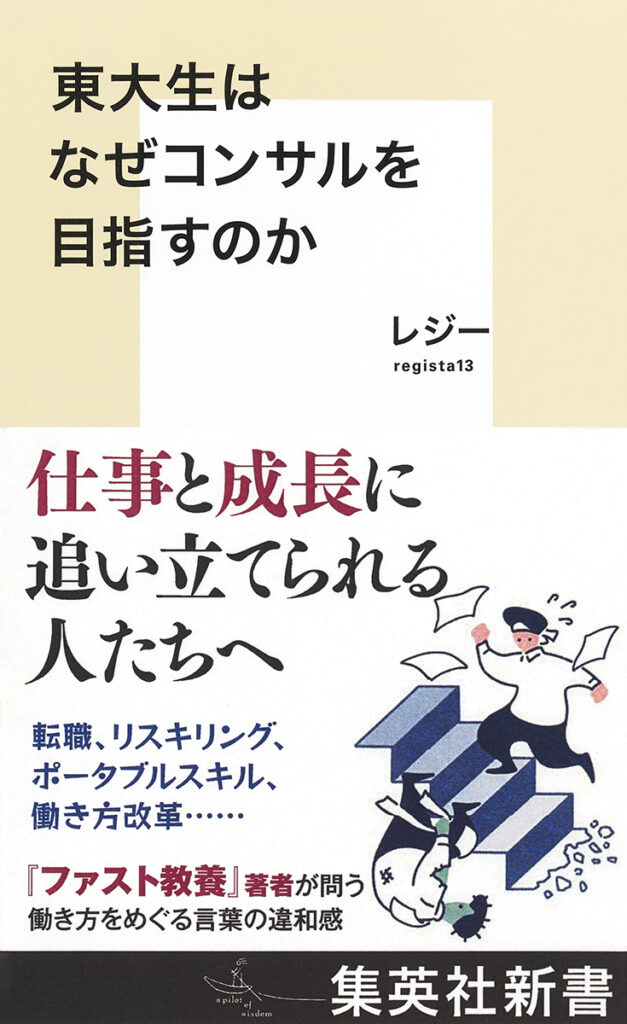








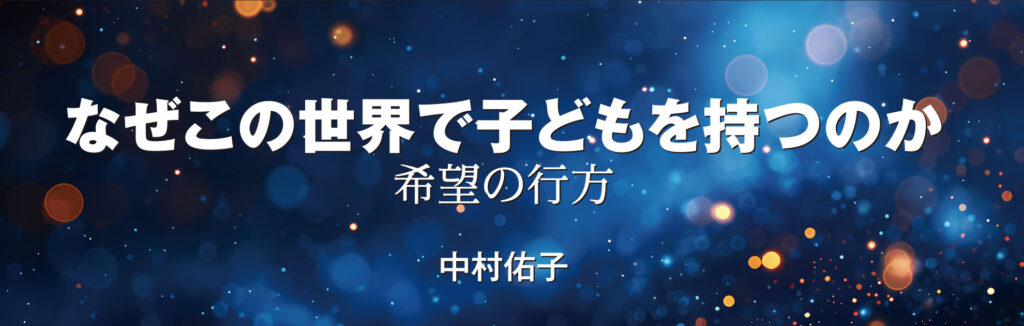

 青木 理×藤原辰史
青木 理×藤原辰史



