フィクションの世界や、歴史や伝承のなかで語り継がれてきた「魔女」。その精神は、現代の私たちの生活や社会、世界の見え方を変えうる力を持っている。本連載ではアメリカ西海岸で「現代魔女術(げんだいまじょじゅつ)」を実践しはじめ、現代魔女文化を研究し、魔術の実践や儀式、執筆活動をおこなっている円香氏が、その歴史や文脈を解説する。
今回は現代魔女の考え方の核になった新宗教、Wicca(ウイッカ)の成り立ちを追う。
ウィッカとは何か
現代の魔女文化を理解しようとするとき、私たちはまず、Wicca(ウイッカ)という新宗教に目を向けなければならない。ウイッカとは、「私は魔女だ」と世界で初めて証言した人物ジェラルド・ガードナーとその仲間たちが実践し、世に広めた魔女の霊的実践ないし宗教のことだ。現代魔女たちのすべてがウイッカだというわけではない。だが、現存するほぼすべての現代魔女の実践は何かしらの形でこのウイッカから影響を受けている。私自身もウイッカではなく、また私自身の考え方は英国伝統派ウイッカとは異なっている箇所が多くある一方で、私の実践する現代魔女術にもウイッカから取り入れた要素が多くある。Traditional Witchcraft(伝統派ウイッチクラフト)と呼ばれるウイッカとは別の流れを主張する流派でさえ、実際にはウイッカの考えが混ざっている場合が多い。したがって、現代魔女の文化を知るためには、まずこのウイッカについて知る必要がある。
ウイッカは古い異教の神々を崇拝する宗教である。これを初期のウイッカの実践者たちは「古き宗教」と呼んだ。彼らは石器時代の角のある男神(有角神)と母なる女神への信仰を中心とする「豊穣の宗教」が地下で密かに受け継がれてきたという物語を掲げた。これをキリスト教以前の自然崇拝の名残とみなし、「古き宗教」と称したのだ。少なくともウイッカの中心人物であったジェラルド・ガードナーはそう定義していた。また、彼らの行う実践は古代の神々の力を借りて魔術を行うためのシステムであり、その実践を通して自身と世界への理解を深める神秘的な伝統である。
この「古き宗教」はガードナーが文化人類学者マーガレット・マレーの「魔女カルト理論」を下敷きに20世紀に編みだした創造的な新宗教であり、後に「ウイッカ」と呼ばれるようになった。先にあらかじめ述べておくが、現在のウイッカの実践者や現代魔女の世界でガードナーの言ってることを文字通り受け取る者は殆どいない。しかし、このガードナーが晩年に見出した「古き宗教」のコンセプトは後の魔女文化に多大な影響を与えている。
ウイッカの父 ジェラルド・ガードナー
ジェラルド・ガードナーは1884年、ランカシャーの裕福な家庭に生まれた。幼少期に喘息を患った彼は、温暖な気候を求めてマデイラ島へと移住。青年期を迎えると、セイロン、北ボルネオ、マレーシアの茶とゴムのプランテーション経営者や税関職員として、原住民や東洋の文化と密接に関わる生活を送るようになる。ガードナーは背が高く、ユニークな髪形と口ひげを蓄え、腕にはタトゥーがあった。アマチュアの文化人類学者でもあった彼はナイフの研究にも熱心であったと言われる。人類学、宗教、オカルティズムに関する多くの書物を読み、フリーメーソン、心霊主義、儀式魔術、そして様々な部族の魔術的実践に情熱を燃やしていた。
1936年、52歳でロンドンに引退したガードナーは、2年後、ニューフォレストに移住する。そこで彼は、クリスチャン・チャーチの薔薇十字団劇場を発見し、入団。
やがて演劇活動を通じ、彼は古代宗教の生き残りとされる魔女の集会に出会うことになる。かくして1939年9月、「オールド・ドロシー」と呼ばれる魔女によって、彼は魔女の集会「ニューフォレスト・カヴン」へと入門した。
彼は古代の魔女のカルトの生き残りに出会った——少なくとも、ガードナーはそう語っている。ガードナーはこの魔女たちの信仰を絶やさない様に受け継ぎ、現代に甦らせようとした。ここでいう魔女たちの信仰が後に魔女の宗教——ウイッカとして知られる事になる。ジェラルド・ガードナーは1949 年に後のウイッカにつながる儀式要素を小説「高等魔術の助力」として発表する。しかし、この本はあくまでも建前上はフィクションとして発表したものだった。その背景には、当時のイギリスにおいて魔術の実践がいまだ違法であったという事実もある。イギリスでは1735年から20世紀に至るまで魔術、霊媒を裁く法律、通称アンチウィッチクラフト法が実在した。この法が1951年に新たに詐欺に関する法律が制定されるとともにようやく廃法となると、その翌年の1952年、ガードナーは公の場所で自分は魔女であると宣言、そして1954年にはウィッカについての初の著書『今日のウィッチクラフト(Witchcraft Today)』を発表する。
ウイッカの定義
ウイッカ、その名称もまた歴史的な論争の的となってきた。「ウイッカの父」と呼ばれるジェラルド・ガードナーだが、本人はその呼称とは裏腹に、自らがウイッカを創始したとは考えていなかった。彼の説明では、失われかけたウィッチクラフトが絶えることへ危機感があり、残り火を吹き返す意識で活動していたのだという。つまりガードナーからすると彼のはじめた現代魔女運動は「創造」でも、ましてや「でっちあげ」でもない「復興」なのだ。故にこの一連の運動はある時期までは現代魔女復興運動と呼ばれていた。この点に関して、今でも英国伝統派ウイッカの人々は「復興」と考えているようだ。そもそも、ウイッカが「復興」なのか「再創造」なのかも議論を呼ぶデリケートな話題ではある。80年代以降の例えばスターホークのような現代魔女たちは自らの宗教や霊性運動を「再創造」であると自ら認識する傾向がある。私自身も現代魔女文化は「再創造」の側面を強調して語ることがあるのだが、これは明らかに70年代のアメリカで生まれた新しい解釈である。歴史学のコンセンサスもウイッカの骨格はガードナーが多岐にわたる資料を再構成したものだということになっているが、完全に捏造したわけでもない。私の考えではウイッカは意図的にガードナーが「でっちあげ」たものでも「ジョーク宗教」でもないことは最初にはっきり言っておこう。
ガードナーは自分たちの「古き宗教」を「Wicca」(ウイッカ)とは呼んでいなかった。彼は「Wica」(ウィカ)という綴りを一貫して使用していた。「Wicca」(ウイッカ)という綴りが一般化していくのは、1950年代後半以降のことである。この微妙な綴りの違いは、一見些細な問題に思えるかもしれない。だが実際には、これは現代魔女文化の形成過程における複雑な事情を反映している。
そもそも、なぜガードナーは「Witch」ではなく「Wica」という言葉を選んだのだろうか。これには、当時の文化的・社会的背景が深く関係している。「Witch」という言葉はキリスト教が主流である欧米では長年、否定的な意味合いを持って使用されてきた。特に1950年代のイギリスでは、「黒魔術」や「悪魔崇拝」といった言葉とも混同され批判の対象になった。ガードナー達は自分たちの実践を、そうした否定的なイメージから区別し、つまり、無害な善い魔女であるかのように取り繕う必要があったのだ。70年代以降に普及したウイッカン・リードとして知られる魔女の信条の中にも「三倍の法則」として、彼らの基本的な倫理原則がみられる。「三倍の法則」とは、「あなたの行いは、良いことも悪いことも、三倍になって返ってくる」という考えだ。多くのウイッカン(ウイッカの魔女)はこれに従い、基本的にウイッカンは「呪い」などの害悪魔術を行わないことになっている。しかし、よく魔女たちに話を聞いてみればわかるが、ウイッカンであっても「魔術には本来白も黒もない」と言うだろう。これは本音と建前の話で、偏見と戦わなければならなかった時代に、無害な善い魔女であるかのように取り繕う必要があったということだ。
「ウイッカ」という言葉の使われ方は、学者や実践者によって異なる。厳密には、ウイッカとはガードナー派やアレクサンダー派など、これらの流派に基づく実践や、それらの流派に関連する出版物を元に実践する人々の系譜を指す。この本の中でも基本的にはそのように定義する。1970年代以降、ウイッカは多くの出版物や個人の実践によって多様化し、特にソロ魔女(グループに属さず独立して実践する個人)の増加により、他の魔術的伝統やニューエイジ文化などを取り入れつつ、より折衷的な形態へと変化した。その結果、アメリカを中心にウイッカという言葉の使用される範囲は広がり、新参者の大量流入により、時には流派や特定の伝統の区別が曖昧になることもあった。このことを快く思わなかった古参の魔女たちによって1980年代以降、アメリカでは「英国伝統派ウイッカ」という呼称が使われるようになった。これはイギリス発祥のガードナー派やアレクサンダー派に基づくウイッカ実践と、それとは異なるアメリカを中心とする折衷的なウイッカ実践を区別するために使われている言葉である。
ここでややこしいのが、「英国伝統派ウイッカ」とは別に「伝統派ウィッチクラフト」という言葉もある。これらは似た名称ながら、全く異なる流れを指す言葉であることに注意が必要だ。伝統派の魔女といった場合は後者を指す。
「英国伝統派ウイッカ」はガードナー派やアレクサンダー派といった、特定の体系化された宗派であり、元々は人から人へフィジカルにイニシエーションが行われていた。その実践者たちが、後にアメリカなどにおいてより折衷化、個人化して広まっていったウイッカの実践と自分たちの伝統とを区別して示すために用い始めた呼称である。
他方、「伝統派ウィッチクラフト」は、そもそもウイッカよりも古い起源を持つと主張する、まったく別のアプローチのことを指す。これらの流派は、ガードナーによって確立されたウイッカの伝統とは違い、より閉鎖的で世襲的であり、実践はより個人的でもある。彼らは民間の魔術やアニミズム、精霊や土地との繋がりを重視し、自分たちの実践がガードナーらのそれより古い魔術的伝統に基づくと主張している。ロバート・コクレンが創始した「トゥバルカインの一族」(Clan of Tubal Cain)などがその代表例である。
つまり「英国伝統派ウイッカ」は、ウイッカの中で特定の実践を表す呼称であり、「伝統派ウィッチクラフト」は、ウイッカそのものとは異なる、独自の魔術的伝統を主張する立場を指す言葉である。ウィッカという言葉を使うときはそれが何を指しているかに注意しなければならない(註1)。
魔女の語源
「『魔女』って女性だけなんですか?」
この質問を、私はこれまで数えきれないほどされてきた。
結論から言えば、「魔女」は決して女性だけではない。男性の「魔女」も存在する。英語の「witch」は、もともと古英語においてはwicce(女性形)とwicca(男性形)があったように、魔術を行う人を指す言葉には男女両方の形が存在していたのである。現代英語では 「witch」は多くの場合女性に対して使われるが、歴史的には男性の魔術師に対しても用いられていた。なぜ多くの人が「魔女=女性」というイメージを持つのか、その変遷については前章で述べたとおりだ。日本における「witch」の訳語としての「魔女」はさらに一ひねりがある。「魔女」に「女」という漢字が含まれているため、字面を見ただけで女性を連想してしまうのは普通の反応だ。この言葉は明治時代、森鷗外らによって西洋の「witch」や「Hexe」の翻訳語として広められ、定着した。「魔」という漢字自体は、仏教伝来とともに6世紀頃に日本に伝わったと言われている。元来は梵語「魔羅(māra)」の音訳で、「仏道修行を妨げるもの」を意味していた。仏教から「魔」の文字を取り入れたことは日本独自の非常にユニークな言葉の成り立ちである。そして、歴史的に「witch」は何も言わなければほとんどの場合女性を指していたので、日本語で「魔女」と「女」をつけて訳したことは理解できる。
ガードナーは『今日のウィッチクラフト』(1954年)の中で、「Wica」を「賢い者たち」という意味で使用している。この語源説は現在では学術的に否定されているものの、初期のウイッカたちは自分たちの説明として好んでこの解釈を使用していた。もう一度言うが、ガードナー自身が自分たちの宗派のことをウイッカ(Wicca)と呼んだことはない。彼は古英語の「wicca」(男性形)と「wicce」(女性形)という言葉の語源について言及した上で、敢えて一つのcで「Wica」と表記することを選んだ。だが、やがて「Wicca」という二つのcを持つ綴りが一般に浸透していく。その過程にも屈折があり、「Wicca」という呼称は、元々はガードナーの初期のライバルであった伝統派ウィッチクラフトの実践者、ロバート・コクレンが彼らの実践する「古いクラフト(the Old Craft)」と区別するため、ガードナーらを軽蔑、揶揄して使用したものだったのだ。それが、1960年代になると、ウイッカの実践者たちも「Wicca」という綴りを使用するようになっていく。その理由は「Wicca」の方が語源的により正確であるからだろう。そもそも、「witch」の最も古い形である古英語の「wicca」(男性形)と「wicce」(女性形)とは、もともと「占い師」「魔術師」といった専門職的な人物を指す言葉で、より中立的であり現在のような邪悪な意味はなかった。古英語=ラテン語語彙集では、「wicca」や「wicce」は、ラテン語で augur(占い師)や hariolus(神託者)などに対応しており、もともとは宗教的あるいは魔術的な専門職を指していた。しかし、教会法において特に女性の職能として取り締まられたことから、後世に「witch=女性」という性別固定の語感が強まったといわれている。
さらに語源を遡ると、古英語「 wicce」「wicca 」は、ゲルマン祖語の動詞 「wiccian」(魔術・呪術を行う)に由来するとされており、その語幹 「wikk- 」は、「予言」や「呪術的行為」、あるいは「死者との交信」といった意味領域に関わっていたと考えられている。こうした語源的背景から、「witch」 という語には、かつて「ネクロマンサー(死者を呼び覚ます者)」としての役割が含意されていた可能性も指摘されている。
しかし、これより上位のインド・ヨーロッパ祖語の語源については、複数の説が存在し、決定的な合意は得られていない。
主要な説として、原インド・ヨーロッパ祖語の推定形weyk-「聖別する・分離する」説、weik-「曲げる」説、weg-/wak-「目覚める・強い」説などがある。オックスフォード英語辞典では起源は「不確実」とされており、議論が続いている。
とはいえ、現代の魔女たちがどのような語源で魔女を説明しようとしていたかという点は、その時代の魔女像を反映するものとして注目に値する。
ガードナーが「Wica」という語を用いた背景には、迫害された魔女たちの異教の実践を復興しようとする意図があったと考えられる。あえて「Wica」=「賢い者たち」という意味でロマン主義的に再解釈し、彼が石器時代から続くと主張する異教の宗教に尊厳を与えようとしたのかもしれない。1970年代後半には、スターホークやマーゴット・アドラーによって古英語「wic」=「曲げる」という語源が強調され、「to bend」(曲げる)や「to shape」(形作る)という意味で解釈された。アクティビストの魔女たちは「現実を変容させる能力を持つ存在」として魔女を捉えたのである。この語源説明はどちらも学術的には正確であるとは言えないものの、彼らのアイデンティティの在り方について思想的意義を持つ解釈を提供している。
ウイッカの特徴と信仰と実践
季節の祝祭サバトと、月のサイクルに合わせた儀式エスバト。
女神と有角神、魔術の実践、生命力の崇拝というシンプルな信念。
ウイッカの特徴は、自然崇拝と多神教的要素が織り交ぜられた、豊かで多様な信仰体系として知られる。ウイッカには「Wiccan Rede(ウイッカン・リード)」と呼ばれる倫理的基盤があるが、教義は存在しない。
実践者の中には環境問題への深い関心の結果として、ウイッカ/現代魔女に興味を持った人たちもおり、彼らはこの惑星や大地を人間が支配できたり、所有しているとは考えていない。惑星と大地を自分たちの偉大なる母、女神として慈しむ。魔女たちはキリスト教、ユダヤ教などの禁欲的な一神教のように肉は罪であるとは考えず、肉体の喜びと生命を謳歌している。
魔女たちも他の宗教のように目に見えない世界のことも扱うが、非物質的現実が物質的現実よりも上位にあるとは考えず、むしろ仲間と一緒に踊ったり歌ったり、ともに宴を囲むような時間を大切にする。女神もスピリットも自ら、あるいは目の前の世界に内在し、私たちを取り巻く世界と自分たちの関係性に重点が置かれている。
ウイッカ/現代魔女たちは、新規参入を求める人たちのために道標を提供してきたが、決して積極的に改宗を求める宗教/文化ではない。英国の心理学者であると同時にウイッカ司祭であり、伝統と心理学を融合させた現代魔女術の理論家であるヴィヴィアン・クロウリーは多くの人々に適した宗教の形を提供するのではなく、少数の、しかし増加しつつある少数の人のための精神的な規律と道筋を提供するものだと説明している。この連載も布教を目的として書かれている本ではない。
また、ウイッカ/現代魔女は多元主義的な宗教であるとも言われ、多様な考え方が存在することに関して寛容である。流派によって、あるいは時代や地域によって一人ひとりの魔女が独自の解釈と実践を持ち、その世界観は複雑で言い表すことが困難だ。教義や聖典がなく、グルがいない宗教の中では同じ流派の中でさえ、多くの差異が存在し、同じ「魔女」といっても対立したり、考え方が違うのが常である。だから魔女たちは別の考え方を持った人たちと棲み分ける方法を学んでいったのだろう。そして彼らの実践は生きた宗教であるため、時代に合わせて常に変化し、常に動いていると考えている。
ここからは、大まかにウイッカの重要な実践を紹介しながら、ウイッカ以外の現代魔女の事例も少し紹介したい。
ウイッカへの参入 どうやって魔女になるの?
まずは「どうやって魔女になるのか」だ。ウイッカの魔女たちをウイッカンと呼ぶが、このウイッカンの世界に足を踏み入れる方法には、大きく分けて二つの道がある。伝統的なカヴンへの参加と、現代的な自己参入(セルフ・イニシエーション)である。
多くの書籍が出版される現在では独学と自己参入が最も一般的だろう。
特定のグループに所属するのではなく一人で活動する魔女をソロ魔女と呼ぶ。
ドリーン・ヴァリアンテ、ファーラー夫妻、レイモンド・バックランド、マリアン・グリーン、スターホーク、ヴィヴィアン・クロウリー、スコット・カニンガム、シルヴァー・レイブンウルフなどの実践者の本やインターネットで情報収集し、独学でウイッカや現代魔女術を学ぶ魔女は多い。もちろん、強い情熱と探求心は要求されるが、ウイッカ/現代魔女は資格制ではないため、自分自身で名乗りをあげ、ソロ魔女として実践を始めることができるのだ。
もしもあなたが現代魔女術の本を日本語で読みたいと思ったら、わたしの連載と並行して、国書刊行会の出版している『魔女たちの世紀』シリーズを読むことをお勧めしたい。このシリーズでは現代魔女術を知る上で最も重要な古典のいくつかが翻訳されており、日本における貴重な実践の教科書となっている。
カヴン
カヴンや特定の伝統への参加には、イニシエーション(通過儀礼)が必要となる。
カヴンとは、通常13人以下で構成される魔女の小さなグループである。この人数は、歴史的には魔女裁判での証言に由来するとされている。13人を超えた場合は二つに分かれ、クラフトの技術を継承していくことが推奨される。また、利害関係の衝突を避けるため、カヴン同士は約3マイル(約4.8キロメートル)離れて活動することが望ましいとされている。
カヴンは元々は閉鎖的なグループである。メンバーは親族のような親密な関係で結ばれており、守るべき秘密や誓約が存在する。彼らはカヴン内では魔女名を名乗り、深い精神的な繋がりと献身が求められる。
また英国伝統派ウイッカの伝統では、儀式はスカイクラッド(全裸)で行われるのが本来のスタイルである。魔女たちはキスを交わしながら魔法円に入り、カヴンのメンバー同士は共にサバトを祝い、生涯にわたるような非常に親密な関係性を結ぶ。
ここまで読んで、ウイッカの文化に対して「閉鎖的なのだろうか?」という印象を抱かれたかもしれない。当時のウイッカの閉鎖的な性格には理由がある。
「愚者と共に時間を過ごすべからず、さもなくば汝も愚者と見なされるだろう。」という一節は、1974年にペイガン誌 『グリーンエッグ』に掲載された『ウイッカン・リード』(通称「ロング・リード」)の一部である。道徳的助言としても読めるが、「誰と儀式を共にするかを慎重に選ぶべきである」というウイッカンたちの慎重で閉鎖的な姿勢を示している。この背景には、当時の社会情勢や魔女という言葉が社会に与えた脅威が深く関係している。アンチウィッチクラフト法の廃止後も、欧米では魔女であることが明らかになった人々は、解雇、職場でのいじめ、子どもの親権の喪失、軍務からの排除など、さまざまな社会的不利益に直面してきた。1980年代から90年代にかけてアメリカを中心に広がった「サタニック・パニック」(註2)の影響もあり、ウイッカンが職場や学校で宗教的差別を受けた事例は現在までも続いている。また、嫌がらせやスパイ行為、タブロイド誌による攻撃も相次いだ。このような背景があるため、彼らは「守秘誓約」や「紹介制」に基づき、信頼できる者だけを慎重にグループに受け入れていたといわれている。こうした姿勢は、外部からは閉鎖的に映るかもしれないが、当時の実践者たちにとっては身を守るための不可欠な戦略でもあったのである。
今日では、オープンなグループや独学の魔女も増え、ウイッカの実践はかつてよりもはるかに開かれたものとなっている。しかし、欧米では魔女がもともと社会的に異端とされ、危険視され、現実に実践者たちが迫害を受けてきたことは心に留めておいてもよいだろう。
ウイッカの「閉鎖性」は決して排他的な思想から生まれたものではなく、社会的な偏見や差別からコミュニティと実践者を守るための、現実的で必要不可欠な防衛戦略だった。
イニシエーション(通過儀礼)と自己参入の道
イニシエーション(通過儀礼)は、秘密結社への入会儀式のように厳粛な雰囲気の中で行われる。英国伝統派ウイッカには三段階の階位制度が存在し、各段階でイニシエーションが行われる。魔法円の中で女神と男神への誓いを立て、魔女としての名前を授かる。これは単なる形式的な儀式ではなく、イニシエートは深い精神的な変容を体験するとされる。
しかし、70年代後半以降、出版物による独学が一般的になると、「自己参入」という新たな道が開かれた。現在では、誰かに魔女にしてもらう必要はなく、師を探して放浪する必要もなく、一人で魔女になることが主流となっている。イニシエーションの本質は自己献身であり、最も大切なのは自分の内面で起こることだという考え方が広まったのである。
通常、自己参入を目指す者は、1年間ほど本を読み、クラフトについて学び、自分が現代魔女術に向いているかを深く考察することが推奨される。
実践の多様化
カヴンやグループで他の実践者から口伝で学ぶことは、より実践的な知識や組織での実践スキルを身につける伝統的な方法である。クラフトの知識は主に口伝で伝えられ、師弟間の信頼関係を築き、それぞれの流派の伝統を継承する重要な役割を果たしてきた。『影の書』と呼ばれる魔術の実践が記述されたレシピ集は魔女たちの間で手渡しで書き写され、次の世代に伝えられてきたものだ。
しかし、現代ではカヴン以外にも様々な実践の形態が存在する。例えば緩やかな繋がりの実践グループ、誰でも参加できる公開儀式、実践道具や書籍を扱う店舗のコミュニティ、オンライン・コミュニティなど、実際にはカヴン以外にも多様な選択肢があり、初学者にも開かれている。インターネット上の情報の質は玉石混淆だ。そして、小さなグループが生まれては数年以内に消えたり、地下に潜ったりを繰り返している。2025年現在、日本では翻訳されている書籍が限られ、実践者も少なく、カヴンも実践グループも非常に珍しい。このような環境で同じ趣味の仲間を発見することは容易ではないかもしれないが、数年熱心にやっていればきっとそのうち仲間を見つけられるだろう。
世界的に見ればソロ魔女が多数を占め、新しい世代の魔女たちは特定の流派や組織に所属したいという意識が薄まっている傾向があるかもしれない。SNSなどを駆使して緩やかな繋がりを求め、現代魔女たちの実践の仕方は50年前とは大きく変化している。例えばウイッカでない魔女や白人以外のアフリカルーツやメキシコルーツの魔女術の実践、異性愛規範に縛られないクィアの魔女たちが多く出てきたことやZ&ミレ二アル世代のマジカル・アクティビズム、悪魔の再評価、ウェールズやコーンウォールのような今までスポットの当たらなかった特定の地域に関連した魔女術の実践など、10年前よりも現代魔女たちの実践は明らかに多様化した良い面もある。一方で良くも悪くも商業化、大衆化が進んでいることは別の世代の魔女達との間に確執を生んでいる。また、別の層では流派や実践の系譜という考え方もしっかり残っており、SNSなどではあまり可視化されないが60代、70代の実践者に出会うこともある。私は彼らと世代を越えて交流できることを嬉しく思う。国境を越えて複数の伝統にイニシエートする魔女もいるため、実践は混ざったり、交流を通してより流動的で複雑な層を織りなしている。世界中に現代魔女のネットワークは存在している。
初学者の方には、まず書籍を丁寧に読み、ソロもしくは信頼できる友人やパートナーと少人数で実践を始めることを推奨したい。また、カヴンやグループの運営には、合意形成、信頼関係の構築、安全な空間づくり、儀式設計などに魔術実践と同等の熱量と経験が要求される。それらのオーガナイズの技法を学んでいくこともこの文化を長く、安心して色々な人と楽しむためには必須である。
現代魔女文化には、閉鎖的なグループと開かれたコミュニティ、師弟関係による伝承と独学、集団での儀式と個人での実践といった、さまざまな形態が存在する。それぞれに独自の良さがあり、実践の方法は非常に多様である。
円
魔女たちがスペルを作ったり、占術を行ったり、魔術を行う儀式空間は必ず円の中で行われる。これは太陽の動きに従って北半球では時計回り、南半球では反時計回りに描かれる。また、円は世界の狭間に象徴的に描かれる。たとえば、夜と昼、生と死、喜びと悲しみなど二つの概念のあわいと表現される。円を描く時はソード、もしくはアセイミーと呼ばれる黒い柄の両刃の短剣やウィッチ・ナイフを使用するのが一般的だ。ウイッカの魔女はアセイミーを別の用途では使用しないが、北米のフェリではそれでパンを切ったりしているので細かい作法は流派によって違う。儀式の場所決めはとても重要である。円を描く時は、その場所が人目につかない場所であるか、隔離された空間で静かに儀式が行えなければならない。
この円は魔女の流派によってはコンパスやクロスロードなどと表現される場合もある。空間を香や塩水で浄化し、ろうそくを設置し、東西南北の四方向に空気、火、水、地の四元素を呼び出し、その後にスピリットや神や女神などを呼び出す。魔術の作業が終わった後は、その場の人々と飲食を共にし、丁寧にお礼を言って神々と精霊を呼び出した順番で帰し、円をひらく。このような流れが一般的だが、流派や地域によってやり方は微妙に異なるので専門書を参考にして自分にあった方法を探求して欲しい。魔女たちの儀式には誘導瞑想、詠唱、ダンスなどが用いられ、即興的な要素が取り入れられることもある。非常に創造的に様々な儀式がデザインされる。
裸体(スカイクラッド)
イギリスで誕生した英国伝統派ウイッカの特徴として、儀式を裸体で行うというものがある。実際には気候などを考慮して柔軟に決められたり、ローブを着る場合もある。現在の書籍でウイッカになったソロ魔女は裸体を重視していないかもしれないし、他の流派の魔女も裸体を重視しないどころか、批判する魔女も多いが、魔女たちの裸体へのこだわりはこの文化を考える上で重要な要素だ。
そもそも、なぜ魔女は図版や絵画の中でしばしば裸で描かれるのか。そして、なぜウイッカンたちは裸で儀式を行うのだろうか。
まず、魔女が裸体で描かれることに関しては面白い逸話が存在する。プロテスタントが強い影響を持ったドイツでは、魔女を描くことが女性のヌードを表現する数少ない社会的に容認された方法であったという説だ。魔女狩りの時代の北ヨーロッパの絵画において、魔女はしばしば裸体で描かれた。歴史学者ロナルド・ハットンによれば、魔女がこの時代に裸体で描かれたのは、単純に裸体が本質的堕落の表現だったからだという。裸体は魔女狩りの時代には魔女たちの堕落を手軽に示す象徴だった。
ガードナーがこの魔女の裸体のイメージに惹かれたのは容易に理解できる。ウイッカの裸体儀式は明らかにヌーディストであったガードナーの嗜好によるものだ。
しかし、ウイッカンが裸体で儀式を行う理由には、いくつか実践的な興味深い説明がある。まず、身体がエネルギーを放出するため、衣服がそれを妨げるというもの。もう一つは裸体によってグループ内の平等と民主主義が強化されるためだという。また、そもそも裸で儀式を共に行うということ自体が、ウイッカンたちの親密で閉鎖的な性格を表しているだろう。彼らの実践は裸体で一緒に実践するほどの信頼関係が要求される。そのような信頼できる相手でなければ、そもそも一緒には儀式をしないということだ。これは理にかなっており、初期のウイッカの実践における試金石であったと考えることもできるだろう。
儀式の中での裸体は日常世界からの分離する強烈な感覚、意識の変化をもたらすと考えられており、日常の自分から、異世界への移行が促される一つの手段である。とりわけ西洋において裸体儀式は宗教儀式としてかなり珍しいものである。西洋においては長らく裸体が野蛮で汚らわしいものと見なされていた。その裸体を神聖な儀式に組み込もうとしたウイッカの実践は、体制的な価値観に抗するカウンターカルチャーとしての側面も持っていたのである。
(次回へつづく)
参考文献
Gerald B. Gardner. Witchcraft Today. Rider and Company, 1954.
Melissa Seims「Wica or Wicca? – Politics and the Power of Words」(The Cauldron no. 129、2008年8月)
Michael Howard「Traditional Witchcraft: Historicity and Perpetuity」(Benjamin Vierling interview、Three Hands Press、2012年)
大野寿子・千艘秋男・野呂香・早川芳枝・池原陽斉「なぜ”witch”や”Hexe”を「魔女」と訳すことができるのか——日本における「魔女」あるいは「魔」の系譜——」(『東洋大学人間科学総合研究所紀要』第10号、東洋大学人間科学総合研究所、2009年、75-92頁)
マーガレット・マレー『魔女の神』(西村稔訳、人文書院、1995年)
マーゴット・アドラー『月神降臨』(江口之隆訳、秋端 勉 監修、国書刊行会、2003年)
スターホーク『聖魔女術 スパイラル・ダンス』(鏡リュウジ+北川達夫訳、秋端 勉 監修、国書刊行会、1994年)
ドリーン・ヴァリアンテ『魔女の聖典』(秋端 勉 訳、国書刊行会、1995年)
Doreen Edith Dominy Valiente『An ABC of Witchcraft Past and Present』(Robert Hale、1973年)
Philip Heselton『In Search of the New Forest Coven』(Fenix Flames Publishing Ltd、2020年)
Ronald Hutton『The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft』(Oxford University Press、1999年)
Ronald Hutton『The Witch: A History of Fear, from Ancient Times to the Present』(Yale University Press、2017年)
Ethan Doyle White, Wicca: History, Belief, and Community in Modern Pagan Witchcraft (Sussex Academic Press, 2015)
註1: 例えば、スターホークはウイッカの魔女から多くの影響を受け、典礼などを引用しているが、実際にはフェリ派のイニシエートである。彼女はCOGにも関わっており、研究者によってはフェリもウイッカに近い流派のように扱われる場合がある。しかし、実際に現在のフェリやリクレイミングの魔女は自分たちをウイッカだと考える事は少ないだろう。むしろ明確に区別しているようにも見える。このような曖昧なケースが沢山あるので「ウイッカ」という言葉を使うときはそれが何を指しているか、どのように使われているかに注意したい。
註2: 1980年代から90年代にかけて、アメリカで「悪魔崇拝者が組織的に子どもたちを虐待・殺害している」という噂が広がり、全米各地で告発が相次いだ社会現象。発端は、ミシェル・スミスという女性が退行催眠により思い出したとする幼少期の悪魔的儀式の体験を記した「ミシェル・リメンバーズ」という書籍の出版だった。この本をきっかけに、テレビのワイドショーでもセンセーショナルに取り上げられ、「年間200万人もの子どもが悪魔の儀式の犠牲になっている」との主張が広まった。最も有名な事例が、1984年から1990年まで続いたマクマーティン保育園裁判で、6年間の裁判の結果、証拠は一切存在せず、すべての容疑者が無罪となった「史上最悪の冤罪事件」として知られる。
現在では、FBIも「悪魔崇拝者が幅広く虐待を行っているという事実はない」と結論づけており、実際は現代の魔女狩りに過ぎなかった。

フィクションの世界のなかや、古い歴史のなかにしか存在しないと思われている「魔女」。しかしその実践や精神は現代でも継承されており、私たちの生活や社会、世界の見え方を変えうる力を持っている。本連載ではアメリカ西海岸で「現代魔女術(げんだいまじょじゅつ)」を実践しはじめ、現代魔女文化を研究し、魔術の実践や儀式、執筆活動をおこなっている円香氏が、その歴史や文脈を解説する。
プロフィール

まどか
現代魔女。アーティスト。留学先のLAでスターホークの共同設立したリクレイミングの魔女達に出会い、クラフトを本格的に学びはじめる。現在はモダンウィッチクラフトの歴史や文化を日本に紹介している。未来魔女会議主宰。『文藝』『エトセトラ』『ムー』『Vogue』『WIRED』などに現代魔女に関するインタビューや記事を掲載。2023年から逆卷しとねとキメラ化し、まどかしとね名義でZINE『サイボーグ魔女宣言』を発売。笠間書院にて『Hello Witches! ! ~21世紀の魔女たちと~』を連載中。


 円香
円香





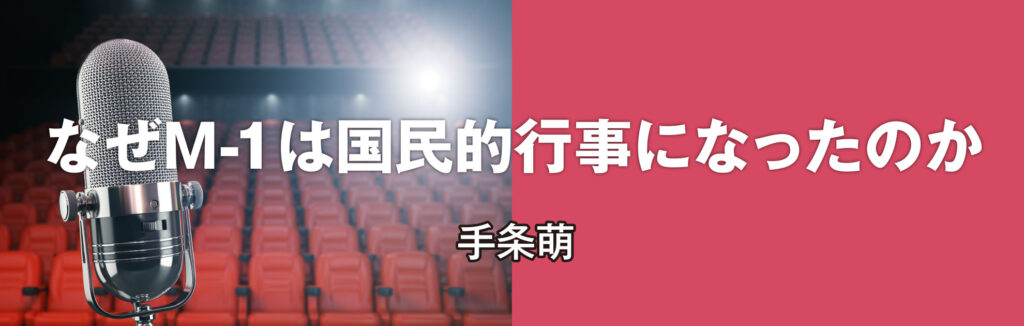



 菱田昌平×塚原龍雲
菱田昌平×塚原龍雲


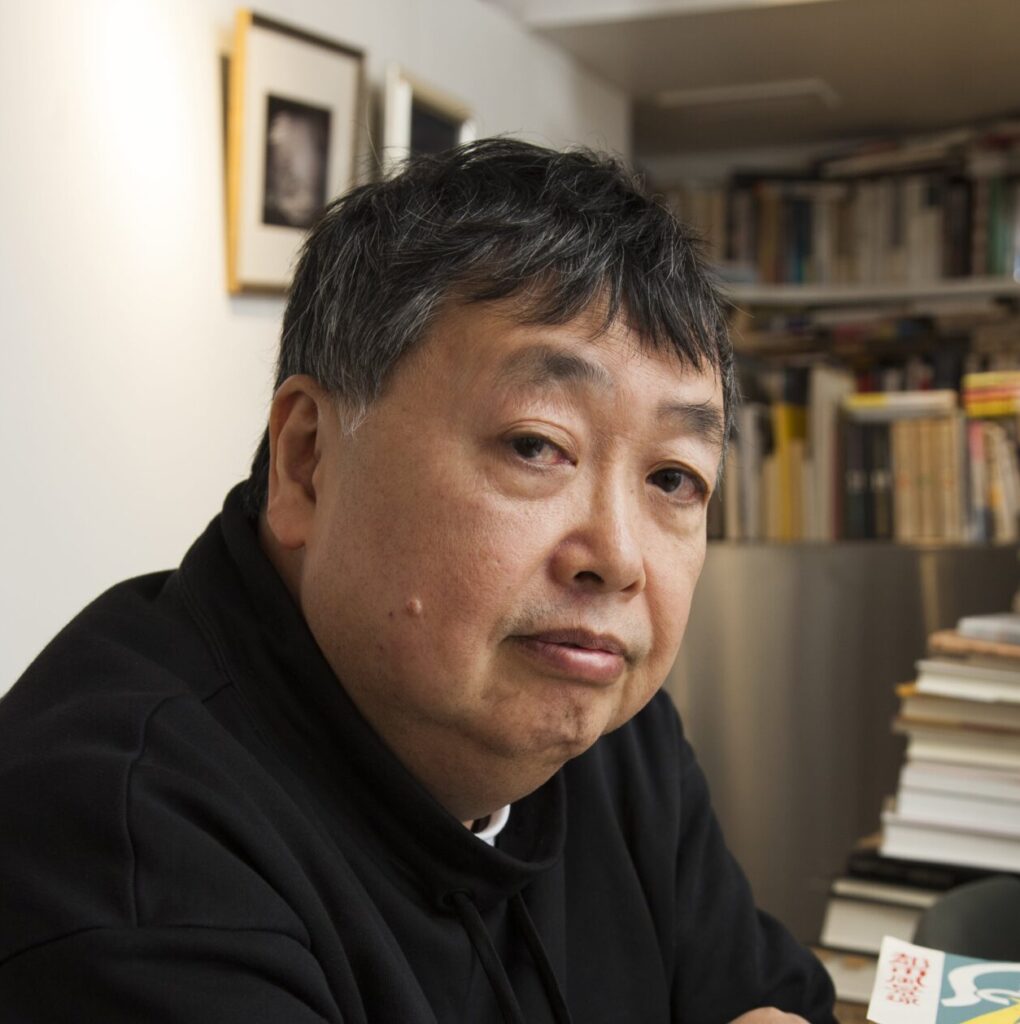
 大塚英志
大塚英志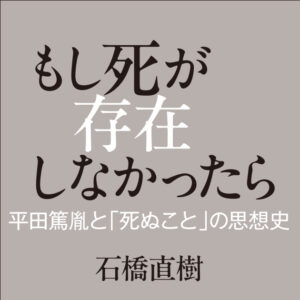
 石橋直樹
石橋直樹