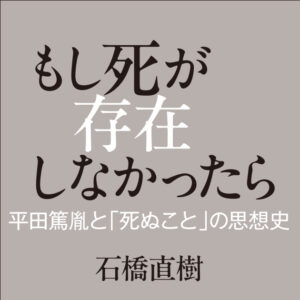なぜ死ぬことは「かすり傷」ではないのか
『死ぬこと以外はかすり傷』[1]というビジネス書がある。
気鋭の経営者やビジネスパーソンの書籍を手がけていた敏腕編集者の箕輪厚介が、自らの仕事術を語り、現代的な成功者になるための生き方が赤裸々に開示された本だ。「死ぬこと以外はかすり傷」というフレーズは、一度は口にしたくなるようなキャッチーさがあり、二〇一八年八月に刊行されるや否や一〇万部を突破し爆発的なベストセラーになった。
彼はいう。新しいことをすると社会的な制約から多くの抵抗を受けるけれども、何があっても結局、死ぬことはないのだから、本能と直感のままにとにかく行動せよ。この「死ぬこと以外はなんでも受け流せ」という呼びかけが、多くの反響を呼んだ要因であるように感じる。
けれどもそこには、死ぬことは「かすり傷」ではない、というメッセージが隠されている。発売当時、一六歳のわたしはそのことに少しだけ驚いていた。
どれだけエネルギーに満ちたビジネスパーソンでも、やっぱり「死ぬこと」は避けるべきものなんだ、と。それはそうだろう。
死は、確かにものすごく怖いものである。
医学は依然として進歩を続け、平均寿命は年々伸び続けており、私たちはかつてないほど長く生きられるようになった。事故や戦争による死もかつてほど身近ではない。進歩し続けている新しい医学がなんとかしてくれる。そんな安心感とともに、死は、日常生活の中から姿を消した。
現代社会は、死を「管理」することに成功した社会である。医療によって容易に人々は延命され、遺体は清潔な冷蔵庫に入れられて腐臭を出すこともなく、分業化した埋葬業者によって効率的に処理される。かつて僧侶や神父たち宗教者が担っていた死の場面は、いまや科学的な専門職の手に委ねられた。
だが、人々の死への恐怖が薄れたわけではない。むしろ、死を遠ざけようとすればするほど、その存在感は強くなっているようにすら思う。
死を知らない社会は、目の前の死をどのように取り扱っていいのかわからない。
私たちは「死」を受け止めることが苦手になっている?
ドラマや映画では登場人物たちが簡単に死に、その死をわたしたちは物語の一つの筋としてただ消費している。ドラマや映画のなかで、登場人物たちは、自分の死を前にして動揺し、恐ろしい表情を浮かべ、あるいは涙する。実際に自分が死ぬときは、あんなに大騒ぎして死にたくはないな……と思ってしまうほど、繰り返し、わざとらしく死を演出している。一方で、フィクションの中の死を見ている私たちは、おそらく無表情で、ここでこの登場人物が死んだのか、という情報を理解するだけにとどまるだろう。わたしたちはフィクションで人が死ぬことを見すぎているし、しかもフィクションでの死は大抵大げさだ。
要するに、演じている側も見ている側も、誰も本当にそこに死があると思って作品に触れているわけではないのである。私たちは死を見ているようで、実際には、死の情報を受け取っているにすぎない。
では、現実の人間が死んだときは、どうだろう。私たちは日々、SNSやテレビや新聞で有名人の訃報を多く見かけている。個人的にもっとも印象に残っているのは、二〇二三年に小説家の大江健三郎が亡くなったニュースだ。私は、確か友人とスーパー銭湯に行っていて、湯船から脱衣所に戻ってきてはじめて大江健三郎の訃報を目にした。六〇年代以降の日本小説を牽引してきた小説家、ノーベル文学賞の最後の受賞者が亡くなったことは、一つの時代が終わったと驚愕を覚えた記憶がある。
「大江健三郎」と検索欄に打ち込み、X(旧:Twitter)の画面をスクロールしていると、「ご冥福をお祈りします」「安らかに」という言葉が、一瞬のうちに大量に流れていった。訃報が流れて、一時間も経っていなかったので、それだけ多くの人が反応していることに驚いた。そして、同時に彼らは本当にこの一人の小説家の死に向き合うことができているのだろうか、とも感じていた。
相手が小説家だろうと俳優だろうと、他者の死とは、どこまでいっても情報でしかない[2]。乃木希典のように明治天皇の崩御に続けて自刃するというようなことは明治の精神と共に終わった。けれども、有名人が亡くなるとき、どういっていいかわからないような感情が確かに残ってしまうのである。それだから、私たちは「ご冥福をお祈りします」「安らかに」という言葉を、ものすごい速さで繰り出していく。弔いの言葉は、自分のうちで処理できない感情を吐き出してしまうことに向いているけれども、本当の意味で死を受け止めることにはならない。
結局のところ、私たちは、他者の死を「処理する」ことに慣れたが、死を「受けとめる」ことにはますます不器用になっているのだ。
コロナ禍の奇妙な感覚
死は、かつてのように共同体の出来事ではなく、極めて個人的で、孤立した経験となった。現実の死を語ることは、どこかタブーに近いものになり、死を恐れることすら「弱さ」の表れと見なされることも多い。
しかし、死の恐れは人間の根源にある。皮肉なことに、死の現実を直視する機会が減るほど、死の想像は肥大化していく。 もっとも近い出来事だと、コロナ禍のときに起きた死をめぐる反応が記憶に新しいかもしれない。連日ものすごい数の訃報が流れ、数字として多くの人が亡くなっているニュースが流れていた。そして、どこかの誰かに起こった死が自分にもやってくるのではないかと、家から出ずに手洗い消毒を徹底し、私たちはいわゆる自己隔離を各々にしていた。
あのときの奇妙な感覚を覚えているだろうか。連日の統計処理された死者数のニュースをみて、きっと自分は運悪く死ぬことなどないだろうという感覚と、もしかしたら、あのよくわからない「死」というものが自分の身の上にやってくるんじゃないかという感覚。その両者が共存していた。コロナ禍という時間は、みんなが、自分の「死」を少しだけ感じながら生きていく時間だったのかもしれない。そして、経験したことのない「死」が自分にもやってくるかもしれないという恐怖から、私たちは感染対策を徹底していったのだ。
こうしたことは、おそらく死と和解することに社会があまりにも慣れていなかったことに起因するかもしれない。この社会で生きていくなかで、死を直感することはおそらく極めて少ない。誰もが極めて安全な死を、情報として受け取っている。山手線の広告に葬儀屋さんのものが載っているのを見たことは、多分ないだろうと思う。わたしたちの見えないところに死はどんどんと追いやられている。
私たちが生きる現代以前の時代においては、死はもっと身近だった。というより、当たり前だけれども、生きるということは本来、表裏一体に死がまとわりついているのである。現代以前の人は、自分が先祖として人々を見守るであったり、楽園に行くであったり、身近な死を受け入れるための説明をたくさん持っていたのである。死は身近にある怖いものだったかもしれないが、だからこそいつ来てもいいように、理解をしようとしていた[3]。
では、もっと問いを突き進めてみたい。そんなに身近にあるものなら、本来避けられないものでしかないのだから、死なんて怖くはないのではないか。論理的にはそんな可能性が浮かんでくるのである。だから私たちは、次の問いに進んでいかなければならない。
そもそも人はなぜ死を恐れるのか。
「生権力」の時代
死を恐れることは、生物としての本能なのか、文化や言語が作り出した構築物なのか。あるいは、「生きる」という意識の裏面に、必然的に組み込まれた構造なのか。
二〇世紀後半、哲学は「生きていること」そのものが権力の対象となる時代を発見した。哲学者のミシェル・フーコーが『知への意志』[4]で提示した「生権力」という観念は、その最初の大きな転換点だ。
近代以前の権力は「死を与える権利」を中核にしていた。王は臣民を処刑することでその支配を示した。しかし十八世紀以降の社会では、権力の重心が「殺す」ことから「生かす」ことへと移行する。国家や制度は、人々の健康、出生率、寿命、衛生といった「生の総体」を調整・管理する装置となった。すなわち、人々が「生きていること」を管理することが権力の重要な機能になった。これがフーコーのいう「生権力」である。
その後、哲学者のジョルジョ・アガンベンはこの理論を一歩先へ押し進めた。彼はフーコーが描いた「生の政治化」という過程の裏側に、より根深い権力の構造を見出す[5]。アガンベンによれば、近代国家は人々の生を守ると同時に、誰を「生かすに値する存在」とみなすかをも決定する。すなわち、生を包み込むはずの権力は、同時に「ある生を排除する力」でもあるのだ。
つまり、フーコーが描いた「生を管理する権力」は、アガンベンを経て「生を選別し、排除する権力」へと姿を変える。国家は生を保護する名のもとに、特定の生を法の外へと追いやる。この構造こそが、アガンベンが「例外状態」と呼ぶ現代政治の核心である。
アガンベンはコロナ禍の初期に「根拠薄弱な緊急事態によって引き起こされた例外状態」(2020/2/26)[6]と「釈明」(2020/3/13)[7]と題された2つのコメントを発表している。彼は、コロナという感染症への対策として唱導された非常事態措置が、人々の権利を大幅に制限しつつあることに強い異議申し立てを示したのである[8]。この記事は即座に、多くの哲学者から批判を受けて、ある意味で「炎上」をしたものだ。けれども、コロナ禍に関する考察としてアガンベンらしい言葉を残している。
死者──私たちの死者──は葬儀を執りおこなわれる権利がないし、愛しい人の死骸がどうなるのかはっきりしない。私たちの隣人なるものは抹消された。このことについて教会が沈黙しているのは興味深い。いつまで続くのかもわからぬまま、このようなしかたで生きることに慣れていく国にあって、人間関係はどのようなものになるのか?延命以外の価値をもたない社会とはどのようなものか?[9]
アガンベンの国イタリアは、コロナ禍によって多くの死者を出した国の一つである。そうした国の中でアガンベンは緊急事態措置に警鐘を鳴らした。
アガンベンの問題意識は、ウイルスそのものよりも、それをめぐる社会の反応にあった。彼が見たのは、「生き延びること」以外のすべてを停止した社会、すなわち人間関係、宗教的儀礼、政治的討議、友情までもが「感染のリスク」という名のもとに失われていく光景だった。人々は「生き延びること」だけを至上の価値とし、互いを避け、死者を弔うことすらできない。そこには、もはや共同体も倫理も存在しない。ただ「生き延びること」だけが、唯一の信仰として残る。
確かに多くの批判はあるだろう。しかし、後から考えたならば、この指摘はまさに的を射ていたように思われてならない。私たちはいま、「生き延びること」、すなわち「死なないこと」に取り憑かれている時代を生きている。
コロナ禍以後、私たちは死ぬことがとにかく怖いのである。
オーガニックの「生き延びる」思想
「生き延びること」に取り憑かれているとはどういうことだろうか。確かに生きていくということは人間のもっとも重要な価値の一つである。けれども、「生きていくこと」と「生き延びること」は根本的に違うように思う。
私たちは働いたり、友達と遊んだり、本を読んだりして、「生きていくこと」をしている。「生きていくこと」とは、友情や愛情、文化や政治を通じて意味ある人生を営むことをいうだろう。そうした人生を通じて生活は豊かになっていく。一方で「生き延びること」は、自由も共同性も奪われ、ただ生命を維持するだけの状態である。パンデミックは、私たちを「生きていくこと」から切り離し、ただ単に生命があるという状態へと導いている。
たとえば近年、オーガニックやグルテンフリーなど食への関心はますます高まっている。特にオーガニックは様々なところで紹介され、多くの人々が実践しているという。オーガニックの実践には、有機農業、国産種子保護、糖類・パン類の拒否、加工食品・食品添加物の拒否、無農薬推奨などが挙げられる。これらはいずれも化学的な物質を含まないものを食べて、「生き延びること」を目指したものである。
自然食品を重視する食の実践自体は、確かに昔からあったものではある。たとえば、一九二〇年代に桜沢如一が提唱したマクロビオティックという実践は、玄米食などを通じて自然の法則と一体化しようとしていた。けれども、マクロビオティックが明確に目指していたのは、戦争で戦える兵隊を作るための自然食の実践であった。言い換えるならば、戦争で戦って「死ぬこと」ができる肉体を作るために、純粋な自然食を食べることが求められたのである[10]。そうした意味で、オーガニックは全く逆だ。
不純物のない、混じりけのない純粋な食としてのオーガニック、それは生活の中のリスクを極力少なくしていくことで「生き延びること」を目指そうとする運動だろう。オーガニックの人々からすると、食品添加物を摂らないことは発がんのリスクが下がり、より長く生きられるようになっていく。化学的に加工されたものは、文字通り「毒」であるから食べないほうがいい、そうした考えが近年色々なところで見られる。
現代的なオーガニックの実践の流行は、コロナ禍の問題を引き継いていると思う。私たちがまだ忘れることのできていない「生き延びること」だけを考えていた緊急事態宣言下の生活、そうしたものの延長にあるように思う。外から何かを取り込むことをしない、化学的なものを食さない、ただありのままの生命を延長するという「生き延びること」が過剰に重要視されているのである。
「生き延びること」とポピュリズム
実は、政治の世界もまた、「生き延びること」をとても重要視している。そもそも、選挙という政治機構は「生き延びること」を大切にする世界であった。現在の国政選挙においては、「生き延びること」ができていると一票が与えられる。すなわち、生存していることによって一票が与えられ、その一票によって政治家を選出しているのである。
最近になってこのことが、「生き延びること」を重視する食の論理と密接に関連していった。まさに、ポピュリズム的論理においてである。 ポピュリズムとは、しばしば民衆の生存、生活の不安を直接的に政治の中心に据える政治手法である。経済的不安、社会的不安、犯罪や疫病への恐怖など、「生き延びること」に直結する問題を政治課題として掲げている。そうすることによって、分裂する人々の一票を、「私たち」としてまとめていく政治運動である。だから、言い換えると、ポピュリズムとは誰もが抱える「生き延びること」への執着を揺さぶり、その「生き延びること」を目指す人々の集合を、一つの「私たち」にまとめていく運動ということができるかもしれない。
その上で、わたしは、別の可能性はないのかということを考えてしまう。
「生き延びること」ということが、私たちの上にあまりに重要な問題としてのしかかっているために、多くのことを私たちはできなくなってしまっているのではないか。「生き延びること」が重要でないと言っているわけではない。私たちの思考が「生き延びること」をあまりにも重要視しているために、見えなくなっているオルタナティヴがあるのではないのかと思う。
そのためにまず、「死ぬこと」に真摯に向き合ってみるというのはどうだろうか。「死ぬこと」は確かに恐ろしい。けれども、いずれやってくる「死」から目を塞ぎ続けてきた結果、私たちは「生き延びること」以外何も考えられなくなってしまった。私たちが今いる「生き延びること」の時代から、別の可能性を発見するためにはまず「死」について考える必要があるのである。
死と和解すること、それが本連載で目指したいことである。
『遠野物語』と「死との和解」
「死ぬこと」について考える上で、おそらく最も豊かな可能性を示してくれるのは民俗学の世界だろう。民俗学者の柳田國男が書いた『遠野物語』第九十九話には、一八九六年六月の明治三陸津波で犠牲になった人々のゆく先についての話が載っている。それは次のような話である[11]。
福二という人は海岸近くの田の浜へ婿に入っていたが、一八九六年の明治三陸大津波に遭い、妻と子を亡くした。彼は生き残った二人の子どもとともに、元の屋敷跡に小屋を建てて、一年ほど暮らしていたという。
ある夏の初めの月夜のこと、福二は夜中に用を足そうと起きた。便所は離れた場所にあり、波が打ち寄せる浜辺を通る道を歩いていく必要があった。その夜は霧が立ちこめていた。ふと霧の中に、男女二人がこちらに近づいてくるのが見えた。見ると、女はまぎれもなく、先の津波で亡くなった自分の妻だった。
思わずそのあとを追うと、二人はどんどん歩いていき、やがて船越村の方角の、岬にある洞穴のあたりまで来た。そこで福二が妻の名を呼ぶと、彼女は振り向いて、にっこりと微笑んだ。傍らの男は誰かと思えば、やはり波に呑まれて亡くなった者であった。そしてその男は、福二が婿に入る以前に、その妻と深く想い合っていた輩であった。
死んだ妻は「今、この人と夫婦になりました」という。福二は「子どもたちのことは、かわいくないのか」と尋ねると、妻は少し顔色を変え、泣き出した。死んだ人と話をしているとは、すぐには思えなかった。
そのうちに、男女は再び足早に去っていき、小浦へ向かう山の陰にまわって、姿を消した。追いかけようとしたとき、福二はようやく、そうか、あれは死人だったと気づいたという。夜明けまで道の途中で考え込み、朝になって家に戻った。それからしばらくのあいだ、福二は病に伏せて苦しんだという。
間違いなく、この話は大津波で死んだ人々への供養の意味を込めている。筆舌に尽くし難いような死の経験と、必死で和解しようとする意図がここには込められているといっていい。亡くなった人々は死んでも楽しくやっている、新しい男も作って楽しくやっているんだと。そして生き残ってしまったものたちはそのことを悔いて生きていかなくてもいいのだという「死との和解」の物語としてみるべきだろう。
そしてこの話は、死に対する理解として二つの道筋を示してくれているということができる。一つは、最も親しい愛すべき人が亡くなったとき、その耐え難い出来事とどのように和解するかということである。身近な人が亡くなると、私たちはその出来事をどのように乗り越えればいいかわからなくなる。しかし、妻はあの世で愛人でも作ってうまくやっている。そう考えると、自分だけが生きていることの苦悩、いわゆるサヴァイヴァー・コンプレックスからは幾許か解消される。
そして、もう一つは、自らが死ぬことへの恐怖をある程度和らげてくれることでもあるかもしれない。死んだらどこか遠いところに行かなければならないのではなく、この世界の近くで交流している。そのように考えることはおそらく死への恐怖から幾許か解放されるだろう。
柳田國男は実は『遠野物語』を書いたとき、死後の世界の話に非常に興味を持っていた[12]。当時の柳田はいわゆる心霊研究に没頭していたのである。死んだら魂はどこにいくのか、そうした問いが柳田の中にあった。そして遠野に残る死後の世界を語る民話に出会ったのである。遠野に残る死後の世界は、人々が住むこの世のすぐそばにあって、見えないけれども絶えず交流しているような場所に位置している。そういう世界に柳田は魅かれたのだ。
柳田がこのような死後観念を持っていたのには、当時柳田が丹念に読み込んでいた一人の思想家の影があった[13]。柳田は、その思想家を読み込み、死後の世界はこの世から連続した相互関係にあるような場所であると考えていた。
その思想家の名前は、平田篤胤である。
死の思想の幽れた淵源、平田篤胤
江戸時代後期の国学者・平田篤胤は、死後の世界をめぐって独自の思想を築いた人物である。篤胤にとって「死ぬこと」は終わりではなく、魂がこの世を離れたあとに向かうもう一つの世界、篤胤の言葉でいうならば「幽冥界」への移行を意味していた。彼はこの幽冥界を、遠い彼方の異界としてではなく、現実の世界のすぐ裏側に重なるように存在する場として描いている。篤胤は、人々が死後向かう場所である幽冥界について、次のように述べている。
「死者の魂が黄泉の国へ帰る」という古い説は、どうもそのままでは受け入れがたいところがある。では、人が死んだあと、その魂はいったいどこへ行くのか。この国の人々について考えると、古くからの伝承と、現実に起こるさまざまな出来事とを照らし合わせることで、魂が実はこの国土の中にとどまっていることが明らかに知られる[14]。
篤胤は、人が死んだら「黄泉の国」へ行ってしまうということを否定する。どこか遠いところに行ってしまうのではなくて、実はこの国土にとどまっているのだというように考えているのである。篤胤は続ける。
さて、この「冥府」とは、現実の国とは別のどこか遠くに存在する場所ではない。それはこの現実の国の内側にあり、どこにでもあるが、ただ目には見えず、ほのかで、現世とは隔てられているように見えるだけである。だからこそ、中国の人々もまた「幽冥」や「冥府」と呼んだのである。そして、その冥府の側からは、人間の行いがよく見えているらしい……。しかし現世の側からは、その幽冥の様子を見ることはできない[15]。
篤胤が考える「あの世」は、この世の中から離れてどこか遠くに存在する場所ではないという。現実の国と表裏一体にあって、どこにでもあるのだけれども、目には見えないために、私たちの世界と隔てられているように感じるだけだという。しかし、「あの世」の側からは、現世の世界がはっきりと見えるのだという。
なぜ、この世からあの世が見えなくて、あの世からこの世が見えるのか。篤胤は次のようにいう。
これをたとえるなら、一つの灯火の籠を、白い紙と黒い紙とで真ん中で仕切って部屋に置いたときのようなものである。暗い側からは明るい側がよく見えるが、明るい側からは暗い側を見ることができない。このように、両者の違いを理解すれば、また幽冥界がいかに神聖で畏れ多いものであるかも悟ることができよう。(ただし注意しておきたいのは、これは単に現実の世界と隠れた世界の違いを譬えただけであって、幽冥界が「暗く」、現世だけが「明るい」という意味ではない。そう誤解してはならない。)実際のところ、幽冥界にも、それぞれの魂にふさわしい衣・食・住の道がそなわり、まるでこの世と同じような有り様をしている[16]。
あの世とこの世との関係を、篤胤は興味深い比喩で説明している。それは、ひとつの灯火を白と黒の紙で仕切って籠に入れたようなものだという。暗い側からは明るい側の様子がよく見えるが、明るい側からは暗い側をうかがうことができない。現世の人間が死後の世界を直接見ることができないのは、そのためである、と。だが、死者の側からは生者の営みが見えていると、篤胤は考えた。
現代的に考えたならば、夜のガラス窓を考えてみるといいかもしれない。夜暗いときにガラス窓を見ると、暗い外から明るい中は見えるけれども、明るい中からは暗い外はみえない。そんな関係を篤胤は考えているということができるだろう。
ここで注意すべきは、彼が幽冥界を単に「闇」として描いているわけではない点だ。現世が「明」として、幽冥が「闇」として対立するのではない。むしろ両者は、紙一重を隔てて共に存在する、重なり合う世界の二つの相である。
篤胤における「死ぬこと」とは、決して消え去るのではなく、別のかたちで生き続け、しかも生者の世界と絶えず関わりをもっている。幽冥界は、恐怖や穢れの領域ではなく、むしろただ見えないだけの並行世界として位置づけられた。私たちが暮らす現世は、その一部にすぎないという構図を、篤胤は描き出したのである。
幽冥界という思想は、死者と生者とが絶えず交錯する回路でもあった。死者はこの世から消えるのではなく、私たちには見えないこの場所で生き続ける。この奇妙だが妙な親近感のある死の思想。それは、日本史の隠れた裏側をなしているといってよい。
「生き延びること」に強くとらわれてしまうのではなく、さまざまな生き方のオルタナティヴを模索するために、「死ぬこと」の多様性について考えてみたい。「死ぬこと」はいつか私たちに降りかかってくる。これは間違いないことだ。その必然の運命から目を背けるのではなく、いつかやってくる死と和解する道を探ってみること、それこそが現代において喫緊の課題というべきだろう。
「死ぬこと」の思想史、その豊かな内奥に、平田篤胤という一人の思想家を案内人としながら、追っていきたい。
(次回へつづく)
[1] 箕輪厚介『死ぬこと以外かすり傷』マガジンハウス、二〇一八年。
[2] いわゆる「二人称の死」。ジャンケレヴィッチ『死』みすず書房、仲澤紀雄訳、一九七八年。
[3] いわゆる「飼いならされた死」。フィリップ・アリエス『死と歴史』みすず書房、一九八三年。
[4] ミシェル・フーコー『知への意志』新潮社、渡辺守章訳、一九八六年。
[5] ジョルジョ・アガンベン『ホモ・サケル』以文社、高桑和巳訳、二〇〇七年。
[6] Giorgio Agamben, “Lo stato dʼeccezione provocato da unʼemergenza immotivata”, Il Manifesto, 25 febbraio 2020, https://ilmanifesto.it/lo-stato-deccezione-provocato-daunemergenza-immotivata/
[7] Giorgio Agamben, “Chiarimenti”, Quodlibet, 17 marzo 2020,https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-chiariment
[8] 國分功一郎「コロナ禍と世界の哲学者たち」『学術の動向』日本学術会議、第二十六巻第十二号、二〇二一年、六三―六六頁。
[9] ジョルジョ・アガンベン『私たちはどこにいるのか?』青土社、高桑和巳訳、二〇二一年(Kindle版より引用)
[10] 武田崇元・横山茂雄『霊的最前線に立て!』国書刊行会、二〇二四年、六九―七〇頁。
[11] 「土淵村の助役北川清と云ふ人の家は字火石に在り。代々の山臥にて祖父は正福院と云ひ、学者にて著作多く、村の為に尽くしたる人なり。清の弟に福二と云ふ人は海岸の田の浜へ婿へ行きたるが、先年の大津波に遭ひて妻と子とを失ひ、生き残りたる二人の子と共に元の屋敷の地に小屋を掛けて一年ばかりありき。夏の初の月夜に便所に起き出でしが、遠く離れたる所に在りて行く道も浪の打つ渚なり。霧の布きたる夜なりしが、その霧の中より男女二人の者の近よるを見れば、女は正しく亡くなりし我妻なり。思はず其跡をつけて、遙々と船越村の方へ行く崎の洞のある所まで追い行き、名を呼びたるに、振返りてにこと笑ひたる。男はと見れば海波の難に死せり者なり。自分が婿に入りし以前に互いに深く心を通わせたりと聞きし男なり。今は此人と夫婦になりてあると云ふに、子供は可愛くは無いのかと云へば、女は少しく顔の色を変えて泣きたり。死したる人と物言ふとは思われずして、悲しく情けなくなりたれば足元を見て在りし間に、男女は再び足早にそこを立ち退きて、小浦へ行く道の山陰を廻り見えずなりたり。追ひかけて見たりしがふと死したる者なりしと心付き、夜明まで道中に立ちて考え、朝になりて帰りたり。其後久しく煩ひたりと云へり」(柳田國男「遠野物語」『定本柳田國男集』筑摩書房、第四巻、一九六三年、四三頁)。
[12] 横山茂雄「怪談の位相」『遠野物語の周辺』国書刊行会、二〇〇一年。
[13] 渡勇輝「「古」を幻視する」『現代思想』総特集=平田篤胤」二〇二三年一二月、四五〇―四五九頁)。
[14]
「亡靈()の、黄泉國へ歸()てふ古説()は、かにかくに立ちがたくなむ。さもあらば、此の國土の人の死て、その魂の行方は、何處ぞと云ふに、常磐にこの國土に居()ること、古傳の趣きと、今の現()の事實とを考へわたして、明に知らる」平田篤胤「靈能真柱下都巻」『新修平田篤胤全集』名著出版、第七巻、一九七七年、一六九頁。
[15] 「抑()、その冥府と云ふは、此()顯國()をおきて別()に一處()あるにもあらず、直()にこの顯國()の内()いづこにも有なれども、幽冥()にして、現世()とは隔()り見えず、故()もろこし人も、幽冥()また冥府()とは云へるなり。され、其冥府()よりは、人のしわざのよく見ゆめるを(此は、古今の事實の上にて、明にしか知らるゝことなければ、今例を擧()げていはずとも誰も知らなむ、)顯世()よりは、その幽冥を見ることあたはず」平田篤胤「靈能真柱下都巻」『新修平田篤胤全集』名著出版、第七巻、一九七七年、一七〇頁。
[16] 「そを譬()えば、燈火()の籠()を、白きと黑きとの紙もて、中間()よりはり分ち、そを一間におきたらむが如く、その闇方()よりは、明方()のよく見ゆれど、明き方よりは、闇き方の見えぬを以て、此()差別()を曉り、はた幽冥()の畏きことをも曉りねかし。(但し此はたゞに、顯明()と、幽冥()の別()をたとへたるのみぞ、その冥府は闇()く、顯し世のみ、明()きとのことにはあらず、な思ひ混()へそよ、實は、幽冥も、各々某々()に、衣食住の道もそなはりて、この顯し世の狀ぞかし、)」平田篤胤「靈能真柱下都巻」『新修平田篤胤全集』名著出版、第七巻、一九七七年、一七〇頁。

マイクロビオテックやグルテンフリー、オーガニック……現代において、健康志向とスピリチュアルは密接に結びついている。さらに、そうしたスピリチュアリズムは反動的なナショナリズム運動と結びつき、社会のなかの排外主義や差別と結びついてしまっている。こうした健康志向・スピリチュアリズム・ナショナリズムの根底には、人間が生来持っている「死」への恐れがある。 このような時代の流れをどのように捉えればいいのか?「死」の恐怖から、人間は逃げられないのか?この問いを向き合うヒントは、平田篤胤とその門下生たちが辿った足跡にあった。 本連載では国学研究をおこなう著者が、篤胤を「人間の持つ『死』への恐れを乗り越えようとした思想家」として位置づけ、日本の国学の系譜を総攬することで、恐怖から生まれる反動的な思想を乗り越えるための思想を考える。
プロフィール
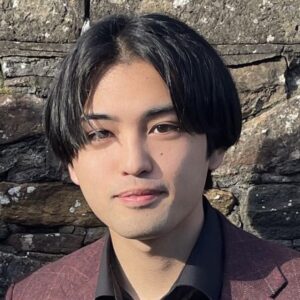
いしばしなおき 宗教学・近世思想史・文学。2001年神奈川県生。論考「ザシキワラシ考」で、2020年度佐々木喜善賞奨励賞を受賞し、民俗学を中心に執筆活動をはじめる(論考はその後『現代思想』「総特集=遠野物語を読む」に掲載)。論考「〈残存〉の彼方へー折口信夫の「あたゐずむ」から」で、第29回三田文學新人賞評論部門を受賞。論考「看取され逃れ去る「神代」」(『現代思想』「総特集=平田篤胤」)の発表以降、平田篤胤を中心とした国学思想を中心に研究を進める。編著『批評の歩き方』等々に寄稿。


 石橋直樹
石橋直樹



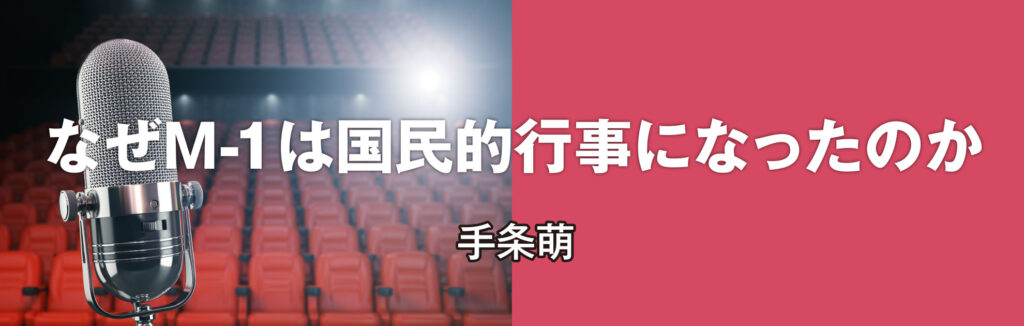





 菱田昌平×塚原龍雲
菱田昌平×塚原龍雲


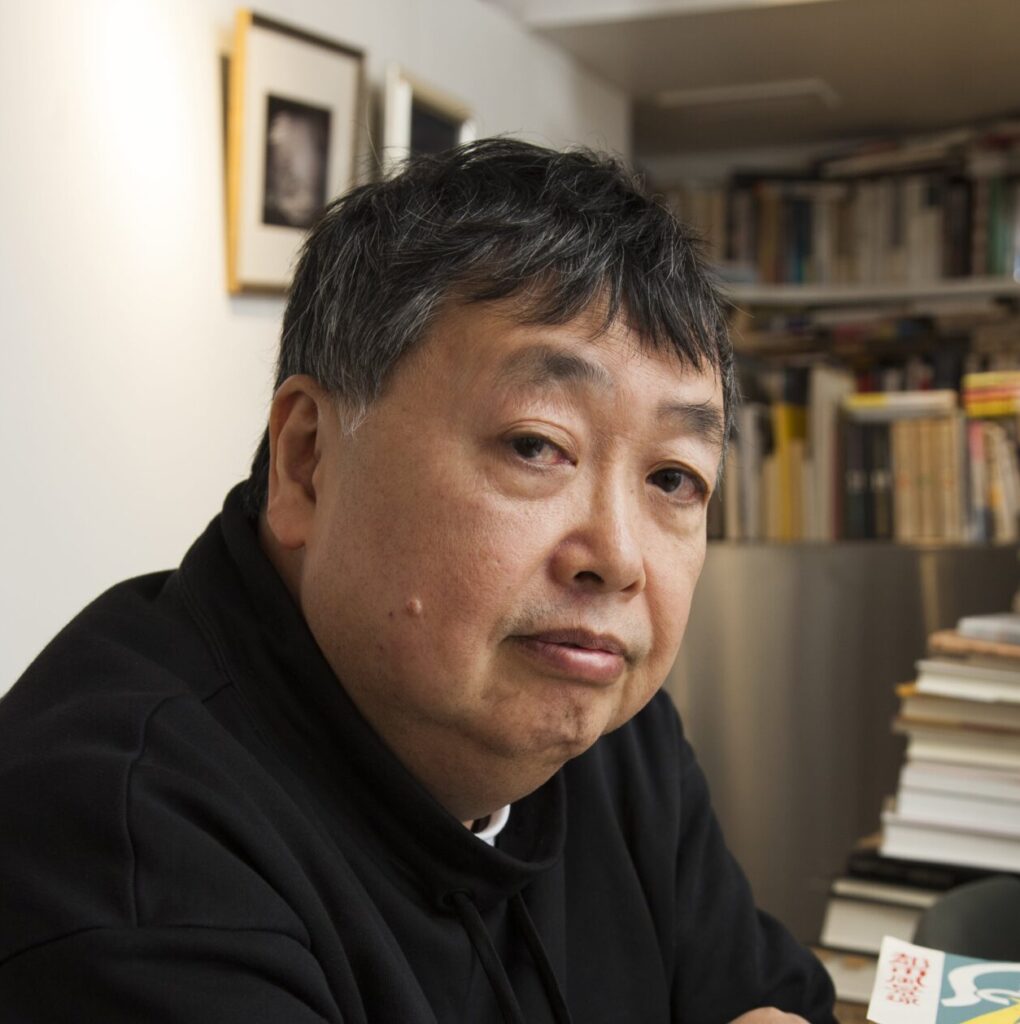
 大塚英志
大塚英志