この夏、広島と長崎への原爆投下から80年という節目を迎えた。それは、「あの日」に焼き殺された人たちが全うできなかった日々であると同時に、被害者たちが生き抜いてきた年月をも意味しており、非常に重たい意味を持つ。一方で「被爆80年」という言葉を耳にするたび、胸に澱が積もっていくような感覚もあった。メモリアルな意味合いを強く感じさせるこの言葉では、現実を捉えきれないと思ったからだ。
原爆被害は過去ではなく、現在進行形の痛みとしてここにある。後遺症に苦しむ被爆者、骨を探し続ける遺族、国による援護を求めて声を上げ続ける人たち――この苦悩に目を向ける時、「被爆80年」を単なる節目として受け止めることはできない。これからも続いていくものだからだ。
本連載では、被爆者の子どもとしてうまれた「被爆二世」がどのように戦後を生き抜いてきたかを伝えている。前回までは、当事者たちの声を通じて原爆が次世代にもたらしたものを探ってきた。連載の再開から第1回となる本記事では、被爆二世と彼らを取り巻く社会の変遷について辿っていく。文献資料を手がかりに、筆者が着目したできごとを中心に綴りたい。まずは、被爆二世たちが生を受けた原爆投下直後の社会にさかのぼる。
「赤ん坊の遺体を渡してください」
そもそも「被爆二世」との呼称は、いつうまれたのだろうか。
1947年6月8日付朝刊の『中国新聞』の記事では、「遺傳的特徴は第二世に傳えられる可能性がある」と書かれてあり、「一世」としての被爆者、「二世」としての子どもたち、という整理がなされていたことがわかる。他の記事や書籍には「被爆者二世」とか「原爆二世」といった表現も見かけられた。「被爆二世」という呼称が定着し始めたのは、1966年に「胎内被爆者・被爆二世を守る会」ができて以降だと思われる。
被爆二世の戦後を考える上で、まず着目すべきは「調査」だろう。
「丁寧に葬らせていただくので、赤ん坊の遺体をABCCに渡してください。もし引き取りを希望されるなら、後でお返しします」
13歳の時に広島で被爆した朴南珠(パク・ナムジュ)さんのもとへ原爆傷害調査委員会――ABCCの職員がやってきたのは、初めて授かった子どもを失った直後だった。ABCCとは、被爆者が受けた放射線の医学的・生物学的な影響を調べるため、米大統領によって1947年に設立された。1975年に改組されて、現在は日米合同で運営する放射線影響研究所となっている。
朴さんは爆心地から1.9キロ離れた場所で、路面電車に乗っている時に被爆した。頭にはガラス片や木片が当たり、血が流れた。年末には突然倒れ込み、意識を失って下痢を垂れ流したが、3日目に突然「水をちょうだい」と言って目を覚まし、以降は体調を取り戻した。
同郷の男性と17歳で結婚し、翌年には双子を身ごもった。しかし、早産だった2人の赤ん坊は、うまれて間もなく亡くなった。「私の人生は、もうこれで終わり」。朴さんはそんな気持ちで泣き尽くした。失意に沈む夫婦のもとを訪れたのは、白衣を着たABCCの職員たち。手に小さな白い箱を携え、遺体を引き渡すよう迫ってくる。
夫は烈火のごとく怒って拒み、双子のなきがらはカトリック教会の墓地に埋葬してもらった。しかし、周囲には「きちんと葬っていただけるのなら」と、引き渡した人も少なくなかったという。原爆が、寺や墓さえも焼き尽くしてしまったからだった。
7万人の新生児を調べたABCC
朴さんのもとをABCCの職員が訪れたのは、1948~54年に実施された「出生時の障害に関する調査」の一環だと思われる。被爆者の子どもに先天的異常や死産、うまれた直後の死亡などが増加したかを調べる目的で行われた。
医師による診察を受けた広島と長崎の新生児は、実に7万6626人にのぼる。医療機関ではなく、あくまで研究所であるABCCが、いかにしてこれだけ多くの赤ん坊を診察することができたのか。
「赤ちゃんが亡くなったことについて、私たちがABCCに伝えたわけではありません。きっと、産婆さんが連絡することになっていたのでしょう」
朴さんがそう述懐するように、実際に助産師が果たした役割は大きかった。
1949年にABCCの遺伝学部長として来日したウィリアム・シャル氏は、手記『廃墟からの歌声 原爆投下後の傷害調査にたずさわった遺伝学者の回想』(利島保・訳、新曜社、2022年)にこうつづっている。
死産や新生児が著しく異常であるか、あるいは出産後すぐに死亡するか、または何らかの障害があった場合には、助産師がすぐに電話してくれるか、オフィスに来て私たちに知らせてくれました。通常は、新生児が明らかに正常であるなら、だいたい週一、二回のペースで、私たちに報告してくれました。いずれの場合でも、保健師を同伴して、医師が子どもの診察のために家を訪問しました。
出産後に得る情報としては、子どもの性別、出産時の生死、先天的異常の有無、出生時体重、新生児死亡だ。しかし、すべての異常や障害がこの時点で明らかにはならないため、生後8~10カ月の間に乳児をABCCへ連れてきて、二度目の検査を実施した。母親から血液を採取することもあったようだ。検査の後には、赤ん坊用の洗顔せっけんを贈っていた。
シャル氏の手記によると、毎年6000~7000人の乳児が広島と長崎でうまれていた。6組の検査チームは休日を問わず週7で検査に出向き、ほとんどの乳児が生後1週間のうちに診察を受けていた。
もう一つ、ABCCが利用したのが配給制だった。
当時、特定の食料については配給制がとられていた。妊婦に対しては特別の配給があり、手続きのため市役所に訪れた妊婦の情報を登録していったのである。
ABCCの遺伝調査について詳細に調べた随一の書といえる『米軍占領下の原爆調査 原爆加害国になった日本』(笹本征男、新幹社、1995年)によると、調査対象となった広島、長崎、呉の3市において、妊婦たちに協力を求める「パンフレット」が配られていた。ただし、同書の刊行段階では、この日本語版の存在が確認できていないとして、「これは遺伝調査における最も基本的な文書が検討されたことがなかったことを意味する」と指摘していた。
このパンフレットを、なんとか確認することができないだろうか。そう思って調べてみると、2014年に広島市立公文書館へ寄贈されていることがわかった。やや日に焼けているものの、傷や汚れも少ない、非常に状態のよい現物を、私は手に取ることができた。
母親たちに配られたパンフレット「流産、死産の場合でも……」
パンフレットといっても、A4よりも少し小さいサイズの紙を半分に折ったものである。
指をくわえる赤ん坊のイラストの下に「お母様になられる方々へ」と、やわらかい筆致で記されている。「近くお母様になられる皆様にABCCよりお願いがございます」との書き出しで、母親たちへの呼びかけがつづられていた。
まず、母子手帳を受け取る際に、ABCCの「出生調査表」も同時に受け取り、両親の名前や生年月日、原爆関係の事柄を書き込むよう求めている。調査表は出産に立ち会う医師か助産師が完成させてABCCに送り、産後一カ月以内にABCCの医師が訪問して「赤ちゃんの健康診断」を行うと説明。その後、丸カッコでくくりながら「(若し不幸にして流産、死産其の他の異常がありました場合でもお宅に伺いますから何卒よろしくお願い致します)」と、念押ししていた。
調査に協力する意義については、こう記されている。
皆様方は此の診察によって赤ちゃんの眞の健康状態をお知りになる事が出来ると同時に科学的調査にも協力して下さる事になるのであります。ABCCの診察所には最も近代的なX線装置とか、其の他の最新の医学の施設がありますので、もし其の必要が認められました場合には赤ちゃんを診察所へお連れ願う事があるかも知れません
子どもを授かった被爆者たちは、わらにもすがる思いだっただろう。自らの体調も思わしくない中、戦後の混乱期での出産だ。無事にうまれてきてくれるだろうか、うまれてきたとしてもこの子の健康をどう守っていけばいいのだろうか……そう思いつめたはずだ。そんな状況下で、「最新の医学の施設」で診てもらうことができたなら、どれだけ安心するだろう。
しかし、ABCCに対して「調査すれども治療せず」との批判があったことはよく知られている。後身の放影研もこの点に言及しており、2017年に広島市内で開かれた設立70周記念式典で、丹羽太貫理事長(当時)は「ABCC設立当初は『調査すれども治療せず』と多くの批判があった。重く受け止め、心苦しく残念に思っている」と述べていた。
手渡されたビスケット数枚、明かされなかった「眞の健康状態」
この事実を踏まえると、パンフレットの呼びかけには引っかかりを覚える。この中では赤ん坊に対する治療こそ約束していないが、「眞の健康状態」は知ることができるとうたっている。親心につけ込む形で、原爆の被害者である母親たちの協力を引き出しているように見えるのだ。
実際に、先の朴さんはこんな風に話している。後に授かった4人の子どもたちが、ABCCの調査対象になったそうだ。
「子どもが2歳になると、ABCCの職員がジープで迎えに来ました。私は子どもに新しい服と下着を着させて、検査を受けるため一緒にABCCへ行きました。帰る時にはビスケットを数枚くれたので、子どもたちは喜んでいましたね。だけど、検査をしてもその結果を教えてくれることはありませんでした。ただデータを集めるために利用されていると思うようになり、検査を受けるのはやめました」
彼女たちが本当に求めていたのは赤ん坊の健康だろう。「眞の健康状態」を知った先のことを求めていたのではないか。
つまり、病気を抱える赤ちゃんには適切な医療を、異常が見つかった時にはすみやかな処置を、それぞれ講じてもらえるよう望んでいたはずだ。医療という「セーフティネット」がない状態で実施される調査に、反発した親たちがいたことは想像にかたくない。しかも調査主体は、原爆を投下したという意味において「加害」側であるアメリカだ。
加えて、本連載において改めて確認しておきたいことがある。「被爆者」の人生に降りかかったものは、同時に、「被爆二世」にも降りかかったという事実だ。
産後すぐに亡くなった赤ん坊がいたことや、子どもたちがABCCの調査対象にされたという事実を巡っては、「被爆者の苦しみ」という文脈で語られることが多かったと思う。これを、赤ん坊や子どもたちの視点から捉え直したい。すると、そもそもこの世に生を受けることができなかった「被爆二世」の存在や、わけもわからないままに血を抜かれ、身体を調べられた、幼い「被爆二世」の姿が見えてくる。語る言葉を持たなかった者たちの経験した「原爆」に思いを巡らせることも、本連載の狙いの一つだ。
ABCCが推し進めた出生時障害調査は、初期に行われた調査としては最大規模となった。その結論は1956年、科学ジャーナル『Acta Genetica et Statistica Medica』にて発表されたが、「両親の被爆歴がここに考察の対象としたその子供の特性に影響を及ぼしたという確証は、本解析からは得られなかった」(※)というものだった。はっきりとはしないものの、遺伝的影響には否定的な結論である。『広島市原爆被爆者援護行政史』(広島市衛生局原爆被害対策部、1996年)は、この調査結果が「被爆二世問題を判断する国の基本的根拠となった」と指摘している。
その後も遺伝的影響の研究は続けられた。ABCCの研究は、被爆二世への「追跡調査」に移行していく中で、社会的な関心も高まっていく。
※放射線影響研究所ホームページ「業績報告書シリーズ」より、『原爆によって起こり得ると思われる遺伝的影響に関する研究』(TR番号21-59B)掲載の日本語訳から引用した。
(次回は11月20日に更新予定です)

広島・長崎に投下された原子爆弾の被害者を親にもつ「被爆二世」。彼らの存在は人間が原爆を生き延び、命をつなげた証でもある。終戦から80年を目前とする今、その一人ひとりの話に耳を傾け、被爆二世“自身”が生きた戦後に焦点をあてる。気鋭のジャーナリスト、小山美砂による渾身の最新ルポ!
プロフィール

ジャーナリスト
1994年生まれ。2017年、毎日新聞に入社し、希望した広島支局へ配属。被爆者や原発関連訴訟の他、2019年以降は原爆投下後に降った「黒い雨」に関する取材に注力した。2022年7月、「黒い雨被爆者」が切り捨てられてきた戦後を記録したノンフィクション『「黒い雨」訴訟』(集英社新書)を刊行し、優れたジャーナリズム作品を顕彰する第66回JCJ賞を受賞した。大阪社会部を経て、2023年からフリー。広島を拠点に、原爆被害の取材を続けている。


 小山 美砂(こやま みさ)
小山 美砂(こやま みさ)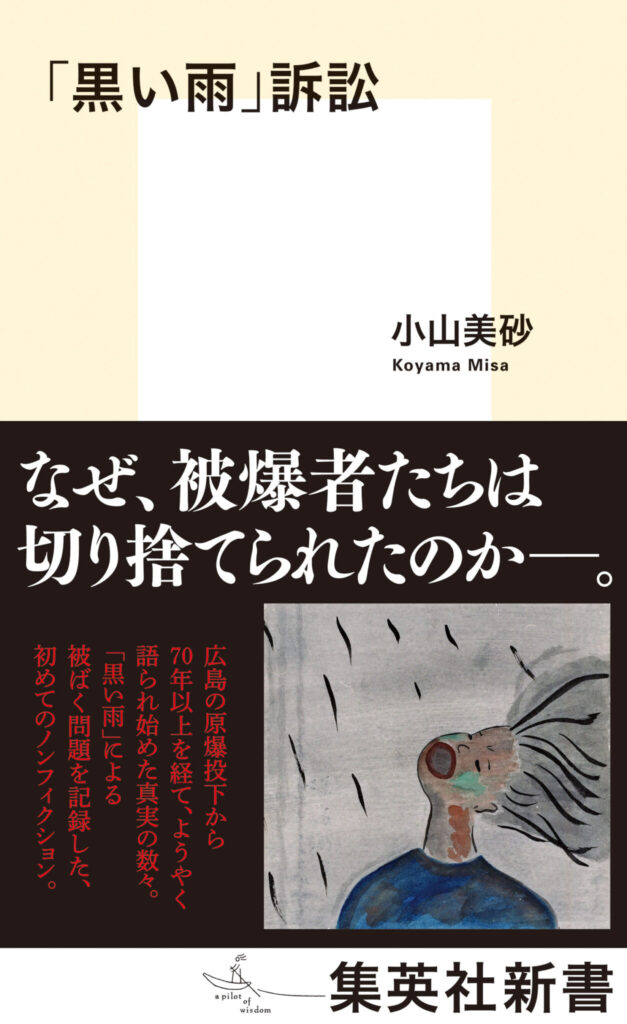





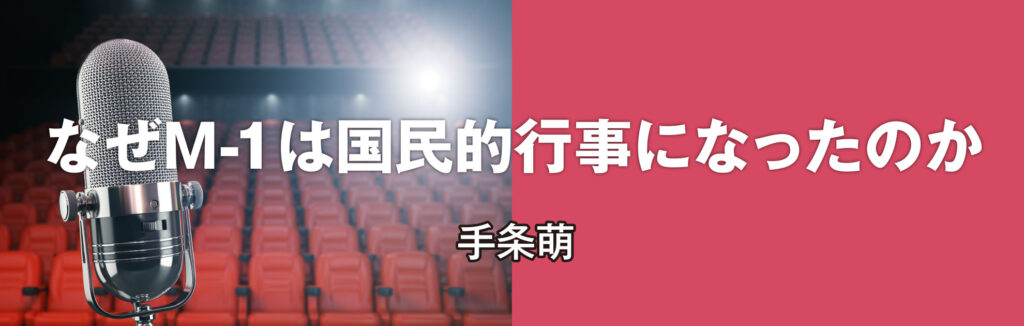



 佐藤喬×谷川嘉浩
佐藤喬×谷川嘉浩



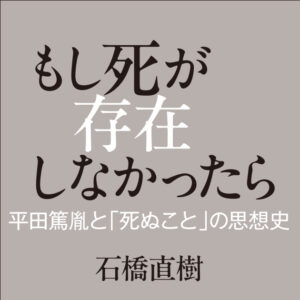
 石橋直樹
石橋直樹