「アパート共和国」――韓国人の住まいとペットの話
 伊東順子
伊東順子不人気だった猫は20年で主演になった
「20年前は助演だった猫が、今回は主演になった」――というのは、昨年公開されたドキュメンタリー映画『猫たちのアパートメント』のことだ。以前この連載でも取り上げた『子猫をお願い』(2001年)のチョン・ジェウン監督の最新作である。女性監督は世界的にも韓国的にもマイノリティなのだが、チョン監督は国内外に分厚いファン層をもつ。よって『猫たちのアパートメント』は日本でも年末に公開され、全国上映が行われている。外国のドキュメンタリー作品としては、異例のことだという。
この映画は『子猫をお願い』からちょうど20年目、チョン監督にとっては「猫映画、第2弾」となる。ただ作品の性格は大きく異なり、前作では脇役にすぎなった猫が、今回は主役となっている。カメラも地上ギリギリの「猫目線」。まさに「地を這うような撮影」の、本格的ドキュメンタリー映画である。
実はこの20年の間に猫たちの地位に変化があった。多くの韓国メディアがそれを指摘していて、そこにはチョン監督自身の言葉も紹介されていた。
「20年前は、猫が遠い存在でしたが、今はみんなに愛されるようになりました」(2022年3月7日付『東亜日報』)
以前も書いたが、韓国で猫は長らく不人気なだけでなく、忌み嫌う人も多かった。「不吉な感じがする」と。そうやって社会から疎外されていた猫と若い女性を重ねたのが、『子猫をお願い』という映画だった。悔しさを噛み締めながら、それでも自由に羽ばたこうとした韓国の女性たち。
あれから20年、女性たちは再び自分たちの分身である猫を通して、韓国社会を見つめ直すことになった。冷ややかに、呆れた表情で。しかし事態はいつのまにか抜き差しならないものになっていた。猫たちが暮らす団地の再開発が決まり、住民も猫も一斉退去を迫られたのだ。
映画『猫たちのアパートメント』
映画の冒頭シーンでは広大な団地が映し出されている。舞台となった「トゥンチョン公団アパート」はソウルの江南エリアにあるマンモス団地であり、1980年の竣工時には「アジア最大」とのほまれも高かったという。
143棟に5930世帯、当時は1世帯4人家族が平均だったので、ざっくり見積もっても人口約2万人以上が暮らしていたことになる。
この時代の公団アパートは立地もよく、今よりもはるかにゆとりある空間に建てられていた。緑も多く、自然にも恵まれた団地の環境は、住民たちにとって暮らしやすいばかりでなかった。
「そこは猫たちにとっても天国のようだった」
映画のナレーションで語られているように、芝生でのんびりと昼寝をする猫たち、ショッピングセンターの前でくつろぐ猫たちの表情は穏やかで幸せそうに見える。
ところが2016年に団地の再開発が決定し、しばらくして住民たちの引っ越しが始まった。こちらも「韓国史上最大の住民移動」だったのだが、退去は予想以上にスムーズに進んでいた。というのは、団地の再開発はすでに2000年から議論されており、それを推進してきたのは、他ならぬ住民たち自身だったからだ。
問題となったのは団地で暮らす猫たちだった。その数は約250匹。20年前は不人気だった猫だが、その後に起きた猫ブームで飼い猫が急増、同時に野良猫や地域猫も増えていった。
解体工事が始まるまでに、猫たちをどこか安全なところに移さなければいけない。そうして結成されたのが「トゥンチョン団地猫の幸せ移住計画クラブ」(通称「トゥンチョン猫の会」)だった。
メンバーはまず猫たちの顔を見分けるために写真を撮り、イラストを描いてパンフレットを作った。その後に専門家たちにも助言を受けながら、それぞれの猫に合った居住場所を探していく。
住民たちが次々に退去していく中で、カメラは取り残される猫たち目線の高さに合わされる。そこから見える風景の変化に、猫たちは戸惑っている風にも見えるし、われ関せずといった風にも見える。
「どうしたいの?」
「ニャア」
主役である猫のセリフは聞き取れない。「ニャア」は「イヤ」なのか「イイ」なのか?
人のいなくなった団地の風景は、まるで日本の郊外にある寂れたニュータウンにも見えるのだが、事情は真逆である。団地があるのはソウルの人気エリアであり、再開発後には35階建ての超高層マンション18棟の建設が予定されている。新名称は「オリンピックパークフォレオン」、2030年には「新しい街」が誕生するのだ。
日本でのニュータウン建設は過去の話だが、韓国ではずっと現在進行形である。ソウル中心部の古い街並みも次々に取り壊され、近年は25階建て以上の高層マンション群が続々と誕生している。
一方、初期のニュータウンでは新たな再開発計画が始まっている。その多くが江南エリアの一等地にあり、売却益を得ようとする人々の関心は高まった。居住者には分譲の優先権が与えられるため、それを目当てに老朽化した団地に人々が群がった。ボロボロのアパートが信じられないような価格で取引された。
世界でも比類のない「アパート共和国」、韓国
韓国語の原題は『猫たちのアパート』である。韓国語の「アパート」という単語は「大型の集合住宅」のことを指しており、日本で言うアパートとはかなりイメージが違う。映画の中にも「アパート暮らしに憧れていた」という発言があって、日本で映画を見た人の中には、意味がわからずに戸惑ったという人もいた。
今や韓国人の6割が「アパート暮らし」といわれるのだが、この単語を日本語に翻訳するのは難儀だ。翻訳者たちは泣きながら「マンション」と訳したりもするのだが、韓国の「アパート」はいずれも高層で大型の団地形式であるため、日本にある5階建ての小型マンションなどをイメージすると間違える。そちらは「ビラ」という別の名称がある。
翻訳が簡単ではないのはおそらく、日本と韓国では住居形式も、居住スタイルも、住まいに対する考え方も違うからだろう。
「だって韓国人は家を住むところではなく、投機の対象としてしか見ていないから」
韓国の人々はこの件になると自虐的であり、映画の中にも再開発の移転補償を目当てに移り住んだ女性がそれを告白していた。
でも、それは仕方ないと思う。だって韓国の富裕層の多くが、そうやって形成されてしまったから。日本でも「土地成金」という言葉があるが、韓国の場合はそれが「不滅の不動産神話」と言われるほどに、人々を魅惑し続けたのだ。
独裁政権時代は政権周辺の人々の独壇場だった不動産投資だが、民主化以降は一般国民にもそのチャンスが拡大された。一攫千金を狙って不動産投資をする人々が増え続けた結果、韓国は「不動産階級社会」と言われるほど、住まいによる階層の序列化が見える形で進んでしまった。その「不動産カースト」の頂点にある住まいが、「アパート」と呼ばれる分譲マンションなのである。
「え、一戸建ではないのですか?」
他国の人がびっくりするほど、韓国の人々の「アパート」に対する偏愛は激しい。ドラマに出てくるような庭付きの豪邸で暮らすのは財閥ファミリーなどの特別な超富裕層や外国人だけ。ほとんどの韓国人は芸能人など含めて「アパート暮らし」だ。
「韓国はアパート共和国ですから」
映画に登場する「猫の会」のメンバーは自嘲するが、実際に国中が高層のマンション群で埋め尽くされている。シンガポールなど土地の狭い都市国家なら理解もできる。ところが韓国では、土地も自然も豊かな農村地帯でも、人々は一軒家ではなくマンションで暮らすことを望むというのだ。
映画を見ながら改めて思ったのは、住まいを巡る日韓の違いだ。まだ使える家が再開発でなぎ倒される韓国と、放置され続けた空き家が都心でも問題になる日本。激変と停滞のコントラストは凄まじい。ここでは韓国が「アパート共和国」が呼ばれるに至った経緯を見てみる。共和国の建国はいつだったのか?
「アパート共和国」の建国と江南開発
韓国で大型アパート団地の建設が本格化したのは1970年代後半である。当初の目的は急激に膨らむ都市人口に対応するためのものであり、日本でも同じ理由で全国に団地が作られた時期があった。大阪の千里ニュータウンや東京の多摩ニュータウンなどは有名だが、それ以外でも1960年代から70年代にかけて日本全国の市町村に公営団地が造成された。
初期の団地の性格は日韓で共通していたのが、その後は全く違う展開となった。一足先に団地暮らしを経験した日本の人々の次なる夢はマイホーム、一戸建てに住むことだった。まさに『積水ハウスの歌』の出てくるような明るい住まい。でも韓国の人々の夢はそこには向かわなかった。
1980年代に韓国で大ヒットしたのは、ユン・スンイルの『アパート』である。軽快なリズムと男性好みの未練がましい歌詞は今でもカラオケの定番だが、そこに登場する「いつも僕を待っていた君のアパート」とは、当時最新の大型分譲マンションのことだった。
韓国の大手建設会社は積水ハウスのような展開はせずに、大型マンション建設に突き進んだ。その「夢の大舞台」となったのは、1970年代に開発が始まった江南エリアだった。「江南開発」は当初は庶民の住居不足解消が理由だったが、実際には富裕層のための開発事業となった。そうなった理由は後で述べる。
狎鴎亭の「現代アパート」(1976年)、大峙洞の「銀馬アパート」(1978年)、蚕室の「チャンミアパート」(1979年)などはいずれも、当時としてはまだ「ソウル郊外」だった江南エリアに建てられた。そして1988年にはその「江南開発」を象徴する大イベントであるソウルオリンピックが開催された。『猫たちのアパートメント』の舞台となったマンモス団地は、オリンピック公園の真横に位置する。
「江南開発」については、2010年に韓国で放映され大ヒットしたドラマ『ジャイアント』(SBS)に詳しい。全60回という大作だが、通して見ると韓国現代史の闇の部分もよくわかる。
独裁政権時代の開発事業は今の韓国からは想像できないほど暴力的であり、同時代の日本と簡単に比較はできない。もちろん日本でも公共事業においては常に「政治家と業者の不適切な関係」が問題になるのだが、政権と建設会社の癒着で推し進められた「アパート共和国」建国の陰には、それとは比べものにならないほど多くの一般国民の犠牲があった。
もっとも理不尽な目にあったのは、都市スラムの住民たちだった。ソウルには朝鮮戦争直後から、家を失った人や北からの避難民などのバラックがあちこちに建てられ、広大な都市スラムが形成されていた。それを一掃してマンションに建て替えてしまおうというのが、1961年にクーデターで政権を奪取した朴正煕の「都市再開発計画」だった。
スラムの撤去は強制的に行われ、立ち退きに抵抗した人々は暴力的に弾圧された。人々は住まいを奪われただけでなく、時には大切な家族や仲間も失った。建設事業のために住んでいる家を追われた人々を、韓国では「撤去民」と呼ぶ。
「団地映画」としての『はちどり』
2018年に公開された映画『はちどり』(キム・ボラ監督)には、その「撤去民」のバリケードが登場している。そんな風景を韓国で暮らした人なら、1度や2度は見たことがあるだろう。「アパート共和国」は常に再開発と撤去を繰り返しながら、どんどん大きくなっていたから。
『はちどり』の舞台は1994年の江南区大峙洞、主人公は中学2年生の少女である。
映画の冒頭シーンは示唆的だ。主人公の少女はドアをドンドン叩きながら「お母さん、開けて」と叫んでいる。ところがどんなに叫んでも母親が出てこない。少女の不安な様子は、見ている私たちも不安にさせる。でもすぐに種明かしがされる。少女は間違えて他の家のドアを叩いていたのだ。
そこからカメラのアングルは引きながら、少女がいる場所が広大な団地であることを映し出す。そのあまりにも画一的な建築構造の中で、自分の帰る家を見失ってしまった少女。
映画は少女の成長物語なのだが、韓国という国家の物語でもあった。「成長痛」が風景を軋ませる。経済発展が犠牲にし、民主化運動が積み残したものは何だったのか。女性監督の柔らかな視線は徐々に焦点を定めていく。
主人公の少女ウニ(パク・ジフ)が家族と暮らす団地は、ソウルで最も教育環境がいいといわれる江南エリアにある。今は高層マンションが立ち並ぶ、ソウル有数の高級住宅街となっているが、当時はまだその「始まり」の頃だ。
商店街で餅屋を営む両親は、子どもたちに店の手伝いをさせている。「そんな時間があれば英単語の一つでも」という、今はもう見られない光景だろう。ただしその両親とて勉強にはやかましい韓国の親だ。子どもたちを塾に通わせ、成績が悪いとガミガミ怒る。
街にはそんな地元民と、新規の転入者である富裕層、さらに押し出される貧困層がいる。その貧困層が「撤去民」である。
なぜ住んでいる家を追い出されてしまうのか。ウニはその意味がよくわからない。違和感はそれだけじゃない。「ソウル大学に合格するぞ」を熱唱させる教師、長男の受験のために「家族は一致団結せよ」と命ずる父親、その兄は妹のウニを殴っている。
「殴られたら我慢しないで。絶対に殴れたら駄目だから」
新しく漢文塾に来た女の先生の言葉はウニだけに向けられたものではない。ソウル大学で学生運動をしていた彼女もまた挫折感の中にいた。
監督のキム・ボラは1981年生まれであり、映画には監督自身が実際に見たことが描かれているという。そこに通底するテーマは「家父長制」であり、兄の暴力は単なる兄弟喧嘩などではなく、家族内の家父長的ヒエラルキーの象徴である。韓国で長男がどれほど特権的に可愛がられてきたか、この世代の韓国人なら記憶している。
そしてこの家父長制は家庭内だけでなく、韓国社会の様々な場面で女性たちを抑圧していた。学生運動や民主化運動なども例外ではなく、それが明らかにされたのは近年のフェミニズム運動の中でだった。
『はちどり』はフェミニズム映画の秀作として、先に紹介した『子猫をお願い』などとともに紹介されること多い。もちろん、それに異論はないのだが、この作品は「アパート共和国」の初期を記憶する「団地映画」としても重要である。
「江南開発」――富裕層はなぜ江南に引っ越したか?
すでに述べたように、この映画には団地で暮らす地元民と、新規の転入者である富裕層、そして撤去民という3つの階層が登場する。「アパート共和国」は階層構造がはっきりしているため、問題意識がそれほど高い人でなくても、この3者が同じ風景の中にいる現場に遭遇したことはあると思う。富裕層と撤去民の関係はまさに「玉突き」のようなもので、押し出す者がいれば、押し出される者がいる。
ではなぜ富裕層が江南エリアに移動を始めたのだろう?
「それは子どもの教育のためでしょう」
韓国に詳しい人なら、韓国の人々がなんらかの行動を起こす際の、最大のモチベーションが「子どもの教育」にあることはよく知っている。映画ではまだ一部富裕層の動きとして描かれているが、しばらくして「教育のための引っ越し」は(それは時には海外への移民も含めて)、子育て中の家族全体のテーマとなった。
「親の転勤で子どもが転校する」のではなく、「子どもの転校のために親が引っ越す」のだ。他国の人にとっては信じがたいのだが、これがなければ「江南開発」は成功しなかったかもしれない。自国民の教育熱の高さを重々承知し、それを最大限に利用したのは朴正煕大統領(当時)だった。
そもそも「江南開発」は、膨れ上がるソウルの人口を漢江の南に分散させるのが目的だった。建設会社はやる気満々だとしても、人々が動かなければどうしようもない。まだ農地しかない辺境の地へ、人々を移住させるにはどうしたらいいか?
まずは公務員住宅を建ててみたが、すこぶる評判が悪かった。交通も不便だし(当時は地下鉄も未開通)、周辺には商業施設もない。何か魅力がなければ、人々は動かない。そこで思いついたのが「名門高校の江南移転」だった。教育熱心な韓国の富裕層なら、それにつられて動くだろうと考えられたのだ。
これには在校生だけでなく同窓会も大反発し、それは大変な騒ぎだったという。しかし独裁政権時代のことであり、大統領の指示は絶対的だ。1976年に京畿高校が江南移転したのを皮切りに、なんと15校もの名門高校が半ば強制的に移転することになったのである。
とんでもない無茶ぶりなのだが、結果的にはこれが功を奏して江南に移住する人々が増え、それを当て込んだマンション建築ラッシュとなった。現代建設を筆頭に財閥系建設会社は先を争って、教育環境が良いと言われるエリアに大型マンションやデパートなど商業施設の建設を進めた。
高校の強制移転から15年余り、1990年代にはすでに「江南は教育環境の良いエリア」という定評ができあがっていた。当初は富裕層が中心だった「教育のための移動」は、すぐに中間層にも広がった。さらに名門高校だけでなく名門中学も移転し、良い進学塾が密集する地区などの人気も高まった。そうやって頻繁に移動する人々にとって、マンションは一戸建てよりもはるかに利便性が高かった。
2000年代に入ると、イ・ヨンエ(LGジャイ)、ペ・ヨンジュン(キョンナム・アパート)などの、芸能人をイメージキャラクターとした高級ブランドマンションのCMも始まった。サウナにゴルフの練習場、フィットネス完備と、マンションはどんどん高級化し価格も上昇した。ソウルや釜山などの大都会だけでなく、地方都市や農村地帯にも現代、LG、サムスン、ロッテなど財閥系の超高層マンション群が出来ていった。
人々が夢見る明るい我が家のイメージは、それらのブランドマンションとなった。旧市街に一戸建て住宅を所有する人たちも、居住エリアの再開発を待ち望むようになった。再開発が認められれば周辺の不動産価格も上がるため、それを目当てに不動産ブローカーが暗躍した。このままでは取り残されると思った人々も、大挙して不動産投資に参入した。投資熱の高まりは不動産価格をさらに押し上げ、物件を所有する「大家」はどんどん金持ちになる一方で、賃貸で暮らす人はますますジリ貧になっていった。「アパート共和国」は構造的に格差を広げる。
映画『ほえる犬は噛まない』――アパート共和国内の文化摩擦
最後にもう一つだけ「団地映画」を紹介しておく。ポン・ジュノ監督の長編デビュー作である『ほえる犬は噛まない』(2000年)もまた大型マンションを舞台にした映画である。
ただし、これは『猫たちのアパートメント』のように心が温まるような話では決してない。ポン・ジュノ流の暗さと残酷さとブラック・ユーモアが詰め込まれた「とんでもない話」であり、その構造は20年後のアカデミー賞作品『パラサイト』の原型とも言われている。そう言われて見直してみると、笑えるぐらい両者には共通点がある。
それについては映画評論家の四方田犬彦氏が書かれた「蚕室四洞薔薇アパート」(『われらが<無意識>なる韓国』作品社、2020年)というエッセイがとても参考になる。ちなみにタイトルの「蚕室四洞薔薇アパート」というのは、「『アパート共和国』の建国と江南開発」のところでふれた蚕室の「チャンミアパート」(チャンミは薔薇という意味)のことである。
四方田氏は1980年に韓国の大学に勤務した際、完成したばかりのこの大型マンションの一室を間借りするのだが、実は当時小学生だったポン・ジュノ監督もそこで暮らしていたのだという。ポン・ジュノ監督は最古参の「団地キッズ」であり、その空間感覚が作品にも影響しているのではないかと、四方田氏は述べている。
それとは別に、私がこの映画に関心をもったのは「犬映画」だったからだ。この映画の翌年には『子猫をお願い』が公開されて、犬と猫が出揃った。監督のポン・ジュノとチョン・ジェウンはどちらも1969年生まれである。男であるポン・ジュノが「ソウルの犬」、女であるチョン・ジェウンが「仁川の猫」というのが興味深かった。さらに面白いなと思ったのは、どちらの映画にも当時はまだ無名だったペ・ドゥナが出ていたことだ。
そして今、この『ほえる犬は噛まない』を「団地映画」という視点で見ると、20年前の韓国が「団地文化が形成される過度期」にあったことがわかる。ここに描かれる「文化と常識の対立」はしばらくして韓国社会全体に広がり、結果的には社会の大幅な意識変革につながっていく。
例えば、当時はまだマンションで犬を飼うことに賛否があったのだった。
映画はマンション内に響き渡る小型犬の鳴き声から始まる。うだつの上がらない大学の非常勤講師ユンジュ(イ・ソンジェ)は、それだけなくてもストレスの日々が続き、犬の鳴き声でイライラはマックスとなる。
そんな時に偶然見かけた犬を鳴き声の犯人だと思い、つかまえてマンションの地下室に閉じ込めてしまう。当時のマンションは駐車場が外にあり、地下には広大な空間があった(『猫たちのアパートメント』ではこの地下空間が、猫たちにとって絶好の住処になっていると解説されている)。
同じ頃、マンションの管理事務所には「飼い犬がいなくなった」という小学生が現れる。職員のヒョンナム(ペ・ドゥナ)は生真面目な性格で失踪した犬を探すのだが、その過程でまたしても別の犬の事件に遭遇する。
映画には犬を巡って様々な立場の人が登場するが、大きく分けると次の3つだ。
①マンションで犬を飼う人。
②マンションで犬を飼うことに反対する人。
③マンションで犬を食べてしまう人。
この映画が撮影された当時の韓国で、この3種類の人々はいずれもお互いが理解できなかった。映画では性別もきちんと分けてあり、①は全て女性 ②と③が男性である。
映画の中で②の男性は、ペットショップでプードルを買ってきた妻に向かって、こんなふうに抗議する。
「ここはマンションだぞ。犬を飼うのは禁止されている。実家の父は一戸建てだから、そっちに連れて行く」
そうだった。当時はまだマンションでペットを飼うのは禁止されていたし、家族の中で父親たちの権限は強く、男系家族の結びつきも盤石だった。ところがそれはあっという間にひっくり返る。映画の中では男性の権威が失墜していく過程が見事に描かれている。
「このままでは犬以下になってしまうかもしれない」
その恐怖心と無駄な抵抗が映画のリアリティを高めている。
それがいかに無駄な抵抗だったのかは、マンションでペットと暮らすのが一般的となった今となっては自明すぎる。そして映画から数年後には女性たちの反乱が起きて、戸籍制度などの「法的な家のしがらみ」も一掃され、女性たちの地位は上がっていく。
「アパート共和国」の魅力と今後
韓国がどのように「アパート共和国」になったのか? その過程をふり返ることは独裁政権や民主化という現代史の流れや、経済成長がもたらしたライフスタイルの変化を知ることになる。
独裁政権と建設会社の癒着、土地成金と不動産投資など、韓国では負の側面が語られることが多いのだが、実際に暮らしてみるとやはり韓国の団地暮らしは快適である。
室内は広々としているし、寒い冬でもポカポカのオンドルが暖かい。暮らしに必要な商業施設も揃っているし、子どもたちの保育園なども敷地内にある。学校や塾も近い。エレベーターとワンフロアの暮らしは高齢者にとっても便利であり、農村部でもマンション暮らしを好むというのはよくわかる。
「もう歳だから、楽をしようと思って自宅を売ってマンションに入った」
私がソウルで暮らしていたマンションには、そんな高齢夫婦が2組いた。韓国の人々は子どもの成長や家族構成の変化にともない頻繁に家を住み替える。高齢者のデイサービスなどにも、大型団地は効率がいい。
そうなのだ。効率化、最適化という点では、「アパート共和国」は理想的なのである。
2000年代初めに、他国よりも早く韓国でインターネットが普及したのは、「集合住宅が多いから」といわれた。初期のADSL回線では圧倒的に優位だったと思う。ケーブルテレビも同様だった。一軒一軒に線をつなぐ必要がない。マンション全体でやってしまえばいいのだ。
さらにいえば、最近は住まいによる階層化が進んだことで、同じマンションに暮らす人々の生活スタイルも似ている。高級マンションには高級車が並び、庶民向けマンションには庶民の車が並ぶ。それは居心地がいいかもしれない。
しかし、それだけでいいのかと、韓国の人々はずっと考えている。猫を一匹一匹確保して移動させるという非効率な活動をしながら、女性たちは自らの生き方を見直していく。
10階建てのマンションが35階建てになり、さらに50階建て、70階建てもある。釜山では100階建てマンションの入居も始まっている。展望は素晴らしいと言うが、果たしてこれがみんなが望んだ明るい未来の姿だったのか。人々は考え始めている。
プロフィール




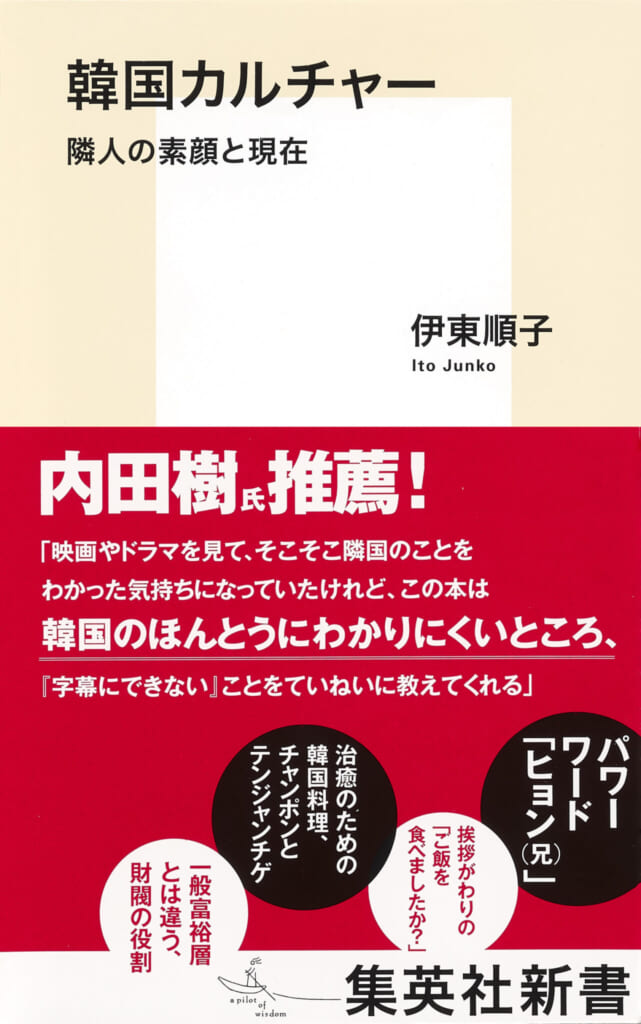












 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

