4月、ようやく韓国にも春が来た。木蓮と桜はすぐに散るが、その合間を縫うようにツツジとレンギョウが地面から吹き出すように咲く。この勢いが韓国の春だ。
韓国の憲法裁判所は4月4日、尹錫悦大統領の罷免を決定した。昨年12月3日の「非常戒厳宣布」から4ヶ月、長かった冬が終わった瞬間、友人たちは泣いたという。
「もちろん罷免だと思っていたけど、ひょっとしたらって…」
人々が不安になったのには理由がある。昨今の世界情勢の中で、自分が当然だと思ってきたことが、どんどん覆されている。軸が大きくズレてしまっているのではないか? さらに韓国国内でも裁判所を破壊する暴徒や裁判官を脅迫する輩が現れ、「極右」なるものが広場を侵食しはじめていた。
それとは別に、韓国メディアがしきりに憲法裁判所の裁判官8名の「出自」を問題にしたことも、国民の不安を煽った。
「革新系3名、保守系2名、中道3名。このうちの何人かが弾劾反対に回るかで命運が……」等々。
ところが結果は案ずることなかれ、「裁判官8名の全員一致で罷免」となった。韓国の司法は決してぶれることなく、民主主義を破壊しようとした大統領を法的に裁断した。この4ヶ月間、大統領も政党もメディアも何もかもが信じられなくなっていた多くの国民は、憲法裁判所の「全員一致」に安堵した。法の支配がきちんと機能している。まだ韓国は大丈夫だと。
民主化後に設置された「憲法裁判所」
韓国は三権分立の国であり、日本と同じく司法は三審制を採用しているが、憲法裁判所はそれとば別の独立した機関である。二度と大統領の独裁を許さないために、民主化後の1988年にアジアでは初めて設置された。「法律に違憲性がないか」、「国民の基本的人権が侵害されていないか」、そして「大統領の弾劾の是非」を判断する。
以前にも二人の大統領の弾劾がここで審理されたことがある。盧武鉉大統領の場合は罷免が認められず復職し、朴槿恵大統領は罷免が決定された。
憲法裁判所は9名の裁判官によって構成され、大統領・国会・大法院(最高裁判所)がそれぞれ3人ずつ指名する。任期は6年だが、それぞれ就任時期にズレがあり、空席ができることもある。現在は国会指名枠の1名が空席となっている。
さきほど「裁判官の出自」と書いたのは、選ばれた経緯のことだ。大統領指名なのか、国会指名なのか。その国会で指名したのはどの党なのか……等々。それによって、メディアは個々の裁判官を、「保守系」、「革新系」、「中道」などに分類する。
今回の8名の場合は、「大統領指名」のうち2名は文在寅大統領時代の指名であるために「革新系」、1名は尹錫悦大統領の指名だったために「保守系」と見立てられていた。また「国会指名」の二人も与党系か野党系に分類され、あたかも「意見が分かれる」かのようにメディアは報じた。でも、それが「誤ったメディアの中立」だったことを、憲法裁判所は「全員一致」をもって満天下に知らしめた。
さらに今回、大統領罷免の決定文を書いたのは、尹錫悦大統領が指名した鄭亨植(チョン・ヒョンシク)裁判官であり、また4月4日に判決を言い渡したのは文在寅大統領が指名した文炯培(ムン・ヒョンベ)裁判官だった。はからずとも憲法裁は国民に向けて、民主主義のもとでの統合をアピールする形となった。
裁判官は貧しい農家の出身だった
「私は1965年に慶尚南道河東郡で、貧しい農夫の3男1女の長男として生まれました。お古の制服と教科書を譲ってくれた親戚のおかげで中学を卒業することができ、高校2年生の時には篤志家であるキム・ジャンハ先生にお会いして、大学4年生まで奨学金をいただくことができました。そのおかげで学業を無事に終えることができ、司法試験にも合格することができました」
判決の翌々日、複数の韓国の友人から「ぜひ、見てほしい」と送られてきたのは、文炯培裁判官の動画だった。録画の日付は2019年4月9日とある。ちょうど6年前に彼が憲法裁判所の裁判官に指名された際の聴聞会のもので、その朴訥な語りは判決文を読んだ時と同じだった。
友人であり韓国文学の翻訳家である斎藤真理子さんは、あの判決を聞きながら咄嗟に「この人の韓国語の発音が好きだ」と言っていたけれど、それは確かに独特だった。韓国語を聞き慣れている人なら気がつくと思うが、地方出身者がきちんと話す標準語といえばいいのだろうか。ソウル生まれの人よりもむしろ正確で丁寧な語り口だった。同じようなことを感じたのは2017年5月、文在寅大統領が光州民主化運動の記念式典で演説した時だった。
「自分が文在寅の演説に感動するとは思わなかった」
あの時、彼の支持者ではない人の心までを動かした語りは、出発して間もない文在寅政権の支持率を80%までに上げた。今回も判決後の世論調査では、憲法裁の弾劾決定を支持する国民は80%超えとなった。ようやく世論が昨年12月の非常戒厳宣布直後に戻った。
慶尚道の言葉はヤクザ映画などの影響もあり、また声の大きい人が目立つせいか、ちょっと喧しく聞こえることもある。関西弁になぞらえることもあるけど、実は無口で無愛想な人も多く、私自身はどちらかといえば九州の人が語る言葉のイメージと重なっている。決して饒舌ではない人々や、むしろ寡黙な人々が韓国社会を支えていると感じることは多い。
文炯培裁判官は定められた6年間の任期の最後に、あの判決文を読むことになった。韓国の現代史というのは、どうしてこうもドラマティックなのだろう。伏線が回収されていくのは、人々の願いがそこにあるからだろうか。
文在寅元大統領は自分が指名した裁判官の姿に感動しただろうか。ただ、ドラマは感動的なものばかりではない。文元大統領は同じ時期に、もう一人の重要人物を検察総長に抜擢していた。それが尹錫悦である。自らが指名した二人が6年後にこのような立場で向かい合うことになるとは、元大統領の心境も複雑だと思う。
韓国社会を支える寡黙な人々
「この人が話しているのを聞くと、なぜか涙が出てしまう」
動画を送ってくれた韓国の友人が言ったように、4月4日の弾劾決定直後から、文炯培裁判官の6年前の動画は拡散され多くの韓国人を泣かせた。それと同時に注目されたのは、動画の中に登場する「キム・ジャンハ」という名前だった。どこかで聞いたことあるが、さて誰だっただろう?
1944年に慶尚南道泗川で生まれたキム・ジャンハさんは、韓方薬の商いをやりながら、多くの困窮学生を援助してきた。家が貧しくて進学を諦める生徒たちを、地元の学校教師たちはキムさんとつないできた。
慶尚南道では有名な篤志家だったが、彼もまた寡黙な人であり、メディアなどへの出演も一切拒否してきた。2019年に文炯培裁判官が任命された時に、「彼もキム・ジャンハの奨学生だった」ことが話題となり、地方のテレビ局がドキュメンタリー制作にのぞんだ。
「私が司法試験に合格してお礼の挨拶に伺うと、私に感謝する必要はない。私はこの社会のものをおまえに与えただけだから、返そうと思うなら私にではなく、この社会に返せという先生のお言葉を私は忘れたことがありません」(文炯培)
https://www.youtube.com/shorts/55qysZZYrFU
そのドキュメンタリー番組には、折に触れてキム・ジャンハさんへの尊敬を語ってきた文炯培さんも登場する。番組が完成したのはキムさんが60年間続けた韓方薬局を閉店した2022年のことだった。
その番組『オルン、キム・ジャンハ』は、翌年4月の百想芸術賞のテレビ部門での受賞を期に全国的に注目された。人気ドラマがタレントが賞を席巻する同賞で、一地方局のドキュメンタリー番組が受賞するのは異例のことだった。翌2023年秋には劇場用の映画に改編されて全国公開された。そして今回、憲法裁の判決を期に、約1年半ぶりに全国の映画館で再上映が始まっている。
映画『大人、キム・ジャンハ』
映画のタイトルを日本語に直訳すると『大人、キム・ジャンハ』となる。今回、韓国メディアは再びキム・ジャンハさんを取り上げる際に、映画を見た人々にインタビューをしていたが、そこからは韓国の人々がいかに「大人」を求めているのかがわかった。
「大人がいなくなった韓国社会」、「本当の大人を探していた」、「人生のモデルがほしかった」等々。
韓国語の「大人」は日本語よりも大きな意味をもつ。私は以前、集英社から出させてもらった新書で1章をつかって、韓国での「大人(オルン)の意味」について書いたことがある。
「成人=大人(オルン)ではないのは、日本も韓国も同じだ。日本では「大人」という言葉は「大人の男性」「大人の女性」みたいに洗練のニュアンスが使われることが多いが、韓国では社会的責任をともなった存在としての意味が大きい……」(『続・韓国カルチャー描かれた「歴史」と社会の変化』集英社新書)
大統領自らが反乱を起こすという異常事態が、社会の分裂を招いた。私たちは分裂する必要などなかったはずだと、憲法裁の判決は教えてくれた。引き裂かれ、傷ついた人々を癒やしてくれる大人に会いたい。それがキム・ジャンハさんの物語を再び呼び起こした。
それにしてもだ。意味はわかっているつもりなのだけれど、この映画のタイトルを日本語に訳すのは本当に難しい。『オルン、キム・ジャンハ』、翻訳家の斎藤真理子さんならどう訳すか、今度会ったら聞いてみようと思う。
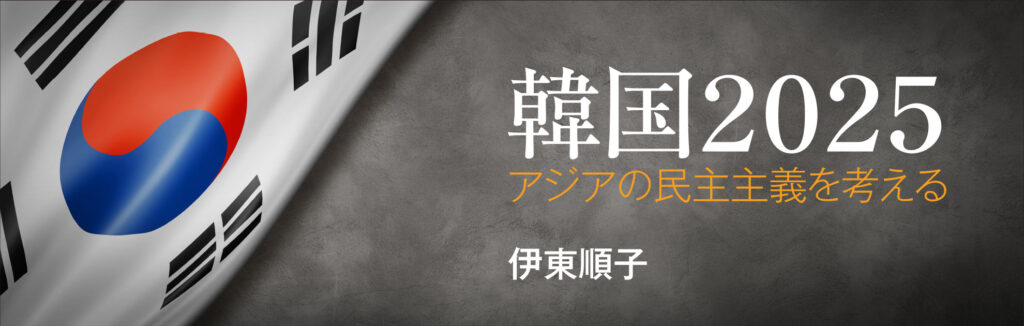
2024年12月に突然出された韓国の非常戒厳令。いまだ韓国社会は揺らいでいるが、市民が積極的に行動する韓国を「民主主義の先進国」として称賛する人もいれば、「韓国民主主義の未熟さが露呈した」と批判的にとらえる人もいる。韓国を巡って日本国内の評価が真っ二つに割れるのは今に始まったことではないが、それぞれが理想とする「民主主義の形」はいったい何だろうか。韓国のリアルをレポートしながら、アジア全体の民主主義を考える。
プロフィール
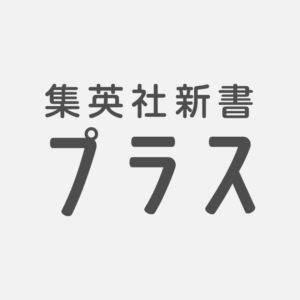


 伊東順子
伊東順子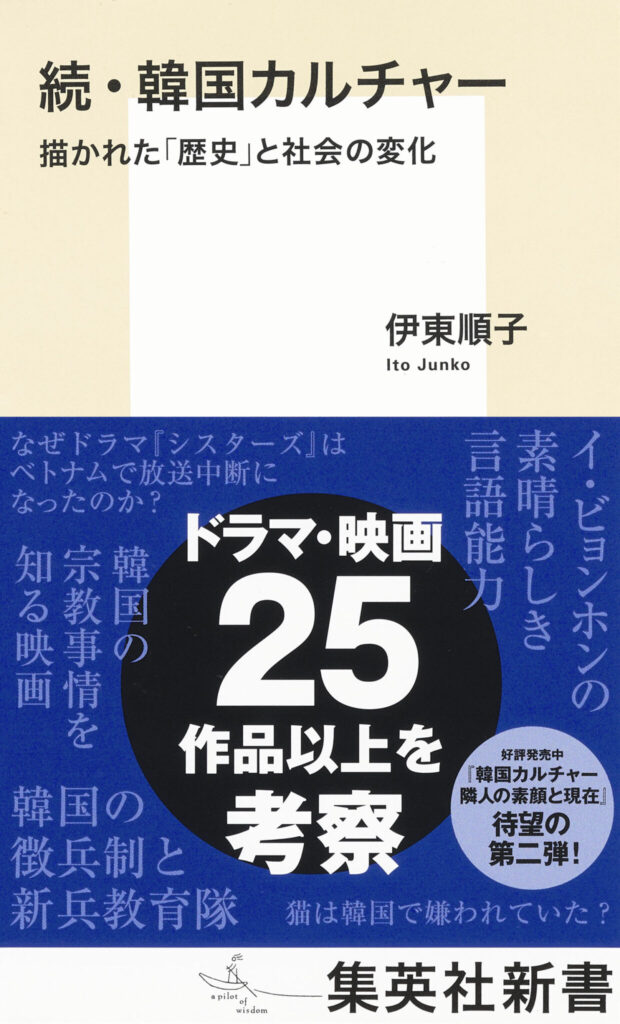











 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり


