米騒動はいかにして起きたのか
2025年3月、スーパーで販売された5キロ当たりの米の平均価格がついに4000円を超えた。前年の約2倍まで高騰する中、農林水産省は備蓄米を放出したが、価格は高止まりしたまま。「令和の米騒動」とも呼ばれる深刻な米不足は、なぜ起きたのか。
農業経済学を専門とし、近著『令和の米騒動 食糧敗戦はなぜ起きたか?』を上梓した東京大学大学院特任教授の鈴木宣弘さんは、全国の生産地を訪れて現場の声を聞き、その要因をこう見てきた。
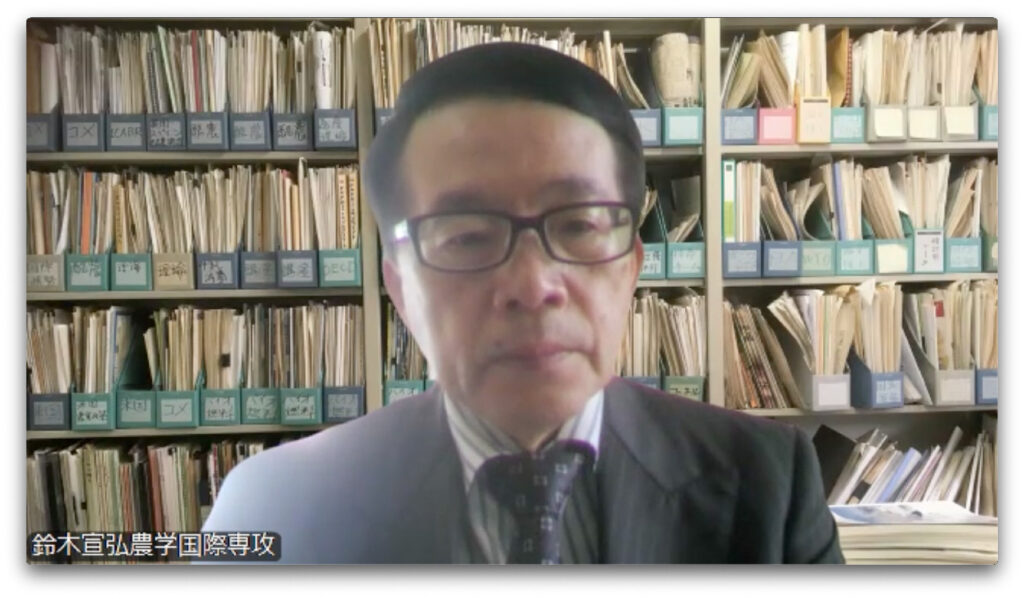
「2023年の不作が発端ですが、さらにインバウンド需要が増加したことも一つの要因ではないかといわれます。しかし、なぜここまで騒動がおさまらないのかという問題の根本には、そもそも減反政策によって米の生産を減らし過ぎてきたという状況がありました。
そしてもう一つ、農家の皆さんは米の生産を減らしているのに価格がどんどん下がり、30年前と比べて半分以下のような値段になってしまった。『これじゃあ所得を得られないから、もう米を作れない』と、稲作をやめる農家、生産を減らす農家が増えていました。
この数年は猛暑の影響で想定以上に生産が減る可能性も高まっている。それでも政府が需要の減少を見込んで生産目標を示すと、結局減らし過ぎになってしまった。23年はそれが顕著に出て、24年産米も暑さの影響が大きくて十分収穫できなかったので、政府の発表より収量がかなり少なかったと考えられます」
減反政策の当初の目的は、需要に合わせて生産調整することで米価を維持することだった。にもかかわらず過去30年間で米価が半分以下まで下がった背景には、デフレの影響もあるが、米については食糧管理制度の廃止があった。食管制度では、農家が収穫した米をJAが集荷し、政府は価格を決定して全量を買い取り、それを消費者に安く売り渡すという調整をしていた。この制度が1995年に廃止され、米価は不安定になったという。
「食管制度があった時代は、JAの集荷率がほぼ100%だった。それが流通の自由化が進むにつれて、JAのシェアも落ちていったわけです。JA以外の業者が農家から買うという流通が増えていく。そうなると農産物は小売部門、特に大手スーパーなどの価格形成力が強いので、小さな農家さんは力関係によって安く買い叩かれることも起こりうる。JAのシェアが減るにつれ、その状況が強まっていったことも考えられます。
今回の米価高騰の前には、2022年の米農家の年間収入から必要経費などを引くと、1万円しか残らない、すなわち1000時間働いて『時給10円』という試算が出ました。そこまで米価が落ち込んでしまったのは、需給の問題というより、買い手側とのパワーバランスによる影響が大きいと思います」
JAの集荷率が高ければ米価を維持する力は強い。だが、流通の自由化とともに大規模な農業法人などは販路を広げてきた。2023年にはJAの集荷率が約4割まで減り、翌年は3割を切るほど急速に落ちた。JAは卸売業者との交渉力を失い、米の価格は変動していく。今回の米価高騰の要因には、JAの弱体化もあると鈴木さんは指摘する。
「米がJAに集まれば過度には高騰しないけれど、60キロ3万円、4万円という高値で買う業者も出てきた。卸売業界も米不足を解消できない状況と判断し、今年は田植え前から秋に収穫する米を高い値段で買う契約を進めるという現象が起きました」
今年5月には小泉進次郎農相が就任し、備蓄米の放出方法を変えた。4月まではJAなどの集荷業者を対象に入札で価格を決めていたが、備蓄米放出の4回目からは小売業者や米穀店との随意契約に変更。それによって備蓄米がより流通するようになり、6月から2000円台という安い価格で店頭に並ぶ米も増えた。こうした政府の動きを、鈴木さんはどう見てきたのか。
「消費者の声が高まってきたから、とにかくまず米の値段を下げるという意気込みはあったが、急場しのぎで米の値段を下げればいいということでは根本的な解決にはならない。5キロ2000円を下回るような米価が当たり前になったとしたら、間違いなく米を作る人はいなくなるでしょう。
今は小さな農家もたくさん頑張ってくれているから、地域社会も維持できている。田んぼには洪水をせき止めてくれるなど国土を守る機能もあるわけです。ところが、近年の農政改革は、田んぼの区画を広げて規模拡大をすること、スマート農業(ロボット技術やICTを活用して超省力・高品質生産を実現する)と輸出を推進すること、そればかりじゃないですか。机上の空論というか、一部の人だけが儲かればいいという論調で、小規模でも頑張っている人たちを非効率の名目で排除していく流れが強まっているように感じます。
これでは日本の豊かな地域社会、そして農業でいえば米の供給量も維持できない。食料としての安全保障と国土を守る安全保障、いろんな側面があるけれど、そういうことも一切考えず、一部の人だけ利益を得られればという発想を見直さなければいけないですね」
国の政策を憂うる中で、鈴木さんは地域の現場から自分たちの力で暮らしと命を守り、コミュニティを強化していく必要があると考える。一つの動きとして、地元の安全でおいしい農産物を市や町が買い取り、学校給食で子どもたちに提供する取り組みが広がっていることを挙げる。
「地元の種を大事にして、生産した農産物をまず地域で循環的に消費していく。そうした動きが自給率を上げることにもつながるようなローカル自給圏づくりが増えてきています。自分たちの地域は自分たちで守る。生産者の皆さんと消費者の皆さんができるだけ身近な形でつながる仕組みづくりをしていくことが、今は一番重要ではないかと思っています」
若い世代の背中を後押ししたい
2025年9月半ば、新潟県三条市の山間部にある下田地区を訪れた。世帯数69軒の駒込集落で米作りをする藤家貴之さん(46)の田んぼは稲刈りの最中だった。今年も新潟は水不足と報じられていたが、米の出来はどうだったのだろう。

「春先までわりと雪が降ったので、水不足じゃないだろうと話していたんです。けれど梅雨にほとんど降らず、7月半ば頃には溜池も空になって、みるみる稲が枯れていくのがわかった。早生品種の収穫量は3割ほど減りました。それでも今年は昼夜の寒暖差があり、コシヒカリの穂が出る頃には雨が降り出したので、そんなに被害が無くて良かったです」
藤家さんは一人で15町歩の田んぼを手がけ、コシヒカリとこがねもち(もち米)を作っている。その田んぼを眺めながら、これまでの2年間を顧みる。一昨年は大変な水不足によって、ほとんど3等米となり収穫量が激減。収入もぎりぎりの状況で何とか乗り越えたが、翌年は逆に長雨の影響でさらに深刻な不作だった。
「農作業していること自体は辛いと思うことはないです。でも、農作物にとっては毎年状況が違うので、過去の経験則は通用しない。今まで通りにやっていると、栄養が足りなくなったり、丈が伸びすぎたり。作る人によって、田んぼの色まで違うんですよ。だから、僕らは相当勉強しなければならないし、経営努力もますます必要になっていますね」
田んぼにいるのが何より好きだという藤家さん。その原体験は小学生の頃、下校して家へ帰ると、祖父が稲刈りをしている田んぼへ駆けて行ったことと振り返る。
「じいちゃんが脱穀した籾を乾燥機に入れるために、いったんコンバインを止めたとき、僕を一人で乗せてくれるんです。子どもだから機械が好きだし、大人に頼られるような気がして嬉しくて。それが田んぼを好きになるきっかけだったかなと」
家業は金属加工を手がけ、クッキーの抜き型を製造する工場を営む。仕事の傍ら、祖父と父が2町歩ほどの田んぼを作り、親戚が稲作をやめるとその田んぼも任されていた。
藤家さんは20歳のときから工場で働き始め、稲作も手伝うようになる。やがて父親が65歳になった年、藤家さんは好きな田んぼを一人で任されることに。専業農家として本格的にスタートしたのが8年前、38歳の時だった。
「周りでも高齢になった人が一気に稲作をやめていく時期でした。うちで代わりに作ってくれないかと頼まれ、その田んぼも借りることにしました。まず大きなトラクターに買い替えて、一人で始めたところ、どんどん田んぼが集まってくるようになった。いずれは20町歩くらい集まることが予想できたので、新しい機械や農舎もだんだん整えていきました」
集落が高齢化する中、後継者がいなくて田んぼを手放す人たちが増えていく。地域の稲作を絶やしたくないという思いから、一人でこなせる限りの田んぼを引き受けていった。5年前には地元の人たちから三条市の市議会議員に強く推され、父親には当初反対されたが、悩んだ末に出馬を決意。それからは市議も務めながら、米作りを続けてきた。
藤家さんが市議として取り組んできたのは、後継者不足や耕作放棄地の問題だった。さらに案じてきたのは、米の価格がこの一年余りで一気に高騰したことだった。
「生産者の立場からすると嬉しいことですが、できれば5年、10年くらいかけて緩やかに値上げしてほしかった。そうすれば消費者の人たちも何とか納得して買ってくれるんじゃないかと。農家としても、こんなに高く売っていいのかという思いがある。一方、備蓄米や輸入米も入ってくることで米の価格が下がるのではないかという心配もあるわけです」
そもそも米の価格はどのように決まるのか。藤家さんに聞くと、例えば、JAに出荷する農家はまず5月くらいに出荷契約をする。JAはその年の収穫見通しや市場の動向を踏まえて、8月に「概算金(仮渡金)」が発表され、農家が米を出荷した際に支払われる。その後、JAと卸売業者が話し合って相対取引価格が決まる。JAはその価格から概算金、経費を引いた差額を、生産者に追加払いするという流れになる。
「つまり、我々としては最初の出荷契約のときに価格が提示されないことが気がかりです。うちは工場もやっているので、製品を受注する際には見積もりを出して契約するけれど、農業ではそれがないんです。2年前まではだいたい30キロ7000円前後のイメージで作っていました。今はJAの概算金も値上がりしているので農家としてはありがたいですが、来年になったらどうなるか、再来年はどうなるのかと考えると、ちょっと怖くなる。米の値段が今後どうなるのか不安定なのは、やはり政治の責任だと思います」
前述したように、米不足が騒がれるようになってからは他の業者から直接買いたいと交渉を受け、JAと契約しない農家も増えている。販路が多様化する一方で生産者の変化も感じていた。
「若い後継者も増える可能性があります。僕のところにも、会社勤めをしながら家の田んぼをやっていた地元の若手が相談に来るんです。会社を辞めて専業でやってみたいと。彼らも根っから田んぼが好きなんですね。近所の人が手放す田んぼを預かるかどうか躊躇していたけれど、米の値段が上がったことでやっと踏ん切りがついたという人が増えているんです」
高齢になった世代の中でも農機具を買い替える人が増えている。今までは古い農機具で我慢していたが、後を継ぐ子どものためにという思いからだ。藤家さんも家では口に出さないけれど、いずれは長男に……と考えるようになったという。
「そのためには米の価格を適正に維持してほしいし、先行きも安定する方向を示してほしい。そうしたら僕らも若い世代の背中を押してあげられるから」
温暖化による猛暑の影響で苦境に陥った米の生産現場。そこから浮かびあがった高齢化による後継者不足や価格変動などの問題は、まさに今の社会が抱える世相と重なり合う。それでも現場を訪ねると、田んぼをこよなく愛し、美味しい米を届けたいと苛酷な自然と向き合い続ける人たちに出会う。その声に耳を傾けることなくして、日本の米の未来も見えてこないのだ。
プロフィール

(うたしろ ゆきこ)
ノンフィクション作家。1964年新潟県生まれ。学習院大学文学部卒業後、出版社の編集者を経て、独立。『AERA』『婦人公論』『プレジデントウーマン』などで、スポーツ、人物ノンフィクション、事件取材など幅広く執筆活動を行っている。
著書に『私は走る―女子マラソンに賭けた夢』、『音羽「お受験」殺人』、『精子提供―父親を知らない子どもたち』『100歳の秘訣』(新潮社)、『一冊の本をあなたに―3・11絵本プロジェクトいわての物語』(現代企画室)、『慶應幼稚舎の流儀』(平凡社)、『鏡の中のいわさきちひろ』(中央公論新社』など。


 歌代幸子
歌代幸子










 田中優子×青木 理
田中優子×青木 理



