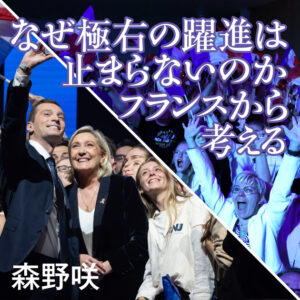YouTube上で学問の知識や教養、お金のやりくりについて教示する動画コンテンツがブームになっている。そうしたコンテンツはなぜ「大学」という名前を冠しているのか。視聴者たちは、なぜそうした動画に熱狂しているのか。フリーランスのライターとして、ポップカルチャーやネットカルチャーについて取材・執筆を続けてきた藤谷千明が迫る。
第4回は、マネーリテラシーをメインに動画コンテンツ、書籍、オンラインサロン、イベントで一大ブームを起こしている「両学長のリベラルアーツ大学」について。前回連載(2023年8月4日掲載)からさらに拡大している「リベ大」は、なぜここまで大きな規模のメディアとなったのだろうか。
■今日も元気よく拡大しているリベラルアーツ大学
「資本主義の終わりより、世界の終わりを想像するほうがたやすい」とは、イギリスの批評家マーク・フィッシャーの言葉ですが、一方この極東の島国では「『お金なくて自由なし』これが資本主義のリアルです」と語る両学長のリベラルアーツ大学(以下リベ大)の書籍『本当の自由を手に入れる お金の大学』(朝日新聞出版)は累計200万部にせまり(2024年11月に発売した改訂版含む)、チャンネル登録数は270万人超えという人気ぶり。資本主義に出口はない、ならば乗りこなしていこうと「お金の教養」を提供する謎のライオンキャラが率いるコミュニティの謎を探るシリーズ、第3回となります。考えあぐねて筆が止まり、公開が遅れてすみませんでした。
この連載の間が止まっているあいだに、リベ大レストランが開店して閉店していました。相変わらず需要と供給と損切の判断が早い組織ですこと。なお現在リベ大学が運営しているサービスは、
リベ大税理士法人/リベ大経理代行/リベ大オンライン秘書/リベ大不動産/リベ大工務店/リベ大引越センター/リベ大ライフサポート/リベ大スキルアップ工房/リベ大クリニック/リベ大デンタルクリニック/リベ大どうぶつ病院/リベ大フェス
だそうです。増えたな〜。なお、リベ大フェスは昨年は開催されていなかったものの、今年8月の三連休に「お金の勉強フェス」として幕張メッセで3日間開催するそうです。たのしみですね。
連載が止まっているあいだも、わたしは時折リベ大のオフ会やイベントに足を運んでいました。リベ大オンラインサロン、リベシティの会員が無料で使えるシェアオフィスが全国に存在しており(しかもどこも立地がよいんだわ!)、そこでは毎日のように勉強会が行われていました。家計管理勉強会、生成AI勉強会や、無料の画像加工ソフト勉強会、リベ大のコンテンツで学ぶ英語、コードがわからなくてもWEBサイトを作る方法などなど……。参加者はみんな真面目そうな人たちばかりで、女性や子ども連れも多く、ある休日にオフィスへいくと入口にベビーカーが数台置いてあることもありました。

正直当初はみんなそろってエグい儲け話をしているものなのかと身構えていたけれど、「この人はブログですごく結果を出しています!」と紹介された方の収益は「月に十数万円」とのことで、内容はややニッチなアウトドア系アイテム紹介ブログでした。すごいことはすごいですよ、だけど「儲かる」の規模がささやかすぎる。なんか、思ってたんと……、ちがう……。ただ、リベシティ会員の人たちと話していて、リベラルアーツ大学が人を集めている理由は、なんとなくつかめて来た気がします。結論から申し上げますと、いわゆる「失われた30年」の受け皿として機能しているからなのではないでしょうか。
■「失われた30年」の受け皿として必要とされる「お金の教養」
バブル崩壊後、経済が停滞したといわれるこの数十年。2024年3月に日経平均株価がバブル時代の頃まで戻ったことが大きなニュースになりました。けれども、街をみたって周囲の羽振りをみたって「あの頃」のような活気は感じられませんけどね。景気が低迷し、就職難と呼ばれ、規制緩和の名のもとに非正規雇用が当たり前になり、平均年収は下がり、社会保険は上がり、手取りは下がり、都市部に限っていえば住宅価格は上がり、少子高齢化も進みました。81年生まれのわたしもこの時代を生きてきたという実感があります。
どんな実感かというと、終身雇用はとっくの昔に幻想になったのに、死ぬまで働く予感だけはある。その上、不安定な雇用のまま働き続けなければならない。そうなると企業を土台とした共同体もおのずと機能しなくなっていきます。そして地域の共同体もやせ細っている。経済的には親世代にも頼れそうな気がしない。子供がいるのであれば彼ら彼女らにはできるだけ負担をかけたくない。端的にいって、将来に不安しかない。かつてであれば中流層だったはずの人たちがこぼれ落ちてしまった。マネーリテラシーを教養とする大学は、そういった「失われた30年」によってこぼれ落ちた彼ら彼女らの不安を受け止める受け皿になっているようにみえるのです。
政治も、社会運動も、思想も、文学も届かなかった、……いや、むしろそれらをそもそもとくに必要としていない人たちの不安に寄り添っているのが、あのライオンなのかもしれません。かつて、新興宗教が都会に出てきた孤独な若者の受け皿になっていたように、バブルに浮かれる社会に疑問を持つ若者の受け皿になっていたように。
ただ、このライオン教祖こと両学長は過去のそれらと違って、信者を煽って団結させて社会をどうこうするような破滅願望は持ってないでしょうし、過剰な搾取や囲い込みを行っているわけでもありませんし、リベシティを支持母体にして政治に進出しようという気配もありません。だって、コスパよく自分自身の経済的自由を獲得すること、それが教義ですからね。ちなみに、「リベシティ」内では禁止事項がいくつかありますが、政治の話は禁止なんだそうですよ。
■誰もひっぱたきたくないし世界を変えたいわけではなかった
さて、「失われた30年」の間にもさまざまな「政治」的な議論や運動がありました。ただ、わたしが若かった頃、いわゆる就職氷河期世代の政治に関わる話は、極端なものばかり目に入ってきました。
2006年に放送された「NHKスペシャル」で特集された「ワーキングプア」という言葉が注目を集めたこともありました。その年の流行語(ユーキャン新語・流行語大賞)にもなったそうです。ちなみに05年が「富裕層」で06年が「格差社会、ワーキングプア」、07年は「ネットカフェ難民」が選ばれています。なんて時代だ! その流れを受けて07年に雑誌『論座』に「『丸山眞男』をひっぱたきたい——31歳、フリーター。希望は、戦争。」という赤木智弘さんによる文章が掲載されました。ワーキングプアなど貧困と政治に関する議論の俎上に上がるのは上の世代(家族のいる人たち)ばかり、自分たちの世代は視界に入っていない。現状の「平和」な社会で自分たちだけが犠牲になるなら、戦争でも起きて全員平等に犠牲になればいい(だから自分たちの世代にもちゃんと目を向けてほしい、極論に向かわせないでほしい)といったものでした。この文章は当時大きな反響を呼び、『若者を見殺しにする国 私を戦争に向かわせるものは何か』という書籍にもなりました。さて、当時のわたしはフリーター当事者であったものの、赤木さんの文章には現在の弱者男性論にも通じる八つ当たり感を覚えてしまって、正直まったくピンと来ていませんでした。今も来てないです。
雨宮処凛さんの『生きさせろ! 難民化する若者たち』(太田出版)は、美大受験に挫折した高卒フリーターの雨宮さんが非正規雇用ゆえの不安定な生活のなかで「プレカリアート」と出会うことから始まります。自身の生きづらさの原因が、労働市場の自由化を進めていった社会や政治(いうわゆる「新自由主義・ネオリベ」と呼ばれるもの)にあるとし、「生きさせろ!」と生存を求め、フリーターや非正規雇用の現状を取材するノンフィクションです。鬼気迫る筆致と「当事者の声」が高く評価され、この年の日本ジャーナリスト会議賞(JCJ賞)も受賞しました。
その後2010年には『生き延びろ! 生きづらい世界を変える8人のやり方』(太田出版)も上梓。バイトで不利益をこうむったら労働組合に入ったり、生活にこまれば生活保護を受けるなど、「死なない方法」はわかったけれど、どう社会を変えたらいいのかわからない……という青年の言葉を引き、「人は、“死なない方法”がわかっただけでは生きていけない」(同書・14ページ)と、さまざまな生き方をしている人に取材を試みたそうです。
本書に登場する人に共通するのは「タダか、限りなくタダに近い額で社会・世界を変えている変えようとしている」と私が勝手に思っている、という点だ。 そして、誰も思いつかないようなやり方で、独自の「生き方」を極めている。
リーマンショック後の「危機」で明らかになったように、もうこれからの世界は市場原理の拝金主義の弱肉強食で自己責任、という価値観では無理なようである。どっかに勤めてるから安心、なんて呑気な言い分も通用しなくなった。もうこうなったら、何かまったく別の生き方や暮らし方、働き方といったものを模索したい。そうして、多くの人に話を聞いたのだ。
(同書15ページ)
紹介されているのはこういってはなんですけれど、映画監督や芸術家、起業家などみなさんとても極端な生き方をされている人たちばかりで、こういった生き方に勇気づけられる読者も多いのかもしれませんが、当時のわたしにはピンと来ませんでした。今も来てないです。
「新自由主義・ネオリベ」的な世界を生き抜くために資本主義の外に出て常識にとらわれない生き方を……というメッセージがこめられている本ですが、多くのひとはべつに強引でデタラメな生き方をして資本主義の外に向かいたいわけではなくて、ただ安定した「ふつうの」暮らしが欲しかっただけなのではないでしょうか。少なくとも、わたしはそうでした。
当時のわたしは極論なんか求めてないしアジテーションも必要としてなかった。赤木さんも雨宮さんもご自身や当事者の「物語」を強調するけれど、誰かの物語や共感がほしかったわけではなかった。ただ、いまここを凌ぐためのノウハウ、そしてそれを試した誰かの再現性のある「情報」がほしかったんです。ちなみにこの頃わたしが一番読んでいて一番ためになったテキストは「2ちゃんねる掲示板」の「一人暮らし板」の書き込みです。バイト先でもネットの友達にもあまり経済事情を話せなかったし、当時は実家の経済状況もよくなくて頼れる状況ではなかったので、ひたすら匿名掲示板で情報を集めていた記憶があります。
あの頃、自分のまわりの同世代ではそういう人とは出会えなくって、学者の方やマスコミの中の人ばかりが盛り上がっている印象がありました。マスコミの中の人たちって、高学歴で高収入のエリートですよね。ずっとそう。そういう人たちのための「考えさせられる」極論が必要とされていたんじゃないかな。ああ、過去形じゃないですね。今もでしょうけど。とはいえ、「エリートのみなさまがた」をいまさら強者だとなじりたいわけでもありません。そういうのは吉本隆明さんが大昔に「大衆」を論じる際にやっていたそうですし。そもそも赤木さんや雨宮さんの言動もある種のエリート批判として機能し、消費されていたはずです。そういう人目を引くための「物語」は今でも手を変え品を変え出てきますし、YouTubeだってその舞台のひとつです(そういう話も今後の連載で取り上げる予定です)。
■開かれたノウハウ、開かれた文体
さて、話をリベ大に戻します。この出版不況の中でもリベ大の書籍は、昨年発売された改訂版も含めると累計200万部近く売れているそうです。この本、よく読むとけっこう変な本で、なんというか「まとめサイト」のような印象を受けるんです。書籍としてのまとまりはあまり感じられなくて(ので、どこから読んでも大丈夫ともいえる)とにかくフラットに情報が並列に並んでいる。リベ大って「キャラクター」は強いけれど「物語」は薄いんですよね。フラットさはテキストにもあらわれていて、要所要所でキャラクターたちのコミカルなやりとりとともに暮らしに役立つ情報が紹介されています。まとめサイトっていうか「やる夫スレ」じゃん。常識的に考えると(JK)読み手を選ぶ文体ですが、結果200万部売れている事実は動かせない。
昨年、この集英社新書プラスの連載から生まれた大ヒット本『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の著者三宅香帆さんのnoteの「批評の文体をひらきたいー2025年から考える」という記事を、ここで紹介させてください。
三宅さんは、いわゆるこれまでの「批評家(評論家)」たちの文体は、わずかな例外をのぞいてあまり自分に向けられたものではないとしています。三宅さんの言葉を借りて「この文体は私のほうを向いている」とわたしが感じる文章は、紙の本のなかにはありませんでした(かっこいいとかおもしろい文章はあるんですけども)。インターネットの中にしかなかった。もしかしたらそういう人は多いのかもしれません。そう、今の時代において、リベ大本の文体こそがもっとも「働いてても読める文体」……なのかもしれません。なんせ(『働いているとなぜ本が読めないのか』でいわれている)「ノイズ」がないですからね。
リベ大本のメインライターを担当したブロガーのヒトデ先生は『新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』(インプレス)を愛読しているそうです。『新しい文章力の教室』はポップカルチャーメデイア・ナタリーの唐木元さん(※当時)が社内で行っていた文章勉強会を一般向けに解説する一冊です。まえがきには「書ける人にとっては当たり前過ぎて誰も説明してくれない基本“歩くときは右足の次に左足を前に出す”というようなプロセスを言語化し、誰でも順を追って身につけられるようにしました」とあります。なお、当時のナタリーの「フラット」で「ノイズ」の少ない文章は、わたしにとって「この文体は私のほうを向いている」と感じられるもののひとつでした。
ノウハウといえば、2024年に雨宮さんは『死なないノウハウ』(光文社)という新書を出しています。こちらは「極端」な話ではなくて、「お金」や「仕事」「親の介護」「健康」「トラブル」「死」のパートにわかれ、様々な専門家に話を聞いて国の制度やセーフティーネットを確認していくインタビュー集です。ただ、やっぱり専門家の方々の人柄やスタンスといった「物語」が重要視されており、情緒豊かな文体で綴られています。本書のあとがきには「私は死なないための知識を得ることによって、ずいぶん優しく、人間らしくなれたと思う」という「物語」仕立ての本でもありました。「死なない方法」だけでは生きていけないわけじゃなかったのはよかったけれど。
また、それに先んじて2023年には『14歳の世渡り術 学校では教えてくれない生活保護』(河出書房新社)という本も執筆しています。
「学校では教えてくれない」……よく見るキャッチフレーズではあるのですが、リベ大でもなにかと頻出するフレーズです。リベ大の両学長は学生時代にインターネットを通じてビジネス(何をやっていたかは具体的には明かされていません)をしていたものの、なまじ成功したばかりに税務署からひどく怒られてしまい「どうしてお金のことを義務教育で教えてくれないんだ!」という経験からリベ大を構想したといいます。『本当の自由を手に入れる お金の大学』も、「学校では教えてくれない」さまざまな国の制度を利用して賢く生きていこうという本でもあります。
ここで、「学校では教えてくれない」という言葉に込められている意味の違いが気になりました。思うに、雨宮処凛さんのいう「学校では教えてくれない」は、ルールからはみ出しても生きていけるようにするという発想で、リベ大の「学校では教えてくれない」は、ルールを利用して合理的にうまくやっていくという発想があるのではないでしょうか。
リベ大のサイト内には学長がおすすめする書籍が掲載されています。

「YouTubeやTwitterでもご紹介したリベ大両学長おすすめの書籍をまとめて掲載しています!お金・投資・保険のことなど、リベ大マインドを学ぶための良書を取り揃えています」
(サイトより)
とのことで、『漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則 』(文響社※マンガ版です)や橘玲さんの『新版 お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 知的人生設計のすすめ』(幻冬舎)、ロバート・キヨサキの『改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学』など、ある意味定番の「お金の話」から、FP検定3級のテキスト類、なぜか『ドラえもん』や『火の鳥』『ブッダ』といった名作マンガなど、さまざまなジャンルの書籍やマンガが紹介されています。ただ並べているだけの書籍もありますし、両学長のコメントが添えられているものもあります。そのなかでも「プログラミングスキル」という項目は両学長のコメントの多さが目立ちます。
高価なパソコンが買えなかったため、自力で組み立て、独学でプログラミング技術を獲得したと語る両学長。技術に関してとくに強い思い入れがあるように感じます。(なお、プロフィールには若くして10億以上稼いだとありますが「どんな」ビジネスだったかはあまり言及されません)この技術者的な思考が「世界を変える」のではなく、今ある世界のルール内で個人の力で生き抜くノウハウを提供するという考えに至った背景なのかもしれません。
次回に続きます。
参考文献
マーク・フィッシャー『資本主義リアリズム(堀之内出版 )
リベ大@両学長『本当の自由を手に入れる お金の大学』(朝日新聞出版)
雨宮処凛『生きさせろ! 難民化する若者たち』(太田出版)
雨宮処凛『生きのびろ! 生きづらい世界を変える8人のやり方』(太田出版)
雨宮処凛『死なないノウハウ』(光文社)
雨宮処凛『14歳の世渡り術 学校では教えてくれない生活保護』(河出書房新社)
赤木智弘『若者を見殺しにする国 私を戦争に向かわせるものは何か』(双風舎)
『現代思想2022年12月号 特集=就職氷河期世代/ロスジェネの現在』(青土社)
三宅香帆『なぜ働いていると本が読めないのか』(集英社)
唐木元『新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』(インプレス)
参考URL
https://chatgpt.com/share/67a70ae6-94e4-8002-865e-3dfd9e9bcbdd
https://www.hitode-festival.com/?p=271

「両学長 リベラルアーツ大学」「中田敦彦のYouTube大学」「日経テレ東大学」…… ここ数年、YouTube上で学問の知識や教養、お金のやりくりについて教授するYouTubeがブームになっている。そうしたコンテンツはなぜ「大学」という名前を冠しているのか。視聴者たちは、なぜそうした動画に熱狂しているのか。フリーランスのライターとして、ポップカルチャーやネットカルチャーについて取材・執筆を続けてきた藤谷千明が迫る。
プロフィール

ふじたに ちあき
1981年、山口県生まれ。工業高校を卒業後、自衛隊に入隊。その後職を転々とし、フリーランスのライターに。主に趣味と実益を兼ねたサブカルチャー分野で執筆を行なう。著書に『オタク女子が、4人で暮らしてみたら。』(幻冬舎)、『藤谷千明 推し問答! あなたにとって「推し活」ってなんですか?』(東京ニュース通信社)、共著に『すべての道はV系へ通ず。』(シンコーミュージック)、『水玉自伝 アーバンギャルド・クロニクル』(ロフトブックス)、『バンギャルちゃんの老後 オタクのための(こわくない!)老後計画を考えてみた 』(ホーム社) など。


 藤谷千明
藤谷千明









 藤原辰史×青木 理
藤原辰史×青木 理