いま地方発のドキュメンタリー番組が熱い。中でも、沖縄の基地問題、教科書問題、ネット上でのバッシングなどのテーマに正面から取り組み、維新旋風吹き荒れる大阪の地で孤軍奮闘しているテレビドキュメンタリストの存在が注目を集めています。
『何が記者を殺すのか 大阪発ドキュメンタリーの現場から』は、毎日放送(MBS)の制作番組『なぜペンをとるのか』『沖縄 さまよう木霊』『教育と愛国』『バッシング』などの問題作の取材舞台裏を明かし、ヘイトやデマが飛び交う日本社会に警鐘を鳴らしつつ、深刻な危機に陥っている報道の在り方を問う一冊です。
このたび、著者の斉加尚代さん、ゲストに現代史がご専門の京都大学人文科学研究所准教授・藤原辰史さんをお招きしたトークイベントが開かれました。
現在、全国順次公開中の斉加さん初監督映画『教育と愛国』の話題で口火が切られたお二人のトークでは、この国の教育、愛国、そして歴史をめぐる状況について大事な議論が展開されました。
※2022年5月16日、丸善京都本店にて行われたトークイベントの模様の一部を記事化したものです。

藤原辰史さん(左)と斉加尚代さん(右)
「歴史から学ぶ必要はない」という歴史学者
藤原 まず斉加さんの撮られた映画「教育と愛国」を見てびっくりしたのが、道徳の教科書の文章に登場していたパン屋さんが、教科書検定によって和菓子屋さんに書き換えられていたという事実があったことです。
斉加 パン屋さんが教科書から外された読み物への検定意見は、「伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度に照らして不適切」というもので、それでパンが外されました。
藤原 もちろん、日本の食料自給率の圧倒的低さという問題がこの記述の背後にあることは重要なのですが、単純にパンが西洋的で日本の文化とは関係ないという方向に行っているのは歴史の事実としておかしいと思いました。例えば日本の戦前のパンの歴史というのはすごく深いんです。日本の栄養学者として非常に有名な佐伯矩という人がいるんですけど、彼が子どもたちに給食をやったらどうかということを東京府知事にお願いに行ったんです。栄養がバランスよく配合されたパンを食べさせるのはどうだろうかと、積極的に推したという歴史があります。
それから第一次大戦の時には、ドイツと日本は戦争状態にあったわけですけど、ドイツの植民地であった青島での戦いで捕まえたドイツ人捕虜を連れて来たのですが、それとともに彼らはソーセージやベイカリーなどの食文化も持ち込んだ。例えば神戸のユーハイムもその一例ですね。そういう歴史をちゃんと学んでいれば、あんな単純な対応にはならないという気持ちで映画を見ていました。
斉加 ですから、パンが西洋だから愛国心に照らして不適切だというのを聞いた時に、いったい日本の歴史とか文化とかどうなってしまうんだろうって、逆の意味でびっくりしたんです。
藤原 僕が考えていたのは、その保守系といわれる政治家たちや学者たちが言っている言葉の最初の部分は、何となく理解できそうなところもある。つまり「誇り」というものを子どもたちが持てなくなった。それは別に国じゃなくても、今、住んでいる場所、あるいは自分が生きることに誇りみたいなのが持てないことに対する危機感が、そういう狭義の愛国主義に走らせているかもしれない。子どもたちが自分を大事にしたいと思う気持ちや自分の尊厳を持ちにくくなっている、という現状認識ならば、私も持っている。
でも、そこからの進み方が、どうもおかしい。子どもたちに誇りを持たせたかったら、美化された歴史では嘘くさくて頭をすり抜けていく。そういう日本の歴史を丁寧に追っていって、ありのままの姿をしっかりと学び、歴史の担い手たちの善悪両面を見つめる方がもっと自分の住んでいる地域に愛着が湧く。そうすれば「今、自分はこの国、この場所に生きているんだ」ということの確認になるはずなのに。歴史学をやっている人間としては、何かすごく矛盾をきたしていると思いました。「愛国者ならもっとやり方あるやろ」と感じたドキュメンタリーでした。
斉加 ありがとうございます。本作の中では道徳の教科書に続いて、歴史の教科書も記述を巡ってさまざまな出来事があります。慰安婦など日本軍の加害について丁寧に触れたがために倒産にまで追いやられた日本書籍という会社の元編集者も出てきます。歴史についていろんな人が語っていくんですが、藤原さん、そこはどんなふうに見ていただきましたか。
藤原 私にとって衝撃的だったのは、やはり東大名誉教授の歴史学者の伊藤隆さんですね。加藤陽子さんとか、鈴木淳さんとか、御厨貴さんとか、綺羅星のような歴史学者を育て、輩出した人なんです。私にとって伊藤隆さんの研究は、実証主義的な日本現代史の研究者としてまず記憶されています。一方で、彼はずっと新しい歴史教科書をつくる運動、そして今、育鵬社の歴史の本の主要執筆者です。僕が一番衝撃だったのは、伊藤さんが「歴史から学ぶ必要はない」と言ったこと。
斉加 育鵬社が目指しているものは何ですかという質問に続いて、歴史から何を学べばいいんでしょうかってお尋ねしたんです。そしたら「学ぶ必要はないんです」というお答えが返ってきました。
藤原 歴史から学ぶ必要がないと歴史学者が言うというのは天変地異に等しいと思います。つまりこれは今、起きている世界中の歴史修正主義、ロシア、ポーランド、ハンガリーから日本まで、あらゆる国で起こっていることですけど、問題は「現在」にしかないという考え方のように感じました。過去のいろいろな複雑な経緯があって現在の問題が起こっているのですが、それを考えるのは意味が無いということを、他ならぬ伊藤さんという歴史家が言ったことが、僕にとってはほんとに衝撃でした。
斉加 私がインタビューさせていただく中で、伊藤さん自身の歴史学者としての歩みの中で欠かせない出来事というのがおありだったんです。かつて岩波書店の『思想』という雑誌に論文を掲載した時にものすごいバッシングを受けたというんですね。当時はSNSのない時代ですから、匿名で雑誌に自分に対する攻撃を書く学者がいっぱいいたんだと。それはファシズム論争といわれていて、今でも歴史学会の中で記録として残っているけども、自分はそれに決して負けなかった、むしろそのファシズム論争で当時の左翼的な歴史学者に勝ったんだ、というようなことをおっしゃっている。だから君はSNSの中のデマやフェイクの話もするけど、昔からそういうのは学者の中ではあったんだという語りをされたんです。
藤原 この問題、大変重要でして。実はいまだに私たち歴史学者にとっても伊藤さんのその論争はトラウマなのです。つまり戦前の日本は「ファシズム国家」ではなかったということを、細かい調査の上で論文に書いた歴史家なんです。何を意味しているかというと、日本というのは戦争をしたけれども、その流れは、ヒトラーのドイツとかムッソリーニのイタリアに比するようなものではないという説を展開したんです。その結果、今も、例えば歴史学の会議とかに出たときに、その伊藤論文が出てくる。戦前の大日本帝国がファシズム研究の比較研究の対象にならない、その根拠としてまだ出てくるんですよね。
斉加 やっぱりそうなんですか。
藤原 伊藤さんにとってもトラウマだったけど、私たち歴史学にとっても、ナチスと日本の共通点を探る研究が難しくなったという、ある種のトラウマとして今も残っている。そういう意味で、伊藤さんが映画「教育と愛国」の中ですごく軽い言葉で、斉加さんのインタビューを受けていたのを見て、ここまでになっちゃったかという衝撃でした。
斉加 おっしゃるように、ちょっと軽い言葉には聞こえるんですけど、発していらっしゃるオーラやその存在感というのは、テレビ制作者としてはとても魅了される空気感でした。今、ああいうご発言をするというのは、日本の戦後の歴史の、もしかしたら重要な一面なんじゃないかとも感じたんです。
藤原 そうですね。伊藤隆さんは、いわゆる教条的な「反日歴史学者」に徹底的に批判されたという過去を、その左翼が教科書会社を支配し事実を歪め、日本の悪い点ばかりを強調したという考えと結びつけ、それとは違った傾向の教科書を出版して対抗しようとしているように思えます。それだったらそれで伊藤さんの根幹にある歴史実証主義で勝負すれば良いのですが、「反日」というレッテル貼りに見られるように、言葉が軽くて驚きます。
世界で進行する「あの素晴らしい国をもう一度」
斉加 この『何が記者を殺すのか』という書籍の中でも、自分自身、現場に行ってデマとかフェイクを流している人たちや、歴史を書き換えようとしている人たちに取材してきたんですが、共通するのは何とも言えない「軽さ」なんです。そして事実をきちんと確かめずに、意図的に書き換えていく力にネットの中の人々が加勢していくのはなぜだろうというのを、ずっとこの書籍を書きながら考えてきたんです。
藤原 私もこの『何が記者を殺すのか』を読んでからその言動の軽さについて考えていました。本に出て来ますが、斉加さんがデマを流している方との電話取材に成功します。そこでのやりとりで感じられたのはどんなことでしょうか。
斉加 話ができたのは、ヘイトの陰謀論をつくりだしている当事者なんですが、本人はそれに気付かない。自分の論はコピー・アンド・ペースト、「コピペ」なんだと言うので、私が「作り話ですか」と、そのフェイクデマを流しているブログ主に聞いても「いや、事実なんだ」という語りをずっと繰り返すんです。
藤原 自覚が無いんですね。
斉加 そして政治の流れに呼応するというか、そのフェイクに乗っかる人たちが増えていっている気がします。それがこの映画や、この書籍を出した動機なんです。だから、この本のタイトルは『何が記者を殺すのか』ですが、例えば狙われた人によっては、何が学者を殺すのか、何がアーティストを殺すのか、とも言えます。確か、ナチスドイツでも権力者の意に沿う音楽はOKだけど、意に沿わない音楽は駄目とか、そういう選別がされていったんですよね。
藤原 そうです。面白いのは、ナチスの芸術政策です。もっとも重要な政策は、退廃芸術というのと大ドイツ芸術という2つのジャンルに芸術を分けたことです。大ドイツ芸術というのは、例えば筋骨隆々の金髪で青い目の男の人が大地を耕しているっていう、ナチスの「血と土」のイデオロギーにぴったりの絵ですね。もう一方の退廃芸術というのは、例えばピカソのような抽象芸術とかですね。その退廃芸術を、ほんとにひどいんですけど、ナチスは身体障害者の写真を隣に置いて「ほら、似ている。どちらも健康的でなく、退廃してるだろ」ということを見せつけておとしめていくんです。
ただこれは、実際に彼らは退廃芸術展と大ドイツ芸術展という2つの展覧会を同時やるんですが、結局ドイツの人たちがどっちに行ったかというと、退廃芸術のほうにたくさん行ったわけです。
斉加 そうだったんですか。
藤原 ええ。結局関心があるわけです。表現の不自由展もそうだと思うんですけど、やっぱり見たいというもののほうに行ったわけです。
斉加 その退廃と大ドイツの選別を聞くと、杉田水脈議員が言うところの国益にかなった研究と、他国のプロパガンダに利用されている研究という切り分けに似ているような気がしますね。
藤原 そうですね。それで言えば、僕なども多分他国に利用されている研究者と思われていると思うんですけど(笑)。
斉加 国益とか生産性を上げるという言葉がありますが、それは今、力を落としている日本をもっと盛り上げるためには、結局、政治家の言うとおりにしないといけない、そうしないと反日だというふうに言われている。そんな気がしませんか。
藤原 それで私が斉加さんにお願いしたいのは、この映画を次はぜひ海外に運んでいただきたい。この『何が記者を殺すのか』を読んだ後に特にそう思いました。どういう意味かというと、この本で書かれてあるように、今日本で起こっている歴史教科書の改ざん、そして検定が通った後も文科省のプレッシャーと教科書会社の忖度で、従軍慰安婦や強制連行という言葉を削るという、採択後までも介入するような在り方に加えて、政府を批判する人たちを執拗にSNSでバッシングするということは、実は世界中、かなりいろんなところで起こっていることなんです。
もっと言うと、日本よりもかなり厳しい状況に置かれている国もたくさんあります。例えば、衝撃だったのはポーランドでした。ポーランドではアウシュヴィッツにポーランド人が関わったことなど、自民族のイメージを崩すような発言をした歴史学者は逮捕されたり、大学を辞めさせられたりする法律が通ってしまったのです。
どの国も歴史修正主義的な、「あの素晴らしい国をもう一度」という言説をしゃべる政治家に人気が出てきたし、歴史教科書もそういうふうに書き換えられるところが多かった。ハンガリーもそうで、中東欧が特にそうやられてきました。
斉加 世界的な潮流なのですね。
藤原 それからロシアもそうですね。プーチンが去年出した論文によると、ベラルーシもウクライナも一つの同じロシア圏として存在するので、分裂する必要はないんだ、ゴーゴリもウクライナ人だけどロシア語で小説を書いているだろ、という大ロシアを標榜する内容です。他方で彼はアメリカの原爆も批判しているんですね。これは極めて政治的です。なぜかというとロシアがナチスとの戦争の中でやった虐殺行為を西ヨーロッパ諸国が批判するものですから、「いやいや、アメリカだって広島・長崎に原爆を落としただろ」というわけです。
歴史学者の橋本伸也さんは、『紛争化させられる過去』(岩波書店)の中で、ロシアによるアメリカに対する歴史の戦争の仕掛けの背景があったからこそ、オバマの広島訪問が実現したのではないか、と推測されています。オバマは「原爆投下は非人道的なジェノサイドと何が違うんだ」というプーチンの非難に対して、ある種の「かわし」を試みた。いやいや、私たちは原爆に対して、もちろん謝罪はしないけれども、こういう形で向き合っている、と。ほんとは向き合っていないんだけど、向き合っているというアピールをして、それから真珠湾に安倍さんが行くという茶番劇のような和解のシーンをやった。
紛争地を撮影されている写真家の方に聞いた話ですが、日本では、オバマが被爆者の方を抱いている写真をどの新聞社も掲載したんですけども、いやいや、そんな単純な問題じゃない。宝島社もこれが和解であるような大きな新聞広告を出したけど、それで日本人が癒やされているようでは、今の歴史を巡る世界政治の状況には届きません。海外のある新聞は、オバマ大統領と安倍首相が慰霊碑の前で目線を合わさず、すれ違っている写真を載せて、これが歴史をめぐる対話なのかと読者に問うています。斉加さんがこの『何が記者を殺すのか』にお書きになったことは、むしろ世界問題としてあるんだとすごく感じています。

引き裂かれる公教育の現場
斉加 そういう背景を読み解く上での歴史から学ぶものは多くありますよね。私も指摘しましたが、経済の低迷とナショナリズムの高揚は相関関係にあります。
藤原 はい、今のこの世界を覆っている問題を語る上では、やっぱり経済の状況というのは重要だと思います。なぜかというと、リーマンショックではっきりとわかったように、これ以上、各国が利潤を出していく手段がだんだんなくなっている。では、どうやったらライジングアゲインできるかを悩み抜いた結果、労働力を非正規雇用にしたり、かなり露骨に「人権」の領域に手を出し始めたりしたわけです。つまり聖域だった労働権に介入することで、利益をえる方法を編み出した。
斉加 人類の長い歴史の中でこれまで獲得してきた人権を、なぜそんなやすやすと壊しにかかるんだろうって思うんですね。
藤原 それは莫大な利益になるからだと思います。
斉加 ああ。
藤原 労働者の賃金を低い水準に落とせるからだと僕は思います。人権を壊しにきているというのは、単に権力者が悪魔だからというよりは、それ以上に儲かるから。だってそれによっていくらでも人件費を下げられるわけですから。人件費削減は経営者には甘い蜜です。
実際、今の日本の富裕層とそうでない層とでは、この安倍政権ですごい差が広がりましたけど、それを覆い隠すための心理的装置としてのナショナリズム、つまりこの映画「教育と愛国」が指摘している問題があると思うんです。
斉加 うん。あるかもしれないです。でも、映画の中で「日本人というアイデンティティーを備えた国民をつくる」と安倍元総理は明言されるんですけど、大阪の教育現場を取材しているといろんなルーツの子がいるんですよね。中国人、韓国人、フィリピン人、その他、いろんな国のアイデンティティーの子どもたちがいます。そうすると先生は、教科書に政府見解というものが載ってきたときに、教え方にすごく苦悩するというんですよ。他国のアイデンティティーを持つ子を前にどうしたらいいのかと。以前だったら目の前の教室にどんな子どもたちがいるかによって教え方を変えることができたんだけども、今、教科書どおりに教えなかったら、それを告発して、その小学校とか先生を攻撃する政治家が現れてしまうというのが現状です。
藤原 そうですね。斉加さんが、大阪の教育現場への攻撃がどれほど凄惨かを明らかにしたのは、今回の映画の肝だと思います。
斉加 先生たちはすごく神経質になっていて、自由に教えられないという事態になっています。でもこれもすごく矛盾するんですが、「歴史はもっと多元的に見ましょう」という文科省の方針も一方にあるじゃないですか。
藤原 はい、そうです。
斉加 だけども教科書どおり政府見解を教えなさいとなると、真面目な先生ほど考え込んで、どう教えたらいいか分からなくなってしまう。
藤原 日本政府はSDGsで多様性を認めましょうと発信しておきながら、他方、道徳の教科書では極めて単純な食べものを通じた国民統合の話を載せている。この2つを同時にやらされている現場が、まさに非常に苦しんでいると。
斉加 だから公教育が、本来は格差をなくす装置にならなければいけないと思うんですけども、大阪で維新政治の教育改革を見ていると、その格差をなくす方向に行っているとは到底思えないんです。でも、そういう格差を広げるような政治に、一般の人たちは支持をする、拍手喝采するという現象も起きています。
藤原 自分で自分の首を絞めるような。これはやはり、世界中で同時多発的に起きている現象ですね。やはり映画「教育と愛国」を海外でも見てもらいたいと思います。きっと、ああ自分の国と似ている、と思う人が多いはずです■
構成/木村元彦
プロフィール
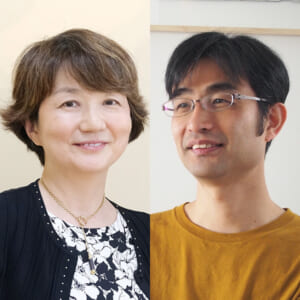
斉加尚代(さいか・ひさよ)
1987年に毎日放送入社後、報道記者等を経て2015年から同放送ドキュメンタリー担当ディレクター。担当番組は『なぜペンをとるのか─沖縄の新聞記者たち』『沖縄 さまよう木霊─基地反対運動の素顔』『バッシング─その発信源の背後に何が』など。『教育と愛国─教科書でいま何が起きているのか』ではギャラクシー賞テレビ部門大賞。映画『教育と愛国』で初監督。個人として「放送ウーマン賞2018」を受賞。著書に『教育と愛国―誰が教室を窒息させるのか』(岩波書店)、『何が記者を殺すのか-大阪発ドキュメンタリーの現場から』(集英社新書)がある。
藤原辰史(ふじはら・たつし)
1976年北海道生まれ。歴史学者。専門は農業史と環境史。島根県立横田高校卒業後、京都大学総合人間学部卒業。京都大学人間・環境学研究科中途退学。京都大学人文科学研究所助手、東京大学農学生命科学研究科講師を経て現職。主な著書に『ナチス・ドイツの有機農業』(第1回日本ドイツ学会奨励賞)、『ナチスのキッチン』(第1回河合隼雄学芸賞)、『戦争と農業』、『給食の歴史』(第10回辻静雄食文化賞)、『食べるとはどういうことか』、『分解の哲学』(第41回サントリー学芸賞)など多数。第15回日本学術振興会賞受賞。


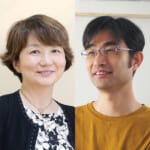 斉加尚代×藤原辰史
斉加尚代×藤原辰史










 菱田昌平×塚原龍雲
菱田昌平×塚原龍雲



 大塚英志
大塚英志
 石橋直樹
石橋直樹