快適な暮らしのために提示される数々のリスク管理と、健康を得るためのハウツー。「自分らしくあれば良い」という声援。
どれももっともらしいけれど、これらは「この私」の救済に本当になりうるのでしょうか。
人類学の知見を用い、他者と生きる人間の在り方を根源から問うたのが、磯野真穂さんの新刊『他者と生きる リスク・病い・死をめぐる人類学』です。
本書の刊行を記念して、著者の磯野真穂さんと、精神医学者の松本卓也さんをお迎えしました。
研究会などで言葉を交わしているお二人ですが、じつは磯野さんの新刊の第1章は、松本さんの何気ない一言にインスパイアされて書かれたそう。
お二人には『他者と生きる リスク・病い・死をめぐる人類学』について、昨今の新型コロナウイルスをめぐる状況とも絡めながら縦横無尽に語っていただきました。
※2022年1月29日、東京・下北沢の本屋B&Bにて行われたトークイベントの模様の一部を記事化したものです。

患者の想像力を「操作する」レトリック
松本 『他者と生きる』の話に関係しますが、まず磯野さんの前著『なぜふつうに食べられないのか』もすごく面白い本でした。摂食障害の人にとって、診断によって病名がつくというのはある種のアイデンティティの獲得にはなるけれど、それによって「この病気なんだから、こうなるはずだ」みたいなことにとらわれていって、「食べる」という行為が持つ他者との関係性が見えなくなっていく──というお話だったと僕は理解しているんですが。
磯野 ありがとうございます。今お話ししてくださった、「食べる」ということの手触りみたいなものが失われていくことへの問題意識を、もう少し丁寧に展開させていったのが今回の『他者と生きる』です。
拒食や過食に苦しんじゃう方って、一日中食べ物で頭がいっぱいになり、栄養学などの専門書をしっかり読み込んでいることは珍しくありません。そしてその結果「何を食べるか」という判断基準が、専門書に書かれているアドバイスといった、身体の外側に移譲していくんですよね。松本さんが読み取ってくださったように、関係性の中で食べる、関係性の中で食べ物を調整するということが難しくなってゆく。
松本 僕、1年間くらい、炭水化物を抜いていたときがあるんですよ。それで結構痩せたんですけど、そのときって、コンビニとかに行ってものを選ぶときの動作が違うんです。普通だったら、商品を見て「これとこれ」って選んで手に取るだけなんだけど、それよりも商品の裏面のカロリーとか炭水化物の量を見て選ぶみたいな感じになる。商品を手にとって、くるっとすばやく回転させるようになる(笑)。だから、外部の数字とかの指標に判断基準が移譲されるというのはすごく分かります。
磯野 第2章で心房細動の患者さんの話を書いたんですけど、特に自覚症状の何もない人に対して予防医学の論理や価値観を注入して、駆動させるためには、その人の想像力に入り込んでそれを操作する以外にない。心房細動の波形が心電図で記録されるけれど、脈が乱れているという自覚症状が見られない患者さんの場合、「心房細動があると脳梗塞になるかもしれない」という想像力を持って内服をしてもらわないといけない。
松本 心房細動というのは、心臓の動きが微妙になって、中で血が固まりやすくなる症状です。さらに、その固まった血が脳に飛ぶと脳の血管が詰まって脳梗塞になったりするので、心房細動が起こる人は血液が固まりにくくなるワルファリンといった薬を日頃から飲んでおくように、と言われています。って、何の解説してるんですか、僕は(笑)。
磯野 いや、ありがとうございます(笑)。それで、そのワルファリンといった抗血栓薬を飲むと、その副作用として出血しやすくなります。血が止まりにくくなるって結構怖いことだと思うんですけど、それでも患者さんにそのリスクを引き受けて内服してもらうには、「この薬が自分にいいことをもたらしている」という実感を持ってもらわなければならない。そのために何がなされるかというと、言葉、つまりレトリックが駆使されるわけです。「(薬を飲むと)血液サラサラになる」だったり「(薬を飲まないと)長嶋茂雄さんみたいになるかもしれませんよ」だったり……。
松本 医療機関って、科学的なエビデンスに基づいていろんなことを決めて、すごい強力な力で我々を管理しているわけじゃないですか。でも実際には、そんなにうまくいっているわけじゃない。そこで、人々が自発的に医学の権力に従ってくれるようにするために使われているのが、言葉に基づいたイメージの力である、ということですよね。
たとえば心房細動を起こした人に「長嶋さんみたいになっちゃう」と言えば、それだけでイメージがぱっとできあがって、その人の意思と行動がある一定の枠組みに収まるようになる。医学的権力とされているものが実際に支配を及ぼすときに、イメージの力、レトリックの力にめちゃくちゃ頼ってるというのは、すごく興味深い指摘だなと思いました。
なぜ自己啓発本は「狩猟採集民」を持ち出すのか
松本 あと、コロナについての話のところも興味深かったです。感染が広がり始めた初期のころ、志村けんさんや岡江久美子さんが亡くなったときに、「火葬や収骨の際にも遺族は同席できず、遺骨の入った骨壺だけが玄関先に置かれる」といった「痛ましい死」のイメージが一気に拡散された。でも実はその当時でも、コロナで亡くなった人の遺体の扱いに関して、「遺族が収骨にも立ち合えない」といったことがガイドラインなどに明示されていたわけではなかったんですね。
磯野 はい、国や関連医学会、あるいは葬儀系の団体が出すガイドラインやマニュアルなどにはそう書かれていないんです。
松本 にもかかわらず、志村さん、岡江さんの死などを通じて広まったイメージが遺体の取り扱い方などを強力に規定することになった。これも、行政が明確に文書で定めて権力を行使しているというよりは、イメージの力で世の中が動いていることがすごく多いということですよね。これも慧眼だと思いました。
それから、『FACTFULNESS』などの自己啓発本に、狩猟採集民のイメージがしばしば持ち出されるという話も面白かったです。
磯野 「狩猟採集民の特性がいまだに私たちの脳には刻み込まれ、私たちはそれによって動かされている」といった話が、一般向けの医学書に出てくる話ですね。もともとは、糖質制限について医師が一般向けに書いた本などを読んでいるときに目に止まりました。原始時代の狩猟採集民は糖質をとっていなかったのに今は大量に糖質を取るから病気になるんだって話です。「なんでこんなに狩猟採集民が出てくるんだろう」と思ったんです。狩猟採集社会はある意味人類学のオハコではありますが、その視点から見るとあまりにも荒すぎるのに、なぜか確信に満ちた筆致で書かれている。なぜ、一般向けの医学書に出てくる狩猟採集民は猛獣に襲われてばかりいるのか。彼らの生活がそれだけだったはずはないじゃないですか。
松本 「そんなに猛獣に襲われてばっかりいなかったでしょう?」と(笑)。
磯野 そうそう。でも、狩猟採集民の生活と、現代社会の私たちの生活との乖離がいろんな問題を引き起こしてるんだと言われると、「確かに」と思っちゃうわけですよ。この「確かに」は一体なんだろうと。ある問題の原因を語ろうとすると、そこに歴史を入れて考える必要が出てきます。しかし疫学的なデータというのは相関関係を示すだけですから、なぜこうなっているのか、という歴史は語りづらい。加えて、人間一般の話をしたいときに、その問題を個別の歴史に紐付けてしまうと、それはある個人、あるいはある地域限定の話になってうまくいかない。でも、狩猟採集民までさかのぼれば全人類をカバーできるわけです。私たちの想像力の中で。
松本 基本的に「歴史意識」がないというのは最近ベストセラーになっている啓発本などに共通の特徴だと思います。古い言い方だけれど、下部構造を無視しているものが多い。人々が抱えている問題の背景にどういう経済的、社会的条件があるのかということをあんまり考えない。それがどこかで「あ、歴史意識が欠けてる、歴史から考えないと」となったときに、今の産業構造が……とかではなくて、一気に旧石器時代まで戻っちゃうみたいなことがありますよね。
磯野 まさに。たとえば『スマホ脳』の著者はスウェーデンのお医者さんなので、本当ならもっとスウェーデンの話を書くべきだと思うんです。でも、それだとグローバルな話にできないじゃないですか。それが、狩猟採集民を持ち出した瞬間に全世界の話にできる。
でも、それをみんなおかしいと思わず「そうだよね」と納得してしまうんですよね。

医大の一般教養の授業で学んだこと
松本 僕は以前から、磯野さんの医療に対する立ち位置みたいなところを聞いてみたいなと思っていました。たとえば、僕は高知医大に行ったんですけど、医学部って基本的に医学の勉強しかしないんです。1〜2年生の一般教養の授業も、僕が行っていたような地方の大学だと、講師陣にバラエティがないんですよ。だから、一人の教員が医療倫理学と文化人類学を教えているとか……。
磯野 待って、無理があるでしょ、それは(笑)。何でも屋ですか。
松本 そういう感じなんです。でも、その授業がすごくよかったんですよ。フーコーとイリイチについて教わったりして、だからフーコーの『臨床医学の誕生』とかは大学1〜2年生のときに読んでいたんです。松本少年(笑)にとってはそういうのが、オアシスだったんですよね。もともと、中高生のときから哲学とか好きで、医学の勉強はあんまり面白いと思わなかったから。
磯野 何で医学部行ったんですか(笑)。
松本 ともかくそういう一般教養の授業を受けて得た思考のイメージが、まずは物事を相対的に見なきゃいけないということだったんですね。医学って、「こういう病気はこう診断してこう治療するのが絶対だ」という感じになりがちなんですけど、それを相対化するような思考を1〜2年生のときに教えてもらえたのはすごくよかったと思います。
と同時に、そこである種の医学や医療全般に対する反骨精神みたいなものを身につけてしまったわけです。これは自分の職業否定にもなるんです。今でも基本的に「まあ、ほとんどのことは方便でしょう」と思ってるんですよ。
たとえば新型コロナウイルス感染症が流行して以来、インフルエンザの感染者が激減しました。もちろん受診控えもあるのかもしれませんが、2020年度は「ゼロコロナ」ならぬ「ゼロインフルエンザ」と言ってもいい状況でした。それで、2021年度は、去年少なかったから今年はインフルエンザが流行するからワクチンを打つべきだ、という専門家の言説が盛んに喧伝されたわけですが、2021年度もやっぱり「ゼロインフルエンザ」に近い状況です。
こういうのを見たときに、「ああ、やっぱり方便だな」って思うんですよ。自分のやってる精神科領域でも「これは方便だ」って思わざるをえないことがいろいろあって、ある種の精神医学批判みたいなことをどうしても考えてしまうんです。批判とは言っても、悪いところを見つめながら、どうやったらちょっとでもましに使えるかということを日々考えているんですけど……。
なぜ運動生理学から人類学へ移ったか
磯野 私は、もともと運動生理学をやっていて、元もとはかなり「科学の子」だったんです。「自然科学的に物事を運べばすべてが解決する」と思ってたくらい純粋な。大学では人文科学の授業もあったんですけど、松本少年とは違ってそこで目を開かれることはなかった(笑)。
ただ、スポーツのさまざまな現場に立ち会う中で「科学的にやれば物事が解決するわけじゃない」というのは強く感じるようになりました。あと、運動生理学をやっていたときのゼミの先生がすごく変わった人で、「俺は絶対に運動はしない」と言ってたんですね。
彼はAT値(運動強度を増していくとき、筋肉のエネルギー消費に必要な酸素供給が追いつかなくなり、血液中の乳酸が急激に増加し始める強度の値。強度がAT値を超えると無酸素運動となり、AT値を下回ると有酸素運動になる)の専門家だったんです。で、スポーツは疲れたらパフォーマンスが落ちる、そして人間がへとへとになるポイントはAT値だということで、「まったくトライアスロンの練習をしなくても、AT値に達しないペースでやれば完走できる」という仮説を立てたんですよ。事前に実験して自分のAT値を計算して、「これでいけるはずだ」と練習ゼロでトライアスロンに出たんです。
松本 そしたら?
磯野 完走できなかったんですよ(笑)。
松本 落ちがついた(笑)。机上の空論ということ?
磯野 その実験で彼が証明したのは、「実験室の中でいくら結果が出ていても、人間は世界とのいろんな関わり合いの中で生きてるから、実験データだけでは人間のパフォーマンスは測れない」ということだったんですよね。
さらに、研究の中でスポーツ選手に話を聞いていると、朝に見たテレビ占いの結果にショックを受けてケガをしたから、絶対もう占いコーナーは見ません、とか言っている人がいて。どれだけ科学的なトレーニングを積み上げても、人間が生きるのは実験室の外側で、そこでは「科学的」は通用しない。閉鎖的な空間の中で結果が出ても、開放的な空間の中ではよく分からないことが起こるんだということに、大学3〜4年のときに気づいたんです。それでアメリカの大学でいろんな授業を聞いていたときに、「あ、人類学って面白い。これが私のやりたいことだ」と思って、専攻をスイッチしました。
精神分析における「人間」とは
磯野 私から松本さんに伺いたかったのは、本の第7章で取り上げた「人とは何か」についてです。あの章では、統計学をベースにした統計学的人間観、一つの身体の中に一つの個人が宿っていると考える個人主義的人間観、そして多様な「人」のあり方を前提とする関係論的人間観について論じています。松本さんのご専門である精神分析においては、どういう人間観が用いられているんでしょうか。
松本 精神分析的な人間観というのは、まずやっぱり個人が前提になりますね。自分に病いが起こって、それを自分が治療者のところへ行って治療するわけだから、ある意味個人主義でないと成り立ちません。
ただ、個人が意識の主体だと考える一方で、自分の中にはそうして自分を支配しているのとは別の、無意識というものがうごめいていると考えます。そして面白いのは、この無意識というのは他者と結び付いていると考えられていることです。
磯野 どうやって結び付くんですか?
松本 たとえば、ユングのいう「集合的無意識」は、個人の無意識の深層に、みんながある程度共有している、トランスパーソナルな部分があるという考えです。フロイトやラカンの考える集合的無意識は家系、先祖ですね。
磯野 先祖?
松本 たとえば、ギリシャ悲劇の『オイディプス王』で、主人公オイディプスの身に不幸が起こるのは、家系が呪われているからです。オイディプスの父親のライオスが悪いことをしたがために「おまえの家系は根絶やしになる」という呪いを掛けられる。オイディプスが支配するテーバイの国が飢饉に見舞われたり、オイディプスの娘アンティゴネーが子どもを産むことなく死んでしまうのは、その表れなわけです。そういうふうに、無意識とはその家系、家族の歴史の中である種の集合的広がりを持っているものとしてとらえられるんですね。
だから、個人というものがあることが前提なんだけど、その個人を掘り下げていくと、ある種の集合性、歴史性みたいなものが見えてくる。個人モデルを突き詰めることによって他者とのつながりを見ていくというのが、精神分析における人間観ということになります。
磯野 面白いですね。でも、突き詰めていくと無意識のところで他者とつながってるんだったら、やっぱり個人はいないっていうことになりませんか。
松本 でも、やっぱり精神分析に行ったら、お金を払うのはその個人ですからね。
磯野 そこではっきり個人が見える(笑)。
「早すぎる死」とは何なのか
磯野 今回の本で、人間観についての話を取り上げたのは、医療の現場でしばしば耳にする「生存率の比較」についての言説に違和感を持ったことがきっかけです。
松本 ある病気になった人の5年生存率とかですか?
磯野 そうです。よく、がん患者で代替医療にはまってしまった人に対して、医療者が生存率を持ち出すでしょう。「標準治療だと代替医療よりも生存率が7年も長いんですよ。だから標準治療を選ぶべきです」という言い方。個々人の人生の長さというものがとてもシンプルに比較され、そこには当然の如く「人生は長いほうがいい」という価値観がくっついているわけです。
そういうことが可能なのは、「個人」というものがまずあって、時間はその外側に存在している、かつそれが一定の速度で流れているということが自明のこととされているから。だからこそ「あの人は早すぎる死だった」というような言い方がされるわけです。
「早すぎる死」を迎えた人に対して、「いや、あの人は深く生きた」「やりたいことをやって生ききった」みたいに言われることもあるけれど、なんだか二番手感があるというか。「この治療をすれば7年平均寿命が延びますよ」みたいに言われるときの、「だって、当然長く生きたほうがいいでしょう?」という抗えない感じに、ずっと違和感があったんです。それで、7章で「人間とは何か」という話をした後に、「時間」をテーマにした終章を置くことにしたんですね。
ちなみに「時間」というものを考えてみたくなったもう一つのきっかけは、2019年に亡くなった哲学者・宮野真生子さんとの共著である『急に具合が悪くなる』です。この本は、がんで闘病中だった宮野さんとの往復書簡の形を取っていますが、実際に手紙を交わしていた時間は3カ月くらいしかないんですね。だけど、その中では、「え、あれからまだ3日しか経ってないの?」とか「これってもう3カ月くらい前のことだと思ってた」というような、不思議な時間が流れていたんです。
これって、多分みんな経験したことがあると思うんですよ。子どものときって、すごく時間がゆっくり流れてるように感じるじゃないですか。
松本 一瞬が永遠のようですよね。
磯野 はい。そういう時間の多様な流れ方に目を向けたときに、ただ単純に「60歳で亡くなったから早すぎる死ですよね」と言われるのは、何か安易すぎる。でも「人生は長いほうがいいでしょう」と言われると、それに反論しづらい。なので時間論についてはまったく素人なんですけど、この違和感を元にあえて踏み込んでみました。

どんな人に読まれたい?
磯野 会場からいくつか質問やご意見も来ています。これは糖尿病専門医の方から。
「本書の中の、医師がレトリックを使って情報発信者の意図のままに想像力を操作するという話の部分を読んで、糖尿病と初めて診断された人に対して自分が行っている説明について改めて考えました」。
松本 糖尿病の場合は、イメージを患者さんに植え付けるためにどんなメタファーを使っているんですかね。
磯野 糖尿病そのものについてはよく知りませんが、関連する話題として美馬達哉さんが『リスク化される身体』の中で、「おなかの出た中年男性」のイメージが、メタボ浸透に一役買ったというお話をされています。
ただ私はこの本の中で、「メタファーを使うことがいけない」と言いたかったわけでは全然ないんです。そうではなく「ファクト」とされるものの曖昧さとか、「ファクト」として引き受けられるまでにいわゆる「科学的」ではないものが含み込まれることを示したかったんです。その背景には例えば、ただ、論文を読める人、エビデンスを理解できる人が語っていることが「唯一の真実」といった語り口への違和感があります。
松本 「真実は、いつも一つ」みたいな。
磯野 そうです。だから「ファクトVSデマ」といった戦いのような構図が出来上がる。もちろん文脈によってはそのようなことが大切なわけですが……。
松本 それが駄目っていうことじゃないですよね。
磯野 そうなんです。
あと質問で、「この『他者と生きる』は、どんな人に読まれたいでしょうか。私の本の中で一番抽象性が高いとおっしゃっていましたが、研究者や専門家でしょうか、病気や死に関する興味のある一般の人でしょうか」。
前半の「情報とリスク」に関する部分は、今回のコロナ禍における専門家からの情報発信について、なんだかよくわからないけど違和感を覚える、といった方達に読んでほしいです。あと後半の、人間観や時間についての部分は、「自分が過ごしている時間ってどんな意味があるのかな」とか、いわゆる「早すぎる死」を身近で体験して「あれは何だったんだろう」と思っている人に読んでもらえたら嬉しいですね。
ちなみに、「一番抽象性が高い」って言っても、私の本の中でという意味で、松本さんの本なんてこれ以上に抽象度が高いですからね(笑)。
松本 そうですか?
磯野 私の本が2階建てくらいだとしたら、松本さんの本は65階建てくらいな感じです(笑)。『他者と生きる』の後半は議論が抽象的にはなりますが、いつもより読むスピードを少し落としていただければ大丈夫だと思います。

撮影/野本ゆかこ
構成/仲藤里美
プロフィール

磯野真穂(いその・まほ)
人類学者。専門は文化人類学、医療人類学。2010年早稲田大学文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。早稲田大学文化構想学部助教、国際医療福祉大学大学院准教授を経て2020年より独立。著書に『なぜふつうに食べられないのか-─―拒食と過食の文化人類学』(春秋社)、『医療者が語る答えなき世界――「いのちの守り人」の人類学』(ちくま新書)、『ダイエット幻想――やせること、愛されること』(ちくまプリマ―新書)、共著に『急に具合が悪くなる』(晶文社)がある。
松本卓也(まつもと・たくや)
1983年、高知県生まれ。高知大学医学部卒業。自治医科大学大学院医学研究科博士課程修了。博士(医学)。現在、京都大学大学院人間・環境学研究科准教授。専門は、精神病理学。主な著書に、『創造と狂気の歴史 プラトンからドゥルーズまで』 (講談社選書メチエ)、『人はみな妄想する』(青土社)、『享楽社会論』(人文書院)、『〈つながり〉の現代思想』(共編、明石書店)、『症例でわかる精神病理学』(誠信書房)など。主な訳書に、ヤニス・スタヴラカキス『ラカニアン・レフト』(共訳、岩波書店)などがある。


 磯野真穂×松本卓也
磯野真穂×松本卓也
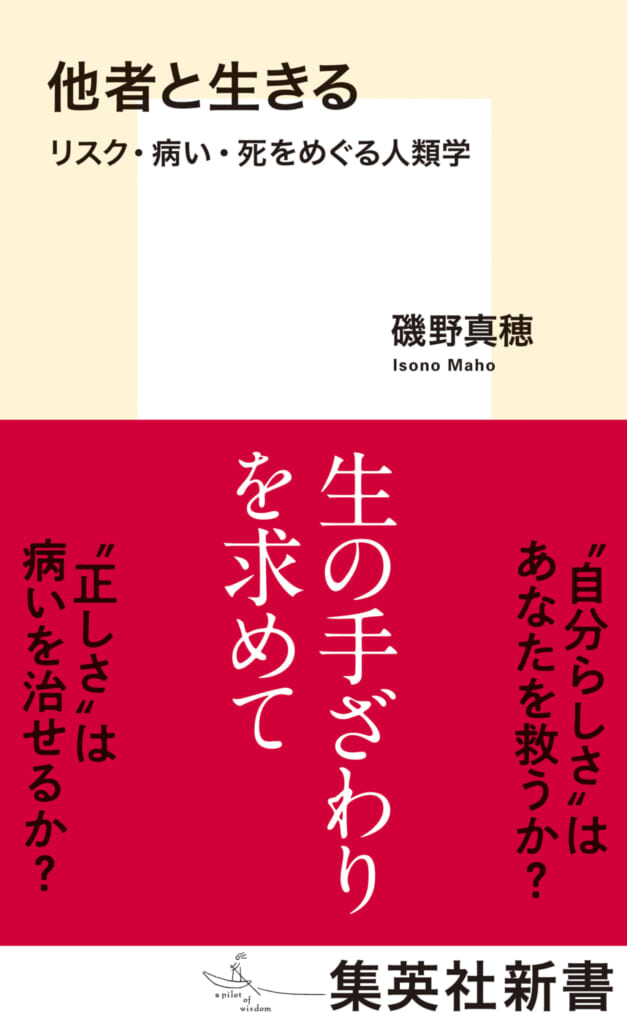










 大塚久美子×塚原龍雲
大塚久美子×塚原龍雲

 苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり
苫野一徳×岩内章太郎×稲垣みどり

